金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

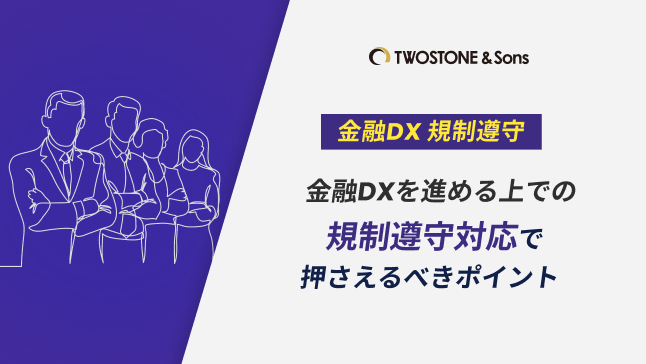
金融業界で進むデジタル化において、規制遵守は避けて通れない重要な課題です。効率的かつ安全に金融DXを進めるためのポイントと実践的な対策を詳しく解説します。
金融業界では今、急速なデジタル化の波が押し寄せています。ペーパーレス化やオンラインサービスの普及、さらにはAIによる業務効率化など金融機関の運営体制はかつてないほどの変革期を迎えています。しかし、そうした変革の裏で多くの金融機関が頭を悩ませているのが「規制遵守」、つまりコンプライアンスへの対応です。
「せっかくDXを推進しても、法規制に抵触してしまえば意味がない」
これは、金融業界に身を置く多くの方が抱えている切実な懸念でしょう。規制は日々厳格化しており、従来のアナログな運用方法では対応が難しいケースも増えています。一方で、デジタル技術をうまく活用すれば、より効率的かつ確実なコンプライアンス体制が構築できます。
本記事では、金融DXを推進する際に必ず押さえておくべき規制遵守のポイントを解説します。
デジタル化によって
を理解すると安全かつスピーディなDX推進を実現できるでしょう。さらに、これらの課題に対して有効なソリューションを提供している企業の活用も視野に入れながら、実務に活かせるヒントを紹介していきます。

金融DXを進める際に見落とされがちなのが「規制対応」です。単に業務の効率化やコスト削減だけを目的にデジタル化を進めてしまうと、法令やガイドラインとの整合性が取れず大きなリスクを招く可能性があります。
金融業界には、資金洗浄防止(AML)・本人確認(KYC)・個人情報保護法・金融商品取引法など多岐にわたる規制があります。DXの推進は、これらすべてに対して適切な管理体制を整えることと一体で進めなければなりません。
金融DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、金融機関の業務やサービス、顧客体験を根本から変革する取り組みを指します。単なるIT化とは異なり、組織の在り方やビジネスモデルそのものの見直しを含む広範な変革です。例えば、オンラインバンキングの導入やAIによる融資審査、チャットボットによるカスタマーサポートなどすでに多くの取り組みが実用化されています。
また、近年ではクラウドサービスの導入やデータ活用を高度化しており、従来の枠組みでは対応できない新たな業務モデルが次々と登場しています。その結果、競争力の維持にはDXの推進が不可欠となってきました。
一方で、金融業界におけるデジタル化には数多くの課題が存在します。まず挙げられるのが、既存システムとの互換性や連携の問題です。多くの金融機関ではレガシーシステムが依然として中心にあり、新しい技術との統合が難航しています。
さらに、セキュリティやデータガバナンスの課題も無視できません。金融データは機密性が高く、取り扱いを一歩誤れば顧客の信頼を失い、行政処分の対象となる恐れもあります。こうした背景から、DXを進める際にはシステム導入だけでなく、業務プロセスの見直しや人材育成、そして法令遵守の仕組み作りが求められています。
金融DXが規制遵守に与える影響は、大きく「良い影響」と「悪い影響」の2つに分けて考える必要があります。DXによって業務の透明性が向上してリスク管理がしやすくなる一方で、新しい技術に既存の規制が追いつかずにかえってリスクが増す場面も存在します。
デジタル技術を活用することで、情報の一元管理やリアルタイムなデータ追跡が可能となります。例えばクラウドベースのCRMやKYCツールを導入すると、顧客情報の変更履歴やアクセスログを自動的に記録・保管できるようになります。これにより、監査対応やトレーサビリティが向上するでしょう。
さらに、AIによる不正検知システムやAML対応の自動化ツールを導入すれば、従来は人手に頼っていた監視業務を効率化でき、規制違反のリスクを低減できます。DXの推進は、法令遵守を「業務の一部」として自然に組み込む仕組みを構築しやすくする点でも大きな効果をもたらしています。
一方でDXの進行が速すぎると、法的枠組みが技術の進化に追いつかず、規制違反が発生するリスクが高まります。特に新しいクラウドサービスや外部ベンダーとの連携に関しては、金融庁のガイドラインや監督指針に沿った詳細な対応が求められます。適切なリスク評価やベンダー管理を怠ると、情報漏えいや業務停止などの深刻な事態を招きかねません。
また、規制改正に即応できない体制では、DXが進んでも結果的に内部統制が不十分な状態に陥ります。例えば、システム上の不備でマネーロンダリング対策が機能しない、API連携で誤送金が発生するなど実際にトラブルへ発展したケースもあります。このようなリスクを回避するには、単に技術を導入するだけでなく、法務部門や監査部門と連携して組織全体でリスクマネジメントを行う体制の構築が不可欠です。
金融DXを進めるにあたり、遵守すべき法令やガイドラインは多岐にわたります。これらの規制は、業務の透明性や顧客保護、金融システム全体の健全性を確保するために設けられています。デジタル化が加速する中で、それぞれの規制にどのように対応するかが、企業の成長と信用に直結するのです。
ここでは、金融機関が特に意識すべき5つの主要な規制について詳しく見ていきます。
銀行法は、銀行が営むべき業務やその範囲を明確に定めています。この法律によって銀行は、信用供与・預金の受け入れ・為替取引といった基本的な銀行業務を中心に展開し、それ以外の業務に関しては厳しい制限を受けるのです。
金融DXが進むと、新たなデジタルサービスの導入やAPI連携による他業種との協業が増加します。しかしその際に業務範囲規制を軽視すると、銀行法違反となる可能性があります。例えば、フィンテック企業との協業で生まれる新サービスが銀行固有の業務範囲を逸脱していないか、事前に法的な評価が必要です。
このようなリスクに対応するには、法務やリスク管理部門と連携してサービス設計の初期段階から法的な整合性を検討する体制を整えることが不可欠です。さらに、業務範囲規制に関する最新動向を常に把握し、柔軟かつ確実に対応する姿勢が求められます。
参考:銀行法
個人情報の保護は、金融機関の信頼を左右する重要なテーマです。個人情報保護委員会が公表している「金融分野における個人情報保護ガイドライン」では、金融機関が取り扱う情報の範囲や管理方法、第三者提供の条件などが細かく定められています。
DXの推進により、顧客の取引履歴・行動履歴・生体情報など従来以上に膨大かつ機微なデータが蓄積されるようになりました。このようなデータは、AIによる分析やターゲティングマーケティングに活用できる反面、漏えいリスクも高まります。
ガイドラインに則った情報管理体制を構築するには、システム開発の段階からプライバシーバイデザインを意識する必要があります。また、個人情報の利用目的を明確にし、必要最小限の範囲での取得・利用の徹底が法的リスクの低減につながるのです。
参考:個人情報保護ガイドライン
マネーロンダリングやテロ資金供与対策は国際的にも厳しい監視対象となっており、日本の金融機関にも高度な対応が必要です。金融庁は「AML/CFTガイドライン」にもとづき、各金融機関にリスクベースアプローチ(RBA)の導入と内部管理態勢の強化を求めています。
金融DXの推進によって取引がオンライン化し、非対面の口座開設や送金サービスが普及する中で、不正取引の監視はより困難になっています。従来のルールベース型の監視だけでは、高度化する不正手法に対応しきれません。
そのため、トランザクションモニタリングにAIを導入して異常検知の精度を高める試みが進んでいます。また、顧客の属性や取引パターンに応じたスコアリングを活用してリスクに応じた監視レベルを設定することも有効です。AML/CFTは一度の対策で完結するものではなく、継続的な改善とアップデートが求められる分野なのです。
金融機関において法令違反や不正行為を防止するためのコンプライアンス体制は、経営基盤そのものといっても過言ではありません。特にDX推進時には新たなシステムや外部ベンダーとの連携が増えるため、従来のコンプライアンスフレームワークでは対応しきれない場面も出てきます。
PwC Japanが提唱する「コンプライアンス・リスクマネジメント」では、予防・検知・対応という3段階での包括的な管理が重要であるとされています。例えば、規制改正を自動で検知し関連部門に通知する仕組みを構築することで、規制違反を未然に防げるようになります。
また業務プロセスの可視化と内部統制の強化は、DXの副産物としても得られるメリットです。こうした管理手法をIT基盤に組み込むことで、規制遵守をより確実なものにできるのです。
参考:PWC
金融機関が扱うデータは、攻撃者にとって極めて高い価値を持ちます。そのため、サイバーセキュリティは金融DXにおける重要課題の1つです。金融庁は2024年に改定された「サイバーセキュリティ対策ガイドライン」で、システムの多層防御やインシデント対応体制の強化を促しています。
特にクラウド化やAPI連携が進む中で、アクセス経路の増加によりセキュリティホールが生じやすくなります。これに対応するには、ゼロトラストモデルの導入や多要素認証、暗号化通信の徹底が欠かせません。
また、万が一の攻撃を想定したBCP(事業継続計画)を策定して平時から定期的な演習を行うことで、実際の被害を最小限に抑える備えが整います。セキュリティ対策は一時的な施策ではなく、日常的な業務に組み込むことが前提です。
近年、金融業界において「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が急速に進んでいます。この流れは単なる業務効率化にとどまらず、規制対応やコンプライアンス管理にも革新をもたらしています。多様化・複雑化する法規制に迅速かつ的確に対応するためには、アナログ的な対応では限界があるでしょう。金融DXの推進は、このような課題を根本から見直し、効率的な規制遵守を実現するカギとなるのです。
データ管理を自動化することで、金融機関における監査対応が格段にスピードアップします。実際に、クラウドベースのデータベースやAIによる自動記録機能によって必要な情報を即座に抽出できる環境が整備されつつあるのです。
このような環境が整備され、銀行が顧客情報や取引履歴を一元的に管理すると、監査担当者からの要請に対して迅速かつ正確に資料を提出できます。従来は紙媒体や複数のシステムにまたがったデータを人力で確認する必要があり、膨大な時間と労力がかかっていました。今後は、リアルタイムで情報を可視化してログ管理を自動で行えるため、コンプライアンス上のリスクも軽減されるでしょう。
AIや機械学習を活用したリスク検知システムの導入により、不正行為を従来よりも早く発見できるようになります。これは、いわゆる「アノマリー検出」と呼ばれる手法で、通常とは異なるパターンの取引を自動で抽出する技術です。
この仕組みは、マネーロンダリング対策や不正送金の防止において極めて有効です。例えば、通常とは異なる高額な海外送金や同一IPアドレスからの複数口座アクセスといった異常を瞬時に感知し、警告を発することで初動対応を早められます。これにより、金融犯罪の未然防止に寄与し、結果として規制機関からの信頼を高めることにもつながるのです。
コンプライアンスに関する社員教育は金融機関にとって不可欠ですが、従来の集合研修には限界がありました。金融DXの進展によってeラーニングやオンデマンド研修といったオンライン教育ツールが普及し、社員1人ひとりの理解度や進捗に応じた柔軟な学習が可能になっています。
これらの教育ツールの普及により、全社員に対して一貫した教育を提供できる上、受講履歴や理解度の可視化も容易になるのです。例えば、特定の法改正について即座に社内周知を行い、理解度テストを通じて教育効果を確認できる体制が整備されれば、企業としてのコンプライアンス体制の底上げにつながります。知識の属人化を防ぎ、全社的なリスク感度を高めることが可能です。
金融DXのもう一つの利点は、業務プロセスの標準化によって規制対応がより明確かつ再現性の高いものになる点です。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの技術を活用すれば、規制対応に必要な手続きを正確かつ効率的に自動化できます。
顧客の本人確認(KYC)や反社会的勢力のスクリーニングといった法定業務は、手順が複雑でありながらミスが許されません。そこで自動化を導入すると、処理の均一性とトレーサビリティを確保しながら人的ミスを防ぐことが可能になります。標準化されたフローがあることで法令変更があった場合の対応もしやすくなり、柔軟かつ継続的な改善が促進されます。
クラウドサービスの活用は規制対応だけでなく、セキュリティ体制の強化にもつながります。従来のオンプレミス型のシステムでは、サーバー管理やセキュリティアップデートが担当者任せになりがちであり、脆弱性が見過ごされるケースも少なくありませんでした。
一方クラウドサービスでは、常に最新のセキュリティパッチが適用されるだけでなく、二重認証やアクセス制限など高度なセキュリティ機能が標準搭載されています。また、万が一の災害やサイバー攻撃時にも迅速なデータ復旧が可能であるため、事業継続性の観点からも有利です。
特に金融機関は個人情報や資金取引などの機密情報を多数扱うため、セキュリティ対策の強化は避けて通れません。クラウド技術の活用により高い可用性とセキュリティ水準を同時に実現し、規制機関の求める水準に的確に応える体制を構築できるのです。

金融業界では、マネーロンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)、個人情報保護法(PIPL)などの規制が年々強化されています。そんな中で、デジタル技術を活用した規制遵守の効率的かつ確実な実行が求められているのです。
ここでは、金融DXを通じてコンプライアンス対応を高度化させた3つの主要金融機関の取り組みを紹介します。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)はAML/CFTに関する金融庁の指摘を受け、デジタル技術を駆使した改革を進めました。その中心となったのが、取引モニタリング体制の高度化とグローバルでの統合的なリスク管理です。
同社はAIを活用した異常取引検出システムを導入し、疑わしい取引の迅速な発見と報告体制を構築しました。このシステムは、大量の取引データをリアルタイムで解析して過去のパターンとの相違点を自動で抽出する仕組みです。このシステムを利用することで、従来の手作業中心の検知方法に比べて精度とスピードが大きく向上したのです。
さらに、コンプライアンス部門とIT部門が連携し、ガバナンスの強化に向けた組織体制の再構築を行いました。このようにMUFGは、単なるツールの導入にとどまらず、全社的なDX推進体制を整えることで規制対応力を飛躍的に高めています。
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)では、内部管理態勢の強化を目的としてデータガバナンスと内部監査のデジタル化を進めました。金融庁の「金融検査・監督に関する考え方と進め方」においても、SMFGの取り組みが評価されています。
その一例として、全社横断的なデータ連携基盤の構築が挙げられます。この基盤によって各部門が保有する情報を一元化し、規制対応に必要な証跡データの抽出が格段に容易になりました。従来は複数のシステムから手動でデータを集めていたため作業負担やヒューマンエラーが避けられませんでしたが、自動化によって対応スピードと正確性が向上しました。
また、監査業務にはデータ分析ツールを活用し、リスクの高い取引や部門を自動で抽出できるようになっています。これによって重点的な監査対象の選定が可能となり、限られたリソースを効率的に活用しています。DXによってリスクの可視化と対応精度の向上が図られ、ガバナンス水準の底上げにつながっているのです。
みずほ銀行は、個人情報保護に関するガイドラインへの対応強化を進める中でクラウドサービスの活用によるシステムの刷新を行いました。個人情報保護委員会の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に則った対応が急務とされる中、DXを活用した施策は注目を集めています。
特に顧客データの管理については暗号化やアクセス制御を強化し、クラウド上でも高いセキュリティを担保する構成を採用しました。クラウド導入に際しては、米国および国内の複数のセキュリティ基準に準拠した設計と運用が行われています。これにより、万が一の情報漏えいリスクに備えると同時に迅速な障害対応も可能となりました。
加えて、顧客からの開示請求や利用停止などの個人情報保護に関する対応も自動化された問い合わせ管理システムによって効率化されています。これにより、法令で定められた対応期限内での処理が安定的に行える体制を整えました。
参考:みずほ銀行
金融機関がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める際には、単に新しい技術を導入すれば良いわけではありません。特に「規制遵守」を前提とする金融業界においては、業務プロセス・組織体制・社員の意識改革まであらゆる要素を一体として見直す必要があります。
ここでは、金融DXを効果的に推進するための6つの重要なポイントを紹介します。
最初に取り組むべきは、関連する法令やガイドラインを正確に理解することです。例えばAML/CFT対応においては、金融庁が発行する「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に加え、FATF(金融活動作業部会)の勧告も考慮する必要があります。また個人情報保護に関しては、個人情報保護法やその分野別ガイドラインに対応する体制の整備が不可欠です。
これらの法規制は国内外で頻繁に改正されるため、常に最新情報を追い正確に把握する体制を整える必要があります。誤った解釈のままシステム開発や業務設計を行うと、逆にリスクが増大する可能性があります。法務部門と連携しながら明確な基準をもとにDX戦略を設計する必要があるのです。
金融DXの成功には、技術面だけでなく組織としてのガバナンスが問われます。システム導入やデータ活用を進めるためには、情報システム部門だけでなくリスク管理部門や法務部門とも緊密に連携する必要があるのです。
多くの金融機関ではDX推進を専門に扱うプロジェクトチームや横断的なタスクフォースを設置し、部門間の壁を越えた協働体制を整えています。また経営層が率先してDXの必要性を発信することで、全社的な理解と支持を得られます。こうした組織的支援があってこそ、規制対応と業務効率化の両立ができるのです。
どれだけ高度なシステムを導入しても、それを扱う人材の理解度が低ければ期待した効果は得られません。特に金融業界では、個人情報やマネーロンダリング対策など取り扱う情報の機密性や重要性が極めて高いため、社員1人ひとりがリスクを正しく認識する必要があります。
そのためには、DXに関する技術的知識だけでなくコンプライアンスや法令理解を含めた研修の定期的な実施が重要です。Eラーニングやケーススタディ形式の研修を取り入れ、業務に即した学習機会を提供することで、実務への応用力を養いましょう。
金融DXは多くの専門分野が交差するため、自社内だけで全てを網羅するのは現実的ではありません。とりわけ、セキュリティ設計や法令遵守、クラウド環境の整備といった領域では、高度な専門性が求められます。
そのため、ITコンサルティング企業やリーガルテック企業、監査法人といった外部パートナーを積極的に活用することが重要です。外部の視点を取り入れることで、見落としていたリスクの発見や先進的な対応策の導入が可能になります。適切なパートナー選定が、DXの質とスピードを左右するといっても過言ではありません。
デジタル化が進むと同時にサイバー攻撃や情報漏えいのリスクも増大します。特にクラウドサービスやAPI連携を導入する場合には、通信経路の暗号化、アクセス権限の適切な設定、脆弱性対策といったセキュリティ対策が不可欠です。
また、ゼロトラスト・アーキテクチャの導入やSOC(Security Operation Center)による常時監視体制の構築など、最新のセキュリティモデルへの移行も検討すべきです。万が一インシデントが発生した場合の初動対応体制や外部との連絡手順も含めて、事前に計画を整えておきましょう。
金融DXは一度実施すれば完了するものではありません。規制は年々高度化し、テクノロジーも日進月歩で進化しています。したがって、導入後も定期的な見直しと改善を繰り返すことがリスク軽減と業務最適化のカギになるのです。
ユーザーからのフィードバックを活かし、システムの使い勝手や対応スピードを改善するPDCAサイクルを回すことが求められます。また、法令改正に応じたアップデートや外部監査による評価を定期的に実施することで、常に最適な状態を維持できるでしょう。
金融DXの推進において規制遵守を強化したいとお考えの金融機関には、『株式会社TWOSTONE&Sons』へご相談ください。
『株式会社TWOSTONE&Sons』は金融分野における豊富な実績と専門性を有しており、法令対応を含めた包括的なDX支援を行う企業です。
公式ホームページでは、金融機関向けの事例紹介や規制対応を見据えたシステム構築支援、継続的な運用改善まで、具体的なサービス内容が掲載されています。特にAML/CFT対応や個人情報保護法対応においては、専門チームが最新の規制動向を把握した上で、貴社に最適なソリューションを提案します。
「どこから始めればいいかわからない」「自社の体制が適切か確認したい」とお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが丁寧にご相談に応じます。

金融業界における規制遵守は、今や単なる義務ではなく企業の信用を守るための重要な戦略課題です。一方で業務負担の増加や人材不足といった課題に対応するためには、効率的かつ柔軟な業務体制の構築が求められます。
その実現手段として注目されているのが金融DXの推進です。適切な設計と体制、そして継続的な改善を組み合わせることで、コンプライアンス強化と業務効率化の両立が可能となります。
もし金融DXに関する課題を抱えている場合は、実績豊富な外部パートナーの支援を受けることでより確実かつスムーズに推進できます。まずは現状の課題を整理し、未来の業務像を描くところから始めてみましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
