金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

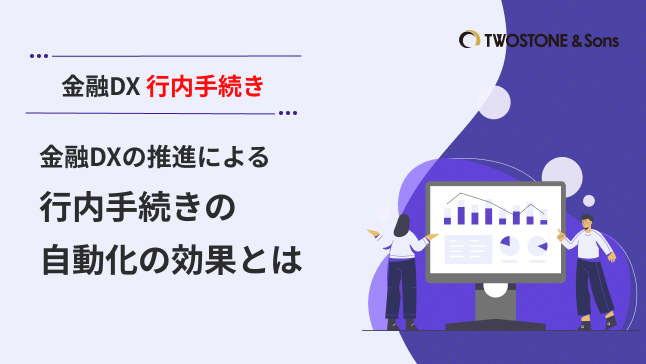
紙の書類やハンコによる煩雑な業務にお悩みの金融機関の皆さまへ向けて、金融DXの必要性と行内手続き自動化の効果をわかりやすく解説します。業務効率や顧客満足度の向上を目指す方におすすめの内容です。
紙の書類にハンコ、煩雑な手続きといった従来の業務フローに、日々の業務効率や顧客満足度の面で課題を感じている方は多いのではないでしょうか。特に金融業界では、正確性とスピード、さらに法令遵守のすべてが求められるため、業務の見直しが急務となっています。そのような中で注目されているのが「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
この記事では、金融DXを進める背景を踏まえた上で、行内手続きをどのように自動化し、どのような効果を得られるのかを解説します。また、実際にDXを進める際に役立つサポート体制についても紹介するため、金融機関に携わる方々にとって実践的なヒントを得られる内容になっています。読み進めることで、自社に適したDXの方向性を明確にし、業務改善や顧客満足の向上につなげられるでしょう。

急速に進展するデジタル社会において、金融業界が取り残されないためにはDXの推進が不可欠です。デジタル技術の導入は単なる業務効率化にとどまらずサービスの質を高め、法規制への対応力を強化する手段としても注目されています。
金融DXとは、クラウドやAI、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの先端技術を活用して業務フローを見直し、サービス提供の質を高める取り組みを指します。従来のアナログなプロセスでは顧客対応や内部管理のスピードに限界があり、手作業によるミスや情報の属人化といった問題が発生しやすくなっていました。
しかし現在、テクノロジーの活用で業務全体を自動化・効率化し、より正確かつ迅速な対応が可能になっています。特に銀行や証券会社といった金融機関では、業務の複雑性と法規制の厳格さからDXの効果が大きく表れやすい分野といえるでしょう。
参考:日本金融監査協会
社会全体でスマートフォンやインターネットが普及した今、金融サービスに対する顧客の期待も大きく変化しています。顧客満足度を高めるためにはそうしたニーズを的確に捉え、サービスを進化させる必要があります。
一昔前までは、銀行に出向いて窓口で手続きを行うのが一般的でした。しかし現在は、アプリを使った口座開設やネットバンキングによる資金移動など非対面での取引が主流になっています。実際、スマートフォンから24時間アクセスできる利便性を求める顧客が増えており、それに応じた体制構築が金融機関に求められているのです。
こうした背景から、窓口業務のデジタル化やチャットボットの導入、ペーパーレス化の推進といった施策が進められています。これらの施策により、行員の負担を軽減しながら顧客にとっても快適な取引環境を提供できるようになっています。
顧客は画一的なサービスよりも、自分のニーズに合った提案を重視するようになりました。これに応えるには、膨大な顧客データを分析して行動パターンやライフステージに応じたサービスを提供する必要があります。
DXによってデータ分析の精度が向上すれば、顧客ごとに最適なローンの提案や投資商品の提示が可能になります。AIによるレコメンド機能を活用すれば、担当者が把握しきれない潜在ニーズにもアプローチでき、契約率や顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
時間をかけずに手続きを終えたいというニーズは、年齢層を問わず高まっています。特に若年層では、対面でのやりとりや紙の提出に煩わしさを感じることも珍しくありません。
そのため、本人確認のオンライン化(eKYC)や自動契約システム、電子署名などの導入が進んでいます。これにより、ユーザーはどこにいても短時間で手続きを完了でき、金融機関側も処理のスピードと正確性を高めることが可能です。
金融機関における行内手続きは、複雑で多岐にわたる業務が絡み合っています。これまでこれらの業務は多くの書類や手作業によって行われていましたが、近年その非効率性が問題視されるようになっています。従来の手法では多くの時間がかかり、エラーが発生するリスクが高いためです。
では、金融機関にはどのような課題が残っているのでしょうか。ここでは3つ具体例を挙げて説明します。
多くの金融機関では、依然として手作業で行われる手続きが数多く残っています。例えば、顧客の個人情報の入力や更新作業、取引の確認、書類の署名などが挙げられます。これらは一見すると簡単な作業に見えますが、膨大な量を処理するためには相当な労力と時間が必要です。
特に業務がピークを迎える時期には、従業員が残業をしてでも対応しなければならないこともあります。このような非効率な手作業に依存した手続きは企業にとって大きな負担となり、業務の進行速度を遅らせ、最終的には顧客への対応が遅れる原因ともなり得ます。
さらに手作業に頼ることにより、ヒューマンエラーの発生も避けられません。情報入力ミスや書類の処理漏れなどは、金融機関における信頼性に関わる重大な問題となる可能性があります。これらのリスクを減らすためには、業務プロセスの見直しと改善が欠かせません。
金融業界は、法規制やコンプライアンスに対する対応が厳格です。そのため、企業は日々の業務において複雑な規制に対応する必要があるのです。しかし、従来の手作業中心の業務では厳しい規制に適切に対応することは困難であるため、多くのコストがかかります。
金融機関で顧客の取引情報を保存する際には、特定の法規制に基づいて、保存方法や保存期間を慎重に決定する必要があります。こうした規制に対応するための手続きが手作業に依存している場合、時間と労力がかかり、その分コストが膨らむでしょう。
また、法規制が頻繁に変更されるため、それに合わせて手続きやシステムの修正が求められ、追加の人員や外部の専門家を雇う必要が出てくることもあります。規制対応が不十分であれば罰則や訴訟などのリスクも高まり、企業の信用の低下にもつながりかねません。
顧客は、金融機関に対して迅速で効率的な対応を求めるようになっています。特に、オンラインバンキングやスマートフォンアプリを使って日常的に取引を行う顧客層は、速やかな手続きやサービス提供を期待しています。しかし手作業が多く残る業務環境では、これに応えることが難しくなりがちです。口座開設や融資申請の手続きが遅れると、顧客は他の金融機関に流れてしまうかもしれません。
また顧客情報の確認や取引履歴の処理が遅れると電話やメールでの問い合わせが増加し、対応に追われる状況が生まれます。顧客にとっては、少しでも迅速でスムーズな対応を求めているため、対応が遅れることは満足度の低下を招きかねません。このような事態を防ぐためには、業務の効率化と迅速な対応が求められています。
行内手続きを自動化すると、金融機関は多くの業務課題を解決できます。自動化は単なる作業の効率化にとどまらず、顧客対応のスピードや精度の向上、さらには法規制対応の強化にもつながる施策です。
ここでは、行内手続きを自動化することによって得られる5つの主なメリットを紹介します。
自動化を進めることで、従業員が行っていた多くの手作業をシステムが代わりに行うようになります。これにより、従業員はより付加価値の高い業務に専念でき、作業負担を軽減できるでしょう。例えば、顧客情報の入力や書類の確認、取引履歴の保存など繰り返しの多い業務を自動化することで単純作業にかかる時間を削減できます。これらの時間が削減できると、従業員の労働時間をコア業務に効率的に使うことが可能です。
処理を手作業で行っていると、ヒューマンエラーは避けられません。特に金融業務では、情報のミスや誤入力が大きな問題を引き起こす可能性があります。しかしシステムによる自動化では、規定通りに正確なデータ入力や処理が行われ、エラーの発生を減少させられます。その結果、取引の精度や正確性が向上し、信頼性の高いサービスを提供できるでしょう。
自動化によって手続きがリアルタイムで処理されるようになります。リアルタイムで処理すれば顧客のリクエストに即座に対応できるようになり、迅速なサービスを提供できます。
例えば、オンラインバンキングでの資金移動や口座開設の手続きが自動化されると、顧客は24時間いつでも迅速に対応可能です。これにより、顧客満足度が向上し、市場での競争力を高められるでしょう。
手作業が多い業務は時間と人員を大量に消費しますが、自動化を進めることで人的コストを削減できます。自動化によって一部の業務がシステムに置き換わることで、人手がかからなくなるためです。
また、業務の効率化により時間の無駄を減らせば、リソースを有効に活用できます。コスト削減によって企業全体の利益率が向上するだけでなく、競争力も強められるでしょう。
金融機関が遵守すべき法規制は多岐にわたります。手作業で法規制対応業務を行っていると、変更があるたびに修正作業が必要となり大きな負担になりかねません。しかし、システムを導入することで規制変更に自動的に対応できるようになり、手間を大きく減らせます。顧客情報の管理やデータ保存方法を法規制に則った形で自動的に処理できると、コンプライアンス違反のリスクを減少させられるでしょう。

金融機関が行内手続きを効率化し持続的な競争力を確保するには、単にツールを導入するだけでは不十分です。根本的な業務の見直しから始まり、段階的に自動化を進めていくことが求められます。
ここからは、金融DXを推進し、業務自動化を成功させるための6つのステップについて解説します。
最初のステップは、現在の業務プロセスの正確な把握から始まります。各部門でどのような手続きが行われているのかを棚卸しし、どの工程に時間や手間がかかっているかを洗い出しましょう。
例えば、紙ベースでの申請や承認作業、Excelでの情報管理、メールでのやりとりなど非効率な業務が日常的に行われているケースが少なくありません。これらの課題を明確にすることで、自動化すべき対象を正しく特定できます。さらに、業務プロセス全体の可視化を通じて、重複業務や無駄な承認フローなど構造的な問題点も浮かび上がってくるでしょう。
課題を把握したら、次は自動化によって実現したい目標を設定します。ここでは、「業務時間を年間○時間削減する」「人為的ミスを○%減らす」「顧客対応のレスポンスを○時間以内にする」など、定量的かつ具体的な目標を掲げることが重要です。
目標を明確にすることで導入するツールや運用体制の方向性が定まり、関係者の認識統一にもつながるでしょう。また、経営層の意思決定を促す材料としても定量的な目標は有効です。将来的なKPI設定や効果測定の基準にもなり、導入後の改善活動にも役立ちます。
目標が定まったら、それに見合ったツールを選定します。金融機関ではセキュリティ面や法令遵守への配慮が求められるため、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)、OCR(文字認識)、ワークフローシステムなど特定業務に特化した信頼性の高いソリューションを導入する必要があります。
例えば、定型的な入力作業にはRPAを活用し、紙書類のデジタル化にはOCRを用いるといった組み合わせが効果的です。ツールの導入に際しては単なる価格や機能比較にとどまらず、既存システムとの連携性やサポート体制、将来的な拡張性にも注目する必要があります。
ツールの選定と並行して、導入環境の整備も進めなければなりません。特にレガシーシステムとの統合や、クラウド環境への対応が課題になるケースが多く見られます。
インフラ整備では、セキュリティポリシーの見直し、データ管理体制の強化、ネットワークの最適化など基盤となるIT環境を総合的に整える必要があります。加えて、部門横断的なプロジェクトチームを編成し、情報共有や進捗管理が円滑に進む体制を構築することも重要です。
システムを導入するだけでは業務は改善されません。実際にそれを使いこなす従業員の理解と協力があって初めて、自動化は機能します。
そのため、ツールの操作方法だけでなく、業務フローがどのように変化するのか、どのような目的で導入されたのかといった背景も含めた研修が求められます。現場の負担感を軽減する工夫として、段階的な導入やOJT形式の教育も効果的です。また、トレーニングを通じて現場からのフィードバックを吸い上げる仕組みを整えることにより、導入の障壁を下げられるでしょう。
自動化を実装した後も、それで終わりではありません。運用開始後は、定期的な評価と見直しが欠かせません。事前に設定したKPIと実績を比較し、目標が達成されているかを検証する必要があります。
さらに、現場からの声を反映してプロセスを微調整したり新たな業務に自動化を拡張したりと、継続的な改善活動が求められます。長期的に業務効率化を実現し、DXの定着を後押しするためには、柔軟な対応が欠かせません。評価の仕組みを制度化し、定期レポートの作成やPDCAサイクルの導入によって組織全体で改善する文化を育てていきましょう。
行内手続きの自動化は、業務の効率化や人為的ミスの削減といった大きなメリットをもたらします。しかし、その導入にはいくつかの重要な注意点が存在します。十分な検討を行わずに進めてしまうと、かえって非効率や混乱を招く恐れがあるためです。
ここでは、金融DXを推進する際に留意すべき3つのポイントを詳しく解説します。
最初に考慮すべきは、システム導入にかかるコストの把握とその資金計画です。自動化を進めるには業務プロセスに合致したシステムを導入する必要があり、そのためにはソフトウェア購入費やインフラ整備費、コンサルティング費用などが発生します。これらを明確に見積もった上で、段階的に予算を配分することが不可欠です。
特に中小金融機関では一度に多額の投資を行うのが難しいケースもあるため、フェーズごとに導入計画を立て、スモールスタートで進める方法が有効です。また、補助金や助成金などの外部資金の活用も視野に入れると、財務負担を軽減しながらシステム導入を進められます。
システム投資は一時的な支出ではなく、長期的な業務効率化とコスト削減につながる戦略的な施策であることを意識しましょう。
次に注目すべき点は、新たに導入するシステムが既存の業務フローにどう適合するかです。いくら高度なシステムでも、現行業務と連携が取れていなければ業務が分断され、かえって非効率になる恐れがあります。これを防ぐためには、事前に詳細な業務フロー図を作成し、どの工程を自動化するかを明確にする必要があります。
また、現場の担当者の意見を取り入れることも重要です。実務を担う人々の視点からは、見落とされがちな業務上の課題や障害が浮かび上がる場合があります。加えて、業務ルールや法規制に対応した設計を行うことで、トラブルの発生を未然に防げるでしょう。
より実効性の高いDXを実現するためには、業務の一部だけでなく、全体の流れを意識した統合的な自動化を図ることが重要です。
最後に、情報セキュリティ対策の強化は金融機関にとって最優先事項です。自動化によってシステム間のデータ連携が進むと、情報漏えいや不正アクセスといったリスクも増加します。そのため、セキュリティポリシーの見直しと最新の対策導入が欠かせません。
例えば、アクセス権限の細分化やログ管理、暗号化通信の採用は基本的な対策です。また外部ベンダーとの連携時には、セキュリティ水準が自社基準に達しているかの確認も大切です。
さらに、従業員へのセキュリティ教育を継続的に実施し、日常業務の中でのリスク意識を高めることで、内部からの情報漏えいも防げるでしょう。安全性と利便性を両立させる取り組みが、信頼される金融サービスの提供につながります。
行内手続きの自動化を検討している金融機関にとって、外部の専門パートナーの活用は大きな支えになります。『株式会社TWOSTONE&Sons』は金融業界に特化したDX支援を提供しており、数多くの導入実績と業務への深い理解が強みです。
同社は、業務フローの可視化からRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)導入、カスタム開発によるシステム連携、さらには導入後の保守運用まで一貫した支援体制を整えています。これにより、金融機関の業務に最適化されたDX推進が可能です。
また公式HPでは、実際の導入事例や支援内容、金融DXに関する最新情報を紹介しており、検討中の担当者にとって参考になるでしょう。
「どこから手をつけるべきかわからない」「自社の業務に合うツールが知りたい」といった悩みをお持ちの場合は、ぜひ一度、『株式会社TWOSTONE&Sons』への相談を検討してみてください。

金融機関における行内手続きの自動化は、業務の効率化やリスク管理の高度化を実現するために欠かせないテーマです。今回ご紹介した「業務の見直し」「目標設定」「ツールの選定」「インフラ整備」「人材教育」「運用後の評価」という6ステップを踏むことで、無理なく段階的に自動化を進められます。
自社だけで進めるのが難しい場合には、専門知識と豊富な実績を持つパートナー企業への相談が効果的です。行内手続きの自動化を本格的に進めたいとお考えの際は、『株式会社TWOSTONE&Sons』へご相談ください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
