金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

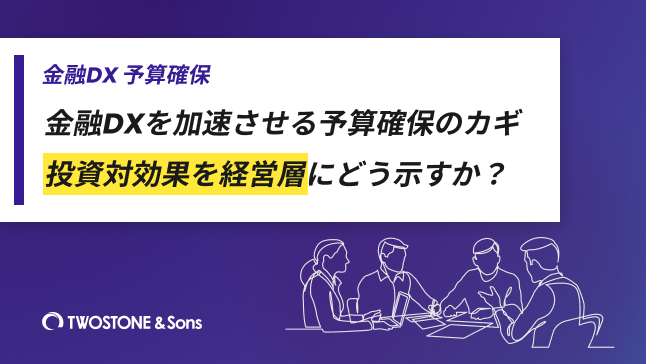
本記事では、金融業界特有のハードルとともに、金融DX推進における予算確保のための具体的なアプローチを紹介します。投資対効果の示し方や、DXがもたらす業務効率・顧客満足度・競争力向上といったメリットについても詳しく解説します
「DXの必要性は理解しているが、予算が取れない」
これは多くの金融機関が直面している現実です。経営層の理解や支援が得られず、デジタル戦略が絵に描いた餅になってしまうケースは少なくありません。特に金融業界は、変化を避けがちな企業文化やレガシーシステムの制約が多くDX推進におけるハードルが高い傾向にあります。
しかし、いまこそDXに本気で取り組むべきタイミングです。経営層に対して正しく投資対効果を示しDX予算を確保できれば、業務効率の向上や顧客満足度の改善、ひいては企業競争力の強化につながるでしょう。
この記事ではまず、金融業界でDX化が急がれる背景を解説し、その上でDX推進によって得られる具体的なメリットを提示します。特に、経営層に納得してもらうための説得材料としてどのように投資対効果を見せれば良いかについても掘り下げます。

金融業界が直面する外部環境の変化は著しく、かつての延長線上では事業の継続が難しい状況になっています。フィンテック企業や異業種からの参入が進み、スピード感あるサービス提供や顧客体験の高度化が求められる中で、伝統的な業務プロセスやITインフラのままでは競争に耐えられません。
顧客との接点がデジタルへと移行している今、金融機関のデジタル対応は単なる利便性の提供にとどまりません。顧客のニーズをリアルタイムで把握し、迅速にサービスへ反映させる体制が求められています。DXは業務効率化の手段にとどまらず、企業の存続をかけた経営課題といえるでしょう。
DXに取り組む意義は多岐にわたりますが、特に以下の5つの観点からメリットを整理しておくことで、経営層への説得材料として活用できるでしょう。
DX環境が整備されると、システム開発や業務改善のスピードが向上します。これまで外部ベンダーへの発注や紙媒体での承認を要していたプロセスが、内製化や電子化により迅速に進行するようになります。
例えば、新たな金融商品を企画する際に、顧客データをもとにプロトタイプを即時開発してテストマーケティングを数週間以内に実施できれば、事業機会を逃すことがないでしょう。金融DXの推進は、現場の機動力を高め、チャンスを確実に掴むための基盤となります。
DXを進める中で注目されているのが「内製化」です。自社内にエンジニアやデータアナリストなどの人材を配置することで、外部委託にかかるコストや時間の削減につながります。
また、内製化によって事業部門と開発部門の距離が縮まり、業務理解にもとづいた迅速な対応が可能になります。こうした柔軟性は業務改善を日常的に行う土壌をつくり出し、継続的な価値創出を支える基盤となるのです。
DX推進のカギを握るのは人材です。必要なスキルセットを明確にし、デジタルに強い人材を的確に採用・育成していくことで組織のデジタル対応力は飛躍的に高まります。
例えば、単なるITスキルのある人材ではなく、ビジネスと技術を橋渡しできる人材を育てることが求められます。教育研修やオンボーディングプログラムの設計を通じて、戦略的な人材育成ができるでしょう。
DXによって蓄積されたデータを活用することで、感覚や経験に頼らない意思決定が可能になります。売上動向や顧客の行動パターン、リスク予測などをデータにもとづいて判断できれば、精度の高い経営が実現するでしょう。
特に金融業界では、信用リスクの評価や融資判断など定量的な根拠が求められる場面が多くあります。AIやBIツールを活用して可視化された情報は、意思決定のスピードと精度を引き上げてくれるでしょう。
デジタル技術の導入により、顧客との接点が変化します。オンラインでの契約手続きやチャットボットによる24時間対応、スマートフォンアプリの利便性向上など顧客にとってストレスのない体験が実現できます。
また、顧客データの活用によってニーズを先読みした提案やパーソナライズされたサービスも提供できるでしょう。顧客満足度の向上は、結果としてブランド価値の向上にもつながります。
金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、単なる業務の効率化や利便性向上にとどまらず、企業の収益性や競争力を向上させる可能性があります。
ここからは、金融DXがどのように利益向上に寄与するのか、そのポイントを具体的に解説していきます。
DXを推進する最大のメリットの1つは、業務の効率化を実現してコスト削減につなげられる点です。これまでは手作業やアナログで進めていた業務を、デジタルツールや自動化によって効率化できます。例えば、書類の確認や伝票の処理、さらには決済や口座管理などの業務を自動化することで時間と労力を削減できるのです。
業務を自動化すると、人的リソースをより重要な業務や付加価値の高い業務に振り分けられます。また、リアルタイムでデータが分析できるようになるため、問題が発生した場合でも迅速に対応できトラブルシューティングのコストや無駄を減らせます。結果として、業務の無駄を減らしてコストを削減でき、利益率向上につながるのです。
金融DXの推進によって、顧客との接点がより深く、より効率的になります。顧客のニーズや行動をデータとして収集して解析することで、よりパーソナライズされたサービスを提供できます。顧客一人ひとりに最適化された商品やサービスを提供すると、顧客満足度が向上してリピート率を高められるでしょう。
また、オンラインでの取引が簡単に行えるようになるため、顧客はいつでもどこでもアクセスできます。特に若年層の顧客やデジタルネイティブ世代にとって、オンラインで完結するサービスは魅力的であり、収益を向上させる大きな要素となります。このように、顧客体験の向上は収益増加に直結するのです。
金融DXの推進よって膨大なデータをリアルタイムで収集・解析し、そこから有益なインサイトが得られます。このデータは、顧客の行動履歴や取引履歴、さらには市場動向など多岐にわたります。これらのデータの活用によってターゲットを絞ったマーケティング施策が可能となり、より高精度で効果的な営業活動を行えるのです。
例えば、顧客がどの金融商品に興味を持っているのか、過去の取引内容からどのサービスがリピートされやすいかをデータとして可視化できます。これをもとにターゲットを絞ったプロモーションや個別のニーズに合わせたサービスを提供することで、売上の拡大を図れるのです。
金融業界においても、オンライン化の進展は避けられません。特に、近年ではインターネットバンキングやモバイル決済などのオンラインサービスの普及が加速し、オンライン業務の拡充が必須の時代となっています。DXを推進すると、オンラインプラットフォームを強化でき、サービスの提供範囲を広げられるのです。
これにより、顧客は店舗に足を運ぶことなくさまざまな金融サービスを受けられ、利便性が向上します。競争が激化する中でオンライン業務を充実させることは、企業の市場競争力を強化して他社との差別化を図るための重要な手段となるのです。また、オンラインサービスの提供によって顧客数の増加や新規事業の創出も見込め、さらなる収益拡大が期待できるでしょう。
DXを推進すると、企業はリアルタイムで市場動向や顧客のニーズ、さらには内部の業務プロセスに関するデータを即座に取得できるようになります。データをもとにした迅速な意思決定が可能となり、経済状況や市場の変化に対応した新しい金融商品の開発や、効率的なリソース配分を素早く行えるでしょう。
このような即時の意思決定は、利益率向上にもつながります。顧客の要求にタイムリーに応じることで失われる機会を減らし、利益の最大化を図れるのです。リアルタイムデータを駆使して常に最適な戦略を取ることで競争優位を確立でき、利益率の向上に寄与します。

金融DXは一部の先進的な企業において、すでに大きな成果を上げています。
ここでは、国内大手金融グループの取り組みを参考にしながら実際のDX推進のあり方とその成果について紹介します。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、グループ全体で「デジタル・トランスフォーメーション戦略」を明確に打ち出し、従来の金融ビジネスの変革を推進しています。その中核となるのがデジタルサービスの創出と業務のデジタル化です。
具体的には、API基盤「Open MUFG API」の提供を通じて外部企業との連携を強化し、デジタルエコシステムの構築を進めています。また、クラウド技術の活用によって社内外のシステム連携を柔軟かつ迅速に行う体制を整え、開発スピードを高めることで新サービスのリリースを加速させています。
こうした取り組みの結果、顧客体験の向上はもちろん社内業務の効率化も実現し、収益性の改善にもつながりました。デジタル領域における戦略的投資を着実に実行することで、MUFGは業界内でも先進的なポジションを確立しているのです。
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)は「デジタルによるビジネス変革」を掲げ、DXを全社的な取り組みとして推進しています。特に注目すべきは、AIとビッグデータの積極的な活用です。
SMFGでは、AIを活用した与信モデルの構築や音声認識技術を用いたコンタクトセンターの高度化など、現場業務の最適化に力を入れています。加えて、フィンテック企業やスタートアップ企業との連携によって革新的なサービスの共創を実現しています。
デジタルチャネルにおいてもユーザーインターフェースの改善やモバイルアプリの機能拡充を図り、顧客満足度の向上を目指しているのです。DXが単なるIT化ではなく、顧客と企業の接点を変革する手段として機能している好例といえるでしょう。
みずほ銀行は「スマート銀行構想」を掲げ、業務・顧客接点・商品提供のすべてをデジタル化する方針を明確にしています。とりわけ、業務プロセスの自動化と組織構造の刷新に注力している点が特徴です。
みずほではRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAI-OCRを導入し、事務処理の自動化を徹底的に推進しています。また、クラウド環境の整備によって社内システムの柔軟性と拡張性を高め、変化への即応体制を強化しています。
これにより店舗業務の削減や管理コストの低下を実現し、経営資源の最適配分が可能となりました。金融機関にとって重い負担となっていた旧態依然のオペレーションを見直し、新しいビジネスモデルを構築している点で先進的な取り組みといえるでしょう。
参考:みずほ銀行
DXを推進するには、戦略だけでなく適切な予算配分が不可欠です。
ここでは、大企業が金融DXを進める際の具体的な予算目安を導入対象別に紹介します。実現可能なDXプランを構築するためには、これらの費用感を把握しておくことが重要です。
クラウド基盤は、DXの基礎となるインフラです。業務システムの柔軟な運用や拡張性を確保するために必要不可欠な投資であり、導入には大規模な予算が求められます。
特にオンプレミス環境からクラウドへの移行を行う際には、データ移行費用やセキュリティ対応、システムの再設計などが発生します。長期的にはインフラコストの最適化が期待できるため、初期投資と考えると良いでしょう。
参考(抜粋):NSK
AIによる分析は、顧客行動予測やリスク評価、商品レコメンドなど多岐にわたる用途があります。小規模なPoC(概念実証)レベルでは数百万円で開始可能ですが、本格的な運用を想定する場合には数千万円単位の投資が必要です。
AI導入の際は、モデルの設計だけでなく、学習データの準備・モニタリング体制の構築・倫理的配慮まで含めた全体設計が求められます。高い精度と信頼性を担保するためにも費用と時間を惜しまず取り組むべき分野でしょう。
参考(抜粋):neural opt
クラウド型RPAは業務自動化をスピーディに実現できる手段です。オンプレミス型に比べて初期コストは抑えられるものの、年間のライセンス料やカスタマイズ費用、保守運用の外注費などが必要になります。
RPAを導入することで、日常的な事務作業やデータ入力、レポート作成といった定型業務を削減し、人的リソースをより戦略的な業務へ転換できます。特に大量処理を行う部門では、高い費用対効果を見込めるでしょう。
参考:日立
金融機関が顧客とつながる上で、モバイルアプリの存在は重要です。利便性の高いアプリは、顧客接点を増やして利用頻度を向上させるカギとなります。
アプリの企画・設計から実装・セキュリティ対策・定期的なアップデートまで長期的な視点で運用する必要があります。そのため、初期開発だけで1億円を超えるケースも少なくありません。安定性とUX(ユーザー体験)を両立するには継続的な投資が求められます。
参考:フリーランス名鑑
金融業界にとって、セキュリティ対策は最重要課題です。サイバー攻撃への備えや個人情報保護法への対応など、多層的な防御策が求められます。
最新の脅威に対応するには、侵入検知システム(IDS)や脅威インテリジェンス、従業員教育プログラムなどを総合的に導入する必要があります。セキュリティ事故が発生すれば、損失だけでなくブランド価値の低下も招くため、投資を惜しむべきではありません。
参考:@IT
DXを推進する上で重要なのは「人」です。最新技術を理解して社内で活用できる人材の確保と育成は、持続可能なDX戦略に直結します。
教育研修や外部講座の受講、リスキリングの仕組みを整備するには一定の予算が必要です。また、外部コンサルタントやITパートナーとの協業により、実践的なスキルを社内に取り入れることも重要です。投資として見れば、将来的な社内コスト削減やサービス品質の向上に貢献する分野といえるでしょう。
参考:PRTIMES
金融DXを推進するには、明確な予算確保が不可欠です。しかし、企業内での大規模な投資には経営層の理解と納得が必要です。そのためには、順序立てたアプローチが求められます。
ここでは、予算確保を経営層に打診する際の基本ステップをご紹介します。
まずは、金融DXが企業にとってなぜ重要なのか、その意義を経営層に理解してもらう必要があります。単なる技術導入ではなく、業務効率の向上・顧客体験の刷新・競争力の強化といった戦略的意義を強調することが重要です。
例えば「顧客接点のデジタル化により、顧客満足度が30%向上する可能性がある」といった具体的な目標設定が有効です。また、デジタルシフトの遅れが競合優位性の低下につながるリスクも明示し、DX推進が緊急課題であることを伝えましょう。
次に、予算申請に説得力を持たせるためには投資対効果(ROI)を数値で示しましょう。これは経営層が注視するポイントの一つです。
例えば、AIを活用した与信判断システムの導入によって審査工数が50%削減され、人件費年間1,500万円の圧縮が見込めるといったシナリオを提示します。さらに、顧客満足度の向上や成約率の改善による売上増加も加味し、5年後までの中長期的な収益モデルを構築することで、説得力のあるシミュレーションが可能となります。
提案の信頼性を高めるには、同業他社の成功事例を紹介するのが効果的です。経営層はリスクを嫌う傾向があるため、「他社もすでに取り組んでいる」という事実が判断材料となるのです。
例えば、三菱UFJフィナンシャル・グループはクラウドネイティブなサービス設計とAPI連携を強化しています。また、三井住友フィナンシャルグループは「金融×非金融」の掛け合わせによる新規事業開発を進めており、株式会社みずほ銀行も業務自動化とモバイルアプリの刷新を通じて顧客対応の質を向上させています。
これらの実例は、自社のDX施策が特異ではなく、業界全体の流れだと裏付けてくれるでしょう。
DXには当然リスクが伴います。セキュリティ事故・初期導入の失敗・ユーザーからの不満・運用コストの増加などがその代表例です。これらを意図的に隠すのではなく、あらかじめ想定されるリスクとして提示した上で対策案を併せて示すことが信頼構築につながります。
その上で「クラウド移行に伴う情報漏えいリスクに対し、ゼロトラストセキュリティを採用し、データアクセスを多層的に管理する」といった施策を挙げると、計画の堅実性が伝わるでしょう。また、導入後の運用体制やトラブル発生時の対応フローも具体的に説明するとさらに安心感を与えられます。
一気に大規模な導入を行うのではなく、まずは小規模な実証実験(PoC: Proof of Concept)から開始する方法も効果的です。これにより、実際の業務にどれだけ有効かを検証できると同時に関係者の理解を深める機会にもなります。
例えば、「営業支援ツールを特定の部署で3ヶ月間導入し、商談件数の変化を検証する」といった具体的なプロジェクトを設定します。成功事例として社内で共有すれば、他部署や経営層の巻き込みも進みやすくなるでしょう。段階的な展開によってリスクを最小化しながら着実にDXの成果を広げていくアプローチです。
DX推進のための予算確保は、専門的な知識や豊富な実践例が必要になります。DX戦略の立案や実行には、高度な知見と実績が必要です。特に金融業界におけるDXは、技術だけでなく法規制や顧客対応の観点からも慎重な設計が求められます。
そのような背景の中で、多くの金融機関のDX推進を支援しているのが『株式会社TWOSTONE&Sons』です。当社は金融業界を中心に、事業戦略の立案からテクノロジー導入、人材育成まで一貫して支援する体制を整えています。予算確保のための準備は、知識の少ない従業員が全て揃えることは難しいでしょう。そのような企業のために、クラウド移行支援・AI活用による業務高度化・DX人材のリスキリング支援などを行っています。
公式ホームページでは、過去のプロジェクト事例や支援メニューの詳細、コンサルティングの進め方などを紹介しています。金融業界でDX推進のための予算確保に悩んでいる企業は、ぜひ一度ご相談ください。

金融業界におけるDX推進は、もはや選択肢ではなく生存戦略の一部となっています。その実現には、明確なビジョンと戦略、そして適切な予算の確保が不可欠です。
予算確保のために経営層を動かすためには、具体的なROIの提示や成功事例の紹介、実証実験の実施といった段階的かつ論理的なアプローチが重要です。全社的な巻き込みを図りながら一つずつ成功体験を積み重ねていくことが、DXの成功につながります。
DXの推進には多くの壁がありますが、専門的な支援を受けることでそのハードルを下げ、成果を最短距離で導き出せます。金融DXを自社の未来を担う成長戦略として位置づけ、確実な実行へとつなげていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
