金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

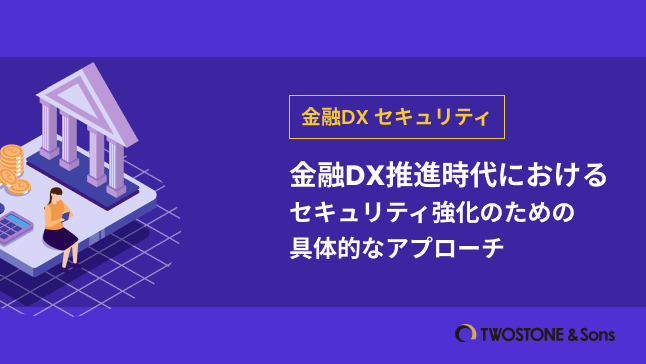
金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、業務効率化と顧客体験の向上が注目されています。しかし、同時にサイバー攻撃や情報漏えいといったリスクも増加しています。本記事では、金融DXを安全に推進するために必要なセキュリティ対策について、解説しています。
近年、金融業界では「紙とハンコ」の文化から脱却し、業務の効率化と顧客体験の向上を目指すためにデジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進んでいます。一方で、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクも増大しており、「便利さ」と「安全性」の両立が大きな課題となっています。
実際にオンラインバンキングやペーパーレス化が進む中で、不正アクセスやマルウェアによる被害が顕在化しつつあります。特に金融機関では、機密性の高い個人情報や資産情報を扱うため、わずかなセキュリティの隙が重大な信用失墜につながる恐れがあるのです。
本記事では、金融DXの推進に伴うセキュリティ強化の重要性を理解し、具体的にどのようなアプローチが有効なのかを丁寧に解説していきます。単なる理論ではなく、実務に即した対策や事例を交えて紹介するため、現場での実践に役立てることが可能です。セキュリティを確保しながらDXを安心して推進したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

金融DXを推進するにあたり、セキュリティ対策は単なる補助的な要素ではなく、根幹を支える極めて重要な要素として位置づけられています。利便性や業務効率の向上といったDXの恩恵を享受する一方で、それに伴う情報リスクやサイバー脅威の拡大は無視できません。特に金融業界では、取り扱うデータの機密性が極めて高いため、一度の情報漏洩や不正アクセスが甚大な被害と信用失墜を引き起こす恐れがあります。
では、なぜこれほどまでにセキュリティの強化が求められているのでしょうか。ここでは、セキュリティリスクが高まっている具体的な要因について、順を追って掘り下げていきます。
金融DXとは、金融機関がデジタル技術を活用して業務プロセスや顧客サービスを革新する取り組みを指します。これは単なるIT化ではなく、業務構造や企業文化の変革を伴う大規模な改革です。ここには、紙ベースの手続きをオンライン化し、データ分析を活用したパーソナライズされた商品提案を行うことが含まれます。
このような変革によって顧客の利便性が飛躍的に向上し、従業員の作業負荷も軽減されるでしょう。加えてリアルタイムでの情報把握や意思決定の迅速化を図れるため、企業全体の競争力を高める手段として期待されています。ただし、デジタル化の恩恵を享受するためには、同時に高いセキュリティレベルを確保しなければなりません。
日本の金融業界では、多くの金融機関がDXに取り組み始めています。大手銀行では、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIによる業務効率化が進み、地方銀行でも電子契約の導入やオンライン相談の体制整備が行われています。
一方で、中小規模の金融機関では、人材や予算の制約があり、DXが進まない場合もあるでしょう。また、既存のレガシーシステムとの互換性や社内の業務フローとの整合性に課題を抱えているケースも少なくありません。こうした状況下でDXを加速させるには、堅牢かつ柔軟なセキュリティ体制を構築することが前提となります。
DXによって利便性が高まる反面、サイバー攻撃の標的になるリスクも高まっています。特に金融機関はサイバー犯罪者にとって魅力的な攻撃対象であり、標的型攻撃やランサムウェアによる被害事例も年々増加しています。
さらに、リモートワークやクラウドサービスの普及によってセキュリティ管理が複雑化していることも課題の1つです。そのため、従来の境界防御型のセキュリティモデルでは、社外からのアクセスや社内の内部不正への対応が困難になっています。
このような背景から、「ゼロトラスト」や「多要素認証」などの新しいセキュリティ概念が注目され始めています。つまり、金融DXを安全に進めるには従来の考え方から脱却し、包括的かつ柔軟なセキュリティ戦略の構築が求められているのです。
参考:金融庁(ゼロトラストについて)
参考:金融庁(多要素認証について)
金融DXを進める上で、セキュリティ対策の強化は避けて通れないテーマです。しかし現実には、多くの金融機関がさまざまな課題を抱えています。最新技術の導入に意識が向く一方で、セキュリティの基盤整備が後回しになるケースも珍しくありません。
ここでは、特に金融業界に顕著な5つの課題を取り上げ、その背景と影響を明らかにします。
セキュリティ対策の根幹を支えるITインフラは、導入から10年以上が経過しているケースも少なくありません。特に勘定系システムや顧客管理システムなどの基幹システムは業務への影響が大きいため容易に刷新できず、結果として老朽化が進行しやすくなっています。
老朽化したインフラには、最新の脅威に対応する機能が不足しています。暗号化技術やアクセス制御機能が古いままであれば、サイバー攻撃の標的になりかねません。こうした脆弱性はシステム全体の信頼性を損なうだけでなく、万一の情報漏えい時には企業の信用に致命的な打撃を与えます。
そのため、クラウドベースの柔軟なセキュリティプラットフォームやゼロトラスト型のアーキテクチャへの移行が重要です。段階的な移行計画を立てることで、業務への影響を最小限に抑えながら近代化を進められるでしょう。
金融機関は高度な個人情報や取引データを扱うため、常にサイバー攻撃のターゲットとなっています。中でも懸念されるのが、不正アクセスによる機密情報の流出や改ざんです。
実際、フィッシングメールやランサムウェアといった攻撃手法が巧妙化し、従来のウイルス対策ソフトやファイアウォールだけでは対応しきれない場面が増えています。また、従業員のアカウントが乗っ取られた場合、内部からの攻撃に対しては防御が困難になる傾向があります。
これに対抗するには、ID・パスワードだけでなく生体認証や多要素認証(MFA)の導入が効果的です。アクセスログのリアルタイム監視やAIによる異常検知を組み合わせることで、より高度なセキュリティ体制を構築できるでしょう。
技術的な対策が整っていても、それを正しく運用するのは現場の従業員です。セキュリティ意識の低さや操作ミスが原因で発生するインシデントは少なくありません。特に近年はリモートワークの普及により、社外での端末使用やデータ持ち出しのリスクが高まっています。
これに対応するためには従業員1人ひとりが基本的なセキュリティ知識を持ち、適切な判断ができる環境を整えることが重要です。定期的なセキュリティ研修やシミュレーション訓練、内部通報制度の整備は有効な手段といえます。
また、単に知識を伝えるだけでなく、業務と結びつけた実践的なトレーニングを行うことで、現場に根づくリスク意識を高められます。最新のサイバー攻撃事例や内部不正のケーススタディを共有すると、当事者意識を育てられるでしょう。
金融業界では、金融庁をはじめとする監督機関からのガイドラインや国際的な規制への対応が不可欠です。特に近年は、FISC(金融情報システムセンター)の安全対策基準やGDPR(EU一般データ保護規則)への準拠など、対応すべき基準が多岐にわたっています。
これらの規制は単にセキュリティの観点にとどまらず、データの保存場所やアクセス権限、ログ管理の方法にまで及びます。そのため、社内体制の見直しや文書化、コンプライアンスの強化が必要となり、現場への負担が大きくなりがちです。
このような複雑な対応を乗り越えるためには、専門的な知見を持つ外部パートナーとの連携がカギを握ります。最新の法規制にもとづいたコンサルティングを受けることで、現行の体制に潜むリスクを洗い出し、優先順位を付けた対応策を講じられるでしょう。
参考:金融庁|金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン
近年、金融業界においてもアウトソーシングや外部クラウドサービスの活用が進んでいます。これにより業務効率は向上しますが、一方でセキュリティ管理の範囲が広がり、統制が難しくなっているのが現実です。
特に問題となるのは、外部委託先のセキュリティレベルが自社の基準に達していない場合です。万が一委託先がサイバー攻撃を受ければ、その影響は自社のサービスにも波及します。にもかかわらず、外部企業に対して継続的なセキュリティ監査を行っている企業はまだ少数です。
対策として、委託先の選定時にセキュリティ評価を必須とし、契約段階で情報漏えい時の対応ルールを明確化する必要があります。また、共同でBCP(事業継続計画)を策定し、万が一のリスクに備えましょう。
金融業界においてセキュリティ対策は、単なるIT部門の責任にとどまらず、もはや経営戦略の中核をなす重要な課題といっても過言ではありません。近年はサイバー攻撃の手口が巧妙化・高度化しており、それに対抗するには従来の延長線上にある対策では十分とはいえない状況です。
では、実際の現場でどのような具体策を講じるべきなのでしょうか。ここでは、金融機関が優先的に取り組むべき6つの実践的なセキュリティアプローチについて、詳しく紹介します。
金融機関がセキュリティ対策を強化する第一歩として、最新のセキュリティツールの導入が不可欠です。
例えば、セキュリティツールには、エンドポイント検知・対応(EDR)やネットワーク監視ツール(NDR)があります。これらは、社内外からの不審なアクセスやマルウェアの侵入をリアルタイムで検出して即座に対応することが可能です。また、セキュリティ情報・イベント管理(SIEM)を活用すると、ログの一元管理と異常検知が効率化され、複数の脅威を同時に可視化できます。
導入の際は、既存システムとの互換性を確認し、過剰投資にならないように段階的な運用が求められます。最先端のツールを導入することで、未知の脅威にも柔軟に対応できる環境を整えられるでしょう。
システムがいかに堅牢でも、人間のミスがセキュリティホールとなることは避けられません。そのため、従業員1人ひとりのセキュリティ意識を高める教育が欠かせません。
具体的には、年に1〜2回の集合研修やeラーニングを活用し、フィッシングメールの判別方法、情報持ち出しのリスク、パスワード管理の徹底などを学ばせるようにしましょう。さらに模擬的な攻撃シナリオを用いた訓練(レッドチーミング)を実施することで、実践的な対応力も養えます。
教育を形骸化させず、現場の状況や時流に応じた内容に更新することが大切です。
金融業界では一秒の遅れが致命的な損失につながるため、リアルタイムの脅威検出体制の構築は重要です。
その対策として有効なのが、AIや機械学習を活用した監視システムです。実際に、通常とは異なるトラフィックパターンやアクセス元を即座に検出して自動で遮断する技術が登場しています。また、ユーザー行動分析(UBA)を用いて従業員や顧客の平常時の行動と逸脱を比較すると、内部不正の兆候を早期に察知できます。
システムを導入することで、被害の発生を未然に防ぎ、攻撃に対する初動対応を迅速に行える体制を整備することが大切です。
クラウドサービスの活用が進む中、クラウド環境特有のセキュリティ対策が求められています。特に、データの暗号化はかかせません。
暗号化とは、データを特定の鍵で変換して第三者が内容を読み取れないようにする技術です。万が一、クラウド上に保存された顧客情報や取引記録が漏えいしたとしても、暗号化されていれば直接的な被害を抑えられます。
さらに、鍵の管理方法にも注意が必要です。キー管理システム(KMS)を導入すると、アクセス制御と監査ログの取得が自動化され、より安全な運用ができるでしょう。
セキュリティ対策は一度構築して終わりではありません。定期的な見直しと評価があってこそ、真に効果を発揮します。
まず、内部監査や外部ベンダーによるセキュリティ監査を定期的に行い、ポリシーの遵守状況や実施体制を客観的に評価することが必要です。さらに脆弱性診断では、システムやネットワークに潜むセキュリティホールを洗い出し、修正対応を迅速に行う体制が求められます。
近年では、自動化されたスキャナーツールも普及しており、月単位での診断も現実的になっています。継続的な改善を前提としたPDCAサイクルを回す意識が重要です。
金融業界では、クラウドベンダーやシステム開発会社など複数の外部パートナーと連携する機会が増えています。それに伴い、第三者によるセキュリティリスクも見逃せません。
このリスクに対応するには、まず契約時に情報管理体制を明文化したセキュリティ条項を設けることが重要です。また、定期的なセキュリティ評価や監査を義務付けることで、委託先の体制もチェックできます。
さらに、第三者リスク管理(TPRM)の専門部署を設置すると、業務委託先のリスクを一元的に管理し、全体最適を図る体制が整えられるでしょう。信頼できるパートナーシップを築くためには、互いの責任範囲と対応方針を明確にする姿勢が不可欠です。

金融業界では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が競争力強化や業務効率化の手段として注目されていますが、同時にセキュリティ強化の面でも大きな可能性を秘めています。最新の技術を活用することで、従来のセキュリティ対策では難しかった「リアルタイム性」や「予測的対応」が可能となり、より高度な防御体制を構築できるようになってきました。
ここでは、金融DXがもたらす具体的なセキュリティ強化のアプローチについて見ていきましょう。
AI(人工知能)と機械学習は、セキュリティ分野において強力なツールです。特に金融機関においては、不正取引やフィッシング攻撃などの検出に活用され始めています。
AIを活用した脅威検出では、膨大なログデータや通信トラフィックをリアルタイムで解析し、通常とは異なる振る舞いや異常なパターンを瞬時に認識することが可能です。従来のように「既知のウイルス定義」に依存するのではなく、「振る舞い」に着目してリスクを特定するため、未知の攻撃やゼロデイ攻撃への対応力が向上するでしょう。
機械学習の導入によって、システムは過去の脅威データから学習を繰り返し、次第にその精度を高めていきます。これにより誤検知を減らし、正確に本当に危険なアクティビティのみを抽出できるようになります。今後さらに多様化する攻撃に備える上で、AIの導入は避けて通れないステップといえるでしょう。
クラウドサービスの利用が拡大する中で、セキュリティリスクへの対応も複雑化しています。しかし、金融DXではこのクラウド環境においても、より強固なセキュリティ体制が求められています。
この状況下では、クラウドネイティブなセキュリティ対策が重要です。例えば、CSPM(Cloud Security Posture Management)と呼ばれる仕組みでは、クラウド環境の設定ミスや非推奨な構成を自動的に検出し、管理者に警告を出します。設定ミスが重大な脆弱性に直結するクラウド環境において、こうしたツールは欠かせません。
また、クラウド上での通信やデータ保存には、TLS(Transport Layer Security)やAES(Advanced Encryption Standard)などの高度な暗号化技術が使われます。これらのツールは、例え通信経路上でデータが盗み見られたとしても、内容を解読されるリスクを最小限に抑えることが可能です。金融業界におけるクラウド活用はセキュリティを犠牲にするのではなく、むしろ強化につなげる戦略として進化しています。
セキュリティ対策において、インシデントへの「迅速な対応」は被害の最小化に直結します。そこで注目されているのが、セキュリティオートメーションの導入です。
オートメーション化によって異常を検知した瞬間に自動でアラートを出したり、ネットワークからの隔離処理を実行したりできます。これまで人の判断を待っていた対応が秒単位で完了するようになれば、マルウェアの拡散やデータ漏えいを未然に防げるでしょう。
このための代表的なツールにSOAR(Security Orchestration, Automation and Response)があります。これは複数のセキュリティツールを統合し、シナリオに応じて自動でアクションを実行できる仕組みです。例えば、特定のIPアドレスからの不審なアクセスがあればそのIPをファイアウォールでブロックする、といった対応が自動で行われます。
また、オートメーションによってセキュリティ担当者の負担も軽減されます。人的リソースの限界がある中、機械による自動処理で対応の質とスピードを両立できる点は特に金融業界にとって大きなメリットです。
金融DXは利便性や業務効率の向上をもたらしますが、その裏には必ずセキュリティ上の課題も存在します。特に、金融機関は個人情報や資産データを扱うため、一度のセキュリティ事故が信頼の失墜につながる重大なリスクを抱えています。DXを安全に推進していくためには、技術の導入以前に慎重な準備と運用の見直しが不可欠です。
ここでは、金融DXにおけるセキュリティ対応の注意点を3つ解説します。
新たなシステムやツールを導入する際、最初に実施すべきなのが、セキュリティリスクの評価です。魅力的な機能に目を奪われがちですが、セキュリティ対策が不十分なまま運用を開始すると思わぬ脆弱性を抱えかねません。
このリスク評価には「脅威モデリング」という手法が有効です。システムの構造を可視化し、どこに脅威が潜んでいるか、攻撃経路や被害の可能性をシナリオごとに分析することで事前にリスクを洗い出せます。特に、外部APIとの通信部分や認証機構の構成、ログ管理の方法などは侵入のきっかけになりやすいため、重点的に確認する必要があります。
加えて、既存の社内システムとの連携部分にも注意が必要です。統合によって新たな攻撃面(アタックサーフェス)が生じる可能性があるため、全体のアーキテクチャを見渡した上で、適切な対策を講じましょう。
セキュリティ対策は一度策定すれば終わりではありません。サイバー攻撃の手口は日々高度化しており、時代に合わないルールのままでは効果的な防御は期待できません。したがって、定期的にセキュリティポリシーを見直し、現状のリスクに即した内容へとアップデートする必要があります。
特に注目すべきは、リモートワークやクラウドサービスの活用に伴う新たなリスクです。従業員の自宅や外出先からのアクセスが当たり前となった今、エンドポイント管理やアクセス制御の基準も柔軟に見直さなければなりません。
また、見直しに際しては経営層から現場までの意識統一が必要です。単なる文書の改訂にとどめず、全従業員に対して新方針を共有して実行可能な運用体制に落とし込むことで、ポリシーが実効性を持つようになります。
金融DXでは、クラウドベンダーや外部システム提供会社、開発パートナーなどさまざまな第三者と連携するケースが増えています。こうした関係性の中でセキュリティ事故が発生する事例も少なくありません。したがって、外部パートナーとの間でセキュリティ基準を明文化し、合意の上で運用することが重要です。
例えばSLA(Service Level Agreement)において、脆弱性対応の時間枠、インシデント報告のプロセス、ログデータの保管期間など具体的な内容を契約に含めるべきです。また、第三者によるセキュリティ監査の実施やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)取得の有無も判断材料の1つです。
自社だけが対策を講じていても、連携先が甘ければ結果的に全体のリスクが高まります。パートナー企業とのセキュリティ連携を強化することが、安全なDX推進につながるでしょう。
金融業界では、DXは推進するものであり、多くの企業がセキュリティ強化に向けて取り組んでいます。クラウド技術の導入や生体認証、ゼロトラストセキュリティなどの先進技術を積極的に推進することで、不正アクセスや情報漏えいを防ぎつつ、顧客の利便性も高めているのです。以下に、金融DXを推進しながらセキュリティ強化を実現した大手銀行の事例を紹介します。
株式会社三井住友銀行は、Microsoftとの戦略的提携により、クラウド基盤をMicrosoft Azureへ段階的に移行しています。Azure Active DirectoryやDefender、Sentinelを活用し、ゼロトラスト型のセキュリティ体制を構築しているのです。さらに社員向けにクラウドやセキュリティの研修を体系的に実施し、人的リスクを低減させています。これにより、高度な情報セキュリティを実現しているといえるでしょう。
参考:株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行では、スマホアプリにFIDO2準拠の指紋や顔認証を導入しています。パスワードに頼らず、生体情報は公開鍵暗号で保護され、サーバーに保存されないため不正アクセスが防げるのです。ワンタイムパスワードも併用し、フィッシング詐欺対策も強化しているでしょう。こうした技術により、安全かつ利便性の高い認証システムを提供しています。
参考:株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行は、ICキャッシュカードとスマホアプリで指静脈認証や顔認証といったマルチ生体認証を導入しています。これにより、従来の暗証番号や印鑑に頼った本人確認をオンライン認証に置き換えているのです。不正引き出しのリスクが大幅に減少しているといえるでしょう。富士通のFinplexサービスを基盤に採用し、高いセキュリティを実現しています。
参考:株式会社みずほ銀行
参考:富士通株式会社
金融業界におけるセキュリティ課題は、技術的・運用的な複雑性を含んでいるため、専門的な視点からのアプローチが欠かせません。セキュリティ対策に行き詰まりを感じている方は『株式会社 TWOSTONE&Sons』へご相談ください。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』は、先進的な技術知見と豊富な実績を持つITコンサルティング企業で、特にクラウド移行・セキュリティ強化・DX推進に強みがあります。公式サイトでも紹介している通り、業種特化型のDX支援や堅牢なシステム設計によって、企業のデジタル変革を安全かつ確実にサポートします。
「どこから着手すればいいかわからない」「既存システムとの統合に不安がある」「社内リソースだけでは対応が難しい」
そんなお悩みを抱える企業様は、ぜひ一度『株式会社 TWOSTONE&Sons』にご相談ください。セキュリティリスクを最小限に抑えつつ、金融DXを力強く推進するための最適なソリューションをご提案いたします。

金融DXは、単なる技術導入にとどまらず、業界全体の競争力を左右する戦略的な取り組みです。そして、その基盤を支えるのがセキュリティの強化です。
これからの金融業界が安心・安全にDXを推進していくためには、技術と運用の両輪でバランスよくセキュリティ対策を行う必要があります。そして、信頼できるパートナーとともに歩むことも、DX推進の成功への近道です。
貴社の金融DXを加速させるために、まずは信頼できる専門家に相談する一歩から始めましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
