金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

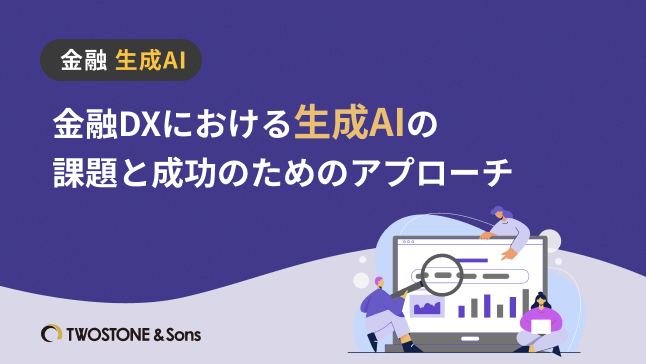
金融DXが加速する中、生成AIなどの先端技術が業務効率化やセキュリティ強化に注目されています。本記事では、金融業界における生成AIの役割や導入時の注意点をわかりやすく解説しています。
デジタル化の波があらゆる業界を飲み込む中、金融機関においても変革は待ったなしの状況です。そこで、紙ベースの業務やハンコ文化を見直して効率性と顧客満足度の向上を目指す「金融DX」が加速しています。一方で、利便性が増すほどにサイバーリスクも高まり、セキュリティ対策がさらに重要になってきました。
中でも注目されているのが、生成AIをはじめとする先端技術の導入です。これらの技術は業務効率の向上だけでなく、セキュリティの強化やリスク管理にも大きな効果をもたらします。とはいえ、新しい技術を単に導入するだけでは不十分です。どのように活用し、どこに注意を払うべきかを理解することがこれからの金融業界には欠かせません。
本記事では、生成AIの導入背景やその役割を踏まえながら金融DXとセキュリティ強化の関連性についてわかりやすく解説します。今後の業務改善やセキュリティ対策に役立つ情報を得たい方は、ぜひ最後までお読みください。

金融DXを進める上で、生成AIの活用は重要なカギを握っています。従来のデジタルツールに比べて生成AIはより柔軟かつ高度な情報処理能力があり、顧客対応の品質向上やリスク管理の高度化にも寄与しています。金融機関が今後の競争を勝ち抜くには、技術の正しい導入と活用が不可欠です。
近年、金融業界が直面している課題は、急速に進化する顧客ニーズとサイバー脅威への対応です。顧客はいつでもどこでも金融サービスを利用できる柔軟性を求めるようになっており、応えるためには24時間対応可能な仕組みが求められます。そこで注目されているのが、生成AIのチャットボットやナレッジベースです。
例えば、自然言語処理を活用したAIチャットボットを導入すれば、問い合わせ対応の効率が向上するでしょう。定型的な業務をAIに任せると担当者はより高度な対応に集中できるようになり、業務全体の生産性が高まります。さらに、これらのシステムは過去の対応履歴やパターンを学習するため、精度の高い回答や分析が可能になるでしょう。
導入の目的は単なる業務効率化にとどまりません。生成AIはリスク検知や不正取引の監視にも応用が広がっており、セキュリティレベルの底上げにも貢献します。今や生成AIは、金融機関が信頼性と効率性を両立させるための基盤技術といえるでしょう。
金融DXとは単なるIT化ではなく、業務そのものの在り方を根本から見直し、デジタル技術によって変革していく取り組みです。この取り組みの中で、生成AIが果たす役割は日々拡大しています。例えば、融資審査において過去のデータを解析して与信判断を自動化するシステムは意思決定のスピードと正確性を向上させるでしょう。
マーケティング分野でも、顧客の行動パターンや嗜好をAIが分析することで、パーソナライズされたサービスの提供が可能になります。これにより、顧客満足度の向上だけでなく、クロスセルやアップセルといった収益機会の創出にもつながるのです。
特に注目されているのは、セキュリティ面での生成AIの活用です。AIは大量のログデータやネットワーク通信をリアルタイムで解析し、不審な動きや異常なパターンを早期に検出します。AIを活用することで、従来のように事後対応に追われるのではなく、攻撃を未然に防ぐ「予防型」のセキュリティ対策が可能です。
生成AIは金融DXのあらゆるフェーズで中核を担う存在になりつつあります。ただし、効果的に活用するためには、専門的な知識と実績のあるパートナーの支援が不可欠です。生成AIの選定やカスタマイズ、運用管理に至るまで継続的なサポート体制を整える必要があります。
生成AIは多くの可能性を秘めていますが、導入を進める中ではいくつかの重要な課題が浮かび上がってきます。特に、金融機関のように高度な信頼性と透明性が求められる業界においては、各々の課題に対して戦略的な対処が不可欠です。
ここからは、生成AI導入における主なリスクとその対策を解説します。
生成AIの性能は、学習に使用されるデータの質に依存します。不正確な情報や偏ったデータをもとにした学習は、誤った判断や不公平な結果につながるリスクがあります。
特に金融機関では、信用スコアやローン審査など個人の生活に直結する判断を行う場面が多いため、データの公平性と正確性が欠かせません。偏りのあるデータを使用すれば、特定の属性を持つ顧客に対して不利な処理をするおそれがあります。
このリスクを軽減するには、学習データの段階で厳密な品質管理を実施しデータの出所や構成を継続的に検証する体制が欠かせません。また、バイアス検出ツールや第三者による監査の活用も有効です。
生成AIは大量の個人情報や金融データを扱うため、セキュリティ対策が不十分であれば重大な情報漏えいや不正利用を招く可能性があります。
特に生成AIが外部のクラウド環境で動作する場合、サイバー攻撃のリスクは高まるためです。過去にはAIモデルから訓練データが逆算される「モデル反転攻撃」が報告されており、金融データの保護は一層の注意が求められます。
このような脅威に対抗するためには、暗号化技術やアクセス制御の強化に加えて生成AIを取り巻く環境全体をゼロトラストモデルにもとづいて設計することが効果的です。さらに、AIの挙動をリアルタイムで監視して不審な動きを検出する仕組みを組み込むと、被害を抑えられるでしょう。
生成AIは高度なアルゴリズムによって動作しますが、その内部の判断過程が人間には理解しづらいという「ブラックボックス問題」があります。特に説明責任が重視される金融業界では、AIが出した結論の根拠を明確に示す必要があります。
例えば、なぜある顧客に融資が却下されたのか、理由がわからなければ、顧客からの信頼を失うばかりか法的なトラブルに発展する可能性も否定できません。
この課題に対しては、説明可能なAI(XAI: Explainable AI)の導入が求められます。モデルの予測理由を可視化する技術を活用すれば、AIの判断に納得感を与えて社内外の透明性を高められるでしょう。
金融業界には、AIの活用に対する明確なガイドラインや規制が次々と整備されつつあります。欧州のAI法(AI Act)をはじめ日本でもAIガバナンスに関する議論が進んでおり、これらに迅速に適応していく必要があります。
しかし、AI技術の進化は規制の変化を上回るスピードで進んでおり、常に最新の法令や基準に準拠する体制の維持は容易ではありません。違反が発覚した場合の社会的・経済的なダメージも大きいため、法務・コンプライアンス部門との連携が不可欠です。
対応策として、専門家のアドバイスを受けながら各国の規制動向を常にモニタリングし、生成AIの活用方法やシステム設計に反映していくことが求められます。さらに、グローバル企業であれば各国拠点での対応レベルを統一するためのポリシー整備も重要です。
生成AIの導入によって業務の効率化が期待される一方で、現場の従業員からは「自分の仕事が奪われるのでは」という不安が生まれる場合があります。また、AIを活用するには一定のITリテラシーが必要となるため、導入初期には操作ミスや誤解によるトラブルが発生しやすくなります。
このような心理的障壁を取り除くためには、単にツールとして導入するのではなく、従業員1人ひとりがAIを理解して業務に活かせるようにする教育体制が重要です。AI研修や社内勉強会の開催に加え、実際の業務に即したトレーニングプログラムを用意することで、導入の効果を高められるでしょう。
また、AIは従業員の仕事を奪うものではなく、煩雑な作業を減らして人間ならではの判断力や対人スキルを発揮するための支援ツールであるという意識の醸成も、長期的な定着には欠かせません。
金融業界におけるDXは、単なるシステムの入れ替えではなく、業務のあり方そのものを見直し、競争力を高めていくための取り組みです。こうした動きの中で、さまざまな業務の効率化や高度化を支える技術のひとつとして、自然な形で活用が広がっているのが生成系のツールや仕組みです。その中核を担う技術として、生成AIへの注目が高まっています。ここでは、金融DXの実現に向けて生成AIが特に活用されている代表的な業務を3つ紹介します。
マーケティング業務の高度化と効率化に大きく貢献します。たとえば、顧客データや取引履歴をもとに、個別に最適化された広告コピーやメール文章を自動で作成できます。これにより、従来の一斉配信ではなく、顧客一人ひとりの興味関心に沿ったアプローチが可能です。
また、WebサイトやSNSのコンテンツ制作にも活用でき、A/Bテスト用のコピーやバナー案を短時間で複数用意できる点は大きな強みでしょう。さらに、キャンペーンの反応予測や効果分析にも役立ち、マーケティング戦略全体の精度向上が期待されます。
カスタマーサポートの分野でも、生成AIは重要な役割を担い始めています。具体的には、チャットボットによる24時間体制の問い合わせ対応や、問い合わせ内容の自動分類、回答文の作成などが挙げられます。これにより、対応スピードが向上するだけでなく、オペレーターの業務負担も軽減されるのです。
さらに、顧客の感情分析も可能で、不満や疑問を察知して適切なタイミングで有人対応に切り替える仕組みも整っています。多言語対応にも柔軟に対応できるため、グローバル展開を進める金融機関にとって有用なソリューションです。
金融業界では、業務レポートや会議資料、投資分析報告書など、文章作成にかかる工数が膨大です。生成AIを導入することで、定型的な文書の下書きを自動生成し、担当者は確認と編集に集中できるようになります。これにより、文書作成の生産性が飛躍的に向上するのです。
また、会議音声の文字起こしや要点の自動要約といった機能も実用化されており、議事録作成の効率化にも貢献しています。加えて、法令遵守や情報の正確性を担保するためのコンプライアンスチェック機能と組み合わせれば、品質とスピードを両立した文書作成が可能になるでしょう。
生成AIの活用は単なる業務効率化を超え、顧客体験の向上や新たなサービス創出といった観点からも注目されています。特に金融業界では、膨大なデータを扱い正確性とスピードが求められる中で、生成AIの導入が加速しています。
ここでは、主要な金融機関における導入事例、それぞれの取り組みがもたらす実際の効果や課題について整理していきましょう。
三菱UFJ銀行では、2024年10月に生成AIを活用した社内業務支援ツールを導入しました。このツールは、従業員が作成する文書の下書きや法令にもとづく説明文のドラフト生成に用いられており、主にバックオフィス部門での作業時間短縮を目的としています。
実際に導入後、月間200件以上の業務が自動化され、従業員の作業負担が軽減されました。さらに、社内文書の品質を一定に保ちつつ法務・リスク管理部門によるチェックもスムーズになったという報告があります。今後は営業部門への展開も検討されており、生成AIが全社的な業務効率化のカギを握ると見られています。
参考:三菱UFJ銀行
みずほ銀行では、2023年より生成AIを用いたお客様対応の自動化に取り組んでいます。特に注目すべきは、FAQの自動生成や問い合わせ対応文のテンプレート作成への応用です。これによりオペレーターの応答時間が平均で20%以上短縮され、対応品質の均一化にも寄与しています。
また、社内では開発部門がプログラミング作業に生成AIを活用する動きも進んでおり、コードレビューの効率化やテストケースの自動生成といった高度な用途にも拡張が期待されています。このように、みずほ銀行では業務の多様な領域においてAI活用を推進しており、今後の全社展開に向けた基盤作りが進められているのです。
参考:みずほ銀行
楽天銀行では早期からチャットボットによる顧客対応を導入しており、2024年には生成AI技術を統合した新しいチャットシステムへと進化させました。従来型のチャットボットと異なり、ユーザーの入力意図を文脈から理解したより自然な応答が可能です。
例えば、複雑な振込手続きに関する問い合わせでも、AIが段階的に案内を行い、ユーザーが迷うことなく操作を完了できるようサポートします。導入後の調査では、ユーザー満足度が従来比で約1.4倍に向上し、問い合わせ件数そのものも減少するという好循環が生まれています。
参考:楽天銀行
ソニー銀行では、2024年9月に生成AIを活用したローン審査補助システムの運用を開始しました。従来、人間の担当者が判断していた与信情報の分析にAIを活用することで、申請から審査完了までの時間が平均で30%短縮されました。
このシステムでは、過去の膨大な審査データをもとにAIがリスク分析を行い、審査担当者に対して合理的な判断材料を提示します。最終的な判断は人間が行うものの、事前準備の負担が軽減されてより迅速かつ的確な与信判断が可能となりました。今後は住宅ローンだけでなく、その他のローン商品への展開も視野に入れています。
参考:ソニー銀行
野村證券では、2025年4月に生成AIを活用したリサーチレポート作成支援システムを導入しました。アナリストが収集したマーケットデータや企業情報をもとにAIが初期ドラフトを作成し、それをもとに人間が仕上げるというプロセスです。
このシステムの導入によって1本のレポート作成にかかる時間が従来の半分以下となり、アナリストはより高度な分析や顧客対応に時間を割けるようになりました。また、AIが複数の視点から仮説を提示するため、新たな投資観点の発見にもつながるという副次的効果も報告されています。
参考:野村證券

金融機関が生成AIを導入して成果を上げるには、単にツールを導入するだけでは不十分です。業務に適したAIを選定し、それを活用するための組織体制や人材育成、データ環境の整備までを視野に入れた全体設計が必要になります。
ここでは、導入を成功へと導くための5つのステップを順に解説します。
最初に行うべきは、現行業務の徹底的な棚卸しです。どの業務が時間やコストを多く消費しているか、どの作業に人的リソースが集中しているかを把握しなければAI導入による改善効果を正しく見積もることはできません。
例えば、定型的な文書作成・FAQ対応・社内報告資料の作成などは生成AIによって自動化できる可能性が高い分野です。反対に、判断や交渉を必要とする非定型業務は今のAIの性能では完全な自動化は難しいため、候補から外す判断も必要になります。
生成AI導入の成否は、導入目的と目標の設定に左右されます。目的が曖昧なままでは技術選定や業務設計の方針もぶれてしまい、結果的に「何を達成したかったのかわからない」という事態になりかねません。
「問い合わせ対応のスピードを上げたい」「社内文書の品質を標準化したい」「新人研修を効率化したい」といったように、明確な課題意識を持つことが重要です。そこから逆算する形でKGI(最終目標)やKPI(中間指標)を設定すれば、プロジェクトが迷走するリスクを抑えられるでしょう。
また、経営層・現場・IT部門それぞれの視点を取り入れ、全社的な合意形成を図ることも大切です。目的が共有されると現場の協力を得やすくなり、導入後の運用もスムーズに進みます。
生成AIの性能は、与えるデータの質と量によっても左右されます。導入前にまず確認すべきは、社内にどのようなデータが存在し、どのような形式で保存されているかという点です。特に、文書データやFAQデータ、問い合わせ履歴など言語処理に関連する情報が整備されているかが重要なポイントです。
実際、多くの企業ではデータが各部門に分散していたり形式がバラバラだったりするため、導入初期においてはデータ統合とクリーニング作業が必要になります。また機密情報や個人情報を含むデータについては、匿名化処理やアクセス制御を適切に行い、コンプライアンスを遵守する姿勢が求められます。
さらに、AIに学習させるデータだけでなく、継続的にパフォーマンスを監視するための評価用データセットも準備しておくと導入後の効果検証が容易になるでしょう。
市場にはさまざまな生成AIソリューションが存在しますが、業種や業務内容に応じて適切なAIを選ぶことが不可欠です。汎用的な大規模言語モデル(LLM)をそのまま利用するのか、業務に特化したカスタムモデルを構築するのかによって必要なコストや開発体制が異なってきます。
機密情報を扱う金融業界では、外部クラウドを避けてオンプレミスでの運用を求める場合も多いです。その際には、セキュリティ要件を満たすモデルであるかを確認する必要があります。さらに、業務固有の専門用語や文体に対応させるには、追加学習(ファインチューニング)やプロンプト設計といった技術も活用する必要があるのです。
実務での活用を想定するのであれば、AIベンダーとの連携やPoC(概念実証)を実施して業務適合性を事前に確認しておくとリスクを軽減できるでしょう。
導入後の成功には、技術面だけでなく「人」の理解と活用能力が欠かせません。AIを効果的に使いこなすには、利用者がAIの仕組みや限界を理解して適切に指示を与えるスキルが求められます。
そのためには、社内研修やハンズオン形式のトレーニングを定期的に実施し、利用部門の担当者が自信を持ってツールを活用できるように支援する必要があります。また、現場からのフィードバックを収集し、AIの出力結果が業務に即しているかどうかを随時見直していく体制も不可欠です。
さらに、AI導入後も運用状況をモニタリングし、不具合や誤動作に迅速に対応できる保守体制を整備しておくことが安定稼働のカギになります。IT部門だけでなく、現場と連携しながらPDCAサイクルを回すことは生成AI活用の定着を支える柱となるでしょう。
金融業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、競争力の維持と顧客満足度の向上に直結するものです。その中で生成AIは、業務の高度化と変革を支える革新的なテクノロジーとして注目を集めています。
ここでは、生成AIが金融DXを後押しする理由を具体的に解説します。
生成AIは、大量のデータ処理や書類作成など反復的な事務作業を自動化する力を持ちます。例えば顧客対応において、AIが問い合わせ内容を解析し、適切な回答案をリアルタイムで生成します。これによってオペレーターは確認や調整に集中でき、対応速度と精度の向上が見込めます。業務効率化が進むことで、人的リソースをより付加価値の高い業務へ振り向けられるでしょう。
金融商品やサービスは顧客1人ひとりのライフスタイルや資産状況に応じた対応が求められます。生成AIは、顧客の属性データや過去の取引履歴をもとに最適な提案を自動生成できます。例えば保険や資産運用の提案において、ユーザーに合わせたシナリオを提示することで、納得感のある選択を後押しできるでしょう。パーソナライズされた体験は顧客満足度の向上に寄与し、継続的な関係構築にもつながります。
金融業界では、為替や株式などの市場変動に対して迅速な判断が不可欠です。生成AIは大量のニュース記事やSNS投稿を瞬時に解析し、トレンドやリスク要因を抽出する機能を備えています。意思決定者が正確かつ迅速な対応をするためには、最新情報の共有が欠かせません。リアルタイムでのインサイト提供により、企業全体の判断力が高まり、競争優位性を維持しやすくなるでしょう。
手作業で行われていた審査業務や契約書の作成なども、生成AIの導入によって自動化が進んでいます。例えば、ローン申請時の信用スコア分析やコンプライアンスチェックにAIを活用することで、作業のスピードと正確性が上がるでしょう。これにより、人為的ミスの削減と運用コストの削減が実現できます。
金融機関にとって、リスクの予測と回避は極めて重要です。生成AIは過去のデータパターンを学習し、信用リスクや市場リスクの兆候を早期に察知する役割を果たします。さらに、自然言語処理によって規制文書の内容を正確に読み取り、コンプライアンス違反の可能性を提示する機能も強化されています。これにより、企業はリスクに対して先手を打つ運用がしやすくなるのです。
生成AIの導入は大きな変革をもたらす一方で、データの扱いや運用設計には高度な知識と実績が求められます。『株式会社 TWOSTONE&Sons』は、企業のDX推進に伴走し、戦略立案から導入支援、運用保守までをワンストップで提供しているプロフェッショナル集団です。
特に生成AIの領域では、ChatGPTをはじめとする最新技術のビジネス活用に精通しており、企業ごとの業務プロセスや課題に応じたカスタマイズが可能です。さらに、コンプライアンスやセキュリティに配慮した設計で、安全なAI導入を支援しています。
「生成AIを導入したいが、どこから着手すべきかわからない」「自社に合った使い方を模索している」という課題をお持ちの企業は、ぜひ一度ご相談ください。

生成AIは、金融業界におけるDXを加速させるカギとなる存在です。業務効率化・パーソナライズ対応・迅速な意思決定支援・業務自動化、そしてリスク管理の高度化まで多方面でその効果が期待されています。これからの時代、生成AIを活用できる企業こそが変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実現できるでしょう。
導入に際しては、自社に適した戦略設計と信頼できるパートナーの存在が不可欠です。『株式会社TWOSTONE&Sons』のような専門家の支援を受けながら、生成AIの可能性を最大限に引き出していきましょう。行動に移す一歩が未来を変える第一歩になります。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
