金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

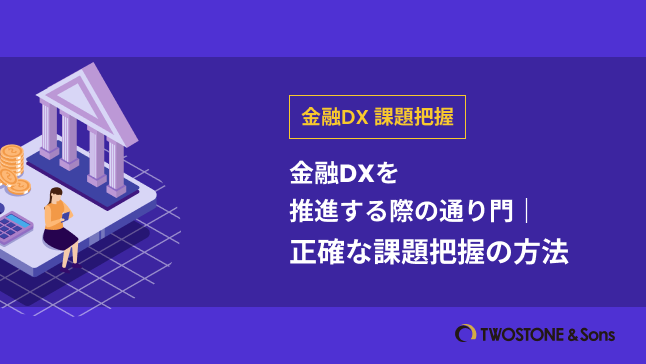
金融DXにおける現状課題の把握や業務改善、人材スキル育成、経営層への提案ポイントまでを網羅的に解説しています。DX推進を成功させたい金融機関の担当者さま必見の内容です。
「金融DXを進めたいが、何から手を付ければいいのかわからない」——
そう感じたことはありませんか。多くの金融機関がデジタル化の波に直面する中、DXを推進する目的が曖昧なままプロジェクトが動き出し、結果的に現場に定着しないケースが増えています。最大の原因は「自社の課題を正確に把握できていないこと」にあります。方向性を誤れば、どれほど最新の技術を導入してもその効果は限定的です。
この記事では、金融DXを成功に導くために欠かせない「課題把握」の重要性とその具体的な方法を5つのステップに分けて詳しく解説します。読み進めていただくことで組織内の課題を明確にし、DXの方向性に自信を持って取り組めるようになるでしょう。

金融DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にIT技術を導入するだけではなく、デジタルの力を活用してビジネスモデルや業務プロセスを根本的に変革して顧客体験の向上や競争優位性の確立を目指す取り組みです。例えば、オンラインバンキングの導入やAIによる融資審査の自動化など、業務効率と顧客満足の両立を実現する手段として注目されています。
特に金融業界では、レガシーシステムの維持費や人手に依存するオペレーションが課題とされており、DXによる改革が急務です。しかし、単なるシステム刷新では本質的な変革には至りません。成功のカギは、自社の課題を深く理解してその解決策をデジタルの力で導き出すことにあります。
金融DXを成功させるためには、出発点となる課題を明確にする必要があります。課題把握が不十分なまま進めると方向性を誤り、せっかくの投資が無駄になるリスクもあります。
最初に必要なのは、現状の業務やシステムの状況を正しく把握することです。現在の問題や制約を理解しなければ、どの領域にデジタル技術を適用するべきかが見えてきません。顧客対応のスピードが遅い原因がオペレーションの複雑さにあるのか、それともシステムの応答時間にあるのかを把握することで、改善の優先順位が明確になります。
正しい方向性が定まれば、プロジェクトの無駄を省いて限られたリソースで最大の効果を発揮できるでしょう。
次に重要なのは、業務プロセスに存在するボトルネックの特定です。手作業で行われている処理や、部署間での情報伝達の遅れが業務全体の効率を下げているケースが少なくありません。ボトルネックを定量的に把握することで、どの業務を優先的に自動化・効率化すべきかが見えてくるでしょう。
プロセスマイニングや業務フロー分析などの手法を活用すれば、改善点をデータとして捉えられ、納得感のある改革が可能となります。
課題の明確化は、経営層だけでなく現場の意識改革にも直結します。現場のメンバーが「なぜ今この業務を変える必要があるのか」を理解すれば、改革に対する抵抗感は下がるでしょう。逆に目的が見えないまま変化だけを求められれば、DXは失敗に終わる可能性が高まります。
課題意識を組織全体で共有することは、DX推進のスピードと質を左右する重要な要素です。
では、どのようにして社内の課題を明確にすればよいのでしょうか。ここからは、具体的な5つのステップを順に紹介します。
まず着手すべきは、経営層が掲げるビジョンと現場の実態とのギャップを明らかにすることです。例えば「3年以内に顧客満足度を20%向上させる」という目標がある場合、それに必要な施策がどれほど進んでいるのか、現場がそれを意識して業務を行っているのかを確認する必要があります。
目指すべき未来と現状の乖離を定量的に可視化することで、取り組むべき改革領域が見えてくるでしょう。
次に、部署ごとの業務フローを整理して全社的なプロセスとして統合する作業が求められます。金融業界では、支店業務・融資・審査・カスタマーサポートなどが縦割りで動いていることが多く、部門を越えた連携の中で見落とされている課題が潜在しています。
業務フローを図式化し、プロセス間のつながりや重複、遅延箇所などを明らかにすることで、ボトルネックの把握と改善計画の立案がスムーズになるのです。
次に実施したいのが、現場の声を聞くためのヒアリングです。業務プロセスは形式上整っていても、実際には「非公式な手順」や「裏ルート」で対応しているケースも多く存在します。そうした“現場ならではの実情”は、トップダウンでは把握しきれません。
ヒアリングでは、各部門の代表者や実務担当者に対して具体的な業務内容や課題感を確認し、文書化することが重要です。これにより、机上の理論だけでなく実際の運用に基づいた改善施策が検討できるのです。
改革を進める上で欠かせない視点が、人材のスキルとデジタルリテラシーの把握です。どれほど高度なシステムを導入しても、現場が使いこなせなければ意味がありません。特にベテラン層が多い金融業界では、ツールへの抵抗感や操作ミスによるトラブルが発生しやすいため、事前の評価が不可欠です。
評価の方法としては、アンケート調査や実技を含むテストの実施、研修履歴の確認などが有効です。こうした取り組みにより、教育体制の整備や支援体制の構築がスムーズになるでしょう。
最後に、これまで集めた情報を基に課題を構造化して経営層に対してわかりやすく共有します。課題を単発的に羅列するのではなく、「戦略的課題」「業務課題」「技術的課題」などカテゴリ別に整理することで、意思決定が加速するでしょう。
また経営層に提示する際には、課題に対してどのようなデジタル施策が考えられるのか、ROI(投資対効果)やリスクも併せて説明すると、より現実的な議論が展開されます。
金融機関がDXを進める際には、単なる業務のデジタル化にとどまらず、経営ビジョンに基づいた戦略設計が求められます。特に近年は、顧客中心主義の浸透によってサービス提供の在り方そのものを再定義する動きが加速しています。経営層が目指すべき未来像を明確に持ち、それに連動するかたちでDXを推進することが競争優位性の確立には不可欠です。
顧客体験(Customer Experience:CX)の質が、金融機関のブランド価値や選ばれる理由に直結する時代です。従来のように「店舗に来てもらう」スタイルから「いつでもどこでも利用できる」サービスへの移行が進んでいます。
例えばスマートフォンでの口座開設やローン審査、チャットボットによる24時間対応といった非対面チャネルの拡充は、利便性を高めるだけでなく顧客満足度や信頼度の向上にもつながります。これにより利用頻度の向上や他サービスへのクロスセルも期待でき、収益機会を広げる結果となるのです。
こうした顧客体験向上の取り組みを支えるためには、データ分析やAIを活用したパーソナライズ戦略、UI/UXの洗練された設計が欠かせません。サービスに「感動」や「気づき」を加える姿勢が他社との差別化を生む大きなポイントとなります。
金融機関にとってDX推進は成長へのチャレンジである一方、システムの堅牢性や法令遵守といった「守り」の強化も重要な要素です。したがって、安定性と成長性をバランスよく追求する「バランス型経営戦略」が注目されています。
このような戦略では、新技術の導入やサービス刷新と同時に既存インフラの信頼性向上やセキュリティ強化も両立させます。例えば、クラウド基盤への移行により柔軟性を確保しつつ、ゼロトラストセキュリティの考え方で内部統制を徹底するといった手法が効果的です。
また、ガバナンス体制の見直しやリスク管理の高度化も不可欠です。経営層が積極的に関与しIT戦略と経営戦略を一体化させることで、変化に柔軟に対応しながらも堅実な事業運営が可能になります。
テクノロジーの積極的な導入は、金融DXを加速させる推進力となります。AIやRPA、ブロックチェーン、クラウドといった技術は単なる業務効率化にとどまらず、イノベーションの源泉として金融機関の競争力を高めています。
例えば、RPAを導入することで定型業務の自動化が進み、人的リソースをより付加価値の高い業務へとシフトさせられるでしょう。またAIを活用した信用スコアリングは、従来では融資判断が難しかった層へのアプローチを可能にし、収益の多様化に貢献します。
さらに、ブロックチェーン技術による決済の即時化やスマートコントラクトの導入により、信頼性の高い取引環境の構築も現実的になってきています。これらの技術活用は、顧客に対する新たな価値提供のみならず、業界全体の枠組みに変革をもたらす可能性を秘めているのです。

DXを推進する上で、業務フローの最適化は欠かせない要素です。多くの金融機関では、依然としてアナログな業務慣行や部門間の連携不足、情報共有の不十分さが存在しており、これが生産性や顧客対応力の低下を招いています。これらの課題を明確にし、段階的な改善を図ることが、真の意味でのDX成功へとつながります。
デジタル化が進む中でも、金融機関の現場では紙の申請書類や電話でのやり取りが根強く残っているケースが多く見られます。これにより、手続きの迅速性や正確性に課題が生じ、顧客の不満や業務の非効率化につながっています。
例えば住宅ローン申請や口座開設といった手続きで、紙の書類の提出を求められたり窓口に出向かなければならなかったりする場面は、依然として少なくありません。こうした従来型プロセスは顧客側の負担を増やすだけでなく、社内でも人手による確認作業が必要となり、全体のリードタイムを延ばす要因となります。
この課題に対処するためには、申請から承認、契約までを一貫してオンラインで完結させる仕組みの導入が有効です。ペーパーレス化によって記入ミスの削減やトレーサビリティの向上も期待できます。
金融機関においては複数の部署が連携して業務を遂行する必要がありますが、その情報の連携が不十分な場合、業務フローに停滞が発生します。顧客情報の更新が営業部門で完了していても、それがリスク管理部門や融資部門に反映されていなければ判断ミスや処理の遅延が発生しかねません。
このような「サイロ化」は組織の柔軟性を奪い、迅速な意思決定を妨げます。そうならないために各部門が保有するデータを統合し、リアルタイムで情報共有できる環境を整備しましょう。ERP(統合基幹業務システム)やCRM(顧客関係管理)といったシステムを連携させ、部門を越えて共通の情報基盤を構築するといった手段があります。
顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応するには、担当者が必要な情報にすぐにアクセスできる状態でなければなりません。しかし実際には、情報が分散管理されていたり属人的に管理されていたりと、対応に時間がかかるケースが多く存在します。
顧客との過去のやり取りや契約履歴、対応履歴が別々のシステムや紙ベースで管理されている場合、確認に時間を要するだけでなく誤った情報提供のリスクも高まるでしょう。このような状況は、顧客満足度を損なう可能性があります。
対応策としては、情報を一元管理して検索性やアクセス性を高めるIT基盤の整備が挙げられます。加えて、顧客接点を持つ全ての部門で情報をリアルタイムに更新・共有できる運用体制を整えることも不可欠です。これにより、顧客ニーズに迅速かつ的確に応えられ、信頼関係の構築にもつながるのです。
DX推進において見過ごされがちなのが、実際に業務を担う従業員の視点です。現場のリアルな声を収集し、業務上の非効率や改善の余地を明らかにすることで、より実効性の高いDX戦略を描けるのです。
ここからは効果的なヒアリング手法を紹介しながら、業務課題の見える化をどう実現するかについて解説します。
個別インタビューは、従業員の業務に対する悩みや改善提案を深く掘り下げるための有効な手段です。特に現場の担当者は日々の業務の中で感じる非効率やボトルネックに敏感であるため、直接意見を聞くことで表面化しにくい課題が浮き彫りになります。
インタビューを実施する際は事前に目的を明確にし、質問項目を準備しておきましょう。また、相手の発言を否定せずに傾聴する姿勢を持つと、率直な意見を引き出しやすくなります。「手続きに時間がかかる理由は何か」「他部署との連携で困る場面はあるか」といった具体的な問いかけは効果的でしょう。
匿名アンケートは、従業員が本音を伝えやすい環境を提供する手法として有効です。特に職場の上下関係や人間関係が影響する職場環境では、個別面談では得られない意見が集まりやすくなります。
アンケートを作成する際は自由記述式と選択式をバランスよく取り入れ、具体的な業務内容や改善希望についての回答を促しましょう。結果は集計・分析した上で全体にフィードバックを行い、「意見が反映された」と実感してもらうことが信頼構築につながります。
個別インタビューやアンケートだけでは把握しづらい部門間の連携課題を明確にするには、対話型ワークショップの導入が効果的です。複数の部門から従業員が集まり、課題やアイデアを共有することで、組織を横断した改善の糸口を見つけることができます。
ワークショップでは、現場で実際に発生している課題をテーマとして取り上げ、グループディスカッション形式で意見を出し合います。ホワイトボードや付箋などを使って意見を可視化すると、参加者全体で共通認識を持ちやすくなるでしょう。
こうした場を定期的に設けることで、業務改善への関心が高まり、DXを推進するための土台が徐々に築かれていきます。
DX推進を成功に導くカギは、テクノロジーだけではありません。従業員一人ひとりがデジタルリテラシーを高め、変化に柔軟に対応できるスキルを身につける必要があります。
ここでは、金融業界において求められるスキルセットとその習得方法について紹介します。
まず必要なのは、業務で使用するシステムやツールの基本的な理解です。これにはExcelや業務管理システムの操作だけでなく、クラウドやAIといったテクノロジーの基礎的な概念も含まれます。
デジタル技術は日進月歩で進化しているため、継続的な学習が不可欠です。オンライン研修や社内勉強会を活用し、日常業務とリンクさせながら学べる環境を整備することで、学習効果が高まります。また、実践を通して知識を定着させる機会を増やすようにしましょう。
システム開発やDX導入においては、IT部門と現場担当者の橋渡し役が欠かせません。この役割を果たすには、専門用語をわかりやすく翻訳し現場のニーズを正確に伝えるコミュニケーション能力が求められます。
実際の現場では「要件定義が曖昧だったために、期待通りのシステムが導入されなかった」といったトラブルが起こりがちです。こうしたミスを防ぐには、ヒアリング力や要約力を備えた人材の育成が必要です。OJTに加え、ケーススタディやロールプレイを通じたトレーニングを行いましょう。
急激な社会変化や顧客ニーズの多様化に伴い、金融業界でも柔軟な対応力が求められています。そのためには従業員自身が主体的に学び続ける姿勢を持ち、変化を前向きに捉えるマインドが不可欠です。
自律的な学習文化を育むためには、組織としてのサポート体制も重要です。資格取得支援や社内ナレッジ共有制度の導入など、学ぶ意欲を後押しする仕組みを整えましょう。モチベーション維持のためには、目に見える成果や上司からのフィードバックも有効です。
DXを実行に移すには、現場レベルでの改善だけでなく経営層の理解と意思決定が不可欠です。そのためには、経営層に納得してもらえる形で提案を行う必要があります。
ここでは、経営判断を促す提案方法を具体的に紹介します。
経営層に対しては、主観的な意見だけでなく、客観的なデータと組み合わせて伝えることが重要です。例えば「月に〇時間の工数削減が見込まれる」「顧客満足度が〇%向上する可能性がある」といった数値を用いると、提案の説得力が増すでしょう。
さらに、現場からの声や具体的な事例を添えると提案のリアリティが高まり、実行のイメージがしやすくなります。数字と実態の両面から支える資料を用意することが、成功への第一歩です。
提案内容が、どのような経営課題に対応し、どのような成果をもたらすのかを明確に伝えることは不可欠です。目的が曖昧なままでは、経営層の優先順位に入らず、提案が棚上げされてしまうリスクがあります。
たとえば、「業務効率化によって人件費を削減できる」「顧客対応の質が向上し、離脱率の低下が期待できる」といったように、経営に直結する効果を具体的に示す必要があるでしょう。目的と成果の因果関係を明確にし、納得感のある構成で伝えることが重要です。
提案を採用してもらうには、実行可能な計画がセットになっていることが前提です。具体的なスケジュールや予算、必要な人員などを明示すると、「これなら始められる」と感じてもらいやすくなります。
また、短期・中期・長期と段階的に成果を出す設計にすると、リスクを分散しながら着実に進められるでしょう。さらにPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回す仕組みを組み込むと、継続的な改善が可能となります。
金融業界のDXは、単なるIT化ではなく、経営と業務の両面からの見直しが求められます。現場の声を反映した提案、組織の特性に応じた改善施策、そして人材育成までを含めた全体最適が必要です。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、金融業界に特化したDXコンサルティングを行っております。業務改善の現状把握から課題抽出、具体的な解決策のご提案まで一気通貫でサポートいたします。DX推進に悩むご担当者さまは、ぜひお気軽にご相談ください。

金融DXを成功に導くためには、現場の課題を的確に把握し従業員の声を活かした改善が不可欠です。そのためには、ヒアリングやアンケート、ワークショップなどを通じて業務の可視化を図り、同時に人材のデジタルリテラシー向上にも取り組む必要があります。
さらに経営層への提案においては、数字と現場感を融合させた説得力ある構成が求められます。『株式会社TWOSTONE&Sons』では、そうした複合的な課題に対応できる支援体制を整えております。金融DXを成功させる第一歩として、ぜひ私たちにご相談ください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
