金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

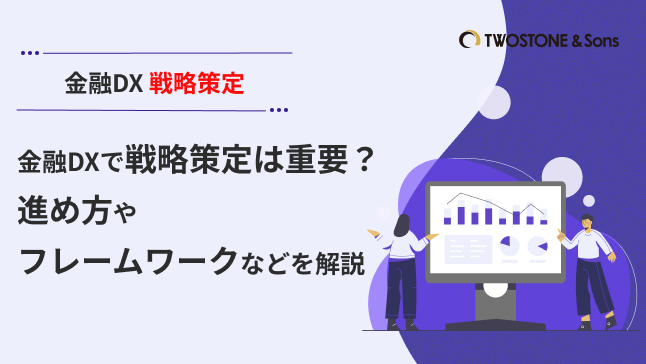
金融DXにおいて戦略策定は全社的なビジョンの構築や業務の効率化、顧客満足度の向上などのために重要な要素です。金融DXで戦略策定をする際は、達成すべきビジョンを定める、DXに取り組む領域を決めるといったステップで進めていきましょう。
金融業界におけるDXは、単なる技術の更新にとどまらず、企業全体の成長戦略に深く関わる重要な取り組みです。
DXを推進することで、業務効率の向上だけでなく、顧客満足度の向上やセキュリティ対策の強化、そして規制遵守の徹底など、多方面での改善が期待できます。結果として、企業は持続的な競争優位性を確立できるでしょう。
変革を成功させるには、明確なビジョンの策定やリソースの最適な配分、人材の確保と育成といった戦略的ステップが欠かせません。
これらを適切に進めることで、新たな技術を効果的に活用し、変化の激しい市場環境にも柔軟に対応できるようになるでしょう。
本記事では、金融DXにおける戦略策定の重要性と具体的なステップについて解説します。

金融業界は競争が激化し、テクノロジーの進化が急速に進む中で大きな変革の時を迎えています。
このような金融業界を取り巻く環境が変化する時代において、金融機関が持続的に競争優位性を維持するには、戦略的なDXの実施が求められます。
戦略策定が重要な理由は、次のとおりです。
金融業界におけるDXは、データ活用・顧客サービス・セキュリティ対策・規制遵守など、企業の基盤となる多岐にわたる分野に影響を与えるため、戦略策定でDXの方向性を明確にしましょう。
金融DXで戦略策定をする際は次のようなステップで進めていくのが一般的です。
それぞれのステップを詳しく解説します。
金融DXを進めるにあたり、まず明確にしておきたいのが「何を達成するのか」というビジョンです。
例えば、顧客中心のサービスの提供、効率的な業務プロセスの構築、セキュリティの強化、データ活用による意思決定の改善など、具体的な目標を掲げることが挙げられます。
ビジョンを設定する際には、現状の業務課題・市場の動向・競合他社の動きなどを総合的に分析し、どの領域において最も価値を生み出せるかを考えることがポイントです。
また、ビジョンは企業の上層部だけでなく、社員全員が共感できる内容にする必要があります。
明確なビジョンがあればスタッフの協力が得やすくなり、戦略の実行もスムーズに進むでしょう。
次に、どの領域に焦点を当てて取り組むのか決定しましょう。
金融機関におけるDXの主な領域は次のとおりです。
領域 | 概要 |
顧客体験の向上 | 顧客との接点をデジタル化し、利便性の高いサービスを提供する |
業務の効率化 | RPAやAIを活用して、日常業務を自動化し、コスト削減を実現する |
データ活用 | ビッグデータやAIを活用し、より効果的なマーケティングにつなげる |
セキュリティ強化 | サイバー攻撃や情報漏洩を防ぐための強固なセキュリティ対策を導入する |
金融DXの対象領域は多岐にわたるため、リソースの成約を踏まえながら、どこに最も注力すべきかを慎重に検討してください。
金融DXを成功させるためには、適切な人材の確保が不可欠です。
デジタル技術に精通したIT部門のスタッフだけでなく、データサイエンティストやAIの専門家、顧客体験に詳しいマーケティング担当者など、各分野における多様な知識を持つ人材が求められます。
また、人材だけではなく社内体制も整備する必要があります。
DX専任のプロジェクトチームを結成し、部門間での連携を強化しましょう。
チームは、戦略策定から実行に至るまで、各部門と協力しながら進めていくのがポイントです。
さらに、全社員がDXを理解し、意欲的に取り組むようにするための社内教育や啓発活動も実施しましょう。
戦略を具体的な成果につなげるためには、アクションプランを明確にすることが欠かせません。
目標達成までのタイムライン・予算・必要なリソース・担当者などを整理し、実行可能な計画に落とし込んでください。
例えば、顧客体験の向上を目指す場合、どの顧客接点をデジタル化するか、どのようなツールを導入するか、サービスの改善にどの程度の投資が必要かを明確にします。
また、業務効率化ではRPAやAIの導入準備・社員研修・モニタリングの方法などを具体的に検討しましょう。
また、これらのアクションを実行するためのプロセスも整理し、誰が何をいつまでに行うのかを明確に定義することで、プロジェクトをスムーズに進めることが可能になります。
金融DXの戦略策定は、単発の取り組みではなく、継続的な改善が求められます。
そのため、定期的な評価を続けましょう。
データを活用して戦略の進捗状況や成果を測定し、必要に応じて見直すことも大切です。
また、企業内外のフィードバックを反映させながら、改善策を実施していきましょう。
新しい技術や市場環境は日々変化しているため、柔軟に対応できるように改善のサイクルを回し続けることで、長期的な成功へとつながるでしょう。
金融機関がDXの戦略策定した事例として以下が挙げられます。
それぞれの事例を詳しく解説します。
株式会社横浜銀行では令和6年8月にDX戦略を策定しました。
DX戦略を策定することで、地域に根差すインフラ機能のひとつとしての金融サービスの提供にとどまることなく、デジタル技術を用いたサービス提供を目指しています。
具体的には、従来活用しきれていなかったデータを積極的に利活用し、顧客に新たな価値を提供できるように取り組んでいます。
このような取り組みを受けて、同社では令和6年11月に情報処理の促進に関する法律第31条の規定に従い、経済産業大臣よりDX認定事業者として認定されました。
DX認定とはDX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度であり、横浜銀行のDX戦略策定が適切であったといえるでしょう。
株式会社 百十四銀行は、2023年度から2025年度までを計画期間とするDX戦略を策定しました。
背景には人口減少や超高齢化の進行だけでなく、脱炭素・循環型社会への移行やデジタルシフトの加速など、金融機関を取り巻く環境は多様化・複雑化しています。
このような状況に対して同社は地域社会とともに持続的に成長することを目標に掲げ、DX戦略を策定しました。
同社も株式会社横浜銀行と同様にDX認定事業者として認定されており次のような重点分野を掲げています。
これらの取り組みを通じて、地域社会への貢献と企業としての持続可能性の向上を目指しています。
金融DXで戦略策定する際のポイントは以下のとおりです。
それぞれのポイントを解説します。
金融業界におけるDXの推進は、一度で完結するものではなく、長期的な取り組みが求められます。
しかし、多くの企業が途中で停滞してしまうのは、目先の課題や短期的な成果にとらわれてしまうことが一因です。
中断せずに進めるためには、社内での理解と協力を得て、従業員が共通の目標に向かって進むことが鍵となります。
具体的には定期的な進捗確認や問題解決のためのコミュニケーションを心がけてください。
特に金融業界では、セキュリティや規制対応が求められるため、途中で計画を見直す際も統合性を保つ必要があります。そのため、戦略には柔軟性を持たせておくことが欠かせません。
金融DXの取り組みを成功させるためには、大きな目標を掲げる一方で、小さなステップから始める姿勢も大切です。
一度に多くの領域に手をつけることはリスクが高く、リソースの分散や混乱を招く原因となります。
例えば、最初に顧客管理システムのデジタル化や、工数のかかる業務の自動化から始めるといった形で、まずは小さな成功体験を積み重ねましょう。
スモールステップの利点は、仮に失敗した場合でも影響を最小限に抑えることができる点です。最初のプロジェクトが成果を挙げれば社内の関心や意欲も高まり、その後の取り組みがよりスムーズに進展するでしょう。
また、小さな成功の積み重ねが従業員の信頼と参加意識を高め、大きな変革を支える確かな土台となります。
金融業界におけるDX化は慎重に時間をかけて丁寧に進めるのもポイントです。
デジタル技術を取り入れること自体は比較的早い段階で可能ですが、業務プロセスや企業文化に浸透させるには継続的な努力と時間が必要です。
特に金融機関では、顧客情報やデータのセキュリティが厳重に求められるため、新技術を取り入れる際には十分なテストやリスク管理を徹底しましょう。
また、DXには従業員やステークホルダーの理解と協力が不可欠です。急激な変化は不安や抵抗を生む可能性があるため、段階的に進めていくことが円滑な推進につながります。
結果として、時間をかけることで企業全体がより確実に新しい技術を受け入れ、変革を支える基盤を構築できるでしょう。
金融DXを進めるためには、新しい技術を導入するだけではなく、技術を効果的に運用できる人材を確保しましょう。
特に、金融業界におけるデジタル化は、規制やセキュリティの面でも高度な専門知識を必要とするため、専門的なスキルを持つ人材が求められます。
また、デジタル技術を活用して業務改革を進めるには、テクノロジーを理解するだけでなく、業務全体の視点で改善を提案できる人材が適しています。
人材確保の主な手段としては、以下の3つが挙げられます。
それぞれの方法について解説します。
金融DXを進めるためには、新たなスキルを持った人材を外部から採用するのもひとつの手段です。
特に、AI・データ分析・クラウドなどの専門スキルを持つ人材を確保することで、DXプロジェクトの加速が期待できるでしょう。
採用する人材は、単に技術的なスキルだけでなく、金融業界の規制やリスクへの知識も兼ね備えた人材が理想的です。
また、企業文化への適応力を重視することで、長期的な活躍が見込める人材を確保できるでしょう。
外部人材の採用とあわせて、既存の従業員に対する教育施策も有効です。
すでに企業文化や業務フローを理解している従業員に新しい技術を教えることで、スムーズなDX化が可能になります。
教育は一度きりではなく、継続的に実施してください。
業務内容や役割に応じた研修を通じて、実践的なスキルの習得を促すことで、従業員の自主的な成長と企業のDX推進の両立が図れるでしょう。
金融DXの進行において、外部パートナーの力を借りることもひとつの方法です。
特に、専門的な知識や技術が求められる分野では、外部のコンサルタントやITベンダーと協力することが効果的です。
外部パートナーは、自社だけでは解決できない問題に対して専門的なアドバイスを提供し、実務的な支援を行います。
また、外部パートナーの活用によって、最新の技術やトレンドに対する知識を得ることができます。
外部パートナーを選ぶ際は、業界経験や過去の実績を考慮し、信頼できるパートナーを選ぶことが成功の鍵です。

金融業界におけるDXの戦略策定では、企業が抱える課題や機会を明確にし、競争優位性を高めるための計画を立てるのがポイントです。
以下のようにさまざまなフレームワークを活用することで、現状分析や未来の方向性を具体化し、効果的な施策を実行に移すことが可能になります。
金融DXを推進する際に特に有効なものです。それぞれのアプローチが、企業にどのように役立つのかを解説します。
SWOT分析は、企業の戦略策定における基本的なフレームワークのひとつです。
企業の内部環境と外部環境を分析し、以下の4つに分類する手法です。
カテゴリー | 概要 |
強み(Strengths) | 既存の顧客基盤や強固なブランド力、業務プロセスの効率性など |
弱み(Weaknesses) | 古いシステムの依存やデジタル化の遅れ、セキュリティや規制遵守に関するリスクなど |
機会(Opportunities) | 新しい技術や規制緩和の動向、顧客のデジタルニーズの高まりなど |
脅威(Threats) | 競合の新規参入やサイバー攻撃のリスクなど |
SWOT分析を活用すれば、リスクとチャンスの両面を考慮した戦略策定を実現できるでしょう。
アンゾフの成長マトリクスは、以下のように市場と製品の2軸から成長戦略を4つに分類するフレームワークです。
カテゴリー | 概要 |
市場浸透戦略 | 既存市場でのシェア拡大を目指す戦略で、顧客に対して新しいデジタルサービスや機能を提供が含まれる |
製品開発戦略 | 新しい金融サービスやプロダクトを開発し、既存市場に導入する戦略 |
市場開拓戦略 | 新しい市場に進出することで成長を目指す戦略 |
多角化戦略 | 新しい市場と新しい製品を組み合わせる戦略 |
金融DXにおいては新しい市場や製品を開拓するための方針を明確にするために効果的です。金融機関は自社の成長の方向性を見出し、リスク管理しながら着実にビジネスを拡大できるでしょう。
PEST分析は、以下の4つのカテゴリーを分析するフレームワークです。
カテゴリー | 概要 |
政治(Politics) | 政府の規制や政策が金融業界に与える影響を分析 |
経済(Economics) | 経済的要因が金融業界に及ぼす影響を分析 |
社会(Social) | 社会的なトレンドの変化が、消費者の金融行動やニーズに与える影響を分析 |
技術(Technology) | 新技術の発展が金融業界に与える影響を分析 |
PEST分析を用いることで、金融機関はこれらの外部環境要因を把握し、変化に柔軟に対応できる戦略の策定につながります。
ビジネスキャンバスモデルは、企業のビジネスモデルを視覚的に表現するフレームワークで、以下の9つの要素から構成されています。
構成要素 | 概要 |
顧客セグメント | どの顧客層をターゲットにするかを決定 |
価値提案 | 顧客に対して提供する価値を定義 |
チャネル | 顧客にどのようにサービスを届けるかの方法を決定 |
顧客との関係 | 顧客との関係性をどのように築くかを定める |
収益の流れ | サービスを提供することで得られる収益の仕組みを設計 |
主要リソース | DXを進めるために必要なリソース(人材・技術・インフラ)を特定 |
パートナー | 外部のパートナーと連携して、戦略を進めるための協力関係を築く |
コスト構造 | DXに必要なコストを計画し、収益とコストのバランスを取る |
企業は全体像を把握しながら戦略の明確化につなげられるでしょう。
デザイン思考は、ユーザー中心のアプローチで問題解決を行うためのフレームワークです。
金融業界においても、顧客のニーズに基づいた新しいサービスやソリューションを提供するために有効です。
デザイン思考は顧客の課題を深く理解し、アイデアの創出からプロトタイプを作成してテストを繰り返しながら解決策を探ります。
その結果、実際のニーズに合致したサービスを設計することにより、より価値のあるサービスの提供につなげられるでしょう。
3C分析は、以下の3つの視点から戦略を立案するフレームワークです。金融DXを推進するうえでも非常に有効な分析手法といえるでしょう。
構成要素 | 概要 |
市場・顧客 | 競合他社の動向を把握し、どのような価値を提供できるかを分析 |
競合 | 競合他社の動向を把握し、自社との違いや競争優位性を明確にする |
自社 | 自社の強みや弱みを分析し、どのようなリソースを活用してDXを進めるかを明確にする |
3C分析を活用すれば、企業は自社の強みを明確にしながら、競合との差別化を図ると同時に、顧客の期待に答える戦略を策定できます。
金融DXの戦略策定をどのように進めていいのか分からない、という企業の担当者の方は『株式会社 TWOSTONE&Sons』にご相談ください。
当社ではDX推進に必要なソリューションを幅広く提供しています。
単にITツールやシステムを導入するだけでなく、戦略設計・ITコンサルティング・人材紹介などもワンストップで対応可能です。金融DXの戦略策定を総合的にサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。

金融業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるシステムの刷新ではなく企業のビジネス戦略や価値提供のあり方そのものに影響を与える取り組みです。
そのためには明確なビジョンの設定と、取り組む領域を選定し、適切な人材やリソースの確保が欠かせません。一度にすべてを変えようとせず、スモールステップを重ねながら、じっくり時間をかけて進めていくことが成功への近道です。
また、SWOT分析・PEST分析・アンゾフの成長マトリクスなどのフレームワークを活用することで、内外の環境を的確に把握し、より実効性の高い戦略を策定できるようになるでしょう。
金融DX戦略に取り組み、事業の持続的成長につなげていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
