金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

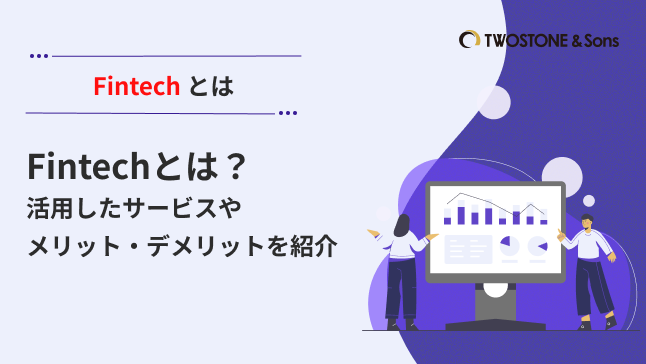
Fintechとは何かを理解し、それを活用した金融DX推進のポイントを詳しく解説します。企業が知っておくべき活用法や注意点、そして『株式会社 TWOSTONE&Sons』による支援体制についても丁寧にご案内いたします。
金融業界ではデジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進んでおり、その中でも Fintech(フィンテック) は特に革新的な役割を担っています。しかし、こうした新しい技術が広がる一方で、「Fintechとは何か」「具体的にどう活用できるのか」を正しく理解している企業や個人は、意外と多くありません。
本記事では、金融DXを推進する視点から、Fintechの基本をわかりやすく解説します。現代の金融サービスがどのように変化しているのかを知ることで、Fintechの核心を理解し、自社のDX戦略に活かすヒントが得られるでしょう。

Fintechとは、「Finance(金融)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語で、最新のIT技術を活用して金融サービスを革新する概念です。
銀行や証券会社などの金融機関だけでなく、スタートアップや大手企業など幅広い業種で活用されており、既存の金融ビジネスモデルを根本から変革しつつあります。
Fintechの普及は、単にサービスの利便性を高めるだけでなく、金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)の推進、コスト削減、新たなビジネス機会の創出といった多方面で社会に大きなインパクトをもたらしています。
Fintechの基盤となる技術は多岐にわたり、その中でも特に注目されているのがブロックチェーン技術・人工知能(AI)・API連携の3つです。これらの技術が金融サービスの質と幅を拡げているため、それぞれの特徴と役割を理解することが重要です。
ブロックチェーンは「分散型台帳技術」として知られ、データの改ざんが極めて困難な仕組みを提供します。
金融取引の記録や契約情報の管理にこの技術を活用することで、高い透明性と信頼性が実現されました。
現在では、暗号資産(仮想通貨)の基盤技術としての役割にとどまらず、送金や決済プロセスなどの幅広い領域に応用が広がっています。
その結果、不正リスクの軽減と業務コストの削減を同時に実現できる手段として、金融業界でも注目を集めています。
AI技術の進展により、金融機関は顧客の信用評価やリスク分析を、これまで以上に高精度で実施できるようになりました。
AIは膨大なデータを機械学習によって解析し、個々の顧客の返済能力や行動パターンを予測します。これにより、与信判断の精度が大きく向上しています。
さらに、チャットボットをはじめとする自動応答システムの導入により、顧客対応の効率とサービス品質も改善されています。AIが一定レベルの問い合わせに対応することで、人的リソースの負担を軽減しながら、顧客満足度の向上も同時に実現できるのです。
API(Application Programming Interface)は異なるシステム同士をつなぐ技術であり、金融サービスの連携や拡張を容易にしています。APIを活用することで、銀行や決済サービス、保険などの機能を柔軟に組み合わせて新しいサービスを迅速に提供できるようになります。
外部の決済プラットフォームと連携し、ユーザーは複数の金融サービスをシームレスに利用するといったことも可能です。こうした連携は顧客体験の向上とサービス競争力の強化につながるでしょう。
Fintechを活用したサービスは単に技術を使うだけでなく、ユーザーの利便性向上や新たなビジネスモデルの構築を目指しています。ここでは、特に注目されている日本企業を5社紹介し、それぞれの強みと独自性を解説します。
株式会社マネーフォワードは、個人や法人向けの資産管理・会計ソフトを提供し、幅広いユーザーから支持されています。主力サービスは銀行口座やクレジットカード、電子マネーの情報を一元管理できるクラウド型の家計簿アプリです。これによりユーザーは複数の金融サービスをまとめて把握でき、資産管理が効率化されます。
マネーフォワードの強みは、金融機関や行政システムとのAPI連携を積極的に推進している点です。これにより最新の情報をリアルタイムで取得し、正確なデータ管理を可能にしています。法人向けには、経理や給与計算、請求書発行などの業務効率化ツールを提供し、中小企業のバックオフィス業務を簡素化している点も特筆されます。
参考:株式会社マネーフォワード
フリー株式会社は、中小企業や個人事業主を主な対象としたクラウド会計ソフトを開発しています。シンプルな操作性と高い自動化機能を特徴とし、特に経理業務に不慣れなユーザーでも簡単に使いこなせる点で評価されています。銀行やクレジットカードと連携することで自動で仕訳を生成し、手入力の手間を削減しているのです。
この企業はFintechのAPI技術を活用し外部サービスとの連携を強化しているため、会計以外の金融業務も一元管理が可能です。請求管理や入金確認などもスムーズに行えるため、経営者の負担軽減に直結しています。フリー株式会社は、金融サービスの利便性と業務効率の両立を実現している代表例です。
参考:フリー株式会社
株式会社Kyashは、スマートフォンを使った新しい決済サービスを提供しています。Kyashの特徴はプリペイド型のバーチャルカードやリアルカードを発行し、日常の支払いをキャッシュレス化できる点です。利用者はカードを通じて簡単にチャージや送金ができ、リアルタイムで利用履歴を確認できます。
また、KyashはAPIを公開して他の金融サービスやアプリとの連携を促進しているため、多様な決済ニーズに対応可能です。ユーザーにとってはポイント還元や利用状況の見える化など便利でお得な仕組みが整っているため、若年層を中心に人気を博しています。KyashはFintechの技術を活かし、キャッシュレス社会の実現を加速させています。
参考:株式会社Kyash
株式会社FOLIOは投資分野に特化したFintech企業で、AIやビッグデータを活用した資産運用サービスを提供しています。独自のアルゴリズムにより市場動向やリスクを分析し、個人投資家向けに最適化されたポートフォリオを提案します。投資初心者でも手軽に分散投資が可能となり、資産形成を支援する仕組みが整っているのです。
このサービスはスマートフォンアプリを中心に展開され、投資の透明性と手軽さを両立している点が評価されています。FOLIOはAI技術とFintechを融合させることで従来の証券会社にはない新しい価値を創出しており、投資の民主化に貢献しています。
参考:株式会社FOLIO
株式会社Paidyは後払い決済サービスを提供しており、オンラインショッピングの利便性を高めています。ユーザーはクレジットカードなしでも簡単に買い物ができ、月末にまとめて支払いが可能です。これにより消費者の購買行動がスムーズになり、EC事業者の売上向上にもつながっています。
PaidyはAIを活用して与信判断をリアルタイムで行い、リスク管理を徹底しています。この技術により、不正利用の抑止と利用者の安心感が確保されているのです。後払い決済の普及により、Fintechがオンライン消費の成長を支えている事例として注目されています。
参考:株式会社Paidy

Fintechは金融業界に革新をもたらし、多くの企業や消費者に恩恵を与えています。しかしその一方で導入に伴うリスクや課題も存在し、慎重な検討が必要です。
ここでは、Fintechがもたらす代表的なメリットとデメリットを分かりやすく解説します。企業がこれらを正しく理解することで導入後のトラブルを防ぎ、効果的な活用ができるでしょう。
Fintechが企業にとって価値ある理由は多岐にわたりますが、特に注目すべき3つのメリットに絞って紹介します。これらは、企業の業務改善や競争力強化に直結する重要なポイントです。
まず、Fintech導入によって金融手続きの利便性が高まります。従来の銀行窓口や紙ベースの申請作業に比べて、オンラインでの取引が可能となり時間と労力の節約が実現します。例えばクラウド会計や自動決済システムを活用すると、経理処理は自動化され、ミスや遅延のリスクを低減できるでしょう。
この利便性の向上は従業員の業務負担軽減に直結し、より戦略的な業務に注力できる環境を整えます。加えて顧客にとっても、決済や融資申請のスムーズさが向上しサービス満足度が高まるため、企業の信頼性向上にもつながります。
Fintechのもう1つのメリットは、金融包摂の促進です。金融包摂とは、これまで金融サービスにアクセスしづらかった低所得者や地方在住者、若年層などに対して金融サービスを公平に提供する動きのことです。Fintechはインターネット環境さえあれば利用できるため、物理的な銀行支店が少ない地域でも高度な金融サービスが受けられます。
例えばスマホ決済やオンライン融資サービスは、従来の金融機関の枠を超えた利用を可能にし、新たな経済参加者を生み出しています。これにより地域経済の活性化や消費の拡大が期待でき、企業の事業展開においても新たな顧客層を取り込む機会が増えるのです。
FintechはAI(人工知能)技術を積極的に取り入れ、業務の効率化とコスト削減を実現しています。AIは膨大なデータを瞬時に分析し与信判断やリスク評価を自動化できるため、従来の人手による作業を削減します。また、不正検知や市場動向予測にも役立ち、企業のリスク管理体制を強化しているのです。
結果として金融サービスの提供にかかるコストが下がり、利益率が向上します。さらに業務が効率化されることで顧客対応の迅速化も可能となり、顧客満足度の向上に寄与します。AIの導入は、今後のFintechの競争力を左右する重要な要素の1つです。
一方で、Fintechには注意すべきデメリットも存在します。これらは導入後のトラブルやサービス品質の低下を防ぐために、企業が事前に把握し、対策を講じるべき重要な課題です。
Fintechサービスの多くはインターネットを介して金融情報をやり取りするため、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まります。特に顧客の個人情報や決済情報が狙われやすく、不正アクセスによる被害は企業の信用失墜につながります。
したがってFintechを導入する際には、厳格な情報セキュリティ対策が不可欠です。多要素認証の導入や暗号化技術の活用、定期的なセキュリティ監査を実施することでリスクを最小限に抑えられます。加えて、万が一の被害に備えた対応策や保険も検討すると安心です。
Fintechサービスは便利である一方で、利用者のITリテラシーに依存する側面があります。特に高齢者やITに不慣れなユーザーにとっては操作が難しく感じられ、サービスの利用が進まない場合があります。結果として、一部の顧客層を取りこぼすリスクが発生します。
企業側はシンプルで直感的なUI設計を心掛けることが重要です。また、操作方法のわかりやすいマニュアルやサポート体制の充実も不可欠です。さらに、オフラインでのフォローや教育プログラムを実施することにより、多様な利用者層をカバーできるよう工夫する必要があります。
Fintechは革新的な技術を用いるため、既存の法規制や制度との整合性に課題が生じやすい分野です。オンライン決済や仮想通貨の取扱いには複雑な法律が絡み、違反すると厳しいペナルティが課されます。規制の変更や新たな法令の施行によって、急遽サービス内容を変更せざるを得ないケースもあります。
企業は常に最新の法規制を把握し、専門家の意見を取り入れながらコンプライアンスを徹底しなければなりません。適切なガバナンス体制を構築し法令順守を優先課題として管理することが、Fintech事業の持続的成長に不可欠です。
金融DX(デジタルトランスフォーメーション)は単に業務のデジタル化を進めるだけではなく、金融サービス全体の革新を目指す取り組みです。その中心に位置するのがFintechの活用です。
Fintechの適切な導入と活用は金融機関や企業の競争力を高め、顧客満足度の向上や業務効率化に直結します。ここでは、金融DXを推進する上で効果的なFintechの活用法を4つの視点からご紹介します。
Fintechは、金融業務のデジタル化を加速する最適なツールです。例えば、従来は紙ベースで行っていた与信審査や契約手続きをオンライン化することで処理速度が向上し、人的ミスも減少します。電子契約やスマホ決済の普及は顧客にとっても利便性が高く、サービス利用のハードルが下がるため顧客獲得や維持に効果的です。
また、クラウド型の会計システムやAIチャットボットなどFintechツールを積極的に導入すれば、社内の業務フローが効率化されコスト削減に寄与します。これにより、金融機関は本来のコア業務である顧客支援や新規事業開発に注力できるようになります。したがって、金融業務のデジタル化は、Fintech導入によるDXの第一歩として重要な役割を果たすでしょう。
Fintechの活用は顧客との接点を多様化し、ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上に直結します。モバイルアプリやウェブプラットフォームを通じて顧客はいつでもどこでも金融サービスを利用可能となり、利便性が高まります。これにより従来の支店依存型のサービスから脱却し、多様な顧客ニーズに対応できるようになるのです。
さらに、AIによるパーソナライズドな提案や24時間対応のカスタマーサポートも可能となり、顧客満足度の向上につながるでしょう。例えば、資産運用アドバイスやローン申請における最適プランの提示など、個々の顧客の状況に応じたサービス提供は他社との差別化につながります。結果として、顧客のロイヤリティ向上と長期的な関係構築が期待できるのです。
Fintechは大量の金融データを収集・解析する技術を備えており、データドリブンな意思決定の基盤として有効です。これにより企業は顧客の行動や市場動向をリアルタイムで把握し、迅速かつ的確な経営判断を下せます。AIを活用した与信リスク評価や市場分析は従来の経験や勘に頼る判断よりも精度が高く、リスクを抑制できるでしょう。
また、予測分析によって将来的な顧客ニーズを先読みし、新商品やサービスの企画に反映させることも可能です。データの有効活用は企業の競争力強化に不可欠な要素であり、Fintechはその実現を強力にサポートします。したがって、金融DXを推進するにはデータを最大限に活かす環境整備が必要なのです。
Fintechは単なる技術導入にとどまらず、オープンイノベーションを促進するプラットフォームとしての役割も果たします。金融機関とスタートアップ企業、ITベンダーが連携し、新しいサービスやビジネスモデルを共創する動きが加速しています。例えばAPI(アプリケーションプログラミングインターフェース)を活用することで、異なるサービス間でのシームレスな連携を行う企業が出てきました。
このような協業により従来にはなかった革新的な金融商品や顧客体験が生まれ、市場の活性化に寄与します。企業がFintechをオープンイノベーションの起点として活用することで、イノベーションのスピードを加速し、競争優位を確立できるのです。金融DXの本質は、こうした多様なパートナーとの協働にあるといえるでしょう。
金融DXの推進においては、最新のFintech技術を効果的に導入し、業務プロセスや顧客体験を抜本的に改善することが欠かせません。しかし、その実現には専門的な知識と豊富な経験が求められます。
当社はお客様の課題を丁寧にヒアリングし、最適なFintechソリューションの提案から導入後の運用サポートまで一貫して対応いたします。セキュリティ面の強化や法規制対応、ユーザー教育のサポートも充実しており、安心して金融DXを推進できる体制を整えています。Fintechを活用した金融DXで企業競争力を高めたいとお考えなら、ぜひ『株式会社 TWOSTONE&Sons』までお気軽にご相談ください。

Fintechは金融業界の構造を根本から変える力を持っており、金融DXの推進において不可欠な技術です。そのメリットは、金融手続きの利便性向上や金融包摂の促進、AI活用による業務効率化など多岐にわたります。一方で、セキュリティリスクや利用者のITリテラシー依存、法規制の課題も存在するため慎重な対策が必要です。
金融DXを成功に導くには、Fintechを単なるツールとしてではなく、顧客体験の向上やデータ活用、オープンイノベーションのプラットフォームとして戦略的に活用する視点が求められます。これにより、競争力の強化や新たなビジネスチャンス創出が期待できるでしょう。
もしFintech導入や金融DX推進についてご不明点があれば、ぜひ『株式会社 TWOSTONE&Sons』にご相談ください。専門家の視点から最適なソリューションをご提案し、皆様のビジネス成長を全力でサポートいたします。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
