金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

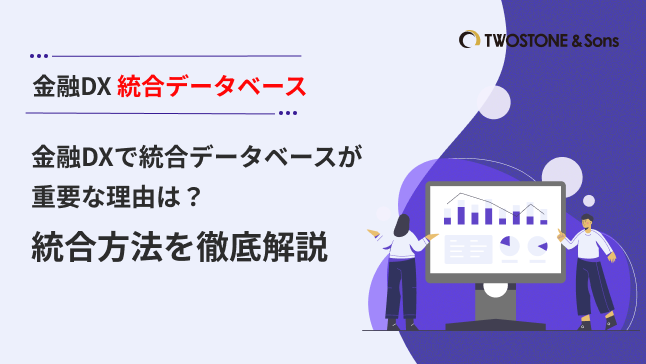
金融機関で顧客情報や取引履歴などのデータが分散している場合、統合データベースでの一元管理がおすすめです。統合データベースを活用すれば、データに基づいた高精度の意思決定や業務効率化が目指せます。統合データベースを活用して金融DXを推進したい企業は、ぜひ参考にしてください。
金融DXを進めるうえで、データの統合は業務効率や意思決定のスピードを向上させ、競争力を強化するために欠かせません。
現在、多くの金融機関では、顧客情報・取引履歴・マーケットデータなどが複数のシステムに分散しており、いわゆる「データのサイロ化」が起きています。
このような状況では、業務の最適化やスピーディな経営判断が難しくなり、他社に後れを取るリスクが高まるでしょう。そこで、統合データベースを活用して情報を一元管理し、リアルタイムで活用できる体制を整えることが大切です。
この記事では金融DXにおける統合データベースの役割や構築ステップについて解説します。

統合データベースとは、異なるシステムやアプリケーションから得られるデータを一元化し、利用しやすくするためのデータベースです。
金融機関においては、顧客情報・取引履歴・マーケットデータなど、さまざまな種類のデータが複数のシステムに分散しています。
これらのデータが分断されたサイロ化の状態では、データの整合性が保てず、意思決定に時間がかかるだけでなく、業務の効率も低下します。
一方、統合データベースを活用することで、すべてのデータを中央で管理・処理し、リアルタイムで活用できる環境を整備可能です。
金融業界で統合データベースが必要な理由は次のとおりです。
それぞれの理由を解説します。
金融機関がDXを成功に導くには、データ活用が不可欠です。
DXが進んでいる企業では、テクノロジーを活用して業務を自動化し、意思決定のスピードを高めています。
こうした取り組みを金融機関で実現するには、縦割りで分散しているデータ構造の見直しが必要でしょう。部門ごとにデータが孤立している状態では、情報を活用するための手間が増え、迅速な意思決定を妨げてしまいます。
統合データベースを活用すれば、すべての部門やシステムが共通のデータを活用できるようになり、全社的に一貫した判断が行いやすくなるでしょう。
多くの金融機関では、各部門やシステムで異なるデータを管理しており、その結果、情報のサイロ化が生じています。
例えば、顧客の口座情報や取引履歴を営業部門とマーケティング部門とで別々に管理している場合、顧客の全体像を把握できず、効率的な営業活動や戦略の立案が難しくなります。
また、情報のサイロ化は、データの不完全性や重複といった課題を招き、分析や活用の妨げになる可能性があります。こうした問題を解消する手段として、統合データベースの活用が効果的です。
統合データベースは、業務効率化にも貢献します。
従来のシステムでは、異なるデータを手作業で統合する必要がありました。
統合データベースを活用することで、時間とリソースの削減につながります。
また、リアルタイムでデータが更新されるため、業務の進捗状況や結果を即座に把握でき、迅速な対応も実現します。
例えば、顧客からの問い合わせに対して即座に情報を引き出して対応できるようになれば、顧客満足度の向上が期待できるでしょう。
作業時間が減ることで、従業員はより付加価値の高い業務に集中でき、企業全体の生産性が高まるでしょう。
データドリブンとは、意思決定をデータに基づいて行う企業文化のことを指します。
統合データベースを活用すれば、感覚や経験だけに依存しない最新かつ正確なデータをリアルタイムで活用できる環境が整います。
その結果、データを駆使して戦略的な判断が下せるようになり、業務の透明性や成果の向上につながるでしょう。
さらに、従業員のデータ活用スキルが向上すれば、データに基づく意思決定が企業全体に浸透していき、競争力の向上も期待できます。
金融業界では、日々膨大な量のデータが蓄積されています。これらのデータを有効活用するには、分散した情報を統合し、一元的に管理することが欠かせません。
例えば、顧客情報・口座情報・取引履歴・マーケティングデータ・コンプライアンス関連のデータが挙げられます。これらを部門間で連携すれば、業務の効率化や迅速な意思決定が可能になるでしょう。
また、データ活用することで、よりパーソナライズされたサービスを提供でき、顧客満足度の向上にもつながります。

金融DXにおける統合データベース構築は次のようなステップで進めていきましょう。
それぞれのステップを詳しく解説します。
統合データベース構築の最初のステップは、どのデータを統合するかを明確にすることです。
金融機関には、顧客情報・取引履歴・リスク評価データ・マーケットデータ、さらには経済指標など多岐にわたるデータが存在しています。
上記すべての統合は現実的ではないため、まずはビジネスにおいて価値のあるデータを特定し、その後、必要に応じて他のデータも統合するアプローチが必要です。
例えば、顧客情報と取引履歴を統合すれば、顧客ニーズの把握やマーケティング活動の精度向上が期待できます。
統合対象が決定した後は、以下のような対象データを加工しましょう。
多くの金融機関では、異なる部門で異なるシステムを使用しているため、データの形式や精度にばらつきがあります。
そのため、データを統合する前に、一定の加工を施す必要があります。
H4:データフォーマットを統一する
異なるシステムから取得したデータのフォーマットを統一します。
例えば、顧客名や住所などの情報を異なるフォーマットで保存している場合、一貫性のある形式に変換しましょう。
あるシステムで「氏名」として管理されている情報が、別のシステムでは「名前」と記録されていることがあります。
データフォーマットを統一する際には、各項目の意味や構造を十分に理解したうえで作業を進めましょう。
H4:欠損データや異常値を検出・補正する
データによっては欠損や異常が考えられるため、検出して補正します。
顧客情報や取引履歴など、欠損や異常値が含まれている場合、意思決定に支障をきたしかねません。
そのため、データ加工の段階で欠損値や異常値を発見し、適切な補正が必要です。
異常値であればデータエラーの可能性が高いため、確認のうえ修正しましょう。
欠損データについては適切な方法で補完するか、あるいはそのデータ項目を削除する判断を行います。
H4:重複データを削除する
データ統合の過程で、同一のデータを複数の場所に保存しているケースがあるため、不要であれば削除しましょう。
例えば、同じ顧客情報を複数のシステムにおいて異なるフォーマットで保存している場合、データの重複が発生することがあります。
重複データを削除するためには、厳密なマッチングルールを設定し、システムを通じて自動的に削除するのが一般的です。
また、削除後も元のデータが失われないよう、バックアップを取りましょう。
データを加工したら集積方法を決定し、実行に移します。
データの種類や活用目的によって、最適な集積場所の選定が必要です。
そのため、以下のように複数の選択肢から最適な方法を選びましょう。
それぞれの集積方法について解説します。
データウェアハウス(DW)は、大量のデータを効率的に保存し、分析するためのシステムです。
金融機関においては、取引データ・顧客データ・会計データなどを集積するために使用しています。
データウェアハウスは、複数の異なるソースからデータを集めて一元管理が可能です。
この仕組みを活用することで、データの整合性を保ちながら、分析やレポーティングが効率的に行えるようになります。
特に、リアルタイムデータを集積し、迅速な意思決定を支援するためには、データウェアハウスが欠かせません。
データレイク(Data Lake)は、構造化データだけでなく、テキストや画像、音声などの非構造化データも含めた膨大なデータを保存するためのシステムです。
金融業界では、従来のデータベースでは扱いきれない種類のデータが多く存在します。
例えば、顧客とのやりとりで生まれるテキストデータやSNSデータ、あるいは音声データなどが該当します。
データレイクはこれらのデータも取り込み、分析のために統合が可能です。
多種多様なデータを一元的に扱えることがデータレイクの強みといえるでしょう。
CDP(Customer Data Platform)は顧客に関するデータを一元化するためのプラットフォームです。
CDPはさまざまな部門が別々に管理しているデータを統合し、顧客それぞれのプロファイルを把握できるようにします。
金融機関においては、CDPで一元化した顧客の過去の取引履歴や問い合わせ履歴などを組み合わせることで、より精度の高いマーケティングやパーソナライズしたサービスを提供可能です。
DMP(Data Management Platform)はマーケティング活動で使用しているデータを管理するプラットフォームです。
主に広告配信に関連するデータを集積しますが、顧客の行動データや広告反応データを分析するためにも使用されます。
金融機関が提供するサービスの中には、顧客向けの広告やプロモーションが含まれており、パフォーマンスを最適化するためにはDMPが重要な役割を果たします。
PIM(Product Information Management)は、製品やサービスに関する情報を管理するためのシステムです。
金融機関においても、金融商品やサービスの情報を一元管理し、顧客に対して正確な情報提供が欠かせません。
PIMを活用すれば、金融商品の詳細・条件・利率などをデータベース化し、顧客や営業担当者が必要な情報に迅速にアクセスできるようになります。
また、商品の販売戦略やプロモーション活動をデータに基づいて最適化が可能です。
データ仮想化は、複数のデータソースから情報を仮想的に統合し、ユーザーに対してリアルタイムでアクセスできるようにする技術です。
データ仮想化により、異なるデータベースやシステムに保存しているデータを一元化できるため、データの実際の場所に関係なくアクセスすることが可能になります。
金融機関においては、迅速なデータの取り込みと分析が求められるため、データ仮想化は効率的なデータ活用を支える重要な技術です。
DAM(Digital Asset Management)は、画像やビデオ、文書などのデジタルコンテンツを管理するシステムです。
金融業界では、広告素材やプロモーションコンテンツ、顧客向けに提供している情報をデジタルで管理することが欠かせません。
DAMを導入すれば、コンテンツの整理・検索・配信が効率的に行えるようになります。
また、コンテンツの使用履歴やアクセス状況の追跡も可能で、マーケティング活動の効果を測定する際に役立ちます。
金融業界においてデータの統合は、効率的な業務運営、迅速な意思決定、そして競争力を維持するために非常に重要です。しかし、データ統合が進まない場合、次のようなリスクが発生し、企業の成長を妨げかねません。
ここでは、データ統合が進まないことによるリスクについて解説します。
金融機関におけるデータ統合が遅れると、意思決定が遅くなります。
現代の金融業界では、リアルタイムでのデータ分析とその結果に基づく迅速な意思決定が必要です。
例えば、顧客の取引履歴や市場の動向に基づいた投資判断を行う際、データが統合していなければ、必要な情報を素早く把握できない可能性があります。
その結果、最適なタイミングでの意思決定ができず、競争に遅れを取ってしまうでしょう。
データ統合が進まないと、業務効率が低下しかねません。
さまざまなデータを統合していない場合、各システムを確認したり手作業でデータを移行したりする必要があり、業務の効率が低下します。
例えば、顧客情報が複数の部門で異なるシステムに保存している場合、同じ顧客の情報を何度も入力することになり、無駄な作業が増えてしまうでしょう。
無駄な作業が増加したことで従業員は本来の業務に集中できず、余分な時間を取られてしまいます。
データ統合が進まないと、顧客との関係性を構築できない可能性があります。
顧客情報が複数のシステムに分散している場合、顧客のニーズを正確に把握することが困難になり、結果的に顧客満足度が低下しかねません。
顧客のフィードバックや新たなニーズに対応して関係性を強化するためには、データの統合による迅速かつ柔軟に対応できる体制が必要です。
データ統合が進まないと、不要な出費が増加するリスクもあります。
複数のシステムでデータを管理している場合、それぞれのシステムに対してメンテナンスコストがかかってしまうでしょう。
例えば、異なるシステムで同じデータを管理している場合、そのデータの重複や更新作業にコストがかかります。
また、データの整合性を保つために、手動でデータを同期させる作業が発生すると、その分の人件費や作業時間がかさんでしまいます。
金融DXを進めるうえで、統合データベースの構築は欠かせない要素です。
しかし、統合データベースの構築には専門的な知識が求められるため、自社だけで対応するのは難しい場合もあるでしょう。
そのような企業は、『株式会社 TWOSTONE&Sons』へご相談ください。当社は、金融DXの推進に必要なITソリューションの提供はもちろん、適切なIT人材の紹介も行っています。
「統合データベースが構築できない」「金融DXが思うように進まない」とお悩みでしたら、一度お問い合わせください。

統合データベースとは、複数の情報を一元的に管理し、効率よく活用するための仕組みです。
例えば金融機関であれば、顧客情報・取引履歴・マーケットデータなどをまとめて管理することが挙げられます。
金融DXを成功させるには、こうしたデータの統合が不可欠です。
統合が進まないと意思決定の遅れや業務効率の低下を招き、競争力の低下につながる可能性があります。
そのため、まずは統合すべきデータを明確にし、データウェアハウスやデータレイクといった手法を活用して、着実にデータの整備を進めていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
