金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

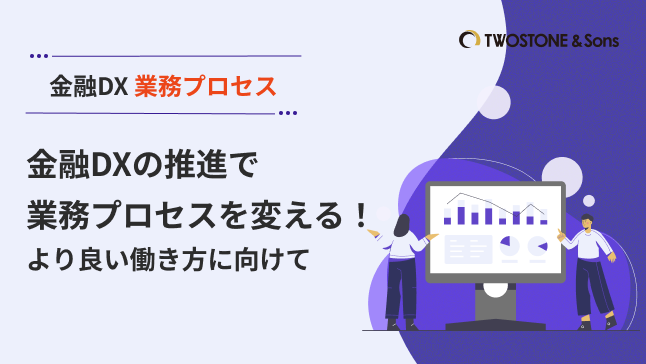
金融DXによって業務プロセスの最適化を目指す企業様向けに、具体的な推進手順や注意点をわかりやすく解説しています。導入前の準備からツールの選定、社内教育や定期的な見直し方法まで、実践的な内容を網羅的にご紹介しています。
日々の業務で「非効率さ」を感じることはありませんか。「紙ベースの処理が多く、同じ情報を何度も入力しなければならない」「部署間での情報共有が遅く、対応が後手に回ってしまう」こうした課題は、金融業界においても深刻です。
しかし、それらの問題は今、デジタルの力によって変わろうとしています。本記事では、金融業界で注目されている「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」に焦点を当て、業務プロセスをどのように改善し、働き方をどのように変えていけるのかを解説します。読み進めていただくと、業務の効率化だけでなく働く人の生産性や満足度の向上につながるヒントが得られるでしょう。今後の金融機関の在り方を見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。

デジタル技術の活用が進む中、金融機関では「DX」の推進が重要になっています。従来の紙・対面を中心としたプロセスからオンラインやクラウドを基盤とした業務への転換が求められており、それが金融DXの中心的な役割です。単なるIT化とは異なり、金融DXは業務そのものを根本から見直して付加価値の高い働き方を目指します。
ここからは、まず金融DXとは何かを明確にし、その必要性と背景について具体的に見ていきましょう。
金融DXとは、金融機関がデジタル技術を活用して業務やサービスを根本から変革し、新たな顧客体験と業務効率を実現する取り組みです。単なるデジタルツールの導入ではなく、ビジネスモデル自体を見直して変化に強い柔軟な組織へと進化させることを目的としています。
例えばAIによる与信判断の自動化やスマートフォンで完結する口座開設、クラウドによる情報共有などがその一例です。これにより、業務時間の短縮、ミスの削減、そして顧客満足度の向上を実現できます。
ではなぜ今、金融DXの推進が強く求められているのでしょうか。そこには、いくつかの社会的・業界的背景があります。
ここでは、主に3つの要因に注目して解説します。
近年の金融業務は、商品・サービスの多様化に伴い手続きや管理の煩雑化が進んでいます。新しい規制対応や個別対応の増加により、現場の業務負荷は高まり続けているのです。
こうした状況に対応するには、業務フローの見直しと一元管理が不可欠です。金融DXでは、紙の書類や複雑な手続きをデジタル化することで時間と人的リソースの削減が可能になります。クラウドベースの業務管理システムを導入すれば部署を横断する情報共有が迅速になり、判断のスピードも格段に上がるでしょう。
金融業界に限らず、日本全体で深刻化している人材不足の問題は金融機関にとっても避けられない課題です。特に中小金融機関では少人数で幅広い業務をこなす必要があるため、従業員一人ひとりの負担が大きくなりがちです。
このような環境では、業務の自動化やデジタルツールによるサポートが大きな効果を発揮します。AIチャットボットを導入すれば顧客対応を一部自動化でき、人手に頼らずに一定の品質を保ったサービス提供が可能になるでしょう。金融DXを活用すれば、限られた人材で高いパフォーマンスを維持できる環境を構築できるのです。
金融DXを進めやすい環境が整いつつある点も見逃せません。政府は近年、電子署名法や電子契約に関するガイドラインを整備し、金融業界におけるデジタル化を後押ししています。これによりオンラインでの本人確認や契約締結が法的にも認められ、非対面でのサービス提供が現実的になっています。
また、個人情報保護法やマイナンバー制度などに基づいた適切なデータ管理体制を整えることで、セキュリティを担保しながら安心してデジタル活用を進められるのです。制度面での支援が進む今こそ、金融DXに取り組む絶好のタイミングです。
参考:法務省(電子署名法)
参考:公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)
金融DXが進む中で、業務の効率化や生産性の向上だけでなく現場で働く人々のニーズに対応する取り組みも注目されています。実際に金融機関で働く人材が求めているのは、単なる業務のデジタル化ではありません。働きやすさや成長の機会、自分らしい働き方への期待が高まっています。
ここでは、そうした要望を反映した具体的な環境整備や支援策について見ていきましょう。
金融機関では依然として紙ベースの業務が根強く残っており、ファイリングや書類の押印、物理的な保管が日常業務の多くを占めています。こうした作業は非効率である上に、人的ミスの原因にもなります。また、膨大な書類を扱うストレスは、従業員のモチベーションを下げる一因でもあるといえるしょう。
そのため、まず必要なのがペーパーレス化の推進です。書類の電子化を進めることで、検索性や共有性が向上するでしょう。例えばクラウド上に文書を保存する仕組みを導入すれば、場所や時間に縛られず業務に取り組めるようになり、さらに電子署名やワークフローシステムを導入すれば、承認プロセスも迅速になります。
これらの取り組みによって、単に紙業務の削減にとどまらず従業員一人ひとりの働き方に柔軟性をもたらし、全体としての業務品質の向上にもつながるでしょう。特にテレワークが可能な業務環境が整えば地理的な制約を受けずに優秀な人材を確保しやすくなり、組織の競争力を高める効果も期待できるでしょう。
DXの推進に対して前向きな職員が多い一方で、ITツールへの苦手意識を持つ人も少なくありません。新しいシステムが導入されたとしても、使いこなせなければかえって業務の混乱を招く可能性があります。そのため、ITリテラシーの底上げはDXを進める上で欠かせない要素です。
現場では、実務に即した研修が求められています。単なるマニュアルの配布ではなく、実際の業務でどのようにツールを活用するかを体験しながら学べる仕組みが必要です。また、業務中にわからない操作に直面した際にすぐに質問できるサポート体制の構築も欠かせません。
導入支援やOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて段階的に理解を深められるよう配慮することで、職員の心理的なハードルを下げられます。これにより、DXによる変革が「業務を奪う脅威」ではなく「成長の機会」として捉えられるようになり、職場全体に前向きな空気が広がります。
金融業界は長時間労働のイメージが根強く残っています。定型的で繰り返しの多い業務に時間を費やしていると、どうしても残業が発生しやすくなるのです。特に月末月初や決算期には業務が集中し、プライベートの時間を犠牲にしている人も多く見られます。
業務の自動化と可視化は、この問題を解決する手段の1つです。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入すれば、手作業で処理していた定型業務を機械が代行できるでしょう。またタスク管理ツールを活用すれば、業務の進捗をリアルタイムで把握でき、無駄な作業や属人化を防げるのです。
残業を削減できると職員のワークライフバランスが整います。仕事のパフォーマンス向上だけでなく健康維持や家庭との両立もしやすくなり、結果的に離職率の低下にもつながります。時間的なゆとりは、従業員が自己研鑽やキャリアアップに時間を充てる余地も生み出すのです。
従来の金融業界では、時間と場所に厳しく縛られた働き方が主流でした。しかし、テクノロジーの進化と社会の変化により、自律性のある働き方への関心が高まっています。特に若年層の人材は、ライフステージに応じた柔軟な勤務体系を重視する傾向があります。
つまり、リモートワークやフレックスタイム制の導入によって、従業員が自らの働き方を選択できる環境を整えることが求められているのです。このような柔軟な制度は、業務効率の向上だけでなく従業員のモチベーションやエンゲージメントの維持にもつながります。
加えて、成果主義や目標管理制度の見直しも重要です。単に出勤時間や勤務時間の長さで評価するのではなく、業務の成果に基づいた評価制度を導入することで従業員の自律性が高まり、より主体的に仕事へ取り組む姿勢が醸成されます。
このように、自律性を尊重した柔軟なワークスタイルは優秀な人材の確保と定着にもつながります。金融業界が抱える人材不足への対策としても、有効なアプローチとなり得るでしょう。
金融業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単に技術を導入するだけの取り組みではありません。その本質は、業務プロセスを見直し、より効率的で柔軟な働き方を実現する点にあります。この過程で従業員の働く環境は変わり、モチベーションや業務成果にも好影響が生まれます。
では、具体的にどのような影響があるのでしょうか。ここからは5つの側面から詳しく解説します。
金融機関の日常業務には、データ入力や帳票作成、取引確認などルーティン化された作業が多く含まれています。これらは正確さが求められる反面、繰り返しが多く人の時間とエネルギーを大量に消費してきました。
こうした作業にRPA(Robotic Process Automation)を導入すれば、人が行っていた定型業務をソフトウェアロボットが担えるようになります。RPAは24時間稼働できヒューマンエラーも最小限に抑えられるため、業務の正確性とスピードの両面で効果を発揮するでしょう。
従業員はこれにより、より戦略的で創造性を求められる業務に時間を充てられるようになります。顧客とのコミュニケーションの質を高めたり、新しい金融商品を提案する業務に集中できたりするようになれば、個人としての成長実感も得やすくなるでしょう。
このように、業務の自動化は「省力化」だけでなく「価値ある業務へのシフト」を可能にし、働きがいの向上にもつながっていきます。
従来の金融機関では、月末の処理や帳簿の締め作業など時間がかかる業務が集中し、残業が常態化しがちでした。しかし、DXによる業務効率化が進むとタスクの分散処理や自動化が実現でき、繁忙期でも一定の業務負担に抑えられるようになります。
例えば、ワークフローシステムを用いて書類の承認プロセスを電子化すれば、上司の押印を待つためだけに残業する必要はなくなるでしょう。また、AIによってレポート自動生成や顧客対応の一部自動化すると属人化した業務を標準化できるため、業務全体のスピードが向上します。
その結果、従業員は時間的な余裕を持って働けるようになり、ワークライフバランスの改善が見込まれるのです。プライベート時間の確保は心身の健康維持につながり、長期的に見て職場の定着率にも良い影響を与えるでしょう。
このように、業務の効率化は単なる時間短縮にとどまらず、組織全体の健全な働き方の実現に直結しています。
書類を物理的に保管・運搬していた従来の方法では、必要な情報にアクセスするまでに時間がかかるケースが多々ありました。特に複数部門にまたがる案件や顧客対応では、情報の遅延が業務全体のボトルネックとなっていたのが実情です。
そこで、ドキュメント管理システムやクラウドストレージの導入が有効です。書類の電子化により、場所を問わず必要な情報を即座に閲覧・共有できるようになります。これによって社内での確認作業や進捗報告がスムーズになり、意思決定のスピードが向上するのです。
また、情報のバージョン管理やアクセス権限の設定も容易になるため、セキュリティ面でも安心して運用できます。これは金融業界のように機密性が求められる業種にとって、大きなメリットといえるでしょう。
こうした情報共有の円滑化は業務の迅速化だけでなく、チーム間のコミュニケーションの活性化にもつながります。ひいては業務の属人化を防ぎ、誰が業務を引き継いでもスムーズに進行できる体制が整うのです。
金融機関では、営業・事務・企画・リスク管理など部門ごとに役割が明確に分かれています。しかし、業務が縦割りになることで、部門間の情報共有が不十分になりがちです。その結果、同じ顧客に対して異なる対応がなされるなどサービス品質にムラが生じてしまうのです。
これに対し、デジタル化によって情報を一元管理すると部門を横断した連携が可能になります。CRM(顧客関係管理)システムを導入すれば営業が取得した顧客情報を他部門でも活用でき、より適切な提案や対応が実現するでしょう。
また、チャットツールやオンライン会議システムの活用により、部署間のリアルタイムな連絡が可能になります。これまでメールや電話でのやり取りに時間を取られていた連絡業務が簡素化され、組織全体のスピード感が増すでしょう。
このような連携の強化は、従業員一人ひとりが「組織の一員として貢献している」という実感を得やすくなり、部門間の垣根を越えた協働が企業文化として根付けば、自然と一体感のある職場環境が育まれていくでしょう。
ライフスタイルの多様化が進む中、働き方に柔軟性を求める声は年々強まっています。特に子育てや介護と仕事を両立したいというニーズは、無視できない課題となっています。従来のように「9時から17時、週5日出社」といった画一的な働き方では、多様な人材を活かしきることは難しいでしょう。
そこで、リモートワークやフレックスタイム制の導入は働きやすい環境づくりに直結します。これを導入すると、従業員は業務の内容やライフイベントに応じて自分に合った働き方を選択できます。通勤時間の削減は体力的・精神的な負担を軽減し、業務への集中力を高める効果もあるのです。
さらに柔軟な働き方を実現するには、成果を正しく評価する制度の整備が欠かせません。勤務時間ではなく成果で評価される仕組みに変えることで、個々の自律性を尊重したマネジメントが可能になるのです。
このように、柔軟性を重視した働き方は従業員の満足度を高め、離職率の低下や採用力の強化にもつながっていきます。企業が長期的に発展していくためには、こうした人的資本への投資が不可欠です。

金融DX(デジタルトランスフォーメーション)は単にITツールを導入するだけではなく、業務の在り方そのものを見直す取り組みです。特に金融業界では、従来の紙ベースや属人化された業務プロセスを見直してより効率的で柔軟な仕組みに進化させることが求められています。
ここでは、金融DXが具体的にどのように業務プロセスを変革し、業務効率やサービス品質の向上に寄与するのかを詳しく見ていきましょう。
紙の契約書は保管スペースを要する上、必要な情報に迅速にアクセスするのが難しいという課題があります。これに対し、契約書の電子化は業務の効率を高めるのです。
例えば電子契約サービスを導入すると、契約書はクラウド上に保管され、キーワード検索や分類が容易になります。これにより、過去の契約内容を確認したい場合でも数秒で目的のファイルを表示できるようになり、さらに、ファイルの改ざん防止機能やアクセス権限が管理できるため、セキュリティ面でも安心して運用できるのが強みです。
このように、契約関連の業務がデジタル化されると書類を探す時間が削減され、顧客対応のスピードや正確性が格段に向上します。業務の属人化も防げるため、誰が対応しても均質な運用が可能になるのです。
金融機関では顧客との接点が多岐にわたるため、情報が部門ごとに分断されがちです。しかし、顧客情報を一元管理すると顧客対応の質を高められるかもしれません。
CRM(顧客関係管理)システムを導入すると、顧客の属性・取引履歴・問い合わせ履歴などを1つの画面で確認できるようになります。これにより、担当者は顧客のニーズを正確に把握した上で最適な提案が可能となります。
また情報がリアルタイムで更新されるため、部署間での引き継ぎもスムーズになります。結果として、顧客満足度の向上やクレームの削減につながるのです。
従来の与信判断では、担当者が申請内容を手動で確認して過去の信用情報や収支状況を照らし合わせて判断する必要がありました。そのため、審査に時間がかかることが避けられませんでした。
しかしAIを活用した与信審査は、こうした課題を根本的に解決します。AIは、過去の膨大な取引データや信用スコアを基に、リスクを数値化して即座に判断が可能です。これにより、数日かかっていた審査が場合によっては数分で完了するケースもあります。
また人間の主観による判断のばらつきを排除できるため、公平かつ透明性の高い審査が実現します。ミスのリスクが低減し、顧客にとっても安心感のある対応となるでしょう。
金融業務の多くは、帳票作成やデータ入力、確認作業などのルーティン業務が占めています。こうした作業に時間を取られると、本来注力すべき顧客対応や企画業務に十分なリソースを割けないという悩みも少なくありません。
RPA(Robotic Process Automation)をはじめとする自動化ツールの導入により、こうした定型業務は効率的に処理できるようになるかもしれません。例えば月末の残高報告や口座振替のデータ照合など、人手による確認が必要だった業務も自動化することで作業時間を短縮できます。
結果として業務の正確性が向上し、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、組織全体の生産性向上にもつながるのです。
金融DXの最終的な目的の1つは、データドリブンな経営の実現です。これを可能にするのが各システム間のデータ連携の強化です。
従来、営業・経理・マーケティングなどの部門で使用するシステムが分断されている場合、情報の共有には時間と手間がかかっていました。しかしAPI連携などの仕組みを整備することで、異なるシステム間でもリアルタイムにデータが反映されるようになります。
営業活動のデータが即座に経理システムに反映されれば、リアルタイムで収支分析が可能になります。これにより意思決定のスピードが加速し、経営の精度も高まるでしょう。
また、顧客の行動データや購買履歴を分析することでパーソナライズされた提案が可能になる点も見逃せません。データを活用する文化が根付き始めると、企業全体の競争力が自然と高まっていくのです。
金融業界でのDXは、単なるIT化ではなく業務全体の在り方を見直す絶好の機会です。効果的にDXを推進するためには、計画的かつ段階的な進め方が重要です。
ここで紹介する7つのステップに沿って取り組むことで、無理のない形で業務プロセスの改革を進められるでしょう。
まず取り組むべきは、現在の業務のどこに無駄や重複があるのかを把握する作業です。この段階では、関係者へのヒアリングや業務フローの可視化を通じてボトルネックや手作業によるミスの発生箇所を洗い出すことが必要です。
例えば、紙ベースで行っている帳票管理やシステム間の手入力によるデータ転記などが該当します。現状の課題を具体的に把握することが、次のステップにつながる土台となります。
現状の課題が明確になったら、次はDXによって何を達成したいのかを定義しましょう。目的が曖昧なままでは途中で方向性がぶれてしまいます。「業務の効率化による人員の再配置」「データを活用した迅速な意思決定」「顧客対応の質の向上」など、具体的なゴールを設定します。同時に、経営層から現場レベルまで一貫した理解と共感を得ることも不可欠です。これによって組織としての推進力が高まり、DXプロジェクトが形骸化するリスクを減らせます。
DXを進める上で欠かせないのがデータの整備です。導入予定のツールが高度な分析機能を持っていても、元となるデータが不整合だらけでは効果を十分に発揮できません。顧客データの名寄せや項目の標準化、古い情報の整理などあらかじめクレンジングを行うことが重要です。これにより、新しいツールの性能を最大限に活かせる状態を整えられます。
市場には多種多様なDXソリューションが存在しますが、すべてが自社に合うとは限りません。選定時には、現場の実態に即した業務フローに対応しているかどうかを重視しましょう。
例えば、審査プロセスの自動化を目指す場合にはAI与信機能があるツールが、顧客管理の高度化を目指すならCRM(顧客関係管理)ツールが有効です。実際の業務にフィットするかどうかを見極めるため、無料トライアルやデモを活用しましょう。
一度に全社導入を行うと、現場が混乱し逆効果となる恐れがあります。そのため、まずは一部部署や業務に限定してパイロット導入を行い、実際の運用を通じて効果や課題を検証しましょう。この段階でフィードバックを得て調整を行うことで、全社展開時のリスクを軽減できます。また成果を数値で可視化しておくと、他部署への導入を進める際の説得材料になります。
どれだけ高性能なツールを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。現場従業員のデジタルリテラシー向上は、DX推進において避けて通れない要素です。具体的には、操作方法だけでなく「なぜこのツールを使うのか」「業務がどう変わるのか」まで理解を促す研修を行うと良いです。定期的な勉強会やeラーニング、マニュアルの整備など多角的なアプローチで社内全体の底上げを図りましょう。
DXは導入して終わりではなく、継続的な改善と進化が求められます。導入後は定期的なレビューを行い、当初の目的に対して効果が出ているかを確認する必要があります。さらに、業務環境や顧客ニーズの変化に応じてツールや業務フローのアップデートも重要です。このようなPDCAサイクルを継続することでDXの真価が発揮されるでしょう。
金融業界に特化したDXの推進は、業界構造や規制、顧客ニーズを深く理解したパートナーと進めることが成功のカギとなります。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、数多くの金融機関と協働してきた実績を基に貴社の業務特性や課題に応じた最適なソリューションをご提案いたします。ツールの選定から導入支援、現場教育、定着支援まで一貫して伴走いたしますので、DXに不安を感じている方も安心してご相談ください。

金融DXは、業務の効率化やデータ活用による意思決定の迅速化、顧客サービスの高度化を実現する力強い手段です。適切なステップを踏んで進めることで、導入時の混乱を避けながら、持続的な効果を得られます。また、社内のデジタルリテラシーを高めて継続的な見直しを行うことも成功には欠かせません。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、金融機関のDX推進において、実行性の高い戦略策定と現場密着型の支援を行っております。未来志向の業務プロセス改革を進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
