金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融


金融DXを成功に導くためには、web3の技術だけでなく制度・UX・組織対応までを包括的に検討する必要があります。本記事では、web3を金融DXに活用する具体的な方法や留意点を解説しています。初めての方でも安心して読める内容です。
急速に進化するテクノロジーの波に乗り遅れないために、金融業界では「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」への取り組みが加速しています。一方で「web3」という新たな概念が注目を集めており、これまでのインターネットとは異なる分散型の仕組みが、多くの業界に変革をもたらし始めています。特に金融分野では、金融DXとweb3の相乗効果によってより安全で透明性の高い金融サービスの提供が可能になりつつあるのです。
本記事では、まず金融DXとweb3の関係をわかりやすく整理し、次にそれらを組み合わせることでどのような未来が切り開かれるのかを詳しく解説します。読み進めると、次世代の金融ビジネスがどう変わるのか、またその変化にどう対応すべきかが明確になるはずです。金融業界での競争力を高めたい方や今後の動向を正しく理解しておきたい方にとって、有益な情報を得られるでしょう。
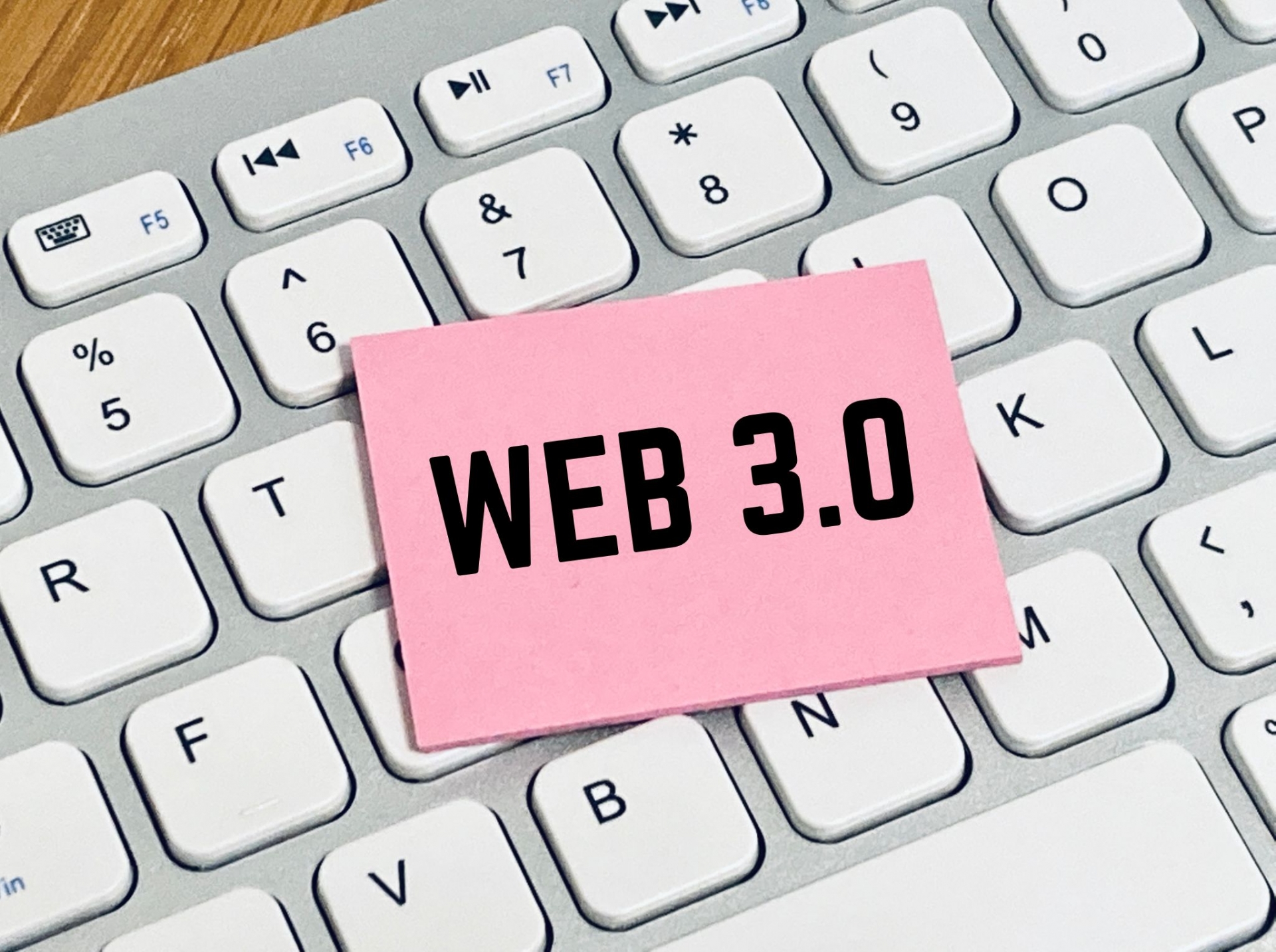
テクノロジーの革新がもたらす金融の変化は単なるIT化にとどまりません。金融DXとweb3はそれぞれ独立した概念のように見えますが、実は相互に作用し合いながら、これまでにない新しい金融サービスの創出を支えています。
金融DXとは、金融業界における業務やサービスのデジタル化を通じて、業務効率の向上や新たな価値提供を実現する取り組みです。単に紙からデジタルに置き換えるのではなく、顧客体験やビジネスモデルそのものの再構築を目指します。オンラインバンキングの進化やスマートフォンアプリによる金融商品へのアクセスなどがその一例です。
デジタル技術を活用することで顧客との接点が増え、ニーズに合わせたサービス提供が可能になります。また、AIやビッグデータの導入によりリスク管理やマーケティングも高度化も進んでいます。
web3とは、ブロックチェーン技術を基盤とした次世代のインターネット概念です。従来の中央集権的な構造とは異なり、ユーザー自身がデータの所有権を持ってサービスを共同で運営する分散型の仕組みが特徴です。代表的な例としては、仮想通貨・NFT(非代替性トークン)・DAO(分散型自律組織)などがあります。
web3の特徴は、情報の改ざんが困難で透明性が高い点にあります。金融業界においては、取引の信頼性やセキュリティを高める要素として期待されているのです。
金融業界におけるweb3の役割は多岐にわたりますが、特に重要なのは「信頼性の確保」「効率化」「分散管理」の3点です。従来の金融システムは中央管理者の存在を前提としていましたが、web3ではユーザー間で直接信頼関係を構築しながら取引が行われます。
また、スマートコントラクト(自動実行される契約)によって人的介在を最小限に抑えた処理が可能になり、業務効率の向上にもつながります。さらにweb3の思想はユーザーのデータ主権を尊重するため、顧客情報の取り扱いに関する新たな価値観を提示しているのです。
金融DXとweb3を連携させることで、これまでにないサービス設計が可能になります。ここではその具体例を紹介します。
顧客認証は金融サービスにおいて重要な要素ですが、従来は金融機関が顧客情報を一元管理してきました。そこでweb3の思想を取り入れると、「自己主権型ID(Self-Sovereign Identity:SSI)」の導入が進みます。これは、個人が自分の情報を自身で管理し必要に応じて各サービスにアクセス許可を与える仕組みです。
SSIを活用することで、ユーザーは複数の金融サービスにまたがって同一のIDを利用できるようになり、手続きの簡略化とセキュリティの向上が期待されます。加えて、金融機関側もデータ管理コストを削減できるという利点もあります。
分散型金融(DeFi:Decentralized Finance)は、ブロックチェーン上で提供される金融サービス全般を指します。銀行や証券会社といった仲介機関を介さずに、ユーザー同士が直接取引できる点が特徴です。
DeFiを導入することで取引記録がすべてブロックチェーン上に記録され、誰でも確認できる状態になります。これにより、金融取引の透明性が向上するのです。また、スマートコントラクトを活用すれば契約条件が自動的に実行されるため、人的ミスの削減や業務効率の向上にもつながります。
NFT(Non-Fungible Token)は、唯一性を持つデジタル資産の証明手段です。金融分野では、土地や不動産などの現物資産をNFT化してデジタル上で取引・管理する取り組みが始まっています。
これにより資産の分割所有や売買が容易になり、これまで参加が難しかった個人投資家にも新たな投資機会を提供できているのです。さらに、NFTに履歴情報を付与することで資産の由来や所有者の変更履歴も明確になり、信頼性の高い資産管理が可能となっています。
DAO(Decentralized Autonomous Organization)は、スマートコントラクトを基盤にして構築される分散型組織です。金融機関の運営にDAOの仕組みを取り入れると、投資家や顧客が意思決定に参加できるようになります。
この過程ではガバナンストークンを通じて提案や投票が行われ、透明性のある意思決定が実現されます。これによって組織の信頼性や利用者との関係性が深まり、長期的な成長を目指せるのです。特に資産運用会社などでは運用方針の見える化と柔軟な対応力が求められるため、DAOとの親和性が高いといえるでしょう。
金融サービスでは、個人情報の管理と保護が最重要課題の1つです。従来の中央集権型システムでは一箇所に情報が集中するため、サイバー攻撃による情報漏えいリスクが常に存在していました。
web3では、データを分散的に保管することで特定のポイントに依存しない安全性の高い構造を実現できます。顧客自身が情報の取り扱いを管理できる仕組みも整っており、金融機関と利用者の間での信頼関係構築にも役立ちます。
近年、ブロックチェーン技術をはじめとしたWeb3の進展により、金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は新たな局面を迎えています。これまでの金融DXは主に業務のデジタル化や自動化に焦点を当ててきましたが、Web3を取り入れることで「信頼性」や「分散性」といった新たな価値軸を加えることが可能となりました。
ここでは、Web3の技術を金融DXに応用し、実践的な成果を挙げている国内企業の事例を3つ紹介します。
三井住友信託銀行は、不動産登記情報の管理業務においてブロックチェーン技術を活用した取り組みを行っています。背景には、登記情報の真正性の確保や煩雑な情報管理の効率化が求められていた点があります。
実際に同社は、2018年に不動産情報コンソーシアムと連携し、登記簿情報のブロックチェーンによる管理実証を実施しました。この取り組みでは、ブロックチェーンが持つデータの改ざん耐性や透明性を活かし、登記情報の信頼性向上と同時に取引プロセスの迅速化を目指しました。
その結果紙ベースでの確認作業が不要となり、関係者間のデータ連携がスムーズになったことで業務の省力化とリスク低減が実現しました。将来的にはこの仕組みを全国の不動産取引に広げる構想も視野に入れています。
参考:三井住友信託銀行株式会社
通信業界大手のKDDIもWeb3技術の活用に積極的です。特に注目すべきは、NFT(非代替性トークン)を活用した顧客エンゲージメント施策です。この取り組みの目的は、従来のポイント付与やメールマーケティングでは得られにくかった顧客のロイヤルティ向上を図ることでした。
2024年には、地域創生イベントと連動したNFTの発行を通じて来場者に限定アイテムを提供するプロジェクトを実施しました。NFTは所有者の証明ができるだけでなく、他者への譲渡や再利用も可能であるため、単なるノベルティにとどまらない体験価値を生み出します。
この施策により、ユーザーとの中長期的な関係構築が進み、デジタルマーケティングの高度化につながっています。さらに、ブロックチェーン上に顧客の行動履歴を記録することで次の施策立案にも活用可能なデータ資産を蓄積する形になりました。
参考:KDDI株式会社
SBIホールディングスは、金融グループとしては異例ともいえるスピードでWeb3領域に参入しており、特にDeFi(分散型金融)事業において存在感を高めています。背景には、中央集権的な金融モデルから脱却して透明性と柔軟性を備えた金融サービスへの進化を目指す姿勢があります。
同社は、2022年時点で暗号資産を活用した資産運用サービスや海外のDeFiプロジェクトへの出資を進めてきました。これにより、個人投資家が中央機関を介さずに資産を運用できる環境を整備し、新たな金融インフラの構築を実現させたのです。
また、SBIは独自のステーブルコイン開発やブロックチェーン上での決済基盤整備にも着手しており、単なる技術導入にとどまらずグループ全体でWeb3のエコシステムを形成しようとしています。このような姿勢は、国内外の金融機関にとって今後のDX戦略を見直すきっかけとなるでしょう。

金融DXを推進する上でweb3の技術をどのように実際のサービスに取り入れるかが、今後の金融業界の競争力を左右します。デジタル変革と分散型技術の融合は、顧客体験の向上だけでなく取引の透明性やセキュリティの強化にもつながるためです。
ここでは、具体的にどのような方法で両者を組み合わせられるのか、5つの視点から掘り下げていきます。
従来の金融取引では中央集権的なデータベースに依存しており、システム障害やサイバー攻撃のリスクが常に存在していました。これに対してweb3の中核技術であるブロックチェーンを活用すると、トランザクションの真正性と整合性を担保しやすくなります。
ブロックチェーンは取引履歴が改ざんされにくく、誰がどのタイミングで何をしたかを明確に記録できるため不正の抑止にもつながります。またスマートコントラクトを用いれば、取引の自動化も可能になるのです。ローンの契約が成立した時点で自動的に資金が移動する仕組みを構築することで、人的ミスや処理の遅延を削減できるでしょう。
ただし、ブロックチェーン技術の導入にはシステムの複雑化やスケーラビリティの課題があるため、適切な設計と運用体制の構築が欠かせません。
金融サービスを利用する上で欠かせないのが、本人確認のプロセスです。現在主流のKYC(Know Your Customer)では銀行や金融機関が個別に顧客情報を管理しており、重複登録やプライバシーの懸念が生じています。そこで注目されているのが、自己主権型ID(Self-Sovereign Identity)です。
SSIでは個人が自らのデジタルIDを所有・管理し、必要に応じて情報の開示範囲を制御できます。例えば特定の金融サービスを利用する際、住所や年齢など最低限の情報だけを一時的に提示することが可能になります。このアプローチは顧客の利便性を高めるだけでなく、金融機関側の個人情報管理の負担も軽減するでしょう。
しかし、SSIの普及には法規制の整備や標準化の促進が必要であり、導入時にはその動向を注視する必要があります。
分散型金融(DeFi)は、仲介者を介さずに金融取引を行える新しい仕組みです。ブロックチェーンとスマートコントラクトを組み合わせることで、ピア・ツー・ピアの貸付や即時送金が実現可能になります。従来の金融機関では処理に数日かかる国際送金も、DeFiを活用すれば数分で完了する場合があるのです。
また、DeFiは金融包摂の観点からも注目されています。従来の金融機関のサービスを受けられなかった人々でも、インターネット接続さえあれば資産運用や融資を利用できます。これによって新たな顧客層へのアプローチが可能となり、金融業界の裾野が広がっているのです。
とはいえ、DeFiの分野はまだ法整備が追いついておらず、利用にあたってはリスク管理や規制対応が不可欠です。
NFT(Non-Fungible Token)は、唯一無二のデジタル資産を表現できる技術です。金融領域では、NFTを用いて資産や契約の所有権を明確に示す活用が進み始めています。例えば、不動産の権利証をNFTとしてトークン化すれば、売買の履歴や所有の正当性をブロックチェーン上で管理できます。
また、デジタル証券(セキュリティトークン)や知的財産権の管理にも応用が可能です。スマートコントラクトと連動させることで、使用権の移転やロイヤリティ支払いなどを自動で処理できます。これにより、透明性とスピードを兼ね備えた新たな資産管理の仕組みが実現するのです。
ただし、NFTの法的な位置付けや税務処理についてはまだ課題が多いため、慎重な対応が求められます。
DAO(Decentralized Autonomous Organization)は、中央の管理者を置かずにコミュニティ全体で運営方針や意思決定を行う組織形態です。金融業界においてDAOを取り入れることでユーザー参加型の商品設計が可能となり、顧客ニーズにより即したサービス開発が進みます。
例えばある投資ファンドの運用方針をDAOで決定する場合、トークンを保有する参加者が議決権を持ちます。この仕組みにより、特定の利益団体に偏らない、透明性の高い運営が期待されるのです。また、DAOの運営はスマートコントラクトによって管理されるため、投票や配当の仕組みも自動化され、効率化が図れます。
ただし、DAOは法的な整備が進んでいない分野であり、規制対応やガバナンスの問題に対する慎重な検討が必要です。
Web3の技術を金融DX(デジタルトランスフォーメーション)に活用する際には、ただ技術導入を進めるだけでは不十分です。技術の裏側にある制度、ユーザー体験、そして業務プロセスとの適合性を含め、包括的な視点が求められます。
ここでは、Web3と金融DXを組み合わせる上で意識すべきポイントを具体的にご紹介します。
Web3は、従来の金融システムとは異なる分散型の仕組みで成り立っています。そのため現行の法律や制度と齟齬が生まれやすく、コンプライアンスリスクを正しく管理するためには法規制の動向を常にチェックする姿勢が不可欠です。
例えば、暗号資産(仮想通貨)に関連する法律やNFT(非代替性トークン)の取り扱いに関するガイドライン、さらにはDAO(分散型自律組織)の法的立ち位置など法制度の整備は国によって異なります。日本においては、金融庁や経済産業省などが発信する情報に注意を払い、導入予定の技術が法的に問題ないかどうかを事前に確認することが重要です。
また制度と技術のギャップを埋めるためには、社内に法務・コンプライアンスチームとの連携体制を構築し、法的視点からのリスク分析も取り入れながら開発・導入を進める必要があります。
Web3の特性を活かすためには、顧客が直感的に操作できるインターフェースの設計が不可欠です。DeFi(分散型金融)やNFT、自己主権型ID(SSI)といった仕組みは、技術的に複雑であるがゆえにUX(ユーザーエクスペリエンス)の設計が甘いと利用者にストレスを与えてしまいます。
例えば、ウォレットの接続・ガス代(手数料)の設定・秘密鍵の管理などWeb3独自の操作は一般ユーザーにとって馴染みが薄いため、案内表示や導線設計を工夫する必要があります。
そのため、プロトタイプ段階からユーザビリティテストを実施し、ユーザーの理解度や操作性を検証する必要があるのです。UX設計では、「どのようにすればユーザーが安心してWeb3サービスを使えるか」という視点を忘れずに取り入れるようにしましょう。
Web3の導入は、既存の金融システムや業務フローに影響を及ぼす可能性があります。そのため、一気に全面的な改革を目指すのではなく、まずは特定の領域や限定的なユースケースから段階的に取り組むことが効果的です。
例えば、社内の契約管理業務にNFTを活用してみる、特定の顧客グループに自己主権型IDのログイン機能をテスト導入してみるなど小規模な実証実験(PoC)を通じて課題やメリットを検証するアプローチが有効です。
また、業務担当者や開発チームだけでなく、経営層を含めた全社的な理解と合意形成も欠かせません。新しい技術は導入後に定着しなければ意味がないのです。段階的な導入によって社内の混乱を抑え、スムーズに金融DXの成果につなげていきましょう。
Web3と金融DXの融合には、専門的な知見と実践的なプロジェクト推進力が求められます。特に、制度設計・UX構築・段階的導入など複数の要素が複雑に絡み合うため、自社だけでの推進に不安を感じる企業も少なくありません。
そこで、Web3の活用や金融DXに関心をお持ちの方は、ぜひ『株式会社 TWOSTONE&Sons』までお気軽にご相談ください。当社は、最先端技術と実行支援の両軸で貴社のデジタル変革をサポートいたします。
初期構想段階のアイデア整理から実証実験の計画、導入支援までワンストップで対応可能です。複雑化するWeb3市場において、迷わず前進するためのパートナーとして私たちがお手伝いさせていただきます。

金融業界の未来を切り拓くカギとなるのが、「金融DX」と「Web3」の融合です。以下のような先進技術を活用すれば、これまでにない顧客体験や業務効率化の実現が可能になります。
しかしながら、その導入には制度理解、ユーザー視点、社内の調整などいくつもの課題が伴います。だからこそ、信頼できる外部パートナーとともに段階的に取り組む姿勢が重要です。
もし今後の推進に向けた課題や疑問がある場合は、ぜひ『株式会社 TWOSTONE&Sons』へご相談ください。未来の金融を共につくっていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
