金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

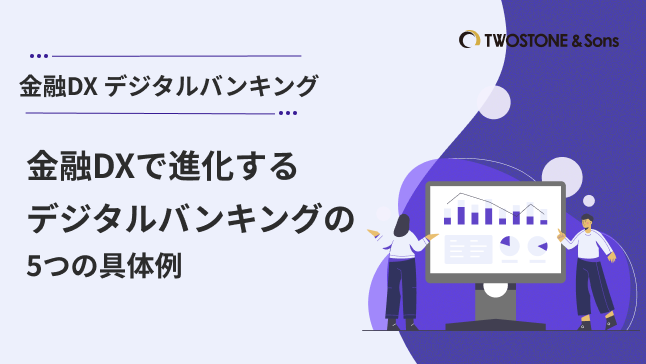
金融DXを推進してデジタルバンキングを開発する際には、セキュリティ対策やユーザーインターフェースの最適化、柔軟な組織体制が重要です。デジタルバンキングの導入方法や事例を知りたい方は必見です。
近年、銀行の窓口に足を運ぶ機会が減ったと感じていませんか。ネットバンキングやスマホアプリを使えば、振込や残高確認などがいつでもどこでも簡単にできる時代になりました。このような変化を支えているのが「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。特にその中核を担うのが「デジタルバンキング」で、私たちの金融体験そのものを大きく変えようとしています。
本記事では、金融DXとデジタルバンキングの基本的な関係性から、なぜ今デジタルバンキングが必要とされているのか、そしてそれがどのように実践されているのかを5つの具体例とともに紹介します。この記事を読むことで、金融業界の変革の全体像がつかめるだけでなく、どのように企業が金融DXの波に乗るべきかのヒントも得られるでしょう。

テクノロジーが進化し続ける中、金融機関もその変化に対応しなければ生き残れない時代となりました。ここでは、金融DXとデジタルバンキングがどのように関係しているのかを整理していきます。
金融DXとは、デジタル技術を活用して金融業界の構造やサービスを根本から変革し、業務効率化・顧客体験の向上・新たな収益モデルの構築を実現する取り組みを指します。具体的には、AIによる審査の自動化・オンライン契約・APIによるサービス連携などが含まれます。
単なるシステムの導入ではなく、企業文化や業務プロセスそのものを変える必要がある点が特徴です。金融DXによって従来の人手による煩雑な手続きがスムーズになり、顧客との接点も多様化しています。
デジタルバンキングは金融DXの具体的な形のひとつで、インターネットやモバイルアプリを通じて提供される銀行サービス全般を指します。店舗に依存しないサービス展開が可能となるため、場所や時間に縛られずに取引が行えるようになります。
今では口座開設から融資申込、資産運用までを一気通貫でオンライン上で完結させる銀行も増えており、利用者にとって利便性が向上しているといえるでしょう。
金融DXの中核には、顧客中心のサービス改革という視点があります。デジタルバンキングはその最前線にあり、DXの推進によって実現される成果を直接的に体感できる分野です。
システムの刷新や業務フローの再設計といった裏側の変革が、デジタルバンキングという表現を通じて顧客に提供されます。つまり、金融DXを進めるほどデジタルバンキングの機能やサービスの進化が期待できます。
急速な社会変化と顧客ニーズの多様化により、金融業界にはこれまで以上の柔軟性とスピードが求められています。ここでは、なぜデジタルバンキングの導入が急務なのか、3つの視点から見ていきます。
消費者はスマートフォンを通じて、あらゆるサービスを手元で完結させることを求めています。買い物・交通・食事の注文だけでなく、金融取引に対しても同様の利便性が期待されています。
若年層を中心に来店不要で即時に対応できるサービスが好まれる傾向があり、これは従来型の対面中心の銀行業務では対応しきれません。しかしデジタルバンキングによって、こうしたユーザーの期待に応えられるでしょう。
金融業界では、フィンテック企業の台頭により競争が一層激しくなっています。これらの新興企業は、柔軟なシステムと優れたUI/UXを武器に若い世代の支持を集めています。
伝統的な銀行も、この流れに対応しなければ、顧客を失うリスクがあるのです。競争に勝つためにはスピーディでパーソナライズされたサービス提供が不可欠であり、デジタルバンキングの導入はその基盤となるのです。
人手に依存した業務は、人的ミスの発生リスクや人件費の増加といった課題を抱えています。加えて、各種書類の管理や紙ベースの手続きは業務スピードの阻害要因となります。
そこでデジタルバンキングの導入によって口座開設・ローン申請・本人確認などのプロセスを自動化・効率化すると、業務負担の軽減とコスト削減が可能です。金融機関にとって、持続可能な経営を実現するための一手ともいえるでしょう。
金融DXを進める上でデジタルバンキングの開発は避けて通れない要素です。従来の業務を見直し、テクノロジーの力でサービスを再構築することによって多くの利点が得られます。
ここでは、その中でも特に注目されている5つのメリットについて、具体的に解説します。
最初のメリットは、顧客対応のスピードが格段に上がる点です。従来の金融業務は、多くの場面で人手による処理に頼ってきました。口座開設やローン審査、住所変更などすべてに時間がかかっていました。
しかしデジタルバンキングを導入すると、これらの手続きの自動化が可能になります。例えば、本人確認をAIで即時に行い、わずか数分で口座を開設できるケースも珍しくありません。
対応が迅速になることで、顧客の満足度も大きく向上します。待ち時間の短縮だけでなく、手続きの簡素化や透明性の向上にもつながるためです。こうした取り組みは、競争優位性の確保にも役立つでしょう。
次に挙げられるメリットは、サービス提供の時間制約を取り払える点です。デジタルバンキングではインターネットを通じて金融サービスを提供するため、時間や場所に縛られません。
従来の銀行窓口では営業時間外には対応ができず、顧客は平日の日中にしか手続きが行えませんでした。そのため、働いている人にとっては不便な状況でした。
一方デジタルバンキングでは、深夜でも休日でもスマートフォン1つで振込やローン申請、投資商品の購入が可能です。これにより、ユーザーのライフスタイルに寄り添ったサービスが実現します。
また、チャットボットや自動応答システムの導入により、有人対応でなくても基本的な質問に即座に応じることが可能です。結果として、顧客満足度の向上と業務負担の軽減を同時に達成できるでしょう。
デジタルバンキングは、金融機関の内部業務の効率化にも大きく貢献します。特に、従来人手で行っていた業務の自動化が進むことで、作業時間と人的コストの削減が見込めます。
実際に、住宅ローンの審査では、書類確認や信用情報の照合に多くの時間を要していました。しかし今ではAIとRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の組み合わせにより、工程を短時間で処理できるようになっています。
こうした業務効率化により、従業員はより高度な判断や顧客対応に集中できるようになりました。また、エラーの削減やデータの一元管理も実現できるため、全体の生産性が向上するでしょう。
結果的に、コストを抑えつつより高品質なサービスを提供できる体制が整います。これは、企業の競争力を高める重要な要素となるでしょう。
デジタルバンキングの導入は顧客データの取得と分析を容易にし、それを活用したサービス改善に直結します。従来、顧客のニーズ把握はアンケートや対面ヒアリングに頼っていました。
しかし現在では、ログイン履歴・取引履歴・クリック動線など膨大なデジタルデータが蓄積されます。そのため、これらを分析すると個々の顧客に最適な商品提案ができるようになるのです。
例えば、給与の入金日や生活費の支出パターンから適切な貯蓄プランを自動提案する機能があります。さらに、住宅購入を検討しているタイミングでローン商品の案内を行うなど、的確なタイミングでのアプローチも可能になります。
顧客一人ひとりに寄り添ったサービスを提供することでエンゲージメントが高まり、長期的な関係構築へとつながります。データを資産として捉えて最大限に活用する姿勢が、今後さらに求められるでしょう。
最後に、新たな収益源の確保もデジタルバンキングの大きな利点です。これまで金融機関の収益モデルは、預金・貸出・手数料収入が中心でした。
しかし、デジタルバンキングではAPI連携を活用した外部サービスとの連携が可能となり、従来とは異なる形の収益モデルが生まれています。実際に、保険や投資、家計管理アプリなどとの連携を通じて利用者の行動データから最適な提案を行い、成功報酬や連携手数料を得る仕組みが増えています。
また、プラットフォーム化を進めることで、金融機関が単なるサービス提供者ではなく顧客の生活全体を支援する存在へと変化できます。こうした付加価値の高いサービスは価格競争に巻き込まれるリスクも低く、持続的な収益基盤を支える力になります。
金融サービスのデジタル化が進む中で、こうした多角的な収益確保の手段は重要です。単にコスト削減を目的とするのではなく、新たな成長戦略として活用する視点が求められます。

ここまでは、デジタルバンキングの導入による5つのメリットを紹介しました。実際に多くの金融機関がDXに取り組んでおり、それぞれが独自の戦略と技術を駆使してサービスを展開しています。
ここからは、国内主要銀行によるデジタルバンキングの具体的な取り組みについて解説し、その特徴や工夫から学べるポイントを見ていきます。
三菱UFJ銀行は日本最大規模のメガバンクとして、早い段階からデジタルバンキングの開発に着手してきました。その中核サービスが「三菱UFJダイレクト」です。
三菱UFJダイレクトのサービスの最大の特徴は高いセキュリティと多機能性の両立です。ワンタイムパスワードや指紋認証によって不正ログインのリスクを低減しつつ、スマートフォンから預金残高の確認、振込、定期預金の作成までを一括して行えます。
またユーザーインターフェースの改善にも積極的で、直感的な操作性を実現しています。実際に、UI/UXの最適化を進めたことで利用者の離脱率が低下し、サービス定着率が向上したとのことです。
三菱UFJ銀行がここまでの利便性と安全性を確保できている背景には、金融とITの専門チームが密に連携し、顧客の声を反映しながらPDCAを回している体制があります。今後もさらなる機能拡充が期待されます。
みずほ銀行もまた、大規模なデジタルシフトを進めている金融機関の1つです。代表的なサービスが「みずほダイレクト」で、個人顧客向けにオンラインでの金融取引を幅広く提供しています。
みずほダイレクトの特筆すべき点は、手続きの簡素化とサポート体制の充実です。例えば、住所変更や公共料金の引き落とし口座変更など、煩雑だった手続きをオンラインで完結できるようになっています。
さらに操作に不安を感じる高齢者層にも配慮し、サポート体制を強化しています。画面案内やチャットサポートの導入により、デジタルに不慣れなユーザーでも安心して利用できるようになりました。
みずほ銀行は「デジタルと人間の融合」を掲げており、あくまで顧客体験を中心に据えた設計思想が反映されています。利便性の追求だけでなく、誰もが使いやすい環境づくりを重視している点が印象的です。
参考:みずほ銀行
三井住友銀行(SMBC)は、スマートフォン特化型のバンキングサービスを強化することで、若年層やビジネスパーソンの獲得を図っています。主力サービスである「スマートフォンバンキング」は、アプリの利便性を最大化するよう設計されています。
スマートフォンバンキングのサービスのカギとなるのが「シンプルさ」と「スピード感」です。具体的には、アプリの起動から残高照会、振込までの操作を最小限のステップで完了できるように設計されています。またワンタッチでメイン機能にアクセスできる構造になっており、操作の迷いを最小限に抑えています。
さらに、取引履歴や支出分析機能なども搭載しており、家計の見える化を支援する機能も充実しているのが特徴です。金融機関という枠を超えて、生活全体をサポートするサービス設計が見受けられます。
SMBCの取り組みは「アプリが窓口になる時代」への的確な対応であり、これからのバンキングの在り方に一石を投じるものといえるでしょう。
auじぶん銀行はKDDIと三菱UFJ銀行が共同出資して設立された新しい形の銀行で、モバイルファーストの思想を徹底したデジタルバンクです。
auじぶん銀行の最大の強みは、KDDIの通信インフラを活用した「スマートフォンに最適化された金融サービス」です。銀行アプリから通信契約やポイント管理まで一元的に連携できる点が、従来の銀行との差別化要因となっています。
また、AIを活用した「住宅ローン審査のスピード化」も注目されています。顧客がスマートフォンで申し込みを行うとAIが信用情報を自動で分析し、迅速に審査結果を提示するという仕組みです。
他にも口座開設や資産運用サービスなど、すべてがアプリ1つで完結する設計となっており、スマホ世代にフィットした利便性の高さが高く評価されています。
このように、auじぶん銀行はIT企業と金融の融合による新たな価値を提供しており、既存の金融業界に刺激を与える存在となっています。
参考:auじぶん銀行
楽天銀行は、インターネット専業銀行として国内最大級の規模を誇ります。楽天グループとの連携を武器に、他行とは異なるユーザー体験を提供している点が特徴です。
まず注目したいのが、「楽天ポイント」との連動です。口座の利用に応じてポイントが付与され、楽天市場での買い物に活用できます。この「ポイント経済圏」は利用者の囲い込みに効果的で、リピーターの創出に貢献しています。
また、API連携を積極的に推進しており、他の金融サービスや家計簿アプリとの接続性が高いことも魅力の1つです。さらにログインや取引認証には生体認証を採用し、安全性と快適性を両立しています。
楽天銀行は、銀行機能を1つのサービスととらえるのではなく、「楽天エコシステム」の中核として位置づけています。その戦略性とユーザー中心設計は、今後の金融DXを考える上で重要な示唆を与えてくれるでしょう。
参考:楽天銀行
ここまで、国内主要銀行のデジタルバンキング事例を紹介してきました。しかし、こうした取り組みを自社で実現するには、具体的な推進プロセスを理解することが欠かせません。デジタルバンキングの導入を成功させるには、段階的かつ戦略的な金融DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められます。
ここでは、デジタルバンキング開発を進める上で重要な5つのステップを紹介し、それぞれの取り組み方やポイントを詳しく解説していきます。
金融DXを始める第一歩は、自社の現行システムの棚卸しです。なぜなら、既存インフラの制約を把握しないまま新しい技術を導入しても期待される効果が得られない可能性があるからです。
評価の際には、勘定系システムやチャネル系システム、CRM(顧客管理システム)などの業務基盤に注目しましょう。それぞれがどのように連携しているか、セキュリティや拡張性は十分か、保守運用にどれだけのコストがかかっているかを洗い出すことが重要です。
さらに、他システムとのAPI連携のしやすさも評価ポイントとなります。モダナイゼーション(老朽化システムの刷新)が必要な部分があれば、早期に方針を固めることで後の開発工程がスムーズになります。
このプロセスは時間と労力がかかるものの、基盤を見直すと無駄なコスト削減や柔軟な設計が可能になるでしょう。
次に取り組むべきは、顧客が本当に求めているサービスの把握です。顧客視点に立ったサービス開発を行うと利用率の高いプロダクトへとつながります。
まず既存チャネルの利用データを分析し、どの時間帯にどの機能が使われているのかを把握しましょう。次に、Webアンケートやインタビュー調査などを活用して定性的なニーズも収集します。
このとき大切なのは、潜在的な不満や未充足ニーズを見逃さないことです。例えば、「窓口は混雑しているが、アプリでは手続きできない」といった声は、新たなサービス開発のヒントになります。
加えて、ペルソナを設定し、ライフスタイルに応じたニーズを可視化すると、より具体的なUX設計が可能になります。顧客理解を深めることは、差別化戦略にもつながる重要な工程です。
顧客ニーズが明確になったら、それを実現するためのテクノロジーとインフラの選定・整備を行います。システム開発においては、クラウドサービスやマイクロサービスアーキテクチャの活用がカギとなります。
クラウド化によって、柔軟なリソース配分とスケーラビリティが得られるでしょう。また、マイクロサービスを導入することで機能単位での開発・改修が可能になり、開発スピードと保守性が向上します。
DXを推進するには、セキュリティ対策も不可欠です。多要素認証や暗号化通信、AIによる不正検知などを取り入れ、安心して使える環境を構築しましょう。FinTech業界では、ゼロトラストセキュリティの導入が急速に進んでいます。
さらに、API基盤の整備によって外部サービスとの連携が容易になり、将来的なサービス拡張にも柔軟に対応できます。テクノロジーは目的ではなく手段であるため、顧客体験を向上させる視点を持って取り入れることが重要です。
システムやサービスが整備されたとしても、活用するのは最終的に「人」です。したがって、従業員が新しい仕組みに適応し、自ら変化を受け入れられる体制を築く必要があります。
教育研修では、操作マニュアルの提供だけでは不十分です。デジタルの基礎リテラシーだけでなく、顧客目線での思考やイノベーションマインドを育むプログラムが求められます。
また、社内にDX推進チームや担当者を配置し、現場との橋渡し役を担ってもらうことも有効です。これによりトップダウンとボトムアップの両面から改革が進みやすくなるでしょう。
意識改革を進める上では、「失敗を許容する文化」も大切です。変化に伴うトライ&エラーを積極的に支援する風土をつくることで、現場からの創発的な提案が増えてくるでしょう。
最後に、社内リソースだけでなく外部との協業を前提とした戦略を持つことが、金融DXの成功には不可欠です。なぜなら、すべての技術やノウハウを自前で用意するには限界があるためです。
例えば、UI/UX設計に長けたデザイン会社、セキュリティ技術に強みを持つスタートアップなどと協業するのもよいでしょう。他にも、顧客分析を支援するデータサイエンティストなど外部パートナーの専門性を活用することで、高品質なサービスを短期間で実現できます。
またAPI公開によるオープンバンキングの取り組みを通じて、FinTech企業や異業種との連携も加速しています。共創によって新たな金融サービスの形が生まれ、顧客価値の最大化につながるでしょう。
重要なのは、信頼関係を構築して継続的にパートナーと目線を揃えるマネジメント力です。単なる委託関係にとどまらず共に未来を描くビジョンを持つことで、持続可能なイノベーションが実現するでしょう。
デジタルバンキングの開発は、技術的な課題だけでなく運用面や顧客対応における多くの配慮が求められます。どれほど優れたテクノロジーを導入しても、基本的な方針を誤れば信頼性を損ない、顧客離れにつながりかねません。
ここでは、金融DXを成功に導く上で特に注意すべき3つのポイントを紹介します。
なぜセキュリティを最優先にする必要があるのでしょうか。それは、金融サービスが扱う顧客情報には、口座情報や本人確認書類、取引履歴などセンシティブな内容が含まれているためです。もし情報漏えいが起きれば企業の信用失墜は避けられません。
まず、サイバー攻撃への備えとしてWAF(Web Application Firewall)やIPS(侵入防止システム)などの導入を検討しましょう。また、クラウド環境で運用する場合にはクラウドセキュリティフレームワークにもとづいた設計が欠かせません。
さらに、社内のアクセス管理も重要です。ゼロトラストアーキテクチャを導入し、「信頼せず、常に検証する」という原則にもとづいた運用体制を構築することで内部不正のリスクも軽減できます。
安全性を高めることは、利用者に安心感を提供し長期的な顧客関係の構築にも直結します。
金融サービスは、誰もが日常的に使うものです。そのため、デジタルバンキングでは直感的に操作できるユーザーインターフェース(UI)が重要です。
顧客がスムーズに取引を行えるようにするためには、情報の整理や操作導線の工夫が欠かせません。アプリやWeb画面では「次に何をすべきか」がすぐにわかる設計が求められます。
このようなUIを実現するには、UI/UXデザイナーによるユーザーテストやプロトタイピングを積極的に活用しましょう。また、視認性の高いフォントや配色、誤操作を防ぐボタン配置など、細部まで配慮が必要です。
操作性の高いインターフェースは利用率や継続率の向上にもつながり、結果として収益性にも貢献するでしょう。
金融業界を取り巻く環境は、テクノロジーの進化や法規制の変更によって日々変化しています。そのため、DXを進める企業には柔軟性が求められます。
具体的には、組織内にアジャイル開発を取り入れる体制を整えましょう。アジャイル開発とは、短期間で機能をリリースし、ユーザーの反応をもとに改善を繰り返す開発手法です。この方法を採用することで、市場の変化に迅速に対応できます。
また、定期的な社内レビューやKPIモニタリングを実施し、ボトルネックを早期に発見・修正できる仕組みも整備しましょう。こうした取り組みが、DXの持続的な推進を支えます。
変化に強い組織を構築することは、デジタルバンキングの成否を左右する要素の1つです。
金融DXの成功には、技術、デザイン、業務の知識をバランスよく備えた信頼できるパートナーが欠かせません。そのようなパートナーとしてぜひご注目いただきたいのが、『株式会社 TWOSTONE&Sons』です。
当社は「デジタル技術で企業の変革を支える」を企業理念に掲げ、BtoB分野でのDX支援に豊富な実績を誇るコンサルティング企業です。特に、銀行や証券会社など金融機関との協業に強みを持ち、セキュリティ設計・UI/UX開発・クラウド移行支援に至るまで、ワンストップでトータルサポートを提供しています。
また、公式HPにも記載している通り、「コンサルティングからシステム開発、運用保守まで一貫して対応可能な体制」が当社の強みです。さらに、金融システム開発の経験豊富なエンジニアが多数在籍しており、現場に即した高い提案力を誇ります。
もし貴社がデジタルバンキングの導入を検討しているのであれば、ぜひまずはご相談ください。

デジタルバンキングの開発は単なるアプリケーションのリリースにとどまらず、顧客視点、技術力、そして組織力の三位一体で進める必要があります。特に金融DXにおいては、セキュリティの徹底やユーザー体験の最適化が成功のカギとなります。これらを実現するためには、慎重な計画と段階的な推進が不可欠です。
また、デジタル化を進める上で、信頼できるパートナーの存在が重要です。豊富な実績を持つ支援会社と協力することで、自社の強みを最大限に活かしながらデジタルバンキングの開発を確実に進められるでしょう。
今後、金融業界の競争がさらに激化する中で、デジタルバンキングは進化を続ける不可逆的な流れです。貴社がその変革に乗り遅れないためにもまずは一歩を踏み出し、自社の未来に向けて準備を始めましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
