金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

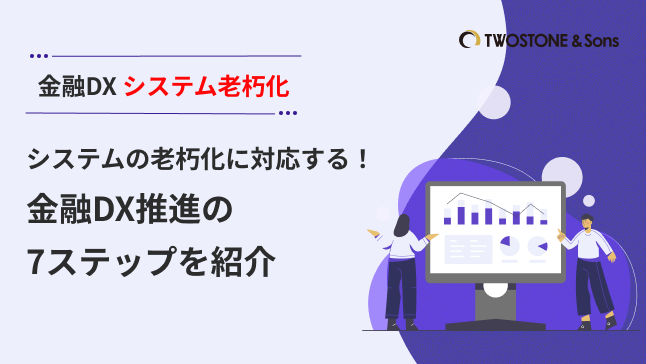
金融DXの進め方とシステム老朽化から脱却する際の注意点を専門的に解説します。老朽化リスクの回避と業務最適化に向けて、『株式会社 TWOSTONE&Sons』が金融業界のDX推進をサポートいたします。
金融機関の多くが長年使用している基幹システムに今、大きな課題がのしかかっています。それは「システムの老朽化」です。日々進化するデジタル技術に対して既存のシステムが柔軟に対応できず、業務の非効率やセキュリティ上の不安が顕在化しています。「なんとか運用できているから」と後回しにしてきたものが、ここで企業の成長を阻む障害となっているのです。
本記事では、金融業界におけるシステム老朽化の現状とそのまま放置することで生じるリスクを詳しく解説します。その上で、老朽化したシステムから脱却しDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するための7つのステップをご紹介します。
業界の動向や課題への理解を深めたい経営層の方、情報システム部門の責任者、またはDX推進を検討している方にとって、本記事は実践的なヒントとなるでしょう。

金融業界では、20年以上前に構築されたホストコンピューターやCOBOLベースの基幹システムが、いまだに多くの企業で稼働しています。これらのレガシーシステムは当時のビジネス要件には適していたものの、クラウド環境やAPI連携といった現代の技術との互換性が低く、顧客ニーズの多様化や迅速なサービス提供への対応が困難になっています。
さらに問題を深刻化させているのが、「2025年の崖」と呼ばれる構造的課題です。これは、基幹システムの老朽化と、それを担ってきた技術者の大量退職が重なることで企業の競争力や経営の持続可能性に大きな影響を及ぼすと経済産業省が警鐘を鳴らしている問題です。とりわけCOBOLに精通した技術者の定年退職が進む中、システムの構造を把握できる人材が不足しており、障害対応や仕様変更にかかるリスクが増大しています。
このような状況下では、現場が「下手に手を加えるとシステム全体が不安定になる」といった懸念を抱え、抜本的な刷新が見送られがちです。その結果、業務効率の低下だけでなく、新たなサービス開発やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の足かせにもなっています。
今後の金融機関にとって、レガシーシステムの更新やモダナイゼーションは避けて通れない課題です。2025年の崖を回避するためには、単なる延命措置ではなく、技術と組織の両面から持続的な改革に踏み切る必要があるでしょう。
参考:経済産業省
老朽化したシステムを使い続けることによる影響は多岐にわたります。ここでは、5つの観点からその深刻性を明らかにします。
老朽化したシステムの保守には、高額なコストがかかります。パーツの入手が困難であったり専門技術者が限られていたりすることで、運用コストが年々増加する傾向にあるのです。
例えばCOBOLを扱えるエンジニアが少なくなっている現状では、単なるコード修正にも高い外注費が必要になります。これによりIT予算の多くが「守りの投資」に偏ってしまい、本来注力すべきイノベーションや顧客体験向上への投資が難しくなるのです。
継続的なコスト増は最終的に企業の収益構造を圧迫する要因となり、経営に柔軟性がなくなってしまいます。
金融業界では、キャッシュレス化やスマートフォン対応など急速な業務プロセスの変化が求められています。しかし老朽化したシステムでは、こうした変化に迅速に対応するのが困難です。
業務フローを変更しようとすると全体のシステム構成に影響を及ぼすため、慎重な調整が必要になります。その結果導入に時間がかかり、競合他社に遅れを取る原因となるのです。
さらに、顧客のニーズは常に変化しています。システムが現代の業務に適応できないと、サービス満足度の低下や顧客離れにもつながりかねません。
古いシステムは最新のセキュリティパッチや暗号化技術に対応できない場合が多く、サイバー攻撃の標的になりやすい傾向があります。特にインターネットとの接続を前提としていなかった設計では、外部からの侵入に対する防御が十分ではありません。
情報漏えいや不正アクセスは企業の信頼を一気に失墜させるリスクがあり、金融業界のように個人情報や資産情報を取り扱う業種においては致命的なダメージとなり得ます。
そのため、古いシステムをそのまま使い続けること自体が大きなセキュリティリスクにつながってしまうのです。
システムの老朽化が進むと社内での対応が困難になり、外部の特定ベンダーに頼らざるを得なくなります。しかもそのシステムに精通しているベンダーが限られている場合、価格交渉力が低くなり、不利な契約条件を受け入れざるを得ないケースも少なくありません。
さらに外部ベンダーに依存することで、新たな機能追加や改善提案が遅れるリスクもあります。企業が市場環境の変化に素早く対応するためには、ベンダーロックインから脱却し柔軟なIT戦略を描くことが求められます。
ベンダーに頼らず自らの判断でシステム構築や改善を進められる体制づくりが、これからの金融機関には不可欠です。
企業の成長戦略としてDXは避けて通れない課題です。顧客接点のデジタル化、業務の自動化、AIやデータ活用による新しい価値の創出などさまざまな領域での改革が求められています。
しかし古いシステムのままでは、こうしたDX施策を進める際に技術的な制約が生じます。API連携ができない、データ構造が古く統合できない、モバイルアプリとの接続が困難など、制約が多く残ってしまうのです。
結果として競合企業が進めているDX戦略に後れを取り、顧客ニーズへの対応が鈍くなることで、企業の競争力が低下するリスクが高まるのです。
金融機関にとって、顧客との信頼関係は事業の根幹を支える要素です。しかし基幹システムの老朽化が進行すると、提供するサービスの質やスピード・利便性・安全性にまで悪影響が及びます。顧客満足度が低下すればブランドイメージの毀損や離脱のリスクが高まり、結果として企業の競争力を損なう恐れがあります。
ここでは、システム老朽化が具体的に顧客体験にどのような支障をきたすのかを見ていきます。
老朽化したシステムは処理能力が低く、トランザクションの処理やデータの連携に時間がかかる傾向があります。例えば口座開設やローン審査、送金などの基本的な業務においてもリアルタイムでの対応が難しくなり、顧客にとっての待ち時間が増加します。
このような状況が常態化するとサービス全体の品質が劣化し、「対応が遅い」「使いづらい」という印象を与えることにつながるでしょう。特にスマートフォンなどを通じて即時性を求めるユーザーにとってはストレス要因になりかねません。スピーディで快適なユーザー体験を提供するためには、システムの刷新によって処理速度を改善し、業務フロー全体を最適化する必要があります。
顧客のライフスタイルが多様化する中、金融サービスには利便性の高さが求められています。特にスマートフォンからのアクセスやアプリケーションによる取引など、モバイル対応は今や基本的な条件といえるでしょう。
しかし、レガシーシステムは最新のUI/UX設計やAPI連携、クラウドサービスとの統合が難しく、新しいデジタルチャネルの実装に制限がかかります。その結果モバイル上でのサービス展開が不十分となり、若年層やITリテラシーの高い顧客層に対して魅力的な選択肢を提示できなくなってしまいます。
顧客の期待値に応える柔軟性を確保するには、システム全体をモダナイズし、変化に対応できる基盤を整備しましょう。
老朽化が進んだシステムは、想定外の負荷や障害に対して脆弱になります。過去にも日本国内の金融機関で、システムトラブルによりATMが利用できなくなったりインターネットバンキングのログインが不可能になったりするケースが報告されています。
こうした障害は顧客の日常生活に直接影響を及ぼすだけでなく、ビジネスユーザーにとっては致命的な信用損失にもつながりかねません。また、復旧までの対応が遅れれば遅れるほど顧客からの不満や問い合わせが殺到し、カスタマーサポート業務にも大きな負荷がかかります。
システムの信頼性を高めるには、稼働率の高いインフラを導入して障害時の迅速な切り替えが可能なアーキテクチャを整備することが重要です。
金融サービスでは、個人情報や取引履歴などの機密性が高いデータを扱います。レガシーシステムでは、セキュリティパッチの適用が遅れたり最新の暗号化技術に対応できなかったりする場合があり、サイバー攻撃のリスクが高まるでしょう。
もし情報漏えいが発生すれば顧客の信用を一瞬で失うだけでなく、行政機関からの指導や法的責任を問われる可能性もあります。さらにSNSなどを通じて瞬時に悪評が拡散し、ブランドイメージに深刻な打撃を与えることにもなりかねません。
顧客が安心してサービスを利用できるようにするためには、堅牢なセキュリティ対策と継続的なアップデートが不可欠です。そのためにも、セキュリティ要件を最新水準に合わせられる柔軟なシステム基盤の整備が求められます。
サービスの質が低下し顧客のニーズに応えられない状況が続けば、顧客は他の金融機関への乗り換えを検討し始めます。特に近年では、スマホ銀行やフィンテック企業が革新的なサービスを次々と打ち出しており、これまでのような保守的な体制では顧客を引き留めるのが難しくなってきています。
一度離れた顧客を取り戻すには、多大なコストと時間がかかるでしょう。そのため、既存顧客の満足度を維持しながら新規顧客を獲得していくには、提供するサービスの質を常に改善していく姿勢が必要です。これは単なるシステム更新ではなく、全社的な顧客視点に立ったDX推進が求められる局面だといえるでしょう。
顧客は「今、便利か」「安心して使えるか」をシビアに見ています。裏側のシステムがそれに応えられなければ、選ばれる理由は次第に失われていきます。
金融業界が直面しているシステム老朽化の問題に対し、有効な打開策として注目されているのが「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。DXの推進によって柔軟性と拡張性を兼ね備えたIT基盤を構築し、業務効率や顧客サービスの向上を図ることが可能になります。
ここでは、具体的にどのような側面で金融DXがシステム改革に寄与しているのかを解説します。
まず注目すべき点は、クラウド技術の活用です。従来のオンプレミス(社内設置型)システムではハードウェアの物理的な制限や保守・運用の負担が大きく、システムの柔軟性に欠けていました。これに対してクラウドを導入すると、リソースのスケーラビリティが高まるため業務の拡張や新機能の追加にも迅速に対応できます。
さらに、災害対策やBCP(事業継続計画)にも有効です。クラウド環境は分散構成されているため、特定の拠点に障害が発生してもサービス提供を継続しやすくなります。加えて、ベンダーが提供するセキュリティ更新やインフラ保守により、常に最新状態を維持できる点もメリットです。
このようにクラウド化は単なるコスト削減にとどまらず、システム基盤全体の俊敏性と安全性を高めて金融DXの推進に不可欠な土台を形成します。
次に重要なのは、レガシーシステムからの脱却です。レガシーシステムとは古くから使われ続けてきたシステムのことで、更新が困難であり、他の新しい技術との連携が難しいという問題があります。こうしたレガシー環境では業務フローも手作業中心になりがちで、人的ミスや処理の遅延が生じやすくなるのです。
これに対して、最新のクラウド型業務アプリケーションやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により、事務処理やデータ登録などの定型業務を自動化できます。特に融資審査や口座開設といった手続きは、AIやOCR(文字認識技術)と連携することでスピーディかつ正確な処理が可能になります。
業務の自動化は、人手不足への対応にも有効です。限られた人材で高品質なサービスを提供するには、単純作業をシステムに任せ、担当者はより付加価値の高い業務に専念できるような業務設計が理想です。
さらに、DXの要となるのが「データの一元管理」です。金融機関では顧客情報や取引履歴、契約内容など多種多様なデータを扱います。しかし部門ごとにシステムが分断されていると、情報の取得や共有に時間がかかりスムーズな顧客対応が難しくなるのです。
この課題を解決するためには、CRM(顧客管理システム)やDWH(データウェアハウス)などを活用してデータを統合管理する仕組みを整える必要があります。情報が一元化されることで顧客の属性やニーズに応じた提案やフォローアップが可能になり、満足度向上につながるでしょう。
またリアルタイムにデータを把握できる環境は、経営判断のスピードも高めます。市場の変化や顧客の動向を迅速に反映させられ、競争力のある経営戦略を打ち出す一助となります。

実際に、金融DXを推進してシステムの刷新や業務改革に成功した国内の金融機関は少なくありません。それぞれが自社の課題に応じた取り組みを行い、デジタル技術を活用して成果を上げています。
ここでは6つの具体的な事例を紹介します。
三井住友フィナンシャルグループでは、AIを用いた業務プロセスの改革に力を入れています。特に与信判断や問い合わせ対応といった分野でAIを活用し、正確性とスピードの両立を図っているのです。
また行内に「AI分室」などの専門チームを設け、行員とデータサイエンティストが協働して実用的なAIモデルを構築しています。こうした取り組みにより、業務負担の軽減とともに、顧客対応の質も向上しているのです。
地方銀行である伊予銀行は、店頭業務の効率化を目的にタブレット端末を導入しました。これによって従来紙ベースで行っていた各種手続きをペーパーレス化し、記入ミスや処理の遅延を防ぐ仕組みを整えました。
さらにタブレット上で説明資料や契約内容を視覚的に確認できるようになり、顧客の理解度も高まりました。特に高齢者やデジタルに不慣れな利用者にも優しい設計となっており、地域密着型サービスの一環として高評価を得ています。
参考:株式会社伊予銀行
住信SBIネット銀行は、独自のBaaS(Banking as a Service)プラットフォーム「NEOBANK」を展開しています。これは非金融企業にも銀行機能を提供する仕組みであり、従来の銀行の枠を超えた金融サービスの提供を可能にしています。
この仕組みにより、例えばECサイトやアプリ事業者が、自社ブランドで銀行サービスを顧客に提供できるようになりました。新たな収益モデルの創出と顧客接点の拡大に貢献している事例です。
ゆうちょ銀行では、デジタル戦略の一環として「データドリブン経営」への転換を進めています。全社的なデータ基盤を構築し、部門横断的に情報を活用できる環境を整備しているのです。
これにより、商品開発や業務改善の意思決定において勘や経験に頼るのではなく、客観的なデータを基に判断する体制が構築されつつあります。データ活用は、顧客満足度を向上させるための重要な資源と認識されています。
参考:株式会社ゆうちょ銀行
ふくおかフィナンシャルグループが設立した「みんなの銀行」は、完全非対面・スマホ完結型のデジタルバンクとして注目を集めています。アプリの設計は若年層にも直感的に使えるインターフェースとなっており、口座開設から振込、貯金管理までスマートフォン一台で完結します。
また、API連携を活用することで外部サービスとの連携も進め、顧客の金融体験全体をシームレスにしました。新規層の獲得と運用コストの削減に成功した好例です。
三菱UFJフィナンシャル・グループでは、業務全体のペーパーレス化を強力に進めています。社内文書の電子化はもちろん、顧客との契約や手続きに関しても電子サインやオンラインでのやり取りを積極的に導入しています。
この取り組みによって業務の迅速化とコスト削減を同時に実現しており、従業員の働き方改革にもつなげました。こうした取り組みは、環境配慮の観点からもサステナブルな取り組みとして評価されています。
金融業界がDX(デジタルトランスフォーメーション)を通じてシステムの近代化を図るには、明確なステップを踏む必要があります。単に最新のテクノロジーを導入するだけでは不十分であり、組織全体のビジョンと文化の変革、継続的な改善体制が不可欠です。
ここでは、金融機関が実践的に取り組むべき7つのステップを紹介します。
DXを成功させる第一歩は、現状の業務システムが抱える問題点を正確に把握することです。多くの金融機関では長年使われてきたレガシーシステムが業務効率を阻害し、新しいサービスの開発や導入を妨げています。
例えばCOBOLなどの旧式プログラムで構築された基幹システムは、保守人材の確保が難しい上、処理の柔軟性に欠ける点が大きな障壁です。また、各業務システムが縦割りで構成されている場合、情報の一元化が進まず、顧客対応にも時間がかかる傾向があります。こうした課題が業務全体に与える影響を、定量・定性的な指標で整理すると、改革の必要性を組織内で共有しやすくなるでしょう。
システム改革を進めるには、単なる技術導入にとどまらない「未来の姿」を描く必要があります。DX推進のビジョンは、企業の経営戦略と整合していることが重要です。「24時間365日アクセス可能なスマートバンキングの実現」や「データ活用による最適な顧客体験の提供」など、目指す姿を明確に設定しましょう。
加えて、その実現度を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設けます。例としては、「オンライン手続き完結率の向上」「新規口座開設に要する時間の短縮」「紙文書使用率の削減」などがあります。KPIは数値目標として定義し、定期的にモニタリングする仕組みを整備しましょう。
DXの本質は、テクノロジーを活用して業務プロセスを再構築し、付加価値を高める点にあります。そのためには、データを軸にした業務フローへの転換が必要です。これまで紙ベースや手入力に依存していた情報処理をリアルタイムのデジタルデータで代替し、業務の自動化・省力化を図りましょう。
具体的には、顧客の行動履歴や属性データを活用して最適な商品提案やリスク評価を自動化するアルゴリズムを導入する手法があります。また、事務処理においてもRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やOCR(光学文字認識)を組み合わせることで、人的エラーを削減し、業務の質を高められるでしょう。
新たな業務フローを支えるIT基盤として、クラウドコンピューティングとAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)の活用が欠かせません。クラウドを活用することで拡張性があり、かつ柔軟なシステム構成が可能になり、新規サービスの展開スピードが向上するでしょう。
またAPIを活用すると、外部のフィンテックサービスやパートナー企業とシステム連携を容易にし、オープンバンキングの実現にもつながります。例えば、資産運用アプリとのデータ連携やキャッシュレス決済との統合などが挙げられます。セキュリティとガバナンスを両立させた設計が求められるため、クラウド基盤の構築には慎重な設計と段階的な導入を行いましょう。
全面的なDXは大規模投資を伴うため、失敗のリスクを最小限に抑える工夫が必要です。その手法として効果的なのが、小規模なPoC(Proof of Concept:概念実証)を通じた段階的導入です。PoCでは、特定業務や部門に限定して新システムを試験導入し、課題と成果を検証します。
例えば、ある支店でのみペーパーレス手続きを導入し、顧客の反応や事務作業の効率性を評価するといった形です。この視点で得られたPoCの結果を踏まえて必要な改善を行い、本格導入へと展開していくのです。このように段階的に導入を進めることで、現場の混乱を避けつつ確実なシステム改革ができるでしょう。
技術だけでなく、組織の意識や働き方の改善もDX成功のカギです。特に、長年同じ業務に従事してきた従業員にとってシステムや業務プロセスの変更がストレスとなるため、丁寧な社内教育が求められます。
研修プログラムでは新システムの操作方法だけでなく、なぜDXを推進するのかという背景や目的をしっかり伝えることが重要です。現場従業員の納得感と理解を得ると、スムーズに移行できるでしょう。変化に柔軟な組織文化を育てるためには、経営層が率先してDXに取り組む姿勢を示すことも合わせて求められます。
DXは一度実施すれば終わりではありません。変化の激しい金融環境に対応し続けるには、継続的な改善体制の構築が必要です。そのために定期的なKPIの評価とフィードバックループを組み込み、実際の運用データを基に業務プロセスの見直しを図りましょう。
また、顧客満足度調査や現場の声を収集する仕組みも整え、実際の利用者視点からの改善を積極的に行う姿勢が重要です。PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを組織全体で運用することで、柔軟性と持続可能性を備えたDXの実現ができるでしょう。
金融DXの推進には多くのメリットがある一方で、計画や実行にあたって注意すべきポイントも多数存在します。これらのリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることが、成功へのカギを握ります。
DXは経営層だけで完結するものではありません。むしろ現場で日々業務を遂行する従業員の協力があってこそ、システム改革は効果を発揮します。
例えば新しい業務フローを導入した場合、現場がその意図やメリットを理解していないと、従来の方法に戻るなどの「リバウンド」が発生しやすくなります。このような事態を避けるためには、事前に関係者との対話を重ねることが欠かせません。説明会やワークショップを通じて現場の声を吸い上げ、段階的に理解と納得を醸成する姿勢が求められます。
DXにおいては、開発費用やライセンス料・保守費・教育コストなど多岐にわたる投資が発生します。予算を超える事態を防ぐには、初期段階で中長期的な費用対効果の試算を行いましょう。
特にクラウドサービスの利用や外部ベンダーとの契約においては、月額課金制であるがゆえに使い方次第でコストが変動します。導入前に必要な機能を見極め、利用範囲を明確にすることで、無駄なコストの発生を抑えられるでしょう。
また開発段階では、想定外の仕様変更や連携障害により追加コストが生じやすくなります。これを回避するためには、要件定義フェーズにおいて徹底的なヒアリングとシナリオ設計を行い、ブレのない方針を確立しておくことが求められます。
クラウドの利便性は高い一方で、セキュリティ対策が甘ければ重大なインシデントにつながるリスクも抱えています。特に金融業界では顧客の機密情報を多数扱うため、情報漏えいや不正アクセスへの備えは必須です。
移行に際しては、データの暗号化・アクセス制御・監査ログの取得・二要素認証の導入など多層的なセキュリティ対策を講じる必要があります。また、クラウドサービスプロバイダのセキュリティ基準も事前に精査し、自社のガバナンスに見合った体制であるかを確認しておきましょう。
あわせてBCP(事業継続計画)においても、災害や障害発生時の復旧手順を定めておくと安心です。
特定のベンダーやプラットフォームに依存しすぎると、将来的な技術革新への対応やコスト最適化が難しくなります。これが「ベンダーロックイン」と呼ばれる課題です。
例えば特定ベンダーのAPIを前提としたシステム設計を行うと、別のベンダーへ移行する際に再構築が必要になるケースもあります。その結果、コストや工数が予想以上にかかり、ビジネスの柔軟性が損なわれてしまうのです。
このようなリスクを回避するためには、オープンな標準規格やマルチクラウド戦略を採用しましょう。また、ソースコードやデータ構造の保守性を重視し、自社で一定の技術的自立性を確保することも重要です。
金融DXは全社的な取り組みであり、一部門だけの改革では効果が限定的になります。しかし組織の縦割り構造が強い企業では、部門間で目標や方針が一致せず連携が取れないという課題が生じやすくなります。
例えば、営業部門が新しいCRMツールを導入してもシステム部門とデータ連携が取れていなければ、十分な活用は期待できません。こうしたミスマッチを防ぐためには、経営層主導で全社横断的なガバナンス体制を構築して各部門が一丸となってDXを推進する風土を醸成することが求められます。
さらに、部門ごとのKPIと全社KPIを連動させることで各部門の取り組みが全体目標の達成にどう貢献するかが可視化され、協力体制を強化しやすくなります。
ここまで述べてきたように、金融DXを成功させるには技術的知見だけでなく、業界特有の業務理解や組織文化への対応力が問われます。さらに、複雑なシステム構成や多様なステークホルダーとの調整を乗り越える必要があるのです。
そのような中で、信頼できるパートナーの存在が改革の成否を左右します。『株式会社 TWOSTONE&Sons』は金融業界に特化したDX支援の実績を多数有しており、現場に寄り添ったアプローチと先進技術の導入支援で高い評価を得ている会社です。
単なるシステム導入にとどまらず、ビジョン策定・業務プロセス設計・セキュリティ対策、そして組織全体のDXマインド醸成まで一貫したサポートを提供しております。
本気でシステム改革に取り組みたいとお考えのご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

金融業界を取り巻く環境は、デジタル技術の進化とともに急速に変化しています。こうした状況下で老朽化したシステムに固執し続けることは、業務効率の低下だけでなく法規制や顧客ニーズへの対応力の欠如という深刻なリスクを招きます。
今こそシステム改革に取り組み、金融DXを戦略的に進めるべきタイミングです。ステップを踏んだ着実な導入・部門横断の連携・リスクの把握と回避、そして信頼できるパートナーとの協業が成功を確実なものにします。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』ではこうした一連のプロセスを、貴社の立場に立って支援させていただきます。現状を変えたい、未来の成長に備えたいとお考えであれば、ぜひ前向きにご検討ください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
