金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

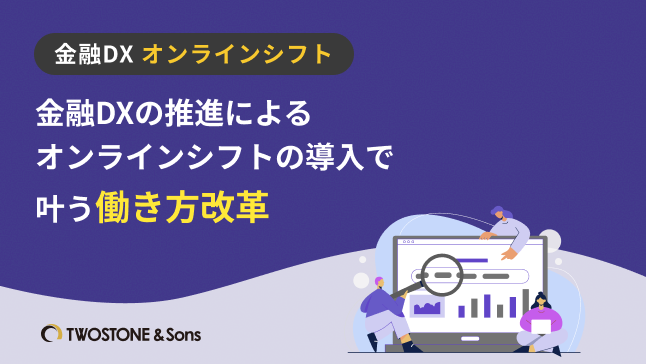
金融DXを推進する上でオンラインシフトは不可欠です。本記事では、導入の具体的ステップと注意点を丁寧に解説し、『株式会社 TWOSTONE&Sons』による支援体制もご紹介します。
「出社していないと仕事をしていないと思われる」「紙の書類がないと不安」——
かつての金融業界では、そんな声が当たり前でした。しかし、今やそれは過去の話です。働き方改革が進む中で金融業界にも変革の波が押し寄せているのです。特に注目されているのが「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進によるオンラインシフトです。
今や非対面での顧客対応が求められるようになり、業務の効率化や生産性の向上も重要なテーマとなっています。テレワークやクラウドツールの導入など、企業の在り方自体が問われる時代に突入しました。
この記事では、金融DXとは何か、そしてオンラインシフトがなぜ今求められているのかを解説しながら、働き方改革を実現するための具体的なヒントを紹介します。
この内容を理解することで、金融機関がどのようにデジタルを活用して競争力を高めているのか、また自社がどのように変革を進めていくべきかが見えてくるでしょう。

金融DXとは、金融業界における業務やサービスのデジタル化を通じてビジネスモデルそのものを変革し、競争力を高める取り組みです。単なるIT化やペーパーレス化にとどまらず、顧客体験の向上や意思決定のスピードアップ、人材の有効活用といった本質的な改革を目指しています。
具体的には、オンラインバンキングの拡充、AIによるローン審査の自動化、チャットボットを用いたカスタマーサポートなどが挙げられます。これらの技術を活用することで、業務効率の向上やコスト削減、さらにはサービス品質の改善も期待できます。
また、金融DXは内部業務の効率化にとどまらず、顧客との接点の質を高めるうえでも重要とされています。紙の書類や対面に依存した従来の仕組みでは、顧客のニーズに迅速かつ柔軟に対応するのが難しくなりつつあり、そうした背景からも、DXによるオンラインシフトの必要性が高まっているといえます。
急速に変化する社会の中で、金融業界も例外ではないといえます。非接触・非対面が当たり前となり、従来の働き方やサービス提供の方法についても見直しが進んでいます。そうした動きの背景には、さまざまな要因があると考えられます。
コロナ禍を契機に、顧客は対面での手続きや相談を避ける傾向が強まりました。特に高齢層以外のユーザーにとっては、スマートフォンやPCから手軽にアクセスできるサービスが求められています。金融機関においても、窓口業務や書類提出といった対面でのプロセスを見直し、ウェブ会議や電子契約などを導入する必要性が高まりました。
この変化に迅速に対応できた金融機関は、顧客からの信頼を維持し、競争優位を確保しています。一方で変革に乗り遅れた組織は、顧客満足度の低下や人材流出といった課題に直面しています。
かつては「金融=対面」というイメージが強くありましたが、今ではネットバンキングやモバイルアプリの普及によりオンラインで完結する金融サービスが主流になりつつあります。住宅ローンの事前審査や資産運用の相談などもスマートフォン一つで行えるようになりました。
このような動きは大手金融機関に限らず、地方銀行や信用金庫にも広がっています。顧客からすれば、「オンラインで手続きできるかどうか」は金融機関を選ぶ重要な判断材料の1つです。もはやオンライン対応は“あって当たり前”の基準になりつつあるのです。
行内での業務に目を向けても、紙の書類を回覧する、押印するためだけに出社するといった従来の習慣は生産性の低下を招いています。特にテレワークが推進される中で、業務をオンラインで完結させる工夫が求められているのです。
電子会議・クラウド上での書類共有・セキュリティを担保したビデオ会議など、業務の非接触化を支えるツールは多数存在します。こうした環境整備によって職員の移動や待機時間が減少し、業務効率が向上するだけでなく働き方の柔軟性も高まるでしょう。
非接触での業務が実現できれば、感染症リスクの軽減だけでなく育児や介護との両立を希望する職員にとっても魅力的な職場になります。これは、人材確保や定着率の向上にも寄与します。
今や金融業界も、他業種と同じく「顧客体験」が重視される時代です。実際にオンラインショッピングでは、ワンクリックで購入から決済まで完了するスムーズな体験が提供されています。それに対して、金融サービスが煩雑で分かりにくければ、顧客は離れてしまうでしょう。
特にフィンテック企業や異業種からの参入が増える中で、金融機関にも顧客目線でのサービス設計が求められるようになっています。使いやすさ・スピード・利便性・セキュリティといった観点から、ユーザーに選ばれる仕組みをどう構築していくかが課題となってきています。
このように他業種と比較して競争力を保つためにも、オンラインシフトの実現は避けて通れないテーマとなっています。時代に適応したサービス提供と社内業務のスマート化を同時に進めることが、真の意味での金融DXといえるでしょう。
金融業界がデジタル化を進める中で、オンラインシフトの導入は単なる時流ではなく、戦略的な選択と捉えられるようになっています。業務の効率化や顧客ニーズの変化に対応するうえでも、オンラインサービスの展開は重要な要素といえるでしょう。
ここでは、金融業界がオンラインシフトを進めることで得られる具体的な5つのメリットを紹介します。
オンラインシフトによって、場所や時間を問わず金融サービスを利用できる環境が整います。これは顧客にとって大きな利点であり、従来の窓口対応に比べて圧倒的に利便性が高くなります。
例えば、スマートフォンを使って即時に口座残高を確認したり、ローンのシミュレーションを行ったりする行為は、今や日常的になりました。来店不要で手続きが完結する仕組みは、多忙なビジネスパーソンや地方在住者にとって大きな価値があります。こうした利便性の提供は、顧客のロイヤルティ向上にも直結するのです。
さらにオンライン上での顧客対応においては、チャットボットやAIアシスタントを活用することで、人的リソースを割かずに一定の質を保ったサポートが可能です。顧客接点が増えるとよりきめ細かなフォローアップも行いやすくなり、サービス満足度の向上が期待できるのです。
オンライン化は、物理的な拠点にかかるコストを削減する手段としても有効です。支店の維持には人件費・光熱費・設備費など多くの固定費が発生します。これらの経費の見直しは、経営効率の観点から重要です。
デジタルチャネルへの移行が進めば対面対応を必要とする業務は限定され、人的資源を戦略的に配置し直す余地が生まれます。結果として、限られたリソースを収益性の高い業務や新規事業開発に振り分けられるのです。
また、支店数を減らしつつもオンライン上で全国の顧客に均一なサービスを提供できるため、地方や都市部といった立地の違いによるサービス格差をなくすことにもつながるでしょう。
オンラインサービスの大きな強みは、営業時間に縛られないことです。24時間365日稼働するデジタルチャネルを整備すると、顧客はいつでも好きなタイミングでサービスを利用できます。
これは単なる利便性の提供にとどまらず、業務全体の効率化にもつながるでしょう。例えば申請や問い合わせの受付を自動化すれば、担当者はデータを基に後日対応するだけで済みます。繁忙期に対応が集中して業務が停滞するといった状況も回避できるのです。
さらに業務プロセスを見直し、デジタルツールと連携させることで、繰り返し作業や入力ミスのリスクを低減できるのです。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用するケースでは、顧客からの申請データを自動的に処理して担当部門へ引き渡すフローの構築が進められています。
オンラインチャネルを介してやり取りされる情報は、すべてデジタルデータとして蓄積できます。これにより、従来のように顧客の行動履歴やニーズを感覚的に把握するのではなく、実際の行動データを基に正確な分析が可能になるのです。
例えば、サイト内の遷移履歴や問い合わせ内容、取引傾向などを分析することで、個々の顧客がどのような関心を持っているかを特定できます。それを基に、最適なタイミングで適切な商品提案を行う「パーソナライズド・マーケティング」が実現できるのです。
加えて、データの利活用が進むことで、金融商品の開発にも好影響を与えるでしょう。市場ニーズの変化を迅速に察知し柔軟なサービス設計につなげると、他行との差別化を図れるのです。
働き方改革の一環としても、オンラインシフトは重要な役割を担っています。特に、子育てや介護などの事情を抱える従業員が安心して働き続けられる環境を整えるには、場所や時間に縛られない業務体制の整備が不可欠です。
リモートワークやフレックスタイム制の導入により、従業員はワークライフバランスを保ちながら生産性の高い働き方が可能になります。これは離職率の低下に直結するほか、優秀な人材の流出を防ぐ効果も期待できるでしょう。
また業務のオンライン化によってマニュアル化・自動化が進むと、属人化していた作業の負担が軽減されます。これによりチーム内での業務分担がスムーズになり、誰かが休んでも業務が滞るリスクを最小限に抑えられるでしょう。
このような柔軟性と効率性を備えた労働環境は、従業員満足度の向上にもつながります。働きやすい職場環境を実現することは長期的な組織力の強化につながり、結果として顧客サービスの質の向上にもつながるのです。
デジタル技術の進化とともに、保険業界においてもオンラインシフトの重要性が急速に高まっています。その結果、顧客接点から業務処理、営業活動に至るまでさまざまな業務で非対面・非接触型への移行が進められているのです。
ここでは、保険会社が実際に取り組むべき代表的な3つのオンライン対応業務を紹介します。
顧客との接点をデジタルに置き換えることは、オンラインシフトの中でも早期に求められる分野です。特に、コールセンターに依存していた問い合わせ対応をオンライン窓口に切り替えることで、時間や場所に制限されず対応可能になります。
また、チャットボットの導入によりFAQの自動応答や簡単な手続きのガイドを即時に提供でき、ユーザーの利便性を向上させると同時に業務負担も軽減できます。自動化による初期対応と必要に応じたオペレーターへの接続を組み合わせることで、顧客満足度を保ちつつ効率を高める体制が整うのです。
契約手続きや請求処理、書類の確認作業といったバックオフィス業務は、日々膨大なリソースを要します。これらの定型業務にRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIを活用することで人的作業を削減し、ヒューマンエラーの防止にもつながります。
例えば保険金支払いの審査プロセスにAIを導入すれば、過去のデータに基づいた迅速かつ適正な判断が可能になるでしょう。こうした無人化の取り組みは業務スピードと品質の向上を両立させ、全体の生産性を大きく押し上げる効果が期待されます。
従来の対面営業から、デジタルツールを活用したリモート営業への移行も急速に進んでいます。顧客データをもとにニーズを可視化し、パーソナライズされた提案を行う手法が注目されているのです。特にCRM(顧客管理システム)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを用いれば、過去の取引履歴や行動パターンから関心度の高い商品を絞り込み、タイミングを逃さず最適なアプローチが可能になります。
さらにオンライン商談ツールを併用することで、営業活動の機会損失を防ぎながらより多くの顧客に効率よく接触できるようになるでしょう。

金融機関がオンラインシフトを成功させるためには、単に業務をデジタル化するだけでは不十分です。顧客体験を向上させつつ業務効率とセキュリティを両立させるには、戦略的かつ段階的なアプローチが求められます。
ここでは、金融DX(デジタルトランスフォーメーション)を円滑に推進するための7つのステップを順を追って解説します。
最初のステップは、現在の業務と顧客ニーズを正確に把握することから始まります。これはDXの方向性を決定づける重要なプロセスです。
例えば、どのサービスが最も利用されているのか、顧客はどのチャネルに不便を感じているのか、業務のどこに非効率があるのかといった点を定量・定性的に調査する必要があります。顧客アンケートや支店の対応履歴、従業員からのヒアリングなどを通じて多角的に情報を収集しましょう。
このようにして得た現状分析に基づき、オンライン化によって解決したい課題や改善すべきポイントを明確にします。ここで分析を曖昧に終わらせてしまうとその後のステップに大きな影響が出てしまうため、時間をかけて丁寧に取り組むべきフェーズです。
次に取り組むべきは、どの業務をオンライン化するかの選定です。すべての業務を一度にデジタル化しようとするのはリスクが高く、混乱を招く恐れがあります。
優先度を考慮しながら、まずは高頻度かつルーティン性の高い業務から対象にするとよいでしょう。例えば、口座開設や住所変更、ローン申請といった手続きはオンライン化によって顧客の利便性が向上します。また、社内の経費申請や承認フローなども自動化による効果が見込める業務です。
こうして具体的なオンライン化の対象を明確にすることで、プロジェクトのスコープを絞り、社内のリソース配分やスケジュール設計がしやすくなります。
業務をオンラインで提供する上で欠かせないのが、堅牢なIT基盤の構築です。金融業界は個人情報や資産を扱う性質上、セキュリティ対策は最重要事項として位置づける必要があります。
例えばクラウド環境の選定においては、金融機関向けに特化したセキュリティレベルを持つサービスを採用するのが望ましいでしょう。また、サイバー攻撃や不正アクセスに備えて、WAF(Web Application Firewall)や多要素認証などの導入も検討すべきです。
さらにITインフラは構築して終わりではなく、運用・保守まで一貫して管理する体制が求められます。万が一のシステム障害やデータ漏えいに備えたBCP(事業継続計画)もあわせて整備しておく必要があります。
参考:金融庁
次のステップでは、実際に利用されるオンラインサービスのUI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザー体験)を設計していきます。単にデジタルで機能が使えるだけではなく、誰もが直感的に操作できる「使いやすさ」が求められます。
例えば、高齢者でも迷わずに操作できるシンプルな画面構成、誤操作を防ぐボタン配置、必要な情報にすぐアクセスできるナビゲーション設計など、細部に配慮した設計が必要になるでしょう。
また、顧客が途中で離脱しやすいポイントを可視化するために、ヒートマップツールやA/Bテストを活用する方法も有効です。これにより、実際の使用状況を基に継続的なUI改善が可能になります。
オンライン化によって、社内業務の流れも変わります。従来の紙ベースの手続きや対面での確認作業が不要になる反面、新たな業務が発生する場合もあります。
このタイミングで、業務プロセスの見直しと役割分担の再定義を行いましょう。具体的には、顧客対応部門とシステム管理部門の連携体制を整え、スムーズな情報共有を可能にすることが必要です。
また、業務フローはできるだけ標準化・自動化を目指すことで属人性を排除し、ミスの少ない運用が可能になります。こうした再設計により、社内の働き方改革にもつながっていくのです。
新しいシステムや業務フローを導入しただけでは、オンラインシフトは成功しません。それを実際に運用・活用する人たちの理解と納得が必要です。
従業員に対しては、システムの操作方法だけでなくなぜオンライン化が必要なのかという背景や意義も含めた研修を行うことで、主体的な関与を促しましょう。また、マニュアルやFAQの整備により実務で迷う場面を減らす工夫も有効です。
同時に、顧客にも新しいサービスの内容や利用方法を丁寧に伝える必要があります。公式サイトやアプリ上でのガイダンス、動画による操作説明、店頭での案内など複数のタッチポイントを通じて周知活動を展開しましょう。
最後のステップとして、導入後の効果検証と継続的な改善が欠かせません。オンラインサービスは導入したら終わりではなく、むしろその後の「運用フェーズ」で差が出ます。
定期的にKPI(重要業績評価指標)を設定し、利用者数・手続き完了率・顧客満足度・問い合わせ件数などをモニタリングします。こうしたデータを基に課題のある部分を特定し、改善アクションを立案・実行する流れを確立させることが重要です。
また改善の過程では、現場の声や顧客のフィードバックも積極的に取り入れましょう。数値データだけでは捉えきれないニーズが浮かび上がる可能性もあります。これらを繰り返し反映させることでサービスの完成度が徐々に高まり、オンラインシフトの本来の効果が出てくるでしょう。
金融業界におけるオンラインシフトは利便性と効率性を高める一方で、新たな課題も生じます。特に多様な顧客層や業務の特性を考慮すると、オンライン化の推進には細心の注意が求められます。
ここでは、導入時に注意すべき主なポイントについて解説します。
オンラインサービスが普及する中で、高齢者やITに不慣れな顧客にとっては操作の難しさがハードルとなります。この層を切り捨てることなく全体の利便性を高めるには、具体的なサポート体制が不可欠です。
まず、ユーザーガイドや動画マニュアルを用意すると、直感的に操作できるように支援できます。また、実店舗やコールセンターでのサポート窓口を継続することも有効です。さらに、必要に応じて訪問サポートやデジタル機器の使い方講座を開催するなど包括的な支援を検討しましょう。
このように、オンライン化に伴う「取り残される不安」を払拭すると、すべての顧客に安心してサービスを利用してもらえる環境を整備できるでしょう。
金融機関は高度な個人情報を取り扱うため、オンライン化によってセキュリティリスクが高まる点も見逃せません。顧客情報や取引データの保護は最優先課題であり、技術的・運用的な両面から万全の対策を講じる必要があります。
技術面では、多要素認証や暗号化通信、ファイアウォールの導入が基本となります。さらに、不正アクセスや異常検知に対応できるリアルタイム監視システムを構築することで、リスクの早期発見と対応ができるのです。
一方運用面では、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めることが重要です。定期的なセキュリティ研修やシミュレーション演習を実施し、社内体制を強化しましょう。ヒューマンエラーを防ぐルール整備も欠かせません。
セキュリティ対策を怠れば、信頼の失墜や重大な損害につながります。だからこそ、徹底したリスク管理を行う姿勢が求められます。
デジタル化の流れが加速する一方で、すべてをオンライン化すればよいわけではありません。顧客の中には、対面による相談やアドバイスを重視する層も存在します。こうしたニーズに応えるには、オンラインとオフラインのサービスを適切に組み合わせるハイブリッド型の対応が有効です。
例えば、事前予約制による来店相談やオンラインでの面談予約、対面での契約締結など顧客の意向に応じて柔軟な選択肢を提供することが重要です。また、対面の機会を減らすのではなく、むしろ高付加価値の体験として位置づけ、丁寧な接客を通じて信頼関係を深めることが期待されているのです。
オンライン化を進めるからこそ、リアルな接点の価値も再評価されるべきです。顧客視点に立ったバランス感覚を持ち、全体最適を図ることが成功のカギとなります。
オンラインシフトや金融DXの推進には、技術面だけでなく、組織体制や顧客理解も含めた総合的な戦略が必要です。『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、業界特有の課題に精通した専門家が在籍し、企画から導入、運用改善に至るまで一貫した支援を行っています。
当社は、これまで多くの金融機関と連携し、業務改革や顧客満足度向上に貢献してきました。UI/UX設計やクラウド基盤の整備、業務プロセスの再設計などオンライン化の成功に欠かせない各ステップを丁寧に伴走しながらサポートいたします。
自社だけでは乗り越えづらい課題があれば、ぜひ一度ご相談ください。状況に応じた最適なソリューションをご提案いたします。

金融業界におけるオンラインシフトは、もはや選択ではなく必須の対応です。顧客の利便性を高めるだけでなく、業務効率や競争力の強化にもつながります。しかし、その推進には、綿密な戦略と現場に根差した取り組みが求められます。
顧客ニーズの分析やUI/UXの最適化、セキュリティ対策、従業員教育、そして顧客へのフォローアップまですべてのプロセスを一つひとつ丁寧に設計することが成功への近道です。また、デジタルとリアルの両立を図ると、多様化する顧客ニーズにも柔軟に対応できるでしょう。
このような時代の変化にいち早く対応し先手を打って金融DXを進める企業こそが、未来の信頼と成長を手にすることができるでしょう。まずは自社の現状を見直し、できる部分から改善に着手してみませんか。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
