金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

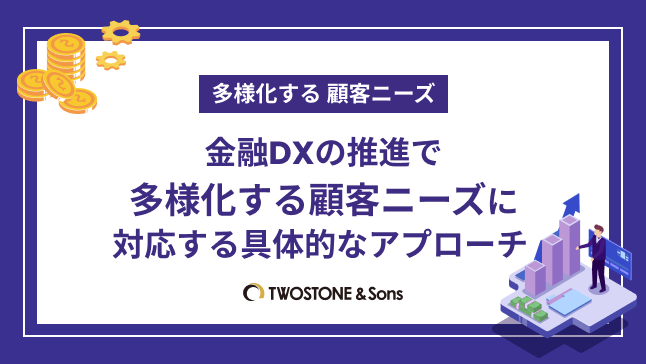
金融DXを成功させるには、顧客ニーズを正確に捉え、段階的な対応と丁寧な運用が重要です。本記事では、具体的な推進ステップや注意点を解説し、『株式会社 TWOSTONE&Sons』の支援内容もご紹介しております。
「ネットで簡単に口座開設ができればいいのに」「もっと自分に合った金融サービスがあれば助かるのに」――
このような声が、今の金融業界における顧客のリアルな期待です。この声に対して、従来の対面中心のサービスでは現代の多様なライフスタイルや価値観に十分対応しきれない場面も増えてきました。
そこで注目されているのが「金融DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。デジタル技術を活用して顧客一人ひとりに寄り添ったサービスを実現することは、顧客満足度の向上だけでなく業務効率の改善やコスト削減にもつながります。
本記事では、金融DXとは何かを整理した上で現代の顧客が本当に求めているサービスや環境について、具体的な要素を5つの観点から紹介します。これを読むことで、金融機関が今後どのように変革を進めていくべきかが明確になるでしょう。

金融DXとは、金融業界においてデジタル技術を活用し、業務プロセスやサービス提供の在り方を根本から変革する取り組みを指します。単なるIT化やシステム導入とは異なり、DXは企業文化や組織構造、サービス戦略そのものにまで影響を及ぼす広範な概念です。
例えば、従来は紙ベースで行っていた口座開設や融資申請などの手続きをスマートフォンやパソコンからオンラインで完結できるようにすることは、金融DXの代表的な例です。さらに、AIを活用したリスク評価やチャットボットによる顧客対応、ブロックチェーンによる安全性の高い取引環境など、多様なデジタル技術の統合が進んでいます。
このような取り組みによって顧客の利便性が向上し、同時に業務の効率化やコスト削減にも貢献できるのが金融DXの最大の魅力です。しかし真に効果を発揮するには、顧客のニーズを的確に捉え、それに即した変革を実行する姿勢が不可欠です。
デジタル化が進む社会において、顧客の期待も従来とは異なってきています。ここでは、現代の顧客が金融機関に求めている代表的なニーズを5つに分けて解説します。
顧客の第1のニーズは、時間と場所を問わず手続きができる利便性です。例えば、平日の昼間に銀行窓口へ行く時間が取れない社会人や子育て世代にとって、自宅や外出先からスマートフォンやPCで操作できるサービスは大きな魅力となります。
オンラインでの手続きが可能になれば顧客は待ち時間や移動時間から解放され、必要なサービスに迅速にアクセスできます。また、本人確認や署名などのプロセスもデジタルで完結できると、業務の効率化にも直結するでしょう。
今後の金融サービスでは、ユーザーインターフェースのわかりやすさやエラーの少ない設計が重要になります。操作のしやすさは、サービスの利用継続において大きなポイントなのです。
顧客一人ひとりの価値観や生活リズムに合わせた金融サービスの提供も、これからの金融DXの重要なテーマです。例えばフリーランスや副業を持つ人は、安定収入を前提とした従来型のローン審査では不利になる場合があります。こうした顧客に向けた柔軟な審査基準や、AIを用いた個別最適化された商品提案が求められているのです。
また、家族構成やライフステージに応じた保険商品や資産運用サービスの提案も顧客満足度を高める上で有効です。パーソナライズされた提案は、顧客にとって「理解されている」と感じられる重要な要素になるでしょう。
サービスを選ぶ際に多くの顧客が重視するのが「料金や契約のわかりやすさ」です。これまでは複雑で不明瞭な料金体系や専門用語の多い契約書が敬遠される傾向にありました。
金融DXを進める上では、料金や手数料の透明性を高めて顧客が納得してサービスを選べる仕組みを整える必要があります。例えば、費用シミュレーション機能の導入やAIチャットボットによるわかりやすい解説機能は、顧客理解を深める有効な手段となるでしょう。
情報の明確化は、信頼関係の構築にも直結します。不安や疑念を抱かせない仕組みづくりが、長期的な顧客との関係性を強固にするのです。
オンラインサービスを利用する際に顧客が不安に感じるのが、情報漏えいや不正アクセスのリスクです。どれほど便利なサービスであっても、安全性が確保されていなければ利用は進みません。
そのため、セキュリティ対策の強化は金融DX推進の前提条件です。二段階認証や生体認証、行動パターン分析による不正検知など最新技術の導入が信頼性を支えています。
同時に、これらの技術を「いかにストレスなく利用できるか」も重要です。複雑すぎる認証や過剰な制限はかえって利用離脱の原因となるため、利便性とのバランスを丁寧に設計する必要があります。
デジタル化が進む一方で、「人とのつながり」を求める声も根強く存在します。特に高齢層やデジタルに不慣れな層にとって、地域に根ざした窓口や電話・訪問によるサポートは安心感を与える要素となるでしょう。
またオンラインチャットやビデオ通話による相談窓口の設置は、場所を問わずパーソナルな対応を可能にします。顧客が「相談しやすい」と感じられる環境づくりは、信頼構築に欠かせません。
こうしたアナログとデジタルのハイブリッド型サービスは、顧客満足を高める新たなモデルとして注目されています。
金融DXの推進により、金融サービスにはこれまで以上に多様で柔軟な対応が求められるようになっています。従来の一律的な提供方法では、現代の顧客が抱える複雑なニーズに応えることが難しくなってきました。
特に、デジタルネイティブ世代から高齢者層まで幅広いユーザーが存在する中では、それぞれの価値観や行動様式に合わせたサービスが不可欠です。
ここでは、こうした変化に対応するために、金融業界が取り組むべき具体的なアプローチを紹介します。
まず重要なのが、顧客セグメントごとのニーズを的確に把握する分析体制の構築です。年齢・職業・ライフスタイル・収入・地域などに基づいて分類されたセグメントごとに、異なる期待や課題が存在します。例えば、20代の若年層はスマホ中心の取引を好む一方で、50代以上の層は安心感のある対面対応を重視する傾向があります。
このような多様性を踏まえると、金融機関は一括りの顧客像を前提にサービスを設計するのではなく具体的なデータを活用してターゲットごとの行動や志向を細かく把握することが大切です。市場調査・アンケート・ユーザーテストなどを通じて得られる情報を基にプロファイルを構築し、それに基づいてサービスを最適化しましょう。
次に注目すべきは、対面と非対面のチャネルをシームレスに融合させたサービスの整備です。デジタル化が進む中でも、「人の温もり」が感じられるサービスへのニーズは根強く存在します。すべてをデジタルで完結させるのではなく、必要に応じて人が介在するサポート体制を残すことで顧客満足度の向上につながるでしょう。
具体的には、オンライン上での事前相談やシミュレーションの後に必要に応じて店舗やコールセンターでの相談を組み合わせる「ハイブリッド型」の対応が効果的です。こうした柔軟な対応は、顧客にとって利便性と安心感の両立を実現します。また、予約制のオンライン面談や時間外でも対応可能なチャット窓口の設置なども、今後の標準となっていくでしょう。
AIやチャットボットの導入は、金融業界における顧客対応の効率化と品質向上の両立を可能にします。例えば、FAQ対応や書類の提出方法、サービス内容の説明など定型的な問い合わせに関しては、チャットボットが即時対応すると顧客の待ち時間を削減できるでしょう。
さらに、自然言語処理技術の進化によってより人間らしい対話が実現され、顧客とのコミュニケーションも円滑に進みます。一方で、複雑な相談や感情を伴う問い合わせには有人対応が必要です。AIが問い合わせ内容を分類して適切なタイミングで担当者に引き継ぐ仕組みを導入することで、効率と丁寧さのバランスを取れるのです。
近年注目されているのが、定額制のサブスクリプション型サービスや、顧客の好みに応じて選べるカスタマイズ商品です。従来の金融サービスは、一度契約するとそのままの条件で運用される形式が主流でしたが、現代の顧客は常に「自分に合った内容かどうか」を重視する傾向があります。
定期的にサービス内容を見直し、アップデートを提供するサブスクリプション型のアプローチは、顧客との継続的な関係性を築く上で有効です。たとえば、投資初心者向けの月額プランでは、経済ニュースの解説や資産状況の分析レポートを毎月届けるなどの工夫が考えられます。
また保険商品では、顧客が必要な補償だけを選べる仕組みを導入することで、無駄のない納得感のある商品設計が可能になります。こうしたカスタマイズ性の高いサービスは、顧客一人ひとりの価値観にフィットしやすく、長期的な信頼構築にも寄与するといえるでしょう。
最後に欠かせないのが、蓄積されたデータを活用して顧客対応や商品開発を迅速に進める「データドリブン」なアプローチです。顧客の行動履歴・利用傾向・フィードバックなどを分析し、リアルタイムでサービスに反映させる体制を整えることで、常に最適な対応を実現できます。
例えばある商品の解約が特定のタイミングに集中している場合、その背景を分析して改善策を講じるといったサイクルをスピーディに回せるようになります。また、AIを活用して将来的なニーズを予測することで、先手を打った商品提案もできるようになるのです。
このようなデータ中心の経営スタイルは、変化の激しい市場環境において有効です。顧客は「自分のことをよく理解してくれている」と感じ、サービスに対する信頼感が増します。そしてそれが、結果的にロイヤルティの向上や他社との差別化へとつながって行くのです。

金融DXは、単にツールやシステムを導入するだけでは期待される成果は得られません。金融DXは「戦略的なステップ」を踏んで進める必要があります。
ここでは、顧客ニーズに真に応えるための金融DXの推進ステップを具体的に解説していきます。
DX推進において最初に取り組むべきは、顧客のリアルなニーズを正しく把握することです。顧客満足度調査・ネットプロモータースコア(NPS)・コールセンターの応対記録・SNSの口コミなど多様なチャネルから顧客の声を収集し、テキストマイニングや感情分析を用いて傾向を可視化します。
その上で重要になるのが「優先順位の設定」です。全ての要望に対応することは現実的ではないため、ニーズの頻度・影響度・収益性への寄与などを基準に、取り組むべき課題を明確にしましょう。的確な分析と選別により、次のステップがより効果的に機能します。
顧客中心のDXを成功させるためには、経営層から現場社員に至るまで全社的な共通認識を持つことが不可欠です。「なぜ今DXが必要なのか」「自社が目指す姿は何か」といった目的とビジョンを明確にし、社内での浸透を図りましょう。
その際、抽象的な表現ではなくKPI(重要業績評価指標)や顧客ロイヤルティ向上といった具体的な成果指標を示すと、社員一人ひとりの行動が経営方針とつながっているという意識が生まれます。目的共有は、組織を1つにまとめる推進力となります。
DXの根幹を支えるのがデータです。顧客情報・取引履歴・アクセスログなどあらゆるデータを安全かつ効率的に活用するためには、データ基盤の整備が欠かせません。クラウド型DWH(データウェアハウス)やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)の導入により、部門間で分断されていた情報を統合して分析の精度を高める環境を構築します。
また、既存システムとの連携も重要です。金融業界ではレガシーシステムが多く残っている現状があり、新旧システムの橋渡しを行うAPI基盤の整備が求められます。これにより、サービス開発のスピードと柔軟性が向上するのです。
DXは一部の部門だけで完結するものではありません。営業、システム、マーケティング、コンプライアンスなど複数の部門が連携し、共通の目的に向かって動く体制が求められます。そこで有効なのが「クロスファンクショナルチーム」の構成です。
各部門から選出されたメンバーが一つのチームとなり、プロジェクトベースで課題に取り組むことで、意思決定のスピードが上がるだけでなく、現場の知見を取り入れた実践的な施策も設計可能となります。部門間の壁を越えることが、顧客視点のDX実現には欠かせません。
顧客との接点は、オンラインバンキング・モバイルアプリ・対面窓口・電話・チャットボットなど多岐にわたります。重要なのは、それぞれの接点において「顧客が求める体験」が提供されているかという視点です。
例えば資産運用に関する相談には、対面やビデオ通話を通じたパーソナルな対応が有効です。一方で口座残高の確認や住所変更などの手続きは、スマートフォンアプリやウェブでの完結が望まれます。顧客の行動データや利用傾向を基に接点ごとの最適化を進めることで、利便性と満足度の両立を図れるのです。
いかに高度なシステムやチャネルを整備しても、それを使いこなせる人材がいなければ成果には結びつきません。そのため、社員のデジタルリテラシーを高める教育は欠かせない要素です。
単なる操作方法の習得ではなく、DXの目的や顧客視点の考え方を含めた「マインドセットの転換」が求められます。eラーニングやワークショップ、ロールプレイングなどを通じて実践的なスキルを習得する機会を提供し、組織全体の対応力を底上げしていきましょう。
DXは一度導入して終わりではなく、継続的な改善が不可欠です。プロジェクトごとにKPIを設定して成果を定量的に評価した上で、どの施策が有効であったか、どの部分に課題が残るかを明らかにします。
その評価結果を踏まえて、次の施策に活かしていく「PDCA(Plan-Do-Check-Act)」サイクルを回すことが重要です。こうした反復的なプロセスを通じて、顧客ニーズの変化に対する柔軟な対応力が身につきます。結果として、競争力のある金融サービスを提供できる体制が整っていくのです。
金融DXを進める上で重要なのは、単にデジタル化を目的とせず「顧客にとって本当に価値のある体験とは何か」を常に意識することです。しかし、技術の導入や業務プロセスの刷新には、いくつかの注意点があります。
ここで挙げる3つのポイントを押さえると、金融DXの成功率を高め、顧客満足度の向上につなげられるでしょう。
金融機関においては、依然として対面での対応を重視する顧客が一定数存在します。特に高齢者層や金融知識が浅い層にとっては、窓口対応や電話サポートは安心感をもたらす存在です。
このような背景から、デジタルチャネルの強化と同時に対面サービスの質を維持しつつ適切な使い分けが重要です。例えば、定型的な問い合わせはチャットボットに任せ、複雑な相談は人による対応に切り替えるといったハイブリッド型のサポート体制が求められます。
顧客の利便性を最優先に考えることで、デジタル化と人の温かみの両立が可能になります。
金融サービスにおけるセキュリティの強化は、DX推進の基盤ともいえる要素です。なぜなら、個人情報や取引データなどの機密性の高い情報を扱う金融業界では、一度のセキュリティ事故が企業の信頼性を損なう恐れがあるためです。
クラウド環境の活用やAPI連携など新しいテクノロジーを導入する際には、アクセス権限の管理や多要素認証の導入、不正アクセスの検知システムなど複層的なセキュリティ対策を整備する必要があります。
また、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を活用し、全社的にリスク管理意識を共有することが欠かせません。顧客が安心してサービスを利用できるよう、セキュリティポリシーの策定と運用を徹底しましょう。
DXを推進する過程では、社内外でデジタル化に対する抵抗感や習熟度の差が生まれる可能性があります。特に業務に長年従事してきたベテラン社員やITリテラシーが高くない顧客にとっては、急激な変化に不安を感じやすい傾向があります。
このような課題に対しては、段階的な導入と丁寧な教育が不可欠です。社内向けには業務内容や役職に応じた研修プログラムを提供し、具体的な事例を通じてDXの意義や操作方法を伝えると効果的です。
一方顧客向けには、FAQや動画マニュアルの整備、店頭での説明会の実施などサポートコンテンツの充実を図ることが望まれます。全体の理解と共感を得ながら、スムーズな変革を進めていきましょう。
多様化する顧客ニーズに対応するためには、自社に適したDX戦略の策定と実行が求められます。しかし、どこから手を付けるべきか、どの技術を導入するべきかといった判断に迷うことも少なくありません。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』は、金融業界に特化したDX推進のコンサルティングを提供する会社です。顧客視点を軸に据えた現状分析から業務プロセスの見直し、システム導入の選定、社員研修の設計に至るまで包括的なサポートを行っております。
また、実績豊富なプロジェクトマネージャーが伴走し、現場の課題に寄り添った具体的な改善策を提案いたします。
もし、金融DXの進め方にお悩みであれば、ぜひ一度『株式会社 TWOSTONE&Sons』までご相談ください。

金融業界におけるデジタル化の波はとどまることを知らず、顧客の期待はさらに多様化しています。こうした状況下で企業が持続的な成長を遂げるためには、顧客ニーズを正確に捉えて適切なDX施策を講じることが不可欠です。
今回ご紹介したように、DX推進には「顧客理解」「全社的な方向性共有」「データ基盤整備」「チーム編成」「チャネル選定」「人材育成」「継続的な改善」という一連のステップが存在します。そして、それぞれの段階で注意すべきポイントを意識すると、DXの質を高められるでしょう。
もし貴社が顧客中心のDXを検討しているのであれば、ぜひ信頼できるパートナーとともに歩むことをおすすめします。顧客に選ばれ続ける金融サービスを実現するために、今こそDXに本気で取り組むタイミングです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
