金融DXの推進によって叶う勘定系システムの刷新|4つの取り組み例を紹介
金融

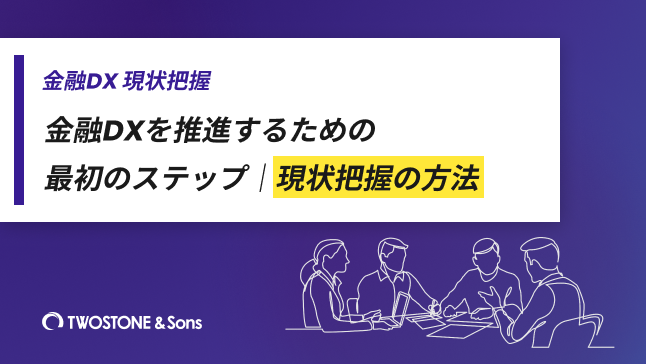
金融DXを成功させるためには、現場の声を正確に把握することが重要です。従業員ヒアリングやデータ収集を通じて、効果的な戦略設計を行い、DX推進を実現しましょう。
「DXを始めよう」と意気込んでも、何から手をつけるべきかわからず戸惑っている金融機関の経営者や担当者は少なくありません。実際、多くの企業がDXに着手しているものの、成果につなげられていない現状があります。その主な要因の一つは、現状の正確な把握が不十分なままプロジェクトが進められている点にあるでしょう。
本記事では、金融業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の基本を踏まえつつ、推進の第一歩となる「現状把握」の重要性と効果的な進め方について詳しく解説します。読み進めることで、なぜ現状把握が必要なのか、どのように実施すればよいのかが明確になるはずです。最終的には、失敗リスクを避けつつ自社に適したDX戦略を描けるようになるでしょう。

金融DXとは、デジタル技術を活用して金融機関の業務プロセス、商品・サービス、顧客体験、そしてビジネスモデルそのものを革新する取り組みを指します。単なるITシステムの導入ではなく、業務効率化やコスト削減にとどまらずに競争力の強化や新たな価値創出を目指す変革です。
近年、フィンテック企業の台頭や顧客ニーズの多様化、さらには非接触型サービスへのニーズの高まりなど、金融業界を取り巻く環境は急速に変化しています。これに対応するには、従来の仕組みや文化を根本から見直して柔軟かつスピーディに改革を進める姿勢が不可欠です。
金融DXを成功させるためには、単に技術を導入するだけでは不十分です。企業としての目的やビジョンを明確にした上で、業務のどの部分をどのように変革するのかを戦略的に設計しなければ投資対効果も期待できません。そのため、取り組みの出発点として現状を正確に把握する作業が重要となります。
金融DXを進める上でなぜ現状把握が重要なのか、その理由は単に「現状を知る」ためではなく、DXを成功に導くための確かな土台を築くためにあります。
ここでは、具体的な3つの視点からその必要性を解説します。
まず、現状把握はDX戦略の設計において欠かせないステップです。なぜなら、現場が抱える問題や非効率な業務フロー、システムの老朽化、人材のスキルギャップなど目の前の課題を正確に特定しなければ、どこに手を入れるべきか判断できないからです。
例えば、顧客対応に時間がかかっているという課題があった場合、それがシステムの問題なのか、オペレーションの問題なのか、人員配置の問題なのかによって取るべき施策は大きく変わります。こうした課題の本質を誤れば、いくら高度なテクノロジーを導入しても期待する成果は得られないでしょう。
現状分析には、業務フローの可視化や従業員へのヒアリング、システム資産の棚卸しといった地道な作業が伴います。これらの工程を丁寧に積み上げることで、現実と理想のギャップが明らかになり、そこに具体的なDX施策を配置していけるのです。
DXは仮説構築と検証の連続です。そのため、出発点となる仮説が正確でなければ以降のプロセスがすべて歪んでしまう可能性があります。現状把握を疎かにすると、表面的な課題に対処しようとして、本質的な問題を見落としてしまうかもしれないのです。
実際に、顧客満足度の低下という結果だけを見て「チャットボットの導入が必要だ」と判断する企業もあります。しかし、実際には問い合わせ窓口の属人化やデータベースの未整備といった根本要因が隠れていることも少なくありません。
こうした誤った仮説を避けるためにも、データや現場の声に基づいた分析が必要なのです。思い込みや過去の成功体験にとらわれずフラットな視点で現状を捉えることが、結果として効果的なDX戦略の構築につながります。
DX推進には、多くの関係者が関与します。経営層、現場社員、IT部門、そして外部のパートナー企業など関係者ごとに持っている情報や問題意識が異なる場合も珍しくありません。このような状況で共通の目標に向かって動くためには、まず「現状」に対する認識を揃えることが必要です。
例えば、現場はシステムの使いにくさを訴えていても経営層はコスト削減の観点でDXを推進しているといったギャップが存在すると、プロジェクトが迷走する可能性があります。現状把握の段階でそれぞれの立場から得られた知見を集約することで、施策の方向性に対する合意形成を図りやすくなるでしょう。
また外部のITベンダーやコンサルティングファームと連携する際にも、現状の資料やデータが整備されているとスムーズな提案や施策設計につながります。こうした準備が不十分だと打ち合わせが形骸化し、時間やコストの無駄が発生しやすくなります。
金融業界でのDXを成功させるには、まず社内の現状を正確に把握することが不可欠です。現状分析を怠ると、無駄な投資や施策の失敗を招くリスクが高まるでしょう。
ここでは、社内の現状を把握するために必要な7つのステップを紹介します。これらのステップは単独で行うものではなく、すべてが連携して高精度な分析を実現します。実行すれば、効果的なDX戦略を描くことができるでしょう。
最初に行うべきは、経営ビジョンとDXの方向性の整合性を確認することです。企業のDXを推進する上で重要なのは、経営陣のビジョンがしっかりとデジタル化の方向性と一致しているかどうかです。経営層がどのような目的でDXを進めようとしているのかを明確にし、その目的に沿った戦略を策定することが出発点となります。
例えば、企業の目標が「コスト削減」なのか「新規事業の創出」なのかによってDXの取り組み方は大きく異なります。もしコスト削減が主な目的であれば業務の効率化を中心にDXを進める必要がありますし、新規事業の創出が目的であれば顧客接点をデジタル化し、データを活用した新たな価値創出に注力するべきです。経営ビジョンに沿った方向性でDXを進めることで企業全体のモチベーションが高まり、戦略も効果的に実行できるのです。
次に行うべきは、現行業務フローとITシステムの棚卸しです。現状を把握するためには、業務の流れとそれを支えているシステムがどのように構築されているのかを明確にすることが重要です。現在使用しているITシステムやツールがどのように業務に活用されているのかを把握すると、DXに必要な改善点や導入すべき新たな技術が見えてくるでしょう。
例えば、業務の中で手作業が多い部分や非効率なフローが存在する場合、その部分にデジタル化や自動化を導入することで効率化が図れる可能性があります。また既存システムの老朽化が進んでいる場合は、アップグレードや新たなシステムの導入が必要となります。このように、業務フローとITシステムの現状を把握すると、DXを実施するために何が不足しているか、または改善すべき点はどこかが明確にわかるのです。
参考:金融庁
次に確認すべきは、従業員のデジタルリテラシーと人材スキルです。DX推進においては、社員のスキルと意識が重要な要素となります。例え優れたデジタルツールやシステムを導入しても、それを使いこなせる人材が不足していれば十分な効果を上げることはできません。
そのため、現状の人材がどれだけデジタル技術に精通しているのか、また新たな技術に対してどれだけ柔軟に対応できるかを確認する必要があります。デジタルリテラシーが低いと感じる部署があれば、その部分に対する研修やスキルアップのプランを立てる必要があるでしょう。また、社内にデジタル化を推進できるリーダーシップを持った人材がいるかどうかも、DXの成否を分ける重要なポイントです。
金融業界では、顧客接点のデジタル化は必須の取り組みです。デジタルチャネルの活用状況を分析することで、顧客体験を向上させるための改善点が浮き彫りになります。顧客との接点がどこにあり、それらがどのようにデジタル化されているのかを詳細に把握する必要があるのです。
例えば、オンラインバンキングやモバイルアプリ、チャットボットなど顧客と接するデジタルチャネルがどれだけ活用されているかを確認し、その利用状況や顧客からのフィードバックを収集しましょう。顧客が使いやすいと感じている部分を強化し、逆に使いづらいと感じている部分を改善することが顧客満足度を向上させるためには欠かせません。
データ活用は、DX推進の中でも特に重要な要素です。金融機関が保有している膨大なデータをどのように活用しているか、その実態と課題を把握することが次のステップとなります。多くの金融機関が顧客データや取引データを蓄積しているものの、それらのデータを十分に活用できていないケースもあります。
データ活用においては、まず「どのデータを活用しているのか」「どのような目的で活用しているのか」を明確にしましょう。そして、そのデータが正確で最新のものであるかどうか、データの整備状況やセキュリティ面の課題の確認も重要です。データ活用の課題を把握することで、AIや機械学習などの高度な技術をどのように活用するか、次の施策を決定するための方向性が見えてきます。
現場の声をしっかりと聴くことは、現状分析において重要です。現場のスタッフが抱える課題やボトルネックを把握すると、実際の業務フローに即した改善策を実践できます。現場の意見を無視してトップダウンで進めるDXは現場での反発を招き、最終的には失敗に終わる可能性があるのです。
現場でどのような問題が発生しているのか、どのプロセスで効率が悪いのかをヒアリングすると実践的な改善策が見つかるでしょう。例えば、手作業が多く時間がかかる業務や既存システムでは処理が遅くて顧客対応が遅れるといった課題があります。現場の意見を反映させることで、実効性のあるDX施策を立てられるでしょう。
最後に、現状分析の結果を経営層と共有し、課題の優先順位を設定しましょう。現場の課題やデータ分析結果を経営層に伝えることによって組織全体で認識が一致し、DX推進に必要なリソースが確保されます。経営層がどの課題を重要視するかを理解し、その優先順位に基づいて施策を実行に移すことが大切なのです。
現状分析の結果を基に、どの課題から取り組むべきかを明確にし、経営層との認識合わせを行って具体的なアクションプランを立てることが、成功へとつながる第一歩です。
金融業界においても、業務フローの効率化は重要な課題となっています。特に、伝統的な業務プロセスに依存している金融機関ではデジタル化が進んでいない部分が多く、業務効率を高めるための改善が急務です。
ここでは、金融機関が直面している代表的な業務フローにおける課題を紹介します。
多くの金融機関では、未だにアナログ作業が残っている業務プロセスが存在しています。例えば書類の手書きや郵送による書類のやり取り、顧客データの手動入力などが挙げられます。これらのアナログ作業は時間と労力を大量に消費し、業務の効率を低下させる原因となっているのです。
デジタル化が進んでいない業務フローはエラーが発生しやすく、情報の遅延や重複が生じる可能性も高くなります。また顧客サービスにおいても、手続きが遅れることで顧客満足度が低下する恐れがあります。これを解決するためには、業務のデジタル化を進めることが必要です。書類の電子化や自動化ツールの導入などから始めましょう。
金融機関では、複数の部門が異なるシステムを使用している場合があります。このため部門間のシステム連携が不十分で、情報が分断されてしまうことがあります。例えば、営業部門が顧客データを管理しているシステムとリスク管理部門が使用しているシステムが統合されていない場合、同じ顧客情報が異なるシステムに重複して登録されることが出てくるかもしれません。
この情報の分断は業務の効率を低下させるだけでなく、誤った情報に基づいた意思決定を招く可能性もあります。これを防ぐためにはシステム間でのデータ共有を円滑にし、統一された情報基盤を作ることが重要です。これによってリアルタイムでの情報アクセスが可能になり、迅速な意思決定ができるようになります。
金融業界では、顧客からの問い合わせや要求への迅速な対応が求められます。しかし、従来の業務プロセスでは、顧客対応が遅れることが少なくありません。例えば、顧客の口座情報の確認に時間がかかる、あるいは手続きに必要な書類を取り寄せるのに時間がかかるといったケースです。
これらの問題は、顧客満足度に大きな影響を与えます。顧客は迅速かつ柔軟な対応を期待しており、遅延や煩雑な手続きに不満を感じやすくなるでしょう。この課題を解決するためには、業務のデジタル化を進めて迅速に情報を取得し処理できる体制を整えることが必要です。特に、AIやチャットボットを活用した自動応答システムの導入が効果的な解決策となるでしょう。
顧客データの活用において重要なのは、プライバシーとセキュリティの確保です。データを収集・分析する際に、顧客の個人情報を適切に保護して漏えいを防ぐことが求められます。これに対する顧客の懸念から、データ活用が進まないケースがあるのです。
金融機関は、厳格なセキュリティ対策を講じ、顧客に対してデータ活用の透明性を示す必要があります。つまり、データの収集方法や使用目的について顧客に明示して信頼関係を築くことが大切なのです。またセキュリティ技術の進化に伴い、個人情報の保護を強化する必要があります。
たとえデータ活用が進んでいても、その分析結果を実際の業務改善につなげるスキルが不足しているケースがあります。データを収集するだけでは不十分で、それをどのように業務に活かすのかが課題となります。
特に重要なのは、分析結果を業務フローに組み込み、日々の意思決定に反映させる力です。データを現場の改善に結びつけるためには、単なる数字の把握にとどまらず、実行可能なアクションへ落とし込む視点が求められるでしょう。

デジタル化が進む中で、金融機関に対する顧客ニーズも急速に変化しています。顧客の期待に応えるためにはこれらのニーズを的確に捉え、柔軟に対応する必要があるでしょう。
ここでは、最近の顧客ニーズの動向について、いくつかの具体例を挙げてみます。
顧客の生活スタイルが変化する中で、スマートフォンを利用した金融手続きの利便性が求められています。これにより、銀行や保険、証券取引など従来は対面で行われていたサービスが、オンラインで完結できるようになりました。顧客は、営業時間に縛られることなく、自分の都合でサービスを利用できることを期待しています。
このニーズに対応するために、金融機関はスマートフォンアプリやモバイルバンキングを強化し、取引や口座開設、融資申請などがすべてモバイルで完結できるようにする必要があります。加えて、スマートフォンを使った顧客サポートの充実やセキュリティ面での強化も欠かせません。
顧客は、個々のライフステージやニーズに応じた柔軟なサービスを求めています。例えば、結婚や出産、住宅購入などのライフイベントに合わせた金融商品やサービスの提供などです。これには、顧客のライフプランを理解してそれに応じた商品提案を行うことが必要です。
また、近年では高齢化社会が進んでおり、シニア世代向けの金融サービスの充実も求められています。例えば、年金に関するアドバイスや相続対策、老後の資産管理に関するサポートなどが必要です。ライフスタイルに寄り添った柔軟なサービスを提供することで顧客の満足度が高まり、信頼を得られるのです。
顧客が求めるサービスはより一層個別化しています。そこでデータを活用すると、顧客一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた提案が可能になります。例えば、顧客の取引履歴や行動データを分析すると、最適な金融商品を提案できるでしょう。
このようなパーソナライズサービスを強化するためには、AIやデータ分析の技術を駆使することが重要です。金融機関は顧客のデータをリアルタイムで収集・分析し、タイムリーに適切な提案を行うことが求められます。こうしたサービスの提供は顧客のロイヤリティを高め、競争優位性を確保するために不可欠です。
金融DXを推進するためには、従業員の意見や現場の実情を正確に把握することが重要です。従業員の声をしっかりと収集し、それを基に改善策や戦略を立案すると、金融機関はより効果的なDXを実現できるでしょう。
ヒアリングの方法にはいくつかのアプローチがありますが、今回はその中でも特に効果的な方法をご紹介します。
個別インタビューは、現場のリアルな声を直接聞き取るための効果的な手法の1つです。従業員が直面している課題やニーズ、業務の中で感じる不便さや改善点などを詳細に把握できます。また、インタビューは対話形式で進めるため質問に対して自由に意見を述べてもらうことができ、従業員が感じている深層の問題を引き出せるのです。
インタビューの際には、以下のポイントを意識するとより有益な情報を得られます。
このように、個別インタビューを通じて現場の実情に即した貴重な情報を得られ、DX推進に向けた具体的なアクションを見つけるための基盤を築けるでしょう。
匿名アンケートは、従業員が自由に意見を表現しやすくするための有効な方法です。特に、業務上で抱えている悩みや不安が職場の人間関係に関連する場合など、個別インタビューでは本音がなかなか出にくいことがあります。そこで匿名の形式を取ると、従業員は自分の名前を気にせず率直な意見を提供しやすくなるのです。
アンケートを実施する際には、次の点を意識すると良い結果が得られます。
匿名アンケートを効果的に活用することで従業員の本音を引き出し、組織の問題点や課題を洗い出せるでしょう。
ワークショップは、従業員同士が集まり意見を交換し合うための場として有効です。異なる部門や役職の従業員が一堂に会することで、普段は聞けない視点や意見を集められます。特に金融機関では各部門の業務が密接に関連しているため、部署を超えた意見交換が重要です。
ワークショップを成功させるためには、以下のポイントに注意すると良いでしょう。
ワークショップを通じて従業員同士がアイデアを交換し合うことで、新しい発見や解決策を生み出せるでしょう。
従業員から収集したデータや意見を基に経営層に対して報告を行う際には、ここで紹介するポイントを意識しましょう。効果的なレポートを作成することで、経営層の理解と共感を得やすくなります。
経営層は、現場の意見だけではなくそれを裏付けるデータにも重きを置きます。現場の声を数値的に示すことで、問題の深刻さや改善の必要性を具体的に伝えられます。例えば、従業員アンケートの結果や業務プロセスの改善効果を数値で示すと、説得力が増すでしょう。
DXを進める上で経営層が関心を持つのは、投資に対するリターン(ROI)です。金融機関におけるDXは単なる技術導入に留まらず、ビジネスの効率化や新たな収益源の創出が目的です。そのため、導入する技術や施策がどのようにROIを上げるのかを明確に伝えることが求められます。
方針が決定した後、実行に移すための計画をすぐに立てることが重要です。経営層からの承認を得た後は、すぐに具体的なアクションプランを作成して実行に移します。この時、期限や責任者を明確にし、進捗管理を行うことで、計画を順調に進められるのです。
金融機関におけるDX推進には、適切な現状把握と戦略設計が不可欠です。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』は金融業界に特化したコンサルティングを行っており、業務効率化やデジタル化を実現するためのサポートを提供しています。業界のトレンドや最新技術を踏まえ、貴社のDX推進を成功に導くための戦略を設計いたします。
金融DXに関するお悩みや課題があれば、ぜひご相談ください。

金融DXを効果的に推進するためには、現場の声を正確に把握し、それを基にした戦略設計が欠かせません。従業員ヒアリングや経営層への報告を通じて現状をしっかりと把握し、改善策を具体的に立てることが成功への第一歩です。
また、適切なデータ収集やROIの明確化、実行計画の策定を行うことで、DXを確実に推進できます。金融DXの進展を実現するために、まずは正しい現状把握から始めましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
