保険DX推進に必須なコンプライアンス対策|内部統制と監査のデジタル化
保険

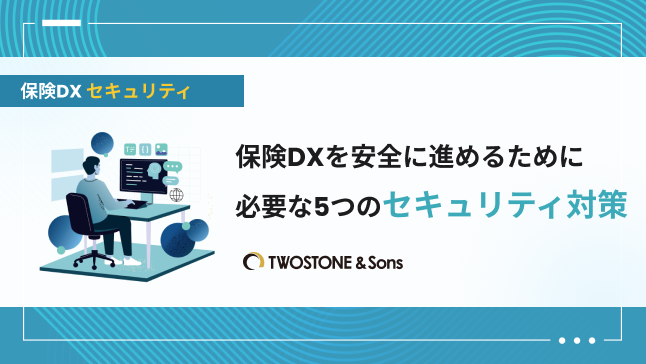
保険DXを円滑かつ安全に進めるためには、情報漏えいや不正アクセスなどに対するセキュリティ対策が欠かせません。本記事では、保険DXにおける課題や基本的な考え方・実際に活用できる具体的なステップまでを丁寧に紹介します。
保険業界でもDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が加速し、業務の効率化や顧客サービスの向上に注目が集まっています。しかしその一方で、デジタル化の進展に伴い、情報漏えいや不正アクセスといったセキュリティリスクが深刻化しているのも事実です。「クラウドを導入したいけれどセキュリティが不安」「社内に専門人材がいないため、どこから手を付ければよいかわからない」など現場での戸惑いの声も少なくありません。
この記事では、保険DXの推進において直面する具体的なセキュリティの課題とそれらに対応するために押さえておくべき法律、さらには実践的な対策について解説します。読んでいただくことで何を重視してシステム選定を進めるべきかが明確になり、安全かつ効果的なDXの第一歩を踏み出す準備が整うでしょう。

保険業界は、個人情報や財務データといった機密性の高い情報を大量に扱うため、DX推進においては特にセキュリティ対策の徹底が求められます。ここではまず、保険DXの基本と、なぜセキュリティがカギを握るのかを確認していきましょう。
保険DXとは、保険業務全体をデジタル技術によって再構築し、業務効率の向上・顧客体験の最適化・新たなビジネスモデルの創出を目指す取り組みです。例えば、紙ベースの契約業務をオンライン化することで手続きの迅速化や人的ミスの削減を実現できます。またビッグデータやAIを活用すれば保険商品の提案精度が向上し、よりパーソナライズされたサービスの提供も可能となるでしょう。
ただし、このようなデジタル化の推進には常にサイバーリスクが伴います。特にクラウドサービスやAPI連携の活用が進む今、セキュリティの堅牢性を確保しなければ業務そのものが停止するような重大な事故につながりかねません。
保険業界では、顧客の個人情報や契約内容、医療・健康データなど極めてセンシティブな情報を扱っています。こうした情報が外部に漏れることは顧客からの信頼を失うだけでなく、法的責任や巨額の損害賠償リスクを招くかもしれません。
また、最近ではフィッシング詐欺やランサムウェアなど攻撃の手口も巧妙化しており、一度の侵害が企業全体の業務に影響を及ぼすケースも増えています。そのためDXを進める際には、最新の技術を取り入れるだけでなく、それを守るセキュリティの体制づくりが不可欠です。
保険DXを安全に進めるためには、直面しやすい課題をあらかじめ把握し、それに対応できる体制を整えておく必要があります。ここでは代表的な3つの課題について解説します。
DXに伴いクラウド環境や外部サービスとの連携が増えると、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃を受けるリスクも高まります。特にセキュリティパッチの適用が遅れたり古いソフトウェアを使い続けていたりすると、システムの脆弱性を突かれてしまいます。
そのため、常に最新のセキュリティ情報に基づいた運用とファイアウォールやIDS/IPS(侵入検知・防御システム)などの多層防御が必要です。
DXによってシステムが増えると、管理対象のアカウントや権限も複雑化します。これにより誰がどの情報にアクセスできるのかを正確に把握するのが難しくなり、不正アクセスや内部不正を見逃す原因になりかねません。
アクセス制御は「最小権限の原則」に基づき、業務に必要な範囲に限定する運用が求められます。また、ID管理を一元化し、監査ログを定期的に確認する体制も重要です。
データのデジタル化は利便性を向上させますが、同時に情報の持ち出しや誤送信による漏えいリスクも増加します。特にクラウドやモバイル端末の利用が一般化する中で、データの流出経路も多様化しているためです。
これに対しては、データの暗号化やDLP(情報漏えい防止)ツールの導入が効果的です。さらに、社員に対するセキュリティ教育を継続的に行うと、人的リスクも低減できるでしょう。
DXを進める上では、テクノロジーの導入やセキュリティ対策と同時に法令順守の視点も欠かせません。法的リスクを回避しながら安全かつ効果的にDXを推進するには、関連する法律を正しく理解しておく必要があります。
ここでは、保険業界が特に押さえておくべき主要な5つの法律を解説します。
金融商品取引法は、証券や保険といった金融商品の取引における公正性と透明性を確保するための法律です。保険商品が投資性を持つ場合、企業は正確な情報開示や社内の監視・管理体制の構築を求められます。DXにより自動化が進む中でも、顧客に対して不利な情報の非開示が起きないようシステム側での監査機能の整備が重要になります。
例えばAIを活用して契約内容の提案を自動化するシステムを導入する際には、提示する情報が適切かつ公平であるかを確認するプロセスが必要です。情報の偏りや不完全なリスク説明が起きると金融商品取引法違反として行政処分の対象になる可能性もあります。開示義務のある情報はあらかじめマスターデータとして管理し、提示漏れが発生しないようアラート機能や監査ログを設けましょう。
参考:金融庁
保険業法では、保険会社の健全な経営を担保するための規定が設けられています。顧客情報の管理や商品設計の妥当性だけでなく、業務の外部委託時にも厳格な管理体制が求められます。例えばクラウドサービスを利用する場合でも、委託先のセキュリティ水準や業務実態を十分に把握した上で契約を結びましょう。
特にDX化によって外部システムとの連携が増加すると、委託先の選定と契約管理がガバナンス強化のカギを握ります。委託契約書には情報漏えい時の報告義務や業務停止時の対応についても明記し、突発的なトラブルにも備える必要があります。また、定期的な委託先監査の実施や、サービスレベル合意(SLA)の順守状況をモニタリングする仕組みも構築すべきです。
参考:金融庁
保険業務においては、氏名・年齢・住所・健康状態といったセンシティブな情報を扱うため、個人情報保護法に対する理解と対応が極めて重要です。
具体的には、以下のような運用レベルでの対応が求められます。
さらに万が一、情報漏えいが発生した際には速やかな報告義務と対応措置が法的に義務付けられています。
加えて、DXの取り組みによりデータ収集が自動化される場合、本人が認識しづらい形で情報が取得されていないかを検証する仕組みも必要です。ウェブ上での契約手続きにおいても、プライバシーポリシーの提示やオプトアウト(同意撤回)の導線を明確に設けるなどユーザーの権利保護に配慮した設計が求められます。顧客データの取り扱いに関する透明性が、企業の信頼性を左右するのです。
参考:総務省
サイバーセキュリティ基本法は、国全体でサイバー攻撃に対応する枠組みを示した法律です。保険会社もこの法律に基づき、自社のサイバーセキュリティ方針や実施計画を見直すことが推奨されます。例えば、サイバーインシデント対応マニュアルの作成や社員へのセキュリティ教育プログラムの導入が有効です。保険DXではクラウドサービスやAPI連携の活用が進むため、外部との接続面でのリスク評価も忘れてはなりません。
また、サイバーセキュリティ基本法では政府機関やインフラ事業者に対して情報共有と連携体制の構築が求められており、保険業界でもその影響を受けています。具体的には、脆弱性情報の早期取得や対策ソフトの適用状況の定期的な点検など、技術的・組織的セキュリティの強化が重要となります。
参考:経済産業省
この法律では、他人のIDやパスワードを盗用してシステムに侵入する行為などが禁止されています。保険会社では、社員や代理店が扱う顧客情報に対するアクセス権限の設定やログイン認証の強化(例:二要素認証)の導入が求められます。また、社内外で発生しうる不正アクセスの兆候を早期に発見するために、SIEM(セキュリティ情報イベント管理)ツールを導入する企業も増えてきました。
SIEMを活用すれば、アクセスログや通信履歴をリアルタイムで分析し通常とは異なる挙動を早期に検知することが可能になります。加えて不正アクセスのリスクは従業員からの内部不正も含まれるため、権限分離の徹底や異常操作の自動アラート設定も不可欠です。発生時には速やかに対応できるようあらかじめインシデントレスポンス計画を策定し、訓練を定期的に行うことで、法令順守と企業の危機管理能力を両立させましょう。
参考:経済産業省

保険業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する際、単なるシステム導入や業務効率化にとどまらず、サイバーセキュリティの確保が喫緊の課題となっています。特に顧客の個人情報や財務データを扱う保険会社では、セキュリティ対策の不備が即座に信頼の喪失や損害賠償に直結するためです。
ここでは、保険DXにおける実践的かつ効果的なセキュリティ対策を5つ紹介します。いずれも今日の脅威環境に即した取り組みであり、法令順守だけでなく業務の信頼性向上にも寄与する内容です。
ゼロトラストセキュリティとは、社内外を問わず「誰も信用しない」という前提でシステム設計を行い、アクセスのたびに認証と検証を行うセキュリティアーキテクチャです。従来のファイアウォールによる境界防御では、VPN経由で内部に侵入された際に対処が困難になるケースがありました。
具体的には、端末ごとに認証手段を設けてユーザーの行動や接続先の状況に応じてリアルタイムでアクセス制御を行います。例えば異常な時間帯や地理的に不審な場所からのアクセスがあった場合、自動的にブロックする仕組みが重要です。
この取り組みは、リモートワークやクラウド活用が進む現代において保険会社の基盤を安全に保つ有力な手段といえるでしょう。
多くの企業では、業務上の便宜を理由に広範なアクセス権限を持たせてしまう傾向があります。しかし、これは内部不正や誤操作による情報漏えいの温床となる危険性があります。特に保険業界では顧客の金融情報や健康状態といった機微情報を扱うため、アクセス権限の最適化が欠かせません。
そこで、業務別に「必要なデータ」「アクセス可能な時間」「操作可能な範囲」を明確に定義し、ポリシーベースで権限設定を管理します。定期的にアクセス権の棚卸しを行い、異動や退職時の即時対応を徹底することで、無用なリスクを回避できるでしょう。
適切なアクセス制御は外部攻撃への防御だけでなく、内部統制の強化にもつながります。
どれだけ強固なセキュリティ技術を導入しても、社員が不用意にフィッシングメールを開いたり安易なパスワードを使ったりしていれば、全体の防御力は低下してしまいます。ヒューマンエラーによるインシデントの発生率は依然として高く、対策の優先度は決して低くありません。
セキュリティ教育では、具体的な事例を用いて学ぶことが効果的です。例えば、実際に保険会社で起きた情報漏えいやマルウェア感染のケースを教材とし、どのような行動が危険だったかを検証します。また年1回の集合研修に加えて、eラーニングやクイズ形式のマイクロラーニングを導入すれば継続的な意識向上につながるでしょう。
最終的に安全を守るのは、現場の一人ひとりの判断と行動です。
暗号化は、情報の保管や送受信の過程において外部から内容を読み取られないようにするための基本的な技術です。保険会社では、顧客の個人情報や契約内容、保険金請求の履歴など取り扱うデータの多くが機密性の高い情報です。
保存データ(静的データ)にはAES(Advanced Encryption Standard)などの強力なアルゴリズムを用い、かつ暗号鍵の管理体制を整える必要があります。通信に関しては、TLS(Transport Layer Security)を用いて、社内外のデータやり取りを安全に保つ仕組みが求められます。
さらに、ファイルやメールの添付データに対しても個別に暗号化を施すことで、情報流出の被害を最小限に抑えられるでしょう。
自社だけでセキュリティ体制を評価する場合、慣れやバイアスによりリスクの見落としが起きやすくなります。そこで、専門のセキュリティベンダーや監査法人による外部監査を活用することが有効です。
外部監査では、以下のような観点からの評価が行われます。
その結果に基づいて改善策を講じれば、自社内だけでは気付かなかった弱点の補強ができるようになるでしょう。
さらに、定期的な監査を制度化することで社員のセキュリティ意識も高まり、組織全体のセキュリティレベルが持続的に向上していきます。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証取得を目指す企業にとっても、外部監査は重要なステップです。
保険業界におけるDX推進においては単に最新技術を導入するだけではなく、セキュリティ対策を企業全体で実践し、持続的に強化していく体制の構築が欠かせません。そのためには、段階的かつ計画的にセキュリティ強化を行う必要があります。
ここでは、全社的な取り組みとして有効な5つのステップをご紹介します。
最初のステップは、自社のIT環境や業務プロセスにおけるリスクを洗い出すリスクアセスメントの実施です。この作業は、現状の脆弱性や潜在的な攻撃ポイントを把握し、優先順位をつけた対策計画の立案につなげるために不可欠です。
例えば、顧客情報を管理するクラウド環境に対してどのようなセキュリティ設定がなされているか、社内システムに不正アクセスの可能性がないかといった観点で評価を行います。この工程を丁寧に行うことで的外れな対策にリソースを割かずに済み、実効性の高いセキュリティ戦略を立てる土台ができます。
次に現行のシステムや運用に潜む課題を明確にし、可視化する作業が求められます。セキュリティ対策が十分に機能しているか、運用体制に隙がないかなど複数の観点から見直しを行いましょう。
例えば、アクセス権限が適切に管理されていないケースや古いバージョンのソフトウェアが残っている場合など、日常的に見落とされがちなリスクが表面化する可能性があります。課題の可視化によって社員全体のセキュリティ意識も高まり、全社的な連携体制の強化にもつながります。
システム上の課題が明らかになった段階で、次に必要なのが具体的な改善方針と対策手順の策定です。ここでは、リスクの高い箇所に優先順位をつけながら段階的に対策を導入していく戦略が重要です。
例えば、「重要データは全て暗号化する」「定期的にアクセスログを監視する」「ゼロトラストアーキテクチャを段階的に導入する」といった具合に、具体的かつ実現可能な施策をリストアップします。加えて、緊急対応マニュアルの整備や社員が守るべきガイドラインの明文化もこの段階で行いましょう。
策定した対策手順を全社的に展開していくには、各部門が協力し合いながら一貫した取り組みを実施する体制が必要です。そのため実行計画を全社で共有し、部門横断的なプロジェクトとして推進していくことが求められます。
特に、情報システム部門と業務部門、営業部門との連携は不可欠です。情報漏えいの多くは技術的な問題だけでなく人為的なミスに起因するため、各部門の実務レベルでの理解と実行が重要になります。計画の共有は、会議や社内ポータルを活用し、誰もがアクセスできるように整備しましょう。
セキュリティ対策は、一度導入して終わりではありません。技術は日々進化しており、サイバー攻撃の手口も常に変化しています。したがって、対策を定期的に見直し、必要に応じてアップデートを行う仕組みを整えることが重要です。
年に1回の大規模レビューだけでなく、四半期ごとに簡易的なチェックを実施するなど定期性を持たせましょう。また最新の脅威情報を収集し、自社の対策と照らし合わせる姿勢も求められます。変化に柔軟に対応できる体制が、安全な保険DXの実現につながります。
保険業界のDX推進において、セキュリティは最重要課題の1つです。自社だけで万全の体制を築くのが難しいと感じる場合は、外部の専門家に相談するのも有効な選択肢です。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、保険業界に特化したDX支援の実績を基に実践的かつ現場に根ざしたセキュリティ対策のご提案を行なっております。特定のソリューションの導入だけでなく、体制づくりや教育面も含めてご支援いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
セキュリティ対策は一過性の取り組みではなく、常に進化し続ける必要があります。そのためには、現場での継続的な教育やPDCAサイクルに基づいた評価・改善が欠かせません。『株式会社TWOSTONE&Sons』では、こうした中長期的な取り組みを視野に入れたサービス設計を行っており、貴社のDX推進を安全に支えます。

保険DXの推進は新たなビジネスチャンスを生み出す一方で、情報漏えいや不正アクセスといったリスクも伴います。これらのリスクを最小限に抑えるためには、単発の対応ではなく組織全体でセキュリティを意識した持続的な取り組みが不可欠です。
今回ご紹介したステップや対策方法を実践することで、より安全なDX環境を構築するための基盤を整えられるでしょう。そして、必要に応じて信頼できるパートナーと連携することで限られた社内リソースを有効に活用し、全社的なセキュリティ強化を図りましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
