保険DX推進に必須なコンプライアンス対策|内部統制と監査のデジタル化
保険

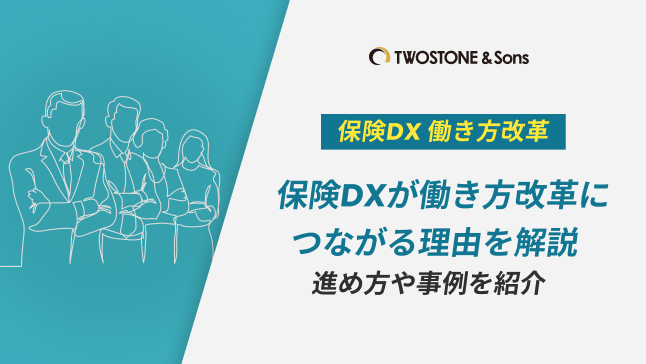
保険DX推進によって確立できる働き方改革について、具体的な推進事例や国の助成制度の活用方法、推進時に注意すべきポイントなどをわかりやすく解説しています。これからDX推進を検討する企業様に役立つ情報を幅広くご提供します。
近年、「働き方改革」という言葉を耳にする機会が増えましたが、保険業界では依然として長時間労働や属人化、非効率な業務プロセスなどが課題として残されています。「このままで本当に良いのだろうか」と疑問を感じながらも、具体的な対策が見いだせずに悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
こうした状況の中で注目されているのが「保険DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。単に業務をデジタル化するだけでなく、保険業務全体の効率を見直し社員の働き方そのものを変えていく手段として期待されています。
この記事では、なぜ保険業界において働き方改革が求められているのか、その背景を明らかにしながら、保険DXがどのようにして業務改善や生産性の向上、多様な働き方への対応を実現するのかを具体的に解説します。
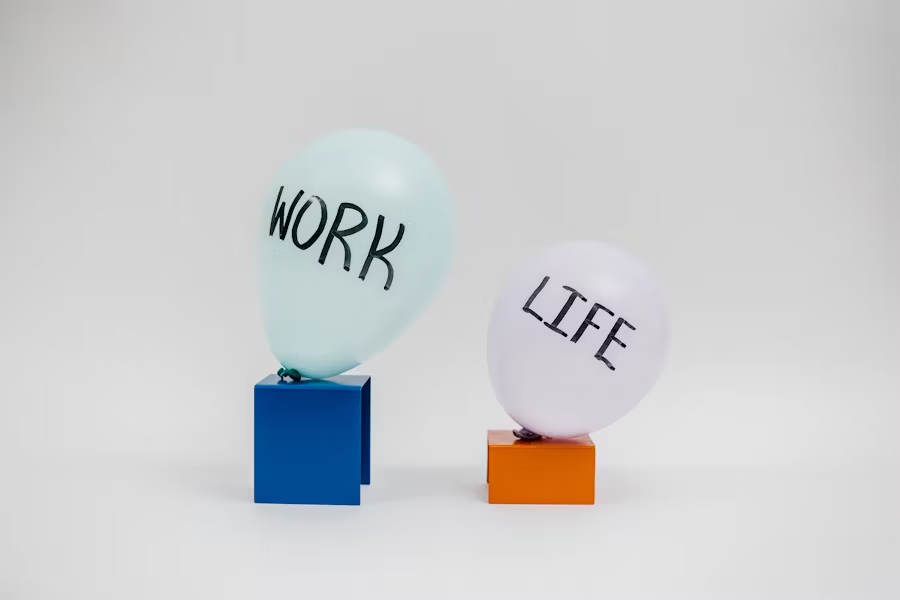
保険業界は長年にわたり、紙ベースの書類や対面営業などのアナログな業務が中心となってきました。しかし、時代の変化とともに、業界全体に変革が求められるようになり、働き方改革が急務となっています。
ここでは、特に重要な5つの要素に着目して、なぜ保険業界で働き方改革が必要とされているのかを説明します。
保険業界では、契約書の作成や顧客情報の入力など煩雑な事務作業が多くの時間を占めています。その結果、社員が本来注力すべきコンサルティング業務や顧客対応の時間が圧迫され、生産性の低下を招いているのです。
例えば、DXを推進しペーパーレス化や業務フローの自動化を図ると、これらの作業を短縮できるでしょう。電子契約システムやCRM(顧客管理システム)を導入すれば、情報の一元管理が可能となり、作業の重複やミスの防止につながります。その結果、限られた勤務時間の中でより多くの価値を提供できるようになり、企業全体の生産性も向上します。
コロナ禍以降、多くの業界でテレワークの導入が進んだ中、保険業界はその対応に後れを取ってきました。紙書類の取り扱いや押印文化が根強く残っていることがその一因です。
そこでクラウド型の業務管理ツールを導入すると、書類の共有や進捗管理をオンラインで行えるようになります。また、ビデオ会議システムを活用すれば営業担当者が顧客との面談を遠隔で実施でき、出張や移動にかかる時間やコストの削減も期待できます。これにより、場所にとらわれず働ける環境が整い、社員の柔軟な働き方が可能になるのです。
属人化とは、特定の業務が一部の担当者に依存しその人以外では対応できない状態です。これは業務の非効率化やリスクの温床となり、組織全体の柔軟性を損なう原因となります。
そこで、業務マニュアルの整備やワークフローの可視化、タスク管理ツールの導入を行うと作業の標準化が進むでしょう。これによって誰でも一定の品質で業務を遂行できるようになり、チーム全体のパフォーマンスが向上します。また、業務がブラックボックス化することを防ぎ、組織的なナレッジの蓄積にもつながるのです。
保険業界は契約ノルマや期限管理、顧客対応など精神的にも負担の大きい職種です。さらに煩雑な書類業務や手作業による入力作業が重なると、社員の疲弊が進み、離職率の上昇にもつながりかねません。
そこで、AIによるデータ入力の自動化やチャットボットによる顧客対応の一次受付を導入すると、社員の業務負荷を軽減できるでしょう。煩わしい作業を自動化することで社員は本質的な業務に集中できるようになり、業務の質と働きやすさの両立が実現します。
女性や高齢者・育児・介護と仕事を両立したい社員など、多様な人材が活躍できる環境づくりも働き方改革の重要な柱です。従来の画一的な働き方では対応しきれない現状があります。
例えば、フレックスタイム制度や短時間勤務制度、リモート勤務の導入は、家庭と仕事の両立を支援する上で有効です。DXによって業務の可視化や進捗共有が容易になれば、こうした制度もより実効性を持って運用できます。誰もがライフステージに応じて柔軟に働ける仕組みを整えることは、企業の持続的成長にもつながるでしょう。
保険業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なる業務効率化を超えた意味を持っています。具体的には、働く人々の労働環境や働き方そのものを柔軟にし、より多様で持続可能な働き方の実現を後押しします。保険DXの推進によって、業務の進め方や情報の扱い方が大きく変化し、結果的に働き方改革の促進につながるのです。
ここでは、その代表的な理由を3つの視点から解説します。
紙ベースで運用されてきた保険業務をデジタルに移行することで、物理的な場所に縛られずに仕事を進められるようになります。これは、リモートワークの導入や営業職の外出先からの対応を可能にし、働く人の時間と行動の自由度を広げるのです。
例えば、顧客情報や契約内容、過去の対応履歴をクラウド上で一元管理すると、出先でもスマートフォンやノートパソコンから即座にアクセス可能になります。これにより、従来はオフィスに戻って書類を確認しなければ対応できなかった業務もその場で完結できるようになります。
保険DXにおいて注目されているのが、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIを活用した自動化ツールの導入です。定型業務やルーティンワークを自動化すると、人が行うべき判断業務や顧客対応に集中できる環境が整うのです。
例えば、新規契約の申込書の入力作業や満期案内のメール送信といった作業は、正確性を求められる一方で時間がかかる業務です。こうしたプロセスを自動化することで担当者の業務時間を削減し、残業の減少にもつながります。
DXによって業務プロセスや進捗状況を可視化し、チーム内で共有しやすくなる環境が整うことも大きな変化の1つです。属人的な作業が排除され、誰でも業務の流れを把握できる状態を作ると、急な休暇や人員の異動があっても対応しやすくなります。
例えば、顧客とのやり取りや進捗状況をCRM(顧客関係管理)ツールで管理すると、チーム内で情報をリアルタイムに確認できるようになります。これにより、特定の担当者しかわからない「ブラックボックス化した業務」が減り、代替要員でもスムーズに引き継ぎができるのです。
保険業界でDXを進める際、ただシステムを導入するだけでは真の働き方改革にはつながりません。重要なのは、自社の業務フローを見直し、どのようにテクノロジーを活用するかを段階的に考えながら進めていくことです。
ここでは、働き方改革につながる保険DXの進め方を7つのステップに分けて解説します。
DXを成功させるためには、まず自社の現状を正確に把握する必要があります。闇雲にシステムを導入しても、業務の実態に合っていなければ逆効果になりかねません。
例えば、「どの業務に時間がかかっているのか」「どのプロセスでミスが多いのか」「情報共有がスムーズにいっていない部分はどこか」など、具体的な課題を明確にしておくことが大切です。これにより改善が必要なポイントが可視化され、後続のステップにおいて的確な対策を立てやすくなります。
また現場の声を取り入れることも重要です。現場で実際に業務を担っている社員からの意見を集めると、課題の本質に迫れます。ヒアリングやアンケートを通じて多角的に課題を抽出し、改善の出発点を定めていきましょう。
課題の洗い出しができたら、次に行うべきは「DXによって解決できる業務」を選ぶことです。すべての業務がデジタル化に適しているとは限らないため、効果が見込める部分から優先的に着手する必要があります。
例えば紙ベースで管理されている申込書や契約書の処理は、電子化によって処理速度と精度が向上します。また、手動で行っていた顧客対応の一部をチャットボットで対応すると、時間短縮と担当者の負担軽減を図れるでしょう。
この選定作業では、コスト面や業務への影響度を総合的に評価し改善効果の高い業務を見極める視点が求められます。デジタル化が「目的」ではなく「手段」であることを忘れずに、具体的な成果が期待できる分野にリソースを集中させましょう。
改善対象となる業務が決まったら、すぐにすべてを一度に改革しようとするのではなく、優先順位を明確にした上で、段階的に着手することが重要です。段階的な推進により、現場の混乱を防ぎ、安定した移行が可能になります。
まずは社内資料の共有方法をクラウド化するなど、影響範囲が限定的で推進のハードルが低い業務からスタートするのが効果的です。その後、基幹業務へのDX適用を進めていくと社員の理解と習熟度が高まり、自然と全社的な改革へとつながっていきます。
このステップでは「スモールスタート・スケーラブル導入」の考え方が有効です。初期段階で成功体験を積むことで現場の抵抗感を減らし、プロジェクト全体を円滑に進めやすくなるでしょう。
改革の準備が整った段階で、具体的なツールやシステムの導入に移ります。ここで選択肢となるのが、クラウド型の業務支援ツール・RPA・AIチャットボットなどです。これらのテクノロジーを活用すると、業務効率を劇的に向上させられるのです。
例えば、顧客情報をクラウドで一元管理すると営業・事務・カスタマーサポート間の情報連携がスムーズになり、二重入力や確認ミスを防止できます。また、RPAを導入すれば定型的なデータ入力や帳票作成業務を自動化でき、担当者はより付加価値の高い業務に集中できます。
導入に際しては、自社の業務フローに適合したツールを選定することが大切です。機能の豊富さだけでなく、操作性やカスタマイズ性、サポート体制も考慮し長期的に活用できるツールを選びましょう。
ツールを導入しただけでは、真の働き方改革は実現しません。実際に業務にツールを取り入れる際には、社員の多様な働き方を考慮した運用設計が求められます。
例えば日報や報告書をチャットツール上で提出する仕組みにすると、出社せずとも業務報告が可能になります。一方で対面でのコミュニケーションが必要な業務には、定期的なオンライン会議やハイブリッド出社体制を導入することも有効です。
このように、DXを活用しながらも、社員一人ひとりの働き方や価値観に寄り添った制度設計を行うことでツールの定着率が高まり、働きやすい環境づくりが実現します。
運用を開始した後に重要になるのが、明確なルール作りとその徹底です。新しいシステムが導入された直後は使い方のばらつきや混乱が生じやすいため、統一された運用方針を示す必要があります。
例えば、情報の保存ルールやアクセス権限、定型業務のフローなどをマニュアル化し、全社員が同じ基準で運用できるようにしましょう。また、操作トレーニングやQ&Aセッションなどを設けて、実務レベルでの習熟度を高めることも大切です。
ルールが明確であるほど属人的な業務が減り、組織全体の柔軟性と再現性が向上します。ツールの運用はあくまで「仕組み」であり、仕組みを活かすのは「人」です。だからこそ、組織的な理解と協力体制が求められます。
最後に、DXによる効果を定期的に評価し、必要に応じて改善を行うプロセスを取り入れることが継続的な改革のポイントとなります。一度推進して終わりではなく、PDCAサイクルを回しながら取り組む姿勢が求められます。
例えば、DX推進後に「残業時間がどれだけ削減されたか」「社員の満足度がどう変化したか」「顧客対応のスピードや品質が向上したか」といった観点で数値を分析し、成果を可視化しましょう。それによって、次の改善アクションを明確に定められるのです。
また、現場からのフィードバックも積極的に取り入れましょう。現場で実際に使用している社員の声には改善のヒントが数多く含まれています。フィードバックの収集と反映をルール化し、柔軟に対応する姿勢がDXの成熟度を高めていきます。

保険業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は単なる業務効率化にとどまらず、社員一人ひとりの働き方そのものを見直す大きなきっかけとなっています。
ここでは、実際にDXを通じて働き方改革を進めた5社の事例を紹介し、それぞれのアプローチや成果について解説します。
営業職の業務効率向上を目的に、明治安田生命は2017年に「MYリンクステーション」という営業支援システムを導入しました。この取り組みのポイントは、ペーパーレス化と情報共有のスピードアップです。
例えば、これまで紙ベースで行われていた顧客情報の管理や提案資料の作成が、すべてタブレット端末で完結できるようになりました。これにより営業担当者は外出先でもリアルタイムに顧客対応が可能になり、業務の生産性が向上しています。
さらに、システムの導入により事務作業にかかる時間を削減できたため、社員の残業時間が抑制され、ワークライフバランスの改善にもつながっています。
参考:明治安田生命保険相互会社
東京海上日動では、2019年からAIを活用した保険金査定支援システムを導入しています。この施策は、保険金請求処理の迅速化と査定業務の質の向上を同時に実現することが狙いです。
このシステムには、交通事故の写真や診断書のデータをAIが解析し、事故の状況や損害の程度を自動で判断する機能が組み込まれています。これにより査定担当者の作業負担が軽減され、より迅速な保険金の支払いが可能になっています。
また、属人的になりがちな査定業務に一定の基準が生まれることで、業務の標準化にもつながり、新人社員でも一定の品質を保った対応がしやすくなりました。
SOMPOホールディングスは働き方改革を本格的に進めるために、リモートワークの制度化とデジタル研修の導入を積極的に行っています。これは、社員の多様な働き方を尊重しながら、学び続ける環境を整備する取り組みです。
全国どこにいても業務が可能になるように、リモートアクセス環境の整備やペーパーレス会議の推進が行われました。これにより、通勤時間の削減や育児・介護との両立がしやすくなっています。
加えて、eラーニングを中心としたデジタル研修プログラムも整備され、社員は自分のペースでスキルアップができるようになりました。これらの取り組みは、働きがいの向上と人材育成の両立を実現する好例といえるでしょう。
第一生命では、定型的で反復性の高い業務に対してRPA(Robotic Process Automation)の導入を進めています。狙いは、業務の自動化を通じて人手不足の解消と社員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることです。
実際に、請求書処理や顧客データの入力作業といった事務業務がRPAで自動化され、これまで人の手で行っていた作業の多くが短時間で正確に処理されるようになりました。
これにより、社員の残業時間が減り、ミスの削減や業務スピードの向上が実現されています。また、RPA導入にあたっては、現場の声を反映しながら改善を重ねることで、より実務に即した運用が可能になっています。
参考:第一生命保険株式会社
住友生命では、2020年以降の急速な社会変化を受けてモバイルワーク制度と電子契約の導入を加速させました。これにより、時間や場所に縛られない柔軟な働き方を実現しています。
例えば、営業職が外出先からタブレットを使って契約手続きを行えるようになり、訪問回数の削減と契約スピードの向上が図られました。さらに、ペーパーレス化が進んだことで、書類の保管や輸送コストも削減されています。
このように、DXによって業務のあり方そのものが変わり、社員のストレスや負担が軽減された結果、顧客対応の質も向上しています。働き方とサービス品質の両立を実現した好例です。
参考:住友生命保険相互会社
働き方改革を推進する上で、企業にとって課題となりやすいのが初期費用の確保です。こうした課題をサポートするために、厚生労働省では「働き方改革推進支援助成金」という制度を用意しています。これは、労働時間の短縮やテレワーク導入などに取り組む中小企業に対して必要な費用の一部を助成する制度です。
この助成金には複数のコースが存在しており、それぞれ対象となる取り組みが異なります。例えば「労働時間短縮・年休促進支援コース」では、就業規則の見直しや労務管理システムの導入費用が助成対象となります。また、「テレワークコース」では、PCや通信機器の購入費用、クラウドツールの利用料なども支援対象です。
申請には事前の計画書提出や実施報告が求められるため、導入前から計画的に準備することが重要です。専門家のアドバイスを受けながら進めると、スムーズに申請・受給が可能になります。こうした制度を上手に活用すると、保険DXによる働き方改革をより確実に、かつ費用を抑えて実現できるでしょう。
参考:厚生労働省
保険業界におけるデジタル化の流れは、年々加速しています。DXを通じて業務効率を高め、社員の働きやすい環境を整えることは今や多くの企業にとって急務となっています。しかし、どの技術をどの業務に導入すべきか、また社員への教育や社内体制の整備など、実行フェーズでの課題も少なくありません。
このような課題を感じている企業様には、保険DXの知見と実績を持つ『株式会社 TWOSTONE&Sons』へご相談ください。当社では、業界特有の業務フローや組織体制に精通した専門スタッフがお客様の課題を丁寧にヒアリングし、最適なソリューションをご提案いたします。

保険DXは単なる業務効率化の手段ではなく、社員の働きやすさを支え、企業の持続的成長を支援する重要な戦略です。営業支援システムやAI・RPA・電子契約といった先進技術の導入によって定型業務の削減やリモートワークの実現が進み、より柔軟な働き方が可能となります。
また、国の助成金制度を活用すると、初期コストの負担を軽減しながら計画的に改革を進められます。重要なのは、将来を見据えて早めに準備を開始することです。現状を正しく把握し、自社に最適なDX戦略を立てることが、成果へとつながります。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』ではこうした一連のプロセスを伴走しながら支援しています。ぜひ、働き方改革の第一歩として、保険DXの推進をご検討ください。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
