保険DX推進に必須なコンプライアンス対策|内部統制と監査のデジタル化
保険

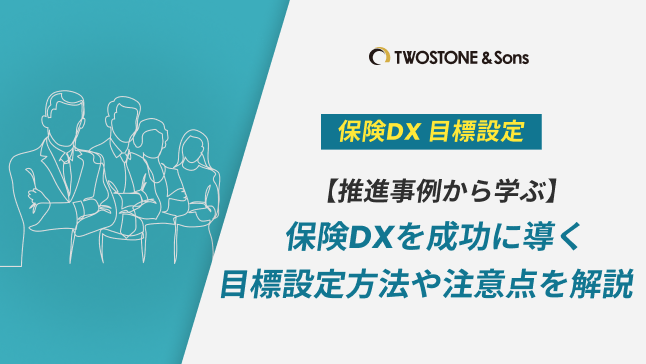
保険DX推進では、的確な目標設定が非常に重要です。本記事では、具体的な数値目標の立て方や社内での効果的な共有方法、優先順位の整理方法など、保険業界で活用できる実践的な考え方とポイントをわかりやすくご紹介しています。
保険業界におけるデジタル化の波は、もはや避けては通れない現実です。しかし、「DXを進めよう」と方針を掲げただけでは実際の現場が動かず、思うように効果を感じられないという企業も少なくありません。特に、DX推進における目標設定が曖昧だとプロジェクト全体の軸がぶれてしまい、推進効果が不明確になる恐れがあります。
本記事では、「保険DXを成功させたいが、どこから手をつけるべきかわからない」と感じている担当者や経営層に向けて、目標設定の重要性と注意点など事例を交えて丁寧に解説します。記事を読むことで、目標設定の基本的な考え方から組織に与える影響、そして最終的にDXを円滑に推進するための視点を得られるでしょう。

デジタル技術の活用は、業務効率化や顧客体験の向上など保険業界に新たな可能性をもたらします。しかし、その成功には「どこを目指すか」という明確な目標が欠かせません。保険DXは単なるITツールの導入ではなく、企業の業務や文化、体制までも見直す大規模な取り組みです。そのため、推進初期から目標を設定することで関係者全体が同じ方向を向き、プロジェクトを一貫して進められるのです。
保険DXとは、保険業務においてデジタル技術を活用して従来のビジネスモデルを抜本的に変革していく取り組みです。これは単にペーパーレスを実現するというレベルではなく、顧客接点の強化や新しい商品開発、契約手続きのオンライン化、さらにはリスク予測や保険料設計へのAI活用などを包括的に含みます。
実際に、チャットボットを活用して24時間顧客対応を実現したり、契約書を電子化して郵送の手間を省いたりすることでユーザーの利便性を向上させる企業も増えています。こうした変革を進めるためには、単なる技術導入に留まらず企業全体の意識改革や業務フローの見直しも不可欠なのです。
保険DXを成功させるためには、「何のためにDXを行うのか」「どのような姿を目指すのか」という目的を明確にし、そこに至るための具体的な目標を設ける必要があります。
ここでは、その理由を3つの観点から見ていきましょう。
第一に、明確な目標を設定すると、組織全体の方向性を揃えられます。DXは一部の部署だけで完結する取り組みではありません。営業部門・カスタマーサポート・商品開発・バックオフィスなどさまざまな部門が関与し、それぞれの業務の中で新しいアプローチが求められます。
例えば、「3年後に新規契約の80%をオンライン完結型に移行する」という目標があれば、それに向けて各部署が何をすべきかが明確になります。営業はオンライン商談のノウハウを蓄積し、IT部門は安定した契約システムの構築を進め、カスタマーサポートはリモートでの対応体制を整えるといった具合に、全体として統一感のあるDXが進行するのです。
このように目標が組織全体の「共通言語」となり、社内での連携をスムーズにするのです。
次に、DXの進捗管理においても、目標は大きな意味を持ちます。目標がなければ何がどれだけ達成できているのかが見えにくくなり、関係者全員の納得感や手応えが得られにくくなります。
例えば「ペーパーレス率90%の達成」「顧客対応にかかる平均時間を30%削減」など具体的な数値目標を設定すると、定期的な評価と軌道修正が可能になるでしょう。目標を基にKPI(重要業績評価指標)を設定すると、担当者が日々の業務の中で意識するポイントが明確になるのです。
進捗が可視化されることにより、プロジェクトがどこまで進んでいるのか、何が足りないのかを全員で共有できる環境が整います。これは、結果としてプロジェクト全体の透明性を高めることにもつながります。
目標は、チームの士気やモチベーションにも影響します。人は成果が見えることで達成感を得やすくなり、さらなる努力を重ねようとする傾向があります。これは、特に長期的なプロジェクトであるDX推進において重要な要素です。
例えば、「半年以内に社内の契約プロセスをデジタル化し、業務時間を20%短縮する」といった短期目標を設定すると、チームメンバーは明確なゴールに向かって集中して動きやすくなります。そして達成した際には、その成功体験が次のフェーズへの原動力になるでしょう。
また、定期的な目標レビューを行うことで成功した点や課題を共有できるため、チーム内でのコミュニケーションや相互理解も深まり、持続的なモチベーション維持が期待できます。
保険DXを推進するにあたり、何をゴールとするか明確に定めることが成功への第一歩です。抽象的な方針だけではなく、実現可能で測定可能な具体的な目標を設定すると、組織内の動きが具体化し、プロジェクト全体が加速するでしょう。
ここでは、現場でよく設定される代表的な目標を5つ紹介します。
保険DXの代表的な目標の1つが、業務効率化の達成です。特にバックオフィス業務における手作業の削減や契約処理、請求管理などの自動化が中心となります。
例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入し、保険金の支払い処理にかかる時間を従来の半分以下に短縮する取り組みが挙げられます。これにより業務に従事する社員の負担を軽減できるだけでなく、ヒューマンエラーの減少にもつながるのです。
また、業務効率化の効果を定量的に把握するためには、処理件数あたりの工数や時間、コストを明確に数値化し、それを目標に設定することが重要です。数値目標があることで、プロジェクトの進捗管理もより正確になります。
デジタル化は、顧客体験の向上にも直結します。顧客満足度を高めるための目標設定も保険DXにおいて欠かせません。
例えば、スマートフォンから簡単に契約内容を確認できるマイページ機能やチャットボットによる24時間対応のサポート体制を整備する取り組みがあります。こうした施策により、顧客の利便性が高まり、契約継続率やロイヤルティの向上が見込まれるでしょう。
さらに、CS(Customer Satisfaction)スコアの導入やNPS(Net Promoter Score)といった顧客満足度を測定する指標を用いて、定期的に評価を行うこともポイントです。数値によって成果を見える化することで、次の施策の改善にも役立ちます。
DXを推進するには、技術導入だけでは不十分です。実際に現場でそれを活用できる人材の育成が重要になります。
例えば内製化を進めるために、社員向けにプログラミングやデータ分析、DXマインドに関する研修を導入する企業も増えています。また、外部の専門家と連携して実践的なワークショップを開催すると、単なる知識の習得ではなく、実務への応用力を養う機会も提供できるでしょう。
人材育成の効果を測るには、研修受講後の社内資格試験の合格率や実際のプロジェクトへの参画数、ツールの活用頻度など具体的な指標を活用すると有効です。これにより、育成プログラムが単なる形式的な施策ではなく、実務成果につながるかどうかを客観的に評価できます。
保険業界における差別化要素の1つとして、新たなデジタル保険商品の開発が注目されています。顧客ニーズが多様化する中で、従来の定型的な保険商品では対応しきれない場面も多くなっています。
例えば、IoTを活用した健康管理アプリと連動する健康増進型保険や走行距離に応じて保険料が変動するテレマティクス保険などがその代表です。こうした商品の開発には、顧客行動データの収集と分析が欠かせません。
新商品の開発目標を明確にするには、開発完了までのスケジュール設定・開発コスト・発売後の契約件数などを指標として設定するのが効果的です。また、ユーザーからのフィードバックを受け取る仕組みを整備し、発売後も継続的に改善していく体制づくりも求められます。
DXの推進には初期投資が必要ですが、その効果を明確に示すことで経営層の理解と協力を得やすくなります。そのため、コスト削減に関する目標設定も重要です。
例えば、紙ベースの契約書を電子契約に移行すると印刷費・郵送費・保管コストを年間数百万円規模で削減できる場合があります。あるいは、外部委託していた業務をRPAで内製化し、人件費を抑えるといった事例もあります。
こうしたコスト削減効果を可視化するためには、「どの工程でどれだけ削減できたか」「前年比で何%コストを抑えられたか」など具体的な数値を継続的にモニタリングする仕組みが必要です。数字に裏付けられた実績があれば、社内の他部門への展開もスムーズに進めやすくなります。

保険業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は単なるITの導入にとどまらず、企業全体の構造改革や顧客との関係性の再構築を含みます。各企業がそれぞれの強みや課題を踏まえ、明確な目標を掲げながら取り組みを進めている点が特徴です。
ここでは、主要保険会社が実際に設定したDXの目標とそれに基づく具体的な戦略を紹介します。
東京海上日動火災保険は、「人の力」と「デジタル技術」の融合を目指したDX戦略を推進しています。背景には、保険契約者の多様化とサービスの高度化が求められている現状があります。
同社は、営業担当者が持つ専門知識や信頼関係とAIによる事故対応の迅速化を組み合わせることでサービスの質を高めてきました。例えば、事故受付から損害査定、保険金支払いまでのプロセスをデジタル化する一方で、顧客対応の場面では担当者が丁寧なサポートを提供しています。
その結果、顧客満足度の向上と業務の効率化を両立させ、継続的な契約維持やクロスセルの拡大を実現しています。今後も「人とデジタルの最適な協働」により、顧客接点の質を高める方針です。
SOMPOホールディングスは、データドリブンな経営の実現をDXの中心に据えています。保険会社が蓄積する膨大な契約情報や事故データを活用し、新たな価値を創出することを目的としています。
同社では、グループ全体で活用できる共通データ基盤を整備し、これによりAIやアナリティクスの活用が容易になりました。例えば、リスク予測や保険引受の精度向上、商品開発のスピードアップにデータを活用したのです。
また、CDO(Chief Digital Officer)を中心とする体制を構築し、全社横断的にDX施策を展開しました。こうしたデジタル戦略の深化は顧客ニーズの変化に柔軟に対応する基盤となり、競争力の強化にもつながっています。
第一生命ホールディングスは「人に寄り添うDX」をスローガンに掲げ、個別最適化されたサービスの提供を目指しています。背景には、高齢化やライフスタイルの多様化により保険ニーズがより細分化されている現状があります。
同社は、顧客ごとの健康状態やライフプランに応じた保険提案を可能にするAIアドバイザーや健康増進をサポートするアプリの導入を進めました。健康データの連携により、日々の行動改善を促す保険商品を提供しています。
これにより、単なる「もしも」の保障ではなく「いつも」寄り添う保険会社としての価値を提供できているのです。今後は、ウェアラブルデバイスとの連携や遠隔医療との協業など、さらなるサービスの高度化が期待されています。
住友生命では、「ウェルビーイング(心身の健康と社会的幸福)」の実現を軸にDXを展開しています。単なる保険提供を超え、生活全体をサポートする存在になることが目標です。
その一環として、健康増進アプリ「Vitality」を中核に据えたプラットフォームの構築を進めました。このアプリでは、日々の運動や健康診断の結果に応じて保険料が変動し、健康意識の向上を促します。歩数や運動量に応じてポイントが貯まり、提携先のサービスと交換できる仕組みも盛り込まれているのです。
こうした取り組みによって顧客との継続的な接点を創出し、ロイヤリティの向上を図っています。今後は、外部パートナーとの連携強化を通じて、サービスの幅をさらに広げる方針です。
参考:住友生命保険相互会社
あいおいニッセイ同和損保は、「防災・減災を通じた社会貢献」をDXの核に据えています。自然災害の頻発が保険事業に大きな影響を与えている現代において、事前のリスク予測と損害軽減は重要なテーマです。
同社は自治体や企業と連携しながら災害予測データを活用し、避難行動の促進や被害最小化のための情報発信を行っています。IoTセンサーを設置した地域においてはリアルタイムでの地震・風水害の状況把握が可能となり、迅速な対応を可能にしているのです。
また、災害後の被害調査や保険金支払いにもAIを活用し、業務の迅速化と顧客の不安軽減を両立させています。今後も「安心・安全な社会」の実現に向けて、デジタルの力を最大限活用していく構えです。
保険DXを成功に導くためには、単にデジタル技術を導入するだけでは十分とはいえません。最終的な成果を明確に意識し、その実現に向けた目標を適切に設定することが不可欠です。
ここでは、保険DXを推進する際に目標設定をどのような手順で進めていくべきかについて、6つのステップに分けて解説します。
まず重要なのは、自社の現在の業務プロセスやシステム環境にどのような課題があるのかを把握することです。これにより、DXを通じて「何を改善するのか」という焦点が明確になります。
例えば、顧客対応に関して時間がかかりすぎている、紙ベースの業務が多く非効率である、部署間で情報共有ができていないといった点が代表例です。
一方で、コールセンターの対応力が高い、営業現場のデジタル機器活用が進んでいるなど強みとなる資産も明確にする必要があります。
この段階では、業務フロー分析や顧客アンケート、社員ヒアリングなど定量・定性の両面からデータを集めることが効果的です。現状を可視化すると、目標設定に向けた土台が整うのです。
DXは全社的な取り組みとなるため、関係する部門や社員の意見を取り入れることが成功のカギとなります。現場の声を反映しなければ、実行段階で反発が起きたり現実離れした計画になったりする可能性があるためです。
IT部門が最新技術を導入したいと考えても、営業部門が現場での運用に不安を抱えていれば導入が進まないというケースもあります。経営層のビジョンと現場のニーズのすり合わせを行い、全社的に納得感のある目標を導き出しましょう。
ワークショップ形式の意見交換会や匿名で意見を募集できる社内アンケートなどを活用すると、さまざまな立場からの意見を効率的に収集できます。
目標は「現実的であると同時に、成長や変化を促すものでなければならない」という点が重要です。単なる現状維持ではなく、将来に向けての変革を実現できるような水準で目標を設定しましょう。
例えば「契約手続きのオンライン化率を1年以内に80%まで引き上げる」など、具体的な数値と期限を伴ったKPI(重要業績評価指標)を定めることが求められます。SMARTの法則(Specific・Measurable・Achievable・Relevant・Time-bound)に沿って目標を設計すると、進捗管理もしやすくなるでしょう。
また、「顧客満足度の向上」「営業職員の生産性向上」「データ活用の精度向上」など、定性的な指標についても数値化を工夫することで達成度をより明確に把握できるようになります。
目標を掲げたら、それを実現するための戦略や施策を具体的に検討する段階に入ります。このフェーズでは単に「システムを導入する」といった表面的な対応ではなく、業務プロセスの再設計や組織改革、スキル向上など多角的な視点で施策を組み立てていく必要があります。
例えば、オンライン契約の導入に向けては顧客向けの説明資料の整備、営業職員のIT研修、セキュリティ体制の強化などが必要になるでしょう。こうした複数の施策をロードマップとして可視化し、どの段階で何を実行するかを明示することで目標に向けた進行がスムーズになります。
施策は費用対効果も意識しながら実現可能性の高い順に優先順位をつけて実施計画を立てていくと、現場の混乱を避けながら改革を進めやすくなります。
施策を実行するには、適切な体制づくりが不可欠です。担当者や責任者を明確にし、プロジェクトマネジメントが機能するような構造を整えることで目標達成に向けた進捗を確実に管理できるでしょう。
例えば、社内にDX専任チームを設置し各部門からの代表者をアサインすると、部門間の連携がスムーズになります。また、定例会議を設けると、情報共有や課題解決が迅速に行える環境を整えられるでしょう。
スケジュールについても、短期・中期・長期に分けてマイルストーンを設定し段階的に成果を確認できるようにすると、関係者のモチベーション維持にもつながります。計画が一目でわかるガントチャートの作成なども効果的です。
目標設定と施策実行の後も計画が順調に進んでいるかを確認し、必要に応じて軌道修正を行うことが成功の秘訣です。DXは一度推進を始めたら完了するものではなく、常に変化し続けるものだからです。
例えば導入したシステムが現場で活用されていない場合、その原因を分析し、研修の追加やUIの改善などの対応が求められます。定期的なKPIレビューや進捗報告会を設けることで、問題の早期発見と対処が可能になります。
また外部環境の変化にも柔軟に対応できるように、半期ごとの戦略見直しなどアジャイル型のPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すことが重要です。変化を前提とした運用により、保険DXの取り組みを継続的に改善・進化させられるでしょう。
DX推進を効果的に進めるためには、現状分析や関係者の意見集約、スキル向上など各段階で適切なツールを活用することが重要です。特に目標設定フェーズでは、業務の可視化や意思疎通の円滑化が成功のカギとなります。
ここで紹介するツールは保険業界のDX推進においても応用しやすく、現場レベルでの課題把握や学習支援に役立つでしょう。
社内の声を的確に拾い上げるには、アンケートの活用が効果的です。Airメンバーシップ アンケートツールは、簡単な操作で社内アンケートを作成・集計できるサービスです。サービス導入の目的は、社員の現状認識やDXに対する理解度、業務に対する課題意識などを収集し、次のアクションにつなげることにあります。
例えば、DX推進の初期段階で「どの業務が非効率と感じられているか」や「どのようなスキル不足が障害となっているか」といった質問を設けると、現場の実態を具体的に可視化できます。その結果、目標設定に必要な前提情報が得られ、関係者の納得感も高まるのです。
参考:株式会社リクルート
DX推進においては、社員のスキル向上が避けて通れない課題です。Udemy Businessは、ビジネススキルやITスキルなど、幅広いオンライン講座を提供する法人向けの教育プラットフォームであり、保険会社における人材育成にも適しています。
例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やデータ分析、DXマネジメントといった専門分野に対応した講座を通じて、社員の学びを支援できるでしょう。受講状況や理解度を管理画面で把握できるため、目標設定における教育計画や人材配置にも反映しやすくなります。つまり、個々のスキルギャップを可視化してそれに応じた成長目標の設計が可能となるのです。
もう1つの支援ツールとして挙げられるのが、マクロミルが提供するQuestantです。このツールは自由度の高いアンケート作成とスピーディな分析機能が特長で、ユーザーインターフェースも直感的でわかりやすい点が魅力です。
このツールではDX施策を実施する前後で社内外にアンケートを行い、施策の効果や満足度を数値で把握できます。さらに、部署別や年代別など細かな分析も可能なため、組織ごとの課題や進捗状況を詳細に評価できます。こうした客観的データに基づいた目標設定は組織内での合意形成を促し、実行の精度を高める要因となるのです。
参考:株式会社マクロミル
DX推進の目標を効果的に定めるためには、いくつかの重要な視点を押さえる必要があります。目標が曖昧であったり現場と乖離していたりすると、実行段階での混乱やモチベーションの低下を招きかねません。
ここに挙げる4つのポイントは、保険業界におけるDX推進の成功率を高めるために欠かせない要素です。
最初に意識すべきは、実行可能で具体的な数値目標を立てることです。抽象的な理想像だけを掲げてしまうと、実際の業務プロセスへの落とし込みが難しくなります。そんな時は、「契約処理の電子化率を半年で80%に向上させる」「顧客対応時間を3割削減する」といった数値ベースの目標を設けましょう。
例えば、新たにCRM(顧客管理システム)を導入する場合は「導入後3ヶ月以内に50%以上の社員が日常業務で活用している状態を目指す」など、期間と定量指標を明確にすると、評価軸がブレずに取り組みを進められます。
どれほど優れた目標でも、共有が不十分であれば意味を持ちません。全社的に方向性を一致させるためには、経営層から現場の担当者まで一貫したメッセージの発信と丁寧な説明が求められます。特に、保険業界は部署ごとの業務内容が異なるため、目標の解釈にズレが生じやすい傾向があります。
例えばDX推進によって業務の自動化が進む場合、現場では「自分たちの役割が減るのではないか」という不安も生まれがちです。そうした懸念を払拭するためには、全社説明会やチームごとのワークショップなどを活用し、目標の背景や意義を丁寧に共有することが重要です。
限られたリソースの中で複数の目標を追う場合、どれを最優先とするかの判断が不可欠です。すべての課題に同時に取り組もうとすると結果として中途半端になり、成果が見えにくくなります。そのため、KPI(重要業績評価指標)を設定し段階的に達成していくアプローチが効果的です。
例えば、「紙媒体の業務削減」と「顧客満足度の向上」という2つの目標がある場合は、まずは業務効率化に集中し、それによって浮いたリソースを使って顧客対応の質を高める、という順序を明確にする必要があります。優先順位が明確であれば現場の判断もスムーズになり、組織全体としての一体感が生まれます。
DXは想定外の変化が多く、最初に設定した目標が途中で適切でなくなる場合もあります。そのため、目標には一定の柔軟性を持たせ、定期的な見直しを組み込む姿勢が求められます。PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回す体制を整えておくと、状況に応じた調整が可能になるでしょう。
例えば、導入予定だったシステムが想定よりも複雑で社員の理解が進まない場合は、いったん目標の達成時期を再設定し、研修期間を延長するなどの対策を講じる必要があります。最も避けたいのは、当初の目標に固執しすぎて現場の疲弊を招くことなのです。
目標設定はDX推進の基盤であり、その質がプロジェクト全体の成否を左右します。しかし、保険業界においては業務内容や規制、顧客ニーズが複雑であるため、的確な目標を策定するには専門的な知見が必要です。
『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、こうした業界特有の事情を踏まえた目標設定のご支援を行っております。自社のDX戦略に合った目標が見つからない、どのように数値化すべきか迷っているというご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。現場の声を取り入れた、実行可能かつ成果につながる目標設計をご提案いたします。

保険DXの推進において目標設定は単なる出発点ではなく、全体の戦略を方向づける重要なプロセスです。現実的かつ具体的な数値目標を立て、全社での共有と優先順位の明確化を図りながら柔軟な運用体制を整えることが求められます。
一方で、自社だけで最適な目標を設計するのは容易ではありません。だからこそ、外部の専門家の視点を取り入れることがプロジェクトの確実な前進につながります。保険DXを確実に成功へ導くために、自社の状況に即した目標設定から取り組みを始めてみましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
