保険DX推進に必須なコンプライアンス対策|内部統制と監査のデジタル化
保険

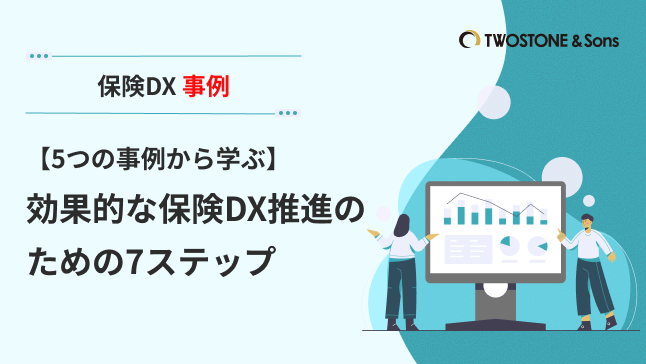
保険DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に役立つ事例と、その際に留意すべき重要なポイントについて紹介します。業務の効率化や顧客満足度の向上を目指す上で欠かせない目的の明確化や現場の声の反映など実践的な視点から解説しています。
現代の保険業界は、急速なデジタル化の波にさらされています。顧客のニーズは多様化し、サービスの迅速さや利便性が強く求められている一方で、従来の業務プロセスは複雑で非効率な部分も多く残っています。こうした環境の中で保険DX(デジタルトランスフォーメーション)を効果的に推進することは、競争力の維持・強化に欠かせない課題となりました。
この記事では、5つの具体的な事例から得られた知見を基に、保険DXを成功に導くための7つのステップを解説します。読み進めると、変化する市場に対応しながら効率化やサービス向上を実現するための具体的な方法と戦略を理解できるでしょう。
保険業界は今、大きな転換期を迎えています。長年にわたって紙の書類や対面営業を中心に発展してきた業界ですが、デジタル技術の進化により、従来のやり方では対応しきれない状況が生まれているためです。顧客はスマートフォンで即座に情報を得られる時代に慣れ、保険商品の申し込みや問い合わせにもスピーディーな対応を求めるようになりました。
一方で、多くの保険会社では依然としてレガシーシステムが稼働しており、業務効率の低下やコスト増加が課題となっています。こうした状況を打開するために、保険DXの推進が急務となっているといえるでしょう。
これまでの保険業務には、いくつかの構造的な問題が存在してきました。まず、契約手続きには大量の書類作成と押印が必要で、顧客は何度も書類に記入する手間を強いられてきました。また、営業担当者が顧客先を訪問して説明するスタイルが主流だったため、顧客の時間的な制約が大きな障壁となっていました。
さらに、契約情報や顧客データが複数のシステムに分散して管理されており、情報の一元化が困難な状態が続いてきました。保険金の支払い査定においても、人手による確認作業が中心で、処理に時間がかかるケースが少なくありません。
加えて、既存システムの老朽化により、新しいサービスの開発や他社システムとの連携が難しくなっているという課題もあります。こうした限界が、顧客満足度の低下や業務コストの増加につながっているといえるでしょう。
顧客のニーズは、デジタル化の波とともに劇的に変わってきています。特に若い世代を中心に、保険の加入手続きをオンラインで完結させたいという要望が高まっており、わざわざ店舗に足を運んだり営業担当者と日程調整したりする手間を避けたいと考える人が増えています。スマートフォンのアプリで契約内容を確認したり、チャットボットで気軽に質問したりできる環境を求める声も強まっている状況です。
さらに、他の金融サービスと同様に、保険でも即座に見積もりを取得し、リアルタイムで比較検討できる仕組みが期待されています。保険金請求の際にも、書類を郵送するのではなく、スマートフォンで写真を撮って送信するだけで手続きが進むような利便性を望む顧客が多くなりました。従来の方法に固執していては、こうした期待に応えられず、顧客離れを招くリスクが高まっているといえます。

保険DXとは、保険業務におけるデジタル技術の導入と活用を通じて業務プロセスの革新や顧客体験の向上を図る取り組みを指します。単にITシステムを導入するだけでなく、業務の根幹から見直し、デジタル技術によって保険商品の設計や販売、契約管理、事故対応までを最適化することが目標です。
データ分析やAI・クラウドサービス・チャットボットなど、多彩な技術を融合させることで従来の業務の枠組みを超えた新しい価値を生み出す取り組みです。保険DXは単なる効率化手段ではなく、企業が顧客に提供する価値そのものを進化させる戦略的な変革といえます。
保険業界がデジタル化を急ぐ背景には、顧客の期待変化や業務の非効率、人手不足など複数の課題があります。これらの要素を理解することで、DX推進の重要性と対応すべきポイントが明確になるでしょう。
スマートフォンやデジタルサービスの普及により、消費者は日常的にオンライン上で迅速かつ簡便な手続きを期待するようになっています。保険商品においても、契約の申し込みから問い合わせ対応、保険金の請求までをデジタルで完結させたいというニーズが顕著になっています。
そのため、Web上での保険料シミュレーションや申込完了機能、AIチャットボットによる常時対応のカスタマーサポートといったサービスは、競争優位性を高めるカギなのです。これらを実装できない企業は、ユーザーの離反リスクに直面することになります。顧客接点の最適化は、保険DXにおける重要な戦略課題の1つであるといえるでしょう。
従来の保険業務では、紙ベースの契約処理や人手による審査業務、事故対応などが大きな比重を占めており、時間と労力の面で多くの課題を抱えてきました。こうした手法はミスの発生や処理の遅延を招きやすく、組織全体の生産性を低下させてしまいます。
近年ではAIによる書類内容の自動認識や自動審査システムの導入により、業務の正確性とスピードの両立が可能となってきました。さらに、クラウドベースの業務管理ツールを活用することで社内の情報共有がリアルタイムで行えるようになり、部門間連携がスムーズに進みます。こうした改善は単なる効率化にとどまらず、企業資源の最適配置を促進するという面でも有効です。
保険業界では、従業員の高齢化や若年層の採用難により慢性的な人手不足が深刻化しています。このような状況は、顧客対応の遅延やサービスレベルの低下につながりかねず、現場の業務負担も年々増しているのです。
その解決策として、AIチャットボットや音声応答システムの活用が注目されています。これらのツールを導入することで定型的な問い合わせ対応は自動化され、限られた人員がより専門性の高い業務に専念できる環境が整います。結果として、対応の質を落とすことなく業務効率を高めることが可能になるのです。
デジタル技術の積極的な活用は単なる業務支援にとどまらず、慢性的な人材不足という構造的課題を緩和する手段となり得ます。人にしかできない対応力とテクノロジーの補完関係を築くことで、持続的なサービス提供体制を確立することが期待されます。
保険DXを推進すると、単に最新の技術を導入するだけにとどまらず、業界全体に大きなメリットがもたらされます。顧客満足度の向上やコスト削減、業務の効率化など多方面で効果が現れるためです。これらのメリットを事前に理解することで、なぜDXが今後の保険業界に不可欠なのかがより明確になるでしょう。
ここでは主要な5つのメリットを具体的に解説します。
保険DXの本質的な価値の1つは、顧客との接点における体験をいかに向上させるかにあります。現代の顧客はスピーディかつ正確な応対を当然のように求めており、それに応えられない企業は選ばれにくくなっているのです。
そこでAIチャットボットを導入すると、保険契約の内容確認や請求手続きなど、くある問い合わせに即座に対応できるようになります。24時間365日利用可能な環境は、顧客にとって非常に利便性が高く、利用満足度を押し上げる要因となるでしょう。
さらに、CRM(顧客関係管理)システムと連携することで個々の契約者の履歴情報をもとに最適な対応が可能となり、パーソナライズされた体験が実現します。こうした取り組みは顧客の信頼獲得に直結し、結果として企業に対するロイヤルティ向上にも貢献するのです。
保険業界では、申込書の処理や手入力による登録作業など、反復的で人手に頼る業務が数多く存在してきました。こうした作業は人的エラーのリスクが高く、生産性の足かせともなってきたのが現状です。
そこで有効なのが、OCR(光学文字認識)とAIを組み合わせた業務自動化です。紙媒体で提出された書類をOCRで読み取り、AIが内容を自動仕分け・データ化することで、これまで人が担っていた作業を効率化できます。
この自動化により処理時間が短縮されるだけでなく、人的ミスの削減にもつながり、業務全体の品質が向上します。また、ペーパーレス化によって保管スペースや印刷関連コストも削減され、企業のコスト構造自体を見直すきっかけにもなるでしょう。
保険業務は多岐にわたり、審査基準や対応手順も複雑です。従来のやり方では経験豊富な担当者に依存する属人化が起きやすく、担当者の退職や異動によって業務が滞るリスクが存在しました。
そこで、デジタル化により審査フローや対応マニュアルをシステム化し、標準化を進めれば誰が担当しても一定の品質を保てるようになるでしょう。ワークフローの自動化やルールベースの判断支援により判断基準が明確化されるため、属人化のリスクが軽減します。これにより業務の安定化が図られ、組織としての強靭さを高められるのです。
デジタル化された顧客情報や契約データは、これまで活用しきれなかった貴重な資産です。保険DXによりこれらのデータを一元管理し、高度な分析を行う環境が整うと新たな商品開発やマーケティング戦略が進展します。実際に顧客のライフスタイルや健康状態をリアルタイムに把握できるウェアラブルデバイスのデータを取り込み、個別のリスクに応じたカスタマイズ保険を提供する事例が増えています。
このようなデータドリブンの保険商品は顧客のニーズにピンポイントで応えられるため、結果として競争力が高まるのです。また、リスク管理の精度向上により保険料の設定もより公平かつ合理的に行えるというメリットもあります。
デジタル化が進む中で、保険会社の競争環境は激化しています。保険DXを推進して業務効率や顧客サービスの質を向上させた企業は、市場での優位性を確実に築けるでしょう。
例えば、迅速かつ正確な契約手続きや保険金支払い対応を実現できれば顧客からの信頼が高まり、口コミやリピートにつながります。また、新しいサービスや商品の投入スピードも向上し競合他社よりも先手を打てるため、顧客獲得のチャンスを増やせます。さらに、業務効率化によるコスト削減で利益率も改善され、財務面でも強化されるのです。
これらの効果により、自社の持続的な成長が見込めるでしょう。
保険DXの実践には多様なアプローチがあります。日本の主要な保険会社はそれぞれの強みを活かしながら独自の技術導入を進め、業務改革や顧客サービスの向上を実現しているのです。
ここでは、具体的な5社の事例を通じて、DXの取り組み内容や効果を詳しく紹介します。これらの成功例から、自社のDX推進に活かせるヒントが得られるでしょう。
明治安田生命保険相互会社では、契約書類の処理業務を抜本的に見直すため、AI-OCR(人工知能を搭載した光学文字認識)技術の導入を積極的に進めています。従来の保険契約書類は手書きの申込書や異なる様式の書類が混在しており、人の手による入力作業には膨大な時間と労力を要していました。さらに、読み取りミスや入力ミスといったヒューマンエラーも避けられず、業務全体の効率化に課題がありました。
そこで同社は、手書き文字や印刷文字を高精度で読み取ることが可能なAI-OCR技術を導入しました。この技術は、従来読み取りが難しかった非定型の書類にも対応可能で、入力作業の自動化を実現しています。特に、複雑な保険商品においても情報を正確にデジタルデータへ変換できるため、書類の処理スピードが向上しました。これまで数分かかっていた入力作業が数十秒で完了するようになり、業務全体の生産性が改善されています。
この取り組みにより社員は単純作業から解放され、顧客へのコンサルティングや複雑な案件対応に集中できる体制が整いました。
出典参照:デジタル技術を活用した保険金・給付金請求におけるお客さま体験価値(CX) の向上について|明治安田生命保険相互会社
アフラック生命は「ADaaS」と呼ばれる独自のデジタルサービス基盤を構築し、顧客対応の全体最適化を目指しています。ADaaSはチャットボットや音声認識技術を組み合わせ、顧客からの問い合わせに自動で応答可能な体制を実現しています。
例えば、保険商品の内容確認や契約内容の変更手続き、保険金請求に関する質問などを24時間いつでも対応できるようになりました。これにより顧客の利便性が向上し、問い合わせのピーク時にも迅速な対応が可能になりました。
また、対応履歴をAIが分析することで、よくある質問の改善や新たなサービス開発にもつなげています。ADaaSは保険会社と顧客の接点を増やし、デジタルチャネルでの信頼構築に貢献しているのです。
出典参照:ADaaS ― Aflac Digital as a Service ― の開始について |アフラック生命保険株式会社
第一生命はビッグデータ解析を活用し、保険リスクの評価精度を高める取り組みを進めています。多様なデータソースから得られる顧客の健康情報や生活習慣、過去の保険請求データなどを統合解析することで、より詳細かつ個別のリスクを把握しているのです。
例えば、特定の疾患リスクが高い顧客を早期に特定し、予防医療の提案や適切な保険商品を案内できるようになりました。この解析により保険金支払いの適正化が進み、リスクの偏りを抑えつつ顧客には必要な保障を提供できるようになったのです。
さらに、こうした精密なリスク評価は新商品の設計にも役立ち、顧客ニーズにマッチした保険商品の開発を加速させています。ビッグデータの活用は保険業界に新たな価値創造の可能性を示しています。
出典参照:第一生命と日立が「医療ビッグデータ」活用の共同研究を開始|株式会社 日立製作所
日本生命保険相互会社では、顧客満足度の向上と業務効率の両立を目的にチャットボットの導入による24時間対応のサポート体制を整備しています。従来、保険に関する問い合わせは営業時間内に限られており、利用者のタイミングに応じた対応が難しいという課題がありました。そこで、時間や曜日を問わず対応できる体制の構築が求められていたのです。
このニーズに応える形で導入されたのがAIを活用した自然言語処理技術によるチャットボットです。このチャットボットは単なるFAQの自動回答にとどまらず、契約内容の照会や手続きの進め方、保険金請求のステップといった多岐にわたる質問に柔軟に対応可能です。ユーザーが入力した内容を理解し、最適な情報をリアルタイムで提供することができるため、顧客はわざわざコールセンターに電話をかける必要がなくなり、気軽に保険に関する相談ができるようになりました。
損害保険ジャパンはクラウド技術を活用し、業務プロセスの標準化と効率化を進めています。クラウド基盤の導入により、各支店や部門間の情報共有がリアルタイムで可能になりました。このクラウドの導入によって事故受付から保険金支払いまでのプロセスをシステムで一元管理し、ステータスの可視化と自動化を実現したのです。これにより、作業の二重チェックや手戻りを減らし、全体の処理スピードがアップしました。
さらに、標準化によりどの拠点でも均一なサービス品質を確保し、属人化によるリスクを低減しています。クラウド基盤を土台としたDX推進は、変化する市場ニーズに迅速に対応できる柔軟な組織運営を支えているのです。
出典参照:損害保険ジャパン、Gemini Code Assist 導入で開発スピードアップ!~内製化で DX を加速~ |グーグル合同会社
保険DXの成功は単に最新技術を導入すれば達成できるものではありません。企業の業務プロセスや組織文化に深く根差した課題を整理し、計画的かつ段階的に取り組むことが重要です。前述の企業事例からも見られたように、各社が自社の実態に即したアプローチでDXを進めています。
そこで、ここでは保険DXを効果的に推進するために欠かせない7つのステップを解説します。これらのステップを順に踏むことでDXの推進がスムーズになり、持続可能な変革が実現できるでしょう。
最初のステップは、自社の業務内容を詳細に洗い出し、現状を可視化することです。保険業務は契約受付、審査・保全・保険金支払い・顧客対応など多岐にわたりますが、それぞれの業務がどのように実施されているかを明確にしなければなりません。
例えば、どの業務で手作業が多いのか、どこに時間がかかっているか、情報の流れはどうなっているかをマッピングします。こうした可視化は課題抽出の土台となるため、現場の担当者や管理者からのヒアリングや実際の業務観察も含めて実施すると効果的です。現状を正確に把握できなければ的確な改善策を立てられないため、この段階での丁寧な分析がDX成功のカギを握ります。
業務の全体像が見えたら課題や非効率を洗い出し、詳細に分析します。例えば、書類の手入力が多くミスが頻発している、情報共有が遅延している、顧客対応に時間がかかっているなど具体的な問題点をリストアップします。
さらに、課題の背景にある原因を掘り下げることも重要です。手作業の多さがシステムの不整備によるものか、担当者のスキル不足なのか、顧客情報の管理方法に問題があるのかなど多角的に分析します。この分析により、どの課題にどのような手段が最適か把握できるため、対策の選定もスムーズに進むでしょう。
課題分析を踏まえ、デジタル化すべき業務領域に優先順位をつけて整理します。すべての業務を一度にデジタル化するのは現実的ではなく、コストやリソースの観点から段階的な推進を行いましょう。
例えば、契約書類のデジタル化や顧客問い合わせ対応の自動化は、効率化効果が高く比較的始めやすい領域として優先されます。逆に、複雑なリスク評価モデルの刷新や基幹システムの全面改修はコストも期間もかかるため、長期計画の一部に組み込みます。
優先順位は、業務インパクトの大きさ、技術的実現可能性、社内の受容性などを総合的に判断して決めると効果的です。この段階で明確なロードマップを策定することがDX成功に直結するでしょう。
優先順位が決まれば、それに沿って具体的にどのツールや技術を導入するか計画を立てます。例えば、AI-OCRで契約書類の読み取りを自動化したりチャットボットで顧客対応の24時間体制を構築したりする場合、それぞれのツールの機能、導入コスト、運用負担を検討します。
技術選定にあたっては、自社の既存システムとの連携性やセキュリティ要件も重要な判断材料です。クラウド基盤を活用する際は、情報漏えいリスクを最小限に抑えるための対策が必須です。また最新技術だけでなく、業務の実態に最適化されたソリューションかどうかも重視しましょう。導入計画は具体的なスケジュールと予算を明確にし、関係部署と連携しながら策定します。
技術導入計画と並行して、DXを推進するための組織体制を整備します。成功事例に共通するのは、社内に明確な責任者やチームを設置して推進役を担わせている点です。デジタル戦略担当部門を設立し、現場の声を吸い上げながらプロジェクトを統括させる、というのが一例です。この体制により現場と経営層の橋渡しがスムーズになり、現場の抵抗感を減らす効果も期待できます。
また、DX推進に関する権限を明確にし、適切な意思決定を迅速に行える環境づくりが重要です。推進責任者には、技術理解だけでなく業務知識やコミュニケーション能力も求められます。こうした体制を整えることでDXの浸透と継続的な改善を支えられます。
新しいツールや技術を導入しても、それを活用する社員が使いこなせなければ効果は限定的です。したがって、教育・研修プログラムの構築が欠かせません。例えば、AI-OCRの運用方法やチャットボットの管理、クラウド基盤の利用手順などを体系的に学べる研修を用意しましょう。また、新しい業務フローの具体的な変更点を理解し、現場の疑問や不安を解消するフォロー体制も重要です。実践的なトレーニングやワークショップを実施し、社員が自信を持って新システムに対応できる環境を整えましょう。教育によって社員のDXに対する抵抗感が減り、積極的な活用を促進できます。
DXは一度の推進で完了するものではなく、継続的に改善を繰り返すプロセスです。推進後は運用状況や効果を定期的に評価し、課題があれば速やかに対応しましょう。
例えば、チャットボットの回答精度をモニタリングして改善したり、ビッグデータ解析のモデルをアップデートしたりすることが挙げられます。このPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを確実に回すとDXが業務に定着し、企業全体の生産性向上や顧客満足度向上に直結します。また、改善の過程で新たな技術やサービスの導入も検討し、変化する市場環境に柔軟に対応できる組織を目指しましょう。こうした継続的な取り組みが真のDX成功を支えます。
保険業界におけるDX推進は効率化や顧客満足度向上をもたらす一方で、計画の不備や現場の理解不足が原因で失敗するリスクもあります。
ここでは成功に導くために特に注意すべき4つのポイントを解説します。これらを踏まえることで、DXの効果を最大化し、組織全体の成長につなげられるでしょう。
DXは単なるIT導入や業務のデジタル化ではなく、企業のビジネスモデルや組織文化を変革する取り組みです。そのため、まずはDXの目的を具体的に定め、経営層から現場まで全社員で共有することが不可欠です。目的が曖昧だと各部署で取り組みの方向性がバラバラになり、効果的な連携が難しくなります。
例えば、「顧客対応の迅速化による顧客満足度の向上」「契約手続きの自動化で業務効率を30%改善」など、明確な目標を設定しましょう。全社共有の際は、経営層からのメッセージや説明会を活用し、全員の理解と共感を得ることが重要です。これによりDX推進のモチベーションが高まり、社内の一体感が生まれます。
DXの成否を分けるのは、現場での使いやすさです。システムや業務フローの設計は現場の意見を取り入れて実用的に作り込む必要があります。現場の担当者が使いにくいシステムは結局活用されず、効果が薄れてしまうからです。
例えば、営業担当者が直感的に操作できるインターフェース設計や、事務処理の手間を減らすワークフローを優先して設計しましょう。導入前にはパイロット運用やヒアリングを重ねて改善を続けることが重要です。こうした工夫が現場の負担軽減と業務効率化に直結し、DXの成功を後押しします。
新しい仕組みを導入した後のサポート体制が不十分だと、トラブル対応や疑問の解消が遅れ、利用者の不満が蓄積します。DXの定着と効果的な運用のためには、迅速かつ丁寧なサポート体制の構築が欠かせません。具体的には、専任のサポートチーム設置や問い合わせ窓口の整備、FAQやマニュアルの充実が挙げられます。
また、定期的に操作講習会を開催することで社員の理解度を高められるでしょう。これにより新しい業務フローが自然に浸透し、現場の負担が減るだけでなく社員のスキル向上も期待できます。
保険業界は個人情報や契約情報など機微なデータを扱うため、DX推進においてセキュリティ対策は最優先事項です。万が一情報漏えいが起きると、企業の信用失墜や法的問題につながるリスクが高いためです。
対策としては、アクセス権限の厳格管理、通信の暗号化、多要素認証の導入などがあります。さらに、定期的なセキュリティ監査や社員教育も不可欠です。特に現場の担当者がセキュリティ意識を高く持つことで、ヒューマンエラーによるリスクも抑えられます。安全かつ効率的なDX推進のために、セキュリティ対策が最初から組み込まれた設計を心がけましょう。
保険DXは、単なる業務のデジタル化にとどまらず、ビジネスモデル全体の変革を意味しています。今後は、AIやビッグデータを活用した商品開発が進み、顧客一人ひとりのライフスタイルに合わせたパーソナライズされた保険が提供されるようになるでしょう。
また、IoT機器と連携した新しいサービスも登場し、事故や病気の予防支援まで行う保険会社が増えていく見込みです。デジタル技術を活用することで、保険会社は単なるリスクのカバーだけでなく、顧客の生活を総合的にサポートする存在へと進化していきます。
保険DXを成功させるには、明確なアクションプランが欠かせません。第1のステップとして、経営層がDXの重要性を理解し、全社的な戦略として位置づける必要があります。
次に、現状の業務プロセスを詳細に分析し、どの部分をデジタル化すれば最も効果が高いかを見極めましょう。優先順位をつけて段階的に進めることで、リスクを抑えながら着実に成果を上げられます。システム導入にあたっては、既存システムとの連携を考慮し、段階的な移行計画を立てることが重要です。
また、従業員向けの研修プログラムを整備し、デジタルツールを使いこなせる人材を育成していく取り組みも並行して進める必要があります。定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を修正する柔軟性も持ちましょう。
DX推進には、適切な社内体制の構築が不可欠となります。まず、DX推進を専門に担当する部署やチームを設置し、責任者を明確にすることから始めましょう。経営層と現場をつなぐ役割を果たせる人材を配置することで、スムーズな意思決定が実現します。
IT部門だけでなく、営業や契約管理など各部門から人材を集めた横断的なチームを編成すると、現場の声を反映した施策を打ち出せます。デジタル人材の採用や育成計画も重要なポイントです。外部のコンサルタントやベンダーとの連携体制を整えることで、専門知識を活用しながらプロジェクトを進められます。
さらに、成果を測定するためのKPIを設定し、定期的にレビューする仕組みを作ることも忘れてはなりません。
保険DXを真に成功させるには、自社だけで完結させるのではなく、外部パートナーとのエコシステムを構築することが重要になってきます。例えば、InsurTech企業と協業することで、最新のテクノロジーを迅速に取り入れられます。医療機関や自動車メーカーなど異業種とのデータ連携により、これまでにない付加価値の高いサービスを提供することも視野に入ってくるでしょう。
API連携を活用すれば、他社のプラットフォームと接続し、顧客接点を広げることも実現します。オープンイノベーションの考え方を取り入れ、スタートアップ企業との共同開発やアクセラレータープログラムの運営も効果的な手段です。エコシステム全体で価値を創造する視点を持つことで、競争力を高められます。
保険業界のDX推進に取り組む際は、実績豊富なパートナーの存在が重要です。『株式会社 TWOSTONE&Sons』は、保険業界に特化したDX支援を通じて最新の技術導入から業務改革の設計・教育・定着支援まで幅広く対応し、実用的な解決策を提供しています。
保険業界特有のニーズや業務プロセスを深く理解しているため、ただツールを導入するだけでなく現場に寄り添った実践的なDX推進が可能です。お困りの際は、まずはお気軽に『株式会社 TWOSTONE&Sons』までご相談ください。専門スタッフが丁寧にヒアリングを行い、貴社に最適な解決策をご提案します。
–end
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
