保険DX推進に必須なコンプライアンス対策|内部統制と監査のデジタル化
保険

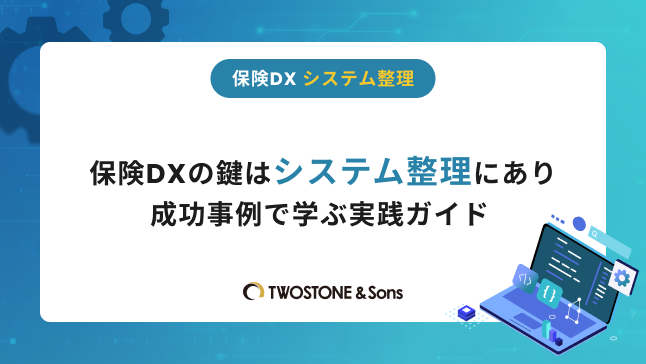
保険業界ではDXの必要性が叫ばれながらも、レガシーシステムや人材不足、法規制といった課題により思うように進んでいないのが現状です。本記事では、DX成功の鍵を握る「システム整理」に着目し、その基本概念から実践手順・成功事例・注意点までを分かりやすく解説します。
さらに、信頼できる支援企業の紹介も行い、実際に一歩を踏み出すためのヒントを提供します。将来に備えた業務基盤の再構築を検討している方にも、必読の内容です。

保険業界ではDXの必要性が叫ばれながらも、実際の進行は遅れています。その背景には、レガシーシステムの存在やサイロ化した情報資産の分断、デジタル人材の不足など、複数の構造的な課題があります。
また、法規制やセキュリティへの懸念もDXを慎重にさせる一因です。DX推進には、この障壁を整理・克服する戦略的なアプローチと、経営層の強いコミットメントが不可欠です。
DX推進の最大の障害は、長年使われ続けるレガシーシステムの存在です。旧来のプログラム言語や複雑なカスタマイズにより、柔軟な連携やデータ活用が困難になっています。加えて、担当者の高齢化や属人化が進み、新技術導入を妨げています。多くの保険会社では、基幹システムが20年以上前の技術で構築されており、その保守運用だけでIT予算の大半を消費してしまう状況です。
過去の度重なる制度改正に対応するため、システムが複雑化・肥大化し、変更に多大なコストと時間がかかる状態となっています。結果、ユーザー体験の向上や業務効率化といったDXの本質的な価値が発揮されにくく、競合他社や新興企業との差が開いていく懸念があります。
DXを阻む要因の一つが、部門ごとに分断されたサイロ化データの存在です。契約情報・顧客データ・営業記録などがバラバラに管理されていると、全社的なデータ利活用が困難になります。例えば、同一顧客が複数の保険商品を契約していても、商品ラインごとの別データベースでは顧客の全体像を把握できません。
さらに、データ形式や定義の不統一により、横断的な分析やレポート作成にも大きな手間がかかります。こうした課題を解消するには、統合データ基盤の整備と部門間連携、そしてデータガバナンスの確立が不可欠です。CRMやDWHなど共通インフラの導入も、DX推進の基盤となります。
保険業界では、デジタル人材の確保と育成が大きな課題です。ITに強い人材が不足し、業界の高齢化も相まって新技術への対応が遅れがちです。多くの保険会社では、システムの運用・保守に人材が偏り、デジタルサービス開発やデータ分析に精通した人材は限られています。既存社員のデジタルリテラシーも十分とはいえず、DXの必要性やその効果への理解も浸透していません。
さらに、人事評価制度が従来型のビジネスモデルを前提としており、イノベーションを促す環境が整っていない場合もあります。結果、AIやクラウド、APIなどの技術を活用した柔軟なシステム構築が進まず、業界全体の競争力低下に繋がっています。
保険業界では、個人情報を扱うという特性から、コンプライアンスやセキュリティへの意識が非常に高く、これがDX推進のスピードを鈍化させる要因となっています。特に新たなデジタルサービス展開時には、個人情報保護法や金融商品取引法など多くの法規制への対応が不可欠です。
情報漏えいやサイバー攻撃のリスクも高まるため、セキュリティ対策への投資も欠かせません。経営陣がこうしたリスクに過度に慎重になることで、クラウド導入やAPI連携などの革新的な取り組みが進まないこともあります。しかし、セキュリティ対策を徹底し、ガイドラインに沿った運用体制を構築すれば、これらの課題は克服でき、むしろ業界内での信頼性向上に繋がります。
DX推進の鍵となる「システム整理」とは、単なるシステム更新ではなく、IT構造全体を見直し最適化することです。レガシーシステムや重複機能を整理し、コスト削減・業務の迅速化・柔軟化を図ります。
分断データの統合で部門横断の情報活用が可能になり、真のデジタル化が実現しました。技術的負債の解消で将来の拡張性も確保します。複雑化したシステムの整理はDXの第一歩です。これはDX成功の土台であり、ビジネス戦略と連動させた計画的な取り組みが求められます。
システム整理とは、企業が保有するIT資産や情報システムを全体的に見直し、重複・老朽・非効率な仕組みを排除して最適化するプロセスです。この整理は、単なるシステム統合にとどまらず、業務プロセスやデータ構造、ITインフラ全体の再設計まで含まれます。
例えば、保険業務でありがちな契約管理・顧客管理・請求処理などが別システムで管理されている場合、それぞれのデータ整合性が取れず、手作業が発生します。非効率を排除するために、まずは現行のシステム資産を可視化し、何がどこでどう使われているのか把握が必要です。
その上で、業務に必要な機能の選定、役割の再構成、アーキテクチャの再設計へと進みます。
システム整理は、IT投資の無駄を省くだけでなく、データの一元管理や自動化、迅速な意思決定に繋がる「攻めのIT戦略」への第一歩といえます。
保険業界におけるDXでは、「システム整理」が重要なテーマとして位置づけられています。なぜなら、保険業務は商品開発から契約・顧客対応・事故対応・支払いに至るまで、非常に多岐にわたり、それぞれが異なるシステム上で処理されていることが多いからです。
このような状況では、データの一貫性が保てず、情報共有や業務の自動化が進みにくくなります。さらに、多くの保険会社では古いレガシーシステムが今も現役で使われており、新しい技術との統合が困難な状況です。結果、DXの恩恵を受けにくい「非効率な構造」が温存されてしまいます。
システム整理は、これらの課題を一掃し、柔軟性と拡張性のあるシステム基盤を構築するための鍵です。顧客対応のスピード向上、商品開発サイクルの短縮、データ活用による経営判断の質の向上など、保険DXを本質的に実現するには、まずこの整理が出発点となります。
DXを進める上でシステム整理がもたらすメリットは大きく3つあります。それは「業務効率とITコストの最適化」「顧客体験(CX)の向上」「意思決定の高度化」です。この3点は単なるシステム更新にとどまらず、企業競争力を根本から高める要素となります。
保険業界では、複雑な商品や規制に対応するために積み上げられてきたシステムの整理が、業務プロセスの見直しと同時に進めることで大きな効果を発揮します。
システム整理は、業務効率向上とITコスト最適化をもたらします。保険業界では、複数アプリや紙処理が並存し、業務重複や時間浪費が発生します。例えば、契約データの複数システム入力や部門ごとの類似システムが課題です。これらを統合・自動化すれば作業時間が削減され、人的リソースも有効活用できます。
また、ITコスト見直しでクラウド化等へ予算を集中でき、古いシステムの保守コスト削減分は革新的投資へ回せます。結果、効率的で柔軟な業務運営が実現します。
システム整理で顧客対応品質が大幅に向上します。契約や問い合わせ対応のオンライン化で待ち時間や手間が減少し、顧客情報の一元管理でどのチャネルでも一貫したサービスを提供でき、顧客の不満や混乱を減らせます。
また、スマホアプリやウェブサイトでのセルフサービス拡充により24時間365日対応が可能です。これが顧客満足度向上や継続的な関係構築、リピート契約に繋がります。
顧客の行動データやニーズを正確に把握すれば、新保険商品の開発やチャネル拡大など新規ビジネス展開も可能に。顧客接点強化が企業の成長を支える土台となります。
システム整理とデータ統合で、意思決定の精度とスピードが飛躍的に向上します。サイロ化情報が集約され、リアルタイムの状況把握や将来予測が可能です。
例えば、契約状況や解約率の分析、顧客属性ごとの収益性評価などが迅速かつ正確に行えます。外部データ連携も容易になり、市場動向や競合情報を含めた総合的な分析も可能です。
これにより、マーケティング戦略やリスク管理がデータに基づき判断でき、組織全体の意思決定が合理的かつ迅速になります。経営層から現場まで同じデータを共有することが、真のデータドリブン経営への第一歩です。
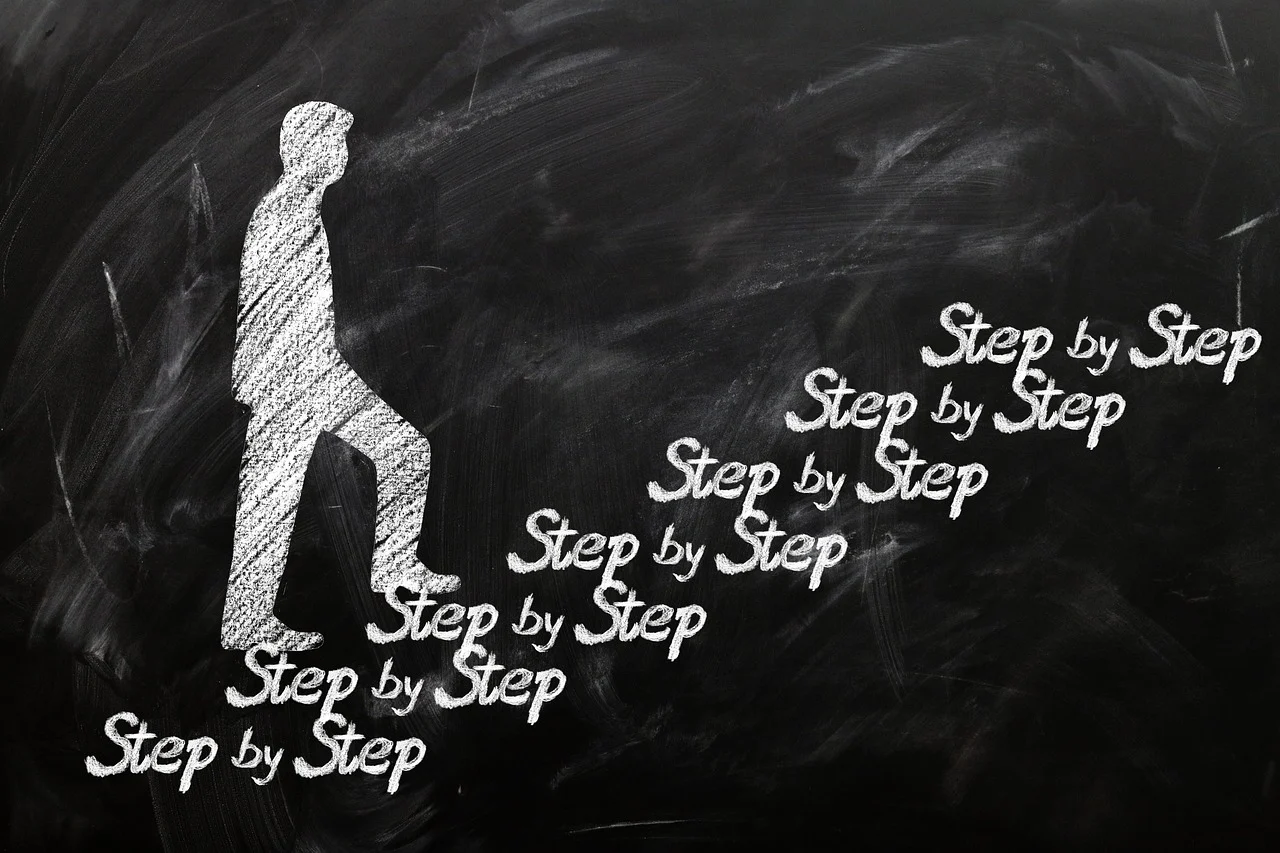
保険DX成功には、思いつきではない明確な手順のシステム整理が不可欠です。適切な6段階の手順を着実に踏むことで確実な成果を得られます。
これらステップは連携し、どれか一つ欠けてもバランスが崩れます。保険業界では商品の複雑さや規制の厳しさから、綿密な計画と柔軟な対応力が必要です。DXリーダーは全体像を把握し、各ステップの適切な管理が重要です。
DXの第一歩は現状の正確な把握です。多くの保険会社では複数システムが混在しブラックボックス化しています。長年の改修で全体像が不明確になり、変更影響も予測困難です。業務フローやシステム構造、利用状況を洗い出し、非効率や重複を明確にします。
具体的にはシステム構成図作成、データフロー可視化、性能測定等を実施し、ユーザーの声も収集し評価します。この「可視化」でDXの優先順位と本質的課題を把握でき、根拠ある改善策に繋がるため極めて重要です。
現状把握後は「理想像」の設計です。単に最新システム導入ではなく、自社の業務や戦略に最適なアーキテクチャを描きます。
ビジネス目標との整合性を保ち「なぜ必要か」を明確にしましょう。保険業界では、柔軟な商品開発・提供、顧客データ一元管理、リスク分析高度化を考慮した設計が求められます。
将来の拡張性も視野に、柔軟なモジュール構造・API連携前提・クラウド適応性を含む構成で、将来変化を見据えた設計で長期安定運用を目指します。
理想構成決定後は、実現に向けた移行計画策定です。全システム一括入替は非現実的なため、段階的かつ優先度に基づく計画が必須です。特に保険業界では、契約管理などミッションクリティカル業務が多く、慎重な戦略が求められます。
ビッグバン型でなく、並行稼働や部分切替えでリスクを最小化し「いつ」「どの領域から」「どの順で」移行するか明確にし、成果指標も設定するのです。
業務プロセス変更や社員教育も含む総合的スケジュールを立案し、明確なロードマップで関係者が目標と進捗を共有し、成功率を高めます。
DXはシステム部門だけでなく全社的な理解と協力が不可欠です。現場・経営層・IT部門等あらゆる関係者と合意形成し、共通認識と目的意識を持つことが重要です。経営層には投資対効果、現場には業務効率化等のメリットを立場に合わせ説明します。
変更による一時的不便や学習コストも正直に伝え、現実的な期待値を設定します。現場業務直結の変更には抵抗が出やすいため、対話と説明責任で納得を得ることが必要です。
定期的な報告会や意見交換で不安や誤解を解消し協力体制を構築することで、丁寧な対応で改革の障壁を減らし円滑な推進に繋げます。
計画実行時は、小規模範囲で効果検証する「スモールスタート」が有効です。PoCや一部拠点・部門での先行導入で、実際の運用課題や改善点を把握します。特にUIの使いやすさ、データ連携の正確性、処理速度等は実運用でしか分かりません。
小さな成功体験の積み重ねで、失敗リスクを避け確実に前進し、初期の成功事例共有で、改革への理解と期待を高め、次への推進力とします。
ここで得た知見は全社展開時の精度向上とリスク軽減に繋がり、初期成果は社内の理解と協力を促します。
DXは一度きりでなく継続的な改善が求められます。市場や顧客ニーズは変化するため、システムや業務も進化させる必要があります。
中長期視点でKPI再設定や技術トレンド反映等、定期的な見直しを計画的に行うことが不可欠です。初期DX成果の定着には、働き方や業務プロセスを組織文化に根付かせることも重要です。デジタル人材育成やイノベーション促進風土の醸成にも継続的に取り組みます。
定期的な振り返りと次の目標設定の繰り返しでDX成熟度を高めるアプローチが効果的です。この継続的な改革サイクルが真のDX定着の鍵です。
システム整理によるDX成功事例は、先進技術と業務改革を一体化した取り組みにあります。ソニー損保やSBI損保、大同生命の実例から、AI・OCR・テレマティクスなどを通じた運用改善と新サービス展開が見て取れます。これらは単なる技術導入ではなく、「システム整理→新技術導入→業務成果」の流れを示す好事例です。
システム整理が単なるIT投資ではなく、事業戦略と直結した取り組みであることがよく分かります。次節では、各社が具体的にどのような成果を出したかを詳しく見ていきます。
ソニー損害保険株式会社は、スマホ連携AIドライブログ「GOOD DRIVE」で事故リスク低減に成功しました。2015年開始の同サービスは、契約管理システムとのAPI連携を可能にしました。スマホアプリと車内デバイスで運転特性を計測、AIスコア化で最大30%の保険料をキャッシュバックされる仕組みです。
これにより安全運転意識を向上し、急ブレーキ等の危険運転を検知・フィードバックし運転行動改善を促進しました。蓄積データ分析で事故リスクの高い時間帯・場所を特定し顧客へ助言も行います。
AI・IoTのテレマティクスでレガシー保険モデル脱却と顧客行動変革を同時実現しました。事故リスク削減に加え、安全運転促進で社会貢献も行います。利用者事故率は非利用者比で低減し、データ活用の成果が示されています。
参考:ソニー損保ニュースリリース|AIを活用した運転特性連動型自動車保険「GOOD DRIVE」販売開始
アフラック生命保険株式会社は2022年春、クラウド型プラットフォーム「ADaaS(Aflac Digital as a Service)」を立ち上げ、代理店や顧客に向けた業務支援サービスを本格的に開始しました。その中核となる「募集人教育AI」は、保険営業担当者がAIアバターを顧客役として活用し、ロールプレイング形式で営業話法を訓練できる画期的な教育ツールです。
AIは音声認識や自然言語処理の技術を用いて会話を分析し、営業に必要なキーワードが盛り込まれているか、話し方が適切かなどをリアルタイムで評価します。従来は先輩社員が顧客役を担っていた研修も、時間や場所にとらわれず自己学習できるため、育成の質と効率が格段に向上しました。
2022年9月時点で8,870人以上が利用しており、挙績(新規契約獲得数)は未導入者に比べて約1.3〜1.5倍に上昇しました。これは、システム整理を通じて教育プロセスを標準化し、成果に直結させた好事例です。ADaaSは営業活動のオンライン化と効率化を同時に実現し、コロナ禍以降のニューノーマルにも柔軟に対応しています。
参考:保険の「挙績」が30%以上アップ、アフラックがAIアバターの営業ロープレで成果
明治安田生命保険相互会社は、医療関連書類の処理効率を高めるため、シナモンAIが開発した高精度AI-OCR「Flax Scanner」を導入し、DXを加速させています。同社では従来、「診療明細書」や「調剤明細書」といった書類を手作業でデータ化しており、膨大な業務量と人件費が課題でした。
さらに、これらの書類は医療機関ごとにフォーマットが異なる非定型帳票であり、作業が属人的かつミスが発生しやすい構造となっていました。この背景のもと、2023年11月からは「健康診断書」へのFlax Scannerの適用を拡大し、AIが91項目の項目を約3秒で読み取り、全体の読み取り精度は平均89.06%、重点項目では90.69%と極めて高い精度を記録しています。
特筆すべきは、スマートフォンで撮影された写真のような品質の低い画像でも対応可能である点です。書類提出の手間も軽減され、顧客利便性の向上にも寄与しています。
Flax Scannerは「特徴量学習型」と呼ばれる方式を採用しており、従来主流だった「座標定義型」のように事前に各書類のレイアウトを登録する必要がありません。帳票ごとに設計を変えずとも、AIが内容の意味を自動で理解し、構造を解析してデータ化します。
結果、現場では属人的だったデータ入力業務をAIに任せることで、従業員はより戦略的な業務に注力できるようになり、生産性と精度の両立を実現しました。これは、保険業界における非定型業務のデジタル化とシステム整理の優良事例といえるでしょう。
参考:明治安田に高精度AI-OCR「Flax Scanner」の提供を拡大
保険業界におけるシステム整理を成功に導くには、技術面だけでなく運用・体制面の注意が不可欠です。中でも「セキュリティ対策」「法規制の遵守」「人材の確保と育成」の3つは、DXを円滑に進めるための重要な要素です。
短期的な成果を追求するあまり、これらの基盤整備をおろそかにすると、長期的には大きなリスクとなります。慎重かつ戦略的に対応すべきポイントを押さえておきましょう。
DXでは大量の顧客データや機密情報を扱うため、セキュリティ対策は最優先の課題です。クラウド導入やAPI連携によってシステムが開かれた構造になるほど、情報漏えいや不正アクセスのリスクも増します。
特に保険会社が扱う情報には、氏名や住所といった個人情報だけでなく、健康状態や資産状況など、極めて機微性の高い情報も含まれるため、データ暗号化・アクセス制御・インシデント対応の仕組みなど、万全な対策が求められます。
具体的には、多要素認証の導入・通信の暗号化・定期的な脆弱性診断・アクセスログの監視などが基本です。さらに、クラウドサービスを利用する際は、サービスレベルの確認やデータの所在地管理も重要です。
保険DXを推進する際には、業界特有の厳格な法規制とガイドラインの遵守が不可欠です。個人情報保護法、保険業法、金融商品取引法などの法令に加え、業界団体のガイドラインにも対応が必要です。金融庁は「ITガバナンスに関する論点整理」で、システムリスク管理と経営層の関与を明確に求めています。
また、損保協会や生保協会も、それぞれ個人情報保護やサイバーセキュリティのガイドラインを策定し、保険会社には高い管理水準を求められるでしょう。特に近年では、データの越境移転規制やAI利用の倫理規範など、新たな規制も増えており、常に最新動向を把握する必要があります。
参考:金融庁 |「金融機関のITガバナンスに関する対話のための論点・プラクティスの整理」
参考:日本損害保険協会 |「損害保険業界における個人情報保護ガイドライン」
参考:生命保険協会 | 「生命保険業界におけるサイバーセキュリティ対策ガイドライン」
DX推進において、システムやツールだけでなく「人材」の確保と育成が鍵を握るでしょう。多くの保険会社では、ITに精通した人材が不足しており、変化への対応力にも課題があります。特に、クラウド技術やデータ分析、AIなどの最新技術に関する知識と経験を持つ人材は限られています。
保険業務の知識とIT技術の両方を理解し、橋渡しできる人材も貴重です。そのため、既存社員のリスキリングや外部専門人材との協業体制の構築が求められます。リスキリングでは、オンライン学習やハンズオン研修、社外セミナーなどの学習機会を提供することが効果的です。ベンダーマネジメントやプロジェクト管理のスキルも重要になります。
保険業界でのDXやシステム整理にお悩みの企業は、『株式会社TWOSTONE&Sons』にご相談ください。「BREAK THE RULES」のビジョンを掲げ、企業のDX推進とIT人材支援を多角的に展開しています。エンジニアプラットフォーム事業では、実践型スクール「tech boost」や転職支援「TechStars Agent」などを通じて、DXを支える技術者の育成と供給を行っています。
また、マーケティング分野では、SEO対策から広告運用まで一貫した支援が可能です。保険業界特有の課題にも柔軟に対応できる体制を整えておりますので、頼れるパートナーとしてぜひお任せください。

保険業界のDXを成功させる鍵は、技術導入だけでなく、その土台となる「システム整理」にあります。レガシーシステムの可視化と統合・データの一元管理・段階的な移行計画の策定などを通じて、業務効率と顧客満足度を大きく向上させることが可能です。
また、セキュリティ・法規制対応・人材育成といった体制整備も、DXを持続的に進めるための要です。現状のシステム環境を正確に把握し、理想的なアーキテクチャを設計した上で、ステークホルダーの合意を得ながら段階的に改革を進めていくことが重要になります。
今こそ、全社的な視点でシステムを見直し、保険DXの基盤を築く一歩を踏み出しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
