保険DX推進に必須なコンプライアンス対策|内部統制と監査のデジタル化
保険

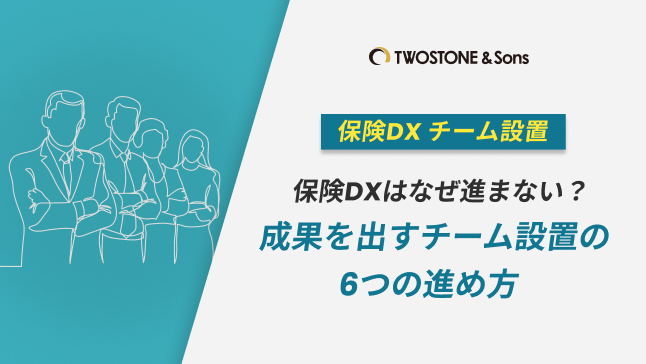
保険業界のDX推進で成果が出ないとお悩みではありませんか?現在、日本の多くの保険会社が同じ課題を抱えています。
本記事では、これらの障壁を乗り越えるための専門チーム設置の具体的手法を6ステップで解説します。適切な体制構築により、顧客満足度の向上・業務効率の劇的改善・商品開発の迅速化などの成果を実現可能となるでしょう。

保険業界のDX推進は世界的な潮流となっていますが、日本市場では思うように進展していません。多くの保険会社がデジタル変革の必要性を認識しながらも、具体的な成果を出せずにいるのが現状です。
この遅れは顧客離れと業務非効率を招き、業界全体の競争力低下につながっています。デジタル人材の確保も難しく、技術導入のハードルも上がっています。なぜ日本の保険DXが進まないのか、以下より詳しく見ていきましょう。
海外の保険会社がデジタル技術を活用した新サービスを次々と生み出す中、日本の保険業界は周回遅れの状態に陥っています。少子高齢化や規制緩和などの厳しい環境変化に加え、顧客ニーズの多様化という課題に直面しながらも、デジタル対応が追いついていません。
顧客体験の向上とコスト削減が本来のDXがもたらす恩恵を享受できず、市場シェアの縮小リスクが高まっています。特に若年層の顧客獲得でのデジタルサービスの遅れは致命的な弱点です。
日本の保険業界でDXが進まない背景には、複雑化したレガシーシステムという技術的課題があります。長年運用されてきた基幹システムは最新技術との統合が困難で、契約管理での紙媒体の主流化もデジタル化を阻んでいます。
縦割り組織による部門間連携の難しさ、成熟ビジネスモデルで培われた前例踏襲型の企業文化も大きな障壁です。これにより、デジタル変革への意識改革が進んでいません。経営層のIT理解不足も深刻で、投資判断が遅れる要因です。
保険業界でDXを成功させるには、専門知識と権限を持ったチームの設置が不可欠です。多くの成功事例を見ると、通常の組織体制では変革の推進力が不足しがちになります。
専門チームを設置することは変革の核となり、全社を巻き込む求心力を生み出します。また各部門の壁を越えて迅速に意思決定できることが強みです。以下より、チーム設置の必要性を詳しく見ていきましょう。
専門チームは保険会社全体のDX戦略を推進する原動力として機能します。経営層の意思決定と現場の実行をつなぐ架け橋となり、戦略の具体化と実装を加速させる役割を担います。
保険業界では、複雑な商品構造と規制要件を理解した上でのデジタル変革が必要です。専門チームがこれらの要素を統合的に捉え、全社一丸となった取り組みへと昇華させることで、断片的な取り組みではなく、一貫性のあるDX推進が可能になります。
保険業界のDXでの最大の障壁となるのが、部門間の壁と縦割り組織構造です。専門チームの最大の価値は、この壁を越えて調整できる権限と専門性にあります。
商品開発・営業・保全・支払い・ITなど多岐にわたる部門が絡む保険ビジネスでは、一部門だけの努力では真の変革は起こせません。専門チームが部門間の利害を調整し、全体最適の視点で解決策を導き出すことで、従来なら実現困難だった改革も可能になるでしょう。
専門チームは日常業務から離れた「変革拠点」です。通常の業務プロセスと慣習にとらわれない環境で、大胆な発想と実験が可能になります。
保険業界は伝統的にリスク回避的な文化が強く、イノベーションが生まれにくい傾向があります。専門チームでは失敗を許容し、トライ&エラーを奨励する文化を育てることで、創造性と挑戦精神を引き出すことが可能です。
チームから生まれたアイデアが、やがて会社全体の変革を促すきっかけとなるでしょう。
専門チームを中心としたDX推進には、明確な成果が期待できます。実践企業では顧客満足度の大幅な向上と業務効率化の両方を実現しています。
顧客目線ではサービスのパーソナライズ化、社内では業務プロセスの抜本的改革が実現可能です。さらに新商品・サービス開発のスピードも格段に向上し、市場投入までの時間を短縮できます。
以下より、保険DXでチーム設置するメリット3つを詳しく見ていきましょう。
専門チームの設置により、顧客データの統合と活用が飛躍的に向上します。従来バラバラに管理されていた契約情報と行動データを一元化し、AIによる分析を通じて個々の顧客に最適な提案ができるようになります。
例えば自動車保険では運転傾向に基づく保険料設定、生命保険では健康状態に応じたプランの提案など、真の意味での「一人ひとりに合わせた」商品設計が実現可能です。
専門チームは保険DXにより業務の根本的な見直しと再設計をします。AI・RPA・ブロックチェーンなどの先端技術を駆使した業務プロセスの再構築が可能です。
AI・RPAを活用することで、保険金請求処理や契約確認作業など従来人手に頼っていた業務プロセスを自動化できます。これにより、業務ミスの削減とペーパーレス化を同時に実現可能です。
紙ベースだった保険金請求手続きがスマホ完結型に変わり、処理時間の短縮と顧客満足度向上ができるでしょう。
専門チームの存在は、新しい保険商品とサービスの開発速度を大幅に向上させます。AIや機械学習などの活用で、市場動向と顧客ニーズを正確に分析し、新商品の開発に役立てることが可能です。
従来の保険商品開発は部門間調整に時間がかかりましたが、専門チームが中心となることで承認プロセスが簡素化されます。さらに、顧客の声を迅速に反映した商品開発を実現可能です。迅速に市場の変化に対応し、競争力のある革新的な商品を提供することで、新たな市場開拓にもなるでしょう。
日本の保険業界でも、専門チーム設置によりDXを成功させている事例が増えています。以下は、東京海上日動、大同生命、第一生命の成功事例です。これらの企業は、DX専門チームの設置により業務効率化に成功しました。
成功企業がチーム設置によりどのような取り組みを行い成功したのか、詳細に見ていきましょう。
東京海上日動は「DXリーダー」と「DXコア」の2層構造による人材育成体制を確立しています。2023年度には約700名のDX人材を育成しました。
特筆すべきは周辺事業ではなく保険コア事業そのものへの集中投資です。保険の契約手続きや保険金支払いプロセスの自動化などのDXを実施しました。
成果として、2019年度末と比較して事務量を16.7%削減することに成功しました。これは、当初の目標15%削減(200-250億円/年相当の利益貢献)を上回っています。
参考:パーパスストーリーを支える戦略と経営基盤|東京海上グループホールディングス
大同生命は、アクセンチュアと共同で約10万件の医療データを分析し、2020年に医務査定業務へのAIモデルを導入、業界初のビジネスモデル特許を取得しました。
社内チームとしては、2021年に新設された「共創戦略部」がDX戦略を統括しています。これにより、保険加入の完全リモート化や業界初の「請求書レス支払」など革新的なサービスを次々と実現しています。
医療ビッグデータによるAI活用とDX専門チームにより、より多くの顧客へ最適な保証を提供可能にしました。
参考:【大同】ビジネスモデル特許の取得~業界初となる医務査定業務へのAI活用~| 大同生命
参考:デジタルトランスフォーメーション戦略 | 大同生命を知る | 大同生命
第一生命は、保険(Insurance)とテクノロジー(Technology)を合わせた「InsTech」戦略を展開しています。その中核となるのが、新規ビジネスの企画からシステム構築までを一気通貫で実行するDXプロジェクト推進部です。
同部門は「得意分野の異なるプロフェッショナルの集団」として構成され、全社から必要なスキル保持者を募集してプロジェクトチームを組成しています。個人保険分野と団体保険分野の開発を同じ部署で担当することで、部門間の情報共有を促進し、統合的なアプローチを実現しました。
注目すべきは、「挑戦する社員には活躍の場を用意する」という価値観のもと、失敗を恐れずに新しい取り組みに挑戦できる環境を整えている点です。これにより、伝統的な保険業務にデジタル技術を融合させる革新的なプロジェクトが継続的に推進されています。
参考:Insurance Technologyへの取組みについて|第一生命について|第一生命保険株式会社
参考:イノベーションの現場から | 仕事を知る | 第一生命テクノクロス株式会社 採用サイト

保険業界でDXを成功させるには、専門チームの設置が欠かせません。しかし、人材を揃えるだけでは、期待する成果にはつながりません。大切なのは、チームづくりの進め方を戦略的に考えることです。
目的の明確化から始まり、現場との連携、経営層の支援まで、段階を踏んで取り組むことで、実効性のあるDXが動き出します。以下より、成果につながる6つの進め方を紹介します。
専門チーム設置の第一歩は、経営戦略と連動した明確な目的設定です。「なぜDXに取り組むのか」「どのような成果を目指すのか」を具体化することから始めます。
単に「デジタル化を進める」ではなく「顧客体験の向上により契約更新率を15%向上させる」などの形で数値目標を設定します。またKGI(重要目標達成指標)だけでなく、進捗を測るKPI(重要業績評価指標)も設計しておきましょう。
保険DX推進には多様なスキルセットを持つメンバー構成が不可欠です。技術面だけでなく、ビジネス面の知見も重要な要素となります。
理想的なチーム構成は、IT技術者・データサイエンティスト・保険商品の専門家・マーケティング担当者などです。外部からの人材登用と社内人材の活用をバランスよく組み合わせることで、技術的先進性と業界知識を兼ね備えたチームが形成できます。
DX推進を「片手間」の業務にしないことが成功の秘訣です。チームメンバーは本来業務と兼務ではなく、DX推進に専念できる体制を整えましょう。専任体制により、短期的な業務圧力に流されることなく、中長期的な変革に注力できます。
また報告ラインを明確にし、経営層に直接つながる仕組みも重要です。既存の組織構造に埋もれてしまうと、大胆な変革は難しくなります。専任メンバーの評価基準も通常の業務評価とは分けて設計することで、変革への挑戦を促すでしょう。
DXの成果を確実にするには、現場の業務知識を活用することは極めて重要です。技術偏重のアプローチでは実務との乖離が生じ、導入後に使われない危険性があります。専門チームと現場部門との定期的な対話の場を設け、実務上の課題と改善点を吸い上げる仕組みを作りましょう。
「現場アンバサダー制度」を導入し、各部門から選抜された担当者がDXチームと定期的に情報交換する例も増えています。現場の声を反映させることで、真に役立つソリューション開発が可能になります。
DXの成功には「スモールスタート」が効果的です。1度に全てを変えようとするのではなく、特定の業務と顧客接点に絞った施策から着手します。明確な成果が見えやすい領域からスタートし、短期間で効果を実証しましょう。
成功事例を社内に共有することで、変革への抵抗感が低減し、次のステップへの推進力が生まれます。また失敗した場合のリスクが抑えられることもメリットです。
DX推進で最も重要な要素が経営層の強いコミットメントです。形だけの支援ではなく、実質的なリソース配分と意思決定の迅速化が求められます。経営層が定期的に進捗をレビューし、課題解決に関与する体制を作りましょう。
また中長期的な視点での評価が重要で、将来的な競争力と顧客価値の向上などの観点での評価が必要です。トップ自らがDXの意義と方向性を発信し続けることで、全社的な変革機運が高まるでしょう。
保険DX専門チームを設置しただけでは、成果は自動的に生まれません。チームの潜在能力を最大限に引き出すための運営方法が重要です。
成功している保険会社のDXチームに共通するのは、明確な権限付与と意思決定プロセス、部門を超えた緊密なコミュニケーション体制、失敗から学ぶ文化の醸成、そして効果測定と柔軟な方向転換の仕組みです。以下より詳しく見ていきましょう。
DX専門チームが成果を出すには、適切な権限移譲が不可欠です。予算執行権や人事権、システム変更の決定権など、必要な権限を明確に付与しましょう。
保険業界では慎重な意思決定文化が根付いているため、専門チームにどこまでの決定権を与えるかを事前に定義することが重要です。決裁金額の範囲や決定できる案件の種類など、具体的な基準を設けておくと混乱を防げます。
また決定プロセスのスピードを上げるため、経営層への報告・承認ルートの短縮化も可能です。
DX専門チームが孤立した「異物」にならないよう、全社との円滑なコミュニケーション体制を構築することが重要です。定期的な進捗共有と相互理解の場を設けましょう。
具体的には月次の全社DX進捗報告会、週次の関連部門とのすり合わせミーティング、経営層との隔週での戦略レビューなどです。
社内ポータルやチャットツールなどを活用した日常的な情報共有も効果的です。透明性の高いコミュニケーションが変革への抵抗を減らし、協力体制を生み出します。
イノベーションを生み出すためには、失敗を恐れず挑戦できる環境作りが欠かせません。リスク回避傾向が強い保険業界では、この点に意識的に取り組む必要があります。
「早く小さく失敗し、そこから学ぶ」という価値観を共有し、失敗を前向きに評価する文化を作りましょう。「ベストフェイル賞」のような失敗から得た学びを称える仕組みや週次での「学びの共有会」などが効果的です。
DX推進は長期的な取り組みですが、定期的な効果測定と軌道修正の仕組みが不可欠です。数値化できる指標を設定し、進捗を可視化していきましょう。
例えば、クオーターごとの成果レビューを実施して、当初の想定通りに進んでいるか、また市場環境の変化に対応して方針を修正する必要はないかを検討します。KPIは業務効率化率・顧客満足度・新規契約率など複数の観点から設定すると良いでしょう。
保険業界でDX専門チームを設置する動きが活発化していますが、多くの企業が類似の失敗パターンに陥っています。チーム設置の注意点を事前に把握し、適切な対策を講じることで、成功率の高いDX推進が可能になります。
多くの企業が陥りがちな失敗パターンを理解し、それぞれに対する具体的な対策を検討することが重要です。以下より詳しく見ていきましょう。
役割分担が曖昧になることで、プロジェクトの責任範囲が不明確化し、業務の停滞と重複が発生します。大企業で特に顕著に見られ、責任の擦り付け合いが起こりやすい 現象として知られています。
これを回避するには、既存部門とDXチームの業務範囲を明確に定義し、権限と責任を文書化することが必要です。定期的な責任範囲の見直しと調整を実施し、部門間の連携を促進する仕組みを構築しましょう。
各部署からPCに詳しそうな人間が集められ、DXチームが結成されましたが、ほとんど若手で「上司よりはPCに詳しい」というだけの人という状況は多くの企業で見られます。
チームメンバーはそれぞれ専門分野も経歴も異なり、考え方・優先順位・スピード感も異なります。必要なスキルを体系的に整理し、技術・業務・管理の各分野からバランスよく人材を選定することが重要です。
不足するスキルは外部専門家の活用または研修による補完を検討しましょう。
「思ったほど効果が上がらない」「当初思い描いた姿からスケールダウンしている」など事実上の失敗に陥っているケースが少なくありません。短期の成果主義や現場の時間・予算不足がDXプロジェクトの阻害要因となっています。
DXは長期的な取り組みであることを経営層に理解してもらい、段階的な成果指標を設定することが重要です。小さな成功体験を積み重ねながら、継続的な改善を図る文化を醸成しましょう。
DXチームと所属部署の仕事を合わせた総量をだれも把握していないという状況は、実質的な支援体制の不備を示しています。これには、予算不足、経営層のコミットが少ないことなどが問題です。
看板だけのチーム設置を避けるため、十分な予算と人的リソースを確保し、経営層の継続的なコミットメントを得ることが必要です。チームメンバーの本来業務との調整と評価制度の見直しも必要でしょう。
『株式会社TWOSTONE&Sons』は36,000名を超えるITパーソンと数多くの新規事業推進実績により、他社では真似できない一気通貫したDX支援を提供しています。
戦略コンサルティングからITソリューション・人材マッチング・研修プログラム・デジタルマーケティングまで幅広く対応可能です。目標実現に向けたKPI設計や人員計画の作成を支援し、要件定義から運用保守まで全フェーズをサポートします。
まずは無料診断で御社のDX推進状況を確認してみませんか。

日本の保険業界でDXが進まない根本原因は、レガシーシステムや縦割り組織などの構造的課題にあります。この壁を乗り越えるには、適切な権限と専門知識を持つ「DX専門チーム」の設置が有効です。
専門チームは全社的なエンジンとなり、部門横断的な課題解決とイノベーション創出を実現します。自社に合った体制構築にお悩みなら、専門家の知見を活用して、確実な一歩を踏み出しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
