保険DX推進に必須なコンプライアンス対策|内部統制と監査のデジタル化
保険

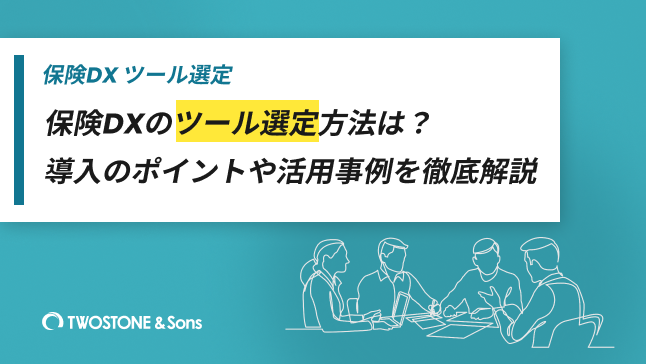
保険DXを推進するためにはツール選定が欠かせません。ツール選定の際は自社の課題に合っているのかや導入する目的の明確化などのポイントを押さえておきましょう。ツールを有効活用するために、導入後は従業員に周知するのも大切です。
保険業界におけるDXの推進は、業務効率化や顧客サービスの向上を目指すうえで効果的な取り組みです。
保険DXによって業務効率化や顧客サービス向上を目指すにあたっては、専用のツール導入が欠かせません。
ツールを導入しないとデータ分析以外の業務に時間がかかってしまいます。
保険DX推進の用いるツールはいくつもあるため、選知ポイントを押さえて導入につなげましょう。
この記事では保険DXに欠かせないツール選定ポイントや導入後の注意点などを解説します。

保険業界を取り巻く環境は従来よりも変化しています。
例えば、少子高齢化が深刻化している現代において高まっているのは医療や介護のニーズです。
また、競争が激化しているため、他社と差別化したサービス提供が求められるでしょう。
このような状況に対して、保険会社は保険DXとして、DXへの取り組みが求められます。
保険DXの取り組み例として、顧客対応の迅速化やデータ分析の高度化、業務プロセスの自動化などが挙げられます。
これらの取り組みによって、企業の競争力を高め、業務の効率化とサービス向上が期待できるでしょう。
保険DXを進める目的は、業務の効率化・データ活用の最適化・顧客サービスの向上などです。
このような保険DXを進めるためには専用のツール導入が欠かせません。
例えばデータ活用する場合、従来の方法ではデータ分析に工数がかかってしまううえに、ミスにつながる恐れがあります。
保険DXにおいてツール導入するメリットは次のとおりです。
それぞれのメリットを解説します。
保険業務のデジタル化によって手作業が減少し、業務効率が向上します。
例えば、契約書類の自動化や顧客対応のチャットボット導入により、従来の時間がかかる業務を短縮可能です。
これにより、従業員はより重要な業務に集中でき、サービス品質も向上します。
また、営業活動においても、顧客情報や過去の取引データにすぐアクセスできるようになるため、顧客への的確な提案が可能です。
業務効率の向上は、コスト削減にも直結し、競争力の強化が期待できるでしょう。
デジタル化により収集されたデータは、経営判断に好影響を与える可能性を秘めています。
保険業界では、膨大な顧客情報や契約履歴、リスクデータが日々生成されています。
さまざまなデータの活用によって、市場動向の予測やリスク管理が可能です。
特に分析ツールを導入すればデータを視覚化できるため、経営者はリアルタイムで戦略的な意思決定を行えるようになります。
データは数字で見るよりも、グラフやチャートで見る方がすぐに情報を認識可能です。
その結果、柔軟かつ迅速な経営判断が可能となり、業界の変化に即応できる体制を整えることができます。
保険業界は、複数の部署や関係者の密接な連携が求められます。
デジタルツールの活用により、顧客情報や契約状況、業務の進捗状況などをリアルタイムで共有可能です。
これにより、従来のように情報の伝達遅延や誤解を避けることができ、チーム間でスムーズなコミュニケーションが実現します。
特に、複数の営業担当者やカスタマーサポートが関与する場合、情報の一元化とアクセスの容易さは業務の効率化につながるでしょう。
迅速で精度の高い顧客対応が可能となり、顧客満足度の向上が期待できます。
保険業界におけるツール導入は、新たなサービスやビジネスモデルの創出を促進します。
例えば、AIを活用した保険商品設計や、データに基づくパーソナライズされた保険提案が可能になるでしょう。
また、ブロックチェーン技術の導入により、契約の透明性やセキュリティが向上し、新たな信頼性のあるビジネスモデルを実現できます。
モバイルアプリの活用によってリアルタイムでの保険契約管理が可能となり、顧客が自分の保険内容を簡単に確認できるだけでなく、保険金請求をスムーズに行うことも可能です。
これにより、顧客体験の向上が図られ、より多くの顧客に迅速かつ効率的なサービスを提供することができます。
このようにツール導入によって新たなビジネスモデルを創出すれば、競合との差別化が可能です。
保険DXの推進にあたっては、次のようなツールを活用しましょう。
これらのツールは、営業活動や顧客管理、コミュニケーションを円滑にするため、業務のスピードと精度向上が期待できます。
オンライン会議システムは、保険業務におけるコミュニケーションを円滑にするための重要なツールです。
テレワークや外出先からであっても、営業担当者と顧客とのリアルタイムでのやり取りが可能です。
代表的なオンライン会議システムとして、ZoomとGoogle Meetが挙げられます。
Zoomは、無料プランでも高機能なビデオ会議を提供し、大人数でのウェビナーやセミナーを実施できます。
画面共有やチャット機能も備え、資料の共有や迅速な問題解決が可能です。
一方、Google MeetはGoogle Workspaceとの統合が進んでおり、カレンダーやメールから直接会議に参加できる利便性が特徴です。
これにより、顧客との打ち合わせや社内ミーティングを効率的に行うことができ、物理的な制約を超えて、どこからでも仕事が可能となります。
CRM(顧客関係管理)は、顧客データを集約し、効果的に活用するためのツールです。
保険業界では、顧客との関係を深め、リピート契約や新規契約を促進するために活用できます。
また、CRMの活用によって顧客情報を一元管理すれば、過去の取引履歴に基づいたパーソナライズされたサービスの提供が可能になります。
代表的なCRMとして挙げられるのがSalesforceとKintoneです。
Salesforceは、強力なデータ分析機能とカスタマイズ性に優れ、営業活動やマーケティング活動の効率を向上させます。
特に、顧客とのインタラクション履歴を詳細に把握することで、契約更新や新商品の提案を最適化できます。
Kintoneは、業務プロセスに合わせて柔軟にカスタマイズ可能で、営業チームが顧客情報を簡単に共有できる点が特徴です。
これにより、チーム全体で顧客対応が統一され、迅速な対応が可能となります。
SFA(営業支援システム)は、営業活動の効率化を図るためのツールで、営業担当者の活動記録や案件進捗の管理をサポートします。
保険業界においても、営業活動の可視化や進捗管理、予測精度の向上は求められているため、SFAの活用は有効でしょう。
代表的なSFAには、Dynamics 365とGENIEE SFA/CRMがあります。
Dynamics 365は、Microsoftのプラットフォームであり、営業活動のデータを一元管理し、AIや機械学習を活用した予測分析が可能です。
これにより、営業チームは最適なタイミングでアクションを起こすことができます。
対して、GENIEE SFA/CRMは、直感的なインターフェースとレポート機能が特徴で、営業活動の進捗をリアルタイムで把握可能です。
保険業界特有の複雑な商談を効率的に管理できるため、営業チームの生産性向上が期待できます。
MA(マーケティングオートメーション)は、保険業界において顧客獲得や既存顧客の維持を効率化するために活用されています。
MAによって顧客の行動データをベースに、自動で適切なマーケティングメッセージを送信可能です。
その結果、顧客一人ひとりのニーズに合った対応ができるため、リード獲得の精度向上が期待できるでしょう。
代表的なツールとして、SATORIとBowNowが挙げられます。
SATORIは、Webサイトやメール、SNSなど複数のチャネルを通じて顧客データを収集し、その情報をもとに個別対応のマーケティングが行えます。
BowNowはシンプルなインターフェースで導入が容易で、顧客の反応を追跡し、自動化されたマーケティングキャンペーンを実施可能です。
これにより、保険業界の競争激化に対応し、効率的に営業活動を支援できます。
BI(ビジネスインテリジェンス)は、データを活用して経営判断をサポートするためのツールです。
保険業界では、膨大な顧客データや契約情報を分析し、営業戦略やサービス改善に活かすために利用されています。
BIツールにより、リアルタイムで業務の進捗や市場動向を把握し、迅速かつ適切な意思決定が可能となります。
代表的なBIとして挙げられるのがLooker StudioとTableauです。
Looker Studioは、データの視覚化と詳細な分析が得意で、営業成績や顧客行動に関する洞察をリアルタイムで提供します。
Tableauは、豊富なビジュアライゼーション機能を有し、複雑なデータセットを直感的に操作できるため、非専門家でも簡単にデータ分析が可能です。
保険業界において、迅速かつ効率的なコミュニケーションを実現するためには、チャットツール導入が有効です。
特に、営業職のように外部とのやり取りが発生する部署にとって、チャットツールは業務を効率化するために役立ちます。
代表的なツールには、SlackとChatworkがあります。
Slackは、リアルタイムでのメッセージ交換だけでなく、ファイル共有や外部ツールとの連携も可能です。
営業チームや保険代理店など、複数の部署で連携を取る場合に効果的です。
Chatworkは、日本国内で広く使われており、シンプルで直感的なインターフェースを持つため、スムーズな情報共有が可能になります。
保険業界において顧客対応やリスク分析、業務自動化において重要な役割を担っているのがAI(人工知能)です。
AIツールを利用すれば、顧客の行動予測や自動化された保険プランの提案が可能となり、業務の効率化と顧客満足度の向上につながるでしょう。
例えばChatGPTはコールセンター向けのトークスクリプトを自動で作成可能です。
一方、Geminiは高度なデータ解析機能を備えており、顧客の購買傾向を分析して、パーソナライズされた提案ができます。
AIを活用することで、保険業界はより効果的に顧客ニーズに応え、サービスの質を向上させることが可能になるでしょう。

保険DXに用いるツールを選定する際は次のようなポイントを押さえておきましょう。
それぞれのポイントを解説します。
保険DX促進のためには、自社の具体的な課題に合ったツールを選びましょう。
保険業界における課題は多岐にわたり、例えば営業活動の効率化や顧客管理の向上、リスク分析の精度向上などがあります。
これらの課題に応じて、適切なツールを選ぶことが大切です。
例えば、営業活動の効率化が課題であれば、営業支援ツールであるSFAの導入が有効です。
一方、顧客データを効果的に管理し活用したい場合は、CRMツールが適しています。
ツール選定の際には、まず自社の課題を明確にし、それにマッチした機能を持つツールを選びましょう。
ツール導入の目的を明確にすることも、ツール選定のポイントです。
保険DXの促進はツールを導入して終わりではありません。
導入したツールによって競合との差別化や新たなサービスの創出など、DXの目的を果たす必要があります。
ツール導入だけで満足しないためにも、なぜツールが必要なのか目的を明確にしましょう。
導入目的を明確にしておけば、導入計画や運用設計もスムーズに進められます。
さらに、目的に対してどれだけの成果が得られているのかの効果測定もしやすくなるでしょう。
保険DXのツール選定において、既存システムとの連携ができるかの確認が欠かせません。
保険会社によっては、既に顧客管理システムや営業支援ツールを導入している場合があります。
そのため、新たに導入するツールが既存のシステムと連携できるかを確認する必要があります。
システム間でデータの共有ができない場合、手作業でのデータ入力や転記が発生し、業務の遅延やミスにつながりかねません。
ツール選定の際には、API連携やインポート・エクスポート機能など、システム同士の互換性を重視し、導入後の運用が円滑に進むように考慮するのがポイントです。
ツール導入後の運用が円滑に進むかどうかは、サポート体制の充実度に依存します。
サポート体制が充実しているツールは、トラブルシューティングや運用におけるアドバイスを提供してもらえるため、導入後の迅速な課題解決が期待できます
ツール選定の段階でどのようなサポート体制が整っているのかを確認しましょう。
例えば、電話もしくはメールだけのサポート窓口ではなく、電話やメール、チャットなど複数のサポート窓口が用意されている場合、トラブル発生時に問い合わせやすくなります。
ツールを選定する際は無料トライアルの有無を確認しましょう。
無料トライアルを利用すれば、ツールが自社のニーズに適しているか実際に試すことができます。
また、トライアル期間中に機能や操作性を確認し、実際の業務にどの程度活用できるかを見極められます。
トライアルによって導入後の学習コストや運用時の問題点を事前に把握できるため、よりスムーズなツール導入につなげられるでしょう。
もし導入を検討しているツールが無料トライアルを提供していない場合、他のユーザーのレビューやフィードバックも参考になります。
ツールの選定時には、オンプレミス型とクラウド型の違いも確認する必要があります。
オンプレミス型は、企業内にサーバーを設置し、システムを自社で管理する方式です。
セキュリティやデータ管理に対する独自の要求がある企業には向いているものの、導入コストや維持費用が高くなることがあります。
一方、クラウド型は、インターネットを通じて提供されるサービスで、サーバーの管理やメンテナンスが不要です。
利用者数や負荷の増減に対応しやすく、初期投資を抑えられるため、中小企業にも適しています。
どちらのタイプが自社にとって最適か、セキュリティ要件や予算、運用コストを考慮して選びましょう。
ツールを選ぶ際に、パッケージ型と簡易開発型のどちらを選択するかを検討することも大切です。
パッケージ型は、業界や業務に特化したソフトウェアが既に完成形として提供されているため、導入までの時間が短縮され、すぐに使用を開始できます。
ただし、企業の特定のニーズに完全に合致するとは限らないため、カスタマイズの余地が限られることがあります。
対して、簡易開発型は、基本的な機能を持ちながらも、自社のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。
長期的な活用が期待できる一方で、導入には開発リソースや時間が必要です。
自社の業務に合ったアプローチを選び、必要な機能を持つツールを見極めることが求められます。
保険業界では実際に専用のツールを用いて保険DXを促進しているケースがあります。
ツールを用いた保険DX促進の事例は次のとおりです。
両社の事例について詳しく解説します。
SBI日本少額短期保険株式会社は生成AIを業務に導入しました。
同社は家財保険事故ケースの保険金支払い事例を匿名化し、生成AIに学習させたことで、社内事故対応業務の効率化を実現しています。
保険商品の理解度は従業員によって異なるため、不明点がある場合、特定部署や従業員らの指示を仰ぐ状況でした。
しかし、生成AIが過去のケースを学習したことで、所属部署や経験値に関わらず、従業員が事故対応業務に対応できるようになりました。
また、生成AIに過去のケースが蓄積されているため、膨大な過去の事故事例から参考となる資料を探し出す工数の削減にもつながっています。
参考:SBI日本少額短期保険株式会社|SBI日本少短、生成AIを活用した社内事故対応業務の効率化を実現
共栄火災海上保険株式会社は、顧客情報と通話履歴の一元管理に取り組みました。
そのために導入したツールがコンタクトセンター向けのCRMです。
以前は複数の異なるシステムで情報が管理されており、業務効率が低下していました。
しかし、FastHelpの導入により、顧客データの自動入力や他システムとの連携が可能となり、業務の効率化と生産性向上につながりました。
具体的には、顧客情報が一元化され、通話録音の簡単な聞き起こしや未完了案件の管理が可能となり、オペレータの負担を軽減できています
さらに、従業員が顧客対応を意識する仕組みを導入し、顧客満足度の向上にも貢献しています。
参考:テクマトリックス株式会社 | FastHelpと他システムとの連携強化でセンターの生産性向上と応対品質向上を実現
保険DXを促進するには、ツール選定だけでなく、次のような注意点も把握しておきましょう。
それぞれの注意点を解説します。
新しいツールの導入時は従業員に周知しましょう。
ツールが効果的に活用されるためには、従業員全員が目的や使用方法を理解し、積極的に利用する必要があります。
導入前にツールの選定理由や期待される効果を共有することで、従業員は変化に対して前向きに取り組めるでしょう。
また、ツールを導入した後も定期的に進捗状況を確認し、従業員からのフィードバックを収集するのもポイントです。
フィードバックをもとに、必要な改善策を講じることで、ツールの活用を最大化できます。
導入したツールを形骸化させないためにも、従業員にツール導入を周知しましょう。
オンボーディングとは、新しいツールやシステムを導入した際に、従業員がそのツールを効果的に使いこなせるようにサポートするプロセスです。
ツール導入時には、オンボーディングを通じて従業員に必要なトレーニングの提供が有効です。
例えば、オンラインの研修セッションやマニュアルの提供によって、従業員がツールの基本的な機能や操作方法を理解しやすくなります。
オンボーディングプロセスを段階的に行うことで、従業員の負担を減らし、スムーズな導入が可能となります。
さらに、サポート体制を整備しておけば、問題が発生した際に迅速に解決できるようになるでしょう。
ツールを導入した後は、どれほどの効果があったのかを定期的に検証しましょう。
効果検証は、ツールが導入目的を達成しているかを評価するために行います。
例えば、業務の効率化や顧客対応の改善が実際に達成されているか、具体的なデータを基に評価します。
効果検証を行うことで、ツールの効果を数値化でき、問題点があれば改善の方向性を見つけられるでしょう。
また、検証結果を関係者に報告し、フィードバックを基にさらなる改善を行うことで、ツールの活用範囲を広げ、効果の最大化が期待できます。
定期的な効果検証を通じて、ツールの運用がより効率的になり、結果的に企業の業績向上につながります。
効果検証にあたってはPDCAサイクルを回しましょう。
PDCAはPlan(計画)から始まり、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のステップを繰り返すことで、徐々に計画をブラッシュアップ可能です。
保険DXを推進するためにはツール選定が有効です。
しかし、さまざまなツールが発表されているため、どれを導入すればよいのか迷ってしまうかもしれません。
保険DXのツール選定に迷ったら『株式会社TWOSTONE&Sons』にご相談ください。
当社は保険会社の課題に応じたITソリューションを提供しています。
また、実践型の研修カリキュラムも提供しているため、従業員のITリテラシー向上にもつながります。

保険DXを推進するためには、専用のツール導入が欠かせません。
SFAやCRMなどのツールを導入して、自社の業務効率向上などを目指しましょう。
ツール選定にあたっては自社の課題の洗い出しや既存システムとの連携可否、サポート体制などを確認することが大切です。
十分に検討せずに導入すると、期待した成果が得られず保険DXが停滞しかねません。
また、導入後の従業員への周知や効果検証実施など、導入してからの体制構築も成果を引き出すためのポイントです。
自社に合ったツール選定によって保険DXを成功につなげましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
