保険DX推進に必須なコンプライアンス対策|内部統制と監査のデジタル化
保険

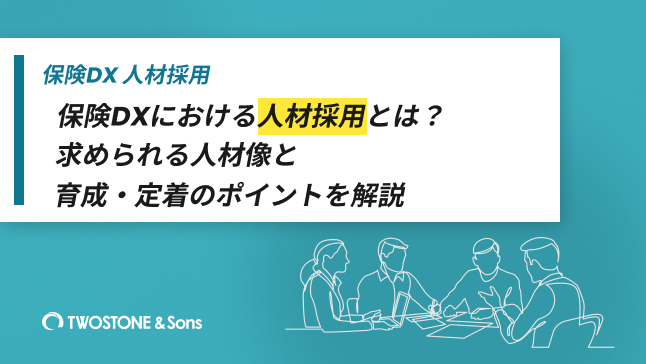
保険DXを推進するには、業務理解とITスキルを兼ね備えた人材の確保が重要です。本記事では、求められる人材像や採用・育成の課題、成功事例をもとに、人材採用の実践ポイントをわかりやすく解説します。
近年、保険業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する中で、「どのような人材を採用すべきか」「どう育成し定着させるか」といった人材戦略の重要性が一段と増しています。AIやクラウドなどの技術導入だけでは、DXは成果につながりません。業務への深い理解と変革を推進するマインドを併せ持つDX人材の確保こそが、保険業界の未来を左右するといえるでしょう。
本記事では、保険DXに求められる人材像や採用時の課題、成功のための工夫、さらに先進企業の事例も交えながら、戦略的な人材採用のヒントを解説します。

保険業界では、契約手続きのデジタル化やAIによる査定業務の自動化など、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みが急速に進んでいます。しかし、これらの施策を成功に導くには、単なる技術導入にとどまらず、それを企画・運用・改善できる人材の確保が不可欠です。業界特有のレガシーシステムや紙文化が根強く残る中で、業務理解とデジタル知識を併せ持つ人材は極めて貴重な存在となっています。
さらに、従来の保険営業モデルから、顧客接点の最適化や体験価値の向上を重視する方向へと価値観がシフトしており、「テクノロジーを活用して何を実現するか」を構想・推進できる人材へのニーズが高まっています。こうした背景から、保険DXに特化した人材採用・育成の取り組みは、企業の競争力を左右する戦略的課題として注目を集めているのです。
保険DXを推進する上で鍵となるのが「どのような人材が変革を担えるか」の明確化です。AIやRPAといったテクノロジーの導入にとどまらず、顧客接点の再設計や業務フロー全体の見直しなど、DXには多面的な視点と実行力が求められます。保険業界特有の商習慣や法規制への理解と、ITスキルの両立が不可欠であり、従来の専門人材とは異なる新たな人材像が浮かび上がっています。
ここでは、保険DXを成功へ導くために求められる人材像を5つの観点から見ていきましょう。
保険業界には、引受や査定、契約管理など複雑で専門的な業務が数多く存在します。一方で、DXを推進するには最新のテクノロジーへの理解が欠かせません。この両者を橋渡しできる「ハイブリッド人材」は、現場と開発サイドの共通言語を持ち、実務に即した形でテクノロジーを活用する推進役として重宝されます。
例えば、紙での手続きを前提とした業務をRPAやOCRで自動化する際、業務フロー上の制約や例外処理に精通しているかどうかで導入のスムーズさは大きく異なります。単なるITスキルだけでなく、現場に即した理解と調整力を兼ね備える人材こそがDXを実行可能な計画へと落とし込む存在といえるでしょう。
DXは既存の業務プロセスや組織体制に大きな影響を与える「変革」です。そのため、導入には現場の不安や抵抗も伴います。そこで重要となるのが、関係者の理解と協力を得ながらプロジェクトを牽引できるリーダーの存在です。
単に技術的な知識があるだけでなく、組織のビジョンを描き、関係者を巻き込んで進めていける推進力やコミュニケーション能力が求められます。特に保険業界では、支社・営業・契約管理など部署をまたぐ連携が不可欠となるため、各部門の利害を調整しながら合意形成を図れるリーダーシップがDXの成否を左右します。戦略を語れるだけでなく、現場に根を張って動ける実行型のリーダーが必要です。
保険DXの推進においては、技術や顧客ニーズ、法制度の変化に迅速に対応する柔軟性が欠かせません。従来型の一括導入型プロジェクトよりも、段階的に試行錯誤しながら進める「アジャイル型」のアプローチが主流になりつつあります。そうした中で求められるのが、変化を前向きに捉え、常に学びながらスピーディーに実行できる「アジャイル人材」です。
例えば、保険商品に新たなデジタルサービスを組み込む際には、リリース後の利用状況に応じて即座に改善策を講じる必要があります。計画通りに進めることだけを重視するのではなく、「小さく始めて素早く学び、次につなげる」姿勢がDXには欠かせません。業務経験の多寡に関わらず、自ら新しい技術やフレームワークに関心を持ち、変化に適応できる人材が、DXを内製化していく土台となります。
デジタル技術の導入が目的化してしまうと、本質的な価値創出にはつながりません。保険DXでは「誰の、どんな課題を解決するのか」という視点が極めて重要であり、ユーザー起点で発想できる人材の存在がプロジェクトの方向性を左右します。
特に保険業界では、高齢者やデジタルに不慣れな層も多く存在するため、画一的なUI/UXでは十分な利便性を提供できません。顧客の声に耳を傾け、体験価値の向上にこだわる姿勢が欠かせません。例えば、請求手続きの簡素化やチャットボットによるサポートなど、利用者にとっての「わかりやすさ」「使いやすさ」を徹底的に考え抜く力が求められます。
保険契約や給付請求といったシーンで「安心」「信頼」を感じてもらえるサービス体験を設計できるユーザー志向の人材は、顧客ロイヤルティの向上にも大きく貢献します。
DXにおいてデータは単なる副産物ではなく、意思決定の根拠そのものとなります。特に保険業界では、契約情報・請求履歴・健康診断データなど多様かつセンシティブな情報を扱っており、これらを活用して商品設計やサービス改善につなげる「データドリブン人材」が不可欠です。
このタイプの人材には、データの収集・分析だけでなく「なぜその施策を打つのか」をロジカルに説明し、社内の合意を形成する力が求められます。また、現場から経営層まで異なる視点でのアウトプットを設計し、ビジネス全体にインパクトを与えるための指標設定や可視化スキルも重要です。
データリテラシーは一部門の専門スキルではなく、DXを進める全員に求められる素養です。特に中心となるデータドリブン人材は、保険ビジネスの意思決定を科学的に支える「頭脳」として組織の中核を担う存在となります。

保険業界におけるDX人材の採用は、単にITスキルの高い人材を獲得すれば良いというものではありません。業界特有の業務知識、法規制、顧客層への理解など、保険ビジネスの本質を押さえた人材が求められるため、採用活動では多くの課題に直面します。ここでは、DX人材採用においてよく見られる3つの障壁を解説します。
DX人材はさまざまな業界で需要が高まっており、特にデジタル人材の獲得競争が激しいIT・スタートアップ業界との比較で、保険業界は「魅力的なキャリア」として認知されづらいのが現状です。結果として、応募者が少なく、書類選考の段階で適任者が見つからないという企業も少なくありません。
加えて、DXの経験を持つ中堅人材は転職市場でも高年収帯に位置することが多く、給与水準・働き方・成長環境などの面で他業界と比較されやすい傾向があります。母集団形成の段階でつまずくと、組織にとっての最適な人材との出会いのチャンスがそもそも生まれないため、採用活動全体の見直しが求められます。
DX人材を採用できたとしても「配属先の既存職種」とのミスマッチが起こるケースは少なくありません。例えば、エンジニアやデータアナリストとして採用された人材が、保守的な業務フローに組み込まれてしまい、本来のスキルを発揮できずに終わるといった事例もあります。
保険業界では法規制や業務特性から変更に慎重な文化が根強く、革新的な提案が受け入れられにくい土壌も一部に残っています。こうした文化的な壁を乗り越えるには、事前に職種の目的や役割、期待成果を明確にした上で、チーム間の相互理解を促進する仕組みが不可欠です。
保険業界では、採用後1年未満でDX人材が離職してしまうケースも見受けられます。これは主に、入社前後のギャップが大きいこと、あるいは社内での受け入れ体制が整っていないことに起因しています。
例えば「裁量を持って施策を進められると思っていたが、実際は決裁プロセスが多くスピード感に欠けた」といった不満や、「DXに対する理解が限定的で、周囲と連携が取りにくかった」といった孤立感が離職要因になります。
定着率の向上には、採用時点での現場とのすり合わせに加え、入社後のオンボーディング・定期的なフォローアップ・メンタリング制度など、入社後のケアと組織内での適切な配置が欠かせません。採用はあくまでスタートであり、育成と活躍支援までを含めた「戦略的人事」が求められています。
保険業界でDXを成功させるには、単に人材を募集するだけでなく、「誰を」「どのように」「どこに」採用・配置するのかを具体的に設計することが不可欠です。ここでは、採用活動を効果的に進め、DX人材の定着と活躍につなげるための3つの実践的な工夫を紹介します。
DX人材の採用において最初に重要なのが「どのような業務に、どんな能力を持つ人が必要なのか」を明確にすることです。曖昧な募集条件では、応募者とのミスマッチが生じやすくなります。
例えば「データ活用を推進する人材」とひとことでいっても、求められるスキルは統計解析・BIツール操作・機械学習モデルの構築など多岐にわたります。そのため、職種ごとに求めるスキルや経験をリスト化し「スキルフレーム」として社内で共有・定義しておくことが大切です。
このスキルフレームを活用すれば募集要項の精度が高まり、採用後の期待値とのギャップも減らせるため離職リスクの低下にもつながります。
優秀な人材を採用しても、社内の受け入れ体制が不十分であれば、力を発揮できないまま離職してしまう可能性があります。特に、デジタルに慣れていない現場部門との協業が求められる保険業界では、DX人材と既存組織との文化的摩擦が起きがちです。
この問題に対応するためには、DXを推進する意義を経営層から明確に発信し、現場部門と新たに加わる人材の双方に対して「なぜ変革が必要なのか」「どんな役割を担うのか」を丁寧に説明することが求められます。
さらに、DX推進に関する社内研修やワークショップを設け、社員全体の理解促進と協力体制の醸成を図ることも有効です。
採用活動においては、主観的な印象だけでなく、客観的なデータに基づいた評価を取り入れることが成功のカギとなります。そこで有効なのが、HRテック(人事領域のテクノロジー)やアセスメントツールの活用です。
例えば、適性検査・スキル診断ツールを使えば、応募者の論理的思考力・学習能力・DX業務に必要な行動特性などを可視化できます。また、過去の採用データや活躍人材の特徴を分析し、自社にとってフィットする人材像をデータとして明らかにすることも可能になります。
こうしたツールを取り入れることで、選考精度の向上だけでなく、内定後の育成プラン策定にも役立ち、長期的な人材活用の土台を築くことができます。
DX人材の採用が難航する中、社内人材の育成・リスキリングによって戦力化を図る企業が増えています。既存社員は業務知識や社内文化への理解が深く、DXスキルを獲得することで即戦力となる可能性が高いため、育成による人材確保は中長期的に大きな効果をもたらします。
外部のDX専門家と共同することは、社内にない知見や経験を活用し、保険DXの推進を加速させる有効な手段です。特に導入初期のフェーズでは、課題の可視化や実行プランの立案、業界動向を踏まえた技術選定などにおいて高い効果が期待できます。また、社内のプロジェクトメンバーと専門家が密に連携することで、現場に即した実践的な知識を習得でき、将来的な内製化や人材育成にもつながります。外部の知見を借りながら、継続的に学びを深める姿勢が重要です。
育成したDX人材を点で終わらせず、組織的に活用するには「DX推進チーム」の立ち上げが有効です。部門横断で構成された小規模なチームが、業務改善や新技術の検証を主導することで、DXの社内展開を加速させます。
さらに、外部パートナーやコンサルタントによる伴走支援を受けることで、DX人材が学んだ知識を実務に落とし込みやすくなり、成果にもつながりやすくなるでしょう。段階的な目標設定と内製化支援の体制を整えることで、継続的なDX人材の活用が可能になります。
デジタル変革が加速する中、保険業界でもDXを支える人材の採用・育成が急務となっています。特に、業務知識とテクノロジーを兼ね備えた人材の確保は、多くの企業にとって大きな課題です。ここでは、実際にDX人材の確保や育成に成功している保険会社の取り組みを紹介し、自社の参考となるポイントを解説します。採用から育成、定着までの一貫した戦略を学ぶことで、自社のDX推進にも活かせるヒントが見つかるでしょう。
住友生命では、デジタル人材の外部登用に頼るのではなく、既存のシステムエンジニア職を対象に、社内育成によるDX人材の発掘と強化を進めています。背景にあるのは、健康増進型保険「Vitality」の開発・提供に伴う事業モデルの転換です。
そこで求められたのが、テクノロジーに加えてビジネス感覚やプロジェクト推進力を兼ね備えたハイブリッド人材です。同社ではこれに対応すべく、「Vitality DX塾」など独自の教育プログラムを通じた育成に加え、イノベーティブ人財診断・人間力診断・DX検定の3種のアセスメントを活用し、適性ある人材を社内から発掘しました。
こうした取り組みにより、DXプロジェクトではエンジニアが企画段階から関与し、ビジネス視点で課題解決をリードする体制が構築されました。
参照:住友生命保険相互会社|アセスメントで適性を見極め、ビジネスセンスを醸成。住友生命保険が取り組むDX人材育成
アフラック生命保険株式会社では、DXを通じて「生きるための保険」のリーダーとなるべく、デジタルテクノロジーの活用と同時に、DXを牽引する人材の育成にも力を入れています。特に注目されるのが、全社員の約3割をDX人材に育てるという明確な目標のもと、2022年からスタートした「DX人財育成プログラム」です。
このプログラムでは、テクノロジーの基礎知識はもちろん、データサイエンスやユーザー体験(UX)に対する理解など、幅広い視点からのスキル習得を支援しています。単なる座学にとどまらず、デザイン思考やアジャイル開発手法を取り入れた実践型の学習スタイルを採用しているのが特徴です。
さらに、自社開発のクラウド型サービス「ADaaS(Aflac Digital as a Service)」を通じて、営業活動や顧客対応をデジタルで支えるインフラ整備も進めています。
株式会社かんぽ生命保険では、「CX(顧客体験)向上のためのDX推進」を旗印に、リアルとデジタルを融合させた業務効率化と体験価値の向上に取り組んでいます。そうしたなか、2022年度から始まったのが「新卒デジタル採用」です。中長期的な視点で、生命保険業に精通したデジタル人材の育成を目的としたこの取り組みは、現場OJTだけでは補えない教育課題を浮き彫りにしました。
この課題を受け、株式会社かんぽ生命保険は、AVILEN社と連携し、同社の知見をもとに「DX人材向けスキル定義と育成計画」の策定に着手します。目指すべき人材像を明確にし、職場ごとに異なる業務ニーズとのバランスを取りながら、部門横断での教育体系を再設計しました。育成ロードマップでは、OJTとOFF-JTの効果的な配分や、部門ごとの教育ギャップの解消が図られています。
参照:かんぽ生命が「新卒デジタル採用」人材向けの育成ロードマップを策定 – AVILENがスキル定義から育成計画まで総合支援
保険業界におけるDX推進には、適切な人材の採用と育成が不可欠です。『株式会社 TWOSTONE&Sons』では、保険業界特有の業務構造とDXに求められるスキル要件を理解した上で、戦略的な人材採用をサポートします。採用戦略の立案からスキル要件定義・HRテックの活用による候補者評価・オンボーディング支援まで、一貫したサービスを提供しています。さらに、採用後の定着支援やリスキリング施策の設計にも対応しており、クライアントの成長戦略と人材戦略をつなぐ伴走型の支援が可能です。DX人材の採用・育成でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

保険DXの推進は、単なる技術導入にとどまらず、企業文化や人材戦略の変革が求められます。成功のカギを握るのは、自社に合ったDX人材の採用と育成、そしてそれを支える明確なビジョンと継続的な体制づくりです。
テクノロジーと業務を横断的に理解するハイブリッド人材、変革を牽引できるリーダー層、顧客体験を重視した視点など、多様なスキル・志向を持つ人材が不可欠です。加えて、社内リスキリングや外部パートナーとの協働も重要なポイントとなります。
DXを単なるプロジェクトで終わらせず、企業成長のエンジンとして定着させるために──まずは人材採用・育成から、始めていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
