保険DX推進に必須なコンプライアンス対策|内部統制と監査のデジタル化
保険

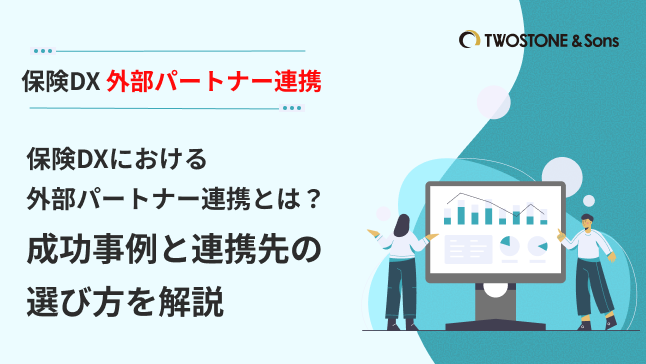
保険DXを成功させるには外部パートナーとの連携が不可欠です。本記事では、連携のメリットや成功事例、パートナーの選び方、リスク対策や推進ポイントまで詳しく解説しています。社外との共創を通じて、自社のDXを効果的に前進させましょう。
DX(デジタルトランスフォーメーション)が保険業界にも本格的に求められる中、社内の人材やリソースだけで変革を完遂するのは困難になっています。そこで注目されているのが、外部パートナーとの連携によるDX推進です。ITベンダーやコンサルティング会社、InsurTech(インシュアテック)企業など、社外の知見を戦略的に活用することで、業務効率の向上や新サービスの創出につながる事例も増えています。
本記事では、保険DXにおける外部パートナーの活用方法を中心に、メリット・成功事例・パートナー選定時のポイント・リスクとその対策までを幅広く解説します。自社DXを加速させたい企業は、ぜひ最後までご覧ください。

保険業界においてDXを推進するには、単なるシステム導入にとどまらず、業務プロセスの変革や顧客接点の最適化など、企業全体を巻き込んだ取り組みが求められます。しかし、社内の人材だけでこれらの変革をリードするのは容易ではありません。
特に保険会社は、レガシーシステムの存在や規制対応といった業界特有の制約があるため、柔軟かつ専門的な対応ができる外部の知見が不可欠です。例えば、AIやビッグデータ解析に強みを持つIT企業と連携すれば、保険引受の精度向上や契約者の行動予測が可能になります。
このように、外部パートナーとの連携は、社内に不足する技術・知識・実行力を補完し、DXの成功確率を高めるうえで重要な要素です。
保険DXを推進する際には、目的や課題に応じて最適な外部パートナーを選定・活用することが重要です。外部パートナーには、システムインテグレーター・クラウド事業者・InsurTech企業・コンサルティング会社など多様な種類があり、それぞれに異なる強みと役割があります。この章では、パートナーの主な分類と役割、そして効果的な活用のポイントについて解説します。
近年、保険業界における外部連携の動きが加速している背景には、いくつかの構造的な変化があります。まず、保険契約や顧客接点が急速にデジタル化する中で、従来の自社内完結型のアプローチでは対応しきれない局面が増えていることが挙げられます。また、AI・ビッグデータ・クラウドなど、急速に進化するデジタル技術を活用するには、それらに精通した外部の専門性が不可欠です。
さらに、経済産業省や金融庁も業界全体のDXを後押ししており、保険各社は持続可能な経営のためにスピード感ある変革が求められています。そのため、IT企業・コンサルティングファーム・InsurTechベンチャーなどとの連携を通じて、自社の限界を超えた変革に挑む企業が増えているのです。
参考:経済産業省|デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)
外部パートナーとの連携には、多くのメリットがあります。第一に、専門性の高い知見や技術を迅速に導入できる点です。例えば、AIによる保険引受の自動化、チャットボットによる顧客対応、基幹システムのモダナイズなど、社内だけでは対応が難しい領域にも取り組みやすくなります。
第二に、プロジェクト推進のスピードアップが図れる点です。経験豊富な外部人材の参画により、要件定義やシステム実装などを短期間で進められるようになります。さらに、客観的な第三者の視点を取り入れることで、自社だけでは気づけない課題や改善点が見えるようになるのも大きな利点です。
外部パートナーと連携する際には、いくつかの注意点があります。まず重要なのは、「目的の共有」です。単なる外注先ではなく、DXのゴールに向けて一緒に歩むパートナーである以上、ビジョンや目的を最初にしっかりとすり合わせる必要があります。
次に、連携の実効性を高めるには役割分担の明確化が欠かせません。社内の推進体制とパートナー側の担当範囲を明確にし、プロジェクト進行中の意思疎通が滞らないようにすることが大切です。
また、パートナー選定時には業界知識・過去の実績・担当者との相性なども慎重に確認する必要があります。特に保険業界は法規制や顧客対応において特有の要件が多いため、業界経験のある企業・チームを選ぶとスムーズに進めやすくなるでしょう。
このように、外部連携は単なる委託ではなく、戦略的なパートナーシップとして捉えることが成功のカギとなります。
保険DXを加速するうえで、他業界との連携やテクノロジーパートナーとの協業は欠かせない要素です。実際、先進的な保険会社では、AIやクラウド、データマネジメントなどの領域で外部パートナーを活用し、業務の高度化や新たな顧客価値の創出に成功しています。ここでは、具体的な企業の取り組み事例をもとに、外部連携の効果や実現プロセスを見ていきましょう。
株式会社NTTデータは、保険DX推進のパートナーとして多くの実績を持つIT企業です。特に、同社が注力しているのがBPS(Business Process Services)とAIの融合による業務の高度化です。BPSとは、保険会社の業務プロセスそのものを外部のパートナーが受託・運用する仕組みであり、業務効率化とコスト削減を同時に実現するアプローチとして注目を集めています。
NTTデータは、長年にわたりシステムの開発や運用を担ってきた経験と技術力を活かし、業務処理の自動化や、顧客データの利活用基盤の構築を支援しています。特に、AIによる引受査定のサポートや顧客対応チャットボット、ナレッジベースの最適化など、顧客接点に直結する業務を対象にした施策を多数展開している点が特徴です。
参照:DATA INSIGHT|データ活用による「保険DX」で導く保険業界の未来像
第一生命保険株式会社は、自社のDX戦略の中核となるIT基盤DMAP(Data-Management Analytics & Platform)を構築するにあたり、エンタープライズクラウドデータ管理のリーディング企業であるインフォマティカと連携しました。データの利活用を加速させるために、リアルタイム連携が可能なインフォマティカの製品群を採用し、社内外の膨大なデータを一元的に管理・活用できる環境を整備したのです。
DMAPの導入により、社内各所に分散していた情報資産が統合され、ユーザー自身が必要なデータを検索・抽出・加工できる仕組みが整いました。このデータ基盤は、顧客の健康状態を支援するサービス開発や、引受査定の高度化などにも活用され、保険ビジネスの変革を後押ししています。
参照:インフォマティカ|第一生命、DX戦略の柱となるIT基盤「DMAP」構築にインフォマティカ製品を導入
アフラック生命保険株式会社は、「DX@Aflac」の取り組みの一環として、保険業界の枠を超えた新たな価値提供を実現するためのクラウド型デジタルサービス基盤ADaaS(Aflac Digital as a Service)を開発・運用しています。ADaaSは、顧客・販売代理店・ビジネスパートナーといった多様なステークホルダーをデジタルでつなぐことを目的に構築されたもので、利用者は目的に応じた機能を柔軟に選択・活用可能です。
この基盤により、アフラックはInsurTech企業との協業も積極的に展開しています。例えば、AIやIoTを活用した募集人支援サービスや、顧客ニーズに応じた商品提案を実現するデジタルマッチング機能などを実装し、リアルとデジタルの融合による感動的なユーザー体験の提供を進めています。
参照:DX@Aflac | アフラックの価値創造ストーリー | 企業情報

外部パートナーとの連携は、保険DXを加速させる大きな推進力となる一方で、プロジェクト進行におけるさまざまなリスクも孕んでいます。特に情報セキュリティや品質管理、契約上の合意形成など、事前に備えておくべき課題は多岐にわたります。ここでは、代表的なリスクとその対策について整理し、安心して連携を進めるためのポイントを見ていきましょう。
保険業界では顧客の個人情報や契約データなど、機微な情報を多数扱うため、外部パートナーとの情報共有には高度なセキュリティ対策が不可欠です。クラウドサービスやAPIを介した連携が一般化する中で、情報漏えいや不正アクセスのリスクは常に存在します。
対策としては、ISO 27001やSOC2といった情報セキュリティ認証の取得状況をパートナー選定基準とすることが有効です。また、ゼロトラストアーキテクチャの導入や、通信データの暗号化、アクセス権限の厳格な管理の徹底により、セキュリティレベルの向上が期待できます。
外部ベンダーとの共同プロジェクトでは、納期の遅延や成果物の品質に関するトラブルが起こりやすいのが現実です。要件の認識差や進行管理の不徹底が原因となり、予定していた効果が得られないケースも見受けられます。
こうしたリスクを防ぐためには、初期段階での要件定義とゴールのすり合わせを丁寧に行うことが重要です。加えて、進捗管理を支援するプロジェクトマネージャー(PM)の配置、アジャイル開発やウォーターフォールの適切な手法選択、定期的なレビュー体制の構築も効果的です。ベンダーとのコミュニケーションを密に保つことで、早期のリスク検知と対処が可能になります。
外部パートナーとの協業においては、プロジェクトの遂行に関するルールや責任分担を明確に定めた契約の整備が欠かせません。曖昧な契約内容では、トラブル発生時の対処や責任所在が不明確となり、重大な損失につながるリスクがあります。
契約時には、成果物の定義・納期・知的財産権の帰属・損害賠償の範囲などを明文化することが基本です。さらに、業務委託だけでなく、共創型のパートナーシップの場合は、意思決定プロセスやコンフリクト時の対応手順も含めたガバナンス体制の整備が求められます。両社間の信頼関係を築き、合意形成の場を適切に設けることが、安定した協業体制を構築するカギとなります。
外部パートナーと協力してDXを推進する際、単なる業務委託にとどまらず、共通のゴールに向けた協働体制の構築が重要です。特に、経営視点でのビジョン共有や、データ基盤の整備、継続的な改善プロセスなど、複数の要素をバランスよく整えることで、プロジェクトの成功確度が高まります。ここでは、外部パートナーとの連携を円滑かつ効果的に進めるための5つのポイントを解説します。
DXは単なるシステム刷新ではなく、企業のビジネスモデルや価値提供のあり方そのものを変革する取り組みです。そのため、現場レベルの施策だけではなく、経営層が明確なビジョンを提示し、自らの言葉で社内外にメッセージを発信することが不可欠です。
また、外部パートナーに対しても、経営層の直接コミットにより、連携の重要性や全社的な優先順位が明確となり、協働体制の質が高まります。トップダウンでの牽引力と、現場との双方向のコミュニケーションの両立をもって、DXはより実効性を伴ったものとなります。
DXを進めるうえでの土台となるのが、データ活用の基盤です。顧客情報、業務プロセス、外部環境データなどを横断的に扱える環境を整えることで、外部パートナーとの連携の質も飛躍的に向上します。
特に重要なのは、サイロ化された業務情報を統合し、現状の業務プロセスを「見える化」することです。業務可視化によってボトルネックが明らかになり、どこにテクノロジーを適用すべきかが明確になります。また、共通の業務理解があることで、外部パートナーとの技術検討やシステム設計も円滑に進められるようになります。
外部パートナーとの関係を単なる委託先と発注元にとどめるのではなく、共創型の関係へと発展させることが、DX成功のカギを握ります。特に保険業界では、規制対応や既存システムとの連携など、業界特有の課題を踏まえた柔軟なアプローチが求められるため、協業相手との信頼関係が不可欠です。
共創型の関係を築くためには、課題やゴールを早期に共有し、要件定義・企画段階からパートナーを巻き込むことが重要です。また、対話を通じてお互いの専門性を活かし合い、新しい価値をともに生み出す姿勢を持つことで、形式的な協力に留まらない、真の意味でのパートナーシップが実現します。
DXは一度の取り組みで完結するものではなく、継続的な改善と進化が求められます。そのためには、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)というPDCAサイクルを仕組み化し、日常業務の中に組み込む必要があります。
特に外部パートナーと連携する場合、定期的なレビュー会議や振り返りの場を設け、目標の進捗や実行上の課題の共有が大切です。また、フィードバックループを速やかに回すための仕組みを構築することで、スピード感を持った改善が可能になります。
外部パートナーとのDXプロジェクトにおいては、曖昧な期待値ではなく、成果を定量的に可視化できるKPI(重要業績評価指標)の設定が重要です。例えば契約手続きのデジタル化率・顧客対応の平均所要時間・CXスコアの向上など、業務改善や顧客価値向上に直結する指標を選定しましょう。
また、KPIは社内だけでなく外部パートナーとも共有し、共通の目標として管理することが大切です。これにより、双方のモチベーションが一致し、成果志向の協働体制が生まれやすくなります。KPIに基づいた定期的な評価と改善は、プロジェクト全体の質を高める強力なツールとなります。
DXを推進するうえで外部パートナーとの連携は不可欠ですが、その前提として社内の体制整備と役割の設計が重要となります。どこを自社で担い、どこを外部と連携すべきか、その方針が曖昧なままでは、プロジェクト全体が不明瞭になり、成果も限定的になります。ここでは、外部との協業を見据えた戦略設計の進め方について、具体的な観点から見ていきましょう。
DX推進においては、企画・設計・開発・運用といった各フェーズにおける「誰が、何を担うのか」を明確に定義する必要があります。自社で担うべき業務(例:顧客体験設計、コア業務の判断など)と、外部に委託すべき領域(例:システム開発、クラウド環境の構築など)を峻別することで、効率的な役割分担が可能となります。
重要なのは、内製化すべき領域とパートナー活用で価値を最大化できる領域の見極めです。初期段階での役割整理とドキュメント化は、後のトラブル回避にもつながります。
成功するDXプロジェクトでは、外部パートナーを単なる業務委託先としてではなく、企画段階から一緒に検討し、継続的に対話・調整できる共創パートナーとして位置づけています。そのためには、社内に専任の推進チームを設け、社外とのハブとしての機能を果たす体制が不可欠です。
このチームは、プロジェクトの進行管理だけでなく、業務要件の整理、現場との調整、成果のフィードバックなど多面的な役割を担います。社内外の専門性を掛け合わせることで、実効性のあるDX施策が生まれます。
外部パートナーとの協業を成功させるためには、スモールスタートが有効です。最初から大規模な改革を目指すのではなく、まずは特定業務や部門に限定した小規模なプロジェクトで検証を行い、成功モデルをつくることが鍵となります。
この段階で得られた知見や改善点をもとに、全社展開に向けたロードマップを段階的に設計することで、リスクを抑えつつ着実にDXを拡張可能です。スモールスタートは、パートナーとの相性や実行力を見極める試金石にもなり、持続可能なDXの土台を築く第一歩となります。
自社だけでのDX推進に限界を感じている、パートナー選びで迷っている──そんな保険業界の皆さまにこそ、『株式会社 TWOSTONE&Sons』の伴走支援をおすすめします。
当社は、保険業界をはじめとする保険分野において豊富な支援実績を持つDX支援企業です。デジタル戦略の立案からシステム導入、社内浸透施策に至るまで、企業の課題やビジョンに寄り添った柔軟な提案力が強みです。
特に、ビジネスとテクノロジーの橋渡しとなる共創型DX支援に注力しており、顧客ごとのフェーズや体制に応じた最適なパートナー体制を構築いたします。自社に合ったパートナー選びでお悩みの際は、ぜひ一度『株式会社 TWOSTONE&Sons』へご相談ください。課題の本質に寄り添い、確かな実行力で貴社のDXを支援します。

保険業界のDX推進は、社内リソースだけでは限界があります。変化の激しい市場環境やテクノロジーの進化に対応するためには、専門性を持った外部パートナーとの戦略的な連携が欠かせません。
本記事では、外部連携の重要性とその分類、成功事例、そして注意点や進め方のポイントまで幅広く解説してきました。DXの成果を最大化するためには、経営層の明確なビジョンと共有、データ基盤の整備、KPIの明確化など、パートナーと共に推進するための体制づくりが求められます。
「どこから始めればいいかわからない」「社外連携に不安がある」という場合は、実績豊富な支援企業への相談がおすすめです。信頼できるパートナーと共に、自社のDXを次のステージへ進めていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
