物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

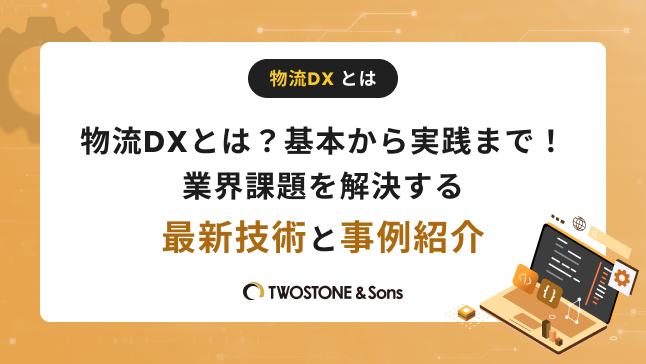
EC(エレクトロニック・コマース)サイトで注文した商品が、翌日や当日に届くことは、今や当たり前のように感じられるかもしれません。
現在、物流業界は深刻な人手不足や働き方改革に関連する「2024年問題」など、さまざまな課題に直面しています。物流業界の課題により、私たちの当たり前の便利さが今、大きく揺らぎ始めています。
そこで注目されているのが、「物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)」です。人手や時間に頼らない持続可能な仕組みづくりが業界内での急務となっています
この記事では、物流DXの基本的な考え方から、なぜ今必要とされているのかをわかりやすく解説します。導入ステップや大手企業の成功事例も紹介していますので、参考にしてください。

物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して物流業界全体を根本から変革する取り組みです。
単なるシステム導入やIT(人工知能)化とは異なり、業務プロセスやビジネスモデル自体を抜本的に見直すことが特徴です。これにより、従来の課題を解決し、新たな価値を創出できるようになります。
物流DXは、人手不足や配送需要の急増などの業界課題に対する根本的な解決策として注目されています。以下より、DXの基本概念から理解していきましょう。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、デジタル技術を使ってビジネス全体を変革することです。経済産業省の定義では、「デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと」とされています。
多くの企業が取り組む背景には、急速に変化する市場環境への対応を迫られている点があります。ただし、単に紙をデータ化するだけではDXではありません。重要なのは、データを活用して新しい価値を創出し、ビジネスの仕組み自体を根本から変えることです。
出典参照:そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か(2/9)|経済産業省
物流業界におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション)は、業界全体の変革において重要な取り組みです。人手不足や2024年問題など、物流業界が直面する課題は深刻です。これらの課題を解決するためには、従来の手法だけでは限界があります。
物流DXでは、AI(人工知能)やIoT(インターネット・オブ・シングス)などの最新技術を活用し、倉庫業務や配送プロセスを最適化します。社会を支えるインフラとしての役割を果たし続けるために、物流DXは不可欠な戦略です。
従来の物流システムと物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の違いは、「判断基準がどこにあるか」です。これまでは、熟練スタッフの経験や勘に頼っていました。例えば、配送ルートの決定や倉庫内レイアウトなど、ベテランの知識に依存する業務が中心でした。
一方、DX化された物流では、データが全ての判断基準です。AIが最適解を導き出し、誰が作業しても同じ品質を維持できるようになっています。経験と勘から、客観的なデータ活用へのシフトこそが、両者の根本的な違いでしょう。
物流業界は現在、複数の深刻な課題が同時に押し寄せる厳しい局面にあります。EC(エレクトロニック・コマース)市場の急拡大で配送需要が増す一方、ドライバーの慢性的な人手不足と高齢化が深刻化し、働き方改革関連法による2024年問題も業界を圧迫しています。
これらの課題が複雑に絡み合う今、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の重要性を理解するため、まずはEC市場拡大の影響を見ていきましょう。
インターネット通販は、現代生活に不可欠なものとして定着しました。スマートフォン1つで商品を注文し、翌日に受け取れる利便性は大きな魅力と言えます。
しかし、利便性の裏側で、物流現場には大きな負担がかかっています。法人向けの大口輸送と比べ、個人宅への「小口配送」が爆発的に増加しました。一つひとつの荷物は小さく、配送件数が増えても運賃収入は伸び悩みがちです。
不在による「再配達」の問題も重なり、現場の疲弊は限界に近づいているのが現実です。社会の利便性を維持しつつ、持続可能な物流を実現するための仕組み作りが求められています。
増え続ける荷物とは対照的に、物流の現場を支える担い手は減少し続けています。特にトラックドライバーの不足は、業界全体が抱える長年の課題といえます。「長時間労働」「荷待ち時間が長い」などの厳しい労働環境のイメージが根強く、若者から敬遠されがちなのが実情です。
さらに深刻なのが、現役ドライバーの高齢化です。実際に、トラック運転者(大型・中小型)の平均年齢は46.7歳となっており、全産業平均よりも高く、50代以上も大きな割合を占めています。このままでは、経験豊富なベテラン層が一斉に退職する将来、社会インフラとしての物流が機能不全に陥る恐れさえあるでしょう。
出典参照:令和5年版 国土交通白書 第Ⅱ部 関連データ集(7ページ)|国土交通省
深刻な人手不足に追い打ちをかけるのが、働き方改革関連法に基づき、2024年4月1日に適用を開始した「2024年問題」です。ドライバーの時間外労働に対して、年間960時間という上限が設けられました。ドライバーの健康を守り、過酷な労働環境を改善するために必要な法案です。
その一方で、これまでと同じやり方では1人のドライバーが運べる荷物量や走行距離が減ってしまいます。結果として、運送会社の売上減少やドライバー自身の収入減につながる可能性が懸念され、労働環境の改善が収入を圧迫しかねないジレンマを抱えています。
コスト面でも物流業界は厳しい状況にあります。昨今の不安定な世界情勢は原油価格の高騰を招き、トラック輸送に不可欠な軽油価格も高止まりしています。
運送コストの中でも燃料費は大きな割合を占めるため、運送会社の経営を直接圧迫しています。特に、2024年後半から2025年春にかけては160円台の推移が常態化しており、2025年4月には 169.4円/L のピークも記録しています。
こうした燃料価格の高騰は、運送コストの中でも大きな割合を占める燃料費負担をさらに膨らませ、運送会社の経営を直接圧迫しているのが現状です。
荷主との力関係や業界内の厳しい価格競争の中で、コスト増加分を適正に運賃へ転嫁することは、容易ではありません。利益が圧迫されてしまうと、ドライバーの待遇改善やDX(デジタル・トランスフォーメーション)化に必要な新しい設備への投資も難しくなります。
出典参照:石油製品価格調査 調査の結果|経済産業省資源エネルギー庁

さまざまな課題を前に、物流の未来に対し不安を感じたかもしれません。しかし、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は問題を解決に導く力強い手段となります。
それは単に業務を効率化するだけではありません。働く人の環境を改善し、企業の収益性を高め、ビジネス全体の成長を後押しします。
以下より、物流DXがもたらす具体的なメリットを4つの側面から詳しく見ていきましょう。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)により、業務効率化による生産性の向上が可能です。倉庫管理システムを導入すれば、広大な倉庫内でも最適なピッキングルートを瞬時に示してくれます。人の経験や勘に頼る必要がなくなり、誰もが効率的な作業が可能です。
AIを活用した配送計画システムも有力な手段となります。交通情報や天候、配送先などの条件をリアルタイムで分析し、最適な配送ルートを自動で算出します。無駄な走行距離や時間の大幅な削減が見込めるでしょう。
注意深く作業をしても、人が介在する限りミスをゼロにするのは困難です。物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、人的ミスを劇的に減らし、サービス品質を高める効果も期待できます。
ハンディターミナルでバーコードを読み取る仕組みを導入すれば、誤った商品をピッキングするミスを防ぐことが可能です。各種システムがデータを自動で連携させるため、手作業による入力ミスも発生しません。
ミスが減ることは、顧客満足度の向上に直結します。同時に、クレーム対応や手戻り作業などの無駄な業務も削減され、現場スタッフの精神的な負担も軽くなります。
業務の効率化と品質の向上は、結果としてコスト削減と収益性の改善に繋がります。物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)による地道なコスト削減は、利益体質が強化され、待遇改善やDX投資への好循環も期待できるでしょう。
AIによる配送ルートの最適化は、燃料費や高速道路料金などの変動費の削減に直接貢献します。倉庫作業を自動化するロボットを導入すれば、人件費や残業代を抑制することも可能です。
顧客が受け取り日時を細かく指定できるシステムや宅配ボックスの活用促進は、再配達を減らしコストを削減するために必要です。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、企業の利益だけでなく、現場で働く人々の環境を改善する上でも重要です。負担が大きいとされてきた作業を、ロボットやITシステムが代替・補助してくれます。
例えば、無人搬送車が自動で倉庫内の荷物を運ぶことで、作業員の歩行距離を削減可能です。パワーアシストスーツを導入すれば、重い荷物を扱う際の身体的な負担が軽減されます。年齢や性別、経験などに関わらず安全に働ける職場の実現に近づくでしょう。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を具体的に進めるためには、どのような技術が使われるのでしょうか。最先端の技術と聞くと、少し難しく感じるかもしれません。しかし、その仕組みは意外と身近なところで活かされています。
以下より、物流の現場を大きく変える力を持つ代表的な技術を4つ紹介します。AI(人工知能)やIoT(インターネット・オブ・シングス)、ロボットなどがどのように課題を解決するのか見ていきましょう。
ベテランドライバーは、長年の経験と勘で効率的な道順を選びます。物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、その「匠の技」をデータで再現し、さらに超える可能性を秘めています。
AIは、交通渋滞の予測データや天候、各配送先の荷物量や時間指定など、人間では処理しきれない膨大な情報を瞬時に分析することが可能です。効率の良い配送ルートと順番を導き出してくれるため、燃料費や移動時間を大幅に削減できます。
ドライバーはルート選定に悩む必要がなくなり、運転業務に集中できるため、安全性も向上します。
IoT(インターネット・オブ・シングス)とは、モノにセンサーを取り付けてインターネットに接続する技術です。物流品質と信頼性の向上に貢献し、物流DXを加速させます。
トラックやコンテナにGPS(グローバル・ポジショニング・システム)センサーを付ければ、荷物が今どこにあるのかをリアルタイムで正確に把握できます。顧客からの問い合わせにも、即回答可能です。
温度センサーを活用すれば、冷凍・冷蔵食品や医薬品など繊細な商品の品質管理が遠隔でできます。設定温度からの逸脱を検知すると即時にアラートを発信できるため、問題の早期対応が可能です。
広大な物流倉庫内でのピッキングや仕分け作業は、人手と時間に頼る代表的な業務でした。その負担を軽減する物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)が、AGV(自動化ロボット)です。
AGVは、床に貼られた磁気テープやQRコードを読み取りながら、決められたルートを自動で走行します。作業員は歩き回る必要がなくなり、定位置で入荷や出荷作業に専念することが可能です。
最近では、棚ごと作業者の元へ移動してくるGTP(自動搬送システム)も普及しています。24時間稼働でき、倉庫全体の生産性を高めることが可能です。
ドローンによる配送は、未来の技術というイメージがあるかもしれませんが、すでに実用化に向けた取り組みが各地で進んでいます。特にその力を発揮するのが、トラックでの配送が非効率なエリアです。
例えば、山間部や離島などの過疎地域への「ラストワンマイル配送」です。交通インフラが整っていない場所にも、空から迅速に荷物を届けることが可能になります。
災害発生時に医薬品や食料などの緊急物資を輸送する手段としても、大きな期待が寄せられていますが、まだ法規制や天候、安全性の確保などの課題は残っています。
人手不足や交通弱者問題を解決する切り札として、今後ますますその重要性は高まっていくでしょう。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進は、ただ最新技術を取り入れるだけでは不十分です。重要なのは、自社の現状を客観的に把握し、課題や目標を明確にした上で、段階的かつ柔軟に進めていくことです。
無理な取り組みは、想定外の混乱や成果の停滞を招く要因になります。まずは小さな取り組みから始め、現場の実情に合わせて展開・改善することが、長期的に成果を出すポイントです。
以下より、推進ステップを5段階に分けて見ていきましょう。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を成功させる第一歩は、業務の現状を正しく可視化することです。出荷件数、作業時間、ミス発生率、人員構成などの数値を整理し、属人化している業務やボトルネックを明らかにするのが重要です。
また、現場担当者へのヒアリングを通じて、感覚的な問題点や改善ニーズも洗い出しましょう。定量と定性の両面から課題を整理することで、DXの方向性が見えてきます。分析がその後の全てのステップの基盤になります。
次に、課題に基づいたDX(デジタル・トランスフォーメーション)戦略を立てましょう。目的を「業務効率化」や「品質向上」などに限定せず、全体最適を意識することが重要です。戦略には、技術導入の範囲、スケジュール、人材配置、予算配分などを明記しましょう。
あわせて、「出荷作業時間を20%削減」「誤出荷件数を半減」など、KPI(重要業績評価指標)を具体的に設定すると成果を客観的に評価しやすくなります。
策定した戦略に基づき、最初は限られた範囲で技術を概念実証(PoC)します。いきなり全体に展開するのではなく、まずは1つの拠点や業務領域に絞ることで、導入時のトラブル、運用上の課題を早期に把握することが可能です。
例えば、自動仕分けシステムを特定のラインに導入し、処理速度や作業負担の変化を検証します。効果検証だけでなく、現場の受け入れ態勢や技術適合性も重要な評価項目です。PoCの結果が成功の判断材料になります。
PoC(概念実証)で効果と課題を明確にした後は、本格的な展開へ移行します。1度に全社導入するのではなく、成功事例を横展開する形で拠点や工程ごとに順次展開していくのが、現実的でリスクが低いです。
業務フローやシステム設定も現場ごとに異なるため、それぞれに応じた柔軟な対応が求められます。現場からのフィードバックを活用しながら、機能の最適化を重ねることが大切です。導入のスピードよりも、定着と効果を重視しましょう。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、単発で完結するものではありません。推進後の効果測定を通じて、目標に対する進捗や成果を定期的に評価し、必要に応じて改善策を講じることが求められます。
KPI(重要業績評価指標)の達成度合いや現場の声をもとに、システムの調整や運用ルールの見直しを行いましょう。また、環境変化や業務拡大に合わせて新たな技術を取り入れる柔軟性も重要です。物流DXを形骸化させないカギになります。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、具体的にどのような形で導入され、成果を上げているのでしょうか。ここでは、実際に物流DXに取り組み、大きな効果を上げている国内企業の事例を3つ紹介します。
各社がどのような課題を抱え、どの技術を使って解決したのかを知ることは、自社の取り組みを考える上で大変参考になるはずです。成功事例から、物流DXの具体的なイメージを掴んでいきましょう。
日本郵船は、AI(人工知能)を活用して船舶の運航スケジュールを最適化するシステムを開発しました。これまでの配船計画は、熟練担当者の経験とノウハウに大きく依存しており、策定に膨大な時間がかかって属人化という課題も抱えていました。
課題解決のために開発されたのが、寄港する船の数や貨物量、燃料消費量などの複雑な条件をAIが分析し、最適なスケジュール案を提示するシステムです。
これにより、計画策定時間を大幅に短縮することに成功しました。燃料効率の良い運航も可能になり、コスト削減と環境負荷の低減にも繋がっています。
出典参照:自動車専用船の運航スケジュール策定支援システムを開発|日本郵船株式会社
佐川グローバルロジスティクスは、大規模物流センターにロボットソーターを導入しました。EC(エレクトロニック・コマース)市場の拡大により急増する小口荷物の仕分け作業は、人手による負担が大きい業務でした。
そこで導入されたのが、自動化ロボット(AGV)が荷物を載せた棚ごと自動で移動し、方面別に仕分けを行うシステムです。AGVは、荷物を滑らせるようにして正確に仕分けシュートへ投入していきます。
従来のコンベア式ソーターに比べて省スペース化を実現しつつ、仕分け能力を向上させました。夜間の自動稼働も可能で、省人化と生産性向上を両立させています。
出典参照:仕分け業務のDXにより、東松山SRCの大幅な生産性向上を実現 ~次世代型ロボットソーター「t-Sort」やRFIDシステムを導入~|佐川グローバルロジスティクス株式会社
日立物流から社名を変更したロジスティード株式会社では、「デジタルツイン」という先進技術を活用しています。デジタルツインとは、現実世界の倉庫や設備を、そっくりそのままデジタルの仮想空間上に再現する技術です。
倉庫内の人やトラック、フォークリフトの動きなどをセンサーでリアルタイムに収集し、仮想空間上で可視化します。これにより、どこで作業の遅れや滞留が発生しているのかが一目で分かります。
他にも、最適な人員配置や設備レイアウトの改善策の検討が可能です。将来の物量変動をシミュレーションし、事前に対策できます。
出典参照:サイバー空間上にサプライチェーン全体を再現し、商品在庫と物流拠点の適正化を支援|株式会社日立製作所
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)には多くのメリットがありますが、計画なしに進めるのは危険です。「とりあえず流行りのシステムを導入しよう」という考えでは、期待した効果は得られません。
現場の混乱を招いてしまう恐れさえあります。成功のためには、事前に注意点やリスクをしっかり理解し、対策を立てることが不可欠です。
ここでは、物流DXを推進する際に特に気をつけたい3つのポイントを解説します。失敗を避け、着実に成果を出すための準備を一緒に見ていきましょう。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を進める上で、避けて通れないのが初期投資コストの問題です。新しい管理システムや自動化ロボットの導入には、まとまった費用がかかります。
このコストを前に、取り組みをためらってしまうケースも少なくありません。大切なのは、単に金額の大小で判断しないことです。その投資によって「どれだけの効果が期待できるか」という費用対効果を冷静に分析しましょう。
例えば、人件費や残業代をどのくらい削減できるのか。配送効率化で燃料費がいくら減るのか、などを具体的に試算します。国や自治体が提供する補助金や助成金を活用することも、負担を軽減する有効な手段です。
長期的な視点で投資価値を見極めることが成功の鍵となります。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、多くのデータの活用により成り立っています。顧客情報や荷物の配送状況、企業の経営データなど、その全てが重要な経営資源です。
デジタル化を進めることは、これらの情報がサイバー攻撃や内部不正による漏えいのリスクに晒されることも意味します。そのため、DXの推進とセキュリティ対策はセットで考えなくてはなりません。
堅牢なセキュリティ基盤を持つ信頼できるシステムを選ぶことが不可欠です。便利さの裏側にあるリスクを理解し、万全の対策を講じましょう。
多くの企業では販売管理や会計などの業務システムを運用しています。新たに物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)ツールを導入する際には、既存システムとの連携が課題です。
システム間の連携がスムーズでないと、同じデータを各システムに手入力する二重作業が発生してしまいます。これではデータを一元管理できず、かえって非効率になる恐れがあります。物流DXの目的は全体最適化です。
検討するツールが、現在使用しているシステムとAPIでデータ連携できるのかを事前に確認し、社内全体のデータフローを設計することが重要です。部分導入が全体のボトルネックにならないよう注意しましょう。
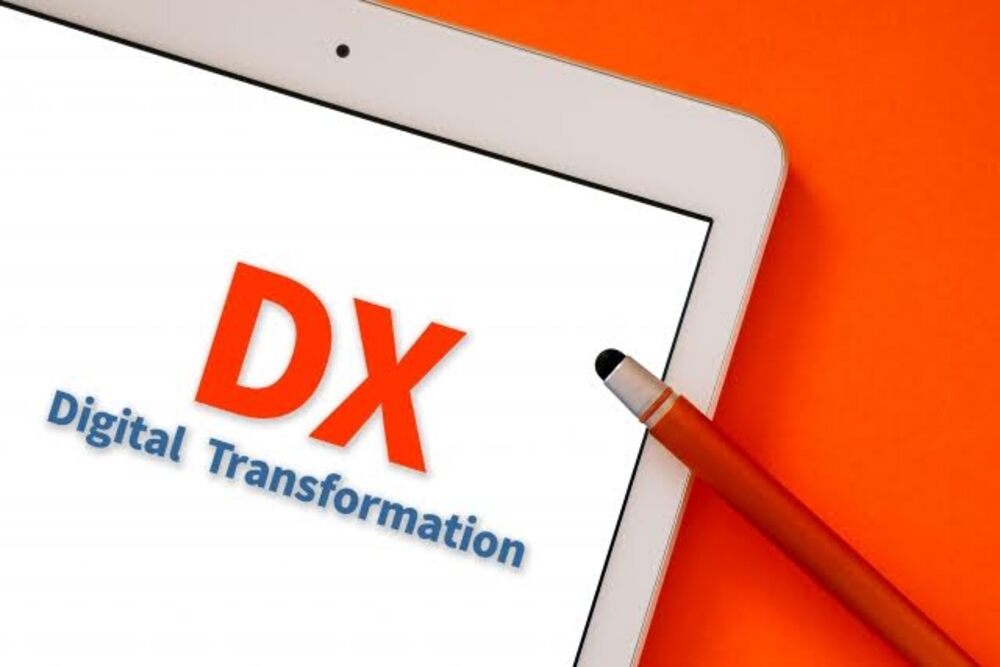
この記事では「物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは」何か、その基本から具体的な手法までを解説しました。物流業界は人手不足や2024年問題など、多くの課題に直面しています。
DXは、これらの課題を乗り越えるための強力な解決策です。物流DXは、単なるIT化ではありません。デジタル技術で業務を変革し、新たな価値を創造する取り組みです。
生産性向上やコスト削減はもちろん、働きやすい環境も実現できます。自社に合ったDXを計画的に進めることが、持続可能な成長への鍵となります。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
