物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

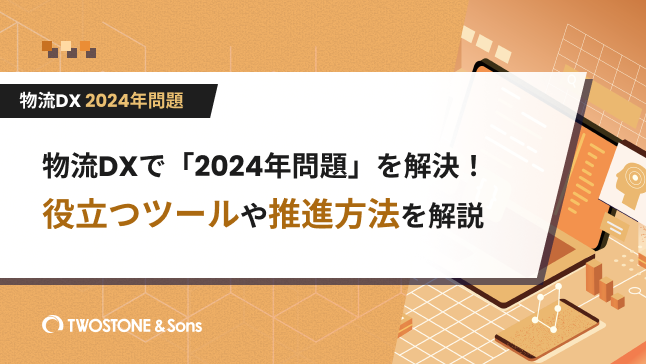
物流業界は今、大きな変革期を迎えています。特に2024年に施行された規制がもたらす影響は避けられず、多くの企業が対応に追われています。ドライバーの労働時間制限や輸送量の減少など業務に直結する課題が山積みの中で、どうすれば効率的に運営を続けられるのか悩む方も多いでしょう。そこで注目されているのが物流DXの推進です。
物流DXとはITを活用して物流業務の効率化や見える化を進める取り組みで、これによって時間やコストの削減だけでなく人手不足の解消にもつながります。
本記事では2024年問題が物流業界に与える影響を詳しく解説し、具体的に役立つツールや推進のポイントを紹介します。これを読むことで今後の変化に備えた戦略を立てやすくなり、持続可能な物流体制の構築が可能です。

2024年問題は物流業界における法改正を指し、ドライバーの労働時間制限や輸送量の減少、人手不足の深刻化が課題です。これらの変化が重なることで、従来の物流ネットワークは機能不全に陥る可能性があります。さらに収入減少が人材不足を加速し、悪循環に陥ることも懸念されています。
これらの問題に対応するために求められているのは単なる業務改善だけでなく、ITの活用による抜本的な変革です。
出典参照:物流の「2024年問題」とは|国土交通省
2024年4月から、ドライバーの時間外労働の上限が年間960時間に制限されます。この法改正は労働環境の改善を目的としたものですが、物流業務の効率化が遅れると輸送力不足を招く可能性が高まります。ドライバーがこれまでこなしていた長時間労働ができなくなるため、単純に労働時間を減らすだけでは対応しきれません。
そのため、配送計画の見直しやルートの最適化が不可欠です。ITを活用すればAIによる配送ルートの自動生成や需要予測が可能となり、限られた労働時間内で最大限の業務を実現できるでしょう。加えて車両や荷物の状況をリアルタイムで把握できるシステムを導入すれば、遅延や無駄な動きを減らせるため効率的に運行管理が進みます。こうしたツールの活用は、ドライバーの負担を軽減しつつ業務を継続する上で欠かせない手段です。
時間外労働の制限によってドライバーの労働時間が減ることは、輸送量の減少につながります。これによってこれまでスムーズに回っていた物流ネットワークに停滞が生じ、配送の遅延や供給不足が発生しかねません。特に指摘されている点は地方や遠隔地の配送ほど影響を受けやすく、物流の均衡が崩れる可能性です。
こうした事態に対処するためには、物流ネットワーク全体の見直しが求められます。具体的には複数の配送業者間での荷物の共同配送や、倉庫の集約化を進めることが効果的です。またIoTセンサーを使った車両や荷物の位置情報のリアルタイムでの管理で配送の遅延要因を早期に発見でき、迅速な対応が可能になります。
こうした取り組みを通じて物流ネットワークの停滞を防ぎ、安定した配送体制の維持が可能です。
時間外労働の制限や輸送量の減少は、ドライバーの収入減にも直結します。これは労働時間が短縮されることで働く時間が減り、賃金も低下するケースが増加するためです。収入が減ることはドライバーの離職を招きやすく、結果として慢性的な人材不足を深刻化させます。この悪循環は物流業界全体の競争力を低下させる大きな要因です。
この課題を解決するためには、労働時間の短縮と収入の確保を両立する施策が必要です。具体的には、業務の効率化で労働生産性を向上させることが挙げられます。物流DXの推進によって配送スケジュールの最適化や作業の自動化が進めば、同じ労働時間でより多くの業務をこなせるようになります。
これにより収入減の影響を緩和し、人材不足の悪循環を断ち切ることが期待できるでしょう。
2024年問題の解決に向けて物流DXを推進すると、業務効率の向上とコスト削減が実現します。労働時間の制限や人手不足という課題に対応しながら、サービス品質の維持や向上も期待できるでしょう。ITツールを活用した物流の見える化は、問題の早期発見と柔軟な対応を可能にし、結果として経営の安定化に寄与します。
これらのメリットが、物流業界の持続的成長を支える重要な要素の1つです。
輸配送ルートの最適化は、物流DX推進の基本かつ重要なメリットの1つです。配送ルートの最適化で不要な走行や迂回を減らし、走行距離を短縮できます。これにより燃料費の削減や車両の摩耗軽減が期待できるため、経営効率が改善されます。
また時間短縮が実現すればドライバーの負担も軽減され、労働時間制限の影響をより小さくできるでしょう。AIやビッグデータを活用したルート設計は交通状況や配送先の混雑状況も考慮し、リアルタイムでの最適化が可能です。これにより、効率的かつ柔軟な配送体制の構築につながります。
積載効率を高めることで、一回の輸送でより多くの荷物を運搬可能です。これにより輸送回数を減らせるため、時間とコストの節約に直結します。特に配送量が多い企業では、積載率の改善が全体の物流効率に大きな影響を与えます。
物流DXの推進で導入されるのは積載計画をITで管理し、空きスペースを最大限活用する方法です。荷物の形状や重量を考慮しながら最適な積み方を提案できるツールも登場しています。これにより、輸送効率が上がり環境負荷も軽減されます。結果として経営の安定化と持続可能な物流体制の確立が可能です。
需要予測の精度が向上すると、過剰な在庫や欠品を防止できます。過剰在庫は保管コストや劣化リスクを高め、欠品は顧客満足度の低下につながるため、適正な需要予測は物流の重要課題です。物流DXの推進によって過去の販売データや季節変動、外部環境の変化をAIが分析してより正確な需要予測を実現します。
その結果、適切な発注計画や配送計画が可能となり無駄な在庫を減らせます。さらに需要の変動に応じた柔軟な対応も実現し、物流全体の効率向上が可能です。これによりコスト削減だけでなく、顧客サービスの質も高まります。
物流業務には大量の事務作業が伴いますが、電子化によって効率化が可能です。紙の伝票や手作業でのデータ入力はミスが起きやすく、処理にも時間がかかります。物流DXの推進で受発注や請求、在庫管理などの業務をデジタル化して作業負担を減らせるでしょう。
具体的にはクラウドシステムを利用すれば関係者間で情報をリアルタイムに共有でき、作業の二重化や遅延を防止します。これによって事務作業の正確性が向上し、迅速な意思決定を支援します。結果的に従業員の労働負荷が軽減され、重要な現場業務に集中できる環境の整備が可能です。
物流現場では状況が刻々と変わるため、リアルタイムでの判断と対応が求められます。物流DXの推進は車両の位置情報や配送状況、在庫データなどをリアルタイムに収集し分析できる環境を整えます。このデータ活用により、遅延やトラブルを早期に発見し迅速に対処可能です。
例えば配送車の位置が予定より遅れている場合、代替ルートの迅速な指示や顧客への連絡の自動化をする仕組みなどが構築可能です。さらに長期的なデータ分析によって傾向を把握し、将来的なリスクの予測や業務改善にも役立ちます。このようにデータドリブンな判断力が、物流の安全性と効率性を支えます。

2024年問題に対応するためには単に現状を維持するだけでなく、先進的な物流DXの推進が不可欠です。効率的な配送や人手不足の解消、業務の自動化など多方面に効果をもたらす施策が求められます。
ここでは2024年問題の解決のために特に注目すべき、5つの推進方法を具体的に紹介します。これらを活用すれば、変化に柔軟に対応しながら物流の質と効率を同時に向上させることが可能です。
配送ルートのAI最適化システムは膨大な配送先と交通情報を解析し、最適なルートを自動で割り出します。これによってドライバーの走行距離や時間を短縮し、燃料消費や人件費の削減につながります。さらにAIは交通渋滞や天候変化などのリアルタイム情報も考慮し、状況に応じてルートを柔軟に変更可能です。
このシステムの導入は労働時間制限の中でも効率よく配送業務を遂行できるよう支援します。手作業でのルート設定に比べてミスが減り、配送遅延のリスクも低下します。加えて複数の配送先をまとめて最適化する機能も備わっており、積載効率の向上も可能です。こうした特徴から、AIルート最適化は物流DX推進の重要なツールとして注目されています。
自動倉庫やロボットピッキングの導入は、倉庫内の作業効率を改善します。手作業に頼っていたピッキング作業や在庫管理が自動化されることで、ヒューマンエラーを減らし作業速度の向上が可能です。これにより、少ない人手でも正確でスピーディーな出荷が可能になります。
物流DXの一環として導入が進むこれらの技術は、人材不足対策にも効果的です。特に繁忙期や人手が不足しているときでも、安定した業務遂行が見込めます。また、ロボットは長時間の作業や重い荷物の取り扱いも得意なため、労働環境の改善にもつながるでしょう。こうしたメリットにより、倉庫業務の効率化と品質向上を同時に実現可能です。
配車管理をクラウドシステム化すると、業務の透明性と効率性が向上します。従来の紙ベースやローカルシステムでは情報共有に時間がかかり変更対応も遅れがちでしたが、クラウドなら関係者全員がリアルタイムで最新情報にアクセス可能です。
これによって配車計画の調整や変更が迅速に行えるだけでなく、ドライバーや管理者間の連絡もスムーズになります。さらに過去の配車データの蓄積・分析により、効率的な運用ルールの策定や課題抽出も可能です。クラウド配車管理は変化の激しい物流現場に柔軟に対応しながら、業務効率を高める重要な基盤となっています。
トラックの動態管理やリアルタイム位置把握システムは、物流の見える化を進める上で欠かせません。GPSやIoT技術を活用して車両の現在地や走行状況をリアルタイムで監視でき、配送遅延やトラブルの早期発見につながります。
これによって運行管理者は状況に応じた適切な指示を出しやすくなり、遅延の回避や顧客対応の迅速化を実現します。また走行データの蓄積により、運転傾向の分析や燃費改善策の検討も可能です。結果として、安全運転の促進やコスト削減にも寄与します。動態管理は、物流DX推進の基盤となる重要な機能です。
電子伝票や電子契約の導入は、物流業務のペーパーレス化と効率化に直結します。紙の伝票は紛失や記入ミスのリスクがあり、処理に時間もかかるため電子化でこれらの問題を解消可能です。電子伝票なら情報が即座に共有され、担当者間の連携もスムーズに進みます。
また電子契約の活用で契約締結のスピードアップが期待でき、業務の停滞を防止します。クラウド上での管理により保管も簡便になり、必要な情報をいつでも検索可能です。これにより事務作業の負担が軽減され、現場により集中できる環境が整います。ペーパーレス化は物流DX推進の重要な一歩として、多くの企業で導入が進んでいます。
2024年問題を解決するためには、効率的な物流業務を支援するさまざまなツールの導入が不可欠です。これらの最新ITを活用したシステムは、労働時間の制限や人手不足といった複雑な課題に直接アプローチできます。
ここでは物流現場で高い実績を持つ代表的なツールを5つ紹介し、それぞれの特徴や導入メリットを詳しく解説します。これらのツールの活用は物流業務の効率化と安全性向上が期待できる、2024年問題の影響を抑える効果的な対策です。
三菱ロジスネクトが提供する無人フォークリフトは倉庫内の積載作業を自動化し、作業効率と安全性を同時に向上させる革新的なツールです。従来の人手によるフォークリフト作業は作業ミスや事故のリスクがあり、作業速度も限られていました。この無人フォークリフトは設定したルートや作業指示に基づき、自律的に荷物の運搬と積み込みを行います。
自動化により人手不足の影響を軽減し、作業時間を短縮可能です。複数台の無人フォークリフトを連携させた運用で倉庫全体の物流フローをスムーズにし、積載作業の効率化を推進します。さらに人的ミスの減少により安全管理も強化され、現場の生産性アップに寄与します。これらの特徴こそ、無人フォークリフトが物流DX推進の中核的なツールとして注目されている理由です。
大和ハウス工業が展開するWMS(Warehouse Management System)は倉庫内の在庫管理業務を高度に自動化し、物流業務の効率化を支援するシステムです。在庫の入出庫状況をリアルタイムに監視し、最適な保管場所やピッキング順序を指示する機能が備わっています。これにより作業のムダを削減し、誤出荷の防止につなげられることが可能です。
正確な在庫情報のデジタル化によって過剰在庫や欠品リスクが抑制され、安定した物流運営が可能になります。また作業履歴やデータの分析を通じて業務改善ポイントを抽出し、持続的な効率向上を図ることが可能です。現場の負担軽減と同時にサービス品質の向上にも貢献するため、多くの物流企業が導入を進めています。
出典参照:フレームワークス|大和ハウス工業株式会社
ハコベルのトラック予約受付システムは倉庫や物流拠点における、バース管理を効率化するためのツールです。バースとは荷降ろしや積み込みのためのトラックの停車スペースを指し、多数のトラックが同時に訪れると混雑や長時間の待機が発生しやすくなります。このシステムを使うことで、トラックの到着時間や順番を事前に予約・管理可能です。
クラウド上で予約情報が関係者にリアルタイムで共有されるため、混乱を減らしてスムーズな運用を実現します。待機時間の短縮はドライバーの負担軽減や燃料消費削減に寄与し、物流全体の効率化につなげることが可能です。さらに予約データの蓄積によってバース稼働率の分析や混雑緩和策の検討も可能になり、現場の課題解決をサポートします。
出典参照:ハコベル|ハコベル株式会社
勤次郎が提供するドライバー管理システム「Universal 勤次郎」はドライバーの労働時間や勤務状況を正確に管理し、法令遵守と安全運転支援を同時に実現するツールです。スマートフォンやタブレット対応で現場での操作性が高く、リアルタイムに勤怠情報や運行状況を確認できます。
労働時間管理だけでなく休憩状況や健康状態の把握も可能なため、違反リスクの低減に効果的です。管理者はこれらのデータを活用して客観的な評価や適切な人員配置が行えるため、人材不足対策やドライバーの負担軽減に貢献します。物流現場の安全性と効率性を支える重要なツールです。
ダイワハイテックスの「CARGOWELL」はIoT技術を駆使した、物流現場向け省人化プラットフォームです。荷物や車両に取り付けたセンサーからリアルタイムで情報を取得し、現場状況を可視化します。これによって作業の遅延やボトルネックを速やかに発見でき、適切な対応が可能です。
クラウド管理によって収集データは多角的に分析でき、作業効率の向上や人員配置の最適化に役立ちます。トレーサビリティ強化や品質管理にも貢献し、省人化と高品質な物流運営の両立を実現します。こうしたシステムは変化の激しい物流環境において、柔軟かつ安定した運用を可能にする重要なツールです。
物流DXの推進は多くの企業で重要な課題とされており、2024年問題の影響を軽減するための具体的な取り組みが進んでいます。実際に先進的な技術やシステムを導入している企業の事例を知ることで、自社の対策や改善のヒントが得られます。
ここで行うのは業界を牽引する3社の取り組みの紹介と、それぞれが2024年問題に対してどのように物流DXを活用して課題解決に取り組んでいるかの解説です。
SGホールディングスは、物流の仕分け業務にロボットを積極的に導入しています。従来の仕分け作業は人手に頼る部分が大きく、作業効率や安全面での課題がありました。ロボットの活用で単純かつ繰り返しの作業を自動化し、ミスの減少と作業スピードの向上を実現しています。
特に人手不足の影響を受けやすい部分にロボットを導入したことで、労働環境の改善や安定した業務運営が可能になりました。これによって2024年問題で求められる労働時間の制限を守りながらも、配送の遅延を防ぐことに成功しています。安全性と効率性を両立させた先進的な物流DX推進の好例です。
出典参照:仕分け業務のDXにより、東松山SRCの大幅な生産性向上を実現 ~次世代型ロボットソーター「t-Sort」やRFIDシステムを導入~ |SGホールディングス株式会社
株式会社日立物流はドライバーの生体情報を、AIがリアルタイムに分析するシステムを導入しています。心拍数や運転時の姿勢などのデータを収集し、疲労やストレスの兆候の検知で事故の未然防止に役立てています。
このシステムによって労働時間が厳しく制限される中でも安全運転を継続し、効率的な運行が可能です。疲労の兆候が現れた際には警告され適切な休憩指示が行われるため、ドライバーの健康管理にも貢献しています。日立物流の取り組みが注目されているのは、人手不足や労働環境の悪化に対する先進的な対策がその理由です。
出典参照:ドライバー自身も気づけない「漫然運転」と生体情報のAI分析による「事故ゼロ」に向けた取り組み|株式会社日立物流
日本郵船は自動車専用船の運行スケジュールを、ITで可視化する取り組みを進めています。船の位置情報やスケジュールをリアルタイムで管理し、各拠点や関係者が情報を共有できる体制を整備しました。
これによって船舶の稼働率向上や配送遅延の防止が実現し、物流の全体効率が高まっています。輸送計画の透明性が増し、急な変更にも柔軟に対応可能になったことが強みです。大規模な物流ネットワークの最適運営に向け、デジタル技術を活用して2024年問題の影響を軽減して安定した物流を支えています。
出典参照:自動車専用船の運航スケジュール策定支援システムを開発 | 日本郵船株式会社

2024年問題は物流業界にとって大きな課題ですが、物流DXの推進によって多面的な解決策が見えてきます。AIによる配送ルートの最適化や自動倉庫の導入、クラウドによる配車管理、さらにはロボット活用や生体情報分析による安全運転支援など多様な技術が効果を発揮しているのも事実です。
具体的な企業事例からもわかるように、最新のITを積極的に取り入れることで労働時間の制限に対応しつつ生産性の向上と安全性の確保を両立できます。建設DXと同様に、物流DXの推進は業界の持続可能な発展に不可欠です。これらのポイントを参考に、自社の物流体制強化を図ることが重要です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
