物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

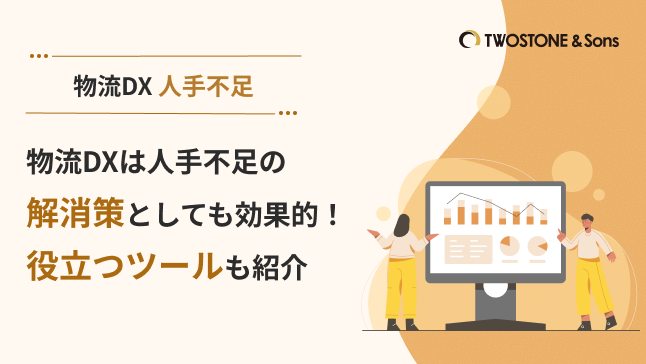
物流業界での人手不足は、さらに深刻な問題となっています。現場の作業が過酷であることや、高齢化の進行、さらにEC市場の急拡大が背景にあり、十分な人材確保が困難になっています。このままでは配送遅延や業務効率の低下など、サービスの質にも影響が及ぶかもしれません。
しかし、物流DXを推進すれば、こうした人手不足の課題に対応できる可能性があります。ITや自動化技術の活用で業務の効率化や省力化が進み、限られた人員で安定的な運用が可能となるでしょう。この記事では、物流業界の現状と人手不足の原因を整理し、物流DXによる解決策と役立つツールの具体例まで詳しく解説します。
この記事を読むことで、物流DXを推進することで得られる効果や、自社の現場に合ったツール選びのポイントを理解できるでしょう。人手不足の悩みを軽減し、効率的な物流体制を築くためのヒントをつかんでください。

物流業界の人手不足には複合的な要因が絡んでいます。まず労働環境の厳しさが大きな要因であり、長時間労働や重労働が続くため、新規人材の定着が難しい状況です。
国土交通省および関連調査によると、トラックドライバーの平均年齢は約47.5歳(大型ドライバー)で、40代後半~50代が中心です。若年層の割合が低く、高齢化が進んでいます。さらに、2024年時点で物流業界では約14.2%のドライバーが不足すると推計されています。
加えて、業界全体で高齢化が進み、若手の新規参入も減少しています。これにより、年々労働力が不足しています。
さらに、EC市場の急速な拡大に伴い物流量が増加している一方で、それに見合う人材確保が追いついていません。こうした背景から、物流現場は慢性的な人手不足に悩まされており、効率的な業務運営が求められています。
出典参照:物流を取り巻く動向と物流施策の現状・課題|国土交通省
出典参照:トラック運送業の現況について|国土交通省
出典参照:日本のトラック輸送産業現状と課題 2024|公益社団法人全日本トラック協会
物流業界の労働環境は、身体的負担が大きいです。荷物の積み下ろしや長時間の運転、また繁忙期には残業が増えるなど、体力的な負担が積み重なります。こうした環境では若手でも離職しやすく、定着率が低下します。
さらに、夜間や早朝の勤務が多く、生活リズムが乱れるため健康面のリスクも高まりかねません。加えて、作業現場では安全管理も徹底しなければならず、ミスや事故のリスクが常に存在しています。こうした厳しい労働環境が人材不足の一因となり、新たな人材確保の障壁にもなっています。
物流業界は高齢化が急速に進んでおり、現役の労働者の平均年齢が上昇しています。高齢化により作業の効率が落ちたり、健康上の問題で勤務継続が困難になったりするケースも増えています。これに対して若手の新規参入は少なく、業界全体で若年層の割合が低下しているのが現状です。
若手が不足する背景には、業務の過酷さやイメージの悪さも関係しています。加えて、他業種と比べて給与面やキャリアパスの魅力が乏しいことも採用難の要因です。このように、高齢化と若手不足が複合的に重なり、人手不足の問題が深刻化しています。
近年、EC市場の急激な拡大が物流業界の負担をさらに増やしています。ネット通販の需要が拡大し、小口配送や即日配送など多様なサービスが求められる中、物流量は急増しています。しかし、配送業務に携わる人材の確保が追いついていまoiteせん。
EC拡大に伴い、以前よりも細かく迅速な配送が必要となったことで現場の業務負担は増大しています。これに対応しきれないと配送遅延やサービス低下を招き、顧客満足度にも影響が出かねません。こうした状況を踏まえ、物流DXによる業務効率化は不可欠な課題となっています。
物流業界が抱える人手不足に対して、物流DXの推進は効果的な解決策となります。業務の自動化や作業効率の向上、属人化の解消など、多方面から現場の負担を軽減できる可能性があります。
さらに、リアルタイムでの業務可視化により無駄な作業を削減し、働き方の柔軟化も実現できるでしょう。これらの要素が組み合わさることで、人材不足の悩みを和らげ、より安定した物流運営が可能になります。
ここでは、具体的な理由を詳しく解説します。
物流DXの大きな利点は、自動化技術の導入で繰り返し作業を効率化できる点です。ピッキングや仕分け作業、在庫管理などの単純作業はロボットや専用システムに任せることで、人手不足の穴埋めになります。自動化は作業ミスの軽減にもつながり、品質の安定化も期待できます。
加えて、重労働から従業員を解放し、労働環境の改善が図れるでしょう。これは従業員の定着率向上に寄与し、新規採用の障壁を減らす効果もあります。自動化による省力化は、業務負担の軽減だけでなく、企業全体の競争力強化にも貢献する重要な施策です。
物流DXは作業効率の改善を可能にします。AIを活用した配送ルートの最適化やIoTによるリアルタイム在庫管理は、無駄な移動や待機時間を減らし、一人当たりの生産性を高めます。これにより、同じ人数でもより多くの業務をこなせるようになるでしょう。
さらに、効率化された作業環境は従業員の負担軽減にもつながり、離職率の低下が期待されます。効率の良い働き方は従業員満足度を高め、人手不足に悩む企業の安定運営に役立ちます。結果として、限られた労働力の有効活用が実現するでしょう。
属人化は物流現場の大きな課題の1つです。熟練者に依存した業務は、新人教育の負担を増やし、現場のリスクを高めます。しかし、物流DXの推進で作業手順や情報をデジタル化・標準化すれば、誰でも同じ品質で業務を遂行できるようになるでしょう。
この標準化により、経験が浅い従業員でもスムーズに業務を覚えられ、教育時間の短縮が可能です。また、業務の見える化により進捗管理や問題点の早期発見も容易になり、組織全体の安定性が向上するでしょう。属人化の解消は持続可能な人材運用の基盤となります。
リアルタイムの業務可視化は、物流DX推進において重要視される機能の1つです。トラックの位置情報や作業状況をリアルタイムに把握できることで、無駄な待機時間や重複作業を減らせるでしょう。即時の状況把握により、遅延や問題にも迅速に対応可能です。
このような業務の見える化は計画変更の柔軟性を高め、全体の効率アップに直結します。結果的に限られた人数でも多くの仕事をこなせる環境が生まれ、人手不足の解消に貢献します。無駄の削減はコスト削減と顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
物流DXにより業務効率が改善されると、シフトの柔軟な調整や部分的な在宅管理も可能になります。こうした働き方の多様化は従業員のワークライフバランスを向上させ、離職防止につながるでしょう。働きやすさは求人応募者にも好印象を与え、採用活動にプラスに働きます。
また、女性や高齢者、育児中の人などこれまで参入しにくかった人材層の活用も促進します。多様な人材が活躍できる環境整備は、慢性的な人手不足に悩む物流業界において欠かせない対策です。結果として、安定した人材確保と業務継続が期待できます。

人手不足を解消するためには、物流DXの推進に役立つツールの導入が不可欠です。効率的な現場運営を支えるためには、荷受け場の管理や自動倉庫、マッチングプラットフォーム、勤怠管理など多様なシステムを適切に活用する必要があります。
これらのツールは作業負担を軽減し、情報の一元管理を実現できるかもしれません。ここでは、実際の導入事例を踏まえ、代表的なツールの特徴と活用法を詳しく解説します。
MOVO Berthはトラックバースの予約や管理を効率化するクラウド型プラットフォームです。荷受け場は物流のボトルネックとなることが多く、トラックの待機時間が長くなると配送効率が低下します。このツールを使えば、トラックの到着時間やバースの空き状況をリアルタイムで管理でき、待機時間を短縮可能です。
さらに、トラックドライバーと荷主間のスムーズな連絡を促進し、荷受け作業の段取りを円滑にします。これにより、現場での人手不足による混乱や無駄な待機を防止し、効率的な運用が実現します。加えて、運行計画の調整やスケジュール管理の負担も軽減され、全体的な業務効率の向上につながるでしょう。
コンパクトシステムが提供するパレット立体自動倉庫は、省スペースで効率的な倉庫管理を可能にします。自動倉庫システムは入出庫作業の自動化により、人的負担を減らし、在庫の正確な管理を実現します。倉庫作業の自動化は作業効率を上げるだけでなく、人手不足の解消にも直結するシステムです。
また、立体構造を活用することで限られたスペースを有効活用し、物流センターの収容能力を高められます。入出庫の自動化はミスの削減にもつながり、トレーサビリティの向上や物流品質の安定につながるでしょう。このシステムは労働力不足を補いながら、より効率的な物流運営を支援します。
出典参照:コンパクトシステム|株式会社ダイフク
トラクルGOは荷主とドライバーをリアルタイムでマッチングするプラットフォームです。物流業界ではドライバー不足が深刻で、効率的な人材活用が求められています。これは荷物の配送依頼とドライバーの空き状況を連動させることで、無駄な空車運行を減らすツールです。
荷主は即座に最適なドライバーを見つけられ、ドライバーも仕事を効率よく確保できるため、双方の負担を減らせます。運行計画の精度向上は配送遅延の防止にもつながり、顧客満足度の向上につながるでしょう。ドライバーの稼働率向上が結果的に人手不足の影響を緩和し、業務の持続可能性を支えます。
出典参照:トラクルGO|エイクロス株式会社
タッチオンタイムはクラウド型の勤怠管理システムで、シフト管理や労働時間の把握を簡単に行えます。物流現場はシフト制が多く、労働時間管理が複雑ですが、このツールの導入で正確な勤怠データの収集と分析が可能です。
労働時間の適正管理は法令遵守だけでなく、従業員の健康管理や働き方改革にもつながります。また、クラウドによる一元管理により、管理者の作業負担が軽減され、柔軟なシフト調整や急な欠勤対応もスムーズになります。結果的に労働環境の改善が進み、人材の定着率向上につながるでしょう。
出典参照:タッチオンタイム|株式会社デジジャパン
物流DXを効果的に推進し、人手不足の課題を解消するには、まず現状の業務を正確に把握することが欠かせません。どの業務で人手が特に足りていないかを可視化し、その情報を基に優先的に改善策を検討します。
加えて、作業を個人任せにせず、システムや仕組みで回すという発想の転換も必要です。こうした考え方の変化が現場全体の効率化を促進します。また、すべてを一度に変えるのではなく、段階的にDX化を進めて実際の効果を示しながら進めることが成功のポイントとなります。
ここでは、具体的な取り組み方を詳しくみていきましょう。
物流現場で人手不足を解消するには、まずどの業務にどの程度の負担がかかっているかを正確に把握する必要があります。多くの場合、感覚や経験で判断されがちですが、業務の可視化は具体的な数値やデータに基づいて行うことが重要です。作業時間、頻度、担当者の人数やスキルレベルなどの情報を集めることで、どの業務がボトルネックになっているかが明確になります。
こうしたデータを基に優先順位をつけ、改善効果の大きい部分からDX推進を進めるのが効率的です。無闇にすべてを一気に変えようとすると混乱が起きやすく、現場の負担も増します。可視化は単なる現状把握だけでなく、改善の成果を客観的に評価する基準にもなり、従業員の理解や協力を得やすくなります。まず現状を正しく把握することで、的確な対策が実現し、人手不足の解消につながるでしょう。
物流業務における人手不足は、属人化した作業や不明確な業務フローが一因となっています。したがって、DX推進では個人の経験や勘に依存せず、誰でも同じ品質で業務を遂行できる仕組みづくりが求められます。作業の標準化や自動化、システム化を進めることで、現場の属人性を解消し、安定した業務運営につながるでしょう。
仕組みで回す発想は業務の一部を自動化機器やシステムに任せるだけでなく、情報の共有や連携も重要です。例えば、トラックの到着状況や荷物の仕分け状況をリアルタイムで共有すれば、担当者間の無駄なやり取りが減り、効率的な調整が行えます。また、問題発生時も早期発見・対処が可能になるため、全体の生産性が向上するでしょう。このような仕組みで業務を回すことで、個々の負担が減り、人材不足の影響を和らげる効果が期待されます。
物流DXの推進は一度に全体を変革しようとすると失敗しやすいため、段階的な取り組みが推奨されます。まずは小規模なプロジェクトや特定業務からスタートし、その効果を明確に示すことで、社内の理解と協力を得ることが重要です。初期段階で成功体験を積み重ねることで、DX推進の意義を共有し、抵抗感を減らせるでしょう。
段階的な進め方では、改善したい業務の優先順位に沿って計画を立てることがポイントです。取り組むべき業務が明確になれば、効果測定も容易になり、費用対効果を評価できます。また、段階的に進めることで問題点や課題も早期に発見しやすく、柔軟に改善策を加えられます。こうした運用の柔軟性は、現場の混乱を防ぎつつDXを推進する上で欠かせません。結果的に持続可能な人手不足解消につながり、企業の成長に寄与します。
物流業界では、人手不足が日々深刻さを増していますが、実際にDXを推進して課題を克服している企業も増えています。成功事例に共通するのは、自社のリソースだけに依存せず、仕組みやツールを活用しながら柔軟に対処している点です。
共同輸送の仕組みを導入したり、外部リソースを活用して負担を軽減したり、AIやロボットといったテクノロジーを活かして作業を効率化したりした企業が注目されています。
ここでは、物流DXを通じて人手不足を解決した3つの具体的な事例を紹介します。
福山通運は2025年1月よりセンコーが保有する中継輸送専用施設を活用し、センコーと共同で中継輸送を行う新たな取り組みを始めました。この施策は、長距離トラック輸送のドライバー不足に対応する目的で企画されました。具体的には、積み替え拠点を活用し、ドライバーが途中で交代することで、1人当たりの運行距離を短縮する取り組みです。
この取り組みにより、長距離運転にともなう労働時間の過剰や安全リスクを抑制でき、持続可能な輸送体制が確立されつつあります。また、共同輸送の実施により、空車の削減や積載効率の向上も実現され、全体の業務効率が上がっています。結果として、ドライバー不足に対する具体的な対策となり、物流現場の人材課題の軽減につながりました。
出典参照:センコー・福山通運が共同輸送を開始|福山通運株式会社
沖縄ヤマト運輸では、地域特有の人材不足に対応するために業務の一部を外部委託するアウトソーシングの仕組みを構築しています。業務内容に応じて、仕分け・集配などを複数の協力会社に委託することで、繁忙期や急な人員不足にも柔軟に対応できる体制を整えました。
この取り組みは単なる業務外注ではなく、委託先と密な情報共有を行いながら、品質管理や安全対策を徹底しています。また、業務マニュアルの標準化や研修体制の整備も進めており、委託業務の質を一定に保つ工夫も施されています。社内だけで人材確保するのではなく、地域全体のリソースを有効に活用する戦略により、持続可能な運営体制が構築された事例です。
佐川急便ではAIを搭載した荷積みロボットを導入し、作業の自動化と効率化を図っています。従来、人手に頼っていたパレット積載作業をロボットが担うことで、熟練労働者でなければ難しかった業務を誰でも再現可能なものへと変えました。
このロボットは、荷物の形状や重量を自動で判別し、最適な積み方をAIが判断して作業を実行します。人手による作業と比べてミスが少なく、作業時間も短縮されるため、現場の負担が軽減されるという成果が得られています。また、作業者の腰痛や過重労働のリスクも抑えられ、安全面の向上にもつながりました。これにより、作業人員の不足を補いつつ、品質と効率を両立する物流現場が実現しています。
出典参照:働き手不足を解消する業界初「AI搭載荷積みロボット導入」への挑戦|佐川急便株式会社

物流業界では慢性的な人手不足が続いており、従来のやり方だけでは対応が難しくなってきました。こうした背景の中で、物流DXは課題を抜本的に見直す機会を提供します。業務の可視化、仕組み化、段階的な改善を通じて、限られた人材でも効率よく運用できる体制を構築することが可能です。
また、すでに多くの企業が物流DXに取り組み、具体的な成果を挙げています。共同輸送による負担分散や、AIによる作業自動化、アウトソーシングによる柔軟な人員確保など、解決策は多岐にわたります。これらの事例を参考に、自社の業務に適したアプローチを検討することが、人手不足に対処する第一歩となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
