物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

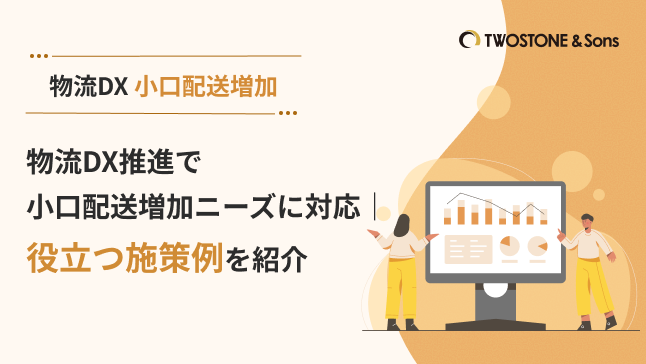
EC市場の急成長と消費者ニーズの多様化により、小口配送の需要は爆発的に増加しています。従来の物流システムでは、対応が困難な状況に直面している企業も多いのではないでしょうか。配送件数の増加に対して人員確保が追いつかず、コスト増加や配送品質の低下といった課題が深刻化しています。
しかし物流DXの推進により、これらの課題を効率的に解決できる可能性があります。AI技術を活用した配送ルート最適化や自動化システムの導入により、小口配送の増加に対応しながら同時に業務効率の向上も実現可能です。
本記事では物流DXを活用して小口配送増加に対応する、具体的な方法を解説します。実際の企業事例も紹介しながら、効果的な施策の進め方や注意点まで詳しく説明していきます。この記事を読むことで、自社の物流体制強化に向けた具体的なアクションプランを立てられるようになるでしょう。

近年では消費者の購買スタイルの多様化とEC市場の拡大により、小口配送のニーズが急増しています。これには単品購入の増加、即日配送サービスの普及などが関係しています。加えて生活圏の広がりや地域別の多様な配送要望などの背景も重なり、現在では小口配送は社会全体の物流構造に影響を及ぼす一角といえるでしょう。
国土交通省の「宅配便取扱個数」(2024年版)によれば、令和5年度の宅配便取扱個数は50億733万個となり、前年度比で145万個、0.3%の増加を記録しています。その内訳は、トラック運送によるものが49億1401万個、航空等を利用した運送が9,332万個となっており、トラック輸送が依然として主流であることがみて取れるでしょう。
こうした複数の社会的要因が絡み合い、従来の大口一括配送から小口多頻度配送へと大きな変化が起きています。
出典参照:令和5年度宅配便・メール便取扱実績について|国土交通省
EC市場の成長は、小口配送需要増加の要因です。コロナ禍を機に消費者のオンライン購買行動が定着し、日用品から高額商品まで幅広い商品がインターネットで購入されるようになりました。従来の店舗販売では大量の商品をまとめて配送していましたが、EC販売では個別の消費者宅への配送が基本となります。
また当日配送や翌日配送といったスピード配送サービスの普及により、配送頻度も増加しています。消費者は複数回に分けて少量ずつ注文する傾向が強くなり、結果として小口配送の件数が急激に増加しました。
現代の消費者は商品の配送に対し、より高度で多様な要求を持つようになりました。単に商品を届けるだけでなく配送時間の指定や置き配サービス、再配達の柔軟な対応など個別のニーズに応じたサービスが求められています。
即時性への要求も年々高まっており、注文から配送までの時間短縮が重要な競争要因です。特に食品や日用品などの必需品については、数時間以内での配送を期待する消費者が増加しています。このような即時配送ニーズに対応するため、小口配送の頻度と複雑さが増している状況です。
フリーランスや個人事業主の増加も、小口配送需要増加の重要な要因です。デジタル技術の普及により、個人でも容易にオンラインビジネスを開始できるようになりました。ハンドメイド作品の販売や個人輸入代行、コンサルティングサービスなど多様な事業形態が生まれています。
これらの小規模事業者は大企業のような大量配送の仕組みを持たないため、必然的に小口配送を利用する機会が多くなります。また在庫を最小限に抑えた運営を行うことが多い点も、頻繁な小口配送が発生する傾向の要因です。
物流DXの推進によって、小口配送の増加による課題に対して効率的な対応が可能になります。具体的にはAIを用いた配送ルートの最適化や倉庫内作業の自動化により、作業効率を高めることが挙げられます。IoTセンサーを使ったリアルタイムの在庫管理も、欠品防止や過剰在庫の削減に効果的です。
これらのテクノロジー導入は配送コストの低減だけでなく、納期遵守率の向上や顧客満足度のアップにもつながります。
AI技術を活用した配送ルート最適化は、小口配送の効率化において効果的な手法の1つです。従来の人力による配送計画では配送先の増加に比例して計画時間が増加し、最適解を見つけることが困難でした。AIシステムは交通状況や配送時間指定、車両容量などの複数の条件を同時に考慮して最適な配送ルートを瞬時に算出します。
機械学習アルゴリズムにより過去の配送実績データから学習し、より精度の高い配送計画を立案できるようになります。これは、配送エリアの特性や時間帯別の交通状況、顧客の在宅パターンなど多様な要素を分析して最適化を図れる機能の1つです。
また、リアルタイムでの配送状況の変化にも柔軟に対応可能です。急な配送先追加や交通渋滞の発生、配送員の体調不良など予期せぬ事態が発生した際も即座に新しい最適ルートを提示できます。
動態管理システムの導入により、配送車両の位置情報をリアルタイムで把握できます。GPS技術とクラウドシステムを組み合わせることで配送の進捗状況を正確に監視し、適切なタイミングでの調整が可能です。
顧客への配送予定時刻の通知や配送状況の共有が可能になり、顧客満足度の向上にもつながります。不在による再配達の削減効果も期待でき、配送効率改善の実現が可能でしょう。
さらに、配送員の労働時間管理や安全運転の促進にも活用できます。過度な長時間労働の防止や事故リスクの軽減により、持続可能な配送体制の構築が可能です。動態管理システムから得られるデータは、配送業務の改善点を特定する貴重な情報源としても活用できます。
自動仕分けシステムの導入により、小口配送の前処理工程を効率化可能です。バーコードやRFIDタグを活用した自動識別技術により、商品の仕分け作業を人手に頼らずに実行できるようになります。
ピッキングロボットの活用により、倉庫内での商品取り出し作業も自動化が可能です。小口配送では多品種少量の商品を取り扱うことが多いため、人力でのピッキング作業は非効率になりがちです。ロボット技術により、正確かつ迅速なピッキング作業を実現できます。
またAIを活用した需要予測により、適切な在庫配置を自動的に決定できます。頻繁に出荷される商品の取り出しやすい場所への配置で、ピッキング効率のさらなる向上が可能です。
クラウド型プラットフォームの活用により、物流業務全体の連携を強化できます。受注から配送完了までの全工程を1つのシステムで管理することにより、情報の共有と業務の効率化が実現します。
複数の配送業者や倉庫との連携も容易になり、配送能力の柔軟な調整が可能です。繁忙期には外部の配送業者を活用し、閑散期には自社リソースを中心とした運営に切り替えるといった柔軟な対応ができるでしょう。
またクラウドシステムにより、リモートワークにも対応した業務体制を構築できます。配送計画の立案や顧客対応などの業務を、場所を問わず実行できるようになります。災害時などの緊急事態においても、業務継続性を確保できる重要な基盤です。
チャットボットやAIを活用した顧客対応システムの導入により、配送に関する問い合わせ対応を自動化できます。配送状況の確認や配送日時の変更、不在連絡などの定型的な対応業務を24時間365日対応可能なシステムで処理可能です。
モバイルアプリやWebサイトを通じた配送追跡サービスにより、顧客自身が配送状況を確認できる環境を整備できます。これにより、問い合わせ件数の削減と顧客満足度の向上を同時に実現できるでしょう。
またデジタル化により蓄積される顧客データの分析で、より良いサービス提供につなげられます。配送時間の傾向分析や顧客の嗜好把握、サービス改善点の特定などデータドリブンな業務改善が可能になります。

物流DXを成功させるためには単なる技術導入にとどまらず、組織全体の意識改革と運用の見直しが必要です。経営層がDX推進の目的を明確にし、現場の意見を反映させながら段階的に変革を進めることが効果的といえます。システムの運用状況を定期的に分析し、課題を洗い出して改善を繰り返すPDCAサイクルの導入もポイントです。
こうした総合的な取り組みによって、小口配送増加の課題に対応可能な持続的な物流体制が実現します。
物流DXにおいて、複数のシステムを連携させることは避けて通れません。既存のシステムと新しいデジタルツールを効果的に連携させるため、API連携やデータ標準化について事前に検討しておく必要があります。
データの統合により、業務全体の可視化が可能です。受注データや在庫データ、配送データなど複数のデータソースの統合で、総合的な判断材料を得られるようになります。これによって小口配送の増加に対し、より戦略的な対応が可能となるでしょう。
また将来的なシステム拡張も考慮した設計が重要です。ビジネスの成長に応じた新しい機能やサービスを追加できる柔軟性の確保により、長期的な投資効果を最大化できるでしょう。
物流DXの最終的な目的は、現場作業者の負担軽減と働きやすい環境の実現です。小口配送の増加により、配送員や倉庫作業員の負担が増加している現状の改善が必要です。
作業者の意見を積極的に取り入れながら、システム設計することが成功のカギとなります。実際の業務フローを詳細に分析し、どの部分をデジタル化すれば効果的かを判断する必要があります。
またデジタル化により生まれた時間を、より付加価値の高い業務に振り向けることも重要です。単純作業から解放された作業者が顧客対応や品質向上に注力できる環境を作ることで、全体的なサービス品質の向上が期待できます。
新しいデジタルツールの導入には、教育体制の整備が伴います。年齢や経験の異なる作業者が等しく新しいシステムを活用できるよう、段階的な教育プログラムの設計が必要になります。
マニュアルの作成だけでなく、実際の業務を通じた実践的な研修も効果的です。現場での問題解決能力を身につけることで、システムトラブル時にも適切な対応が可能となります。
継続的な教育体制も重要な要素です。システムのアップデートや新機能の追加に応じた定期的な研修の実施により、常に最新の知識とスキルを維持できます。これにより、DX推進の効果を持続的に発揮できるでしょう。
大規模なシステム導入を一度に実施するのではなく、段階的なアプローチを取ることが重要です。まずは限定的な範囲でテスト導入を行い、効果を検証してから本格展開を進めるべきです。
各段階での効果測定と改善を繰り返すことで、自社に最適なシステム構成を見つけられます。初期の計画通りに進まない場合も、柔軟に軌道修正できるメリットがあります。
また段階的な導入により、投資リスクを分散可能です。初期投資を抑えながら確実に効果を確認してから次のステップに進むことで、より安全なDX推進が可能になるでしょう。
物流DXにより取り扱うデータ量が増加するため、セキュリティ対策の強化は必須です。顧客の個人情報や企業の機密情報を適切に保護するため、多層的なセキュリティ対策を実施する必要があります。
データガバナンスの仕組みの整備で、データの品質管理と適切な利用を確保できます。誰がどのデータにアクセスできるかを明確に定義し、不正利用を防止する体制の構築が必要です。
また災害時やシステム障害時のデータ復旧計画も、策定しておく必要があります。業務継続性を確保するための定期的なバックアップとリストア手順の確認の実施により、安定した物流サービスを提供できます。
具体的な事例としてある物流企業はAIを活用した配送ルート最適化システムを導入し、配送時間の短縮とコスト削減に成功しました。また倉庫内ではロボットピッキングシステムを取り入れ、作業効率が向上しています。
さらにIoT連携のリアルタイム在庫管理によって欠品や過剰在庫のリスクを減らし、顧客の多様な配送ニーズに柔軟に対応できるようになりました。これらの取り組みは増加する小口配送に対応しつつ、高品質なサービスを維持するための重要な成功要因となっています。
福山通運は長距離輸送と地域配送を組み合わせた、複合一貫輸送システムを構築しています。AIを活用した配送計画によって幹線輸送から地域配送への積み替え作業を最適化し、配送員の待機時間を短縮しました。
同社のシステムではリアルタイムでの車両位置情報と配送進捗を管理し、最適なタイミングで積み替え作業を実行します。これによって小口配送の増加に対応しながら、配送効率の向上を実現しました。
また予測分析により需要変動に対応した車両配置を行い、繁忙期でも安定した配送サービスを提供しています。デジタル化により蓄積されたデータを活用し、継続的な業務改善を実現している優良事例です。
シーエックスカーゴは幹線便のネットワークを活用した、小口配送システムを構築しています。AIによる配送ルート最適化により、幹線便での大量輸送と地域での小口配送を効率的に連携させています。
同社では顧客の配送ニーズを詳細に分析し、配送パターンを最適化しました。定期配送と臨時配送を組み合わせることで、小口配送の増加にも柔軟に対応できる体制を整えています。
さらに配送状況の可視化により、顧客への情報提供も充実させています。配送予定時刻の通知や配送状況の共有により、顧客満足度の向上を実現しました。
日本通運は札幌市の物流センターにおいて、出荷準備作業の自動化システムを導入しています。自動仕分けシステムとピッキングロボットを組み合わせることで、小口配送の前処理工程を効率化しました。
同社のシステムではAIによる需要予測に基づき、商品の最適配置を自動的に決定します。これによってピッキング効率が向上し、小口配送の増加に対応できる処理能力を確保しています。
また作業者の負担軽減も実現しており、より付加価値の高い業務に人員を配置可能です。自動化により生まれた時間を品質管理や顧客対応に活用し、サービス品質の向上を図っています。
出典参照:日通、札幌市の倉庫で出荷準備作業の自動化を開始 |日本通運株式会社
物流DXを進める際には、技術導入のコストや既存システムとの連携の難しさに注意しなければなりません。自動化やAI活用が現場の負担を軽減する反面、急激な変化は従業員の混乱や抵抗を招く恐れがあります。そのため段階的にシステムを導入し、従業員の理解やスキルアップを促す教育体制の構築が重要です。
またデータの安全管理やプライバシー保護にも十分配慮し、長期的に持続可能な物流DXを推進するための計画的な運用が求められます。
新しいシステムの導入初期には、現場作業者の負担が一時的に増加する可能性があります。従来の作業方法と新しいシステムの両方を覚える必要があり、作業効率が低下する期間が発生することもあります。
このような状況を避けるため、十分な準備期間を設けることが重要です。事前の研修や段階的な導入により、作業者が新しいシステムに慣れる時間を確保する必要があります。
また現場の声を定期的に聞き取り、システム改善点の特定も大切です。実際の業務で生じる問題の迅速な解決により、作業者の負担を最小限に抑えられます。
複数のシステムを連携させる際には、予期せぬ問題が発生するかもしれません。システム間のデータ形式の違いや処理速度の差異により、業務に支障が生じることも考えうる可能性の1つです。
このような問題を避けるため、システム導入前に十分な検証を行うことが重要です。テスト環境での動作確認や想定される業務量での負荷テストを実施し、問題点を事前に特定しておく必要があります。
またシステムトラブル時の対応手順を明確にしておくことも大切です。迅速な復旧作業により、業務への影響を最小限に抑えられます。
デジタル化により効率化を図る一方、顧客対応の質の維持も重要な課題です。自動化システムでは対応できない複雑な要求や個別対応が必要な場合に備え、適切なエスカレーション体制を整える必要があります。
AIやチャットボットによる初期対応から人による詳細対応への切り替えをスムーズに行うことで、顧客満足度を維持できます。またデジタル化により蓄積される顧客データを活用し、より個別化されたサービス提供を目指すことも重要です。
定期的な顧客満足度調査によってサービス品質の変化を監視し、必要に応じて改善策を講じることで継続的な品質向上が実現可能となるでしょう。

小口配送の増加は、現代の物流業界が直面する重要な課題です。EC市場の拡大や消費者ニーズの多様化、個人事業主の増加といった社会的変化によってこの傾向は今後も続くと予想されます。
成功のカギは、段階的な導入と継続的な改善にあります。現場作業者の負担軽減を目的とし、適切な教育体制を整えつつスモールスタートでの着実な推進が重要です。
今回紹介した施策や事例を参考に、自社の状況に適した物流DXを推進してみてください。適切な計画と実行により、小口配送増加という課題を成長の機会に変えることが可能なはずです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
