物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

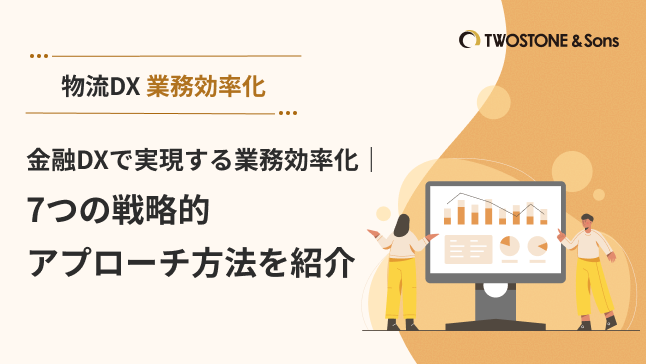
物流業界は現在、慢性的な人手不足や業務の複雑化によって業務効率化の重要性がかつてないほど高まっています。従来の作業スタイルでは手作業や紙ベースの管理が多く残っているため、作業ミスや遅延が発生しやすく、現場の負担が増大しています。
こうした課題を解決し、持続可能な物流体制を実現するためには物流DXの推進が必要不可欠です。物流DXとはデジタル技術を駆使して物流業務の合理化を図る取り組みであり、効率化だけでなくミスの軽減やサービス品質向上も期待できます。
この記事では物流業界が直面する代表的な課題をわかりやすく解説し、それを踏まえた上で業務効率化に役立つツールや推進のポイントについて、具体的に紹介します。これによって物流現場の負担を軽減し、競争力のある物流体制を築くためのヒントが得られるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

物流業界の業務効率化を妨げる問題は多様ですが、大別すると手作業中心の業務体制、システム間の連携不足、そして人手不足に伴う業務負荷の増大に分けられます。これらの課題が複合的に影響し合うことで物流現場の生産性は頭打ちになりやすく、顧客満足度の低下も避けられません。
またこれらの問題は単独での解決が難しく、総合的なDX推進による包括的な改善が必要です。ここではそれぞれの課題を詳しく掘り下げ、物流DXの推進がなぜ重要かを探ります。
物流現場では受発注業務や在庫管理、出荷指示などの多くの作業がいまだに紙の伝票や手入力で行われています。これら手作業が中心の業務はミスが起こりやすく、作業時間も長くかかるため全体の効率向上が妨げられているのが現状です。
バーコードやRFIDといった自動認識技術を導入している企業がでてきています。しかし現場運用が不十分であるケースやシステム連携ができていないケースなど、せっかくの自動化の恩恵を最大限に享受できていない場面も珍しくありません。
この状態を改善するためには物流業務のデジタル化、及び業務自動化を積極的に進める必要があります。デジタルツールの活用によってヒューマンエラーの減少だけでなく、作業の迅速化やデータの即時反映が可能となり、物流業務の信頼性と効率性が向上します。
物流業務は受注管理や在庫管理、配送管理といった複数のシステムを活用して進められますが、これらシステムの間でデータ連携が不十分な場合が多いです。システムが分断されていると情報の重複入力や確認作業が増え、業務の非効率化を招きます。
例えば受注データがリアルタイムで倉庫管理システムに反映されなければ、在庫の誤管理や誤出荷の原因になります。また配送状況の把握が遅れると顧客への正確な納期案内も難しくなり、サービスへの信頼性の低下は想像に難くありません。
こうした課題の解消には、クラウドプラットフォームの導入によるシステム統合が有効です。リアルタイムで情報を共有し一元管理を実現すれば全社的な見える化が進み、迅速かつ正確な意思決定が可能です。
物流業界は慢性的な人手不足に直面しています。特に繁忙期には従業員の業務負荷が高くなり、労働時間の制限もある中で効率的に作業をこなす必要があります。これが現場の疲弊やヒューマンエラーの増加の原因です。
人員が不足すると現場にかかる負担が集中し、作業効率が落ちるだけでなく品質のばらつきやトラブルの発生頻度も増えます。結果的に顧客満足度の低下や離職率の上昇にもつながり、企業全体の経営にも悪影響を与えます。
こうした背景から急務となっているのが、物流DXの推進による自動化やAIの活用です。具体的には倉庫内のピッキングを支援するロボットやスマートデバイス、配送ルートの最適化を実現するAIツールが現場の負担軽減に役立ちます。
物流DXの推進は、従来の物流業務に新たな価値をもたらします。特にデジタル技術を活用した情報共有や業務自動化は、効率化と品質向上を両立させるために不可欠です。
具体的にはリアルタイムデータの活用や配送ルートの自動最適化、ロボットの導入など多角的な施策が効果を発揮します。これらの連動で現場の作業負荷を軽減し、ミスを防止しながらスムーズな物流運営が実現可能です。
ここでは物流DXの推進がなぜ効率化に直結するのか、その代表的な5つの理由について順に解説します。
物流DXの推進によって各工程の情報をリアルタイムで収集し、即座に活用できるようになります。リアルタイムデータは受注状況や在庫レベル、配送状況などを瞬時に把握できるため、状況変化に迅速に対応可能です。
これにより、例えば在庫切れや遅延のリスクを事前に察知し、適切な対策を講じられます。従来の紙ベースや後追いのデータ処理では気づきにくい問題も、リアルタイムでの情報共有によって未然に防ぐことが可能です。
さらに管理者だけでなく現場も最新の情報を共有できるため、指示のズレやコミュニケーションロスが減少します。結果として、全体の作業効率とサービス品質が安定するでしょう。
配送ルートの効率化によって、物流のコスト削減とサービス向上が可能です。物流DXの推進によって、AIやアルゴリズムを活用したルート最適化システムの導入が可能になりました。
これらのシステムは道路状況や交通情報、配送先の優先順位など複数の要素を瞬時に分析し、最適な配送ルートを自動で割り出します。従来の手動でのルート設定よりも正確かつ効率的にルート計画を立てることが可能です。
その結果配送時間の短縮や燃料コストの削減につながり、環境負荷も軽減できるでしょう。また配送遅延のリスクも減るため、顧客満足度の向上にも寄与します。
物流現場における人手不足は深刻な問題です。そこで物流DXの推進により、作業を支援するロボットや自動化機器の導入が進んでいます。
ピッキングや梱包、仕分け作業を担うロボットは単純作業の負担を軽減し、人的ミスの削減にも役立ちます。人手不足の影響を抑えながら生産性を維持できるのがメリットです。
またロボットは疲労や作業時間の制限がなく、一定の品質で安定した作業を続けられます。これによって従業員はより高度な業務や管理業務に注力でき、全体の業務効率アップが期待できます。
ペーパーレス化によって物流業務の迅速化が可能です。従来の紙伝票や手入力の作業は時間がかかるだけでなく、ミスや情報伝達の遅延も発生しやすいです。
物流DXの推進によってスマートデバイスやクラウドシステムを活用した電子化が進み、データ入力や確認作業がスムーズになります。これにより、作業者はリアルタイムで情報を確認・更新でき、業務全体の無駄を削減可能です。
さらにペーパーレスは保管や検索の手間も省き、情報管理の効率化に寄与します。結果として、業務のスピードアップとともに正確性の向上が見込めます。
物流DXのもう1つの重要な効果は、蓄積したデータを分析して需要予測や在庫管理の精度を高められる点です。過去の販売データや季節変動、マーケットトレンドをAIが解析し、適切な在庫量を算出します。
これによって過剰在庫や欠品のリスクが減少し、資金の効率的な運用が可能です。正確な需要予測は配送計画の精度向上にも寄与し、物流全体の効率化につながります。
またデータに基づく経営判断が可能になるため、現場だけでなく経営層も含めた全体の意思決定の質が向上します。これが持続可能な物流体制の基盤です。

物流DXの推進においては、現場の業務を支える多様なツールやシステムの導入が欠かせません。各業務に最適なソリューションを組み合わせることで全体の効率が高まり、作業負荷やヒューマンエラーの抑制にもつながります。
ここでは倉庫管理から配送、現場作業、データ分析、問い合わせ対応に至るまで物流業務の各工程で役立つ主要なツールやサービスを6つ紹介します。それぞれの特徴や導入メリットを理解し、自社の課題に適した選定を進めましょう。
ロジザードZEROはクラウド型のWMS(倉庫管理システム)として、高い評価を得ているサービスです。倉庫内の入出庫管理や在庫管理、棚卸しなどを一元化して現場のミスや作業ロスを削減する設計が特徴です。
導入のメリットは、複数拠点の在庫情報をリアルタイムで可視化できる点にあります。例えば複数の倉庫で同時に稼働している場合でも、統一されたインターフェースで業務を統制できるため管理効率が向上します。
またAPIを活用した外部システムとの連携も容易で、受注・販売システムや配送管理システムとのスムーズなデータ連携が可能です。クラウド型であるため、導入コストや運用負担が抑えられるのも魅力です。
出典参照:ロジザードZERO|ロジザード株式会社
ULTRAFIXはNECソリューションイノベータが提供するTMS(輸配送管理システム)で、配送業務の効率化を目的とした機能が豊富に備わっています。ドライバーの割り当てや車両管理、運行ルートの最適化などを自動化できる点が特徴です。
リアルタイムでの配送進捗の可視化や運行実績のデータ蓄積・分析により、運行管理者の業務負担を軽減します。さらにドライバーの位置情報や稼働状況も把握できるため、安全管理の強化にもつながります。
紙の配送日報や手入力による管理に比べて作業スピードと精度が向上し、トラブルの未然防止にも有効です。複雑な配送計画を立てる必要がある企業にとって、導入効果は高いといえるでしょう。
出典参照:ULTRAFIX |NECソリューションイノベータ株式会社
SMART QBINGは寺岡精工が開発した自動仕分け・ピッキング支援ソリューションで、倉庫作業の自動化を目的としています。従来では人手に頼っていた仕分けやピッキング作業をロボットが担うことで、作業のスピードと精度の安定が可能です。
特に複数商品の同時仕分けや大量出荷に対応する場面で強みを発揮します。AI技術と画像認識の活用で人間の作業者と同等、あるいはそれ以上の精度で作業をこなすことが可能です。
作業環境が統一されるため、新人への教育コストも削減できます。物流業務における自動化の第一歩として、比較的導入ハードルが低いのも魅力のひとつです。
IASが提供するウェアラブルターミナルは手に装着して使える端末として、物流現場での作業効率を高めるアイテムです。バーコードのスキャンや情報確認を手を使わずに行えるため、両手が自由に使える状態で作業が可能になります。
作業中の移動や持ち替えの手間がなくなるため1件あたりの処理時間が短縮され、作業スピードの均一化にもつながります。さらに作業記録はクラウド上に自動で反映されるため、リアルタイムでの進捗管理も可能です。
ハンディターミナルとしての高い堅牢性と軽量設計も現場に適しており、導入後すぐに効果を実感しやすいツールです。少人数でも高精度な作業を維持したい現場に最適といえるでしょう。
出典参照:ウェアラブルターミナル|IDEC AUTO-ID SOLUTIONS 株式会社
LOGINECTはTOPPANが提供する物流向けBIツールです。多様な業務データを可視化し、KPIの進捗やボトルネックを視覚的に把握できるようにするのが特徴です。
複数システムからデータを統合し、ダッシュボード上で一元的に表示できるため現場の状況を素早く把握できます。これによって管理者は状況に応じ、迅速な判断と対応が可能になります。
過去のデータ分析を通じ、業務傾向や課題の明確化も利点です。これまで感覚的に行っていた業務改善をデータドリブンで進めることで、継続的な業務最適化が実現します。
出典参照::LOGINECT®データ可視化|TOPPANホールディングス株式会社
Cognigyは顧客対応や社内問い合わせの自動化を実現する、チャットボットプラットフォームです。自然言語処理に対応しており、複雑な問い合わせにも柔軟に応じることが可能です。
物流業界では配送状況の確認や納期に関する質問、返品対応などの問い合わせ業務が多岐にわたります。これらを自動応答で処理できれば、カスタマーサポートの負荷を軽減可能です。
さらに社内向けにも活用が可能で、マニュアル確認や作業指示の補助などの現場の業務効率にも寄与します。人手をかけずに対応品質を一定に保てるため、労働環境の改善にもつながるでしょう。
出典参照:Cognigy| TDSE株式会社
物流DXを推進する際には、単に新しいツールを導入するだけでは業務効率化にはつながりません。むしろ現場の業務フローや従業員の課題を正しく理解し、それに合ったアプローチを選ぶ必要があります。
また導入のインパクトや結果を適切に測定し、改善を重ねながら取り組む姿勢も大切です。ここでは業務効率化に向けて物流DXを効果的に推進するために意識すべき、5つのポイントを解説します。
物流DXを成功に導く第一歩は、現場の実態に応じた課題を正確に捉えることです。経営層だけで判断するのではなく、実際に業務を行っている担当者の声を集めることが不可欠です。
例えば作業ミスの多発や時間のかかる情報共有、設備の老朽化といった課題は、現場への直接のヒアリングで浮かび上がります。これらの課題を整理し、DXの目的を明確に設定しましょう。
目的が曖昧なまま進めると導入したツールが活用されず、費用対効果が得られません。DXの目的設定を作業時間の短縮や誤出荷率の低下など定量的なものに定めることで、全体の方向性が定まりやすくなります。
物流DXを成功させるには、自社の規模や業務フローに合ったツールを選ぶ必要があります。機能が充実していても現場で使いこなせなければ意味がなく、逆にシンプルでも使いやすく効果が出るツールの方が成果につながるのは明らかでしょう。
まずは現在の課題と業務内容を整理し、どの部分を改善したいのかを明確にします。その上でツールの導入実績やサポート体制、他社事例なども参考にしながら自社の現場に適したサービスを選びましょう。
また複数のツールを導入する場合は、互換性やデータ連携の可否にも注意が必要です。業務全体を俯瞰しながら、部分最適ではなく全体最適を意識した選定が求められます。
物流DXはいきなり全体最適を目指すのではなく、まずは一部業務や拠点に限定した推進からスタートするのが現実的です。小さく始めることで失敗のリスクを抑えつつ、現場に合わせた調整を柔軟に行えます。
例えばひとつの物流センターでWMSを先行導入し、在庫管理の効率化を図った上で、他の拠点に展開するといった流れです。実証を経て得られた成果や課題を蓄積していくことで、より確実な全体導入が可能になります。
またスモールサクセスを重ねることで社内の信頼や理解も深まり、DXに対する心理的なハードルを下げることが可能です。成果の可視化、関係者への共有が次のステップへの原動力となります。
物流DXを進める上で忘れてはならないのが、人と技術の両立です。いくら優れたシステムを導入しても現場で使う人が理解し、納得して運用できなければ定着しません。
ツールの活用にあたっては現場の業務理解や操作教育にも、十分な時間とリソースを割く必要があります。また変化に対する不安を和らげるため、導入前の説明会やフォローアップ体制の整備も有効です。
加えてツールに依存しすぎず、人ならではの柔軟な判断や対応力を活かす場面を残すことも重要です。技術に任せる部分と人が介在すべき領域を明確に分けることで、最適なバランスを保ちやすくなります。
業務効率化を目指してツールを導入する際、既存の業務フローをそのままデジタル化するだけでは十分な効果が得られません。むしろ今までの業務の無駄や非効率を、そのまま引き継いでしまう恐れがあります。
このためシステム導入の前には現行業務を見直して本当に必要な工程か、簡略化できる部分はないかといった視点で再設計することが重要です。業務そのものの最適化がDXの前提になります。
例えば紙で管理していた作業日報をデジタル化する際も単にフォーマットを変えるだけでなく、記入項目の見直しや自動入力の導入を検討するとより効果が高まるため、業務の根本から見直す姿勢が求められます。
物流DXの効果を正確に評価するには、推進前にKPI(成果指標)を設定しておく必要があります。KPIは、業務改善が実際に成果に結びついているかを判断するための基準です。
例えば出荷ミス率の低下や受注処理時間の短縮、在庫差異の削減などの具体的かつ測定可能な指標の設定により、推進効果を定量的に把握できます。これにより、関係者間での成果の共有が容易です。
またKPIの進捗を定期的にモニタリングし、必要に応じて改善策を講じるサイクルを作ることが継続的な改善と定着に役立ちます。推進して終わりではなく、効果を検証し続ける姿勢が成功のカギを握ります。
物流業界では人手不足やコスト上昇などの課題が深刻化しており、現場の改善にはDXの推進が不可欠です。そのようなときは、すでに成功している他社の事例を参考にするのが効果的です。
実際にAIやIoT、ビッグデータを活用して業務効率化に成功している企業では明確な目的のもと、段階的かつ現場起点でDXを推進しています。
ここでは具体的に業務改善に取り組み、成果を上げた企業の事例を紹介します。それぞれの事例から、成功のポイントやツール活用のヒントを読み取っていきましょう。
佐川急便株式会社はGoogle Cloudと連携し、AIを活用した業務の効率化を進めています。特に注目されているのが、AIによる荷物仕分けと配送ルートの最適化の取り組みです。
このプロジェクトでは荷物のデータをリアルタイムで収集・分析し、AIによる最適なルートの自動計算で、ドライバーの負担軽減と配送の精度向上を実現しました。また繁忙期の人員調整や稼働状況の可視化にもAIが活用されており、現場全体の安定稼働につながっています。
加えてGoogle Cloudを通じて社内データを統合・分析する体制も構築しており、継続的な改善が可能な仕組みを整備しています。先進的なAI活用による実践的な取り組みとして、今後も多くの注目を集めそうです。
出典参照:【佐川急便】デジタルトランスフォーメーション(DX)の活用による総合物流機能の強化に向けた戦略的パートナーシップ協定を締結|佐川急便株式会社
ヤマト運輸株式会社は物流の安定運用と効率化を両立させるため、自社独自の輸送ネットワークを構築しています。中でも注目に値するのが、多頻度・少量輸送への対応力を高める仕組みです。
従来では少量出荷の配送は非効率になりがちでしたが、ヤマト運輸は全国に張り巡らせた集配拠点と輸送網を活かし、高頻度配送を実現しています。これにより、荷主企業の在庫圧縮や配送リードタイムの短縮に貢献しています。
さらに集配ルートの自動最適化やトラックの動態管理システムの導入により、輸送効率と環境負荷の削減を同時に達成しました。配送の質を保ちながら効率化を進める先進事例として、業界全体に影響を与えています。
出典参照:実現可能にするヤマトのアセット|ヤマト運輸株式会社
福山通運株式会社では社内に蓄積されたビッグデータをAIと連携させ、物流業務の最適化に取り組んでいます。これは車両の稼働状況や走行履歴、出荷量の推移など多岐にわたるデータが対象です。
これらの情報を基にAIが最適な配車計画を算出し、トラックの空車率を低減させる仕組みを構築しました。その結果として燃料費や人件費の圧縮だけでなく、納期の遵守率の向上にもつながっています。
またAIによる異常検知や予防保全の仕組みも導入し、車両トラブルや業務停止リスクの軽減にも貢献しています。ビッグデータの有効活用が、日々のオペレーション改善に直結している好例といえるでしょう。
出典参照:DXの取り組み | 福山通運株式会社
国際物流を担う株式会社近鉄エクスプレスでは情報のデータ化と自動化を軸に、業務全体の効率化を推進しています。特に輸出入に関わる書類処理の電子化が進んでおり、業務負荷の軽減と正確性の向上を両立しています。
手作業だったインボイスやB/L(船荷証券)などの入力業務をOCRとAIによって自動化し、書類ミスや入力漏れのリスクを抑制しました。さらにクラウドベースで情報を共有できる体制を整えることで、グローバルな業務の効率も高めています。
このような取り組みによって国際間のリードタイム短縮やトレーサビリティ強化にも成功しており、競争力のある物流体制の構築ができました。
株式会社日立製作所は自社の製品を、効率的に届けるための物流基盤強化に取り組んでいます。特に注目されているのが、製品の配送を最適化するために独自開発したロジスティクスソリューションです。
このソリューションでは配送先や在庫の状況をリアルタイムで可視化し、適切なタイミングで製品を出荷できるよう設計されています。またAIによる需要予測も取り入れられており、生産・出荷計画との連携によって効率的な物流運営が可能です。
さらにCO₂排出量の可視化や輸送手段の最適化にも取り組んでおり、環境への配慮も加味したサステナブルな物流が実現されています。大手製造業ならではの視点から、全体最適を図るアプローチは他業種にも応用可能です。
出典参照:物流現場の効率化に貢献するロジスティクスソリューション|株式会社日立製作所
物流DXを推進する際は、システムやツールの導入に目を向けるだけでは不十分です。業務全体を見渡し、どの部分にどのような課題があるのかを見極める視点が欠かせません。
特にデジタル化と相性の良い工程から取り組み始めることで現場に混乱を生まず、成果を出しやすくなります。その上でデータの使い方やプロセス再構築の検討により、単なる自動化にとどまらず本質的な効率化につながります。
ここで紹介するのは業務効率化を実現する上で意識しておきたい、2つの視点です。
業務効率化を目指す第一歩は、現場のプロセスの見える化です。どの工程に時間がかかっているのか、ミスが起きやすいのはどこかといった点の定量的な把握により、改善すべき対象が明確になります。
例えば出荷処理に時間がかかっている場合でも、実際に遅れの原因がどこにあるかは可視化しなければ判断できません。ヒアリングだけでは見えにくい実情も、フロー図や業務ログを通じた整理で具体的な改善策が立てられるようになります。
この作業を通じ、無駄な工程や属人化された作業も発見しやすくなります。可視化は現場と経営層が課題を共有する上でも有効な手段であり、DXの基盤となるプロセスです。
DXの推進において、データの一元化とリアルタイム性は重要な要素です。部署ごとに管理されていた情報を統合し、全社的に共有可能な状態をつくることで判断のスピードと精度が上がります。
例えば受注情報が倉庫や配送部門とリアルタイムで連携していないと、二重入力や確認作業が発生し、全体の処理効率を下げてしまいます。一方でクラウドベースのシステムで連携すれば関係者が常に最新の情報を参照でき、迅速に対応できるでしょう。
またリアルタイム性は、トラブル発生時の早期対応や需要変動への柔軟な対応にもつながります。データが分断されたままでは、正確な意思決定が難しくなるのは想像に難くありません。業務全体の情報をつなぎ、常に最新状態を維持する体制づくりが求められます。

物流DXの推進は、ただのシステム導入ではありません。現場起点の課題整理から始まり自社に合ったツールの選定、スモールサクセスの積み重ね、そして人と技術のバランスを考慮した運用が求められます。
各企業の事例に倣いながら、可視化やデータ活用といった基本的な視点を忘れずに取り組むことが安定的で持続可能な効率化につながります。
本記事で紹介したツールや考え方を参考に目指すべき業務の姿を明確にし、自社にとって最適な形で物流DXを進めていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
