物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

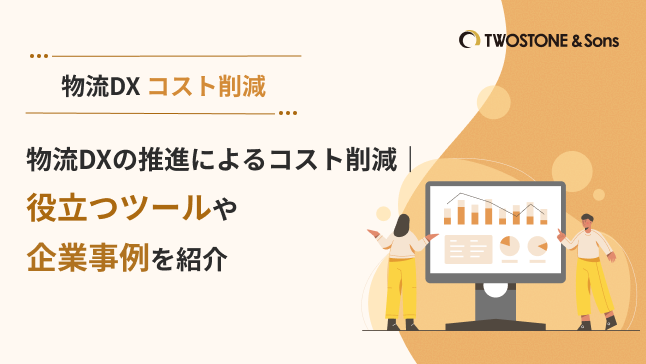
物流業界を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。人手不足や燃料費、人件費の上昇、さらには2024年問題など物流現場が直面する課題は複雑かつ深刻です。
こうした背景から効率化によるコスト削減は、もはや避けて通れないテーマといえます。
しかし、単純なコストカットでは限界があるのも事実です。配送の質を維持しながらコストを抑えるためには、テクノロジーの力を活用した根本的な業務改善が求められます。そこで注目されているのが物流DXの推進です。
本記事では物流業界においてなぜコスト削減が急務なのかを明らかにしつつ、その解決策として物流DXがどのように役立つのかを解説します。さらに実際に役立つツールや企業の取り組みも紹介し、読者が自社の課題を見つけ次のアクションに踏み出せるヒントをお届けします。

物流業界で求められているのは、収益性を高めるためのコスト構造の見直しです。背景には需要の増加に対する供給体制の限界や、外的要因による経費の上昇があります。
従来の業務フローや人海戦術では対応しきれない時代に突入しており、企業の持続的成長には業務の見える化や自動化、最適化といった取り組みが欠かせません。このような流れの中で、物流DXを活用した業務効率化が注目されています。
物流業界では、慢性的な人手不足が続いています。特に配送ドライバーや倉庫作業員の高齢化が進行しており、新規人材の確保が難しい状況です。さらに若年層の物流業界離れも深刻で、採用しても定着率が低いという課題も抱えています。
このような状況では人手による業務処理に限界があるため、効率化が急務となります。ここで役立つのが倉庫内作業の自動化ツールや、配車計画を最適化するシステムです。これらの導入で作業時間を短縮できるだけでなく、従業員の負担も軽減されて離職率の低下にもつながります。
結果として、限られた人員であっても安定した物流オペレーションが実現可能です。
2024年問題とは働き方改革関連法に基づき、トラックドライバーの時間外労働に年間960時間の上限が設けられる問題です。この規制により、長時間労働が前提だった従来の物流体制は大きな転換を迫られています。
これに対応するには単なる労働時間の短縮ではなく、業務全体の再設計が必要です。物流DXの推進によって配送ルートの自動最適化やリアルタイムでの状況把握が可能となり、ドライバーの拘束時間を抑えつつ効率的な配送が実現できます。
また予測精度の高い需給管理によって過剰在庫や不必要な輸送を防止し、無駄な稼働を減らすことが可能です。結果として法規制に対応しながら、利益率の維持・向上が期待できるでしょう。
インターネット通販の急拡大により、個人向けの小口配送が急増しています。特に即日配送や日時指定といった多様なニーズに応える必要があり、物流現場の負担が増しています。
このような変化に対応するには、従来のマニュアル中心の業務では対応しきれません。例えばWMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)の導入により、注文処理から出荷までのプロセスをデジタル化できます。
さらに在庫情報や配送状況のリアルタイムでの可視化により、誤配送や遅延のリスクを低減し顧客満足度の向上にもつながります。ECの成長に伴う業務負荷のシステムによる補完で、持続的な対応体制の構築が可能です。
物流業務において、燃料費と人件費は大きなコスト要因です。特に近年は世界情勢の影響によって燃料価格が不安定となり、企業にとっては予測しづらいコスト負担となっています。
また最低賃金の上昇により、ドライバーや倉庫内の人件費も上昇傾向にあります。このようなコスト圧力に対しては、燃費効率の良い運行ルートの設定や作業時間の短縮による人件費の抑制が有効です。
例えばAIを活用した配車支援システムでは最短かつ渋滞を避けるルートを瞬時に算出し、走行距離を削減できます。また物流センターのレイアウトを分析し、動線を最適化するツールの導入によってピッキング作業にかかる時間と労力を削減可能です。
物流業界にとって、環境への配慮も重要な課題となっています。CO₂排出量の削減や省エネ対策は今や企業の社会的責任としてだけでなく、顧客からの評価にも直結するテーマです。
具体的には積載率の向上による空車率の低減や共同配送の導入、電動車両の活用などが挙げられます。これらの取り組みも、物流DXによって実現可能です。
例えば配送スケジュールの自動調整機能を活用すれば、複数荷主間での積載調整や無駄な運行の削減ができます。またエネルギー使用量の可視化によって効率の悪い工程を把握し、改善アクションへとつなげることが可能です。
こうした取り組みによって環境負荷を抑えつつ、企業としてのブランドイメージを高める効果も期待できます。
物流DXの推進は単なるデジタル化やIT導入にとどまらず、業務プロセス全体の効率化や最適化を実現します。これにより、人手不足やコスト高騰といった物流業界特有の課題に対応可能です。
従来の方法では削減が難しかった時間や労力の無駄を削減できるため、経費削減につながります。こうした効果こそ、物流DXがコスト削減に成功するため必要だといえるでしょう。
ここからは、具体的にどのような形で効果が生まれるかを解説します。
物流DXを推進すると、まず業務効率化と省人化が進みます。従来は人手に頼っていた作業がシステム化され、時間と労力の節約が可能です。
例えば倉庫内のピッキング作業はバーコードやRFIDなどの技術活用によって自動化が進みます。これによって作業ミスが減り、従業員の負担も軽減されます。さらに、配車や配送計画の自動化も効果的です。
配車システムはリアルタイムで道路状況を反映し、最適なルートを割り出します。これにより配送時間を短縮でき、無駄な運行を減らすことが可能です。結果的に必要な人員を抑えつつ高い業務効率を維持できるため、全体のコスト削減に直結します。
物流DX推進では膨大な業務データの活用により、業務の最適化が可能です。まずデータの収集・分析で、現場の問題点や改善点が明確になります。
配送状況や在庫レベル、作業時間などのリアルタイムデータを活用すれば需給バランスの調整や配送計画の精度向上につながります。これにより、過剰な在庫や過剰労働を避けることが可能です。
また機械学習やAIを活用した予測モデルを導入すると、需要変動に応じた柔軟な対応が実現します。季節変動やキャンペーン時の急激な注文増加にもスムーズに対応でき、無駄のない運営を支援します。
データの活用は単なる報告や記録にとどまらず、未来の業務を計画して実行するための土台とすべく利用可能です。最適化を図ることで資源の有効活用とコストの抑制につながり、競争力を高められます。
物流業務には多くの書類や伝票が発生し、その管理には時間やコストがかかります。物流DXの推進によってペーパーレス化が進むと、これらのコストを削減可能です。
電子データの活用により伝票処理や発注管理が自動化され、紙の印刷・保管・郵送にかかる経費が減ります。ミスによる再発行も減少し、作業効率の向上も見込めるでしょう。
さらに書類のデジタル管理は検索や共有も容易になるため、業務の透明性やトレーサビリティが高まります。これによって情報の漏れや誤送信のリスクを抑えられ、管理コストの低減につながります。
加えて環境負荷の軽減にも寄与するため、企業の社会的責任を果たすという観点からも重要です。ペーパーレス化は経済的効果だけでなく、長期的な企業価値向上の一助となります。
物流DXの推進はコスト削減だけでなく、サービス品質の向上にも直結します。業務の見える化や自動化によって配送の正確さや納期遵守が安定し、顧客満足度の向上が可能です。
配送状況をリアルタイムで把握できる仕組みは顧客への情報提供をスムーズにし、信頼感を高めます。こうした透明性は、競合他社との差別化にもつながります。
また物流業務の効率化によりコスト削減が実現すれば、その分を価格競争力の強化や新サービスの開発に充てることも可能です。これが新たな付加価値創造や顧客獲得に貢献します。
結果として物流DXは単なる業務改革に留まらず、企業のブランド力向上や市場での優位性確保の重要な武器となります。将来的な成長戦略の一環としても欠かせない要素です。

物流DXを効果的に推進し、コスト削減を実現するためには段階的な取り組みが必要です。
単にシステムを導入するだけでなく業務の全体像を把握し、課題を洗い出しながら改善を進めることが重要になります。
具体的には業務プロセスの可視化から始まりECRS手法を活用した効率化、デジタル化や自動化の推進、システム連携の強化といったステップを踏みます。その後に行うのが標準化とマニュアル化、PDCAサイクルで継続的に改善していく体制の構築です。
ここでは、各ステップの詳細を解説します。
物流業務の効率化において必要なことはまず、現状の業務内容や流れの正確な把握からです。業務プロセスを可視化すると、どの作業に時間や労力がかかっているか、どこにムダやボトルネックが存在するかが明確になります。こうした現状分析なしに改善策を打つと、的外れな対策となりがちです。
可視化にはフローチャートや業務マッピング、作業時間の計測などの手法があり、これらを活用して全体像を捉えましょう。また、現場からのヒアリングも重要な情報源になります。現場の意見を取り入れることで実態に応じた分析が可能となり、改善効果を高められます。
業務の可視化はDX推進において土台となる作業であり、この後の改善手法やシステム導入の方向性を決める大切な工程です。
ECRSは業務改善の基本手法として広く活用されています。Eは排除(Eliminate)、Cは結合(Combine)、Rは入れ替え(Rearrange)、Sは簡素化(Simplify)を意味し、これらの視点で業務フローを見直すことで無駄を削減します。
例えば重複した作業を排除し、複数の工程をまとめて効率化が可能です。また工程の順序を入れ替えて動線や処理の流れをスムーズにする、手順の複雑さを減らして作業時間の短縮を図るなども効果的です。
ECRSの適用は現場の細かな作業から大きな業務プロセスまで幅広く活用可能であり、物流業務の負担軽減や省人化に直結します。DX推進と組み合わせることでシステム化の優先順位も明確になり、無駄のない効率的なデジタル化が実現しやすくなります。
業務プロセスの可視化と改善案が固まったら、次はデジタル化と自動化を推進します。具体的には紙ベース作業の電子化、及びロボティクスやAI技術を活用し繰り返し作業を機械任せにする方法などです。これにより、作業時間の短縮やヒューマンエラーの減少を実現します。倉庫内の自動搬送ロボットや、AIによる需要予測システムの導入はその代表例です。
さらに受注から出荷までの一連の流れのデジタル管理により、リアルタイムでの状況把握と迅速な意思決定を可能にします。
自動化は初期投資が必要ですが長期的には人件費削減や品質安定につながり、結果としてコスト削減に寄与します。現場の負担軽減にもなるため、労働環境の改善にも効果的です。
物流DXの効果を最大化するには、複数のシステム間連携と情報の一元管理が不可欠です。単独のシステムだけでは情報が分散し、全体最適化が難しくなります。連携により受注管理や在庫管理、配車管理、顧客管理などのデータをリアルタイムで共有可能です。
これによって情報の二重入力や手作業のミスを減らせるほか、迅速な対応が実現します。情報の一元管理は経営層が現場状況を把握しやすくするだけでなく、問題の早期発見や迅速な対応を促進します。
またシステム間連携は拡張性も高め、新たな機能追加やシステム変更にも柔軟に対応可能です。この段階のしっかりした整備が、安定的なDX推進と継続的なコスト削減の基盤となります。
業務の標準化とマニュアル化は、効率化の基礎となる施策です。作業の手順を統一し、誰が担当しても同じ品質・スピードで対応できる環境を整えます。標準化はムダやバラつきを減らし、作業の再現性を高める効果があります。
加えてマニュアル化により期待できる効果が、新人教育の時間短縮や現場の負担軽減です。標準手順を定期的に見直すことで、業務改善のPDCAサイクルと連動しやすくなります。
DX推進においては標準化された作業を前提に自動化やシステム導入が行われるため、無駄のない効果的なデジタル化が可能です。現場に浸透した標準化はトラブルの減少や顧客サービスの安定にもつながり、結果としてコスト抑制に寄与します。
物流DXを推進するには、PDCAサイクルを継続的に実践することが大切です。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルを回しながら業務の質を向上させていきます。
計画段階で設定した目標と実際の業務状況を比較し、改善点を見つけたら速やかに対策を講じることが必要です。これによって変化する環境やニーズに柔軟に対応でき、効率化やコスト削減効果を維持できます。特に物流業務は多様な変動要因があるため、PDCAの定期的な実施が効果的です。
また関係者全員が改善に参加しやすい体制を整えることで、現場の意見や提案を反映しやすくなります。PDCAを通じた継続的な改善は、DX推進の持続可能な成功を支える重要な柱となります。
物流DX推進によるコスト削減では、適切なツールの導入が効果的な手段です。多様な機能を持つツールは現場の課題解決や業務の効率化をサポートし、無駄なコストの削減につながります。特に業務の自動化やデータ活用が可能な製品を選ぶことで、持続可能な改善が期待できるでしょう。
ここからは、物流業界で注目されている4つの具体的なツールを紹介し、それぞれの特徴や導入メリットを解説します。
AI-Smart Readerは紙の伝票や手書きの書類をAI技術で高速に読み取り、デジタルデータ化するツールです。物流現場では依然として散見される紙作業ですが、このツールの導入によってペーパーレス化を推進し、業務効率の向上に貢献します。
具体的には手書き文字や印刷文字の認識精度が高く、複雑な書類も自動で正確に読み取ります。そのため入力ミスの削減や作業時間の短縮が可能となり、結果として期待される効果が人件費や管理コストの圧縮です。
また読み取ったデータは既存の基幹システムや倉庫管理システムと連携しやすいため、スムーズな業務フローを構築できます。AIによる文字認識技術の進化が、物流業務のデジタル化を強力に支援するツールとして注目されています。
株式会社APTが提供するWES(Warehouse Execution System)やWCS(Warehouse Control System)、WMS(Warehouse Management System)は倉庫管理に必要な機能を網羅した統合ソリューションです。これらのシステムを連携させることで在庫管理から入出庫作業、配送準備までの一連のプロセスを効率化します。
WMSは入庫や出庫の管理を担当し、リアルタイムで正確な在庫状況を把握することが可能です。。WCSは自動倉庫や搬送機器と連携し、物理的な作業を自動制御します。WESはこれらの作業全体を統括し、最適なスケジューリングや作業指示を行います。
この3つのシステムの連動で倉庫内の無駄な動きを削減し、作業の効率と精度を高めることが可能です。結果として作業時間の短縮と人員削減につながり、物流コストの低減に役立ちます。
出典参照:WMS・WCS・WES |株式会社APT
Loogiaは配送ルートの最適化を実現するAIプラットフォームです。配送業務において効率的なルート設定は燃料費や時間コストの削減に直結しますが、多数の配送先を考慮した最適ルートを手作業で作成するのは困難です。
LoogiaはAIが地理情報や交通状況、荷物の優先度などをリアルタイムに分析し、最適な配車計画を瞬時に作成します。これにより、走行距離の短縮や配送遅延の防止を図ることが可能です。さらに、配送ドライバーの負担軽減にもつながり、労働環境の改善も期待できます。
また顧客ニーズに応じた柔軟なルート調整や配送数の変更にも対応できるため、変動する業務量にも適応可能です。Loogiaはコスト抑制とサービス品質向上を両立するための有力なツールとして活用されています。
出典参照:Loogia|株式会社オプティマインド
MOVO Berthは物流拠点の荷役作業を効率化するプラットフォームです。特にトラックの待機時間や積み下ろしの作業効率に注目し、物流全体の遅延や無駄を減らすことを目的としています。
このツールはリアルタイムの予約管理機能を備えており、トラックの到着から荷役までのスケジュール調整をスムーズに行えます。このため、拠点内の混雑緩和や待機時間の削減が可能です。待機時間の短縮により、ドライバーの労働時間短縮や燃料消費の抑制が可能です。
さらにMOVO Berthは現場の状況を見える化し、管理者が効率的に作業指示を出せるため全体の運用改善にもつながります。物流DX推進の一環として、拠点運営の効率化とコスト削減を支援するツールです。
出典参照:MOVOBerth|株式会社Hacobu
物流業界ではDXの推進により、多くの企業がコスト削減と業務効率化を実現しています。最新技術を活用しながらの具体的な課題に合わせた施策の展開で、成果を上げています。これらの成功事例が示すのは、物流DXが単なるIT投資ではなく経営課題の解決に直結しているという事実です。
ここでは代表的な4社の取り組みを紹介し、それぞれの取り組みの特徴や得られた効果を解説していきます。
SGホールディングスグループはロボットソーターの導入で荷物仕分けの自動化を進めています。従来の仕分け作業では人手と時間を要していましたが、ロボットの活用により高速かつ正確な処理が可能になりました。
このロボットソーターはバーコード読み取りと仕分け動作を連携させており、人の目視や手作業によるミスを減少させます。結果として作業効率が向上し、処理能力の向上と労働負荷の軽減を両立しました。
また、作業の自動化は人的コストの削減に寄与するだけでなく、品質の均一化にもつながります。これにより、顧客満足度を高めつつ安定した物流サービスを提供できるようになりました。
出典参照:仕分け業務のDXにより、東松山SRCの大幅な生産性向上を実現 ~次世代型ロボットソーター「t-Sort」やRFIDシステムを導入~ | SGホールディングスグループ
ヤマト運輸はGoogleのOptimization APIを活用し、配送ルートの最適化に取り組んでいます。配送ルートの効率化は燃料費や労働時間の削減に直結し、コスト抑制に大きな影響を与えます。
Optimization APIは膨大な配送先データや交通情報を解析し、最短かつ効率的なルートを自動的に算出可能です。これによって従来の経験や勘に頼った配車計画から脱却し、科学的な根拠に基づく計画が可能になりました。
さらにこの技術の導入はドライバーの作業負担軽減、ワークライフバランスの向上などにもつながっています。ヤマト運輸の事例は物流DX推進が環境負荷低減と従業員満足度の両面で効果を発揮する、良いモデルケースです。
出典参照:多様化するニーズと社会課題に対応。Route Optimization API 導入で加速する、ヤマト運輸の業務効率化と働き方改革|ヤマト運輸株式会社
福岡運輸はバース予約・受付システムの導入でトラックの待機時間を短縮し、作業効率の改善に成功しています。トラックの待機時間は労働生産性の低下や燃料浪費の原因となるため、解消が急務でした。
このシステムでは事前予約によりトラックの到着時間を管理し、現場の混雑を緩和しています。リアルタイムで受付状況を把握できるため、スムーズな荷役作業の調整が可能となりました。
結果として平均待機時間の減少によってドライバーの労働負担が軽減されただけでなく、燃料コストの節約にもつながりました。福岡運輸の取り組みは、物流拠点でのDX推進が直接的に運用コストの低減に寄与する好例です。
出典参照:DC/TC 問わず使用できる「バース予約・受付システム」を稼働開始しました|福岡運輸株式会社
株式会社日立物流はAIを活用し、配送計画の実効性を高める取り組みを進めています。配送計画の精度向上は、運行効率の改善とコスト削減に直結する重要なテーマです。
AIは過去の配送データや道路状況、天候情報など多様な要素を分析し、最適な配送スケジュールを作成します。これにより、人間の経験則だけに頼る従来の方法よりも効率的な配車が可能になります。
さらにAIによるシミュレーションにより複数のパターンを検証し、配送遅延やトラブルのリスクを低減できる点も大きな強みです。結果として、配送コストの抑制とサービス品質の両立を実現しました。日立物流の事例は、AIを活用した高度な物流DX推進の代表例として注目されています。
出典参照:AIやIoTを活用し、実効性の高い配送計画を立案する「Hitachi Digital Solution for Logistics/配送最適化サービス」を提供開始|株式会社日立物流
物流DXを推進しながらコスト削減を目指す際には、単に経費を削るだけではなく長期的な効果や運用面のバランスを考慮する必要があります。見かけ上のコスト減少が将来的な負担やリスクにつながる可能性もあるため、計画的かつ戦略的に進めることが重要です。
ここからは物流DXの推進にあたってコスト削減を図る際の注意点を4つ解説し、失敗を避けるためのポイントを押さえていきます。
物流DX推進でコスト削減を図る際は、投資に対するリターン(ROI)を正確に見極めることが不可欠です。新たなシステム導入やツール活用には初期投資や運用コストが発生しますが、その費用対効果を詳細に分析しなければ真のメリットを享受できません。
例えば設備やシステムの導入費用に対してどれほどの業務効率化や人件費削減が見込まれるか、回収期間がどのくらいになるかを計算しましょう。ROIが不透明なまま推進すると、結果的に費用倒れに陥るリスクがあります。
また投資効果を測定するために定量的な指標を設定し、導入後も定期的に評価する体制を整えることが重要です。こうした検証を通じて経営資源を効果的に配分し、持続可能なコスト削減につなげることが可能です。
物流DXの推進にあたってはコスト削減だけでなく、業務改善やサービス向上といった目的を明確に設定する必要があります。目的が曖昧だと施策の優先順位が定まらず、効果の実感が得にくくなります。
例えば単にコストを下げるだけでなく、配送の迅速化や品質安定といった具体的な目標を掲げると、取り組みの方向性が明確です。こうした目的のチーム全体での共有により、現場のモチベーション向上や協力体制の構築も期待できます。
さらに目的に合わせた適切なKPIを設定し、進捗や効果の可視化で推進過程の改善ポイントを洗い出せます。明確な目的と評価基準は、物流DXを戦略的に推進するための土台といえるでしょう。
物流DXは一度に全てを変えるのではなく、段階的な推進が成功に直結します。新技術の導入や業務プロセスの変更は、現場の混乱やリスクを避けるためにも慎重に進めるべきでしょう。
そのためにPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施し、導入予定のシステムやツールが実際の業務に適合するかを検証します。PoCを通じて課題や改善点を早期に発見でき、本格導入後の失敗を防げます。
段階的に小規模から展開し、効果と問題点を確認しながら範囲を広げることで現場負担の軽減と品質維持が期待できるでしょう。こうしたステップを踏むことで物流DXの推進を安定的に進め、確実なコスト削減に結びつけられます。
物流DXの成功は技術導入だけでなく、現場の意識改革と人材育成が重要な要素です。新しい仕組みやツールを効果的に活用するには、従業員の理解と協力が欠かせません。
変化に対する抵抗感を減らし、改善に積極的に参加してもらうための環境整備が求められます。具体的にはDXに関する教育プログラムや研修、定期的な情報共有の場を設けることが効果的です。
またDX推進を担う人材を育成するため、専門知識やスキル向上支援の制度も必要です。これによって現場の業務効率化や品質向上を継続的に推し進める体制が整い、結果としてコスト削減にもつながります。

物流DXの推進は単なる技術導入ではなく、業務全体の見直しと体制構築を通じて初めて効果を発揮します。現状の業務プロセスを可視化し、段階的に改善策を取り入れることで効率化とコスト削減を両立可能です。
本記事で紹介した事例やステップを参考に自社の物流業務や体制を見直し、効果的な物流DX推進を目指してください。実践的な方法を理解し戦略的に取り組むことで、コスト削減と業務品質の向上が可能となるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
