物流DXで課題解決へ|2024年問題と人手不足に立ち向かうための実践ガイド
物流

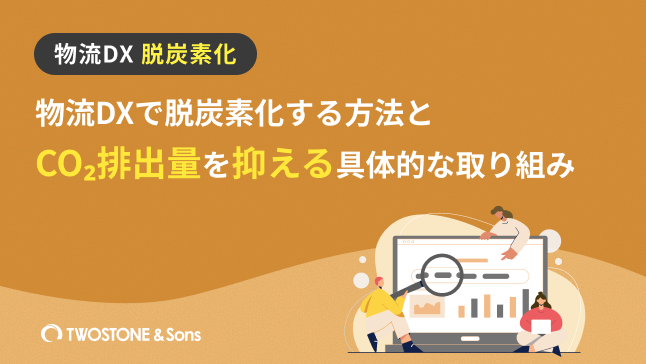
現代の物流業界は、環境負荷の軽減が求められる中で大きな変革期を迎えています。脱炭素化への対応は社会的責任として避けて通れない課題であると同時に、持続可能なビジネスの基盤を築くための重要なテーマです。
物流のCO₂排出量は全産業の中でも高い割合を占め、対策の遅れは環境問題のみならず企業の競争力低下にもつながりかねません。そこで物流DXを推進し、効率化と環境負荷軽減を同時に実現する取り組みが注目されています。
この記事では脱炭素化に向けた物流DXの具体的な方法と、実際に活用されている省エネルギー技術や運用改善策について詳しく解説します。これを参考にすれば、環境対応を強化しつつ業務効率も高める実践的な戦略が見えてくるでしょう。

物流業界は日本全体のCO₂排出量の大きな割合を占めており、その削減は国家レベルでも重点課題となっています。特に指摘されるのがトラック輸送に依存する現状は燃料消費量が多く、環境負荷が高いという点です。
また温室効果ガスの排出抑制が世界的に強化される中、物流企業にも環境負荷削減の責任が求められています。さらに消費者や取引先からも環境配慮を求める声が高まっているため、脱炭素化は企業価値向上にも直結する課題です。
物流業界の脱炭素化には多様なアプローチがあり、技術導入から運用改善まで幅広く展開されています。具体的に挙げられるのは、以下の5つの手法です。
これらの施策を組み合わせることでCO₂排出量削減の効果を最大化しつつ、物流業務の効率化も実現できるでしょう。
電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)の導入は、物流の脱炭素化における直接的な手法の1つです。これらの車両は内燃機関を持たず走行時のCO₂排出がゼロであるため、燃料由来の温室効果ガス削減に貢献します。
EVはバッテリーの容量向上や充電インフラの整備が進むことで、中長距離の物流にも対応できるようになってきました。
一方でFCVは水素を燃料とするため充填時間が短く、長距離輸送に適した特徴を持ちます。ただし初期導入コストや充電・水素ステーションの整備状況、車両の走行距離制限などの課題も残っています。
これらを踏まえ物流企業は自社の配送ニーズや拠点環境を考慮し、段階的な導入を進める戦略が求められているのが現状です。政府や自治体の補助金制度の活用で導入負担を軽減できる場合もあり、最新動向を注視しながら計画的に取り組みましょう。
モーダルシフトとは、CO₂排出量が比較的少ない鉄道や船舶への輸送手段の切り替えを指します。トラック輸送中心の物流構造から環境負荷の低いモードへの転換を図ることは、物流業界の脱炭素化において重要な施策です。鉄道や船舶は大量の貨物を一度に運ぶことが可能なため、トラックに比べて単位輸送あたりのCO₂の排出が抑えられます。
さらに高速道路の渋滞回避や道路インフラの負荷軽減にもつながるため、社会的なメリットも大きいです。しかしモーダルシフトの実現には輸送ルートの再設計や積み替え施設の整備、関係者間の連携が必要となります。
これらの課題に対処しつつITを活用した輸送計画の最適化を行うことで、効率的かつ環境に優しい物流ネットワークを構築できます。結果的にCO₂排出削減とコスト低減の双方を実現できるでしょう。
物流における共同配送や積載効率の向上は、トラックの稼働台数を減らしCO₂排出量の抑制に貢献します。共同配送は複数の企業が配送を協力して行う仕組みで、空車や半空車の走行を減らし輸送効率を高めます。これによって同じ量の貨物を運ぶ際に必要なトラック台数が削減され、燃料消費と排出ガスを低減可能です。
積載効率の向上は、積み込み計画の最適化や荷物の形状に合わせた積載方法の工夫により実現されます。最新の物流管理システムやAI技術を活用すれば、積載率を最大化しながら配送ルートの無駄も省けるでしょう。
こうした取り組みにより期待される効果は、環境面にとどまらず、配送コストの削減や労働時間の短縮など、企業の競争力強化にも直結します。
エコドライブ支援システムはドライバーの運転行動をリアルタイムで分析し、燃費改善と安全運転を促す技術です。急加速や急減速、アイドリング時間の削減など燃料消費を増加させる運転の抑制がCO₂排出の抑制に役立ちます。こうしたシステムが行うのは車両に搭載したセンサーやGPSを活用した、データの収集です。
AI解析を組み合わせ、具体的な改善提案やドライバーへのフィードバックを提供します。これにより、運転技術の標準化や継続的なスキル向上が期待できるでしょう。
導入コストはかかりますが、燃料費削減と事故防止効果を通じて中長期的に経済的メリットを生みます。環境負荷軽減だけでなく安全運転の促進にもつながるため、多くの物流企業で注目されています。
物流施設の省エネ化は脱炭素化に向けた重要な柱です。倉庫や配送センターでは照明や空調、搬送機器の電力消費を抑えるため、LED照明の導入や高効率空調設備への切り替え、省エネ機器の活用が求められます。
また建物の断熱性能を高めることで空調負荷を軽減でき、総合的なエネルギー消費削減にもつながるでしょう。さらに太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギーの導入も進んでいます。施設内で発電した電力の利用によって化石燃料に依存しないクリーンなエネルギー供給が可能となり、CO₂排出を抑制できるでしょう。
こうした取り組みは初期投資が必要ですが、長期的なコスト削減と環境負荷軽減の両立を実現します。物流DXの一環としてエネルギー管理システムを導入し、消費電力の見える化と最適化を進めることも効果的です。
物流DXの推進で脱炭素化を効果的に実現できる可能性が高まります。デジタル技術を活用し、配送ルートの最適化や積載率の向上、倉庫のエネルギー効率化など複数の側面で環境負荷を抑える取り組みが進められています。
さらにEVやFCVトラックの導入支援やサプライチェーン全体のCO₂排出量の見える化も、物流DXの重要な役割です。これらの総合的な実施により、持続可能な物流体制を構築できるでしょう。
配送ルートの最適化は、物流DXがもたらす脱炭素化の基本的な手法の1つです。ITシステムを活用して配送先や交通状況、車両の特性を総合的に分析した効率的なルートの算出により、走行距離を短縮できます。結果として燃料消費量が抑えられ、CO₂排出量の削減につながります。
またリアルタイムの交通情報を反映した動的なルート変更も可能となり、渋滞回避や無駄な停車を減らせるでしょう。これにより配送効率が向上し、ドライバーの負担軽減も期待できます。
加えて複数の配送拠点や車両を一元管理できるため、運用全体の無駄を洗い出し改善が図れます。こうしたルート最適化は、環境負荷軽減と経営効率化を両立させる重要な施策です。
物流DXの活用による積載率の向上、共同配送の実現はトラックの稼働台数削減に直結します。積載率の向上ではAIを使った荷物の形状や重量の分析に基づき、効率的な積み込み計画を立てられます。これにより空車や半空車の走行を減らし、燃料消費削減とCO₂排出を抑制できるかもしれません。
また複数企業間で配送を共有する共同配送は輸送効率を高めつつ、配送頻度や走行距離の減少を促します。共同配送の実現には情報共有や調整が不可欠ですが、物流DXが提供するプラットフォームやコミュニケーションツールが円滑な連携を支援します。
これらの取り組みは環境対策だけでなく物流コストの圧縮や配送品質の向上にも貢献し、企業の持続可能な成長が実現できるでしょう。
物流DXの推進は倉庫のエネルギー効率化と自動化にも及びます。LED照明や高効率空調設備の導入はエネルギー消費の削減に直結し、設備の稼働状況のIoTでのリアルタイムの監視によって無駄を最小限に抑えられます。
また倉庫内の自動化システムやロボット導入は作業効率を高めるだけでなく、稼働時間の短縮と省エネ運用が可能です。AIを活用した在庫管理やピッキング最適化は、作業時間の短縮や人手不足対策にも役立ちます。
こうした施策によってエネルギー消費の見える化と効率的な運用が両立し、CO₂排出の抑制に寄与します。物流DXによって倉庫の運用を高度化し、環境負荷を抑えつつ競争力も維持できるでしょう。
EV(電気自動車)やFCV(燃料電池車)トラックの導入は、物流の脱炭素化において重要な役割を果たします。これらの車両は走行時のCO₂排出がほぼゼロであり、環境負荷の軽減に寄与します。
しかし導入にあたり課題となるのが、車両の運用管理や充電インフラの整備といった存在です。ここで物流DXが活用され車両の走行データや充電状況をリアルタイムで把握し、効率的な運用を支援します。
デジタルプラットフォームの活用により、最適な充電タイミングの提案や車両の稼働状況のモニタリングが可能になり、無駄な充電や空走の防止につながります。さらにバッテリー残量や走行距離を考慮した配送計画の調整もサポートされるため、運行の無駄を最小限にまで抑制できるでしょう。
物流DXはサプライチェーン全体のCO₂排出量を見える化するための、重要な手段となっています。原材料の調達から製造、配送、販売に至る各プロセスで排出される温室効果ガスをデータ化し、詳細に分析できるようになります。
さらに複数の企業や拠点が関与する複雑なサプライチェーンにおいても、デジタル技術を用いて情報を一元管理し全体の最適化を図ることが期待できるでしょう。CO₂排出量の見える化は環境に配慮した企業活動の透明性を高めるだけでなく、ステークホルダーへの説明責任を果たす上でも効果的です。
この取り組みによって持続可能なサプライチェーンの構築が促進され、脱炭素化に向けた実効性の高い戦略を推進できるでしょう。結果として環境負荷の削減と企業の社会的信頼性向上の両立が可能になります。

物流業界で脱炭素化を実現するためには、具体的なツールの導入が不可欠です。これらのツールはCO₂排出量の計測や運用の効率化、さらには環境負荷の低減に向けた戦略立案を支援します。デジタル技術の活用で、環境対策を効果的かつ持続可能に推進できます。
ここで紹介するのは物流DX推進において注目されている、脱炭素化支援ツールです。それらの特徴や活用方法を解説していきましょう。
CO2 Emissions Meterは物流現場の車両から排出されるCO₂を、リアルタイムで計測するツールです。車両ごとの燃料消費量や走行距離を基に正確な排出量を算出できるため、環境負荷の見える化に貢献します。
データはクラウド上で管理され、管理者は各車両の排出状況を詳細に把握できます。これにより、効率的な運行計画の立案や排出量削減に向けた改善策の検討ができるでしょう。
また環境対策の実績報告にも活用でき、ステークホルダーへの説明にも役立ちます。CO2 Emissions Meterは使いやすいインターフェースを備え、現場作業者の負担を軽減しつつ正確なデータ収集の支援が可能です。こうした機能が物流事業者の脱炭素化を後押しします。
出典参照:CO2 Emissions Meter | 株式会社日新
EcoNiPassは企業全体の環境データを一元管理し、CO₂排出量の分析やレポート作成を効率化するソリューションです。多様なデータソースから情報を収集し、統合的な管理によってサプライチェーン全体の環境負荷を俯瞰できます。
特に物流部門においては配送データや燃料消費情報を細かく分析し、改善ポイントを抽出可能です。ダッシュボード機能によって関係者がリアルタイムで状況を把握しやすく、迅速な意思決定が可能になります。
さらに環境関連法規への対応や社内外の報告書作成も支援し、コンプライアンス遵守に役立ちます。EcoNiPassは脱炭素化の進捗管理を効率的に推進するため、多くの企業で採用されているツールです。
MOVO VistaとMOVO Fleetは物流の運行管理や車両稼働状況をデジタル化し、運用の効率化と環境負荷軽減を両立させるツールです。
MOVO Vistaは配送ルートの最適化や荷物の追跡を支援し、無駄な走行の削減に貢献します。MOVO Fleetは車両の状態や燃料消費量をリアルタイムに監視し、エコドライブ支援やメンテナンスの計画立案が可能です。
これらのツールの活用で走行距離や燃料使用量の削減が進み、CO₂排出量の低減に寄与します。また運行データはクラウドで一元管理され、複数拠点や車両の管理がスムーズに行えます。物流DX推進の中で脱炭素化と業務効率の両面で効果を発揮するのが、これらのツールです。
出典参照:Hacobu|株式会社Hacobu
LIFTI carriersは物流業界向けのマッチングプラットフォームとして、荷主と運送事業者の効率的な連携を実現します。積載率の向上や空車の削減を促進し、結果としてトラックの稼働効率を高めCO₂排出量削減に貢献します。デジタル上で荷物情報や運送可能な車両をリアルタイムに共有できるため、無駄な走行や空きトラックの発生を抑制できるでしょう。
加えて複数荷主間での共同配送を促進し、輸送効率の向上に役立ちます。こうした仕組みは環境負荷軽減に直結し、持続可能な物流の実現を支えます。またプラットフォームは操作性に優れ、利用者の負担を抑えながら効率的な運用が可能です。
LIFTI carriersは物流DX推進と脱炭素化双方の達成に寄与する、有力なツールです。
出典参照:LIFTI carriers|株式会社Univearth
近年、物流業界では環境負荷の低減に向けて脱炭素化が急務となっています。輸送に伴うCO₂排出量削減は企業の社会的責任であり、規制対応や顧客からの要求に応える上でも不可欠です。そこで多くの企業がDXを活用して車両の電動化や配送の効率化を推進し、環境負荷軽減を実現しています。
これから紹介する事例は、業界が抱える課題に対してDXを活用した有効な解決策を示しています。これらの取り組みから学び、自社の脱炭素化戦略に活かすヒントを得られるでしょう。
ヤマト運輸は小型EVトラックの導入を進め、配送車両の電動化を加速しています。これらの車両は走行中のCO₂排出を抑え、都市部の騒音問題の緩和にも寄与します。導入に際しては充電インフラの整備や運用方法の見直しも実施し、電動車両の効果を最大限に引き出す体制を構築しました。
さらに運行データを活用して効率的な配送ルートを設定し、無駄な走行やエネルギー消費を減らす工夫もしています。こうした施策は環境負荷の軽減だけでなく、燃料コスト削減にもつながり、経済的な効果も生み出しています。ヤマト運輸の取り組みが注目される理由は、持続可能な物流を推進する模範的な例となるためです。
出典参照:電気小型トラック「eCanter」新型モデル約900台を全国に導入 | ヤマト運輸株式会社
日本郵便は全国の郵便事業における環境負荷低減のため、電動車両の導入を拡大しています。加えて運行管理にはデジタル技術を積極的に導入し、車両の燃料消費や走行データをリアルタイムで把握しています。このデータを分析し、効率的な配送ルートやエコドライブを推奨しているため燃料の無駄遣いが減少しました。
さらに郵便局の施設では省エネ設備の導入や太陽光発電の活用が進み、トータルでの環境負荷削減を実現しています。これらの多角的な取り組みが担っているのは環境対策を物流全体に浸透させ、社会的責任を果たす重要な役割です。
今後も技術革新を取り入れ、より持続可能な事業運営を目指す姿勢がうかがえます。
出典参照:デジタル時代における郵政事業の在り方について|日本郵便株式会社
株式会社スタンダード運輸は協業する複数の事業者と連携し、カーボンフリー輸送の実現に向けた取り組みを強化しています。共同配送や積載効率の改善を通じてトラック台数を削減し、結果的に走行距離の減少によるCO₂排出量の抑制に成功しました。
加えて運行状況をデジタル化して管理し、燃料消費の見える化やドライバーの運転行動改善に取り組むことで、持続的な環境負荷軽減を図っています。こうした協業モデルが生むのは物流全体の効率性向上の貢献による、環境負荷を抑えつつサービス品質を保つ好循環です。
今後も連携体制の強化を通じ、より広範な脱炭素化の推進が期待されます。
出典参照:中小規模事業者向けの脱炭素経営導入事例集|株式会社スタンダード運輸
三井物産はIoTセンサーとAI技術を組み合わせ、配送計画の最適化に取り組んでいます。車両の位置情報や交通状況をリアルタイムに収集し、AIが複数の条件を踏まえた最適なルートを自動生成可能です。この手法によって無駄な走行や渋滞の回避が可能になり、走行距離と燃料消費を効果的に削減しています。
また車両の稼働データを活用し、メンテナンスのタイミングも最適化して安全性を確保しつつ環境負荷の低減に寄与しています。こうしたテクノロジーの活用が持続可能な物流運営を支え、企業の環境責任を果たす取り組みの一環として評価されている理由です。
出典参照:AIやIoTを活用した配送計画の立案により、配送業務の負荷軽減、効率化|三井物産株式会社
三菱倉庫は物流倉庫のエネルギー効率化に注力し、太陽光発電設備を導入して施設の電力を再生可能エネルギーで賄っています。これにより施設内のCO₂排出量削減に貢献するとともに、電力コストの抑制も図っています。
さらに倉庫内の照明や空調の省エネ化も進め、環境負荷軽減と運用効率の向上を両立させました。配送現場においてはEVの小型トラックを導入し、短距離配送におけるCO₂排出量を低減しています。
こうした取り組みは施設運営と配送の双方から環境負荷軽減を追求する総合的な戦略となっており、今後の持続可能な物流基盤の構築に向けたモデルケースとして注目されています。
物流DXによる脱炭素化は、環境負荷の軽減と業務の高度化を両立する有効な手段です。しかし実際に現場で推進していく上では、技術的・人的・経済的な観点から複数の懸念点が浮かび上がります。これらを無視したまま施策を進めると推進が失敗に終わる、現場の混乱を招くなどの恐れもあり、事前に課題を正確に把握し対策を検討する姿勢が求められます。
ここで解説するのは脱炭素化を行う上での、5つの懸念点です。
脱炭素化を物流現場で実現するにはEVトラックや自動倉庫システム、再生可能エネルギー設備などの導入が必要となり、初期投資額が膨らむ傾向にあります。特に中小企業では経営体力やキャッシュフローに余裕がない場合も多く、導入そのものが大きなハードルになります。また単に設備を揃えるだけでなく社内システムとの連携や研修費用も必要となり、導入後のコストも無視できません。
さらに新技術に関してはリースや補助金を活用できる場合もありますが、申請の手間や条件の制約があるため活用の難易度は高いといえるでしょう。こうした状況においては段階的な投資戦略と、中長期的なROIを見据えた費用対効果の明確化が不可欠です。費用が先行するこの段階をどう乗り越えるかが、脱炭素化の実現可否を左右します。
EVトラックや水素エネルギー車両の活用を考えても、充電インフラや水素ステーションの整備が都市部に集中しており、地方や中継拠点では未整備のままというケースが少なくありません。またIoTやAIを活用した倉庫管理システムも、高速通信やセンサー環境が整っていなければ実用レベルに達しません。
このような背景から最新技術の導入に二の足を踏む企業も多く、物流DX推進が思うように進まない一因となっています。解決策としてはインフラ整備を前提にしたスモールスタートや地域連携による共同整備、そして仮設型の設備導入を検討する方法があります。技術に合わせて業務プロセスを再設計する柔軟性も、今後は重要になるでしょう。
現場の業務プロセスを抜本的に見直す必要があるため、現場従業員や管理者の理解と協力が不可欠です。しかし従来型のアナログな業務が長く続いてきた現場では、新しいツールや考え方を受け入れる土壌が整っていないケースが見られます。これが結果として現場の抵抗や混乱につながり、導入の遅れや定着率の低下を招くことがあります。
オペレーション変革を成功させるには関係者全体を巻き込んだ段階的な導入と、現場に合った教育・訓練の整備が不可欠です。また現場からのフィードバックを取り入れ、プロセスを柔軟に調整する仕組みも必要です。現場の声を無視せず、実効性あるプロジェクト推進体制の構築によってスムーズな変革が期待できるでしょう。
脱炭素化の評価指標として基本となるのがCO₂排出量の測定です。しかし実際には企業ごとに異なる計測方法やシステムの分散など、正確な集計が難しくなってきています。業界全体で統一された算定基準や相互接続可能なプラットフォームの普及が、まだ途上にあるのが実情です。
また排出源が多岐にわたるため、どの部分のデータをどう取得するかという基本的な方針さえ定まらないケースも多くあります。こうした課題に対応するにはガイドラインに基づいた独自の基準整備や専用ツールを活用したリアルタイム計測、データの一元管理が求められます。さらに社内外のステークホルダーと協力し、透明性のある測定体制を築くことで脱炭素経営の信頼性向上につながるでしょう。
DXによる業務改革や技術導入が進む中、従業員が抱える精神的・肉体的な負担にも配慮が必要です。新しいシステムへの適応や運用方法の習得には時間と労力がかかり、特に高齢の従業員やITリテラシーに乏しい人材にとっては大きなストレス要因となり得ます。
このような変化に対応するには、OJTやeラーニングを組み合わせた段階的な教育体制が有効です。さらに学習の成果を定期的にフィードバックし、評価制度やインセンティブと連動させることで、従業員のモチベーション維持にもつながります。また労働環境面では、業務負荷の適正配分や働きやすさの確保が重要です。人材への投資は、持続可能な物流DXと脱炭素化の両立に不可欠な要素です。

物流業界の脱炭素化は、もはや選択肢ではなく必須の取り組みとなっています。EVトラックの導入や配送ルートの最適化、省エネ倉庫の運用など環境負荷を低減する手法は多岐にわたります。こうした施策を支えるのが、物流DXの力です。
しかし、その実現には初期投資の課題や現場の変革への対応も求められます。成功のカギは戦略的な段階的推進と、社員を巻き込んだ継続的な改善です。今回紹介した事例やツールを参考に自社の状況に合った形で物流DXを進めていくことが、持続可能な経営への第一歩となります。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
