物流DXで課題解決へ|2024年問題と人手不足に立ち向かうための実践ガイド
物流

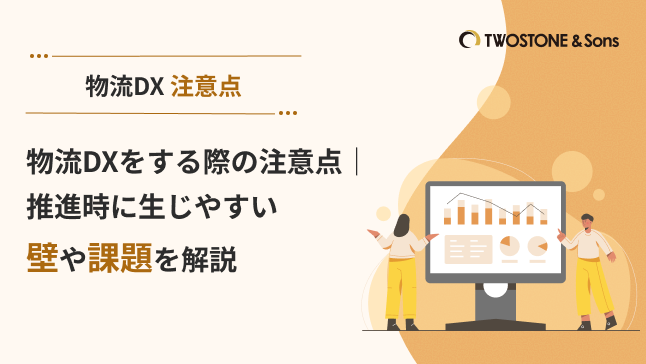
物流現場の人手不足やコスト上昇、脱炭素化への対応など物流業界はかつてないほどの変革を迫られています。その中で注目されているのが、物流DXの推進です。AIやIoT、自動化技術の活用によって業務の最適化や省力化、さらには環境対応まで実現できるでしょう。
しかし物流DXを推進する際にはテクノロジー導入そのものだけでなく、企業文化や現場との連携、法規制、国際展開といった多面的な課題も無視できません。
本記事では物流業界が今直面している課題と、それに対してDXを進める際に乗り越えるべきポイントをわかりやすく解説します。業務改革を進める上での参考として、全体像を把握しながら自社の課題に合った視点を持ちましょう。

物流業界は経済活動の根幹を支えるインフラでありながら、老朽化したオペレーションや人材不足、急速な需要の変化に適応しきれていない現状があります。特に2024年問題と呼ばれるドライバーの労働時間制限や環境対応、グローバル展開への対応は喫緊の課題です。
このような背景から業務効率と持続可能性を両立する物流DXの推進が求められていますが、単なるシステム導入だけでは本質的な課題が解決されません。技術や組織、法制度の3軸を見据えた変革が必要です。
AI・IoT・ロボティクス技術は、物流業務を一変させる可能性を秘めています。倉庫内での在庫管理や仕分け作業へのロボットの導入により、省人化と作業精度の向上が同時に実現できるでしょう。またIoTセンサーによって車両や荷物のリアルタイム追跡が可能になり、運行状況や納品スケジュールの最適化も図れます。
一方、これらの技術は導入後すぐに成果が出るわけではありません。運用設計や既存業務との整合性を考慮しながら、段階的に導入を進める必要があります。
特にAI活用では、データの質と量が運用成果に直結します。業務データの整備が不十分な状態でアルゴリズムを導入しても、期待された効果は出ません。データ基盤の構築と、それを活用する人材の育成を並行して進めることが重要です。
カーボンニュートラルへの国際的な潮流を受け、物流業界にも脱炭素化への対応が強く求められています。輸送手段のEV化や倉庫の省エネ化、モーダルシフトの推進といった環境配慮型の取り組みはいずれもDXとセットでなければ効果的に進みません。
例えば走行距離や燃料消費量のデータをリアルタイムで把握するには、IoTの導入が不可欠です。また排出量の可視化や配送ルートの最適化には、AIや統合管理システムの活用が求められます。このようにサステナブル物流の実現は、DXとの統合を前提とした取り組みであるといえます。
ただし環境負荷削減と業務効率の両立には、全体最適の視点が必要です。部分的な対策だけではかえって別の工程に負荷が集中する可能性もあるため、全体の業務フローを見直しながら進めることが重要になります。
物流企業が国際競争力を維持・強化していくためには、グローバル視点での物流DX推進が欠かせません。特に越境ECの拡大や海外拠点との連携においては、標準化された業務フローとシステムの統合が大きなポイントとなります。
しかしながら国や地域ごとの商習慣やインフラ整備状況の違い、言語や法制度の壁はDX推進の障害となることが少なくありません。そのためグローバル展開を前提としたDXには、多言語対応やクラウド基盤の整備といった準備が必須です。
さらには各国のサプライチェーン全体を俯瞰しつつ調達から出荷、配送に至るすべての工程で一貫した管理を行える体制づくりが求められます。グローバル物流に適した柔軟性と拡張性のあるシステムの構築が、競争力強化の要です。
物流業界では輸送安全や労働環境の保全、環境規制など多岐にわたる法規制への対応が求められます。2024年問題をはじめとする法改正によって労働時間の上限や休憩の義務化が進む中、業務計画や配車戦略の見直しは不可避です。
また電子帳簿保存法やインボイス制度の導入など、物流現場における事務処理のデジタル対応も急務となっています。こうした制度変更に適応するためには、単なる紙ベースからの置き換えではなく、業務全体のプロセス改革が必要です。
加えて業界標準に沿ったデータ連携やフォーマットの統一も進んでおり、自社独自の運用を続けていては他社との連携が難しくなる可能性もあります。規制と標準の両方を意識したDX推進が、将来の持続的成長に向けた前提条件です。
人手不足やコスト上昇、環境規制など多くの課題を抱える物流業界において、物流DXの推進は実用的な打ち手として注目されています。特にテクノロジーの導入によって業務の自動化や効率化が進み、限られたリソースでも安定したオペレーションが実現できるでしょう。
またリアルタイムの情報収集や分析が実行可能となれば、経営判断の迅速化や現場改善も容易になります。サプライチェーン全体を視野に入れた連携強化にもつながり、企業競争力の維持も実現できるでしょう。
物流業界では慢性的な人手不足が深刻化しており、特にトラックドライバーや倉庫作業員の確保が難しくなっています。こうした状況に対して、DXの推進は有効な対策です。
自動化によって人手を減らすだけでなく、作業の正確性と再現性も高まるため品質管理の観点からもメリットがあります。またIoTセンサーやカメラを使った作業監視や検品の自動化も可能になり、現場の業務負担軽減につながります。
結果として人材を創造的な業務に再配置可能となり、業務全体の効率と従業員満足度の向上が実現できるでしょう。人手不足という構造的な課題に対し、根本的な解決の手段として物流DXの推進は欠かせません。
物流コストの中で大きな比重を占めるのが輸送費用です。配送効率を高めることはコスト削減だけでなく、サービス品質の維持・向上にも直結します。物流DXではリアルタイムの交通情報や過去の配送実績を基に、最適なルートを導き出す配送管理システムが活用され、無駄な走行や空荷の発生を抑制できるでしょう。
さらに積載率をAIで自動計算する仕組みや複数の配送先を効率よくまとめるルート統合も可能となり、少ないリソースでより多くの荷物を運べる体制が構築されます。これによって燃料費や人件費を抑えつつ、遅配や誤配送のリスクも軽減できるかもしれません。
配送品質を担保しながらコストを抑えるという難題に対し、テクノロジーが可視化と最適化の手段を提供します。物流DXは効率化とサービス向上を同時に実現するカギです。
物流業務は工程が複雑で、属人化しやすい特徴をもっています。こうした業務の可視化により、現場改善のスピードと精度の向上が期待できます。物流DXは各作業工程の進捗や問題点をデジタルデータとして記録・分析できる仕組みを提供し、状況把握を容易にするでしょう。
例えば倉庫内の入出荷処理時間や作業者の動線、トラックの到着・出発時刻などの一元管理により、どこにボトルネックがあるかを明確にできます。これによって改善施策を立案・実行し、結果を検証するというPDCAサイクルを短期間で回せるでしょう。
属人的な判断に頼るのではなく、客観的なデータに基づく現場運営を可能にして継続的な改善文化の醸成にもつながります。見える化をベースとした運用は、物流現場の柔軟性と対応力を高めるカギとなります。
サプライチェーン全体での最適化を図るには個々の企業や部門だけでなく、関係者全体が情報をリアルタイムに共有し、連携の強化が不可欠です。物流DXはクラウドベースのプラットフォームを通じて荷主や配送業者、倉庫、卸先などあらゆる関係者が同じ情報を見ながら業務を進められる体制を実現します。
これによって発注のタイミングや在庫状況、配送予定の変更などを即時に共有でき、ムダな待機や過剰在庫の発生を抑制できるでしょう。またトレーサビリティの向上により、品質管理やトラブル対応のスピードも改善されます。
分断されていた業務情報が統合されることで、全体最適の観点から効率的な運用が可能です。物流DXは単なる社内改善にとどまらず、サプライチェーン全体のパフォーマンス向上を支える基盤となります。

物流DXの推進は効率化や品質向上につながる一方、見落とされやすい課題も存在します。技術やツール導入に注力するあまり、現場の実態と乖離した施策が進んでしまうケースも少なくありません。注意点を事前に把握しておくことで現場とのズレや運用の非効率を防ぎ、継続的で実効性のあるDX推進につなげられます。
ここで解説するのは物流DXを推進するにあたって見落としがちな、6つの注意点です。
DX推進の目的が経営目標や上層部の要請に偏っていると、現場の具体的な課題を解決できないまま進んでしまうリスクがあります。現場から導入されたツールが使えない、複雑で手間が増えたといった声が上がることも珍しくなく、結果的に定着せず中途半端に終わるケースが後を絶ちません。
推進前には目的と現場課題の両方を明確化し、関係者全員での共有が重要です。必要に応じて現場担当者へのヒアリングや実地調査を取り入れ、その上で優先すべき機能やフローを設計します。目的と運用をつなげる設計がなされれば現場も自然に使いこなしやすくなり、DX推進が組織全体へと浸透しやすくなるでしょう。
物流DX推進では技術・ツールを導入すれば成功、という誤解が生まれやすいです。しかし技術は手段であり、成果はその後の運用や改善プロセスにかかっています。多機能なシステムでも実際の業務にフィットしなければ、活用されずに埋もれてしまう恐れがあります。
これを避けるには導入から運用、改善へと続く体制の整備が必要です。運用チームを組織内に設け、改善サイクル(PDCA)を回しながら使いやすさや効果を継続的に向上させていくことが重要です。ツール導入がDXのスタート地点であり、運用が続いて初めてDXが進んだといえるフェーズに至ります。
DX推進の過程ではシステム開発や連携、カスタマイズなどIT専門知識が必要です。自社にそうした人材が不足していると、外部ベンダー任せになりやすくなることでしょう。しかしこの状態に陥るとブラックボックス化し、トラブル発生時の対応遅れや柔軟な改修ができず運用定着に時間を要する、などのリスクがあります。
この課題に対応するには、自社でITのハブとなる人材の育成が重要です。ベンダー任せではなく、内部に運用管理者や改善担当者を育てながら支援を受ける形式が理想です。長期的には社内で部分的な内製対応ができる体制を整えることが、持続可能なDX推進とコスト抑制にもつながります。
既に使用している基幹システムや倉庫管理システムが後から導入するDXツールと連携できない場合、情報の属人化や二重入力の増加が起こり得ます。これによって業務が非効率になり、現場の負担がかえって増すケースも考えられるでしょう。
この問題を防ぐには導入前に既存システムとのAPI連携、及びデータ仕様の整合性確認が不可欠です。IT部門だけでなく実務担当者も巻き込み、何をどのデータで連携するかを明示的に設計します。全システム間のデータフローを一本化できれば、情報の一貫性が保たれてDXの統合的な運用が可能です。
物流は荷主や協力会社、運送業者など多数の企業が連携して成り立っています。そのため自社だけでDXを推進しても、協力先が同様の基準やツールを使っていない場合は連携が断絶してしまい、効果が出にくくなります。
この課題に対しては荷主やパートナー企業ともDXへの取り組みを共有し、必要に応じて既存プラットフォームの共通化や共通仕様の策定が重要です。共有ワークショップや研修会を開催すると、意識合わせとスムーズな移行が可能です。協力範囲を広げるほど効果は高まり、物流網全体での効率化と透明性の向上が期待できるでしょう。
DXプロジェクトでは初期投資や運用コストに比して効果が見えにくく、ROIが不明瞭になるケースが多々あります。コストは先に発生しますが、業務効率化や品質向上のメリットは徐々に積み重なるため短期的には成果が不透明になりがちです。
この状況に対応するには推進前にKPIを明確に設定し、中期・長期で効果を測定する仕組みを作ることが重要です。推進効果を定量的にレビューし、改善プランに反映させることで経営層や現場双方の理解を得やすくなります。ROIが目に見えるようになると、プロジェクトの継続に対する社内合意が得られやすくなり、DXへの投資が持続可能なものになります。
物流DXを推進する上で多くの企業が直面するのは現場との乖離、推進効果が見えにくいなどの課題です。こうした問題を放置すればせっかく推進したDX施策が根付かず、成果も出にくくなります。
そこで重要になるのが、注意点を解消するための具体的なアプローチです。目的や効果の見える化、システム連携、現場教育といった視点から6つの方法を紹介します。
物流DXを成功させるためには推進の目的を曖昧にせず、可視化が第一歩です。何のためにDXを推進するのか、どの課題をどの範囲で改善するのかを明確にしておかなければ途中で方向性を見失いやすくなります。
現場や経営層の間で認識のズレが生じるとプロジェクトの意思決定が遅れ、定着もしにくくなります。こうした事態を避けるためには課題を洗い出した上で判明した課題に対し、どの機能・プロセスを変えるのかその因果関係を図式化し、全関係者への共有が必要です。
目的の可視化で推進プロジェクトの指針を定め、進捗判断や優先順位の調整が可能です。
DXのツールやシステムを導入する際、どのような業務課題をどの機能で解決したいのかを可視化しないまま進めると、現場では使いこなせず運用が停滞するかもしれません。機能の多さに目を奪われ、本来の目的と合わない導入になってしまうケースも散見されます。
この課題に対処するには導入段階で誰がどのタイミングで、どの機能をどう使うかといったユースケースを整理し、目的と直結する機能から優先して展開する設計が必要です。
導入の目的を具体的に設定しておくことで不要なカスタマイズや過剰投資も防げ、システム活用の実効性が高まります。
新しいツールやプロセスを導入しても社内にその使い方や意義が浸透していなければ、定着は難しくなります。とくに物流業界では紙やアナログ作業に慣れた現場が多く、突然のデジタル化には抵抗感が生じやすい環境といえるでしょう。
そのためDXの推進と並行し、操作方法や目的を理解させる教育・研修の計画的な実施が求められます。座学だけではなく実務に応じたOJTやフィードバックの場を用意し、継続的な学習機会を提供しましょう。
現場がツールを活用できるようになれば定着率も高まり、プロジェクトがスムーズに進行します。教育はコストではなく、成功のための投資と捉えることが重要です。
DXを推進する際には新たに導入するシステムが、既存の基幹システムや業務ツールと連携できるかをあらかじめ確認しておく必要があります。連携できなければ手動での二重入力や業務フローの断絶が発生し、かえって業務効率を低下させる原因になります。
導入前にAPI仕様の確認やベンダー間の調整を行い、システム間のデータ互換性の明確化が重要です。また連携が難しい場合には、段階的に置き換えを検討する柔軟な設計も視野に入れるべきでしょう。
情報がスムーズに流れる環境を整えることでデータ活用や分析の精度が高まり、より効果的な意思決定につながります。
物流DXの効果は短期的に見えにくく、関係者の納得感が得られにくいかもしれません。そのためどのような成果が期待され、どのようなKPIに変化が現れるのかを事前に可視化しておくことが大切です。
例えば作業時間の短縮や入力ミスの削減、在庫回転率の改善など具体的な数値を基にメリットを共有すれば、現場や経営層も推進の意義を理解しやすくなります。効果の見える化は、プロジェクトのモチベーション維持にも直結します。
また定期的な進捗確認の場を設けることで、推進後の運用状況を把握し、必要に応じて改善施策を講じられるでしょう。
DX施策が機能しているかどうかを判断するためには、効果検証のタイミングと指標を明確にしておく必要があります。推進直後の一時的な成果ではなく、中長期的にどう推移していくかを観察できる設計が不可欠です。
例えば業務の理解に時間がかかるため初期段階ほど効果が低く出る、などの前提条件を把握した上でKPIやKGIを設計すれば、評価の精度が高まります。また検証データは定期的に収集し、改善アクションの根拠として活用することが重要です。
このように測定可能な成果を継続的に把握できるようにすれば、DX施策の成功率を高めるとともに、次の意思決定にも役立てられるでしょう。
物流DXを推進するには単にシステムを導入するだけでなく、目的に応じて最適なツールを選定する必要があります。業務の可視化やデータ連携、現場との一体化を実現するには専門性の高いツールやプラットフォームの活用が効果的です。
ここでは倉庫管理・輸配送管理・動態管理の3つの視点から、DX推進を支援する実績のあるサービスを紹介します。これらのツールは日々変化する物流業界の課題に対応し、継続的な業務改善を支えるための基盤です。
株式会社ロジザードが提供するLogizard ZEROはクラウド型の倉庫管理システムとして、多様な業種で導入が進んでいます。入出庫や在庫のリアルタイム管理をはじめ、バーコードを活用した誤出荷防止機能など現場業務の効率化を支援します。
また既存の受注・出荷管理システムとの連携が可能で、ECや実店舗との在庫共有にも対応できます。データはクラウド上で一元管理されるため、複数倉庫を横断した在庫の最適配置や業務の標準化が実現するでしょう。
導入後は運用支援やサポート体制も充実しており、システム定着をスムーズに進められる点が特徴です。倉庫業務の見える化を進めたい企業にとって、選択肢の1つとなるでしょう。
出典参照:ロジザードZERO|株式会社ロジザード
株式会社Hacobuが提供するMOVOは輸配送に特化したクラウド型の管理システムで、トラックバース予約・動態管理・配送進捗などを一元化できます。荷待ち時間の削減やバース混雑の緩和を通じ、ドライバーの拘束時間削減にもつながります。
MOVO Berthでは各拠点の予約状況をオンラインで管理できるため、関係者間の調整業務がスムーズです。さらに車両の位置情報を把握できるMOVO Fleetと連携すれば、遅延やトラブルにも即時対応が可能です。
このようにMOVOは物流現場のオペレーションを支える基盤として、コスト削減や業務効率化に貢献します。DXの成果を最大化するには、輸配送領域のデジタル化も欠かせません。
出典参照:Hacobu|株式会社Hacobu
ライナロジクスのLoogiaは最適配車・配送ルートの自動計算に特化した、動態管理ソリューションです。AIによるルート最適化機能により、配車担当者の経験に依存せず合理的な配送スケジュールを立案できます。
またリアルタイムで車両の位置情報や稼働状況を把握できるため、進捗確認や遅延対応も容易です。過去の走行実績データを蓄積・分析し、継続的なルート改善や積載率向上にもつながります。
導入後の業務負荷軽減だけでなく、燃料消費やCO₂排出量の削減にも貢献できる点が評価されています。Loogiaは脱炭素化と業務効率の両立を目指す企業にとって、実用性の高い支援ツールです。
出典参照:Loogia|株式会社ライナロジクス
物流DXを推進する際には、他社の取り組みや実例から学ぶことが有効です。先進的な企業ではAIやビッグデータの活用をはじめ、サステナブル経営との連携や中長期的な戦略にDXを組み込んだ施策が進められています。
ここでは実際に成果を上げている代表的な企業の事例を取り上げ、どのようにして物流DXを現場に根付かせたのか、それにより何が改善されたのかを解説します。自社に取り入れられるヒントを得るためにも参考になる内容です。
ヤマト運輸株式会社は配送ネットワークの最適化を目的として、AIやビッグデータを活用した物流DXを推進しています。注目すべき取り組みのひとつがデジタル・デリバリー・プラットフォーム(DDP)の導入です。
このプラットフォームでは荷物量や配送エリア、ドライバーの稼働状況などのデータをリアルタイムで収集・解析し、最適な配送ルートを自動で提案します。これによって実現されているのがドライバーの負荷軽減、及び燃料使用量の削減です。
さらに再配達率の低下や顧客満足度の向上にもつながり、現場の業務効率と品質の両面で成果が上がっています。テクノロジーを積極的に取り入れる姿勢が、DX成功の要因です。
出典参照:ビッグデータ・AIを活用した配送業務量予測および適正配車のシステム導入について | ヤマト運輸株式会社
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社は環境配慮型物流を目指したサステナブル経営の一環として、DXを戦略的に位置づけています。温室効果ガスの排出量削減を含む複数のマテリアリティに基づき、さまざまな施策を展開中です。
具体的には倉庫・輸送業務における、IoTセンサーの導入やAIによる配送ルート最適化システムの開発を進めています。またグローバルに展開する物流ネットワーク全体を対象に、CO₂排出量の可視化とデータ統合も進められています。
こうした取り組みによって顧客企業のサステナビリティにも貢献できる体制を整えており、DXによって企業価値の向上と社会課題の解決を両立させる好例といえるでしょう。
出典参照:マテリアリティ事業のデジタル化とDXの推進 |NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
福山通運株式会社では第6次中期経営計画において、DXを経営戦略の柱として掲げています。物流業務の高度化を目指し、AI・IoT・自動化システムを段階的に導入しています。
特に注力しているのは、トラックの動態管理や配送ルートの最適化です。配車システムとGPS連携によるリアルタイムの進捗管理を通じ、作業の効率化とCO₂削減の両立を図っています。また物流センターでは自動仕分け装置、無人搬送車などの導入が進行中です。
現場に密着した形でのデジタル導入を重視しており、社員への研修やITリテラシー向上のための施策も併せて実施しています。経営と現場が連動してDXを推進している点が、持続可能な変革の原動力となっています。
出典参照:DXの取り組み | 福山通運株式会社

物流DXを成功させるには単なるシステム導入にとどまらず、目的や効果を明確にして現場との連携を図りながら推進する視点が欠かせません。また既存の業務やインフラとの整合性、教育体制の構築など初期段階での準備も成果を左右します。
先進的な企業事例から学べるように、DXの推進は持続的な改善を前提とした戦略的な取り組みが求められます。注意点をしっかりと押さえ、社内外の環境変化に柔軟に対応できる体制を整えることで、物流の未来に向けた確実な一歩を踏み出せるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
