物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

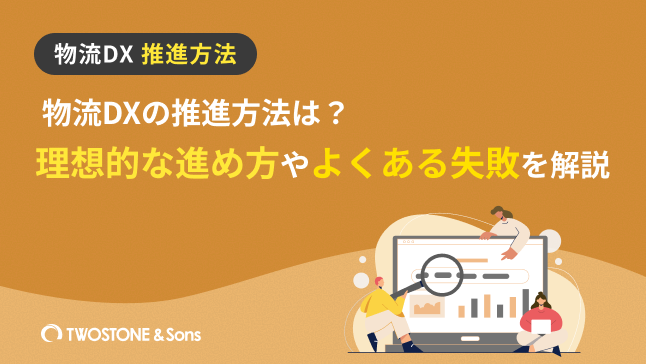
人手不足やコスト増加、顧客からの配送品質への要求など物流業界は今、転機を迎えています。手間がかかる、時間が足りない、効率が悪いなどのさまざまな悩みを抱えている現場は少なくありません。そんな中、物流DXの推進が注目されています。AIやIoTを駆使した業務の自動化・可視化により、省力化や品質向上を同時に実現できます。
本記事では物流DXの概念やその必要性、そして具体的にどう進めればよいのかを整理しました。理想的な推進プロセスと、よくある失敗の回避方法を知ることで自社での推進がスムーズに進むようになります。読み終える頃には現場の悩みに対応しつつ、組織を前向きな変革へ導くヒントがつかめるはずです。ぜひ最後までお読みください。

物流DXとはAIやIoT、ロボット、自動化システムといった先端技術を活用し、物流業務全体をデジタルで最適化・可視化する取り組みを指します。従来の人や紙に頼った運用から脱却し、リアルタイムな情報収集や分析に基づいた判断が可能です。
推進の目的は省力化のほかに配送品質の向上やコスト削減、環境負荷軽減など多岐にわたります。具体的には倉庫の在庫管理にIoTセンサーを使ってリアルタイム把握し、誤出荷や在庫滞留を防ぐ仕組みやAIによる最適ルートの提案、ロボットによる仕分け業務の自動化などが挙げられます。
物流DXは単なるシステム化でなく業務プロセスそのものを可視化・改善し、PDCAサイクルを回しながら進化させる活動です。そのため推進時にはツール選定だけでなく、業務設計・人材育成・運用改善をセットで考える必要があります。
物流DXが求められる背景には業界が長年抱えてきた構造的な課題に加え、外部環境の変化が加速している現状があります。このような従来型の業務体制では対応しきれない場面が増えている要因として考えられるのは、以下の5つです。
こうした中で物流DXは業界の持続的な成長と企業競争力を維持するため、不可欠な取り組みとなりつつあります。
物流業界は慢性的な人材不足が続いており、倉庫作業からドライバーまで採用も定着も容易ではありません。また労働時間制限や社会的要請の影響もあり、少人数で業務を回す体制への移行は急務です。
この課題を解決する手段として、物流DXは有効です。AIを用いた配車システムによってドライバーの負荷を均等化し、ルート提案システムで時間効率も向上します。倉庫ではロボットによる仕分けや自動搬送機による移動、AIによる在庫管理が人の代替・補完になります。
結果として人手に依存しない安定した運用により、現場の負担軽減が可能です。このため不足人材の中でも安心して働ける環境が整い、人手不足の根幹的な改善ができるでしょう。
2024年問題ではドライバーの長時間労働が規制され、時間外労働の上限が設定されます。これまでのやり方では緊急対応や配送の遅延が頻発し、違法な労働を招く恐れがあります。
物流DXが提供するのはこの課題に対応する、有力なソリューションです。IoTセンサーやクラウド管理で稼働時間をリアルタイム把握し、AIによる時間管理とシフト設計によって法令順守を行えます。さらに配車システムは運転時間・休憩時間のバランスを最適化します。
これにより、法規制をクリアしながら効率的な運行が可能です。結果として労働環境を改善しつつ、業務運営を安定化できるでしょう。
現代の物流において、顧客が求めるサービスの質は以前にも増して高くなっています。即日配送や時間指定、細かな追跡情報の提供など従来の人手による対応だけでは限界があります。特にBtoCのラストワンマイル配送では少量多頻度で多様な対応が求められ、柔軟なオペレーションが必要です。物流DXはこうした多様なニーズに対応するための基盤です。
例えば配送ルートをリアルタイムで最適化するAI配車システムや出荷と在庫管理を連携させるWMS(倉庫管理システム)、顧客向けのトラッキングサービスなどが挙げられます。これらの統合的な運用により、人的負担を減らしながら高品質なサービス提供が実現できるでしょう。
顧客の期待値が上がり続ける中、物流DXはサービス品質の維持・向上に欠かせない手段であり、企業価値を左右する要因にもなり得ます。
物流は単体で完結せず、調達から生産、保管、販売、アフターサービスまで一連のサプライチェーンと連動しています。どこか1つの工程で滞留や情報の断絶が発生すれば全体最適が損なわれ、結果起こり得るリスクが納期遅延やコスト増加、在庫過多などです。
そのためサプライチェーン全体を俯瞰し、リアルタイムで情報を共有・活用する仕組みの整備が求められます。物流DXではIoTやクラウド、APIによるシステム連携を通じてサプライチェーンの可視化と一元管理を実現できます。例えば調達データと出荷予定を自動連携し、在庫の過不足を防止するなどがその一例です。
また複数拠点や外部パートナーとの連携も、DXを通じてスムーズに行えるようになります。こうした全体の流れの最適化により、より持続可能で柔軟な事業運営ができるでしょう。
物流は単なるコストセンターではなく、企業の競争力を支える重要なファクターです。迅速で正確な配送や柔軟なオペレーション体制、顧客満足度の高い対応は取引先やエンドユーザーの信頼を獲得し、リピート率や新規取引獲得にも影響します。
しかし競合他社も同様にテクノロジーを導入し始めており、差別化の余地は縮小しつつあります。ここで物流DXの戦略的な推進により、他社よりも優位に立つチャンスを得られることでしょう。例えばデータ分析に基づいた業務改善、AIによる需要予測を活用した先回りの在庫調整などが有効です。
さらに環境配慮や脱炭素化の取り組みも企業価値の評価軸になりつつあり、DXを通じた持続可能な物流体制の構築が求められています。結果として競争環境が厳しくなる中でも、安定した成長とブランド力の強化につながります。
物流DXを推進するには単なるデジタルツールの導入だけでなく、業務全体の再設計と関係者の意識変革が欠かせません。現状を正確に把握した上で課題を明確にし、経営層と現場が同じ方向を見て戦略を立てることが重要です。
さらに段階的な推進と改善を繰り返しながら、データ基盤の整備や人材育成にも注力する必要があります。これらの取り組みを統合的に進めることでDXは実効性を伴い、企業価値の向上と競争力の強化につながります。
物流DXを成功に導く第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。倉庫業務や配送、在庫管理など各プロセスを洗い出し、どこに非効率やロスがあるかを明確にする必要があります。
可視化にあたってはKPIの設定や業務フロー図の作成、業務時間のログ収集などを通じて数値とプロセスの両面からアプローチします。これによって改善すべき優先順位が明確になり、投資対効果の見込みやリスクの洗い出しができるでしょう。
また現場の意見を取り入れることで机上の空論に陥らず、現実的な施策につながりやすくなります。DXは課題の把握から始まり、そこから最適な技術選定や導入計画へとつなげることが成功のカギです。
物流DXは企業全体に関わる変革であり、経営層と現場が一体となって取り組む体制づくりが求められます。まず経営側がDXの意義や目的を明確にし、中長期的なビジョンを策定する必要があります。その上で現場に対して具体的な目標や取り組み内容を丁寧に伝え、納得感のある共通認識の形成が大切です。
トップダウンとボトムアップの両輪で進めることで、現場のモチベーションを維持しやすくなり実行力も高まります。また定期的な進捗確認やフィードバックの仕組みを整えることで、方向性のブレを防ぎつつ柔軟な軌道修正にもつながるでしょう。
DXは技術だけでなく組織文化や意識の転換を含む全社的な挑戦であり、その実現には全員が同じ目標を共有して進むことが不可欠です。
物流DXは一度にすべてを変えるのではなく、スモールスタートから始めて段階的に拡張していくアプローチが有効です。初期段階では影響の少ない部門や拠点で限定的に推進を行い、実際の効果を検証します。
このフェーズでは仮説と実績のギャップを把握し、問題点を洗い出しながら柔軟に改善していくことが重要です。失敗や想定外の事象も早期に把握できるため、全社展開時のリスク低減にもつながります。
また現場の声を反映させながら進めることで推進に対する抵抗感が減り、自然と運用に馴染んでいく効果も期待できます。スモールスタートは時間をかけた慎重な取り組みですが、成功事例を積み重ねることで社内の信頼も高まり、全体へのスムーズな拡大につながるでしょう。
物流DXを継続的に機能させるには、各システムやデータの連携が不可欠です。倉庫管理システム(WMS)や配送管理システム(TMS)、受発注システムなどが独立していては情報の分断が生じ、効率的な意思決定が難しくなります。
そのため共通のデータ基盤を整備し、リアルタイムで情報を共有できる環境の構築が求められます。API連携やクラウドベースの統合プラットフォームの活用によってデータの二重入力や伝達ミスを防ぎ、業務効率を高められるでしょう。
さらにデータの横断的な活用により、異なる部門間の連携やサプライチェーン全体の最適化にもつながります。技術的な整備だけでなく運用ルールやセキュリティ対策を含めた設計が重要であり、導入前のしっかりとした準備が成功への基盤となります。
物流DXの実現には単にシステムを導入するだけでなく、それを運用し改善し続けられる人材の育成が不可欠です。新たな技術に対応できるスキルを持つ人材を社内で育てるためにはOJTだけでなく、外部研修やeラーニングなどの仕組みを活用して段階的に知識と実践力を高めていくことが重要です。
同時にDXに対するポジティブな企業文化を醸成し、失敗を恐れず挑戦できる風土づくりにも取り組む必要があります。従来の業務手法から脱却するには、現場の理解と主体的な参加が欠かせません。
そのためには経営層のメッセージ発信や評価制度の見直しを通じ、変化を歓迎する空気をつくることが効果的です。人と組織の成熟はDXの成果を持続可能なものとし、将来の成長基盤を支える原動力となります。

物流DXを推進する企業が増える一方、実際の現場では成果が上がらないケースも少なくありません。その原因は技術導入の方法や組織体制、意識のずれに起因する失敗にあります。特に現場との連携不足や目的の不明確さ、属人化の放置といった問題がDXの効果を半減させる要因となります。
ここで解説するのは、DX推進の際に多くの企業が陥りやすい代表的な失敗、及びその背景にある課題です。
物流DXの経営主導での推進は必要ですが、現場の実情を無視した一方的なトップダウン型の推進は現場の反発、形骸化などを招くリスクがあります。実際の業務を担っているのは現場であり、そこで発生する課題やボトルネックを正確に理解しないままシステムを導入すると、業務とシステムの間にミスマッチが生じます。
導入されたツールが現場にとって使いにくい、既存フローとの整合性が取れないといったケースにおいて現場は従来の方法を継続する傾向が強く、DXが定着しません。また現場が主体的に関与しない場合、改善提案や運用上の工夫も生まれにくくなります。
こうした問題を回避するには初期段階から現場の担当者を巻き込み、ニーズのヒアリングや実務フローの洗い出しを行う必要があります。現場の理解と協力を得ることで、実効性のあるDX推進が実現できるでしょう。
物流DXではツールやシステムの導入が話題になりやすく、それ自体が目的化してしまうケースが見られます。しかし本来のDXの目的は業務の効率化や生産性の向上であり、ツールはその手段に過ぎません。ツールを導入しただけで終わってしまい、業務の見直しやKPIの設定が不十分だと、期待する成果を得ることは困難です。
ツールの導入によって得られるデータも、活用されなければ意味を持ちません。例えば業務改善のための数値が蓄積されていても、それを分析・活用する体制が整っていなければ単なる情報の蓄積にとどまります。
このような状況を防ぐためにはツール導入の前に目的と目標を明確に設定し、その後の運用計画や効果測定まで見据えた体制を整えることが重要です。導入はスタートであり、定着と活用こそがDXの本質といえます。
物流業務における属人化やブラックボックス化は、DX推進において障害となる典型的な課題です。属人化とは特定の担当者にしかわからない業務や操作が存在する状態を指し、業務の透明性を損ないます。DXの推進によって標準化を図ろうとしても、そもそもの業務内容が明文化されていなければ適切なシステム設計ができません。
ブラックボックス化した業務はエラーや非効率の温床となり、トラブルが発生した際にも原因特定や対処が遅れるかもしれません。また担当者が異動や退職した際にノウハウが引き継がれず、業務の継続性が脅かされる危険性も高まります。
この問題に対処するために必要なことはまず、業務フローの棚卸しです。誰がどのような業務を担当しているかを可視化する必要があります。その上で業務マニュアルや操作手順書を整備し、ナレッジ共有体制の構築によって属人性を解消していきましょう。
物流DXを全社で一気に推進するアプローチは一見効率的に見えるものの、実際にはリスクが大きく、失敗に終わるケースが少なくありません。DXの取り組みは新たな業務設計や運用体制の変更を伴うため、現場ごとの習熟度や対応力に差がある中で全社一律の推進をしてしまうと、混乱を招く可能性があります。
またシステムトラブルや想定外の運用課題が発生した際に全拠点が同時に影響を受けることになり、業務全体の停滞を引き起こす危険性があります。推進効果の検証も行いにくく、改善点が見えないままシステムを使い続ける状況に陥る可能性も無視できません。
こうしたリスクを回避するにはまず一部拠点や業務領域に限定して推進を試行し、成果と課題を分析した上で段階的に範囲を広げていく、スモールスタート型の推進が有効です。改善点を反映しながら段階的に進めることで、DXの定着率を高められます。
物流DXの開始時やその後の見直しの際には単にツールを導入するだけでなく、現場の課題と目的を明確にし、組織の巻き込みや運用設計まで見据えた体制づくりが重要です。現場の声を起点に小さく試しながらKPIを定め、業務改革として進めていくことで現実的かつ持続可能なDXが実現できます。
ここでは物流DX推進の開始や見直しに際し、特に重要な6つの視点を詳しく解説します。
物流DXのスタート地点として重要なのは、現場が抱える具体的な課題の把握です。経営層や管理部門が描く理想像だけでなく倉庫作業員やドライバー、事務担当者など実務を担う現場が日々直面している、業務のムダや手間を掘り下げなければなりません。
現場での業務に直接関わる従業員からヒアリングやワークショップを通じて業務一覧や時間のかかっている作業を整理し、数値やフローに落とし込むと可視化しやすくなります。課題が明確になればそれに対応する技術やプロセス改善案をより精度高く検討できるようになり、導入したツールも実践で使いやすくなります。
現場を無視したDX推進は形骸化しやすく、定着に失敗するケースも珍しくありません。現場の声を起点に据える姿勢がDXを現場に根付かせ、継続的な改善につなげる第一歩です。
物流DXで失敗しないためには全社一斉推進ではなく、まずは小規模な範囲で試行するスモールスタートが有効です。拠点1つ、業務1つ、ツール1つにそれぞれ絞って推進し、効果と課題を検証することによって、わかりやすい成果と改善ポイントを獲得できるでしょう。
小さく始めることで予算や運用リスクを抑えつつ現場に変化の経験を積ませることが可能で、心理的な抵抗も低くなります。試行結果を基に課題の原因分析やモデルフローの設計ができれば、次の展開に必要な要素が明らかとなるため全社展開の成功率も高まります。
また小さな成功事例を積み上げることで組織内の理解が深まり、推進に対する後押しを強化できるでしょう。これによって次の段階への予算獲得や関係者の参画も得やすくなり、無理のないDX推進が可能になります。
DXは推進そのものではなく、何を達成したいのかを明確にする必要があります。目的が不明瞭なまま進めるとツール導入後の効果が見えず、組織内の意欲低下や運用停止のリスクにつながります。そこで必要なのが、数値で測れるKPIの設定です。
KPIは作業時間の短縮や人件費の削減、誤出荷率の低下など具体的な成果を可視化できる指標にします。さらに導入後の進捗を定量的に評価し、目標との乖離を分析して改善策を設計すればプロジェクトに対する説得力と現場の納得感が高まります。
またKPI達成状況を定期的に全体で共有し、成功事例を横展開できる体制を構築すれば現場のモチベーションを維持しつつ継続的な改善につなげやすくもなることでしょう。
物流DXはシステム導入に留まらず、業務プロセスそのものを変革する機会です。単にITツールを導入して業務を補完する形では現場で定着しにくく、無駄なカスタマイズや運用の複雑化を招く可能性があります。
このリスクを回避するためにはまず現行業務を可視化し、なぜそのプロセスがあるのかを理解した上でデジタル化に適した業務フローの再設計が重要です。不要な作業は削減し、必要なプロセスは自動化や標準化を検討します。
業務改革の視点でDXを捉えれば、システムに依存しない柔軟かつ効率的な運用設計ができます。これによって将来的な変更にも対応できる、拡張性と安定性を備えた業務体制を構築可能です。
物流DXは倉庫や配送、調達、営業、顧客対応など各部署が連携して初めて効果を発揮します。部門間で連携せずに個別に進めようとすると業務の断絶や情報の重複が生じ、全体最適が実現しにくくなります。
推進時には経営層や管理部門、現場を含むプロジェクトチームを構成し、目的とルールの共有が必要です。定期的なミーティングを実施し、現場視点での課題や進捗を取り上げることで潜在的な問題にも対処しやすくなります。
また部署の壁を超えた成功体験の共有によって横展開の抵抗を減らし、組織全体としてのDXへの理解と協力を促進できます。連携体制の強化は、現場に根ざした改革の推進力となるでしょう。
物流DXのカギは現場が実際に使い続けられるかにかかっています。そのためツール選定の際には使いやすさや画面構成、操作のしやすさ、現場のITリテラシーに合致しているかを優先しましょう。
導入前には現場による実地検証を実施し、フィードバックを受けながら使い勝手を確認します。UIや操作ステップが煩雑であれば現場は敬遠し、運用が停滞しかねません。
導入後にトレーニングやサポートがあるツールを選ぶと、定着への安心感が高まるでしょう。サポート体制や形式も確認し、トラブルや変更への対応力を把握しておくことが重要です。使いやすさを重視した選定は高い定着率と継続利用につながり、DXの成果を確かなものにします。
物流DXは各企業の規模や業務内容によって最適な推進方法が異なります。しかし多くの先進企業は、段階的な取り組みや現場の巻き込み、デジタル基盤の整備によって効果的な物流DXの推進を進行中です。
ここでは、日本を代表する大手物流企業の事例を通じてどのようにDXを推進し、業務効率化やサービス向上を実現しているのかを紹介します。自社に合った推進方法を考えるヒントになるでしょう。
日本通運株式会社は先進的な物流施設を活用し、持続可能なサプライチェーンの実現に取り組んでいます。物流DX推進の柱として、IoTやAIを活用した自動仕分けシステムや倉庫管理の効率化を進めています。これによる狙いは、入出庫作業の誤出荷防止や時間短縮への期待、及び作業の精度の向上です。
さらに省エネ設備の導入と再生可能エネルギーの活用を組み合わせ、環境負荷低減にも注力しています。こうした施設のデジタル化はサプライチェーン全体の見える化にも寄与し、取引先との連携強化と柔軟な対応力を高めています。段階的に最新技術を導入し、現場の意見を反映する推進方法が成功のポイントです。
出典参照:デジタルプラットフォームで持続可能なサプライチェーンを構築する|日本通運株式会社
ヤマトホールディングス株式会社は物流DX推進の中核として「Yamato Digital Platform(YDP)」を構築しました。このプラットフォームは顧客の注文情報や配送状況をリアルタイムに一元管理し、最適な配送ルートや車両配備を実現しています。こうした情報共有はサービス品質の向上だけでなく、業務効率の改善にもつながっています。
またYDPは拡張性を持ち、他のITシステムやパートナー企業のサービスと連携可能です。これによってサプライチェーン全体でのデジタル連携を促進し、多様化する顧客ニーズに対応しています。導入時には現場の研修や運用ルールの策定を重視し、段階的な展開を進めていることも成功要因です。
出典参照:「Oneヤマト2023」の改革を支えるデジタル戦略の推進|ヤマトホールディングス株式会社
佐川急便株式会社はグーグル・クラウド・ジャパン合同会社と連携し、クラウド技術を活用した物流DXを推進しています。AIによる需要予測や配送ルートの自動最適化が進み、従来の運用を改善しながら効率化を図っています。これにより、配送時間の短縮や燃料の消費削減に成功しました。
さらにクラウド基盤を活用し、全国の配送データや車両情報をリアルタイムに集約・分析して運用の高度化を実現しています。システムのスケーラビリティを確保しつつ、現場の運用に応じたカスタマイズを行うことで実際の業務に適応したDX推進が可能になりました。こうした取り組みは、変化に強い物流体制の構築に寄与しています。
出典参照:【佐川急便】デジタルトランスフォーメーション(DX)の活用による総合物流機能の強化に向けた戦略的パートナーシップ協定を締結|佐川急便株式会社
福山通運株式会社は第6次中期経営計画において、DXの推進を経営戦略の柱に据えています。業務の効率化だけでなく顧客サービスの質向上や新規事業創出を目指し、戦略的なIT投資を実行中です。社内にDX推進組織を設置し、部門横断でプロジェクトを管理していることが特徴です。
具体的には物流業務の自動化やデータ活用による需要予測の精度向上を図り、業務効率化に結びつけています。さらに社員のスキルアップにも注力し、新しい技術の活用が円滑に行われる環境づくりを推進中です。計画的で現場密着のアプローチが、持続可能なDXの実現につながっています。
出典参照:DXの取り組み | 福山通運株式会社
日本郵政株式会社はデジタル技術の活用で業務効率化を図りつつ、人にしかできないサービス品質の向上を目指したDXを推進中です。物流分野では自動仕分けや配送計画の最適化に加え、顧客対応のデジタル化にも取り組んでいます。
AIを活用したチャットボットや問い合わせ対応システムで迅速な顧客サービスを実現し、郵便局や配達員の負担軽減も図っています。加えて全社的なデジタル人材育成を推進し、DX推進のための体制強化に努めています。これにより、顧客満足度向上と業務の持続的改善を両立しました。
出典参照:みらいの郵便局、始動! Vol.1 体温を感じる郵便局へ! 「デジタル郵便局」で描く未来|日本郵政株式会社

物流DXはただツールを導入するだけでなく、自社の課題や業務特性に合わせた推進方法を選ぶことが重要です。各企業の事例から学べるように段階的に進めることや現場の意見を反映する体制づくり、そしてデジタル基盤の整備が成功につながります。
また業務効率化だけでなくサービス品質の向上や環境配慮も視野に入れ、持続可能な物流体制を目指しましょう。これらの視点を踏まえ、本記事を参考に自社に適した物流DX推進方法を検討すれば、今後の競争力強化につなげられます。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
