物流DXで課題解決へ|2024年問題と人手不足に立ち向かうための実践ガイド
物流

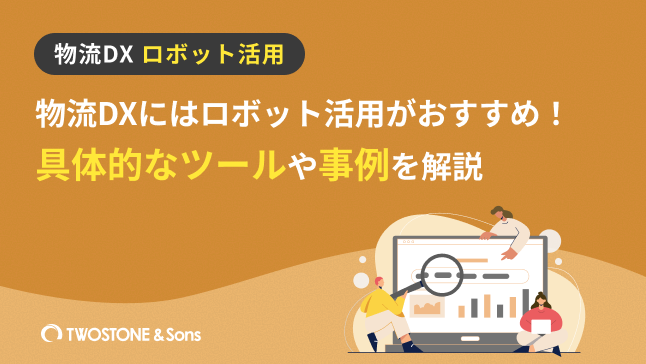
人手不足・コスト高・納期遅延といった物流現場の課題が深刻化している今、解決への道筋として物流DXにおけるロボット活用が注目されています。単なる自動化ではなく、人と協調しながら省人化・効率化・安全性向上につながる技術が急速に進歩しました。
本記事では、物流DXにロボットを活用する6つのメリットやロボット技術の例を具体的にわかりやすく解説しているのでご参考ください。現場での課題に対して具体的にどのような効果が見込まれるのか、事例を交えて紹介します。
この内容を読むと最新テクノロジーに支えられた物流体制の将来像がイメージでき、自社に適した導入方法や判断基準がわかります。変革の第一歩を踏み出すヒントを見つけてください。

物流DXを実現する上で、ロボット技術は中心的な役割を果たします。ロボットは搬送・仕分け・ピッキングといった現場業務を担うだけでなく、センサーやAIとの連携により作業効率の向上と安全性の確保にも貢献するようになりました。
また、人的リソースの最適化やコストの長期的削減にもつながるため、今やロボット導入は単なる自動化の枠を超えた、経営戦略の一部として位置づけられています。
ここでは、物流DXにおけるロボット活用の代表的な6つのメリットについて、具体例を交えながら詳しく紹介していきます。
物流業界では慢性的な人手不足が続いており、特に繁忙期や深夜帯の労働力確保は大きな課題となっています。この問題に対して、ロボットの導入は効果的です。
自律走行型の搬送ロボット(AMR)は、棚から商品を集めて決められた場所まで搬送する作業を正確かつ迅速にこなすのがポイントです。これにより従業員はより高度な業務に専念でき、限られた人員でより多くの処理を可能にする体制が構築されます。
また、昼夜問わず稼働できるロボットの存在は、人的リソースの平準化にも寄与します。導入初期は人員との併用が必要ですが、徐々にタスクを移行することで省人化と安定稼働を両立させられるでしょう。
ロボットを活用することで、人材不足に悩まされない持続可能な現場運営が実現できるようになります。
ロボットを活用することで、物流現場における作業効率は大きく向上します。搬送やピッキングなど繰り返しの多い業務はスピードと正確性の両立が求められますが、人手による作業ではミスやばらつきが避けられません。
一方で、自律型ロボットやピッキングアシストロボットはルートの最適化やタスクの割り当てを自動で処理でき、処理速度を安定して保ちます。作業時間の短縮だけでなく、再作業やエラー対応の減少にもつながります。
また、ロボットが蓄積する作業ログは、分析や改善の材料としても活用可能です。業務フローの可視化やボトルネックの特定が容易になるため、継続的な改善のサイクルを回しやすくなるのも利点です。
効率的な現場運用を実現する上で、ロボット技術の導入は有効な手段となります。
属人化の問題は、物流現場において深刻なリスクとなります。ベテラン作業者の技術やノウハウに頼りすぎる体制では、人員の入れ替えや欠員が業務の質を著しく左右します。ここで重要となるのが、作業の標準化です。
ロボットは与えられた指示やルールに従って一貫した動作を繰り返すため、作業品質にばらつきが出ません。誰が指示を出しても常に一定水準の結果が得られることで、安定した業務体制が実現します。
さらに、ロボット導入に伴い業務プロセスを見直す機会が増えることで、手順の統一や教育資料の整備も進みます。これにより現場におけるオペレーションが可視化され、属人化の解消につながるのがポイントです。
標準化された物流現場は新人教育の効率化や業務の引き継ぎもスムーズに行えるため、組織全体の生産性向上を後押しします。
物流現場では、フォークリフトや重量物の取り扱いなど作業中の事故リスクが常に存在します。特に長時間労働や疲労によって注意力が低下した際には、思わぬトラブルが発生しやすくなるので注意しましょう。
こうしたリスクに対し、ロボット導入は有効な安全対策となります。自律移動型ロボットには障害物検知センサーや停止機能が搭載されており、作業員との接触リスクを最小限に抑えられるのがポイントです。
また、荷物の積み下ろしや移動といった身体的負担の大きい作業をロボットが担うことで、従業員のけがや疲労による事故の発生も減少します。さらに、AIカメラによるエリア監視を組み合わせることで、不審な動きや危険を即座に検知する体制も整えられます。
現代の物流は注文内容や納期が日々変化し、柔軟な対応が求められる時代になっています。季節変動やキャンペーン時など、突発的な業務増加に対して迅速に適応できる体制が不可欠です。
ロボットは作業量・ルート・時間帯の変更に対して設定変更ひとつで対応できるため、柔軟な現場対応を実現します。特にAMR(自律移動型ロボット)は固定ルートに縛られず、リアルタイムの状況に応じて移動ルートを最適化できる点が強みです。
また、ロボットの稼働状況は常に可視化されており、追加導入や稼働シフトの調整も容易です。これにより、繁忙期には稼働を増やし閑散期には縮小するなど、ムダのないリソース運用が可能になります。
不確実性の高いビジネス環境下でも、安定した対応力を持てる体制が構築されます。
ロボット導入は、初期費用がかかる点でハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、中長期的に見れば運用コストの削減や人件費の抑制につながることが多く、経営的にも十分に投資効果が期待できます。
まず、同一の作業をミスなく何度も繰り返せるロボットは、再作業やロスの削減に貢献します。加えて、24時間稼働が可能なため夜間や休日の労働コストも抑制できるのがポイントです。
また、作業員の採用・育成・離職による入れ替えコストが削減される点も見逃せません。ロボットは故障がない限り安定稼働し、保守メンテナンスも計画的に管理可能です。
定量的な費用対効果が見えやすい分経営判断もしやすく、戦略的な設備投資として有効です。

物流DXを推進する上で、ロボット技術の導入は欠かせません。特に自律走行搬送や自動ピッキングなど、人手による作業の効率化と標準化を実現するロボットは注目を集めるようになりました。作業者の負担軽減・省人化・安全性向上にもつながるため、現場の課題を多面的に解決できます。
ここでは、実際に活用されているロボット技術の代表例を5つ紹介します。自社に合った技術選定の参考として役立ててください。
DeliRoは、ROBO-HI株式会社が開発した自律移動型配送ロボットです。主に屋外での配送用途に対応しており、人手を使わずに安全かつ確実に荷物を運ぶ機能を備えています。カメラやセンサーを搭載し、障害物を自動で回避しながらルートを進めます。
飲食店・マンション・企業内の敷地などでの配送ニーズに対応しており、すでに実証実験を終えた商業施設などでは、無人での弁当配送や宅配サービスへの活用が始まりました。人と接触することなく荷物を受け取れる点は衛生面でも安心材料となり、感染症対策としても注目されています。
屋外配送を自動化するというアプローチは、人手不足が深刻な宅配業界の支援としても有効です。DeliRoは、物流DXの中でも「ラストワンマイル」の課題解決に貢献する技術といえます。
出典参照:DeliRo(デリロ) | ROBO-HI株式会社
MujinRobot ピースピッカーは、株式会社Mujinが提供する自動ピッキングシステムです。このロボットは、AIが内蔵されたコントローラーによって物体の形状や位置を自動で認識し、最適な動作で商品をピックアップします。
従来、ピースピッキング作業は人の判断や技術に頼る場面が多く、熟練者でなければ難しいとされてきました。しかしこのロボットは、異なるサイズや形状の商品でも安定して対応できるように設計されており、導入企業では作業時間の短縮と省人化を同時に実現しています。
また、AIが作業ログを蓄積・分析することで、継続的な動作改善も可能です。ピッキング精度のばらつきをなくし、生産性の向上にもつながるこの技術は、倉庫の自動化における重要な一歩といえます。
出典参照:MujinRobot ピースピッカー | 株式会社Mujin
KEY CARTは豊田自動織機が開発したAGV(無人搬送車)で、倉庫内や工場内での自動搬送を担います。磁気テープやQRコードなどのインフラを必要とせず、自己位置推定機能を活用して柔軟に移動ルートを選択できます。
このツールの特長は、運搬対象の変化やレイアウト変更にも対応できる点です。これにより、搬送経路を再構築する時間やコストを抑えられます。また、クラウドベースのフリートマネジメントシステムと連携することで、最適な運行スケジュールを自動で構築可能です。
労働力の不足が顕著な分野において、KEY CARTは効率的な物流の実現に大きく貢献します。作業者の負担軽減に加え、事故防止や作業スピードの安定化にもつながる点が魅力です。
出典参照:KEY CART(キーカート)|株式会社豊田自動織機
オムロンのLD、MD、HDシリーズは自律移動型ロボット(AMR)で、製品の種類や搬送物の重量に応じたラインナップを揃えています。これらは、人の動きを検知して安全に走行しながら倉庫や工場内の資材や製品を効率的に搬送します。
センサーとカメラを駆使してリアルタイムで障害物を認識し、回避しながら目的地へと進むのが特徴です。従来のAGVと異なり固定ルートに依存しないため、設備の変更や急な障害物にも柔軟に対応できる点が大きな強みです。
また、Fleet Managerという集中管理ソフトを活用することで複数台を効率的に制御することが可能となり、倉庫全体の業務最適化が図れます。安全性と柔軟性を兼ね備えたこのシリーズは、物流DXを推進する上で信頼性の高いソリューションの1つです。
出典参照:LD / MD / HDシリーズ | オムロン株式会社
Neubieは、ROBO-HI株式会社が開発した屋内向けの自律搬送ロボットで、倉庫内や施設内における無人搬送を支援します。エレベーター連携や自動ドア開閉などの機能も搭載しており、複雑な建物構造にも対応できる点が特徴です。
このロボットは走行ルートの自由度が高く、建物内でのフロア移動をスムーズに行えるよう設計されています。台車を牽引するタイプで、多様な運搬ニーズにも柔軟に対応できる汎用性の高さがポイントです。
また、クラウド連携を通じて管理者がロボットの稼働状況やログをリアルタイムで把握できるため、トラブルへの迅速な対応や稼働率の最適化が図れます。Neubieは、建物内の多層構造を持つ現場でも省人化と効率化を実現できる優れたロボットです。
出典参照:Neubie(ニュービー)|ROBO-HI株式会社
ロボット技術の導入は、物流DXを推進する上で有効な手段ですが、導入すれば即成果が出るとは限りません。成功には、現場の状況や目的に応じた慎重な計画と準備が必要です。特に、自社の課題を正確に把握し、ROIを見据えた導入方針を立てることが欠かせません。さらに、人とロボットが共存できる設計や、段階的に運用を広げるスモールスタートの考え方も重要です。
ここでは、導入時に意識すべき4つの視点について解説します。
ロボット導入の第一歩は、現場が抱える課題を具体的に把握することです。曖昧なまま導入してしまうと、期待した効果を得られない可能性があるため注意しましょう。どの作業に人手が集中しているのか、どの工程がボトルネックになっているのかを定量的に洗い出すことが重要です。
例えば、ピッキング作業に時間がかかっているのか、荷物の仕分けにミスが多いのかによって選定すべきロボットの種類や仕様は大きく異なります。現場の作業フローを見直し、どの工程に技術導入の効果が出やすいかを明確にすることで導入後のギャップを防げます。
このように、技術選定の前に現状を可視化し、目的を共有した上で施策を検討するプロセスが、物流DXの推進において不可欠です。
ロボット導入には一定の初期投資が必要です。特に中小企業にとっては、コストの妥当性や投資回収期間が導入判断の大きな要素になります。ただ先進的な機器を選ぶのではなく、導入によってどれだけの作業工数や人件費を削減できるかを明確にすることが大切です。
具体的には、業務単位あたりのコスト削減効果や処理スピードの向上による生産性の変化を試算しておく必要があります。また、定期メンテナンスや運用にかかるランニングコストも事前に把握しておくことが重要です。
費用対効果を見極めた上で導入を進めれば経営層の理解も得やすく、長期的な運用体制を構築しやすくなります。ROIを軸にした導入判断が、DXの持続的な推進を可能にします。
物流現場においてロボットは人間の仕事を代替する存在ではなく、補完し合う存在として設計する必要があります。ロボットと人が同じ空間で業務を行う場合、双方が安全かつ効率的に動けるレイアウトやワークフローを構築しなければなりません。
例えば、AMR(自律走行搬送ロボット)と人間の通路が交差する場面では、動線の分離や作業エリアの明確化が求められます。また、ピッキング作業の一部をロボットが担い、最終的な検品を人が行うなど役割分担を設計段階から明確にしておくと連携がスムーズです。
協働の視点を持つことで、技術導入が単なる自動化ではなく現場全体の最適化につながります。ロボットと人が共に力を発揮できる環境を整えることが、物流DXの質を高める重要な要素です。
ロボット技術の導入にあたって、いきなり全社展開するのはリスクが大きいです。理想的なのは、1拠点や1工程など限定した範囲から始めて、運用状況を検証しながら段階的に展開を広げる「スモールスタート」の考え方です。
この手法であれば現場で起こる予期せぬトラブルにも柔軟に対応しやすく、無理のない移行が可能になります。また、現場からのフィードバックを基に運用マニュアルや作業フローをブラッシュアップすることで、次の導入先でもスムーズに運用できるでしょう。
さらに、初期導入時に蓄積されたデータはその後のROI算出やシステム拡張にも役立ちます。失敗を最小限に抑え、成功の確率を高めるためには段階的な導入戦略が不可欠です。
物流DXの実現においては、現場ごとの業務内容や課題に応じた技術の導入が不可欠です。中でもロボットの活用は、作業負担の軽減や業務の標準化に貢献する手段として注目されています。
すでに多くの先進企業が自動搬送やピッキング、荷積みといった反復作業にロボットを導入し、労働力不足への対応と作業効率の向上を両立させました。ここでは、ロボット技術を活用して具体的な成果を上げている企業の事例を3つ取り上げて紹介します。
ヤマト運輸株式会社では、無人自動配送ロボットと宅配便ロッカーを組み合わせた新しい物流サービスを試験導入しています。自律走行可能な配送ロボットがマンションの共用部まで荷物を運び、利用者はロッカーから荷物を受け取る方式です。
この取り組みによって従来必要だった玄関先での対面配達を省略でき、再配達の削減にも寄与します。また、共働き家庭や不在がちな利用者にとっても受け取りやすい仕組みとなっており、顧客満足度の向上にもつながっています。
ロボットを活用することで人手不足の配送現場における業務効率化を進めつつ、環境配慮型の次世代物流モデルを構築する一例です。
出典参照:車道を走行する無人自動配送ロボットにオープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」を搭載した移動型宅配サービスの実証実験を北海道石狩市で開始 | ヤマト運輸株式会社
佐川急便株式会社では、AI技術を搭載した荷積みロボットを物流センターに導入しています。このロボットは積載物のサイズ・重量・最適な積載順序を自動で判断しながら、パレットやコンテナへ効率よく荷物を積み込むことが可能です。
従来は熟練作業員が担っていた複雑な積載作業が自動化されたことで、作業時間の短縮と作業者の身体的負担の軽減を両立しています。さらに、AIによるリアルタイムな積載プランニングにより、積載率の最適化が進み、トラックの台数削減にも寄与しました。
このように、ロボットとAIを融合したソリューションは、労働力不足の緩和だけでなく物流効率の向上にも直結しています。
出典参照:働き手不足を解消する業界初「AI搭載荷積みロボット導入」への挑戦|佐川急便株式会社
日本通運株式会社では、倉庫内作業の省人化と効率化を目的にAMR(自律協働型ロボット)を導入しています。このロボットは、作業者と連携しながらピッキング作業を支援し、指定された商品の場所まで自律走行で移動したり作業者のもとに商品を運んだりできます。
導入前と比べて作業者の移動距離が減少し、1人あたりの作業効率が上がったのもメリットです。ロボットは運行ルートや指示をリアルタイムでアップデートできるため、倉庫内の動線の最適化にも貢献しています。
このような協働型ロボットの活用は、現場の人員負担を軽減しながら一定の作業品質を維持する上でも有効な手段です。物流DXを本格的に推進する上でのモデルケースといえるでしょう。
出典参照:日通、倉庫向け協働型ピッキングソリューションの本稼働を開始| 日本通運株式会社

ロボット技術は、物流DXを推進する上で有効なツールです。人手不足への対応や作業効率の向上、安全性の確保、そして標準化の実現など、多くのメリットをもたらします。導入時には、現場ごとの課題を丁寧に見極めることが欠かせません。
また、段階的な導入や人との協働設計、ROIを意識した運用によって、より確実な成果が期待できます。本記事で紹介した企業事例や技術活用のポイントを参考に、自社に適した取り組みを検討し、将来に向けた物流改革を進めていくことが重要です。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
