物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

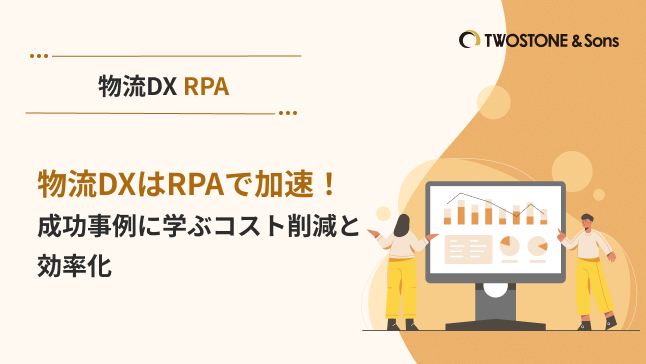
「物流の2024年問題」にあたり、人手不足やコスト高騰といった課題への対策は待ったなしの状況です。DX(デジタル・トランスフォーメーション)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)という言葉は耳にするものの、「何から始めればいいか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、DXの第一歩として適切な手段である「RPA」に焦点を絞り、その基本から導入のメリット・デメリット、大手企業の成功事例、そして現場主導で進めるための実践的なポイントまでを網羅的に解説します。ITに詳しくない方でも、自社での活用を具体的にイメージし、明日からの業務改革のヒントを得られるはずです。

ドライバーの時間外労働上限規制による輸送能力の低下は、業界全体の収益構造に大きな影響を与えかねません。こうした状況下で、テクノロジーを活用して生産性を向上させる「物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)」が急務となっています。
その中でも特にRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、現場の定型業務を自動化し、人手不足の解消やコスト削減に直結する即効性の高い解決策として、今まさに注目を集めています。
物流業界は、かねてよりドライバーや倉庫作業員の人材確保に苦慮してきました。少子高齢化の進行はこの問題に拍車をかけ、経験豊富なベテラン従業員の退職によるノウハウの喪失も懸念材料です。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入すれば、これまで人間が行っていたデータ入力や伝票処理といった定型業務をソフトウェアロボットに任せられます。
これにより、限られた人材を荷役や顧客対応といった、より付加価値の高いコア業務に再配置することが可能となり、人手不足の状況下でもサービス品質を維持・向上させる体制を構築できます。
燃料費の高騰、人件費の上昇、そして2024年問題による輸送効率の低下懸念など、物流業界のコスト構造は厳しさを増す一方です。このような環境で利益を確保するためには、既存業務の抜本的な効率化が不可欠です。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、24時間365日稼働できる「デジタルレイバー(仮想知的労働者)」として、人件費を直接的に削減するだけでなく、残業時間の抑制にも貢献します。
初期投資は必要ですが、長期的に見れば人件費や採用・教育コストを下回り、持続可能な利益体質への転換を力強く後押ししてくれるでしょう。
「この業務はAさんしか分からない」といった属人化は、担当者の不在時に業務が停滞するリスクを抱えるだけでなく、品質のばらつきや非効率の原因にもなります。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入する過程では、まず既存の業務プロセスを可視化し、ルールを明確にしましょう。この作業自体が、業務の標準化を進める絶好の機会となります。ロボットは定められた手順を寸分違わず実行するため、業務品質は常に一定に保たれます。
これにより、特定の個人に依存しない、安定した業務基盤を確立し、組織全体の生産性向上を実現可能です。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は「IT専門家でなくても使える」と言われますが、その能力を最大限に引き出すためには、基本的な仕組みや他のツールとの違いを理解しておくことが重要です。
ここを曖昧にしたまま導入を進めると、期待した効果が得られないばかりか、かえって業務が混乱する可能性もあります。RPAとは一体何で、なぜ物流現場の管理職であるあなたにとって強力な武器となり得るのか、その本質を正しく理解し、導入成功への第一歩を踏み出しましょう。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を簡単に言えば、「パソコン上で行う定型的な事務作業を自動化するソフトウェア」です。人間がマウスやキーボードを使って行う操作(特定のシステムへのログイン、ファイルを開く、データをコピー&ペーストする、メールを送信するなど)を記録・学習し、寸分違わず再現します。
「仮想知的労働者(デジタルレイバー)」とも呼ばれ、一度作業手順を覚えさせれば、文句も言わず24時間365日、高速かつ正確に業務をこなし続けます。プログラミングの知識がなくても、直感的な操作でロボットを作成できるツールが多いという特徴を持ちます。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、しばしばExcelマクロやAI(人工知能)と混同されがちですが、その役割は異なります。Excelマクロは、あくまでExcel内での作業を自動化する機能です。
一方、RPAはブラウザ、基幹システム、メールソフトなど、複数のアプリケーションを横断した一連の作業を自動化できます。また、AIがデータに基づいて自ら学習・判断するのに対し、RPAは事前に定義されたルールに従って動くのが基本です。
AIを「頭脳」とするなら、RPAは「手足」に例えられます。ルールが明確な定型業務はRPA、複雑な判断が必要な非定型業務はAI、と覚えておくと良いでしょう。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)が多くの企業で支持される理由は、その導入ハードルの低さにあります。
多くのRPAツールは、プログラミング言語を書く代わりに画面上のアイコンをドラッグ&ドロップしたり、実際の操作を録画したりするだけで、ロボットの動作を作成可能です。
そのため、業務内容を熟知している現場の担当者が、自ら自動化を進める「現場主導のDX(デジタル・トランスフォーメーション)」を実現しやすいです。
RPAの導入は、単に作業が自動化されるだけでなく、コスト削減・品質向上、そして従業員の働きがい向上といった、多岐にわたる恩恵を企業にもたらします。
これまで「仕方ない」と諦めていた煩雑な事務作業から解放されることで、物流現場にはどのような変革が生まれるのでしょうか。ここでは、RPAがもたらす5つの具体的なメリットを挙げ、貴社が享受できる未来をより鮮明に描いていきます。
これらのメリットを理解することで、導入目的が明確になり、社内での合意形成もスムーズに進むでしょう。
ロボットは、人間のように休憩や睡眠を必要とせず、24時間365日稼働し続けることが可能です。人間よりもはるかに高速で作業を処理するため、これまで数時間かかっていたデータ集計やシステムへの入力作業が、わずか数分で完了するケースも少なくありません。
特に、夜間や早朝に受注データを自動で処理させておけば、従業員が出社した時点ですぐに次の工程(ピッキングや配送計画など)に着手できます。これにより、業務プロセス全体が前倒しで進み、組織全体の生産性が向上します。
定型業務をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)に任せることで、その作業に費やされていた従業員の労働時間を、別の付加価値の高い業務に振り向けられます。結果として、残業時間の削減や、繁忙期に必要だった派遣社員・アルバイトの抑制につながり、直接的な人件費の削減が可能です。
また、人材の採用や教育にかかるコストも軽減されます。これまで外部の業者に委託していたデータ入力などの業務を内製化できれば、外注費の削減も実現します。RPAは、一度導入すれば継続的にコスト削減効果を生み出す、費用対効果の高い投資と言えるでしょう。
人間が手作業で業務を行う以上、どれだけ注意していても入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。特に、WMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)へのデータ入力、請求書作成といった作業でのミスは、手戻りや顧客とのトラブルに直結しかねません。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定められたルール通りに寸分違わず作業を実行するため、ヒューマンエラーは原理的に発生しません。これにより、業務品質が安定し、ミスの修正や確認に費やしていた時間的・精神的コストから解放されます。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、人間の労働時間という制約を受けません。夜間に受け付けた注文データを自動で基幹システムに登録したり、配送状況を関係者に自動でメール通知したりといった活用が可能です。
これにより、受注から出荷、納品までのリードタイムを短縮できます。顧客からの問い合わせに対しても、RPAが関連システムから情報を収集して一次回答を自動生成するなど、迅速な対応が実現します。サービスのスピードと質が向上することで、顧客満足度は確実に高まり、競合他社に対する大きな優位性を築くことにつながるでしょう。
「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)に仕事が奪われる」という懸念は誤解です。RPAが代替するのは、創造性を必要としない、繰り返しの多い単純作業です。むしろ、従業員をこうした退屈な作業から解放し、本来人間にしかできない業務に集中させることこそが、RPA導入の真の目的と言えます。
例えば、改善提案、顧客とのコミュニケーション、複雑なトラブル対応、スタッフの教育といったコア業務に時間を使えるようになれば、従業員のモチベーションやエンゲージメントは向上します。RPAは、従業員の働きがいを高め、企業の成長を支える人材を育む土壌を作ることが可能です。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は多くのメリットを持つ強力なツールですが、万能ではありません。その特性を理解せずに導入を進めると、予期せぬトラブルに見舞われたり、期待した効果が得られなかったりする可能性があります。
光の部分だけでなく、影の部分も正しく認識し、事前に対策を講じることが導入成功の鍵です。ここでは、RPA導入における代表的な4つのデメリットと、それらを乗り越えるための具体的な対策を解説します。リスクをあらかじめ把握しておくことで、より着実なRPA導入計画を立てられるようになります。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、Webサイトのデザイン変更や連携しているシステムのアップデートなど、画面レイアウトや操作手順の変更に弱いという特性があります。昨日まで正常に動いていたロボットが、こうした外部環境の変化によって突然停止してしまうリスクがあります。
対策としては、導入初期からIT部門と密に連携し、関連システムの変更情報を早期に共有する体制を構築することが不可欠です。また、エラー発生時に管理者に自動で通知が飛ぶ仕組みや、軽微な修正は現場で対応できるような保守運用ルールを定めておくことも重要となります。
現場主導で手軽に導入できる反面、各部署でバラバラにRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)化が進むと、誰がどの業務を自動化しているのか、組織全体で把握できなくなる恐れがあります。作成した担当者が異動・退職すると、ロボットの仕様が誰にも分からなくなり「ブラックボックス化」してしまいます。
さらに、管理されていない「野良ロボット」が増殖すると、セキュリティやガバナンス上の大きなリスク要因となるでしょう。対策として、全部署のRPAロボットを管理する台帳を作成し、仕様書や業務フロー図の作成をルール化することが有効です。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、ルール化された定型業務の自動化は得意ですが、人間の判断が必要な複雑な業務や、頻繁に手順が変わる業務には向きません。RPA化の対象業務を誤ると、開発に多大な工数がかかったにもかかわらず、ほとんど効果が出なかったり、メンテナンスばかりに追われたりする結果になりかねません。
これを防ぐには、導入前に業務プロセスを徹底的に可視化・分析し、「繰り返し発生する」「ルールが明確」「電子的データで処理が完結する」といったRPA向きの業務を慎重に選定することが重要です。費用対効果の事前シミュレーションも欠かせません。
ロボットには、業務システムへのログインIDやパスワードといった重要な情報を持たせるケースが多々あります。これらの認証情報の管理が杜撰だと、悪意のある第三者による不正アクセスや、情報漏えいの踏み台にされる危険性があります。
対策としては、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)専用のIDを発行し、必要最小限のアクセス権限のみを付与することが基本です。また、パスワードは暗号化して管理し、ロボットの操作ログを定期的に監視するなど、IT部門と連携して堅牢なセキュリティポリシーを策定・遵守することが求められます。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)が物流現場でどのように活用され、どれほどの効果を上げているのか、具体的なイメージを掴むには成功事例に学ぶのが一番です。
ここでは、業界をリードする物流大手3社が、RPAを駆使してどのように業務改革を成し遂げたのかを紹介します。
各社の取り組みからは、大規模な業務時間削減のインパクトだけでなく、現場主導の推進体制や他ツールとの連携といった、導入成功のためのヒントが見えてきます。自社の状況と照らし合わせながら、RPA活用の可能性を探ってみましょう。
日本通運は、2018年からRPA推進の取り組みを開始し、2021年3月までの約3年間で年間72万時間を超える業務時間の削減を達成しました。
同社は、多くの部署で利用できるよう導入方針を明確にし、業務内容に応じて集約型と横展開型の2種類のロボットを使い分けることで、効率的な展開を実現しています。
この大規模な成功は、トップダウンの明確な目標設定と、現場を巻き込むボトムアップの施策が両輪となって初めて成し遂げられることを示しています。
出典参照:日通、RPA導入の推進で労働時間を72万時間削減 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
ニチレイロジグループは、3年越しの取り組みにより、年間18万時間もの業務をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)化することに成功しました。
この時間は、物流センター勤務の従業員の年間総労働時間の約6%に相当します。同社の際立った特徴は、IT部門主導ではなく、全国の物流センターをはじめとする事業所の従業員が自らシナリオを作成し、業務を変革していく「現場主導」のスタイルを徹底している点です。
時間外労働の削減はもちろん、RPAをきっかけに業務フローそのものを見直す動きにも繋がっています。
出典参照:年間18万時間の業務のRPA化を達成しました。|株式会社ニチレイロジグループ
ロジスティードは、国内330を超える拠点が点在し、業務の標準化が難しいという物流業界特有の課題を抱えていました。同社は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)単体での自動化には限界があると考え、業務改善プラットフォーム「kintone」を組み合わせることで、この課題に立ち向かっています。
kintoneで業務プロセスや情報基盤を整備し、RPAで定型作業を自動化するという役割分担により、全社的な業務改善を推進可能です。ツールを組み合わせることで、より大きな効果を生み出せることを示す好例です。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入は、ツールをインストールすれば終わりではありません。その効果を最大限に引き出し、持続的な業務改善のサイクルを生み出すためには、戦略的なアプローチが不可欠です。
ここでは、RPA導入を成功に導くための具体的な7つのポイントを、計画から導入、運用、展開までのフェーズに沿って解説します。これらのポイントを一つひとつ着実に実行していくことが、RPAという強力な武器を使いこなし、現場の生産性を飛躍的に高めるための確実な道のりとなります。
最初に、「何のためにRPAを導入するのか」という目的を明確にすることが重要です。「コストを10%削減する」「データ入力業務の時間をゼロにする」「リードタイムを1時間短縮する」など、具体的かつ定量的な目標を設定しましょう。
目的が明確になることで、関係者の目線が揃い、導入プロジェクトがスムーズに進行します。同時に、最初は特定の部署の特定の業務に絞るなど、導入範囲を限定することも大切です。スモールスタートで成功体験を積むことが、その後の全社展開に向けた弾みとなります。
次に、自動化の候補となる業務のプロセスを徹底的に洗い出し、「見える化」します。誰が・いつ・何を・どのように処理しているのかをフローチャートなどで整理することで、業務の全体像が明らかになり、どこにボトルネックや非効率が存在するのかが分かるでしょう。
その上で、「繰り返し頻度が高い」「ルールが明確で例外が少ない」「扱うデータが電子的である」といった観点から、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)化に適した業務を選定します。この見極めが、RPA導入の成否を大きく左右します。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)化の対象業務を決めたら、導入にかかる費用(ライセンス費用、開発・保守費用など)と、得られる効果(人件費削減額、生産性向上による利益など)を試算し、投資対効果(ROI)を明確にします。
この試算があることで、経営層への説明や予算確保が容易になります。その上で、自社の目的や規模に合ったRPAツールを選定しましょう。パソコンにインストールする「デスクトップ型」かサーバーで集中管理する「サーバー型」か、あるいは手軽な「クラウド型」か、サポート体制や操作性なども含めて複数のツールを比較検討することが重要です。
最初から全社一斉に大規模な導入を目指すのはリスクが高いアプローチです。まずは、選定した一部の業務で試験的にRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入する「スモールスタート」を推奨します。小さな成功を積み重ねることで、RPAの効果を具体的に示し、現場の協力や経営層の理解を得やすくなるでしょう。
また、実際に動かしてみることで見えてくる課題も多くあります。完璧なロボットを一度で作ろうとせず、まずは作って動かし、現場からのフィードバックを元に修正・改善を繰り返す「アジャイル」な開発姿勢が成功の鍵を握ります。
現場主導で進められるのがRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の良さですが、安定した運用のためにはIT部門との連携が不可欠です。RPAが連携する社内システムの仕様変更や、セキュリティポリシーの遵守、サーバーやネットワークの管理など、専門的な知見が必要な場面は必ず出てきます。
導入の初期段階からIT部門を巻き込み、役割分担を明確にしておきましょう。トラブル発生時のエスカレーションルールを決めておくことで、迅速な問題解決が可能になり、業務への影響を最小限に抑えることができます。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による業務改善を継続的に行っていくためには、外部のベンダーに依存するのではなく、社内にRPAを扱える人材を育てることが極めて重要です。業務を理解している現場の従業員が、自らRPAを作成・修正できるようになれば、改善のスピードは飛躍的に向上します。
ツールの使い方を学ぶ研修会を実施したり、部署内で中心となるキーパーソンを育成したりするなど、計画的な教育体制を構築しましょう。成功事例やノウハウを共有する社内コミュニティを作ることも、スキル向上とモチベーション維持に有効です。
スモールスタートで得られた成功事例とノウハウを元に、いよいよ全社展開を目指します。このフェーズでは、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)活用のための統一的なルール作りが重要になります。
ロボットの開発・命名規則、ドキュメントの管理方法、野良ロボットを防ぐための申請・承認フロー、セキュリティガイドラインなどを定め、全社で遵守する体制を整えましょう。また、RPA推進を専門に行う部署(CoE:Center of Excellence)を設置することで、全社的な活用支援、ガバナンス維持、高度な技術サポートを一元的に行えるようになります。

本記事では物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の鍵としてRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を解説しました。深刻な人手不足やコスト課題に対し、RPAは定型業務を自動化する即効性の高い一手です。
従業員を単純作業から解放し、付加価値の高いコア業務へ集中させることで、企業の競争力は向上します。IT専門家でなくても始められる手軽さがRPAの魅力であり、まずは小さな業務から試行し、現場主導で成功体験を積むことが重要です。
危機をチャンスに変え、未来への優位性を確立するため、今こそRPAによる業務改革を始めましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
