物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

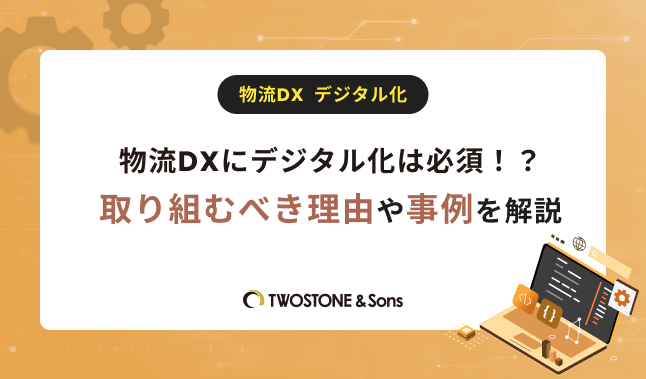
物流業界では人手不足が深刻化し、配送量の増加や多様化する顧客ニーズへの対応が求められています。しかし、他の業界と比較してデジタル化の進展が遅れているのが現状です。
多くの物流企業が抱える課題は、長年培われてきたアナログな業務プロセスからの脱却の難しさにあります。現場では紙ベースの管理や電話での連絡が当たり前となっており、デジタル化への移行に抵抗感を持つ従業員も少なくありません。
本記事では物流業界でデジタル化が進まない具体的な背景から、取り組むメリットや実際の成功事例まで詳しく解説します。記事を読むことで自社の物流業務におけるデジタル化の方向性が明確になり、効果的な推進方法が理解できるでしょう。また実際に導入できるツールや他社の取り組み事例の紹介も、具体的なアクションプランの策定にも役立つ内容です。

物流業界においてデジタル化の進行が遅れているのは、単なる技術的問題にとどまりません。複雑なサプライチェーン構造や中小企業の多さ、長年にわたり築かれた慣習的な業務フローが大きな障壁となっています。さらにIT投資に対する消極的な姿勢や人手依存の文化が根強く残っており、新技術の導入に対する抵抗感も少なくありません。
こうした背景の正しい理解によって自社の課題がどこにあるかを把握し、デジタル化推進への第一歩を踏み出すためのヒントが得られます。
物流業界では長年にわたって培われてきた業務プロセスが根強く残っています。特に現場作業ではベテラン従業員の経験と勘に依存した業務が多く、そのノウハウが標準化されていません。
このような属人化された業務環境ではデジタル化を導入しても、既存の作業方法の変更に対する抵抗が生まれやすくなります。従業員にとって慣れ親しんだ紙ベースの伝票管理や電話での連絡方法が、効率的ではないものの安心感を与える要素であるためです。
さらに現場では、急な変更や例外処理が頻繁に発生するため、柔軟性を重視した人的対応が優先されます。デジタルシステムの導入により、かえって業務の柔軟性が損なわれるのではないかという懸念もデジタル化の推進を阻む要因です。
物流業界は荷主や運送会社、倉庫業者、配送業者など多数の事業者が複雑に連携して成り立っています。このような多層構造では1つの企業だけがデジタル化を進めても、他の連携先がアナログな業務を続けていれば全体の効率化は実現できません。
また扱う商品の種類や配送方法、取引先企業の要求水準もさまざまであり、画一的なデジタル化の手法の適用が困難です。食品配送では温度管理が大切であり、精密機器の配送では振動や衝撃への配慮が必要になります。このような多様性に対応するためにはカスタマイズされたシステムが必要となり、導入の複雑さが増してしまいます。
大手企業がデジタル化を進めても協力会社や下請け企業がついていけない場合、業界全体の効率化は進みません。このような構造的問題が、物流業界のデジタル化を困難にしています。
物流業界のデジタル化には相当な初期投資が必要となります。倉庫管理システムや配送最適化システム、IoT機器の導入など包括的なデジタル化を実現するためには、数千万円から数億円規模の投資が必要になるケースも少なくありません。
特に中小規模の物流企業ではこのような投資をするための資金を調達しにくいケースが多く、デジタル化への取り組みを躊躇する要因となっています。
さらにデジタル化を推進するためには専門的な知識を持つ人材の確保も必要です。システムエンジニアやデータアナリストなどの専門職は人材市場でも希少性が高く、採用コストや人件費も高額になります。このような人材投資も含めて考えるとデジタル化にかかる総コストは膨大なものとなり、これが多くの企業が導入を見送る理由といえるでしょう。
物流業界ではデジタル化による効果を定量的に測定しにくい場合が多く、投資対効果を明確に示せません。例えば配送効率の向上や在庫管理の最適化によって実現可能なコスト削減がどの程度であるか、事前の算出は容易とはいえないでしょう。
特に既存の業務プロセスが複雑で多くの要素が相互に関連している場合、デジタル化による個別の効果を切り分けた評価が困難といえます。
さらに、定性的な効果についても測定が困難です。従業員の働きやすさの向上や顧客満足度の改善など、数値で表現しにくい効果は経営判断の材料として活用しにくいのが現状です。このような効果の見えにくさが、物流業界におけるデジタル化の推進を阻む要因といえるでしょう。
物流業界でのデジタル化の推進によって業務の効率化や人的負担の軽減だけでなく、全体最適によるサービス品質の向上やコスト削減、さらにはデータ活用による経営判断の高度化が期待されます。これらのメリットは単独ではなく相互に影響し合い、結果として競争力の強化につながります。
特に可視化・自動化・予測精度の向上は、現代物流における重要課題を解決する手段として有効です。こうしたメリットを理解し、自社の業務特性に合わせた活用によってデジタル化の効果を最大限に引き出せるでしょう。
デジタル化によって従来手作業で行っていた業務を自動化できるため、人件費の削減が期待できます。例えば在庫管理システムの導入によって棚卸し作業の時間を短縮し、正確性も向上できるでしょう。
事務処理の自動化も重要な効果の1つです。受発注管理システムの導入によって注文書の作成や在庫確認、請求書発行などの事務作業を自動化できます。これによって事務担当者の作業負荷を軽減し、より付加価値の高い業務に集中できる環境を整えられるでしょう。
さらにデジタル化により業務プロセスの標準化が進むため、教育研修コストの削減にもつながります。システムに業務手順が組み込まれているため、新入社員の教育期間を短縮して早期の戦力化を実現できるでしょう。これらの効果により、物流企業は持続的な競争力の向上を図ることが期待できます。
デジタル化により、物流プロセス全体の状況をリアルタイムで把握できます。在庫レベルや配送状況、倉庫の稼働率など経営に必要な情報をダッシュボードで一元管理できるため、迅速かつ的確な意思決定が可能になります。
例えば特定の商品の在庫が不足している場合、システムが自動的にアラートを発して緊急発注や代替商品の提案が可能です。また配送遅延が発生した場合もリアルタイムでの情報共有により、顧客への連絡や代替配送手段の手配を迅速に行えるでしょう。
データの蓄積により、過去の傾向分析や将来の需要予測も高精度で行えます。このような情報活用により、企業は市場環境の変化に素早く対応できる組織へと変革が可能でしょう。
デジタル化により、顧客に対する情報提供の質と速度が向上します。配送状況追跡システムの導入によって顧客はリアルタイムで荷物の配送状況を確認でき、安心感を提供できます。
顧客からの問い合わせに対する対応も改善できるでしょう。統合的な顧客管理システムによって過去の取引履歴や配送実績を瞬時に確認でき、的確で迅速な回答が可能です。またチャットボットや自動応答システムの活用により、24時間365日の顧客サポートが実現できます。
さらにデータ分析により顧客の配送パターンや嗜好を把握できるため、パーソナライズされたサービスの提供が可能です。定期配送の最適化や特別な配送オプションの提案など、顧客のニーズに応じたきめ細かいサービスを展開できるでしょう。
デジタル化によって従来の肉体労働中心の業務から、より知的で創造的な業務へのシフトが可能になります。自動化により重労働や危険な作業を削減できるため、従業員の身体的負担を軽減できます。また作業の標準化によって熟練者でなくても一定レベルの作業が可能になるため、人材育成の効率化も図れるでしょう。
働き方の多様化にも対応できます。リモートワークやフレックスタイムの導入により、優秀な人材の確保と定着を促進できます。また、デジタルスキルを身につけた従業員のキャリアアップ機会の提供により、従業員満足度の向上と企業への定着率向上を実現できるでしょう。
人材不足が深刻な物流業界において、デジタル化は効果的な対策となります。少数精鋭での効率的な業務運営が可能になるため、人材確保の困難さを補うことにつながります。
デジタル化により蓄積されたデータは、新たな収益機会を創出する重要な資産となります。配送データや在庫データを活用した分析サービスの提供により、顧客企業の経営改善に貢献して新たな収益源を確保できます。
プラットフォーム型のビジネスモデルへの展開も可能です。自社の物流ネットワークを活用して他企業の配送業務効率化サービスを提供することにより、新たな市場機会を開拓できます。
さらにデジタル技術を活用した革新的なサービスの開発により、競合他社との差別化を図れます。例えばAIを活用した配送予測システム、ブロックチェーン技術を活用した透明性の高い物流管理システムなど、技術的な優位性を活かした新サービスの展開が可能です。このような新たなビジネスモデルの創出により、企業の成長機会が拡大するでしょう。

物流業界でデジタル化を成功させるには単なるシステム導入にとどまらず、経営戦略の一部として位置づける必要があります。業務プロセスの可視化や課題の洗い出しを先行させることで、導入するテクノロジーの方向性が明確になります。
また、現場との連携や教育体制の構築も欠かせません。特に現場の理解と協力を得ることがプロジェクト成功のカギとなります。段階的にスモールスタートし、PDCAサイクルを回しながら進めていくことが持続可能なデジタル化への道です。
デジタル化の成功には、現場で働く従業員の理解と協力が不可欠です。システム導入前に現場の作業員や管理者から詳細にヒアリングを行い、実際の業務における課題や改善希望を把握しましょう。
現場からの意見を取り入れる際は単なる不満や要望の聞き取りではなく、具体的な業務プロセスや作業手順の分析が必要です。例えばどの作業にどれくらいの時間がかかっているか、どの部分でミスが発生しやすいかなど定量的なデータと定性的な情報の両方を収集します。
また現場の従業員をプロジェクトチームに参加させることで当事者意識を高め、導入後の活用促進につなげることが期待できます。現場の意見を反映したシステム設計により、実用性の高いデジタル化を実現できるでしょう。
物流業界のデジタル化は一度に全てを変えるのではなく、段階的に進めることが大切です。最初に効果が見えやすい部分から着手し、成功体験を積み重ねることで組織全体のデジタル化に対する理解と支持を得られます。
各フェーズでは明確な目標設定と成果測定を行い、次のフェーズへの改善点を明確にします。小さな成功を重ねることで従業員の不安を解消し、デジタル化に対する前向きな姿勢を育成できるでしょう。
フェーズごとの計画では技術的な要素だけでなく、人材育成や組織体制の整備も含めて検討する必要があります。各段階で必要なスキルを持つ人材の配置や研修計画を策定し、組織の変革能力を段階的に向上させていきます。
デジタル化の効果を最大化するためには、質の高いデータの整備と効果的な活用体制の構築が不可欠です。まず現在散在しているデータを統合し、一元的に管理できる仕組みを構築します。データの標準化とクレンジングを行い、分析に適した形でデータを蓄積しましょう。
データの活用においては単なる集計や可視化にとどまらず、予測分析や最適化に活用できるレベルまで高める必要があります。機械学習やAI技術を活用して需要予測や配送ルート最適化などの高度な分析を行い、競争優位性を確保していきます。
経営陣もデータドリブンな意思決定の重要性を理解し、データ活用を推進する体制の整備が必要です。このような包括的なデータ活用体制により、デジタル化の真価を発揮できるでしょう。
デジタル化を成功させるためには、従業員のスキルアップと意識改革が大切です。新しいシステムの操作方法だけでなくデジタル化の目的や効果について十分な説明を行い、従業員の理解を深めましょう。特に長年アナログな業務に従事してきた従業員に対しては、丁寧な説明と段階的な教育が必要です。
研修プログラムでは、実際の業務に応じた実践的な内容を中心に構成します。座学だけでなく実際のシステムを使用した演習や現場でのOJTを組み合わせることで、実用的なスキルを身につけられます。
継続的な教育体制の整備も必要です。システムのアップデートや新機能の追加に対応できるよう、定期的な研修や勉強会を開催します。このような包括的な教育体制により、デジタル化の効果を最大化できるでしょう。
物流業界のデジタル化は単なる技術導入にとどまらず、組織全体の変革を伴う取り組みです。そのため経営層の強力なリーダーシップ、及び継続的なコミットメントが不可欠になります。経営者はデジタル化の重要性を明確に示し、全社的な取り組みとして推進する姿勢を示さなければなりません。
経営層はデジタル化に必要な投資を惜しまず、長期的な視点で取り組むことが大切です。短期的な収益への影響を懸念して投資を控えるのではなく、将来の競争力確保のための戦略的投資として位置づけます。
さらに経営層自身がデジタル技術に対する理解を深め、適切な判断を下せるよう努力する必要があります。このような経営層のリーダーシップにより、組織全体のデジタル化に対する意識改革を促進できるでしょう。
物流業界のデジタル化を進める際には、業務の特性に適したツールの選定が不可欠です。例えばWMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)、またIoTセンサーやGPSを活用した動態管理ツールなどがあります。
これらのツールは業務効率を高めるだけでなく、リアルタイムな状況把握や予測精度の向上にもつながります。自社の目的や課題に合致したツールを選ぶことで、導入の効果を最大限に引き出せるでしょう。
Oracle Fusion Cloud Inventory Managementはグローバル企業での豊富な導入実績を持つ、統合型の在庫管理ソリューションです。複数の拠点や倉庫にまたがる在庫を一元管理し、リアルタイムでの在庫状況把握を可能にします。高度なアルゴリズムによる需要予測機能により、適正在庫の維持と欠品リスクの最小化を同時に実現できるでしょう。
このシステムの特徴は、AIと機械学習を活用した高度な分析機能にあります。過去の販売データや市場動向を分析し、将来の需要を高精度で予測します。さらに、サプライチェーン全体の可視化により、調達から配送までの全プロセスを効率化できるでしょう。
システムの導入効果として、在庫回転率の向上と在庫コストの削減が期待できます。大規模な物流オペレーションを展開する企業にとって、特に有効なソリューションといえるでしょう。
出典参照:Oracle Fusion Cloud Inventory Management|日本オラクル株式会社
ロジモプロは中小規模の物流企業向けに開発された、使いやすさを重視した物流管理システムです。複雑な設定や高度な技術知識を必要とせず、直感的な操作で日常業務を効率化できます。受注管理から配送管理、請求処理までの物流業務を一貫して管理できるため、業務の標準化と効率化を同時に実現できるでしょう。
このシステムの特徴は物流業界の実務に精通した開発チームによる、実用性の高い機能設計にあります。現場の作業者が実際に使いやすいインターフェースと必要十分な機能を備えており、導入後の定着率が高い点もこのシステムの特徴です。またカスタマイズ性も高く、企業の業務プロセスに合わせた調整もできるでしょう。
コストパフォーマンスの高さも重要な特徴の1つです。初期導入費用と運用コストを抑えながら、物流業務の効率化に必要な機能を網羅しています。
出典参照:ロジモプロ|株式会社清長
MOVO Fleetは配送業務の効率化に特化した、クラウドベースの運行管理システムです。配送車両の位置情報をリアルタイムで把握し、配送効率の最適化を実現します。またドライバーの労働時間管理や安全運転支援機能も搭載されており、コンプライアンス向上にもつながるでしょう。
このシステムの特徴は、IoT技術を活用した高度な車両管理機能にあります。GPSによる位置情報の取得だけでなく、車両の稼働状況やドライバーの運転行動を詳細に分析可能です。これにより、燃料消費の最適化や事故リスクの低減を実現できるでしょう。また配送ルートの最適化により、配送時間の短縮と顧客満足度の向上を図れます。
データ分析機能も充実しており、配送パフォーマンスの可視化と改善提案が可能です。過去のデータを活用した配送効率の分析により、継続的な改善活動を支援します。
Logizard ZEROはEC物流に特化した、統合型の倉庫管理システムです。EC事業の急速な拡大に対応できる柔軟性と拡張性を持ち、多様な販売チャネルに対応した在庫管理を実現します。また返品処理や同梱物管理などのEC特有の業務要件にも対応しており、EC物流の効率化を包括的に支援します。
このシステムの特徴はEC業界での豊富な導入実績に基づく、実用性の高い機能設計です。ピッキング効率の最適化や梱包作業の標準化により、作業時間の短縮と品質の向上につながるでしょう。
さらに季節変動や促進活動による注文量の急増にも対応できる、柔軟なシステム設計となっています。繁忙期には作業効率を最大化し、閑散期には運用コストを最小化できる仕組みが構築されています。EC物流の効率化を図る企業にとって、特に有効なソリューションといえるでしょう。
Willogは物流業界における、働き方改革を支援する労務管理システムです。ドライバーの労働時間管理から車両の運行管理まで、包括的な管理機能を提供します。改善基準告示や労働基準法などの法令遵守を確実に行いながら、効率的な運行計画の策定を支援します。
このシステムは物流業界の法令遵守に特化した、機能設計が特徴です。休息時間の確保や連続運転時間の管理など、複雑な労働時間規制を自動的にチェックして違反リスクを事前に防止できます。
システムの導入効果として、労働時間管理の精度向上とコンプライアンスリスクの低減が期待できます。労働集約型の物流業界において、持続可能な事業運営を支援する重要なツールといえるでしょう。法令遵守を確実に行いながら、効率性も追求したい企業にとって、特に有効なソリューションです。
出典参照:Willog|Willog株式会社
物流業界では先進的な企業がデジタル化を積極的に進め、多くの成果を上げています。例えば大手物流会社がAIを活用して需要予測を行い、倉庫作業や配送計画を最適化しています。
また中小企業でもクラウド型システムを導入し、受発注の効率化や業務の可視化に成功した事例も珍しくありません。これらは自社が直面する課題を、どう乗り越えるかの参考になります。業界の動向を知ることで、より実践的なデジタル戦略の構築が可能になります。
福山通運株式会社は顧客の利便性向上を目的として、インターネットブラウザから直接送り状を発行できるサービスを開始しました。このサービスによって顧客は専用ソフトウェアをインストールする必要もなく、Webブラウザから簡単に送り状を作成・印刷できるようになりました。また過去の発送履歴や住所録の管理機能も搭載されており、繰り返しの発送業務の効率化を実現しています。
このデジタル化の取り組みにより、顧客の発送業務にかかる時間を短縮できました。従来は手書きや専用端末での入力が必要でしたが、Webベースのシステムによってどこからでも簡単に送り状を作成できるようになりました。また入力ミスの削減や配送情報の自動連携により、配送品質の向上も実現しています。
出典参照:iSTAR-X|福山通運株式会社
日本通運株式会社は美術品・文化財輸送の豊富な経験を活かし、収蔵品のデジタルアーカイブサービス「SmartMuse」を開始しました。このサービスは博物館や美術館が所蔵する貴重な文化財を高精度でデジタル化し、保存・管理・活用を支援する包括的なソリューションです。3Dスキャンや高解像度撮影により、実物に近い品質でのデジタル保存を実現しています。
このサービスの特徴は、物流企業ならではの専門知識を活かした包括的なサポート体制にあります。文化財の取り扱いから輸送、デジタル化作業まで一貫したサービスの提供により、文化財の安全性を確保しながら効率的なデジタル化を実現しました。またデジタル化されたデータは教育や研究、展示などのさまざまな目的に活用できるよう設計されています。
出典参照:収蔵品デジタルアーカイブサービス「SmartMuse」|日本通運株式会社
ヤマト運輸株式会社は「Oneヤマト」構想の実現に向け、包括的なデジタル戦略を推進しています。この取り組みの目的はAIやIoT、ビッグデータ分析などの先端技術を活用して配送効率の最適化と顧客サービスの向上です。特に機械学習を活用した需要予測システム、IoTセンサーを活用した配送車両の最適運行管理などが注目されています。
デジタル戦略の中核となるのは、顧客データと配送データの統合活用です。顧客の配送履歴や嗜好データの分析により、個別ニーズに対応したサービスの提供を実現しています。
このデジタル化の成果として、配送効率の向上と顧客満足度の改善を実現しました。物流業界のリーディングカンパニーとして業界全体のデジタル化を牽引する取り組みを展開しており、他社の参考事例としても価値の高い内容となっています。
出典参照:「Oneヤマト2023」の改革を支えるデジタル戦略の推進|ヤマト運輸株式会社
物流業界でデジタル化を推進するにあたっては技術選定だけでなく、組織全体での受け入れ体制を整える必要があります。現場とのギャップや既存業務との摩擦によって想定通りに進まないケースも珍しくありません。
また導入前に業務フローを整理しておかないと、システムがかえって混乱を招くこともあります。さらにセキュリティ対策やデータガバナンスも重要な要素です。デジタル化は技術導入ではなく、全社的な変革として取り組む姿勢が求められます。
物流業界におけるデジタル化を成功させるうえで、重要な要因の1つが、現場で働く従業員の理解と積極的な協力です。どれほど優れたシステムを導入しても、実際に使用する現場の反発があるケースや活用方法が不適切なケースでは期待した効果を得ることはできません。特に長年アナログな業務に従事してきた従業員にとってデジタル化は大きな変化であり、不安感や抵抗感を持つことは自然な反応です。
現場の理解を得るためにはデジタル化の目的と効果を明確に説明し、従業員にとってのメリットを具体的に示す必要があります。作業負荷の軽減や業務の標準化による従業員の働きやすさ向上を強調し、デジタル化が従業員の敵ではなく味方であることを理解してもらいましょう。
物流業界でデジタル化を進める際の大きな落とし穴の1つが、過度なカスタマイズによる複雑化です。既存の業務プロセスに完全に合わせたシステムのカスタマイズをしてしまうと、導入コストが膨らみ保守・運用も困難になります。またカスタマイズが多いシステムはアップデートが困難になり、長期的な運用に支障をきたす可能性があります。
適切なアプローチは標準的な機能を最大限に活用し、必要に応じた業務プロセス側の調整です。多くの場合は既存の業務プロセスに非効率な部分や不要な手順が含まれており、デジタル化を機に業務プロセス自体を見直すことでより効率的な運用が可能になります。システムの標準機能に業務を合わせることで、導入コストを抑えながら業務の標準化も実現できるでしょう。
デジタル化の効果を最大化するためには、高品質なデータの蓄積と活用が不可欠です。物流業界では配送データや在庫データなどの多様なデータが日々生成されますが、これらのデータの品質が低いと分析結果の信頼性が損なわれ、適切な意思決定ができなくなります。特に手入力によるデータの場合は入力ミスや表記のばらつきが発生しやすく、継続的な品質管理が必要です。
データ品質管理の第一歩は、データの標準化とバリデーションルールの設定です。住所表記の統一や商品コードの標準化など、データの一貫性を確保するためのルールを定めてシステムレベルでチェック機能を実装しましょう。

物流業界におけるデジタル化は、もはや選択の余地がない必要不可欠な取り組みとなっています。人手不足の深刻化や顧客ニーズの多様化、競争激化といった課題に対応するためにはデジタル技術を活用した業務改革が急務です。
本記事で解説した通り物流業界でのデジタル化推進には多くの障壁が存在しますが、適切な戦略と段階的なアプローチによってこれらの課題を克服できます。現場の理解を得ながら実用性の高いシステムを導入し、継続的な改善を行うことで競争優位性を確保できるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
