物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

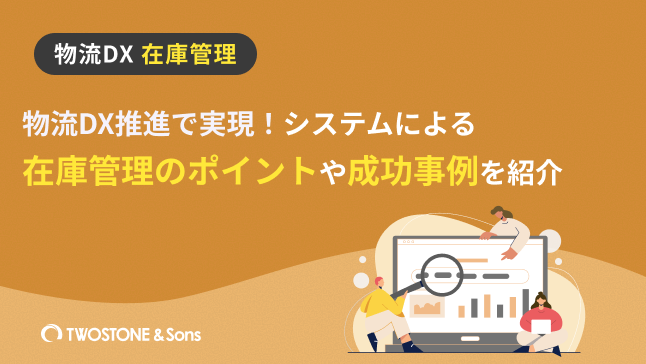
物流業界で働く皆さんの中には、在庫管理の煩雑さや非効率性に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。過剰在庫による保管コストの増大や欠品による機会損失、そして手作業による棚卸業務の負担など在庫管理にまつわる課題は尽きません。
しかし、これらの課題はシステム化によって解決できる可能性があります。デジタル技術を活用した在庫管理システムの導入は単なる業務効率化にとどまらず、物流DX推進の重要な一歩となるでしょう。
本記事では物流業界における在庫管理の具体的な課題からシステム化によって得られる効果、そして導入時のポイントまで詳しく解説します。さらに実際のシステム化に取り組んだ企業の事例も紹介し、貴社での導入検討に役立つ情報をお伝えします。記事を読み終える頃には在庫管理のシステム化の全体像が理解でき、次のアクションが明確になるはずです。

物流業界では顧客ニーズの多様化や配送スピードの向上要求により、在庫管理の重要性が高まっています。しかし、従来の手作業中心の管理方法では、さまざまな課題が顕在化しているのが現状です。
これらの課題を放置するとコスト増加や顧客満足度の低下につながり、企業の競争力を著しく損なう可能性があります。まずは現在の在庫管理にどのような問題があるのか、詳しく見ていきましょう。
多くの物流企業では、在庫データの正確性に課題を抱えています。手作業による入出庫記録は入力ミスや記録漏れが発生しやすく、実際の在庫数と帳簿上の数値に差異が生じやすいためです。
例えば複数の倉庫や拠点で同じ商品を扱っている場合、各拠点の在庫情報がリアルタイムで共有されていないことがあります。その結果、全体としての在庫量が把握できずに適切な発注タイミングを見極めることが困難になります。
また商品の保管場所が曖昧で、どこに何があるかがすぐにわからない状況も珍しくありません。これによってピッキング作業に時間がかかったり、在庫があるにも関わらず欠品扱いになったりするケースが発生します。
データの不正確さは顧客への納期遅延や余分な在庫コストの発生につながり、企業の収益性を圧迫する要因となっています。正確な在庫データなくして、効率的な物流業務は実現できません。
在庫管理の課題として特に深刻なのが、過剰在庫と欠品が同時に発生する現象です。これは需要予測の精度不足や、商品ごとの回転率を適切に把握できていないことが原因となっています。
過剰在庫は、保管コストの増大や商品の劣化・陳腐化による損失を招きます。特に季節商品や流行商品では売れ残りにより、値引きが必要になることもあるでしょう。一方で人気商品や基幹商品の欠品は、顧客の信頼失墜や売上機会の損失につながります。
このような状況が発生する背景には、各商品の需要パターンや季節変動を十分に分析できていないことがあります。また複数の商品を同じような基準で発注していることも、問題を複雑にしている要因です。
さらにサプライヤーとの連携不足によって納期情報を正確に把握できず、適切な発注タイミングを逃してしまうケースも多く見られます。これらの問題を解決するためには、データに基づいた科学的な在庫管理手法の導入が必要です。
従来の手作業による棚卸業務は、物流企業にとって負担となっています。月次や四半期ごとの棚卸作業には多くの人員と時間を要し、その間は通常業務を停止せざるを得ません。
棚卸作業の頻度が限られることで、在庫の正確性を長期間維持することが困難になります。例えば月に一度の棚卸の場合、月中に発生した在庫差異の早期発見ができず、問題の拡大を防げません。
また棚卸作業自体にも多くの課題があります。時間のかかる商品の数量確認やカウントミスの発生などにより、作業効率が低下します。特に大量の商品を扱う物流センターでは、棚卸作業だけで数日を要するケースも珍しくありません。
人手不足が深刻な物流業界において、棚卸業務の負担軽減は喫緊の課題です。効率的な在庫管理システムの導入によってこの負担を軽減し、より付加価値の高い業務に人員を配置できるようになります。
現代の物流業界ではECサイトの普及や消費者ニーズの多様化により、多品種・多頻度の入出庫に対応する必要があります。しかし従来の管理方法では、この複雑な動きへの対応が困難です。
多品種の商品を扱う場合、それぞれの商品特性や回転率を個別に管理する必要があります。しかし手作業での管理では、商品ごとの細かな分析や最適な配置の決定が困難です。結果として、効率的な倉庫運営が妨げられるかもしれません。
また多頻度の入出庫は、在庫データの更新作業を複雑にします。一日に何度も発生する入出庫に対してその都度正確なデータの更新は、人的リソースの面で現実的ではありません。
さらに急な受注や配送要求に対応するためには、リアルタイムでの在庫確認が必要です。しかし従来の管理方法では在庫照会に時間がかかり、迅速な対応が困難になっています。これらの課題を解決するためには、自動化とシステム化が不可欠です。
在庫管理システムの導入は、物流業界のさまざまな課題を解決する有効な手段として注目されています。従来の手作業中心の管理から脱却したデジタル技術の活用により、ミス防止やコスト削減などの改善効果が期待できます。
システム化によって得られる効果は多岐にわたりますが、ここで解説するのは特に重要な4つの理由です。これらの効果の理解により、システム導入の価値と必要性がより明確になるでしょう。
在庫管理システムの最大の利点は、リアルタイムで正確な在庫情報を把握できることです。バーコードやRFIDタグなどの技術の活用によって商品の入出庫が発生した瞬間に、システム上のデータが自動的に更新されます。
この機能により、従来の手作業による記録では避けられなかった入力ミスや記録漏れを削減できます。また複数の拠点を持つ企業でも全拠点の在庫情報を一元管理し、リアルタイムでの確認が可能です。
例えば顧客からの在庫照会に対して、従来は倉庫に確認の電話をかけていた作業がシステム上ですぐに回答できるようになります。これにより、顧客対応の迅速化と満足度の向上が実現できるでしょう。
さらに在庫の場所情報も正確に管理できるため、ピッキング作業の効率化にもつながります。作業者はシステムの指示に従って最適なルートで商品を集荷でき、作業時間の短縮と正確性の向上につながるでしょう。
在庫管理システムは過去の売上データや季節変動を分析し、需要予測機能を提供します。これによって各商品の適正在庫量を科学的に算出し、過剰在庫と欠品の両方を防ぐことが可能です。
システムは商品ごとの販売パターンや季節性を学習し、将来の需要を予測します。例えば、夏季に需要が高まる商品については事前に在庫を増やすような提案を行い、逆に需要が低下する商品については在庫削減を提案します。
またABC分析などの手法を用いて商品を重要度別に分類し、それぞれに適した在庫管理戦略を実行可能です。売上に貢献する商品については厳密な在庫管理を行い、重要度の低い商品については効率性を重視した管理ができます。
さらに自動発注機能の活用により、在庫が一定量を下回った際に自動的に発注処理を行えます。これによって発注業務の効率化と同時に、人的ミスによる発注漏れを防ぐことにつながるでしょう。
在庫管理システムの導入により、従来の棚卸作業が効率化されます。システムによって日々の入出庫が正確に記録されているため、理論在庫と実在庫の差異が最小限に抑えられ、棚卸作業の負担が軽減されるでしょう。
循環棚卸機能の活用によって全商品を一度に棚卸するのではなく、商品群ごとに分けて定期的に棚卸を行うことが可能です。これによって業務を停止せず、継続的に在庫の正確性を維持できます。
またハンディターミナルやタブレット端末の活用により、棚卸作業の効率が向上します。作業者はシステムの指示に従って商品をスキャンするだけで自動的に在庫数が更新され、手作業による集計作業が不要です。
さらに棚卸の頻度を増やすことで、在庫差異の早期発見が可能になります。問題が小さなうちに対処できるため大きな損失を防げ、結果として棚卸に関連するコストを削減できるでしょう。
在庫管理システムはサプライヤーや販売先との連携を強化し、サプライチェーン全体の最適化を支援します。システムを通じたリアルタイムの在庫情報や需要予測データの共有によって、より効率的な物流ネットワークを構築可能です。
例えばサプライヤーに対する在庫状況や発注予定の共有により、生産計画の最適化や納期の短縮が可能になります。また販売先に対しても在庫可能量や納期情報の正確な提供により、顧客満足度の向上につながります。
EDI(電子データ交換)機能の活用によって発注から納品までの一連の流れを電子化することで、ペーパーレス化と作業効率の向上が実現できるでしょう。手作業による伝票処理が不要になるため、処理時間の短縮とミスの削減が期待できます。
さらに複数の物流拠点を持つ企業では、拠点間の在庫移動の効率化につながるでしょう。各拠点の在庫状況を把握し、過剰在庫のある拠点から不足している拠点への移動の自動的な提案により、全体としての在庫効率向上が期待できます。

在庫管理システムの導入を成功させるためには単なるシステム導入ではなく、物流DX推進の一環として戦略的に取り組むことが大切です。デジタル変革を通じて業務プロセス全体を見直し、組織の競争力の向上が求められます。
成功するシステム導入のためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。これらのポイントを理解し、計画的に進めることで効果的なシステム化が実現できるでしょう。
システム導入の成功には現在の業務における具体的な課題を明確に把握し、システム化によって達成したい目的の設定が不可欠です。漠然とした効率化ではなく、定量的な目標設定が重要になります。
課題の明確化には、現場の担当者へのヒアリングや業務フローの分析が必要です。例えば棚卸作業にかかる時間や在庫差異の発生頻度、欠品による機会損失額などを具体的に数値化します。これらのデータを基にシステム導入によって改善すべき優先順位を決定しましょう。
導入目的は、経営層と現場の両方が納得できる内容にする必要があります。コスト削減や業務効率化、顧客満足度向上など複数の観点から目的を設定し、それぞれについて具体的な指標を定めることが大切です。
導入前後での比較ができるようベースラインとなるデータを収集し、改善効果を客観的に評価できる仕組みを構築します。
在庫管理システムの選定では、自社の業務フローに最適なシステムを選ぶことが大切です。システムに業務を合わせるのではなく、業務に合ったシステムの選択によって導入後の運用がスムーズになります。
まず自社の業務特性を詳細に分析します。扱う商品の種類や入出庫の頻度、倉庫の規模、作業者のスキルレベルなどの総合的な評価で、システムに求める機能要件を明確にしましょう。
システムの選定では機能だけでなく、操作性やカスタマイズ性も重要な要素です。現場の作業者が使いやすいインターフェースを持つシステムを選ぶことで、導入後の定着率が向上します。また、将来的な業務拡張に対応できる柔軟性も考慮する必要があります。
さらに、システムベンダーのサポート体制も選定の重要な要素です。導入時のサポートだけでなく、運用開始後の継続的なサポートやシステムのアップデート対応についても確認しておきましょう。
システム導入の成功には、現場での運用定着が不可欠です。どんなに優れたシステムを導入しても使う人がその価値を理解し、適切に運用できなければ期待した効果は得られません。
教育プログラムは利用者のスキルレベルに応じた、段階的な実施が効果的です。基本的な操作方法から始まり、応用的な機能の活用まで体系的に教育を進めましょう。
システム導入初期には現場で発生する、さまざまな疑問や問題に迅速に対応できるサポート体制を整えることが必要です。社内にシステムの専門知識を持つ人材を配置し、現場からの質問に即座に回答できる環境を作ります。
またシステムの運用マニュアルや操作手順書を整備し、作業者がいつでも参照できるようにします。これらの資料はシステムの更新に合わせて定期的に見直し、最新の情報を提供し続けることが大切です。
物流DXの推進において、現場と本社間のリアルタイム連携は重要な要素です。在庫管理システムを通じて現場の状況を本社がリアルタイムで把握し、迅速な意思決定を実行可能にしましょう。
ダッシュボード機能の活用により、経営層や管理者が在庫状況、入出庫実績、異常発生状況などを一目で把握できます。これによって問題の早期発見と対応が可能になり、業務の安定性が向上するでしょう。
また、現場から本社への情報伝達も効率化します。従来の電話やメールでの報告からシステムを通じた自動的な情報共有に変えることで、情報の正確性と伝達速度が向上するでしょう。
さらに本社からの指示や方針変更についても、システムを通じて現場に迅速に伝達可能です。これにより組織全体の一体感が高まり、変化への対応力が強化されるでしょう。現場と本社の連携強化は、物流DX推進の成功に不可欠な要素です。
在庫管理システムの導入では、既存のシステムや他業務との連携性を十分に検討しましょう。単独のシステムとして動作するのではなく、既存のITインフラとの統合でより効果を得ることができます。
例えば既存の販売管理システムや会計システムとの連携によって、受注から出荷、請求までの一連の流れを自動化できます。これによって業務効率の向上だけでなく、データの一貫性も確保できるようになるでしょう。
またWMS(倉庫管理システム)やTMS(輸送管理システム)との連携により、物流業務全体の最適化にもつながります。在庫情報を基にした配送計画の立案や倉庫内作業の効率化など、システム間の連携によって実現できる効果は多岐にわたります。
物流DXの推進において、在庫管理システムの導入は多くの企業で実施されています。実際の導入事例を通じてシステム化の具体的な効果や導入のポイントの理解により、自社での取り組みに活かせるでしょう。
ここでは物流業界の大手企業3社の事例を紹介し、それぞれの特徴や成功要因を詳しく分析します。これらの事例は規模や業務特性の異なる企業での取り組みを示しており、さまざまな状況に応用できるヒントが含まれています。
日本通運株式会社は物流DX推進の一環として、ASP型在庫管理システム「webWins」の開発に取り組みました。このシステムは中小規模の荷主企業向けに設計されており、初期投資を抑えながら高機能な在庫管理を実現できる点が特徴です。
webWinsの開発背景には、荷主企業の在庫管理に対するニーズの多様化があります。従来の物流サービスでは荷主企業は自社で在庫管理システムを構築する必要がありましたが、中小企業にとって高額な初期投資は大きな負担となっていました。
システムの主な機能にはリアルタイム在庫照会や入出庫実績管理、在庫分析レポート作成などがあります。Webベースのシステムのため、荷主企業は自社のパソコンからインターネット経由で在庫情報にアクセスでき、場所を選ばずに在庫管理を行うことが可能です。
出典参照:ASP型在庫管理システム(webWins)|日本通運株式会社
日本郵政株式会社はEC市場の拡大に対応するため、通販事業者の商品を効率的に扱うためのWMS(倉庫管理システム)の機能強化を行いました。このシステム開発は多様な商品特性と高頻度な入出庫に対応するための、重要な取り組みです。
従来のWMSは主に企業間取引の大口商品を想定し、設計されていました。しかし通販事業者の商品は多品種少量で、サイズや形状もさまざまです。また個人消費者向けの配送が中心となるため、小口配送への対応も必要でした。
新しいWMSでは商品マスタの柔軟な管理機能を強化し、商品の特性に応じた保管方法や取り扱い方法を設定できるようになりました。
さらに返品処理や在庫調整などの機能も強化されています。これらの機能強化により、通販事業者の物流品質向上に貢献しています。
出典参照:WMS|日本郵政株式会社
アルプス物流株式会社は電子部品の特性に特化した独自のWMS「ACCS」を開発し、フリーロケーション管理を実現しました。電子部品は形状が小さく、品種が多様で静電気対策を要するなど、特殊な管理要件があります。
従来の固定ロケーション管理では、商品ごとに固定の保管場所を設定していました。しかし電子部品のように品種が多く入荷量も変動しやすい商品では、保管スペースを有効活用できず、効率的な運用が難しいという課題がありました。
ACCSではフリーロケーション管理により、商品を空いている場所に自由に保管可能になりました。システムが各商品の保管場所を自動的に管理し、ピッキング時には最適な取得順序を指示します。これにより、保管効率の向上と作業時間の短縮を実現しました。
出典参照:挑んでいるのは、他にはない保管品質の高み|株式会社アルプス物流

在庫の見える化不足や過剰在庫と欠品の同時発生、棚卸業務の負担、多品種・多頻度入出庫への対応難などこれらの課題は多くの企業で共通して発生しています。
在庫管理システムの導入によってリアルタイムでの正確な在庫把握や需要予測と連動した適正在庫の実現、棚卸作業の効率化、サプライチェーン全体の連携強化が可能になります。これらの効果は単なる業務効率化を超え、企業の競争力向上に直結する重要な要素です。
物流DXの推進は単なるデジタル技術の導入ではなく、組織全体の変革を伴う取り組みです。適切な計画と実行によって在庫管理の最適化を実現し、持続可能な競争優位を構築しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
