物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

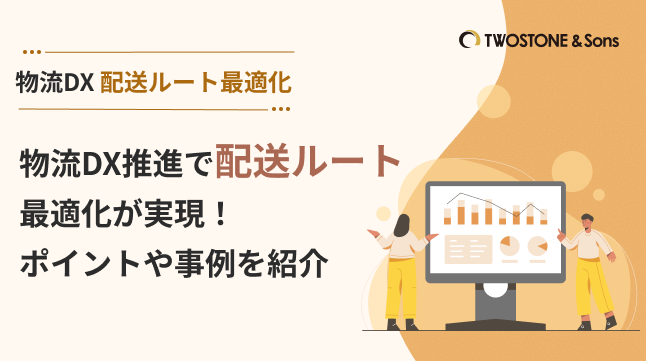
物流業界では、配送の効率化や顧客満足度向上のために配送ルートの最適化が重要視されています。特に近年のEC市場の急成長により配送量が増加し、配送ルートの設計はより複雑になっています。しかし、従来はドライバーの経験に頼る属人的な運用やリアルタイムの交通情報を十分に活用できない状況が多く見られるようになりました。その結果、配送の遅延やコストの増加が生じています。
さらに、多様化する配送制約やラストワンマイルの非効率化も大きな課題です。これらを解決するためには、物流DXの推進によってシステム的に配送ルートを最適化し、効率的かつ柔軟な配送体制を築く必要があります。
本記事では、配送ルート最適化の課題やポイント、実際に成果を上げている事例を詳しく解説します。これにより、読者が自社の物流改革を具体的に進めるためのヒントを得られるでしょう。

近年、物流業界では配送ルート選定の難易度が高まっています。配送量の増加や配送先の多様化によって、従来の手法では効率的なルートの設定が難しくなりました。多くの企業がまだドライバーの経験や直感に頼り、属人的な運用が続いているため配送効率にムラが生じています。
配送全体のボトルネックになっています。これらの課題は物流コストの増加やサービス低下につながり、業界全体の課題として注目されました。
物流業務の現場では、配送ルートの決定はドライバーの経験や個人の勘に依存しています。こうした属人化は配送の効率性にばらつきを生み、新人ドライバーの育成も困難です。ベテランドライバーが不足する現状では経験不足のドライバーが効率的なルートを設計できず、遅延や無駄な燃料消費が増加しやすくなっています。
属人化の解消は、配送業務の標準化と効率化を図る上で不可欠です。システムを活用した配送ルートの最適化は経験に頼らない効率的な配送計画を実現し、業務の均質化を促します。これにより新人でも効率的な配送が可能になり、業務全体のパフォーマンス向上が期待できるでしょう。
固定された配送ルートを前提とするケースが多いため、交通渋滞や事故などのリアルタイムな道路状況を反映できていません。このため予定していた配送時間を守れず、遅延や配送トラブルが発生しやすくなっています。リアルタイム交通情報の活用が十分でないことは無駄な待機時間や燃料消費を増加させ、結果として配送コストを押し上げています。
近年の技術進歩により、交通情報をリアルタイムで収集・分析し、配送ルートに反映させるシステムが登場しました。こうしたシステムを導入することで道路状況の変化に応じてルートを柔軟に変更し、効率的な配送を実現できるでしょう。結果として配送時間の短縮やコスト削減につながり、顧客満足度の向上が期待できます。
現代の配送業務は、時間帯指定や複数配送先の同時対応、荷物の取り扱い制限など多様な条件が課せられています。これらの複雑な制約を考慮しながら配送ルートを設計するのは高度な作業です。単純なルート計画では、こうした条件を満たせず結果的に配送効率が低下してしまいます。
配送ルート最適化システムはこれらの複雑な制約を数学的にモデル化し、最適解を導き出してくれるのがポイントです。条件を正確に反映したルート設計により、配送ミスの減少や顧客満足度を上げられるでしょう。また、業務の効率化によって配送コストの削減にも貢献します。高度なシステムの導入は、今後の配送業務の競争力強化に欠かせません。
配送の最終段階であるラストワンマイルは狭い路地や住宅街での配送が多く、効率化が難しい部分です。駐車スペースの不足や複数回の停車が必要になるため、時間やコストがかかりやすいです。こうした要因が配送全体の効率を阻害し、配送コストの増加や納期遅延を引き起こしています。
配送ルートの最適化により、ラストワンマイルの課題を解決する手法が増えました。例えば、停車回数を減らすための集約ルートの設計や交通量が少ない時間帯を選択した配送計画などが挙げられます。これらの取り組みは現場の負担軽減とコスト抑制に効果的であり、物流の質の向上に貢献します。
物流DXの推進により、配送ルートの最適化は単なる効率化以上の意味を持ち始めています。人手不足の深刻化やコスト圧力の増大、顧客の高まるニーズへの対応、環境問題への配慮が求められる現代では、配送ルートの最適化が企業の競争力を左右する重要な要素です。
ここでは、これらの課題を総合的に解決するために物流DXの中核として配送ルートの最適化に取り組むべき理由を4つに絞って解説します。
物流業界では慢性的な人手不足が続き、ドライバーの負担が増加しています。長時間労働や過密スケジュールは労働環境の悪化を招き、離職率の増加や新規採用の難航を招いています。配送ルートの最適化を図ることで無駄な移動や待機時間を削減し、ドライバー1人あたりの業務負荷を軽減できるのが大きなメリットです。
効率的なルート設計は配送時間の短縮にもつながり、適正な労働時間の確保がしやすくなります。結果的にドライバーの健康管理や安全運転の促進にも寄与し、業務の持続可能性を高める効果があります。こうした改善は人材確保や職場環境の向上にもつながるため、長期的な経営安定に貢献するでしょう。
配送ルート最適化は、物流コストの低減に直結します。従来の非効率なルート設計は燃料消費や車両の稼働時間を無駄に増やし、結果的に運営コストを押し上げていました。効率的なルートを計算し、車両や人員の稼働を最適化することで無駄な走行距離が減少し、燃料費が節約されます。
また、配送時間の短縮により車両の回転率が上がり、同じ台数でも多くの配送をこなせるようになります。これにより車両台数の削減や設備投資の抑制にもつながるのがポイントです。こうした多方面でのコスト削減効果は企業の利益率改善に寄与し、競争力を維持するために不可欠な施策です。
配送の正確さや迅速さは顧客満足度に直結しています。配送ルートの最適化により時間指定や配送先の条件を踏まえた効率的な配送が可能になり、約束した時間内での配達が実現しやすくなるでしょう。これにより、顧客の信頼を得てリピート率の向上が期待できます。
一方で、配送ミスや遅延は再配達を招きやすく、企業にとっては余分なコスト増につながります。最適化されたルートは再配達率の低減に寄与し、配送品質の均一化にもなるでしょう。さらに、顧客からの問い合わせ対応も減るため、サービス全体の効率が高まります。このように配送の精度向上は企業のブランド価値向上と直結し、長期的な顧客関係の構築に役立ちます。
環境問題への対応は、現代企業の重要な経営課題です。配送業務は車両の燃料消費に伴うCO₂排出量が多いため、ルートの最適化は環境負荷の低減に直接つながります。効率的な配送ルートは不要な走行を減らして燃料消費を抑制できるため、結果としてCO₂排出の削減が期待できます。
また、環境配慮を重視するESG経営の観点からも、配送ルートの最適化は重要な施策です。投資家や顧客からの評価向上に寄与し、企業の持続可能な成長に結びつきます。このように配送ルートの効率化は環境対策と企業価値向上を同時に進められる有効な手段です。
配送ルートの最適化を成功させるためには、段階的かつ体系的な手順が大切です。まずは現状の配送データを収集し、課題を明確にします。その上で、配送に関する条件や制約を整理し、最適化に適したアルゴリズムやツールを適用します。さらに実際の運用で効果を検証しながら改善を繰り返すことが欠かせません。
これらの手順を踏むことで精度の高いルート設計を実現し、持続的な業務改善につなげられます。
配送ルートの最適化は現状の正確な把握から始まります。配送先の住所や時間帯、配送頻度、車両の稼働状況など多様なデータを集めることが大切です。これらの情報は運送管理システムやGPSデータ、ドライバーの報告書などから収集できます。
集めたデータを単に蓄積するだけではなく、可視化することを意識しましょう。配送ルートの実際の走行経路や滞留時間、荷物の積み下ろし時間などをマップやグラフで示すと問題点や非効率部分が見えやすくなります。可視化により具体的な課題抽出が可能になり、改善策を検討しやすくなるのがポイントです。また、データの質や収集方法の見直しもこの段階で行い、次の工程へつなげる基盤作りを行います。
最適化アルゴリズムを効果的に活用するためには、配送条件や制約を正確に整理する必要があります。配送時間帯や配達優先順位、車両の積載量、ドライバーの勤務時間、荷物の取り扱い条件など多岐にわたる要素を洗い出します。
これらの条件を明文化し、ルールとしてシステムに入力できる形に整えましょう。例えば、午前中指定の荷物は午後の配送ルートに入れない、冷蔵品は専用車両で運ぶなどの具体的な制約が考えられます。配送先のアクセス状況や交通規制、渋滞傾向も考慮対象に含める必要があります。
条件が整ったら、配送ルートの最適化を実施します。ここで活用されるのがルート最適化アルゴリズムや専用のソフトウェアツールです。これらは複数の制約や条件を考慮しながら、配送車両の経路や順序を計算します。
最適化のアルゴリズムには、線形計画法やメタヒューリスティックス、遺伝的アルゴリズムなど様々な手法があるのでチェックしてみましょう。現場のニーズやデータの特性に合わせて適切な方法を選択し、カスタマイズを行うことが大切です。
これらのツールを活用すると、計算時間の短縮や運用しやすさの面でメリットがあります。導入時にはトライアル運用を通じて精度や使い勝手を検証し、現場への適応を進めていきましょう。
最適化された配送ルートは実際の運用で効果を検証し、課題があれば改善を重ねることが大切です。実運用から得られるデータを基に、計画とのズレや新たな問題点を抽出します。
例えば、交通状況の変動や突発的な配送先の変更、ドライバーの経験による運用上の工夫など、現場の実情は計算モデルだけでは把握しきれないことも多いです。こうした現場の声や実績を反映させて最適化パラメータの調整やルールの見直しを行い、より実態に即したルート設計を目指します。
この改善サイクルを定期的に回すことで、配送効率は持続的に向上します。こうした継続的な運用改善が、物流DX推進のカギです。

物流DX推進は配送ルートの最適化を実現する上で不可欠な要素です。業務の可視化やデータの活用を通じて現場の実態を正確に把握し、効率的な運用を設計する必要があります。さらに、最新のツール導入やドライバーとの連携を強化してリアルタイムデータと連動させることで、変化に対応できる柔軟な配送体制を築けます。
こうしたポイントを押さえることで、持続可能な改善サイクルを回しながら配送効率とサービス品質を高められるでしょう。
配送ルート最適化の第一歩は現状業務の正確な把握です。配送計画や実績、車両の稼働状況、ドライバーの行動パターンまで多角的にデータを収集し、業務全体を見える化します。
可視化にはITシステムやBIツールの活用が効果的です。マップ上に配送ルートや停車ポイントを表示したり時間帯別の配送量や遅延状況をグラフで示したりすることで、ボトルネックやムダな動きを明確に把握できます。
この段階では現場のヒアリングも必要です。ドライバーや配送担当者が感じている課題や改善案を取り入れ、実態に即した分析を進めましょう。正確な現状認識がなければ、最適化は机上の空論に終わる恐れがあります。データと現場の声を融合させた分析から次の施策を導き出しましょう。
現状分析の後はルート最適化ツールを導入し、業務プロセスに組み込むフェーズです。最新のツールは多様な制約条件を考慮しながら、最短経路や効率的な配送順序を提案します。
ツール選定時は自社の配送形態や車両構成、取引先の要望などに適合するかを慎重に判断しましょう。導入後は単にツールを使うだけでなく、業務フローに組み込む運用設計が大切です。管理者と現場が連携し、ツールの提案を現場で活用しやすい形に調整することが効果の向上に寄与します。
また、ツール活用による配送計画の自動化は業務負荷軽減にもつながり、人的ミスも減らせます。導入初期は試験運用やトレーニングを徹底し、現場の理解と協力を得ながら浸透させましょう。
配送環境は常に変化するため、リアルタイムデータとの連携は配送ルートの最適化に欠かせません。交通状況や天候情報、配送先の受け取り状況などを即座に反映できる体制が求められます。
リアルタイムデータの活用により渋滞や事故などの予期せぬ事態に対応し、配送ルートや時間帯の見直しが可能です。これにより遅延を防ぎ、サービス品質の維持に役立ちます。
IoTデバイスやモバイルアプリを使ってドライバーの位置情報を把握したり、配送完了報告を即時に受け取ったりする仕組みも必要です。こうした情報は配送管理システムと連動させることで、全体最適化のためのリアルタイムな判断を支えます。
最適な配送ルートは現場の協力なしには実現できません。ドライバーや配送を担当する従業員とのコミュニケーションを密にし、協調体制を築くことが重要です。
ルート変更や新しい業務手順に対する理解と納得を得るためには、説明会や現場研修を実施しましょう。また、現場の意見や改善提案を積極的に取り入れる姿勢が信頼関係を高めます。
さらに、ドライバーの負担や安全性に配慮した運用設計を心がけることで、現場のモチベーション維持につながります。協力的な環境を作ることで計画通りの運用が可能となり、最適化の効果を引き出せるでしょう。
配送ルートの最適化は一度導入して終わりではなく、継続的な評価と改善が必要です。KPIを設定し、配送時間・燃料消費・遅延発生率などの数値を定量的に評価しましょう。
データを基に効果測定し、目標に対する達成度を明確にします。問題が見つかれば原因を分析し、改善策を検討し実行します。このPDCAサイクルを回すことで、配送効率の向上を図ることがポイントです。
また、環境変化や新たな制約条件に対応できるよう、アルゴリズムや運用ルールの見直しも定期的に行いましょう。こうした改善活動が物流DX推進の成否を左右します。
物流DXの推進により、多くの企業が配送ルート最適化に取り組み始めています。配送業務の効率化やコスト削減、サービス品質の向上を目指して独自のシステム開発や最新技術の導入を進めている企業が出てきました。
ここでは、日本の代表的な物流企業の具体的な事例を紹介し、実際の取り組み内容や成果を解説します。これらの事例は、自社での物流DX推進を検討する上で貴重な参考材料となるでしょう。
佐川急便は膨大な出荷データを活用し、配送ルートを効率化する専用システムを開発しました。このシステムは出荷情報をリアルタイムで取り込み、車両ごとの配送先や荷物量に応じて最適なルートを自動生成します。
従来は経験や感覚に依存していた配送計画をデジタル化し、複数の条件を同時に考慮するアルゴリズムにより無駄な走行や待機時間を減らすことに成功しています。さらに、交通情報や天候データも連携させることで、変動要因にも柔軟に対応できるでしょう。
このシステム導入により配送効率が向上し、ドライバーの負担軽減や燃料費削減にもつながりました。また、配送時間の短縮が顧客満足度の改善にも寄与しています。佐川急便の取り組みは、実務データの活用とIT技術の融合による物流DXの好例といえるでしょう。
出典参照:ルート配送|佐川急便株式会社
ヤマト運輸は配送業務量の予測と配車計画の最適化を実現するため、先進的なシステムを導入しています。このシステムは過去の配送データや季節変動、キャンペーン情報など多様なデータを分析し、将来の業務量を高精度で予測します。
これに基づいて最適な車両台数や配車スケジュールを算出することで、過剰な人員配置や車両の不足を防止し、効率的な運用を実現しました。また、リアルタイムの配送状況を反映しながら配車計画を修正できる機能も備えています。
この仕組みの導入により業務負荷の平準化やドライバーの負担軽減が進み、サービスの安定提供に寄与しました。ヤマト運輸の事例は、データ分析に基づく戦略的な物流DX推進の重要性を示しています。
出典参照:ビッグデータ・AIを活用した配送業務量予測および適正配車のシステム導入について|ヤマト運輸株式会社
NIPPON EXPRESSホールディングスは物流配送の最適化を目的に、独自のシステムを導入しました。このシステムは配送先の地理情報や荷物の特性、車両の性能を詳細に考慮し、複雑な配送制約をクリアしつつ最適ルートを設計します。
特に多拠点間の連携や多品種小ロット配送に対応するため、配送計画の自動化と動的なルート再計算機能を持たせています。これにより配送の遅延や無駄な走行を抑えつつ、柔軟で効率的な物流網を構築しました。
導入後は配送時間の短縮、燃料消費の削減に加えて配送品質の向上も実現しています。NIPPON EXPRESSの取り組みは、多様な物流ニーズに応えるための高度な物流DXのモデルケースとして評価されています。
出典参照:NXグループ、シンガポールのAIテクノロジースタートアップ企業、SWAT MOBILITYへ出資|NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
配送ルート最適化は物流DXの重要な一環ですが、推進の際にはいくつか注意すべきポイントがあります。単にツールを導入すれば効果が得られるわけではありません。実務に応じた計画や現場の理解を得ることが不可欠です。効果的な推進を進めるためには、現場の声を反映させることや段階的に範囲を広げるなどの工夫も必要です。
ここでは、その中でも特に重要な注意点を詳しく解説します。
配送ルートの最適化は実際に現場で作業を行うドライバーや配車担当者の意見を無視できません。彼らは配送業務の細かい状況や制約をよく理解している人材でしょう。ツールやシステム導入前に現場の課題や要望をしっかり把握し、それを反映させることが成功のカギです。
また、現場からのフィードバックを定期的に収集し、最適化計画の改善に活かす仕組みも必要です。単なるトップダウンではなく現場の声を尊重することで抵抗感が減り、導入後の定着もスムーズに進みます。現場参加型の推進体制を整え、現場のノウハウを最大限活用しましょう。
物流DX推進では意気込みが大切ですが、あまりに範囲を広げすぎると管理が難しくなり、失敗リスクが高まります。まずは特定のエリアや一部の配送ルートに限定して最適化を試み、小さな成功を積み重ねることが望ましいです。
初期段階ではシンプルな条件で最適化を行い、運用の課題や効果を把握しましょう。十分な改善が確認できたら、徐々に対象範囲を広げていきます。段階的に推進することで、現場の混乱を防ぎつつ改善効果を着実に実感できます。急がず着実に計画をしていきましょう
配送ルート最適化に使うツールやシステムの選定では価格が判断材料になりますが、単に安価なものを選ぶのは危険です。機能やサポート体制、導入後の運用負荷なども総合的に評価しなければなりません。
安価なツールでは十分な機能が備わっていなかったり、現場の実態に合わなかったりするケースもあります。逆に高機能すぎて現場に負担がかかる場合もあるため、バランスが必要です。適切なツールを選ぶことで、導入後の運用効率や効果が大きく変わります。価格だけにとらわれず、将来を見据えた判断をしましょう。
配送ルート最適化を推進してツールを導入しても、定着しなければ効果は限定的です。新しい仕組みを現場に浸透させ、日常的に活用してもらうための支援が必要になります。
具体的には操作研修やマニュアルの整備、問い合わせ対応の体制づくりなどが挙げられます。定期的なフォローアップや改善提案の場を設けることも効果的です。これらの施策により現場が安心してツールを使いこなせる環境を整え、持続的な運用を実現しましょう。

物流DXを推進し配送ルート最適化に取り組むことは、企業の競争力強化に直結します。効率化やコスト削減だけでなく、顧客満足度の向上や環境負荷の軽減も期待できます。
成功させるためには、現場の声を活かしながら段階的に進めて適切なツールを選ぶことが大切です。また、導入後の定着支援を怠らず、継続的な改善を続ける姿勢も欠かせません。これらを踏まえ、記事の内容を参考に物流DXの一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。配送業務の革新が着実に実現できるはずです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
