物流DXで課題解決へ|2024年問題と人手不足に立ち向かうための実践ガイド
物流

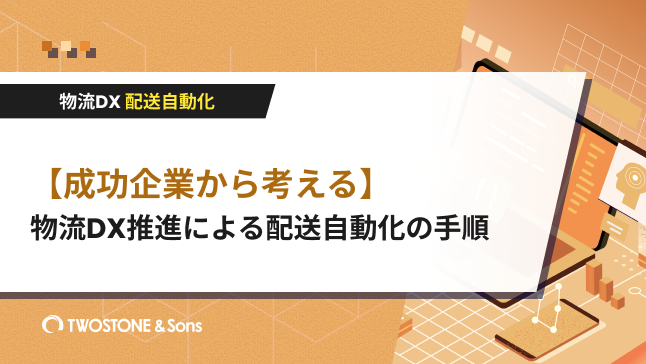
物流業界では人手不足や配送需要の急激な変化により、従来の手作業に依存した配送システムでは対応が困難になってきています。特に労働力確保の難しさや繁忙期の処理能力不足や、配送に関する課題は多くの企業が直面する深刻なものです。
これらの課題を解決する有効な手段が、物流DXの推進による配送自動化です。自動化技術の活用によって人的リソースへの依存を減らし、効率的で持続可能な物流体制を築けます。
この記事で解説するのは物流DX推進によって配送自動化を実現する、具体的な方法についてです。自動化導入のポイントから実際の手順、活用できるツール、成功事例まで幅広く紹介し、あなたの企業での配送自動化の効果的な進行をサポートします。

物流業界における配送自動化とは従来人間が行っていた配送関連業務を、ITシステムやロボット技術を活用して自動化する取り組みです。この自動化は倉庫内での荷物の仕分けや搬送から配送ルートの最適化、配達スケジュールの調整まで物流プロセス全体にわたって適用されます。
配送自動化の範囲は広く倉庫内作業の自動化や配車システムの自動化、在庫管理の自動化など多岐にわたります。これらの自動化によって人的ミスの削減や作業効率の向上、コスト削減などの効果が期待できるでしょう。また24時間体制での稼働が可能となり、繁忙期でも安定した配送サービスを提供できるようになります。
物流DX推進が配送自動化を実現する理由は、デジタル技術の活用により従来の手作業中心の業務プロセスを根本的に変革できるためです。AIやIoT、ロボティクス技術の進歩によって複雑な判断や作業の自動化が可能になりました。
さらにデータ分析技術の発達により、配送パターンの予測や最適化も高精度で行えるようになりました。これによって効率的な配送ルートの自動決定や需要予測に基づき、在庫配置の最適化が実現できるでしょう。
物流業界では荷物の仕分けや梱包、ラベル貼付など多くの単純作業が発生しています。これらの作業を人間が行う場合は長時間の集中力が必要で、疲労による作業効率の低下や人的ミスが発生しやすくなりやすいです。
配送自動化により、これらの単純作業をロボットやシステムで代替可能です。例えば自動仕分けシステムを導入すれば荷物の行き先に応じて自動的に振り分けを行い、人間の作業員は監視や例外処理に集中できます。
また自動梱包システムの活用により、商品サイズに応じた最適な梱包材の選択から梱包作業まで、一連の流れを自動化できます。これによって従来必要だった作業員の数を削減し、人件費の削減と作業精度の向上を同時に実現できるでしょう。
物流業界では季節要因やイベント、セール期間などによって配送需要が変動します。従来の人間中心の配送システムでは繁忙期に十分な人員の確保が困難で、配送遅延や品質低下の原因となっていました。
配送自動化により、需要の変動に柔軟に対応できるシステムを構築できます。自動化されたシステムは24時間体制での稼働が可能で、繁忙期でも処理能力を維持できます。また複数台の自動化機器を連携させることで需要に応じて稼働台数を調整し、効率的な配送体制を維持できるでしょう。
さらに閑散期には自動化システムの稼働を最小限に抑えることで、無駄なコストの発生を防げます。この柔軟性によって年間を通じ、安定した配送サービスを提供しながらコスト最適化の実現にもつながります。
物流業界では長時間労働や体力的負担の大きさから、ドライバー不足が深刻な問題となっています。特に配送件数の増加に対してドライバーの確保が追いつかず、配送サービスの維持が困難になっている企業も多く存在します。
配送自動化により、ドライバーに依存しない配送システムを構築可能です。自動配送ロボットや無人配送車両の活用により、人手を介さずに配送することが可能になります。また配送ルート最適化システムの導入により、1人のドライバーがより多くの配送を効率的に行えるようになります。
さらに倉庫内作業の自動化によってドライバーが荷物の積み込みや仕分けに割く時間を削減し、配送業務により多くの時間を割けるようになります。これにより、限られたドライバーリソースを最大限活用できる配送体制を構築可能です。
物流DX推進において配送自動化を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。適切な業務選定や技術的な整合性の確認、段階的な導入計画の策定など戦略的なアプローチが求められます。
これらのポイントを事前に検討して計画的に進めることで、配送自動化の効果を最大化しながらリスクを抑制できるでしょう。ここでは具体的なポイントについて、詳しく説明していきます。
配送自動化を効果的に進めるためには、自動化に適した業務の正確な選定が必要です。すべての業務を一度に自動化するのではなく、費用対効果の高い業務から段階的に自動化を進めることが成功のカギとなります。
自動化対象業務の選定ではまず現在の業務プロセスを詳細に分析し、どの業務が自動化に適しているかを判断します。一般的に定型的で繰り返し作業が多い業務や人的ミスが発生しやすい業務、労働集約的な業務などが自動化に適しているでしょう。
また、自動化による効果の定量的な評価も大切です。人件費削減や作業時間短縮、品質向上などの効果を数値化し、投資回収期間や収益性を検証します。さらに自動化の難易度や技術的実現可能性も考慮し、短期間で成果を出せる業務からの着手によって社内での自動化推進に対する理解と支持を得られることでしょう。
配送自動化を導入する際には、既存のインフラ設備や関連する法制度との整合性を十分に確認する必要があります。自動化システムが既存の物流インフラと適切に連携できるかどうかが、プロジェクトの成否を左右します。
インフラ面では倉庫の構造や搬送システム、ITネットワーク環境などが自動化システムの要求仕様を満たしているかを確認しましょう。必要に応じて床の補強や電源設備の増設、通信環境の整備などのインフラ改修を計画に組み込みます。
法制度面では自動配送車両の公道走行に関する規制、労働安全衛生法に基づく自動化設備の安全基準、個人情報保護法に関わるデータ取り扱いなどさまざまな法的要件を確認します。特に自動配送ロボットや無人車両を使用する場合、道路交通法や関連する規制の最新動向の把握、及びコンプライアンスの確保が必要です。
配送自動化の導入時には、本格的な運用の前に十分なテスト運用を行い、リスクを段階的に軽減していくことが大切です。いきなり大規模な自動化を行うのではなく、小規模なテストから始めて徐々に範囲を拡大していくアプローチが効果的といえます。
テスト運用では、まず限定的な条件下での動作確認を行います。例えば特定の商品カテゴリーのみを対象とした自動仕分けシステムのテスト、決められたルートでの自動配送車両のテストなどです。この段階でシステムの動作精度や処理速度、エラー発生率などを詳細に測定し、問題点を洗い出します。
リスク対策ではシステム停止時の代替手段の確保や異常発生時の緊急対応手順の策定、データバックアップとセキュリティ対策の実施などを行います。また従業員への教育訓練も重要な要素です。自動化システムの操作方法や異常時の対応、メンテナンス方法などを関係者全員が適切に理解できるよう計画的に研修を実施しましょう。
配送自動化を成功させるためには、新しい自動化技術が既存のシステムとスムーズに連携できることが大切です。単独で動作する自動化システムでは、物流プロセス全体の効率化を実現できません。
システム連携ではまず現在使用している倉庫管理システム(WMS)や輸送管理システム(TMS)、企業資源計画システム(ERP)などとの接続性を確認します。データフォーマットの統一や通信プロトコルの適合性、リアルタイム連携の可否などを詳細に検証します。
またAPIの活用により、異なるシステム間でのデータ連携が実現可能です。在庫情報や配送状況、顧客情報などのデータを自動化システムが適切に取得・更新できるよう、データ連携の仕組みを構築します。
配送自動化を効果的に進めるためには、体系的な手順に沿って進めることが大切です。現状分析から始まりパートナー選定や戦略策定、実証実験までの段階的なアプローチによって成功確率を高められるでしょう。
ここでは、物流DXを推進する中でどのように配送自動化を進めるのかを解説します。紹介する4つの手順を順番に実行すればリスクを最小限に抑えつつ、配送自動化を着実に進められるでしょう。各手順での重要なポイントについて詳しく説明していきます。
配送自動化を進める最初のステップは現在の物流プロセスの詳細な分析、及び改善すべき課題の明確化です。この分析により、自動化の方向性と優先順位を決定可能です。
現状分析では、配送に関わるすべての業務プロセスを可視化します。荷物の入荷から出荷までにどのような作業が発生し、どの程度の時間と人員が必要かを定量的に把握します。また繁忙期と閑散期の業務量の違い、エラー発生頻度や顧客満足度なども測定対象です。
課題抽出では現状分析の結果から、効率化すべき業務や改善すべき問題点を特定します。例えば仕分け作業での人的ミスや配送ルートの非効率性、繁忙期の処理能力不足などが課題として挙げられるでしょう。
これらの課題を重要度と緊急度で分類し、自動化による解決効果を評価します。投資対効果の高い課題から優先的に取り組むことで、限られたリソースを効率的に活用できます。
配送自動化を成功させるためには、適切な専門パートナーの選定が大切です。自動化技術は高度で専門性が高いため、経験豊富なパートナーとの連携が不可欠です。
パートナー選定では、まず候補企業の技術力と実績を評価します。類似業界での導入実績や提供可能な技術ソリューション、サポート体制などを詳細に確認します。また、企業の安定性や継続性も重要な評価要素です。
技術的な適合性も重要な判断基準です。自社の既存システムとの連携性や必要な機能の実現可能性、将来的な拡張性などを技術的観点から評価します。複数の候補企業に対して概念実証(PoC)の実施を依頼し、実際の動作確認を行うことも有効です。
さらに、プロジェクト管理能力やコミュニケーション能力も評価します。複雑な自動化プロジェクトを円滑に進めるためには明確なプロジェクト管理手法と、密に連携できるパートナーが必要です。
配送自動化の成功には、明確な戦略と段階的な推進計画の策定が不可欠です。全体的な方向性を定めながら、リスクを管理しつつ着実に進める計画を立てることが重要といえます。
戦略策定では、まず自動化の目標を明確に定義しましょう。コスト削減や効率向上、品質改善など具体的な数値目標を設定し、達成時期を明確にします。また自動化する業務範囲と優先順位を決定し、投資予算と期待効果を整理します。
段階的推進計画ではプロジェクトを複数のフェーズに分割し、各フェーズでの成果物と評価基準を設定しましょう。第1フェーズでは小規模なテスト導入を行い、問題点を洗い出します。第2フェーズでは対象範囲を拡大し、第3フェーズで本格運用を開始する形です。
各フェーズでは技術的リスクや運用リスク、財務リスクなどを評価し、リスク軽減策を準備しましょう。
配送自動化を着実に進めるためには実証実験と効果検証を繰り返しながら、段階的に改善していくアプローチが必要です。理論的な計画だけでなく、実際の運用を通じて検証を行うことで問題点を早期に発見し、適切な対策を講じられます。
実証実験では、限定的な条件下で自動化システムの動作確認を行います。例えば特定の商品カテゴリーのみを対象とした、自動仕分けシステムのテストや決められた配送ルートでの自動配送車両のテストなどです。この段階でシステムの動作精度や処理速度、エラー発生率などを詳細に測定しましょう。
効果検証では実証実験の結果を定量的に評価し、当初の目標と比較します。作業時間の短縮や人件費の削減、品質向上などの効果を数値化して投資対効果を検証します。また予期しない問題や課題も洗い出し、次の改善サイクルに活かしましょう。

配送自動化を実現するためには、多様な技術ツールの効果的な活用が不可欠です。多くの企業が最新の自動化技術を開発し、実用的で信頼性の高いソリューションを提供しています。
これらのツールの適切な選択、組み合わせでの導入を行うことによって配送自動化につなげられ、配送業務の効率化やコスト削減を実現できるでしょう。ここでは、配送自動化に特に役立つ代表的なツールについて詳しく紹介します。
搬送ロボットは倉庫内での荷物の自動搬送を実現する、重要なツールです。AGV(Automated Guided Vehicle)とAMR(Autonomous Mobile Robot)の2つのタイプがあり、それぞれ異なる特徴をもっています。
AGVは床面に設置された磁気テープや光学マーカーなどの、誘導システムに従って走行する自動搬送車両です。決められたルートを正確に移動可能で、重量物の搬送にも対応できます。一方でAMRはセンサーやカメラを使用して周囲環境を認識し、自律的に経路を決定して移動するロボットです。
これらの搬送ロボットの導入により、従来人間が行っていた荷物の運搬作業を自動化できます。特に重量物の搬送や長距離の移動が必要な作業では、効率改善が期待できます。
出典参照:搬送ロボット(AGV・AMR)|東朋テクノロジー株式会社
Loogia配車作成は配送ルートの最適化と配車計画の自動作成を実現する、クラウドベースのシステムです。複雑な配送条件を考慮しながら、最適な配車計画を短時間で算出できます。
このシステムでは配送先の住所や荷物の容量・重量、配送時間指定、車両の積載容量、ドライバーの労働時間制限などの条件入力によって最適な配車計画を自動的に作成します。AIアルゴリズムの活用により、従来の手作業では困難な複雑な最適化問題の解決が可能です。
また、リアルタイムでの配車計画の調整にも対応しています。急な配送依頼や交通状況の変化に応じて配車計画を動的に修正し、効率的な配送を維持できます。
ULTRAFIXシリーズはリアルタイムの交通情報を活用した、高度な配送最適化システムです。渋滞情報や道路工事情報、天候条件などの外部要因を考慮して最適な配送ルートと配車計画を提示できます。
このシステムの特徴は静的な地図情報だけでなく、動的な交通状況を反映した配送計画を作成可能なことです。GPS情報や交通情報システムと連携し、現在の道路状況をリアルタイムで把握して最適なルートを算出します。
また配送車両の現在位置と配送予定をリアルタイムで監視し、遅延が発生した場合には自動的に配車計画を調整します。これによって配送遅延の影響を最小限に抑え、顧客満足度の維持につながるでしょう。
出典参照:ULTRAFIXシリーズ|NECソリューションイノベータ株式会社
多くの企業が配送の自動化に積極的に取り組み、実際に顕著な成果を上げています。これらの成功事例を参考に、自社に適した配送自動化の推進方法や課題解決のヒントを得られるでしょう。
ここで紹介する企業はそれぞれ異なる技術や戦略を用いて配送自動化を実現し、業務の効率化や品質の向上に成功しています。これらの事例からは具体的な効果や導入のポイントが明確に理解でき、今後の物流改革に役立つ知見を得られるでしょう。
SGホールディングス株式会社は自動仕分けロボット「t-Sort」の導入により、配送センターでの作業効率化と作業員の負担軽減を実現しました。このシステムは、荷物の自動仕分け作業を高精度で実行できます。
t-Sortは荷物に貼付されたバーコードやQRコードを読み取り、配送先に応じて自動的に仕分けを行います。従来の手作業による仕分けと比較して処理速度が向上し、人的ミスも削減されました。
このシステムの導入によって同社では仕分け作業の処理能力が約30%向上し、作業時間の短縮も実現しました。さらに24時間体制での稼働が可能となり、繁忙期でも安定した配送サービスを提供できるようになりました。現在では複数の配送センターにt-Sortを展開し、全社的な配送効率化を進めています。
出典参照:仕分け業務のDXにより、東松山SRCの大幅な生産性向上を実現|SGホールディングス株式会社
ヤマトホールディングス株式会社はEC配送に特化したサービス「EAZY」を開発し、集配効率化を実現しました。このサービスはEC事業者の配送ニーズに特化した、自動化システムを提供しています。
EAZYではEC事業者の出荷データを自動的に取り込み、最適な配送ルートと配車計画を算出します。また荷物の自動仕分けシステムと連携し、配送先に応じた効率的な集配を実現しました。
特に注目すべきは、AIを活用した配送時間の予測機能です。過去の配送データと現在の交通状況を分析し、配送時間を高精度で予測できます。これによって顧客への配送時間の通知がより正確になり、再配達率の削減にも貢献しています。
出典参照:EC向け新配送商品「EAZY」の提供を開始|ヤマトホールディングス株式会社
日本通運株式会社は作業ロボットとRPAを積極的に導入し、労働時間削減を実現しました。同社では、物流センターでの作業自動化と事務処理の自動化を同時に進めています。
物流センターではピッキング作業を支援するロボットを導入し、作業員の移動時間を削減しました。また重量物の搬送作業の自動化によって作業員の身体的負担を軽減し、作業効率を向上させました。
事務処理ではRPAを活用した配送伝票の作成や顧客への配送通知、請求書の処理などを自動化しました。これによって実現したのが事務作業に要する時間の短縮、人的ミスの削減です。
また在庫管理システムとの連携により、リアルタイムでの在庫状況の把握と最適な在庫配置を実現しています。需要予測機能も活用し、効率的な在庫管理を行っています。これらの取り組みにより、同社では年間72万時間の労働時間削減を達成しました。
出典参照:日通、RPA導入の推進で労働時間を72万時間削減|日本通運株式会社

物流DX推進による配送自動化は、人手不足や配送需要の増加といった課題を解決する有効な手段です。単純作業の自動化から配送ルートの最適化まで、さまざまな分野での自動化技術の活用によって効率的で持続可能な物流体制を構築できます。
成功のポイントは現状分析に基づいた適切な業務選定や専門パートナーとの連携、段階的な導入計画の実行です。実証実験を繰り返しながら着実に進めることで、リスクを最小限に抑えながら効果を最大化できるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
