物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

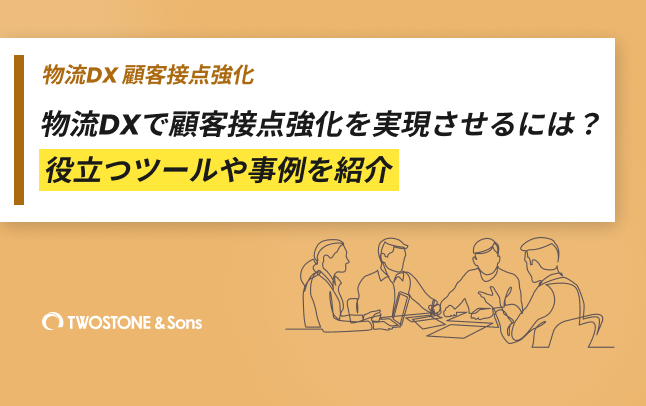
物流業界では配送業務が中心となるため、顧客との接点が限定的になりがちです。荷主企業や最終消費者との直接的なコミュニケーションが不足し、顧客満足度の向上やリピート率の改善に課題を抱えている企業も多いでしょう。
しかし物流DXの推進により、これらの課題を解決できる可能性があります。デジタル技術の活用によってリアルタイムな情報共有や双方向のコミュニケーションが実現し、顧客との関係性を深められます。
この記事では物流業界における顧客接点不足の原因を分析し、DXによる解決策と具体的なアプローチを詳しく解説します。記事を読むことで自社の顧客接点強化に向けた具体的な施策と、導入すべきデジタルツールの選定方法が明確になるでしょう。

物流業界では顧客接点の不足が深刻な課題となっています。配送業務を中心とした業態構造により、荷主企業や最終消費者との直接的なコミュニケーション機会が限定的です。
さらに従来のアナログな情報伝達手法により、リアルタイムでの対応が困難になってきています。また顧客情報のデータ化が不十分なため、個別のニーズを把握して適切な対応を行うのが難しいという問題もあります。
これらの要因が重なることで、顧客満足度向上やリピート率の改善に支障をきたしている可能性を考慮すべきでしょう。
物流業界では配送業務が事業の核となるため、顧客との接点が必然的に限定的になります。トラックドライバーや配送員が荷物を届ける瞬間が主要な接触機会となりますが、この短時間では深いコミュニケーションを図るのは困難です。
また荷主企業との関係においても出荷指示や配送完了報告といった業務的なやり取りが中心となり、戦略的な提案や改善案の共有といった付加価値の高いコミュニケーションが不足しがちです。
さらにBtoC配送では不在配達によって顧客との直接的な接触機会が減少し、顧客の声を直接聞く機会が限られています。この構造的な問題によって顧客のニーズや不満の適切な把握が難しく、サービス改善のための重要な情報を収集できない状況が続いています。
従来の物流業界では電話やファックス、紙ベースの伝票を使用した情報伝達が主流でした。これらのアナログな手法では配送状況の確認や問い合わせ対応に時間がかかり、顧客が求めるリアルタイムな情報提供を行いにくくなってしまいます。
例えば配送遅延が発生した場合でも顧客への連絡が配送完了予定時刻を過ぎてから行われるケースが多く、顧客の不安や不満を招きかねません。また営業時間外の問い合わせには対応できず、顧客の利便性を損なう要因となっています。
さらに情報の共有が部門間で円滑に行われず、顧客からの要望や変更依頼が適切に処理されない場合もあるでしょう。このような情報伝達の遅れや不備により、顧客満足度の低下や信頼関係の悪化を招く結果となっています。
物流業界では顧客情報のデータ化が他の業界と比較して遅れており、顧客のニーズを正確に把握しにくい状況が続いています。配送履歴や問い合わせ内容、クレーム情報などが紙ベースで管理されているケースが多く、データとして蓄積・分析されていません。
このため顧客の配送パターンや要望を体系的に把握できず、個別最適化されたサービス提供が実現できていません。
さらに複数の拠点や部門で分散管理されている顧客情報を統合し、活用する体制も整っておらず総合的な顧客対応の質の向上が難しい状況です。結果として顧客一人ひとりに最適化されたサービスを提供できず、競合他社との差別化が図れない状況が続いています。
物流DXの推進により、顧客接点の強化が実現できる理由は明確です。デジタル技術の活用によってリアルタイムな情報共有が可能になり、顧客の不安を解消できます。
またデジタル接点の整備により、従来の一方向的な情報提供から双方向のコミュニケーションへと進化します。さらに蓄積された顧客データの活用により、一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた対応が実現できるでしょう。
これらの変化により、顧客満足度の向上と長期的な関係構築が期待できます。
物流DXの推進により、配送状況をリアルタイムで顧客に提供できるようになります。GPS機能を搭載した配送車両の位置情報と連動したトラッキングシステムにより、顧客は荷物の現在地や到着予定時刻を正確に把握できます。これによって荷物がいつ届くかわからない不安を解消し、顧客の待ち時間のストレスを軽減できるでしょう。
また配送遅延が発生した場合でも自動的に顧客へ通知が送られ、新しい配送予定時刻を即座に共有できます。さらに天候や交通状況による配送への影響も事前に予測し、顧客に適切なタイミングでの情報提供が可能です。
このような透明性の高い情報共有によって顧客は配送プロセスを理解し、信頼感をもって物流サービスを利用できます。結果として顧客満足度の向上と、長期的な取引関係の構築につながることでしょう。
従来の物流業界では一方向的な情報提供が主流でしたが、デジタル接点の整備により双方向のコミュニケーションが実現します。顧客専用のWebポータルやモバイルアプリを通じ、顧客は配送希望日時の変更や特別な配送要求を簡単に伝達可能です。
デジタル接点により、顧客は自分の都合に合わせて物流事業者とコミュニケーションが取れて利便性が向上します。物流事業者側も顧客の要望や不満を直接把握できるため、サービス品質の向上や新サービスの開発に活用可能です。このような双方向のコミュニケーションによって顧客との関係性が深まり、競合他社との差別化を図れます。
物流DXの推進により蓄積された顧客データの活用により、一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた対応が可能です。過去の配送履歴や配送時間の希望、不在パターンなどの分析によって顧客の行動パターンを把握し、最適な配送プランを提案できます。
例えば平日の夕方に不在が多い顧客には土日配送の優先的な案内、定期配送の顧客には配送間隔の最適化に向けた提案、といったことがその一例です。
さらに、顧客の満足度データと配送実績を組み合わせることでサービス品質の向上ポイントを特定し、継続的な改善を図れるでしょう。このようなデータドリブンなアプローチによって顧客一人ひとりに最適化されたサービスを提供し、顧客満足度の向上と長期的な関係構築を実現できます。

顧客接点強化に向けた物流DXの推進には、段階的なアプローチが効果的です。
これらのアプローチの段階的な実施により、効果的な顧客接点の強化が実現できます。
トラッキング機能の強化は、顧客接点強化における基本的かつ重要なアプローチです。GPS機能を搭載した配送車両と連動したシステムにより、荷物の現在地や配送進捗をリアルタイムで顧客に提供できます。これによって顧客は荷物の到着予定時刻を正確に把握し、配送に関する不安を解消できるでしょう。
また配送遅延や交通状況による影響の事前予測を基にした、自動的な顧客への通知によってプロアクティブな情報提供が可能になります。さらに配送完了時の写真撮影機能や電子サインの取得により、配送証明の透明性も向上します。
結果として顧客満足度の向上と、物流事業者への信頼度アップが期待できるでしょう。
カスタマーポータルやモバイルアプリの構築により、顧客との接点を増やすことが可能です。これらのデジタル接点を通じ、顧客は配送希望日時の変更や特別な配送要求を簡単に伝えられるようになります。また過去の配送履歴や請求情報の確認も可能になり、顧客の利便性が向上します。
さらにプッシュ通知機能により、配送状況の更新や重要な情報を即座に顧客に伝達可能です。配送完了後のフィードバック機能の整備によって顧客の声を直接収集し、サービス改善に活用できるでしょう。
これらのデジタル接点によって顧客は自分の都合に合わせた物流事業者とコミュニケーションができ、従来の電話やメールよりも効率的な情報交換が実現します。
チャットボットやAIオペレーターの導入で、24時間365日の顧客対応が可能になります。よくある質問に対する自動応答機能により、顧客は営業時間外でも配送状況の確認や基本的な問い合わせが可能です。これによる顧客の利便性向上が、満足度向上につながります。
またAIオペレーターは過去の対応履歴や顧客情報を瞬時に参照できるため、一貫性のある対応を提供可能です。複雑な問い合わせについては適切なタイミングで人間のオペレーターにエスカレーションする機能も整備し、効率的な顧客対応を実現します。
データ連携を通じた営業活動とマーケティング施策の統合は、現代の営業戦略において重要です。例えばCRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)とMA(マーケティングオートメーション)の連携によって顧客の行動履歴や興味関心、購買履歴などの情報を一元化できます。
このような連携によって営業担当者は見込み顧客の関心度や購買意欲を可視化し、最適なタイミングでアプローチが可能です。
部門間の情報共有と連携が進むことでリードナーチャリングやクロージングの精度が向上し、結果的に売上の最大化につながります。
物流業界における競争力の維持と顧客満足度の向上には従来の業務効率化に加え、顧客接点の質を高めることが重要となっています。配送の迅速さや正確さに加えてリアルタイムでの情報共有や柔軟な対応力が求められる中、デジタルツールを活用した仕組みづくりが注目されています。
ここで解説するのは物流業界での顧客接点強化のために活用されている、代表的なデジタルツールについての具体的な特徴と導入効果です。
LIFTIは物流現場における受発注・配車業務をクラウド上において一元管理できるサービスで、物流ネットワーク全体の可視性を高めたい企業に適しています。従来FAXや電話によって行われていた業務をデジタル化し、情報の行き違いや二重対応といった非効率を削減できます。
さらにドライバーや取引先とリアルタイムでの情報共有が可能になり、各ステークホルダーが常に最新の状況を把握可能です。これによって配送の進捗やトラブル発生時の初動対応がスムーズになり、顧客への説明も迅速かつ的確になります。
物流ネットワークにおける情報の透明性向上によって顧客からの信頼を得やすくなり、安定的な取引関係の構築につながります。
出典参照:LIFTI|株式会社Univearth
kintoneはサイボウズが提供する業務アプリ作成プラットフォームで、物流業界における多様なニーズに対応できる拡張性が特徴です。顧客からの問い合わせ管理やクレーム対応、配車手配などの業務フローを自社の実情に合わせて自由に設計できるため、業務の属人化を防ぎながら情報共有の効率を高められるでしょう。
また各業務の進捗や担当者の対応履歴が可視化されることでチーム内の連携がスムーズになり、応答スピードの向上にもつながります。さらに他システムとのAPI連携によってCRMや在庫管理ツールなどとも連動可能なため、顧客対応を含む全体最適な運用が期待できます。
現場に合わせた柔軟なカスタマイズ性を持つkintoneは、現場主導でのデジタル化を推進する上で有効な選択肢です。
出典参照:Kintone|サイボウズ株式会社
Salesforceは世界的に広く利用されているクラウド型CRMプラットフォームで、物流業界においても顧客接点の最適化を図るために活用されています。顧客情報や過去の取引履歴の一元管理によって個別対応精度が向上し、パーソナライズされたコミュニケーションにつながるかもしれません。
また問い合わせ受付から対応完了までの一連のプロセスを自動化し、対応漏れや重複対応のリスクを低減できます。さらに配送ステータスの通知を自動配信する機能により、顧客は自ら情報を確認する手間が省け、安心して配送を待てるでしょう。
これらの取り組みは単なる業務効率化にとどまらず、顧客体験そのものの質を向上させてリピート率の改善にも直結します。
出典参照:Salesforce|株式会社セールスフォース・ジャパン
Cognigyはチャットボットを中心としたAI対話プラットフォームで、音声・テキストの両方に対応したマルチチャネルコミュニケーションを実現します。物流業界では配送状況の確認や再配達の依頼、集荷の手配など日常的に繰り返される顧客からの問い合わせ対応に多くの時間を要するケースも珍しくありません。
Cognigyの導入によってこうした定型的なやり取りを24時間自動化でき、人的リソースを削減しつつ顧客満足度の維持につながります。また顧客の入力内容に応じてパーソナライズされた情報提供が行えるため、対応の質が均一化されてブランドイメージの向上にも寄与します。
音声通話やLINE、Webチャットなど複数の接点を一元管理できることも、業務効率化と顧客体験の両立を実現する上での利点といえるでしょう。
出典参照:Cognigy|TDSE株式会社
物流業界では、顧客体験の向上が競争力を左右する重要な要素となっています。特に近年は受け取り方法の多様化や配送状況の可視化など、顧客接点を強化する施策が求められています。こうした中で物流DXの推進は企業のサービス品質を支える、中核的な手段です。実際に、顧客接点強化を図る企業も出てきました。
ここでは実際に物流DXを通じ、顧客接点を強化している代表的な企業の取り組みを紹介します。
ヤマトホールディングス株式会社は顧客の利便性を向上させる取り組みとして、EC配送に特化したサービス「EAZY」を展開しています。「EAZY」は非対面での荷物受け取りや置き配、宅配ボックス、コンビニ受け取りなど生活スタイルに応じた柔軟な選択肢を提供するサービスです。特にEC市場の拡大に伴い再配達問題が顕在化している中、「EAZY」はその解決策として注目されています。
このサービスの特徴は配送員と受取人が直接会うことなく荷物を受け取れる、非対面対応の設計です。さらにスマートフォンから配送状況をリアルタイムで確認でき、置き配の完了通知も即座に届くため顧客の安心感にもつながっています。こうした機能によって従来の宅配サービスでは得られなかった柔軟性とスピード感を実現し、顧客接点の質が向上しました。
出典参照:EAZY|ヤマトホールディングス株式会社
日本通運株式会社では物流業務における出荷作業の効率化と精度向上を目的に、「S-プリンター」という送り状作成システムを導入しています。このツールは送り状発行のデジタル化によって記載ミスや記入漏れを防ぎ、作業時間の短縮に貢献しています。
「S-プリンター」の特徴は送り状の項目を出荷元の業務内容に応じ、自由にカスタマイズできる点です。これによって異なる出荷形態や取引先に応じた書式を自動で生成でき、従業員の作業負荷も軽減されます。結果として、顧客からの出荷依頼に対してスピーディーかつ正確な対応が可能となり、信頼性の高いサービス提供が実現されています。
この取り組みによって企業と顧客間のコミュニケーションが円滑になり、物流における接点が以前よりもスムーズに保たれるようになりました。
出典参照:カスタマイズ可能な送り状発行システム(S-Printer)|日本通運株式会社
佐川急便株式会社は配送業務の品質向上と顧客満足度の向上を目指し、「スマートクラブ」というWebサービスを通じて配送状況のリアルタイム可視化を進行中です。これによって荷物の現在位置や到着予定時間を、スマートフォンやPCから即時に確認可能になりました。
顧客は荷物の所在を把握しながら受け取りの準備ができるため、受け取りミスや不在による再配達が減少しています。再配達の手間が削減されることは配送業務全体の効率化にもつながり、ドライバーの負担軽減やCO₂排出量の低減といった副次的効果も生まれています。
さらに顧客からの問い合わせも配送状況の共有により減少傾向にあり、カスタマーサポートのリソースをほかの対応に回すことが可能となりました。これらの成果が、企業と顧客の接点の質を継続的に高める基盤となっています。
出典参照:【佐川急便】独自サービス“スマートクラブ®”による再配達削減の取り組み|佐川急便株式会社
国際輸送においては配送距離の長さや複雑な手続きが伴うことから、顧客との情報共有が欠かせません。日本通運株式会社では海外貨物の輸送状況を可視化するため、専用の追跡アプリを提供しています。このアプリによって通関や積み替えといった各工程の進捗を、リアルタイムで確認できるようになりました。
特にBtoB輸送においては納期遵守が取引継続に直結するため、正確なステータス管理が求められます。アプリはそのニーズに応える形で通知機能やレポート出力、トラブル発生時の即時対応連絡といった機能を搭載しています。
こうしたアプリを通じた透明性の高い物流体験が顧客の不安を軽減し、信頼感の醸成につながりました。さらに企業側も顧客ごとの輸送ニーズをデータで把握しやすくなるため、継続的なサービス改善にもつなげやすい仕組みとなっています。
出典参照:日本通運の事業領域|日本通運株式会社

物流DXの推進は単なる業務効率化にとどまらず、顧客との接点を豊かにして信頼関係を築く基盤となります。ヤマトホールディングスの「EAZY」や日本通運の送り状システム・追跡アプリ、佐川急便のリアルタイム追跡サービスなど各社はデジタルの力を活用して顧客体験の質を高めています。
本記事で紹介した内容は物流業務の中にどのように顧客志向を取り入れ、ツールやシステムによってその実現を後押ししているかを示す事例です。自社の状況に合わせた施策のヒントとして参考にしながら段階的な改善を進めていくことで、顧客との関係性をより強固なものにしていきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
