物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

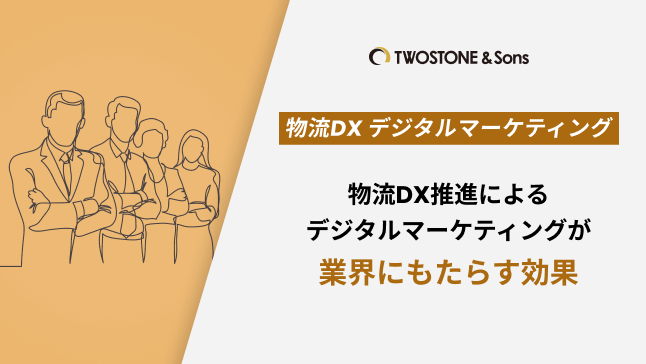
物流業界は今やモノを運ぶだけの存在ではなく、消費者との関係構築やブランド価値向上を担う重要なプレイヤーとなっています。EC市場の拡大によって消費者の期待はこれまで以上に高まり、スピードや正確性だけでなく柔軟な対応力やユーザー体験そのものが問われるようになっています。
このような環境変化の中で注目されているのが、物流DXの推進による業務効率の改善とマーケティング機能の強化です。物流データとデジタル技術を組み合わせることで、企業は新たな顧客接点を創出して継続的な関係性の構築が可能になります。
特に物流業務にマーケティング視点を組み込むことで、企業は単なる配送サービス業から顧客価値を創出するブランドへと進化できるでしょう。
本記事で解説するのは物流業界におけるデジタルマーケティングの実践的なアプローチと、その具体的な効果についての内容です。

物流業界におけるデジタルマーケティングとは単に広告を出すだけではなく、顧客の行動データを活用して価値のある体験を提供する仕組みを指します。
配送履歴や再配達の有無、購入傾向といった膨大な情報を分析してパーソナライズされた広告やメッセージの配信により、高精度なマーケティング施策の実現が期待できます。またSNSやコンテンツマーケティングによってブランドの透明性や信頼性を高められるでしょう。
こうした取り組みによって物流は単なる業務プロセスではなく、顧客満足を創出するマーケティング資産として機能します。
EC市場の成長により物流に求められる役割は変化しているのが現状です。消費者は商品の注文から受け取りまでの一連のプロセスを1つの体験として捉え、その質を重視しています。
そのため企業は単に荷物を届けるだけでなく、安心感や満足感を提供する体験設計が求められます。例えば配送状況のリアルタイム通知や柔軟な再配達オプション、簡易な返品フローなどは顧客の不安を軽減し、信頼感を醸成する上で有効です。
また注文後に届く確認メールの文面や荷物追跡ページの使いやすさなど、細部のUX設計も体験価値を左右します。
こうした仕組みを整えるには、業務フローとデジタル技術の緻密な連携が必要です。体験設計に対する戦略的な視点が、顧客満足のカギとなります。
物流業務の中で日々蓄積されるデータは、マーケティングにとって有益な資源です。配送先のエリア情報や受取時間の傾向、購入サイクルなどの情報はターゲティング精度を高める上で欠かせません。
こうしたデータを活用すれば地域別に異なるプロモーション展開や再購入が見込まれるタイミングでのキャンペーン情報の通知など、より効果的なマーケティング施策が実現します。
例えば定期的に同一商品を注文するユーザーには、自動的な次回配送日の提案や特典付きの継続プランの提示により、購買継続を促進させられるでしょう。
このように物流データを軸にした広告戦略は精度の高いマーケティングを実現し、広告投資の無駄を削減する効果も期待できます。
物流企業の存在は、一般消費者にとって意識されにくい領域です。だからこそSNSやコンテンツを通じ、ブランドの見える化を図りましょう。
例えば配送員の一日に密着した動画や倉庫内の効率化への取り組み紹介、配送トラブルへの対策事例などの日常業務の裏側の発信によって企業の姿勢やこだわりが伝わります。
また実際のユーザーからの声や事例の紹介により、共感や安心感を得やすくもなるでしょう。こうした発信は従来のBtoB中心のイメージを超えた、親しみやすく信頼性の高いブランド像の構築につながります。
コンテンツは定期的な更新によってSEO対策にも効果を発揮し、検索流入の増加も見込めます。認知拡大とブランディング両方の実現のためには、継続的な情報発信が不可欠です。
顧客ロイヤルティを高めるには単発的なアプローチではなく、継続的な関係構築が求められます。ここで活躍するのが、物流データを活用したCRM(顧客関係管理)です。
例えば購入頻度や時間帯、配達先の変更履歴などを分析すれば顧客ごとの嗜好や傾向が明らかになります。それに基づいてパーソナライズされたメッセージや特典を提供すれば、この会社は自分のことを理解しているという感情を生み出すことが可能でしょう。
さらに配送時のフィードバックの迅速なサービス改善への反映により、顧客の信頼度は大きく高まります。CRMと物流の一体化により、単なる配送業務が顧客との絆を育む重要な接点への進化が期待できるでしょう。
物流DXを推進してマーケティングと業務オペレーションを統合するには、高度な設計力と組織体制の整備が求められます。しかし多くの物流現場ではいまだ人力による作業が中心であり業務の最適化と同時にマーケティング活動を展開する余力が限られています。
特に従来型の業務フローでは日々の荷物処理やクレーム対応に追われ、長期的な戦略立案やデジタル施策の実行まで手が回らないというのが実情というケースも珍しくありません。
ここでは物流業務とマーケティング活動の両立を難しくしている要因を、具体的に整理して解説します。
物流部門とマーケティング部門では目的や評価基準が異なるため、両者が同じ目標に向かうのは簡単といえません。物流は配送の正確さや作業効率を重視し、納期遵守率や誤配送の低減が主な評価指標です。
一方でマーケティングは顧客の認知度向上や購買促進を目的に設定されており、ブランド認知度や顧客獲得数、広告の反応率などが成果の目安となります。この違いによって物流側では新しいサービス導入で作業が増えることを嫌う一方、マーケティング側は顧客体験向上のため柔軟な変更を求めることが多くなります。
目的と評価指標が食い違うと双方の折り合いをつけることが難しくなり、結果として連携が進まない原因となり得るでしょう。両部門の共通指標を設定し、双方の視点を理解し合う体制構築が欠かせません。
物流とマーケティングは業務に使う情報やデータの種類が異なるため、情報共有が滞りやすくなります。
物流では配送管理システムや倉庫管理システムを使い、出荷状況や在庫情報をリアルタイムで把握します。一方、マーケティングで行われるのは顧客管理システムやマーケティングオートメーションツールの活用による、顧客行動や広告効果の分析です。
これらのシステムが連携していない場合、重要な情報が部門間で共有されず意思決定や施策に活かされません。
キャンペーン期間中の配送変更や顧客からのフィードバックなどが適切に共有されない場合、顧客満足度の低下につながります。部門間で定期的に連携会議を開き、情報共有のルールやツールを整備すると円滑なコミュニケーションが促進されます。
物流業界ではデジタル化やDX推進の必要性が叫ばれていますが、現実には現場の紙作業や人手依存が残るケースは珍しくありません。特に中小規模の事業者はIT人材や予算が限られ、最新システムの導入が遅れやすい状況にあります。そのため、業務効率の改善やマーケティング連携を進めるための土台が不十分なままという例は枚挙に暇がありません。
さらに、社内におけるITリテラシーの差も課題です。新しいツールを入れても使いこなせなければ作業の負担が増え、かえって効率が落ちます。デジタル技術の導入には現場の声を反映させ、段階的に推進する必要があります。
また教育やサポート体制も整え、従業員全員がDXのメリットを実感できる環境を作らなければなりません。これにより、物流とマーケティングの連携基盤が整います。
市場の変化が速く消費者ニーズも多様化する中、物流業界に求められるのは迅速な対応力です。ECの需要増加や配送方法の多様化により、既存の業務フローだけでは対応しきれない場面が増えています。
しかし多くの物流現場では業務が定型化されており、新しい施策や変化を取り入れる余裕が少ないのが現状です。例えば期間限定キャンペーンに合わせた配送体制の調整や新商品への特別梱包対応など、迅速な現場対応が必要になってきています。
またトップダウン型の組織構造では現場の意見が上層部に届きにくく、柔軟な改善が進みにくいことも影響しています。変化に即応するには現場の自律的判断を促し、部門横断の協力体制を整えることが必要でしょう。この体制が整うことで、変化に強い組織となります。

物流業界でデジタルマーケティングを推進すると、業務効率の向上やコストの削減が見込めます。さらに顧客との接点を強化しつつ、サービス品質や顧客体験の改善も期待されるでしょう。
またこうした取り組みは新たなビジネスモデルの創出や持続可能な成長、さらには競争力の強化にもつながると考えられます。これらのメリットの理解、及び実際の活用が物流企業にとって重要なテーマといえるでしょう。
ここでは、これらのポイントを具体的に掘り下げていきます。
デジタルマーケティングの推進により、物流業務全体の効率化が期待されます。顧客データや配送データを統合し、業務プロセスの最適化への活用により、無駄な作業の削減や作業時間短縮の実現が考えられるでしょう。
例えば配送ルートの最適化や需要予測を活かした在庫管理は、従来の経験則に頼る方法よりも高い精度で実行される傾向があります。またデジタルツールによる自動化やリアルタイム情報共有によって現場での意思決定が迅速になるため、ミスや遅延のリスクも減少する可能性があります。これにより、配送コストや人的コストの抑制も見込めるでしょう。
さらに効果的なマーケティング施策と連携すれば広告費の無駄も減り、投資対効果の向上が見込まれます。こうした複合的な効率改善が、企業の競争優位に寄与します。
顧客体験の向上は、デジタルマーケティングの推進において重要な要素の1つです。配送状況のリアルタイム通知や柔軟な配達オプションの提供は、顧客の安心感や満足度を高める可能性があります。こうした施策は単に商品を届けるだけでなく、ユーザーの視点に立ったサービス設計がなされていることを示しています。
また顧客の購買履歴や配送履歴の分析により、パーソナライズされたコミュニケーションが行えるようになるでしょう。これによって適切なタイミングで情報提供や特典の案内ができ、顧客のロイヤルティ向上にもつながりやすくなります。
さらにSNSやコンテンツマーケティングを活用して物流企業の信頼性や専門性を伝えることも、サービス品質のイメージアップに寄与すると考えられます。こうした全方位の取り組みがCXの改善に結び付き、顧客の継続的な支持を獲得する一助となるでしょう。
物流業界でのデジタルマーケティングの推進によって顧客との接点が増えるだけでなく、これまでにない新しいビジネスモデルが生まれるかもしれません。配送状況や顧客の利用傾向をデータで把握し、そこから得られるインサイトを基に新たなサービスや提案を展開できるためです。
例えば配送データを活用した、サブスクリプションモデルや特定顧客向けのカスタマイズ配送サービスなどが想定されます。また顧客との双方向のコミュニケーションが促進されることでニーズを早期に察知し、新規事業や商品開発のヒントを得られる可能性もあります。
このような接点強化とビジネスモデルの多様化は、物流企業が単なる配送業務にとどまらず顧客価値の創造に積極的に関与する、新たなステージへ進む一助となるかもしれません。
物流企業のデジタルマーケティングの推進により、持続可能な成長や競争力の強化につながる可能性があります。顧客の多様化するニーズに柔軟に対応し、効率的な業務運営の継続によって長期的に安定した収益基盤を築くことが見込まれます。
また環境負荷低減に配慮したエコ配送の訴求、地域密着型サービスの展開といった差別化要素などもデジタル技術の活用により、実現しやすくなるかもしれません。こうした取り組みは社会的評価の向上につながり、顧客や取引先からの信頼を獲得しやすくなります。
さらに競合他社との差異化を図るための情報発信やブランド価値の強化も進めやすくなるため、市場でのポジション維持に寄与すると考えられます。こうした要素が相まって、企業の持続的な成長が期待されるでしょう。
デジタルマーケティングの推進は、物流業界におけるサプライチェーンのシームレス化にもつながる可能性があります。顧客の購買行動や配送データをリアルタイムで共有し、関係各所の連携によって物流全体の透明性が高まるでしょう。
これによって注文から配送、受け取りまでの過程が途切れることなく管理され、トラブルや遅延の減少が期待されます。また各工程での情報共有が進むことで、問題発生時の迅速な対応や改善策の検討も効率的になるでしょう。
さらにサプライチェーン全体の最適化が進むことで、在庫の過不足や無駄な輸送の削減も促されます。結果としてコスト削減と環境負荷の軽減にもつながる可能性があり、持続可能な経営への寄与も期待できるでしょう。
物流業界でデジタルマーケティングを推進する際には、さまざまなツールを活用して効率的かつ効果的に情報を扱いましょう。これらのツールはデータの収集や分析、リアルタイムでの状況把握、顧客体験の向上に貢献します。物流業務とマーケティング活動が密接に連携する環境を整備するため、適切なツール選択と活用方法の理解が求められます。
ここで紹介するのは、代表的な4つのツールについての具体的な特徴と利点です。自社の課題と照らし合わせながら参考にしてください。
MotionBoardは多様なデータを集約し、見やすく可視化できるBIツールとして知られています。物流業界では配送データや在庫状況、顧客情報など多岐にわたるデータを一元管理し、グラフやダッシュボードでリアルタイムに把握できる点が魅力です。
このツールを活用すると、複雑なデータの傾向や問題点を直感的に理解しやすくなります。例えば配送遅延がどの地域で発生しやすいか、売れ筋商品や季節変動の動向などを瞬時に把握できるでしょう。また関係者間での情報共有も円滑になり、意思決定のスピードアップに役立ちます。
さらにMotionBoardはカスタマイズ性が高く、企業のニーズに応じて画面レイアウトや分析軸を調整できるため、さまざまな業務シーンに柔軟に対応できます。これによってデータドリブンな意思決定を支援し、物流業務とマーケティングの両面で効果的な活用が期待されるツールの1つです。
出典参照:MotionBoard|ウイングアーク1st株式会社
Ubisense DIMENSION4™は高精度な位置情報をリアルタイムで取得し、物流現場の動きを細かく可視化できるシステムです。倉庫内や配送センターの物品や作業員の位置把握により、作業の効率化や安全管理に役立てられます。
このシステムを導入すると資産の所在確認や動線分析が容易になり、無駄な移動や待機時間の削減につながる可能性が高まります。またトレーサビリティが向上し、問題発生時の原因特定や迅速な対応が促される点も評価対象です。
さらに位置情報データはマーケティングデータと組み合わせ、顧客への配送精度やサービス改善にも活用できるでしょう。このようにUbisense DIMENSION4™は、現場の細部にまで踏み込んだデジタルマーケティング推進の支援ツールとして注目されています。
出典参照:Ubisense DIMENSION4™|ユビセンス・ジャパン株式会社
iChockは顧客が店頭で支払いを済ませ、その後自宅で商品を受け取れるサービスを提供するシステムです。この仕組みは、物流と販売の境界をデジタル技術でシームレスにつなげる点に特徴があります。
利用者は店舗での決済を簡単に済ませた後、配送日時を自由に設定できるため利便性が高まります。また店舗側は販売と配送のデータを連携させることで、在庫管理や配送計画の精度向上を目指せるでしょう。こうした顧客体験の向上は、リピート率の増加やブランドの信頼獲得につながると考えられます。
加えてiChockのようなツールは顧客の購買データを詳細に収集でき、マーケティング戦略の精緻化に役立ちます。個別ニーズに応じたサービス提供が進むことで、物流とマーケティングが一体となった新たな顧客接点の創出にも期待が持てるでしょう。このようなシステムは今後の物流DX推進において重要な役割を果たす可能性が高いといえます。
物流業界では、配送データの分析・活用が新たな販促施策のカギとなりつつあります。従来、配送情報は業務管理のために活用されてきましたが、近年ではそのデータをもとに顧客ニーズを深掘りし、サービス改善や売り上げ向上につなげる動きが広がっています。
ここでは、実際に配送データを用いて販促を推進した企業の事例を紹介し、それぞれのアプローチと成果について具体的に見ていきましょう。
ヤマト運輸株式会社では、膨大な配送実績データとEC市場の需要動向を掛け合わせ、新たな販促施策を展開しました。ポイントは、地域ごとの荷物の出荷量や受け取り傾向を分析し、エリア別の購買動向を可視化したことです。この分析により、どの地域でどのジャンルの商品が好まれているのかを把握し、EC事業者に対してエリア特化型の販促キャンペーンを提案できるようになりました。
さらに、特定地域でのキャンペーン実施時には、配送拠点の強みを活かして即日配送や時間指定に柔軟に対応する仕組みも構築しました。これにより、商品訴求力を高めながら、顧客満足度も向上させることに成功しています。配送網のデータをマーケティング施策と連動させることで、単なる運送業務を超えた価値提供を実現しました。
出典参照:EC向け新配送サービス「EAZY」の提供開始|ヤマト運輸株式会社
株式会社シービー・クラウドは、自社が提供するラストワンマイル配送マッチングサービスにおいて、配送ルートやドライバーの滞在時間に関するデータを収集・分析し、顧客提案の質を高めています。これらのデータをもとに、非効率なルートの見直しや、滞在時間が長いエリアにおける配送遅延の原因を特定し、配送計画の精度を向上させました。
この仕組みを活かし、店舗や事業所ごとの配送ニーズを可視化することで、企業向けに業務最適化と同時に販促支援も実施しています。例えば、特定エリアで配送頻度が高い小売り店舗に対しては、商品提案のタイミングや在庫調整をアドバイスすることで、売り上げ機会の最大化を図っています。
出典参照:CBcloud、配送業務を補助する新サービス「サクッとコース計算」を提供開始|株式会社シービー・クラウド
物流業界でデジタルマーケティングを進める際には、目的や指標の明確化が重要になります。曖昧な目標設定は施策の効果測定を難しくし、軌道修正も滞る恐れがあるためです。
またターゲット設定の精度を高めるため、市場調査を徹底する必要があります。加えてツールの選定や運用前には自社のリソースや体制を十分に見直し、現実的な運用計画を立てることが求められます。
これらの注意点を押さえた上で推進を進めることが成果につながりやすくなるでしょう。
デジタルマーケティングを推進する際、最初に目的とKPI(重要業績評価指標)をはっきりと定める必要があります。目的がぼやけていると施策の方向性が不明瞭になり、効果的なアクションが取りにくくなるかもしれないからです。例えば売上向上なのか、顧客獲得なのか、ブランド認知の拡大なのかといった具体的なゴールの設定によって必要な施策や評価方法が明確になります。
KPIは目的を達成するための定量的な指標であり、これを適切に設定しないと施策の進捗や成果を把握しづらくなるでしょう。定期的にKPIを見直し、現状の数字と照らし合わせながらの軌道修正も大切です。こうした管理を怠ると施策が空回りしやすくなるため、初期段階での目的・指標の具体化と共有は不可欠といえます。
ターゲットの設定が適切でなければ、どんなに優れたマーケティング施策も効果が薄れてしまう可能性が高くなります。物流業界においても顧客のニーズや購買行動、競合動向を正確に把握するために市場調査が欠かせません。調査を通じて顧客層の特性や行動パターンを理解し、細かなセグメント分けがターゲット設定の精度を高めます。
市場調査では定量データだけでなく、顧客の声や潜在ニーズも取り入れる必要があります。これによって表面的な傾向だけでなく、深層的な動機や不満点を把握できるでしょう。調査結果を基にターゲットを見直すことで、ズレの少ない効果的なコミュニケーション戦略を構築しやすくなります。こうした取り組みは施策の無駄を減らし、顧客満足の向上にもつながると考えられます。
デジタルマーケティング推進に伴い新たなツールやシステムを活用する際は、自社の人的リソースや運用体制を事前にしっかりと見直すことが大切です。ツールを導入しても使いこなせる人材や運用ルールが整っていなければ、期待したほどの効果を得られないでしょう。
具体的には担当者のスキルレベルや業務負荷、既存の業務フローとの整合性を確認し、必要に応じて教育や体制の見直しを検討します。さらに運用面ではツールの定期的なメンテナンスやアップデート対応、トラブル時の対応フローも明確にしておくとよいでしょう。こうした準備が整うことでツールの運用がスムーズになり、効果的なマーケティング活動の継続につながりやすくなります。

物流DXの推進によって業務の効率化やコスト削減、そして顧客体験の向上が期待される状況にあります。デジタルマーケティングはこれらを支える重要な要素であり、適切な戦略とツール活用が効果を高めるでしょう。
現状の課題を整理して目的やターゲットの明確化から始め、段階的に施策を進める姿勢が求められます。継続的にデータを分析して柔軟に改善を加えながら取り組めば、物流業界の変化に対応しつつ持続可能な成長が見込まれるでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
