物流DXで課題解決へ|2024年問題と人手不足に立ち向かうための実践ガイド
物流

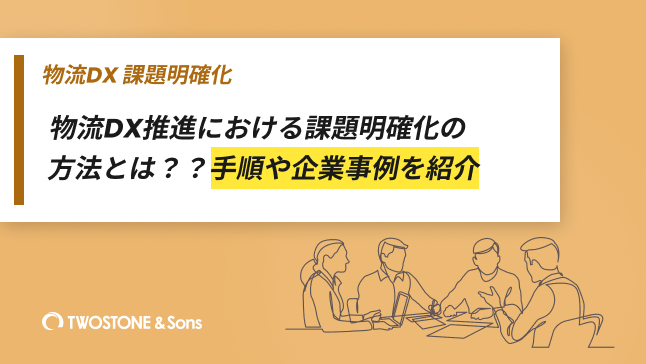
物流業界は業務の複雑化や人手不足が進む現在、DX推進の必要性が高まっているのが実情です。多くの企業が効率化やコスト削減、さらにはサービス品質向上を目指しデジタル化に取り組む一方、推進過程で直面する課題に悩まされているケースも少なくありません。課題が明確でないまま進めると効果を実感しづらく、途中で挫折するリスクも考えられます。
本記事では物流DX推進における課題をいかに明確化するかに焦点を当て、具体的な手順や実際に取り組む企業の事例を交えて紹介していきます。参考にしていただくことで自社の課題を把握しやすくなり、推進をスムーズに進めるヒントが得られるでしょう。これからの物流業界で求められる変革に一歩近づける内容となっています。

物流業界では、従来のやり方だけでは対応しきれない複雑な課題が増えています。人手不足や労働環境の悪化、業務量や複雑性の増加などがその代表例です。さらに2024年問題に伴う法規制対応も求められ、業務の効率化やコスト削減も急務となっています。
このような状況から、物流DXの推進によってデジタル技術を活用した業務の最適化をしなければ、将来的な競争力の維持が難しくなると考えられているのが現状です。これらの背景から、物流DXの推進は避けて通れないテーマになっています。
物流業界では長年にわたり深刻な人手不足に悩まされてきました。特に若年層の労働者が減少し、高齢化が進む中で人材の確保は難しい状況です。加えて労働環境の過酷さも、業界の課題の1つとして指摘されています。長時間労働や夜間作業、体力的負担の大きさが原因で離職率が高くなる傾向にあります。
こうした環境では業務の負担を軽減し、働きやすい職場環境を整える必要性が高まることでしょう。物流DXの推進によって自動化や効率化を進めることが期待され、労働者の負担を減らしながら生産性を維持する方向性が模索されています。また働き手の確保だけでなく、定着率の向上にも寄与する可能性があります。これら労働環境の改善と人材不足への対応が物流DX推進の動機といえるでしょう。
2024年問題とは物流業界における、労働時間規制の強化によってドライバーの勤務時間が制限される問題を指します。これによって配送能力の低下や人員不足の影響などが懸念されています。また労働基準法の改正や安全規制の厳格化も相まって、物流業務の遂行には新たな対応が求められているのが現状です。
こうした法規制への対応は業務の効率化やスケジュール管理の高度化を必要とし、デジタル技術の活用が期待される理由の1つです。例えば配送ルートの最適化、運行管理の自動化などで対応を進める動きがあります。法規制の変化に適応しつつ、安全性と効率を両立させる体制づくりが物流DX推進で重要視されるポイントです。
物流業界は競争が激しく、コスト管理が事業継続に影響します。人手不足による人件費上昇や燃料価格の変動など、コスト圧力は増加傾向にあります。そのため、効率的な業務運営と経費削減の両立が必要です。
物流DXの推進は、これらの課題に対し有効な手段の1つです。デジタルツールを活用して配送ルートの自動最適化や在庫管理の精度向上を図れば、無駄な作業や資源の削減につながるでしょう。さらに業務の見える化によって問題点を早期に発見し、対応策の迅速な実行も期待されます。こうした効率化とコスト削減が将来的な競争力維持が見込まれているため、DX推進が注目されています。
物流DXを推進する際、自社の課題の正確な把握が必要です。課題が明確になれば改善の優先順位や対策が立てやすくなり、業務全体の最適化につながります。特に業務プロセスの可視化やデータ活用を通じ、これまで見えづらかった非効率や属人化の問題を表面化させられるでしょう。
さらに現場の実態とのギャップの把握によって、より現実的で実行可能な改善策を立案できるようになります。ここでは課題の可視化によって得られる、具体的な効果について解説します。
業務の全体像を把握する上で、見える化は基盤となる要素です。例えば物流の各工程における進捗や滞留ポイントをリアルタイムで確認できれば、ボトルネックの特定は容易です。
また配送ルートや配車状況の可視化により、無駄な移動や時間ロスを減らす手がかりが得られます。さらに各担当者の作業状況や業務負荷を把握できれば、適正な人員配置や効率的な業務分担が可能になります。
見える化は判断のスピードと精度を高める上で、欠かせないステップです。日々の業務を感覚や経験に頼らず事実に基づいた管理が可能となるため、業務改善の精度が向上します。
物流現場には日々、膨大な量のデータが蓄積されています。これらの収集・分析により、業務課題の正体を明らかにできるでしょう。例えば倉庫内の出荷ミスや在庫差異の発生頻度と発生箇所の分析により、根本原因を特定する手がかりとなるかもしれません。
またドライバーの稼働率や運行ルートの偏りなど、属人的な運用による非効率もデータで可視化されます。加えてKPI(重要業績評価指標)を明確に設定し、それに基づいた実績データの比較によって改善の必要がある領域を定量的に判断できます。
データの活用によって感覚や推測では見えてこない課題に気づくきっかけが得られ、より実効性の高い改善へとつなげられるでしょう。
属人化が進んだ業務では担当者ごとに対応方法が異なりやすく、ミスや引き継ぎの問題が発生しやすくなります。
そこで課題の明確化を行うと、業務フローの標準化を進められるでしょう。標準化された業務手順が整備されれば誰が担当しても同じ品質で対応でき、教育コストの削減や安定した運用が実現します。
さらに業務内容や進行状況の一元的な管理によって現場と管理者間の情報のズレがなくなり、指示や確認作業が効率化されます。これによって業務全体の整合性が高まり、ミスの再発防止や業務改善の継続的な取り組みができるでしょう。結果として、組織全体の生産性向上につながります。
物流業界におけるDX推進は単なるシステム導入ではなく、業務全体の変革を伴います。そのため推進前の準備段階で、多くの企業が直面する課題の本質を理解することが大切です。課題を正しく認識しないまま施策を進めてしまうと、結果としてプロジェクトの停滞や現場の混乱を招く可能性があります。
ここでは現場だけではなく経営層の視点からも、物流DX推進時によく見られる課題について、5つに整理していきます。
現場では長年の慣習により、紙ベースでの管理や口頭での指示が中心となっているケースが少なくありません。このような環境では業務の進め方が個人に依存しやすくなり、誰がどの業務をどのように行っているかが見えにくくなります。結果として、業務の平準化やマニュアル化が進まず、業務改善や自動化に踏み出しにくくなります。
さらに属人化は担当者の退職や異動時に業務の引き継ぎが難航する要因にもなり、業務の継続性が損なわれるリスクを抱えることになりかねません。DXを推進するにはまず業務を可視化し、再現性のある仕組みに落とし込む必要があります。
多くの物流企業では倉庫管理や輸配送、受発注など業務ごとに異なるシステムを導入している状況が見られます。これでは情報が部門ごとに分断され、リアルタイムでの状況把握やデータの一元管理が困難になる一方です。
例えば出荷状況を確認するために倉庫側と運送会社、営業部門それぞれに問い合わせが必要となる場合、業務のスピードと正確性が損なわれます。このような状態ではデータを活用した意思決定ができずに現場の負担が増すだけでなく、経営判断にも遅れが生じるでしょう。
現場と経営層の間にDXに対する認識のズレがあると、プロジェクトが思うように進まなくなります。経営層がコスト削減や効率化を目的にDXを推進しようとしても、現場がその意図を十分に理解していなければ反発や不安を招くことになりかねません。
実際に現場では自分たちの仕事が奪われるのではないか、という懸念を持つ従業員も少なくありません。こうした不安を放置すると、推進後の運用に支障が出て来るでしょう。DX推進においては現場の声を丁寧に拾い上げ、双方向のコミュニケーションを通じて理解と納得を得ることが欠かせません。
慢性的な人手不足も、DX推進の障壁として頻繁に挙げられます。特に中小規模の物流企業では日々の業務に追われ、改善や変革に割ける時間やリソースが極端に限られているケースは珍しくありません。
結果として業務プロセスの見直しや新しいシステムの検討に着手できず、現状維持が続いてしまいます。現場に過度な負担をかけずにDXを進めるためには外部パートナーの協力を得る、段階的な推進を検討するなどのリソース分散と長期的な視点が必要となります。
ITリテラシーの低さや専門人材の不足も、DX推進における深刻な課題です。既存の従業員が現場業務に精通していても、システム設計やデータ活用といった領域には対応できないケースが多く、技術面での支援体制が整っていないと推進が停滞します。
またDXをリードする役割を担う人材が社内に不在である場合は方向性が不明確になり、現場が混乱する要因にもなります。こうした状況を打開するには、外部の専門家と連携しつつ社内人材のスキルを高めるとともに、継続的な学習を促す企業風土の醸成が求められるでしょう。

物流DXを推進するにあたって最初に取り組むべきは、現状の課題の正確な把握です。課題が曖昧なままではどの技術を活用すべきか、どこにリソースを集中すべきかの判断が難しくなります。そこで重要なのが業務の実態を可視化し、現場の声を反映しながらデータと外部事例を基に課題の本質を明らかにするステップです。
ここでは、課題の明確化から対応方針の設定までの5つの手順を紹介します。
業務プロセスの可視化は、課題解決の出発点です。まずは倉庫業務や輸配送、在庫管理、受発注といった主要な物流機能ごとに業務フロー図を作成し、各ステップでの作業内容や所要時間を整理します。Excelや専用のBPMNツール(Business Process Model and Notation)を活用すると、業務の流れを図式化しやすくなるでしょう。
可視化の目的は属人的な作業や手入力による二重処理、情報の分断などの非効率な要素の発見にあります。現場の協力を得ながら業務フロー図を作成すれば、実態との乖離を防げるでしょう。加えてフロー全体の所要時間の把握により、どの工程にボトルネックがあるのかを客観的に分析できます。
業務フローを可視化した後は、現場の担当者から直接ヒアリングを行うことが必要です。なぜなら図では表現しきれない細かな問題や、現場ならではの非公式な運用ルールが存在するためです。日常的に発生しているトラブルや手戻りの原因、対応に時間がかかっている作業など、当事者の声を通じて初めて浮かび上がる課題も多くあります。
ヒアリングの際は困っていること、改善できると思う作業、他部門との連携での問題といった内容を中心に質問を進めましょう。可能であれば定性的な意見と定量的なデータを、両面から捉えることが望ましいです。
現場のヒアリングを終えたら、次に取り組むべきは定量データの分析です。例えば配送のリードタイムや誤出荷率、在庫回転率、積載率などのKPI(重要業績評価指標)を確認し、数値が基準値と乖離している項目を抽出します。こうした数値は業務のどこに無駄やミスがあるかを示す、客観的な指標となります。
BIツールやクラウド上の物流管理システムを活用したデータ分析により、リアルタイムでの可視化やドリルダウンが可能です。特定の工程だけでなくサプライチェーン全体を俯瞰しながら、改善ポイントを見極める視点が必要です。
自社内の分析を進める一方、他社の成功事例や業界の標準的な運用との比較も欠かせません。なぜなら自社の業務が一般的に見て非効率なのか、あるいは業界全体で課題とされているのかを判断するためには、外部との比較が有効だからです。
例えば同業他社がRFIDや自動ピッキングシステムをどのように活用しているか、その調査結果を自社の業務と照らし合わせると技術導入の方向性が見えてきます。また物流系展示会や業界団体のセミナーで得た情報を基に行うベンチマークも、実用的な手法の1つです。
課題の洗い出しが完了した後は経営層と現場で共通の認識を持ち、改善に向けた優先順位を決定するステップが必要です。経営層はROI(投資対効果)や長期的な経営戦略を重視し、現場は日々の業務効率や作業負担を重視する傾向があります。そのため両者の視点を調整しながら、意思決定を行うことが大切です。
課題の優先順位を決める際は緊急度と重要度のマトリクスを活用すると、整理しやすくなります。さらに改善のインパクトが大きく、実行難易度が低いものからの着手によって短期間での成果創出を目指せます。
課題の明確化を進める上で、業務の可視化や情報の一元管理を支援するツールの活用は欠かせません。特に物流業務は部門間の連携が複雑であり、属人化や情報の分断が起きやすい領域です。こうした課題に対応するには現場の実態を見える化し、リアルタイムでの情報共有を支えるデジタルツールが有効です。
ここでは物流DXの推進に役立つ、代表的なツールを5つ紹介します。自社の課題と照らし合わせながら参考にしてください。
TUNAG for LOGISTICSは物流業界に特化して開発された、情報共有・社内コミュニケーションプラットフォームです。現場と本部の間でのスムーズな情報の行き来を目的とした設計によって業務上の指示や連絡、マニュアルの共有などを一元的に管理可能です。これにより、紙ベースの掲示や口頭での指示に頼らない業務体制を構築しやすくなります。
特徴的なのは各拠点の業務実態や課題を、リアルタイムで把握できる点にあります。現場からの意見投稿機能やアンケート、日報管理などの活用によってボトムアップの課題発見が促進されるでしょう。またスマートフォンやタブレットでも利用できるため、ドライバーや倉庫作業員といった現場従事者との距離を縮める役割も果たします。
出典参照:TUNAG for LOGISTICS|株式会社スタメン
AnyLogiはEC事業者向けに開発された物流業務支援SaaSです。出荷依頼や在庫管理、配送ステータスの確認など従来は別々のシステムで管理されがちだった業務を、一元化できる点が特徴です。複数の物流倉庫や配送業者を利用している企業にとって、業務の効率化と見える化の両立を支援するツールとして注目されています。
特に注目したいのはAPI連携によってECプラットフォームやWMS、配送会社のシステムとスムーズに接続できる点です。これによってシステム間での手入力や確認作業の手間を軽減し、情報漏えいや入力ミスのリスクを下げることが期待されます。
在庫変動や出荷傾向といったデータも蓄積・分析できるため、販売動向や需要予測といったマーケティング面にも活用しやすい構成となっています。
出典参照:AnyLogi|AnyMind Group株式会社
クラウドトーマスは運送業務に特化した、配車・運行管理機能を備えたクラウド型の物流支援システムです。WMS(Warehouse Management System)の機能に加えて配車計画や車両ごとの運行履歴、ドライバーの勤務状況などを一元的に管理できます。特に中小規模の運送事業者にとって、属人的な配車業務を標準化する手段として活用が進んでいます。
地図ベースでの配送ルート確認やAIによる最適配車支援機能を用いることで、非効率なルートや時間の偏りに気付きやすくなるでしょう。また荷主との受発注管理にも対応しており、手配ミスや納品遅延などのトラブルの事前防止にもつながります。
クラウド型であるため複数拠点でも同一の情報にアクセスしやすく、拠点間の情報格差を緩和しやすいのも特徴の1つです。
出典参照:クラウドトーマス|株式会社関通
ロジザードZEROは倉庫管理業務の最適化に特化した、クラウド型のWMSです。複数の倉庫を利用する企業でも、在庫情報や出荷状況をリアルタイムで把握できる点が評価されています。特に委託先の3PL(サードパーティ・ロジスティクス)倉庫とも情報を共有しやすくなるため、在庫精度の向上や誤出荷の防止につながる可能性があります。
導入初期は既存の業務フローを大きく変えずに利用を始められる仕様となっており、従業員のITリテラシーに関係なく使いやすいインターフェースが特徴です。入出庫や棚卸しの記録もリアルタイムで反映されるため、紙での記録や口頭確認に依存しない在庫管理体制の構築がしやすくなります。
出典参照:ロジザードZERO|ロジザード株式会社
Cariotは車両に取り付けたIoTデバイスから走行データを取得し、リアルタイムで可視化するクラウドサービスです。トラック及び営業車両の位置情報や速度、走行履歴、停車時間などを一覧で把握でき、配送進捗の確認や遅延リスクの早期察知に役立ちます。
ドライバーの運転傾向やアイドリング時間も可視化でき、燃費改善や安全運転の意識づけを支援します。加えて予定ルートと実際の走行ルートの比較もできるため、非効率な運行ルートの見直しや配送品質の改善に活用できるでしょう。
またCariotは他の業務システムとの連携も考慮されており、WMSやTMSとのデータ統合を通じて輸配送全体の最適化にもつながります。現場の実態を可視化し、経営判断にも活かせる情報基盤を整える役割が期待されるツールの1つです。
出典参照:Cariot|株式会社キャリオット
物流DXの推進においては現場が抱える課題の、的確な可視化が出発点となります。課題を把握した上で具体的な改善策に結びつけた企業の事例は、他社にとっても指針となるでしょう。
ここでは業務の非効率や情報の分断、人員の偏在といった課題を見える化して効率的な物流体制へとつなげている企業事例を紹介します。それぞれの取り組みにある企業内の課題、それに対しての対応策を具体的に見ていきましょう。
福岡運輸株式会社ではドライバーの拘束時間が長期化していた背景として、トラックの待機時間が業務全体に与える影響が問題視されていました。この課題を可視化するために行ったのが車両の出入り記録や入出庫のタイミングを詳細に記録・分析、及び物流センターにおける荷待ち時間の実態把握です。
結果として待機時間の多くが、荷役前の手配調整や情報の不一致によって発生していることが浮き彫りになりました。ドライバーごとに対応内容が異なっていた点や配送先からの受け入れ対応にばらつきがあった点も明確化され、属人的な対応がボトルネックとなっていたことが確認されました。
同社は可視化した課題を基に、荷役スケジュールの事前共有や受付の予約制導入を進めています。数値に基づいた業務改善の進行により、ドライバーの労働環境にも一定の変化が生まれつつあるようです。
出典参照:DC/TC 問わず使用できる「バース予約・受付システム」を稼働開始しました|福岡運輸株式会社
ヒサノ株式会社では配車業務が一部担当者に依存しており、業務内容が暗黙知化(属人化)しているという課題がありました。この状況では担当者の不在や引き継ぎの遅延により、業務停滞のリスクが常に存在していたといいます。
そこで同社がはじめたのは、配車業務のフロー全体を可視化する取り組みです。具体的には日々の配車計画の作成方法やルート決定の基準、取引先との調整方法を1つひとつ書き出し、現場での作業内容と判断プロセスを言語化して整理しました。
結果として経験に基づいた勘や慣習で判断されやすく、情報共有が限定的であると判明しました。この可視化によって業務プロセスの平準化や標準マニュアルの整備が可能となり、誰でも同じレベルで対応できる仕組みづくりが進められています。
出典参照:DX戦略(社長メッセージ)第2回(2021.9.13)|株式会社ヒサノ
生活協同組合の物流業務を担うシーエックスカーゴ株式会社では、複数拠点における在庫データの整合性に課題を抱えていました。各センターで取り扱う商品の在庫状況がリアルタイムで一致せず、出荷ミスや二重発注といった問題が散見されていた状況です。
同社はまず在庫管理システムを通じ、各拠点のデータ更新頻度や入力方法を精査しました。結果として手入力や紙での記録が残っていたことが一因であると判明し、情報の更新タイミングにばらつきが生じていたことが明らかになりました。
課題の可視化によって再認識されたのが拠点ごとの業務フローの違い、及びその標準化の必要性です。これを受けてシステムの操作手順を統一し、リアルタイム反映が前提となる運用ルールを整備しました。また棚卸しや出荷実績の誤差を、自動的に検出する仕組みも導入されています。
出典参照:事業概要|株式会社シーエックスカーゴ
日立物流株式会社では安全運転の徹底が重要視される一方、ドライバーの運転傾向を把握しきれていないという課題がありました。特に長時間運転による注意力の低下や同一ルートでの慣れによって発生する漫然運転が、事故リスクを高める要因となっているようです。
そこで同社はテレマティクス技術を活用し、各車両の加減速・急ブレーキ・車線逸脱といった運転データを蓄積・可視化する取り組みを開始しました。これによってドライバーごとの運転傾向を把握しやすくなり、危険挙動の兆候を早期に検知する体制が整えられました。
さらに可視化したデータは運行管理者や教育担当者と共有され、指導や安全研修に活用されています。過度な個人責任の追及ではなく再発防止を重視した指導が行われることで、ドライバーの意識向上にもつながっています。
出典参照:ドライバー自身も気づけない「漫然運転」と生体情報のAI分析による「事故ゼロ」に向けた取り組み|日立物流株式会社

物流業務の複雑化や人材不足といった構造的な問題を抱える中、物流DXの推進は業務の持続可能性を高める手段として注目されているのが現状です。その一方でツール導入や業務の見直しに着手しても、具体的な成果に結びつかないケースも存在します。
今回紹介した企業事例やツールの活用方法は、課題の見える化から改善施策の実行までの流れを具体的に捉えるための一助となるでしょう。自社においても目的を明確にし、現場と協働する姿勢で物流DXの取り組みを進めていくことが求められます。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
