物流DXで課題解決へ|2024年問題と人手不足に立ち向かうための実践ガイド
物流

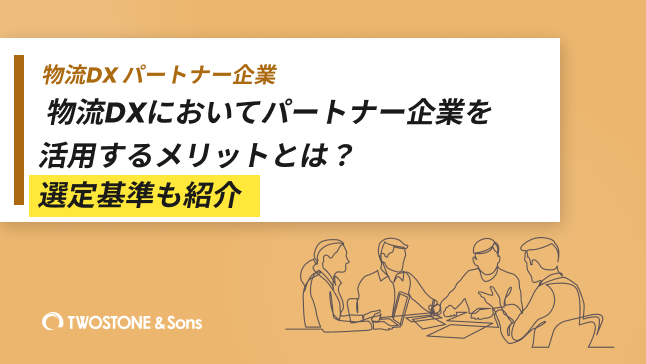
物流業界では、人手不足やコスト高騰、業務の複雑化といった課題が深刻化しています。そのような背景のもと、業務の効率化やサービス品質の向上を目的として、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する企業が増えつつあります。ただし、既存のリソースだけでDXを推進しようとすると、ノウハウの不足や技術的な壁に直面し、思うように進まないことも少なくありません。
そうした状況において注目されているのが、外部の専門パートナー企業との連携です。第三者の視点と実績を取り入れることで、DXの方向性が明確になり、現場とのギャップを埋める一助となる場合があります。
本記事では、物流DXを円滑に推進するためにパートナー企業を活用する意義と、その選定時に注目すべきポイントについて解説します。読了後には、自社がどのように外部の専門家と連携し、現場に応じた改善を積み重ねていくべきかのイメージがつかめるでしょう。

物流DXを推進する上では、単なる技術導入にとどまらず、現場運用への定着や業務プロセス全体の最適化まで見据える必要があります。しかし、すべてを社内で完結させるには、専門知識や人的リソース、現場経験の蓄積など、多くの要素が必要です。
このような中、パートナー企業の存在は重要な役割を果たします。特定分野における実績や、最新のデジタル技術に関する知見を活かすことで、自社だけでは見落としがちな視点や打ち手を取り入れることができるからです。
パートナー企業との連携によって、現場の実態に寄り添った支援を受けながら、自社の体制に無理のないDX推進を進める手段が得られるかもしれません。
物流DXを成功に導く上で、パートナー企業との連携は重要な要素となります。自社単独でDXを推進しようとすると、ノウハウの蓄積不足やリソースの制約により、プロジェクトが停滞してしまうケースも少なくありません。その点、外部の専門企業と協力することで、先進的な技術知識やプロジェクトマネジメント力を取り入れることができ、DXの実行力が向上します。
ここでは、実際に物流DXの文脈で外部支援を活用する主なメリットについて、いくつかの視点から詳しく解説します。
物流DXの推進では、テクノロジーへの理解と業界特有の運用知識の両方が必要となります。しかしながら、企業内にそのすべてを有するケースは限られているでしょう。こうした課題を補う上で、パートナー企業の専門知識や過去の実績は価値を持ちます。
物流領域に精通した外部パートナーであれば、似た課題を抱える他社の対応事例や、特定のツール選定に関する視点など、実践的な知見を提供できる可能性があります。社内の視点だけでは得られないアプローチを加えることで、より効果的なDX推進の糸口が見えてくるでしょう。
現場で直面する課題には、理論だけでは対応しきれない複雑さがあります。運送ルートの最適化、在庫管理の精度向上、属人化した業務フローの見直しなど、実際の運用に根ざした視点が求められる場面も少なくありません。
このような課題に対し、パートナー企業は現場を踏まえた支援を行うことが期待されます。例えば、システム開発の初期段階からヒアリングやフィールドワークを重ねることで、実態に応じた改善策を提示しやすくなるでしょう。
現場に応じた実効的な提案を受けることで、単なる表層的なデジタル化にとどまらず、根本的な業務改革に向けた道筋を描ける可能性が高まります。
パートナー企業との連携によって、物流業務の見直しが進むと、結果的にエンドユーザーへのサービス品質にも好影響を与えます。配送の遅延削減や在庫情報の精度向上などは、顧客体験の向上につながりやすいからです。
また、業務フローの最適化が進むことで、余分な手作業の削減や作業負荷の分散などが期待されます。これにより、社員一人ひとりがより付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。
パートナー企業の支援を受けることで、DX推進が単なるコスト削減にとどまらず、持続的な顧客満足や事業成長に結びつく流れをつくることも考えられます。
短期的な改善ではなく、長期的な成長を見据えた取り組みを支えるためにも、外部の視点を取り入れることが有効とされています。特に、業界動向や技術革新のスピードが速い物流分野においては、社内に閉じた体制だけでは変化に対応しきれない場合もあるでしょう。
パートナー企業との関係性を継続的に築くことで、トレンドを踏まえた提案やシステムの更新など、将来を見据えた支援を受けやすくなります。こうした連携は、変化の激しい環境下で継続的に競争力を維持する上で、役立つ一因となるでしょう。

物流DXの推進を成功させるためには、自社だけで完結するのではなく、信頼できる外部パートナーの存在が欠かせません。技術やノウハウを持つ企業と協力することで、現場の実情に応じた改善策を実行に移しやすくなります。ただし、選定の段階で判断を誤ると、プロジェクトの遅延や追加コストの発生など、さまざまな問題に発展しかねません。
ここでは、パートナー選びで注目したい評価基準や見極めのポイントを紹介します。
物流DXを推進する上では、技術面での課題が数多く存在するため、最新技術への理解や専門的なスキルを持った企業との連携が求められます。特に、在庫管理の自動化やリアルタイムなデータ分析といった高度な技術に対応するには、それに見合った知見が必要です。
選定時には、導入しているシステムの種類やそれを活用した事例を確認することで、実力の一端を把握できます。実際の課題解決に応じた柔軟な技術提案ができるかどうかも見極めの一助となるでしょう。
技術力が備わっていても、業界や企業の特性に応じた提案ができるとは限りません。過去にどのような物流領域で支援を行ってきたのか、また、その中でどのような成果を出してきたのかを確認することが大切です。特に、自社と類似した業種や業態での対応経験がある場合は、現場に応じた提案が期待できます。
また、成功事例だけでなく、プロジェクト中に発生した課題とその対応内容をヒアリングしておくと、より具体的な判断材料となります。
物流業務は企業ごとに異なる業務フローや制約条件を抱えていることが多く、画一的な解決策が通用しないかもしれません。そのため、パートナー企業には一定の柔軟性が求められます。初期の要件定義の段階で対応が難しいとされた部分についても、他の手段を模索したり、段階的な改善を提案したりする姿勢が見られるかどうかがポイントです。
また、急な変更やトラブルが発生した際に、どのように対応してくれるかについても事前に確認しておくと安心です。
プロジェクトの開始前から運用後まで、継続的なサポートが期待できるかどうかも、パートナー選定においては見逃せないポイントです。単にシステムを提供するだけでなく、現場の課題に寄り添い、適切なタイミングでのフォローアップや改善提案を行ってくれる体制が整っている企業は、長期的なパートナーとして信頼しやすいと言えます。
また、物流業務に関する基礎的な理解だけでなく、現場特有の用語や運用の流れについても把握しているかどうかも確認しておきたい部分です。
パートナーとの協働を円滑に進めるためには、技術力だけでなく、コミュニケーションの質が問われる場面も少なくありません。打ち合わせの際に用語の意味を丁寧に説明してくれるか、課題に対して曖昧な回答をせず、明確に方向性を示してくれるかどうかなどを確かめましょう。
また、担当者が頻繁に入れ替わる場合や、伝達事項にズレが生じやすい体制だと、意思疎通が難しくなります。長期的な信頼関係を築くには、一貫した対応体制があるかどうかにも着目することが望ましいでしょう。
物流DXを推進する上で、どのパートナー企業と連携するかは、全体の成果に影響を及ぼす重要な判断材料です。物流業務の多様化・複雑化が進む現在では、単に技術を提供するだけでなく、現場視点に立ったソリューションを提案できる企業が求められています。
ここでは、物流分野において実績を積み、独自のサービスや技術で支援している代表的な企業を紹介します。それぞれの特徴や取り組みから、自社に適した協業先を検討する際の参考にしてみてください。
GROUND株式会社は、AIやロボティクスを活用して物流業務の最適化に取り組んでいる企業です。中でも注目されているのが、株式会社デジタルフォルンと共同開発した「GWES(GROUND Warehouse Execution System)」です。
これは、倉庫内の作業工程を可視化し、リアルタイムで進捗を管理・最適化するためのシステムです。ピッキングや仕分けといった細かな工程ごとの指示が可能となり、作業のムダや偏りを抑える工夫が盛り込まれている点が強みです。倉庫作業のボトルネックを抽出しやすくなるため、業務改善の精度も向上が期待できます。現場の生産性と柔軟性を両立する視点から、導入の検討が進んでいます。
出典参照:物流DX推進のためのパートナーシップ契約を締結|GROUND株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社が開発したAITRIOS™は、エッジAIカメラを活用した画像解析プラットフォームです。物流倉庫内の作業状況を映像データとして収集し、クラウドやローカル環境での処理を通じて、物品の流れや作業者の動線を把握する仕組みを提供しています。これにより、無駄な移動や待機時間の発生箇所を特定し、現場の改善活動につなげられました。
また、AIによる人物検知や自動認識といった高度な機能が備わっており、人的ミスの検出やセキュリティ強化にも貢献しています。物流業務のデジタル化を進める企業にとって、視覚情報を基盤とした分析は有力な手段といえるでしょう。
株式会社Hacobuは、物流プラットフォーム「MOVO(ムーボ)」シリーズを通じて、企業間物流の課題解決を支援しています。MOVOシリーズは、配車計画を最適化する「MOVO Vista」、物流情報を一元管理できる「MOVO Berth」など、複数の機能が組み合わさったシステムです。
これらのツールは、荷主と運送会社の情報連携をスムーズにし、待機時間の短縮や積載効率の向上を目的とした運用が行われています。特に中継輸送や共同配送といった業務において、協力企業間の調整作業を円滑に進めるための基盤として注目されています。DX推進の現場で業務の可視化と最適化を同時に実現するアプローチの一例です。
出典参照:シェアNo.1*1の理由は、圧倒的な現場力とデータ活用の知見。 物流DXツールMOVO(ムーボ)が、あなたの「運ぶ」を最適化します。|株式会社Hacobu
KDDI株式会社が展開する「WAKONX(ワコンエックス)」は、モバイル通信とIoT技術を掛け合わせたアセットマネジメントサービスです。物流現場では、車両・倉庫・パレットなどの資産管理が煩雑になりやすく、適切な配分がされないまま運用されてしまうケースが見受けられます。
WAKONXは、各種物流アセットに取り付けたセンサーからリアルタイムで情報を収集し、運用状況を見える化する仕組みを提供しています。これにより、空き資産の再配置や、拠点間でのシェアリング計画を立てやすくなり、資源の有効活用が進められるようになりました。限られた資源の中で効率を高めるという課題に対する有力な解決策のひとつです。
出典参照:WAKONX(ワコンクロス)について|KDDI株式会社
株式会社日立物流は、自社開発のスマートロジスティクスプラットフォーム「SSCV(Smart & Safety Connected Vehicle)」を活用し、輸配送の効率化や安全性向上を目指した取り組みを進めています。SSCVでは、車両ごとの運行状況やドライバーの運転傾向をリアルタイムにモニタリングし、データ分析に基づいて走行ルートや積載効率を改善する仕組みが組み込まれています。
また、作業負荷の分散や事故リスクの低減にもつながる仕組みづくりが進められました。物流現場に蓄積されたデータを活用することで、業務改善だけでなく新しいビジネスの構築にもつながる展望が示されています。
出典参照:AIカメラを活用したセンシングソリューションの効率的な開発・導入を可能にするエッジAIセンシングプラットフォーム「AITRIOS(アイトリオス)™」のサービスを開始|株式会社日立物流

物流DXの推進に取り組む際には、社内のリソースだけで対応しようとすると、技術的な限界や運用負荷が課題となりやすい傾向があります。こうした場面で支援してくれるパートナー企業の存在は、業務全体の可視化と改善を後押しする貴重な要素といえるでしょう。
紹介した各社の取り組みは、それぞれが異なる視点とアプローチをもって物流現場の課題解決に貢献しています。自社の課題や目的に合った連携先を見つけることが、スムーズなDX推進と持続可能な成長への一歩となるはずです。
まずは事例を参考にしながら、現場のニーズと照らし合わせて方向性を検討してみましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
