物流DXで課題解決へ|2024年問題と人手不足に立ち向かうための実践ガイド
物流

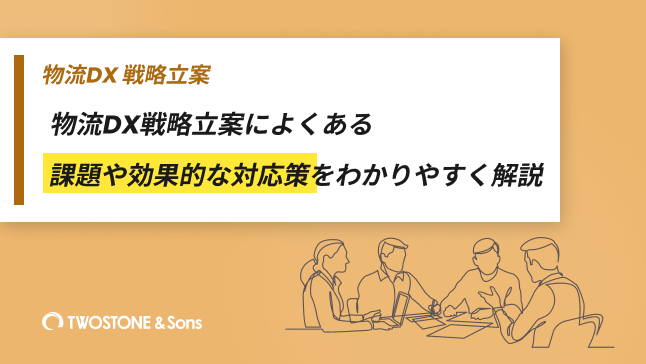
物流業界では人手不足や高騰する燃料費、顧客ニーズの多様化など日々変化する環境に対応するための戦略が求められています。その中でもデジタル技術を活用し、業務効率やサービス品質の向上を図る物流DXは注目を集めています。
しかしDXの推進に際し、多くの企業がその前提となる戦略立案の段階でつまずいているのが実情です。現場と経営層との認識のずれやデータの整備不足、そもそもの目的の曖昧さなどさまざまな壁が複雑に絡み合ってプロジェクトを前に進めづらくしています。
本記事では物流DXの推進に際し戦略立案がなぜ重要なのかを押さえた上で、実際に現場で生じやすい課題やその対応策について詳しく解説します。内容を通じて自社の状況に応じた、現実的なアプローチを見つけていきましょう。

物流DXを効果的に推進するためには目的を明確にし、現場と経営の双方が納得できる形で方針を定めていく必要があります。単に新しいツールやシステムを導入するだけでは期待された効果が得られにくく、むしろ業務の混乱を招いてしまうこともあります。そのため、DXの取り組みを始める前段階での戦略立案は大切です。
戦略立案には現状の業務プロセスや課題の洗い出し、将来的にどのような状態を目指すのかというゴール設定、さらにそれを実現するための手段や評価基準の設計が含まれます。このプロセスを丁寧に行うことで施策の方向性がぶれにくくなり、現場と経営が一体となって進められる体制が整いやすくなります。
戦略立案の段階では、さまざまな課題が立ちはだかりやすいです。特に現場の多様なニーズを正確に把握できない点、経営層と現場の認識ギャップによる意思決定の難しさなどが挙げられます。
加えて既存システムとの連携やデータ統合が困難であることも、壁となりやすいです。こうした課題は人材不足やKPI設定の曖昧さとも関連しており、全体の推進力を弱める要因にもなりえます。
ここではこれらの壁の詳細と対応策を見ていきましょう。
物流業務は倉庫管理や配送、在庫調整など多様な工程が絡み合っており、それぞれの現場で求められるニーズも異なります。戦略を立案する際にこれらの現場の要求や課題を正確に捉えられないと、全社的な視点での効果的な施策を策定しにくくなるでしょう。ヒアリング不足や断片的なデータ収集は、この問題を深刻化させる傾向があります。
対応策としては現場への定期的な意見聴取や業務プロセスの詳細な可視化、さらにはデジタルツールを活用したリアルタイムデータの取得を組み合わせる方法が考えられます。こうした多面的なアプローチによる現場ニーズの多角的な把握が、戦略反映に役立つでしょう。
物流DXを進める上で経営層と現場の間に認識のズレがあると、効果的な意思決定が難しくなります。経営層は全社戦略や収益性を重視する一方、現場は日々の作業効率や安全面を優先するケースが多く、優先順位や課題の捉え方が異なることも少なくありません。このギャップは情報共有不足、コミュニケーション不足などが原因となる場合が多いです。
対策としては定期的な情報交換の場を設けるとともに、双方が理解しやすい共通言語や指標を用いた説明を心がけることが有効です。また現場からのフィードバックを経営判断に反映させる仕組みを作ることで、認識のズレを縮小させる動きが期待されます。
物流DXを推進するには、多種多様なシステムが絡む既存のIT環境との連携が欠かせません。しかし既存システムの多様性や老朽化により、データ統合の難航もあり得ます。異なるベンダーや形式で構築されたシステム間においてデータの互換性が取れず、情報の断片化が起こりやすいです。この状態では全体の業務効率化が阻害されることもあるでしょう。
対応策としてはAPI連携やデータフォーマットの統一、さらにはクラウド基盤の活用によるシームレスなデータ共有環境の構築が考えられます。段階的に統合を進める計画を立てることで、リスクを抑えながら効果を得られることでしょう。
物流業界では慢性的な人材不足が課題となっており、DX推進に携わる専門人材の確保が難しくなってきています。経験豊富なIT技術者やプロジェクトマネージャーが不足すると計画の遂行が滞りやすくなり、結果として戦略が思うように進まなくなる恐れがあります。
さらにDX推進は単なる技術導入に留まらず、業務プロセス改革や組織文化の変革も伴うため、多角的なスキルを求められているのが実情です。解決策としては外部パートナーとの連携や専門コンサルタントの活用、内部人材の育成プログラムの充実が挙げられます。加えて業務の自動化やAI活用によって、負担軽減を図ることも検討されるでしょう。
戦略立案の際にKPIや効果測定の基準が不明瞭だと、進捗状況の把握や改善点の特定が困難になります。物流DXは複数の業務プロセスやシステムにまたがるため指標の選定が難しく、時には目標が曖昧になりがちです。明確なKPI設定がなされていないとどの施策が効果的か判断しづらく、成果を示しにくくなる恐れがあります。
効果的な対応策としては業務の目的に沿った具体的な指標を設定し、定期的にモニタリングする体制を整えることが考えられます。これによって改善点を迅速に把握し、PDCAサイクルを回しながら戦略のブラッシュアップを進める環境が整うでしょう。
物流DXを効果的に進めるには、段階的に戦略立案を進めることが大切です。
まずは現状の物流プロセス全体を詳細に分析し、課題や改善余地を把握します。その上で具体的な戦略と実行計画であるロードマップを作成し、推進体制の構築や適切なパートナー選定を進めましょう。次に必要なシステムやデジタルインフラを整備し、最後に効果検証を通じて全社展開を目指す流れが考えられます。
これらのステップを踏むことで、物流DXの推進がスムーズになるでしょう。
物流DXの戦略立案の第一歩は、自社の物流プロセス全体の詳細な分析にあります。倉庫での在庫管理から配送計画、受発注業務に至るまで各業務がどのように連携し、どこに非効率や課題が潜んでいるかを正確に把握しなければなりません。
さらに現状使用しているシステムやデータ管理の状況も調査し、情報の断片化や重複、リアルタイム性の欠如などの問題点を洗い出します。現場担当者へのヒアリングを通じて、実際の業務で感じている問題や改善要望の直接収集も効果的です。このような多面的な分析を行うことで課題の全体像が見え、戦略を立てるためのしっかりした土台が築かれます。
現状分析の結果を踏まえ、具体的な物流DXの戦略を立案します。ここでは単に課題解決の施策を並べるだけでなく、短期的な目標とともに中長期的に目指すべきビジョンや方向性の明示が必要です。次にそれらを実行に移すためのロードマップを作成し、施策を実行する時期や順序を時系列で整理します。
加えてKPI(重要業績評価指標)を設定し、進捗や効果を数値で把握可能とすれば戦略の適切な管理と必要な修正ができます。ロードマップの共有により、関係者全員が同じ方向を向いて計画を進めやすくなる点もメリットです。
戦略が明確になったら、物流DXを推進する体制づくりを進めます。担当部署や責任者の明確化により、計画の進行管理や現場との連携がスムーズに行われます。また社内リソースだけで対応が困難な場合は専門知識や経験を持つ、外部パートナーの活用も検討すべきです。
パートナー企業を選ぶ際は技術力や物流業務に対する理解の深さ、柔軟な対応力などの総合的な判断が求められます。良好なコミュニケーションが取れる相手かどうかも重要で、双方が連携して課題解決に取り組める環境づくりが円滑な推進につながるでしょう。
戦略に基づき、物流DXに必要なシステムやデジタルインフラの導入を具体的に進めます。倉庫管理システム(WMS)や輸配送管理システム(TMS)はもちろん、IoT機器やAI分析ツールの活用も検討されます。これらのシステムは自社の業務フローや既存システムとの連携性を十分に考慮し、導入後の運用がスムーズになるよう慎重に選定しましょう。
さらに現場の操作性や教育体制の整備により、導入後の定着率を高めることが期待されます。段階的な導入や試験運用を実施し、現場の実態に合った運用方法の模索も有効でしょう。
システム導入や施策実行後は設定したKPIに基づき、効果を丁寧に検証します。物流業務の効率化やコスト削減、安全性向上などの計画した目標に対する成果の具体的な数値による評価が大切です。検証結果から問題点や改善点が明らかになれば、速やかに改善策を検討して実行に移すことで施策の精度を高められるでしょう。
効果が十分確認できた施策は他の部門や拠点へ段階的に展開し、全社的な物流DXの推進を目指します。また成功事例やノウハウを社内で共有し、社員の理解と協力を得ることも継続的な推進に欠かせません。

物流DXを効果的に推進するためには、経営層と現場の双方で連携した戦略が必要です。経営層が明確なビジョンを示し、その方針を基に現場の実情を把握しながら推進体制を整える必要があります。現場の声を反映した実践的な改善策を段階的に進めることで、変化に対する抵抗を抑えつつ継続的な進歩を目指せるでしょう。
ここでは現場と経営をつなぎ、物流DX推進のための具体的な戦略の立案例を紹介します。
物流DX推進において、まず経営層からの明確なビジョンの提示が重要となります。経営者がDXの目的や目標を具体的に示すことで、組織全体が同じ方向を目指しやすくなるでしょう。トップダウンの推進はリソース配分や優先順位の決定において意思決定を迅速化し、現場への浸透を促す役割を果たします。
一方で単なる指示だけでは現場の理解が追いつかず、形骸化の恐れもあります。そのためビジョンを共有する際には丁寧な説明やコミュニケーションを重ね、現場の協力を得ながら進めることが望ましいです。こうした取り組みが、組織全体のモチベーション向上や戦略実行の一体感の醸成に寄与すると考えられます。
現場の実態の正確な把握、及び意見の戦略反映は物流DX推進において欠かせない要素です。現場で日々業務に携わる担当者は課題の本質やボトルネックを肌感覚で理解している場合が多く、彼らの声を軽視すると的外れな施策になるリスクが高まります。
具体的には定期的なヒアリングやワークショップを通じて現場の意見を収集し、業務上の改善案やシステム導入に対する実務的な視点を取り入れることが効果的です。また現場からのフィードバックを戦略に反映させることで、現場の納得感が得られ、推進時の抵抗感を抑えられる傾向があります。結果として、より実践的で持続可能なDX戦略の構築につながりやすいでしょう。
物流DXの推進は一部門だけで完結するものではなく、営業や倉庫管理、IT、経営企画など多様な部門の連携が求められます。そこで横断的な推進体制の構築が重要となり、部門間の情報共有や協力体制を整備する役割を担います。推進チームを組織してメンバーが定期的に進捗状況や課題を共有する場を設けることで、部門間の連携が強化されるでしょう。
こうした体制は各部署の視点や知見を取り入れた多角的なアプローチを可能にし、施策の精度や実効性を高める効果が期待されます。また経営層からの支援を受けて権限を明確にすると、意思決定の迅速化やリソース配分も円滑に進む傾向があります。
物流DX推進は一度にすべてを変えるのではなく、段階的に進めましょう。初期段階では小規模な改善や試験的なシステム導入から始め、成功体験を積み重ねることで現場の理解や協力を得やすくなります。
さらに推進過程で定期的に現場をフォローアップし、進捗や課題の共有が必要です。現場からのフィードバックを基に施策を調整し、必要に応じた追加支援の検討によって持続可能な改善が促されるでしょう。
こうした段階的かつ柔軟なアプローチは変化への抵抗を減らし、長期的なDX推進における組織の適応力向上への寄与が考えられます。
物流DXの戦略立案を効果的に進めた企業の事例は、推進を検討する際の参考になるでしょう。各社が自社の強みや顧客ニーズに合わせて戦略を策定し、現場との連携やデータ活用を重視した取り組みを展開しています。これらの事例からは単なる技術導入ではなく、組織全体の理解と協働が重要であることが分かります。
ここで代表的な大手企業の具体例を紹介し、物流DX推進におけるヒントを探りましょう。
ヤマトホールディングス株式会社は顧客の多様化するニーズを分析し、それに応じた配送網の再編によって業務効率化に取り組んでいます。具体的には配送エリアやルートの見直しをデジタル技術で支援し、配送時間の短縮や運用コストの抑制を目指しています。
またAIやIoTを活用した配送計画の最適化も進められており、リアルタイムの配送状況を把握できる仕組みの整備が可能となりました。
こうした取り組みは顧客満足度の向上だけでなく、ドライバーの負担軽減にもつながっていると考えられます。加えて現場担当者の意見を反映させた段階的な改革が行われ、変革が円滑に進むよう配慮されている点も注目に値するでしょう。
出典参照:次の4年間で新たな事業構造へ|ヤマトホールディングス株式会社
日本通運株式会社では全社的なデジタル化戦略の策定が行われ、物流DX推進の軸として位置づけられています。戦略策定の段階から経営層と現場担当者が連携し、現場の課題や改善点を踏まえた具体的な施策が盛り込まれていることが特徴です。さらに現場とIT部門の密接な連携により、新たなシステム導入がスムーズに進められています。
加えてデータ分析による業務改善提案やKPIの設定にも力が入っており、定期的な進捗確認と課題抽出が実践されています。こうした体制は現場の声を反映しつつ、全社的な視点でDX推進の効果を追求する取り組みとして注目されるでしょう。
佐川急便株式会社はデータ活用を中心に据えた戦略立案により、配送計画の最適化を目指しています。膨大な配送データを分析して配送ルートの見直しや荷物の集約による効率化を図ることで、運用コスト削減に取り組んでいます。また顧客の配送ニーズを細かく把握し、それに合わせたサービス提供が進められている点も特徴の1つです。
さらにAI技術の導入によって需要予測の精度を向上させる試みもあり、変動の激しい物流環境への柔軟な対応が期待されています。こうしたデータドリブンな戦略は現場の負担軽減や配送品質の向上に寄与すると考えられ、戦略的なDX推進のモデルケースの1つとして評価されています。
出典参照:【佐川急便】ルート最適化システム「Loogia」を佐川急便で導入を開始|佐川急便株式会社
物流DXの戦略立案を進める際には、全体の方向性を見失わないよう注意が必要です。戦略は単なる目標設定ではなく、現場の実態や将来の変化を踏まえた具体的な計画として構築されるべきでしょう。
そのため現場の声を丁寧に集めながら、組織全体の課題や業務の特徴を把握してから戦略を策定する流れが望ましいといえます。
また各拠点の事情や運用の違いに配慮しながら、柔軟な対応も大切です。投資対効果の観点から限られたリソースを効率よく活用し、段階的に戦略を進めていくことも考慮すべきポイントとして挙げられます。
戦略立案において最初に求められるのは、現状の課題の正確な把握です。物流業務の中には長年蓄積された慣習や属人的な作業が多く、表面化しにくい問題も存在します。
そのため現場の担当者や管理者からの詳細なヒアリングや業務データの分析を通じ、問題点を具体的に明らかにする必要があるでしょう。課題の内容や発生頻度、影響範囲を客観的に評価しなければ戦略の方向性がずれてしまうリスクも考えられます。
さらに改善案を検討する際は課題の根本原因を探る視点を持ち、単なる表面的な対処ではなく持続可能な解決策につなげる視点が求められます。こうした分析の積み重ねが戦略の精度を高めるために必要です。
物流業務は、地域や拠点ごとに異なる特性や運用ルールが存在します。そのため戦略立案の際には一律の方針を押し付けるのではなく、拠点ごとの状況や課題への配慮が必要です。
例えば都市部と地方の物流拠点では配送需要や交通環境が異なるため、同じ改善策が効果的とは限りません。また拠点ごとに使用しているシステムや作業手順にも差異が見られ、これらを踏まえたカスタマイズや段階的な展開が必要になるでしょう。
現場の実態に即した柔軟な対応が、戦略の実効性を高める上で役立つことが考えられます。こうした配慮は現場の理解と協力を促し、DX推進の土台強化のためにも大切な視点です。
物流DX推進にあたっては限られた予算やリソースを効率的に活用するため、投資対効果を重視する必要があります。新システム導入や業務改善には初期投資だけでなく運用コストもかかるため、戦略策定段階で期待される効果と費用のバランスを十分に検討しましょう。
またすぐに全社展開を目指すのではなく、パイロット的な取り組みを行い効果を検証しながら段階的に拡大していく方法も考えられます。こうした方法はリスクの軽減に役立つだけでなく、実績に基づく説得力ある説明材料として経営層や現場の理解を得やすくなるでしょう。
さらに効果の見える化やKPI設定を明確にし、推進状況を継続的に評価していく体制も必要になるはずです。

物流DXの推進には現状の課題把握や拠点ごとの実情を踏まえた、戦略立案が不可欠となります。戦略は単なる計画ではなく実際の業務や現場の声を反映しつつ、段階的に進めていく柔軟性も求められます。
加えて限られたリソースを効率的に活用し、投資対効果を意識した取り組みが必要です。これらの要素をバランス良く組み合わせながら、会社全体で共有される戦略の構築が物流DXを持続的に推進する上でのポイントとなるでしょう。本記事を参考に、自社の状況に合った計画策定の視点を深めていただければ幸いです。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
