物流DXで課題解決へ|2024年問題と人手不足に立ち向かうための実践ガイド
物流

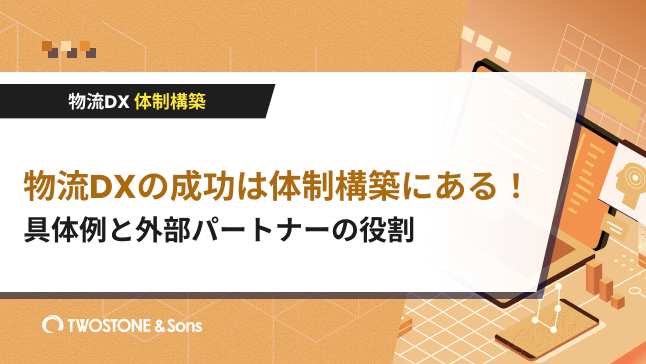
物流業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する際、技術の選択やシステムの導入だけでなく、組織全体の体制構築が重要視されるようになっています。現場から経営層まで一体となって取り組む体制が整うことで、施策の一貫性や現場のニーズの反映が期待されるからです。また変化の激しい環境に対応しつつ持続的に成長を目指すためにも、柔軟かつ強力な推進力が欠かせません。
本記事では物流DXの成功に不可欠な体制構築のポイントや外部パートナーの役割、実際に外部パートナーと協力してDX推進を成功させた企業について具体例を交えて解説します。本記事を参考に、自社にあった実効性の高いDX推進体制の構築を実現させましょう。

物流DXの推進には、多岐にわたる関係部署や現場との連携が不可欠です。単一の部署だけでなく、経営層・現場・IT部門が連携する組織横断的な体制が整っていなければ、施策の整合性が損なわれたり、進捗が停滞したりするリスクが高まります。
さらに現場のリアルな課題や状況を速やかに吸い上げる仕組みがあると改善案を迅速に反映できるため、推進スピードが向上するかもしれません。これらの理由から物流DXの成功には、組織の枠を超えた協力体制や柔軟な推進力の確保が欠かせないといえるでしょう。
物流DXの推進にあたっては、組織内での連携体制の構築が極めて重要になります。複数の部署や役割が関わる中でバラバラに動いてしまうと、施策の一貫性が保てず全体の成果が薄れてしまうリスクがあるためです。組織横断的な連携の強化によって各部門の情報共有や役割分担が明確になり、統一した方向性でDX施策を進めやすくなります。
また方針や計画の共有によってメンバー間の認識齟齬も減り、プロジェクトの効率化や品質向上につながるでしょう。こうした連携体制はDX推進を継続的かつ効果的に行う基盤となり得るため、重視されています。
現場で発生する課題は日々変化し、迅速な対応が求められます。物流DXを成功させるためには現場の声をタイムリーに吸い上げ、それを改善策に反映する仕組みが欠かせません。現場の課題やニーズを的確に把握しなければDX施策が実態と乖離し、効果が薄れてしまう恐れがあります。そのため現場担当者とのコミュニケーションを重視し、課題の見える化や意見収集の仕組みづくりが必要です。
また収集した情報を基に改善案を検討し、すぐに試行錯誤を繰り返せる体制を整えることで問題解決のスピードを上げることが期待されます。このような現場連携の強化がDX推進の実効性を左右する、重要な要素となっています。
変化の激しい物流業界では状況に応じ、柔軟に対応できる推進体制の確保も欠かせません。DX施策の進行中に予期せぬ課題や環境変化が生じやすいため、固定的な体制では対応が難しくなるかもしれません。そのため状況に応じた役割やプロセスの見直し、必要に応じた新たなリソースの投入などの柔軟性が求められます。
さらに外部パートナーの活用によって専門的な知見や支援を取り入れれば、内製では補いにくい部分をカバーできるでしょう。このような変化対応力を備えた体制は推進スピードや成果の質を維持しながら、持続的な改善を実現しやすくします。変化を前提とした柔軟な組織づくりが、DX成功のカギとなるでしょう。
物流DXの推進において体制構築を怠ると、さまざまなリスクが生じやすくなります。特に組織全体の連携が不足すると戦略の方向性がまとまらず、効果的な施策を展開しにくくなることがあります。また現場の課題が経営層に適切に伝わらず、対応が後手に回るケースも珍しくありません。
これらの問題が積み重なると推進スピードが鈍化し、せっかくのDX施策が成果に結びつきにくくなる恐れがあります。こうしたリスクを回避するためには最初から明確な体制づくりに注力し、情報の流れや意思決定の仕組みの整備が求められるでしょう。
物流DX推進で体制構築を怠ると、全社的な戦略の方向性がばらつきやすいです。部署や役割ごとに異なる優先事項が生まれ、統一された方針を共有されないまま進められることがあります。結果として各部署が個別に動くために効率的な連携が難しくなり、プロジェクトの重複や対立も発生しかねません。
また方針の違いによってリソース配分の偏り、重要改善ポイントの見落としなどの可能性もあります。こうした状況では目指す成果が明確にならず、全体の効果が十分に発揮されにくくなってしまいます。したがって戦略の一貫性を保つための体制構築は、推進の基盤となるといえるでしょう。
体制が不十分だと現場で日々発生する細かな課題や問題が経営層に適切に伝わらず、迅速な意思決定が困難になることがあります。物流現場のリアルな状況や課題が経営陣に届かなければ資源投入や施策見直しが後手に回ることもあり、問題の長期化や業務効率の低下につながる場合も想定されます。
また現場と経営層のコミュニケーション不足は信頼関係の希薄化を招き、改善へのモチベーション低下も懸念されるでしょう。こうした事態を避けるためには情報の流れをスムーズにする仕組みづくりが求められ、現場からの意見や声を反映する機会を設けることが重要と考えられます。定期的な報告やフィードバック体制の強化が、対応の迅速化に寄与する可能性もあるでしょう。
物流DXの体制が整っていない場合、部門間の連携不足が生じやすく結果として作業の重複や手戻り、無駄なプロセスが増えるかもしれません。例えば同一のデータを複数部門が個別に扱う場合、処理に時間がかかるだけでなく情報の食い違いや誤りが発生しやすくなります。
また業務フローが分断されているために調整や連絡に余計な工数がかかる、といったケースも想定されるでしょう。これらの非効率は人件費や運用コストの増加を招くこともあり、全体の物流コスト削減を妨げる可能性もあります。
こうした課題を避けるためには部門横断のコミュニケーションや情報共有基盤を整備し、統合的な業務プロセスの見直しが不可欠と考えられます。業務の標準化や一元管理システムの活用も、改善策の1つとして有効かもしれません。
物流DXの推進には専門的な知識やスキルを持つ人材の育成や確保が必要ですが、体制が弱い場合は遅延しやすい傾向があります。技術の変化が速い中で新たなツールやシステムを効果的に運用するには、社内に一定の専門性を持つ人員が必要になるためです。
しかし明確な育成計画や採用戦略がなければ外部に頼り切る形となり、運用面での課題が生じる可能性もあります。専門人材不足は結果として技術導入の遅れや活用不足を招き、DX推進全体の停滞につながるリスクも否めません。
したがって体制構築の段階で人材戦略を含めて計画的に進め、外部パートナーとの協力も視野に入れながら社内リソースの強化を図ることが望ましいでしょう。
体制が整わないと物流DX推進におけるKPI設定や効果測定が不十分になり、施策の評価や改善がうまく進まないかもしれません。具体的な指標が明確でなければ、どの施策が効果的か判断しづらく、進捗管理も困難になりやすいからです。
また評価基準が曖昧な状態では関係者間で認識のズレが生じやすく、改善策の優先順位付けやリソース配分が最適化されにくいこともあります。このためせっかくの取り組みが期待した成果を得られず、社内のモチベーション低下や推進力の減退につながる場合も想定されます。定量的かつ定性的な評価軸を設定し、定期的なレビューやフィードバックを行う体制の整備が効果的な改善サイクルの構築に役立つでしょう。

物流DXの推進においては、効果的な体制を整えることが大切です。単に技術を導入するだけではなく組織の仕組みや役割分担を明確にして、各部門が連携しやすい環境を整える必要があります。
特に多様な部署が関わる物流業務においては、全社的な視点でDX推進を管理する体制が求められます。体制がしっかりしていると情報共有の促進や問題解決の迅速化が期待できるため、推進の成功につながりやすくなるでしょう。
経営層が主導してDX推進委員会を設置すると、全社的な統括と戦略の方向性の維持が図りやすくなります。委員会は各部門の責任者を含めて編成されることが多く、幅広い視点で課題や施策を検討できることが特徴です。経営層の関与によって戦略的な判断がスムーズになり、リソースの適切な配分や投資の優先順位の決定が行いやすくなります。
また経営層の関心が高まれば現場へのメッセージも強まり、DX推進の社内認知度や協力体制が整備されやすいのも利点です。こうした委員会の定期的な運営によって組織全体のDXへのコミットメントを保ちつつ、状況の変化に応じた柔軟な対応が可能になるでしょう。
クロスファンクショナルチームは物流DXの推進において、現場の実情を反映させるために重要な役割を果たします。現場担当者を含む複数部門のメンバーで構成されるため多面的な意見交換ができ、業務プロセスの課題や改善ポイントが具体的に把握されやすくなります。これによって実行可能な施策が検討され、現場での実践に結びつきやすくなるでしょう。
また部門間の連携が促進されることで情報の一元管理や業務の重複防止につながり、全体的な効率改善が期待されます。さらに現場の声を反映した施策は従業員の納得感も高めるため、DX推進へのモチベーション向上も期待できるでしょう。
物流DXの着実な推進のためには、専門知識を持つ人材の育成と専任チームの設置が欠かせません。デジタル技術やシステム運用に精通した人材が社内にいることで、技術的な課題に素早く対応できるだけでなく、継続的な改善活動も推進しやすくなります。専任チームはDX関連のタスクに集中できるため計画立案から実装や運用、効果検証までの一連のプロセスを効率よく進めることが期待されます。
またこうした専門チームは他部署への教育や支援も担うことが多く、組織全体のデジタルリテラシー向上にもつながるでしょう。さらに育成プログラムの計画と実行を通じ、中長期的に必要な人材基盤の強化も図りやすくなります。
物流DXの推進では自社内だけで全てをまかなうことが難しい場合、外部パートナーとの連携が重要な役割を担います。外部の専門企業は最新の技術やノウハウ、そして多くの実績を持つため自社の課題に対し、適切なソリューションを提供しやすい環境づくりができるでしょう。
また外部パートナーは客観的な視点から組織の問題点や改善余地を指摘できるため、新たな発想や改善策の発掘につながることが期待されます。人的リソースが不足している場合には、支援を受けることで推進のスピードアップや品質向上が期待されます。連携を円滑にするためには役割分担や情報共有のルールを明確にし、相互の信頼関係を築くことがポイントとなるでしょう。
物流DXを効果的に推進するためには、適切な体制の設計が欠かせません。体制構築にあたっては現状の課題を把握し、目指すべき目標の具体化から始める必要があります。
また組織の特性や業務の実態に応じ、役割や権限の分担の明確化も必要です。これらのポイントを踏まえた上で全社的な視点から体制設計を行うことにより、各部門が連携しやすく効率的にDX推進が進みやすくなるでしょう。
体制を構築する前にはまず現場や経営層が抱える課題を正確に把握し、達成したい目標の具体的な設定が大切です。課題が曖昧なまま体制設計を進めると役割分担が不明確になり、効果的な推進が難しくなりやすいです。
目標設定は、例えば効率化率や顧客満足度向上などの数値化できる指標を用いると評価もしやすくなるでしょう。課題と目標の整理を経てどのような組織構造や推進体制が必要かを検討し、方針を固めることが推進を円滑にする基盤となります。これによって関係者間での共通理解が進み、協力体制の形成が促進されやすくなるでしょう。
物流DXは全社的な取り組みになることが多いため、経営層の強いコミットメントが欠かせません。経営層が率先して推進の重要性を示し、リソース配分や意思決定のリードによって組織内の協力を得やすくなる傾向があります。トップダウンの体制構築は明確な方針とビジョンの浸透を促し、社員のモチベーション向上にもつながりやすいです。
また経営層が定期的に進捗を確認し、必要に応じて軌道修正を図ることで推進の質を保ち続けることが考えられます。こうした体制は変化が激しい環境下でも、一貫した推進力を維持するために役立つことでしょう。
物流DXは現場の実態に応じた施策でなければ効果が出にくいため、現場担当者からの意見を継続的に収集する仕組みが求められます。定期的なヒアリングやアンケートの実施、現場参加型のワークショップなどを通じて多様な視点を反映させることが有効です。現場の声を反映すると実務に応じた課題解決策が見えやすくなり、推進の実効性が向上します。
また現場の意見が尊重されることで従業員の参加意識や協力意欲も高まりやすくなり、組織全体での推進が円滑に進みやすくなるでしょう。こうした仕組みは、現場と経営層の橋渡し役としても機能します。
物流DXに対応できる人材の育成は長期的な成功に欠かせないため、体系的な研修や外部のセミナー参加が効果的です。社内で専門スキル研修を企画するとともに最新技術や業界動向を学ぶため、外部セミナーへの参加を促すことで知識と技術のアップデートが図れます。
また研修を通じて従業員の理解度やモチベーションを把握し、適宜支援する体制を整えることも大切です。こうした取り組みは単に技術的なスキルだけでなく変化対応力や問題解決能力の向上にもつながりやすく、推進体制の強化が期待されます。
体制構築後は、推進状況の定期的な評価が重要となります。設定したKPIや目標に対する達成度を把握して課題やボトルネックを洗い出すことで、次の改善策の検討が進みやすくなります。評価は単なる結果確認に留まらず、原因分析や対策の立案までを含めることが望ましいです。
こうした改善サイクルを継続的に回すことで体制の課題を早期に発見し修正しながら、DX推進の質を保つことにつながるでしょう。さらに定期的な評価は関係者の意識を高め、体制へのコミットメントを維持する効果も期待されます。
物流DXを推進するにあたり、外部パートナーとの連携が体制構築の重要なカギとなる場合は少なくありません。外部の専門知識や経験を取り入れることで、自社だけでは難しい課題解決やスピード感のある推進が期待されます。
また適切なパートナーの協力により、費用対効果の向上やプロジェクト全体の推進力を強化できる可能性があります。こうしたメリットを踏まえ、外部パートナーの役割を理解しながらの体制設計への活用が効果的です。
外部パートナーは物流DXに関連する専門的な知識や豊富なノウハウをもっていることが多く、自社がまだ持ち合わせていない技術や実践的な経験を補完できる場合があります。例えば新しいIT技術の適用や業務プロセスの改善策など、専門的な観点から提案を受けることが可能であるため、より精度の高い戦略や計画の策定に役立つことでしょう。
さらに多様な業界や企業での実績を活かし、似たような課題に対する効果的な解決手法の紹介も考えられます。こうした知見を取り入れることで自社のDX推進体制に不足しがちな部分を補強しやすくなり、より円滑な推進が期待されます。
外部パートナーとの協働は一見するとコスト増加に感じられることもありますが、長期的にみると費用対効果を高めることにつながるでしょう。専門家の経験や技術の活用によって失敗リスクの低減や無駄な作業の削減が促され、結果として全体のコスト削減につながるケースも多く見られます。
また適切なシステム選定や導入支援、効率的な運用サポートを受けることで資源の最適配分が可能となり、投資効果を高めることが期待されます。こうした視点で外部パートナーの役割を捉え、戦略的に連携を進めることが費用対効果の向上に寄与するでしょう。
物流DXは複数の部署や専門分野が関与する複雑なプロジェクトであるため、外部パートナーの存在が推進力の強化に寄与するケースもあります。パートナーは中立的な立場からのプロジェクトマネジメントの支援、課題解決に向けた調整やファシリテーションの実行が多いため、社内だけで進める場合に比べてプロジェクト全体の停滞を防ぎやすくなります。
また専門的な知見を活かしてリスク管理やスケジュール調整に取り組み、推進速度の維持や品質確保を支える役割も担うことが考えられるでしょう。こうした支援を受けることで、体制全体の一体感や実効性が高まり、DX推進の成果にもつながりやすくなります。
物流DXの推進には、自社内での体制構築が欠かせません。実際に各社がどのように組織や人材の強化に取り組んでいるのか、参考になる部分が多くあります。
ここでは3社の事例を紹介します。これから紹介する企業事例を通じて体制設計や組織改革のヒントを掴みながら、自社の推進体制を見直す際の参考にしてください。こうした取り組みの理解により、自社の課題解決や戦略的な体制構築が進むでしょう。
日本通運株式会社は国内外に広がる物流網の複雑さに対応するため、グローバル事業を統括する組織を一元化し、その機能を強化しました。こうした統括組織の設置は各拠点や子会社で散在していた意思決定、データ管理などを一括して管理する役割を担うとされ、経営層から現場まで一貫性のある戦略展開を支える体制として機能しています。
さらにグローバルな視点からのリスク管理や標準化の推進にも貢献し、物流の効率化や顧客対応力の向上が狙われていると考えられます。これによって物流DXの推進速度が安定的に保たれ、複雑な課題にも柔軟に対応できる基盤が整えられているようです。
ヤマトホールディングス株式会社はデジタル技術に対応した専門人材の育成と採用を戦略的に進めるため、デジタル専門職制度を刷新しています。従来の業務経験だけに頼らず最新のITスキルやデータ分析能力を持つ人材の確保を重視し、専門職を明確に位置づけているのが特徴です。
また社内研修や外部セミナーの活用も積極的に行い、既存社員のスキルアップも図っていると見られます。こうした人材強化の取り組みは急速に進む物流DXに対し、社内での継続的な知識蓄積やプロジェクト推進力の維持に寄与していると考えられます。これにより、変化に柔軟に対応できる人材基盤の構築を目指しているようです。
出典参照:デジタル人材の育成・採用|ヤマトホールディングス株式会社
SGホールディングス株式会社は物流DXの推進にあたり、社内だけでなく外部の専門企業との連携を積極的に進めています。特にIT技術やAI分析などの専門的知見を持つパートナー企業と協力し、先端技術の迅速な活用を目指しています。このような連携は自社の技術リソースだけでは対応しきれない課題に対して補完的な役割を果たすほか、プロジェクトの推進スピードや質を高める効果も期待できるでしょう。
また複数の企業の連携によって新たな物流サービスの開発や業務の効率化も見込めるため、今後のDX推進において外部パートナーとの協働が大切であるといえます。

物流DXを効果的に推進するためには、技術的な側面だけでなく組織全体の体制づくりが欠かせません。今回紹介した企業事例はそれぞれ独自の体制構築や人材育成、外部連携の方法でDX推進を加速させている点が特徴的です。
これらを参考に自社に適した組織設計や連携体制の整備の検討により、推進の精度や速度を向上させやすくなるかもしれません。経営層から現場まで一体となった連携や柔軟な改善のサイクルを意識しながら体制構築を見直すことが、今後の物流DX成功のカギを握る可能性が高いでしょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
