物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流

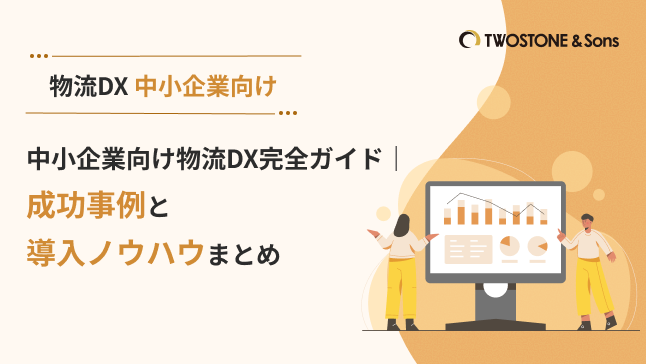
人手不足や2024年問題、コスト増などの経営課題を解決しませんか?本記事では、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の基本から具体的な推進手順、WMSなどのシステム選び、すぐに参考にできる成功事例、活用できる補助金まで、網羅的に解説します。
物流業界は深刻な人手不足と2024年問題により、従来の業務体制では立ち行かなくなってきています。特に中小企業では、限られた予算と人員の中でいかに効率化を図るかが経営の生命線となるでしょう。
そこで注目されているのが物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)です。IoTやAI技術を活用した倉庫管理システム、輸送管理システムなどの導入により、業務効率化とコスト削減を同時に実現できます。
本記事では、中小企業が物流DXを成功させるための具体的なステップから、実際の導入事例、活用できる補助金制度まで、実践的なノウハウを網羅的に解説します。初期投資の負担軽減方法や従業員のスキル不足対策も含め、自社の競争力強化を目指す経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

人手不足や2024年問題など、物流業界が抱える課題は深刻です。その解決の鍵となるのが、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)です。
物流DXとは、IoTやAI、ロボティクスなどの先端技術を活用し、物流業務全体を抜本的に変革する取り組みを指します。本章では、DXの基本定義や従来との違いを分かりやすく解説します。課題解決の第一歩として、まずはその本質を掴みましょう。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、AIやIoT、ロボットなどの先端技術を駆使し、物流の業務プロセスからビジネスモデルまでを根本から変革する取り組みです。
単にツールを導入するだけでなく、データ活用によって業務全体を可視化・分析し、非効率な部分を改善することが真の目的です。
人手不足や2024年問題などの業界の深刻な課題を解決し、生産性の向上と新たな価値創出を目指す、企業の持続的成長に不可欠な経営戦略です。
従来の物流と物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の違いは、人の経験や勘に頼るか、データを起点に業務全体を最適化するかにあります。
例えば、これまで紙やExcelで行われ属人化しがちだった情報管理は、システムによりリアルタイムで一元化可能です。手作業中心だった庫内作業はロボットで自動化・省人化が進み、管理者の勘に頼っていた配車計画も、AIがデータに基づいて実行できるようになります。
このように物流DXは、「属人化」や「生産性の停滞」といったアナログ業務の課題を根本から解決し、効率的で柔軟な物流体制を構築する取り組みです。
中小企業に物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)が必要な理由は、人手不足など、個社の努力では解決できぬ課題に直面しているからです。2024年問題による労働時間規制の厳格化、燃料費や人件費の高騰、そして顧客からの配送スピード向上要求など、中小企業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。
これらの構造的課題に対し、従来の手法では限界があります。生き残りをかけた競争力強化のため、物流DXは必然の選択です。
物流業界が直面する深刻な課題の一つが、慢性的な人手不足と労働力の高齢化です。過酷な労働環境のイメージから若年層が集まりにくく、現場の負担は増大し、長時間労働などの悪循環に陥りがちです。物流業界の有効求人倍率は全産業平均を大きく上回り、特に中小企業では採用活動に苦戦しています。
また、ベテラン作業員の退職により、熟練技術の継承も困難になっています。この課題に対し、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、ロボットや自動化システムで作業を省力化しました。少ない人数でも現場が回る体制を構築し、労働環境の改善と人材確保という、事業継続の根幹に関わる課題を解決します。
「2024年問題」とは、ドライバーの時間外労働が年960時間に制限されることで生じる、物流業界の喫緊の課題です。この規制により、ドライバー1人当たりの輸送力が落ち、運賃高騰や「運べないリスク」に直結します。
この状況を乗り切るには物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)が不可欠です。例えば、輸送管理システム(TMS)で最適な配送ルートを算出して労働時間を短縮したり、倉庫管理システム(WMS)で荷役時間を効率化したりすることができます。これにより、規制に対応しながら生産性を維持・向上させることが可能です。
人件費や燃料費の高騰、2024年問題により、物流業界のコストは増加の一途です。特に価格交渉力が弱い中小企業にとって、このコスト増は利益を圧迫し、競争力を低下させる深刻な課題となっています。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、このコスト課題に対する有効な施策です。例えば、在庫管理システムで過剰在庫をなくし保管費を最適化したり、AIの需要予測で無駄のない輸送計画を立てたりすることで、業務効率化を通じてコスト構造そのものを見直すことが可能になります。
人件費や燃料費の高騰、2024年問題に伴う運賃改定など、物流業界はあらゆる面でコスト増の圧力に晒されています。特に価格交渉力の弱い中小企業にとって、これは利益を直接圧迫し、競争力を削ぐ深刻な経営課題です。
このコスト課題に対する有効な施策が物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)です。在庫管理システムで過剰在庫による保管費を、AIの需要予測で無駄な輸送コストをそれぞれ削減するなど、業務効率化を通じてコスト構造そのものを根本から見直すことが可能になります。
では、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は何から始めれば良いのかという課題に対し、失敗しないための具体的な5つのステップを解説します。
中小企業では限られた予算と人員の中で最大限の効果を発揮する必要があるため、計画的なアプローチが不可欠です。やみくもに推進を進めるのではなく、自社の課題に応じた適切な順序で進めることが成功の鍵となります。
この手順で計画的に進め、リスクを減らし着実に成果へと繋げましょう。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を成功させる最初の、そして重要なステップは、自社の現状を正確に分析し、解決すべき課題を明確にすることです。思い込みや感覚ではなく、「どの業務に時間がかかるか」などをデータで客観的に可視化します。
業務フローやコストを一つひとつ洗い出し、本当の課題を把握することで、後の目標設定やシステム選定が的確になり、物流DXの成功確率が格段に高まります。
現状の課題が明確になったら、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)で「何を、いつまでに、どのレベルまで達成するか」という具体的な目標を設定します。
重要なのは、DXの推進自体を目標にしないことです。「誤出荷率を0.01%未満にする」など、測定可能なゴールを掲げましょう。
さらに、目標達成度を測る指標としてKPI(重要業績評価指標)を定めます。明確な目標とKPIは、進捗を可視化し、関係者の意思統一を促す上で不可欠です。
設定した目標を達成するために、どのようなデジタル技術やシステムが必要になるかを検討し、選定するステップです。
この時、多機能で高価なシステムに安易に飛びつくのは禁物でしょう。中小企業が物流DXを進める上では、自社の規模や予算、そして何よりステップ1で明確化した課題を的確に解決できるかに焦点を当てることが重要です。
「現場の従業員が直感的に使えるか」「導入後のサポート体制は手厚いか」「将来の事業拡大にも対応できるか」などの視点を持ち、複数のシステムを比較検討しましょう。無料トライアルなどを活用し、実際の使用感を試すのも有効な方法です。
導入するシステムが決まったら、いよいよ実行に移ります。しかし物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、一度に変えず段階的に進めるのが成功の秘訣です。特定の部署から始める「スモールスタート」で、初期投資やトラブルのリスクを抑えましょう。
導入後は必ず効果検証を行います。設定したKPIの改善度を測り、効果がなければ原因を分析・改善する。このPDCAサイクルを回すことが、物流DXを成功に導く上で不可欠です。
試験導入で効果が確認できたら、いよいよ全社展開です。この最終ステップで重要なのは、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を社内に定着させることです。新しいシステムの導入は、現場の負担が増えることもあります。
なぜ変革が必要なのかを経営層が丁寧に説明し、研修を充実させるなど、全社的な協力体制を築きましょう。また、「作業が楽になった」などの成功体験を共有することも、従業員のモチベーション向上に繋がります。
物流DXは、推進をし始めて終わりではなく、全社で活用し続けて真の価値を発揮します。

物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進するには、どんな技術があるのでしょうか。近年、クラウド化により中小企業でも導入しやすい価格帯のシステムが増えており、従来は大企業専用だった高機能なツールも身近になりました。
倉庫管理から輸送管理、在庫最適化まで、それぞれの業務領域に特化したソリューションが存在します。本章では、IoT・AIも含め、中小企業のDXを支える代表的な技術の特徴を解説します。
倉庫管理システム(WMS)は、倉庫内の「人・モノ・情報」を一元管理し、業務全体の効率化を図るシステムです。入荷から出庫までをリアルタイムで管理し、バーコードなどを活用することで正確な在庫管理を実現します。
誤出荷や在庫差異といった課題を削減し、作業進捗が可視化されることで、経験や勘に頼った業務を標準化でき、属人化という根深い課題の解決にも繋がります。物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の根幹をなす重要なシステムです。
輸送管理システム(TMS)は、出荷から配送完了まで、輸送に関わる業務を一元管理するためのシステムです。最適な配送ルートの自動計算、リアルタイムでの車両位置把握(動態管理)、日報作成の自動化などの機能を備え、ドライバーの長時間労働や燃料費増大といった課題の解決を支援します。
特に、労働時間が制限される「2024年問題」への対応策として、TMSによる効率的な配車計画や運行管理は非常に重要です。多くの中小企業にとって不可欠な物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)ツールとなっています。
在庫管理システムは、その名の通り在庫管理に特化し、商品の種類や数量、場所などの情報を正確に把握します。在庫を常に可視化することで、過剰在庫によるコスト増大や、欠品による販売機会損失といった経営課題を防ぎます。特に複数拠点を持つ企業には必須と言えるでしょう。
WMSが倉庫作業全体の効率化を目指すのに対し、こちらは適正在庫の維持が主目的です。物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の目的や課題に応じて選定・導入されます。
WMSなどの基幹システムに加え、IoTやAIの活用も物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を加速させる重要な技術です。
例えば、トラックの位置情報をGPSで把握したり、AIが需要を予測したり、倉庫の温度をセンサーで監視し品質管理を自動化したりするのもIoT活用の一例です。
これらの先端技術は、見えなかった課題を可視化し、データに基づく高度な意思決定を実現しました。物流DXをより高い次元へと引き上げます。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進には、解決すべき課題が伴います。特に中小企業が直面する「初期コスト」「スキル不足」「システム選定の失敗」は、乗り越えるべき大きな壁です。
実際に多くの企業がシステムの導入後に想定外の問題に直面し、期待した効果を得られないケースも少なくありません。本章では、これらの導入時の課題と、それを克服するための具体的な対策を詳しく解説します。
中小企業が物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を進める上で、大きな障壁となるのが「初期投資コスト」の課題です。高機能なシステムや自動化設備の導入には多額の費用がかかるため、資金体力に限りがある企業にとっては簡単な決断ではありません。
この課題を乗り越えるには、まず国や自治体が提供する補助金を積極的に活用しましょう。また、近年は高額な買い切り型だけでなく、初期費用を抑えられる月額制のクラウド型システムも増えています。これらを活用し、まずは必要最小限の機能からスモールスタートして効果を見ながら、段階的に投資を拡大していくアプローチも賢明な判断です。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進する上で、コストと並んで深刻な課題となるのが「従業員のスキル不足」です。新しいデジタルツールを導入しても、アナログ業務に慣れた従業員が使いこなせなければ意味がありません。特にベテラン層には、苦手意識や抵抗感を持つ人も少なくないでしょう。
この課題に対応するには、まず誰にとっても操作が分かりやすく、直感的に使えるシステムを選ぶことが重要です。その上で、丁寧な研修の実施や分かりやすいマニュアルの整備など、会社として従業員のスキルアップを支援する体制が不可欠です。組織全体で取り組む姿勢が求められます。
「高機能なシステムを導入したが、自社の業務に合わず使われない」というのは、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)での典型的な失敗パターンです。知名度や機能の豊富さだけで選んでしまうと、現場の課題解決に繋がらず、宝の持ち腐れになってしまいます。
こうした失敗を避けるためには、「自社が本当に解決したい課題は何か」という原点に立ち返ることが重要です。必要な機能を冷静に洗い出し、複数のシステムを比較検討しましょう。無料トライアルで操作感を試し、経営層だけでなく現場従業員の意見を聞くことが、自社に最適なシステム選定の鍵となります。
成功事例は、自社の課題解決のヒントが詰まった最良の教科書です。他社がどのように課題を乗り越えたかを知ることは、自社の成功イメージを掴む上で重要となります。
推進前の悩みから具体的な解決策、そして得られた成果まで、リアルな体験談から学ぶことで、自社のDX推進計画をより現実的で効果的なものにできます。本章では、実際の企業におけるすぐに参考にできる事例を具体的に紹介します。
コンビニ共同配送を担うシーエックスカーゴでは、カゴ車のアナログ管理が深刻な課題でした。電話やFAXの管理では紛失や滞留が頻発し、捜索工数と追加購入コストが経営を圧迫していました。
そこで物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)として、ICタグとクラウドを活用した在庫管理システム『epal』を導入しました。その結果、容器の所在がリアルタイムで可視化され、紛失が激減します。管理工数とコストの抑制、容器の回転率向上も実現した、特定課題に特化したツールの好事例です。
出典参照:物流容器在庫管理システムで複数拠点の混在パレットを一元管理|国土交通省
倉庫業の株式会社坂塲商店では、不規則な混載荷物の荷下ろし作業が深刻な経営課題でした。手作業に頼るしかなく、従業員の高齢化が進む中で、身体的負担の軽減と安全確保が急務となります。
この課題を解決するため、同社は物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)としてAI搭載の知能ロボット「MujinRobotデパレタイザー」を導入しました。3Dビジョンが荷物を瞬時に認識し、これまで困難だった作業の完全自動化に見事成功しました。
結果、作業員の身体的負担はゼロになり、安全性が飛躍的に向上しました。従業員はより付加価値の高い業務へシフトできます。自動化が難しい領域の課題を解決した画期的な成功事例です。
出典参照:荷下ろしロボット導入で複数品種ケースの荷下ろし作業を自動化|国土交通省
運送業の菱木運送では、点呼業務が運行管理者の長時間拘束を招き、なり手不足という深刻な課題に繋がっていました。早朝深夜の不規則な対応が大きな負担だったようです。
そこで同社は、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)として遠隔点呼ロボットを導入しました。管理者は場所を選ばず、ロボットを通じてドライバーの健康状態やアルコールチェックを行える体制を構築しています。
結果、管理者の拘束時間は短縮され、ワークライフバランスが改善します。点呼記録も自動でデータ化され、業務効率化も実現しました。特定の業務に焦点を当てた物流DXが大きな成果を上げた好事例です。
出典参照:AI点呼ロボットの導入で運行管理者の負荷を低減|国土交通省
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の初期コストは大きな課題です。この負担を軽減するのが国や自治体の補助金です。
国土交通省の中小物流事業者支援制度や、中小企業庁のIT導入補助金など、物流業界に特化した支援策が充実しています。ただし、申請には条件や期限があるため、計画的な準備が必要です。本章では代表的な制度と申請の注意点を具体的な事例とともに詳しく解説します。
国土交通省は「中小物流事業者の労働生産性向上事業」を通じ、中小企業の物流DXを後押ししています。この事業は、人手不足などの課題をデジタル技術や自動化設備の導入で解決し、生産性向上を目指します。
具体的には、トラック予約システムによる荷待ち時間削減や、無人搬送車(AGV)による倉庫作業の自動化などが支援対象です。経費の一部補助に加え、専門家による計画策定から導入後までの伴走支援も受けられ、安心して物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の第一歩を踏み出せます。
中小企業が物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を進める上で壁となる導入コストは、国や自治体の補助金で軽減できます。例えばシステム導入には「IT導入補助金」、ロボットなどの省力化設備には「中小企業省力化投資補助金」が活用可能です。
ただし、申請時期や要件は制度ごとに異なり、年度予算に上限があるため、事前の情報収集と計画的な準備が不可欠です。自社の課題解決に適した補助金を見極めて申請することが、中小企業の物流DXを成功させる重要な鍵となります。
「中小企業省力化投資補助金」は、人手不足に悩む中小企業の物流DXに最適な制度です。物流現場の省力化に直結するIoT機器やロボットの導入費用を補助します。大きな特長は、国が認定した製品カタログから無人搬送車(AGV)などを選んで導入する点です。
販売事業者が申請手続きをサポートしてくれるため、初めて補助金を活用する中小企業でも安心できます。従業員数に応じて最大1,500万円と、手厚い支援が受けられるのも大きな魅力です。
出典参照:中小企業省力化投資補助金|独立行政法人中小企業基盤整備機構
「IT導入補助金」は、中小企業が物流DXに不可欠なソフトウェアを導入する際に活用できる制度です。倉庫管理システム(WMS)や在庫管理システムなど、業務効率化に繋がるITツールの導入費用を支援します。
この補助金の魅力は、ソフトウェア本体だけでなく、PCやタブレットなどのハードウェア購入費も補助対象となる点です。専門のIT導入支援事業者がツールの選定から申請までサポートしてくれるため、ITに詳しくない担当者でも安心できます。中小企業が物流DXを始める第一歩として最適な補助金です。
出典参照:IT導入補助金2025|独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業向けの補助金は物流DX推進に有効ですが、申請時には注意が必要です。まず、公募期間は限られるため、公式サイトで日程を確認し計画的に準備しましょう。また、補助金は原則として「後払い」です。
先に全額を支払い、後から交付されるため、事前の資金繰り計画が不可欠となります。最後に、申請には投資の必要性や導入効果を示す事業計画が重要です。自社の物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)における課題と目的を明確にし、説得力のある計画を立てることが採択への近道です。

人手不足や2024年問題に対応し競争力を高めるため、中小企業にとって物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は緊急性の高い課題です。成功の鍵は、自社の課題を明確にし、身の丈に合ったツールを段階的に導入することです。
IT導入補助金などを賢く活用すれば、コストを抑えつつスモールスタートで着実に進めることが可能です。本記事で得た知識を活かし、未来の競争力強化へ向けた第一歩を踏み出しましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
