物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド
物流


物流業界の課題に対応するため、DX推進に取り組みましょう。物流業界はEC市場拡大に伴う小口配送の増加や人手不足により、専門的なツールと知識によるDX推進が求められます。物流業界がDXを推進することでさまざまなメリットが期待できます。
物流業界を取り巻く環境は変化を続けています。例えばオンラインショッピングの普及や小口配送の増加、さらには人手不足といった課題に直面するなかで、企業は競争力を維持、向上させるためにDX推進が必要です。
物流DXは、業務効率の向上やコスト削減、環境への配慮を実現する重要な手段として注目されています。具体的には、ペーパーレス化をはじめとしたデジタル化やAI(人工知能)によるデータ分析、データによるマーケティングによる自動化などが物流DXの取り組みです。
この記事では、物流DXが求められる背景と、それに伴う具体的なメリット、企業事例を交えながら、DX推進の重要性を解説します。DXに取り組もうとしている物流業界の方はぜひ参考にしてください。

近年、物流業界では効率化と迅速化が求められ、デジタル技術の活用が不可欠となっています。特に、EC市場の拡大や労働力不足といった課題に対処するため、物流DXの推進が必要です。経済産業省の発表によれば、令和5年の日本国内における消費者向けEC市場は24.8兆円で、前年比9.23%も増加しました。
物流DXは業務の効率化だけでなく、顧客満足度の向上やコスト削減、環境負荷の低減にも寄与するため、企業にとって競争力を高める重要な手段です。
ここでは物流DXの推進が求められる背景を紹介します。
出典参照:令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました | 経済産業省
オンラインショッピングの普及に伴い、EC(電子商取引)市場が拡大傾向にあります。消費者の購買行動が変化し、物理的な店舗に足を運ぶことなく、インターネットで商品を購入することが当たり前となりました。これにより、物流業界では小口配送のニーズが増加傾向にあります。
小口配送は、少量の荷物を短期間で届けるサービスを指しますが、配送の効率性やコストの最適化が必要です。
物流DXによって、倉庫の自動化や配送ルートの最適化が進み、小口配送の課題解消につながります。デジタル技術の活用によって、トラッキング情報のリアルタイム更新や配送のスピード向上につながり、顧客満足の向上も期待できるでしょう。
日本は少子高齢化が進行しており、労働人口の減少が大きな課題となっています。特に物流業界では、倉庫作業員やドライバーなど、現場で働く人手が不足しており、2017年時点でトラックドライバーが足りないと回答した企業は63%もあります。
物流DXは、この人手不足に対応するための手段のひとつです。例えば、自動化技術やAIを活用することで、作業効率を向上させ、人手を最適に配分できるようになります。
また、ドローンや自動運転車の導入により、配送業務の負担を軽減でき、ドライバーの労働時間や労働環境の改善にもつながります。
出典参照:物流を取り巻く現状について|国土交通省
物流DXを推進するメリットとして、挙げられるのが自動化による生産性の向上です。業務効率化によりコスト削減も期待できます。さらに、脱炭素への貢献として、エネルギー効率の改善が期待されます。ドライバー不足問題を解消し、配送状況の可視化によって顧客満足度も向上するでしょう。
また、業務負担の軽減が従業員満足度向上につながり、企業全体の競争力強化が見込まれます。これらのメリットは企業が持続可能な成長を実現するために欠かせない要素です。
それぞれのメリットを詳しく解説します。
物流業界において、業務の自動化は取り組むべき課題のひとつです。従来の手作業に頼った作業では、ヒューマンエラーや作業の遅れが発生しやすく、効率的な業務運営が難しい傾向にありました。しかし、物流DXを進めることで、自動化技術の導入が可能となります。
自動倉庫やロボットによるピッキング、ドローンを活用した配送など、各工程の自動化が進むことで、効率的な作業を実現できるでしょう。
また、自動化により人件費の削減も期待でき、利益率の向上にもつながります。さらに、リアルタイムでのデータ分析やトラッキングが可能となり、業務の透明性が向上し、顧客対応の迅速化にも貢献するでしょう。
物流業務において、効率化はコスト削減のポイントです。物流DXを進めることで、リアルタイムでのデータ分析やAIによる配送ルートや在庫管理の最適化につながり、コストを削減できるためです。
また、デジタル技術を活用した需要予測により、在庫の過剰や不足を防ぎ、無駄な保管費用の抑制につながります。その結果、企業はコスト削減を実現し、競争力を高められるでしょう。
物流DXは、単なるコスト削減にとどまりません。効率化を通じて業務のスピードアップやサービス品質の向上にも寄与するでしょう。
環境への配慮は、現代のビジネスにおいて企業に求められるテーマです。物流業界においても、二酸化炭素(CO₂)排出量削減は企業の社会的責任として求められています。物流DXに取り組むことで、エネルギー消費の削減や配送効率の向上が期待できるでしょう。
例えば、AIを活用したルート最適化により、無駄な運行を減らし、燃料消費の削減につながります。また、電動トラックや自動運転車両の導入により、二酸化炭素排出量を抑制し、環境負荷を減らすことができます。
加えて、期待できるのが、ブランド価値の向上です。環境配慮型の企業姿勢が消費者や取引先からの評価を高め、企業のブランド価値の向上にもつながります。
物流業界ではドライバー不足への対策も欠かせません。高齢化や過重労働などが原因で、ドライバーの確保が困難な傾向にあるためです。
物流DXの推進によって、無人配送や自動運転車両の活用が現実のものとなり、ドライバー不足の解消が期待できます。自動運転技術が進化すれば、配送業務を効率的にこなすことができ、ドライバーの負担軽減も期待できるでしょう。
また、AIによる運行管理の最適化により、効率的な配送スケジュールを組むことができ、ドライバーの労働時間を短縮できます。これにより、業界全体の労働環境の改善にも寄与します。
物流DXの推進によって可能になるのが、配送状況のリアルタイム可視化です。例えばGPSやIoTセンサーを活用したトラッキング技術により、配送の進捗状況や遅延情報を即座に把握できるようになります。これにより、顧客は自身の荷物の位置や到着時間を正確に確認でき、安心感を得られるでしょう。
また、配送過程でのトラブルや遅延が発生した場合には、迅速に対応でき、顧客対応が向上します。顧客満足度が向上すれば、リピート注文の増加やブランドの信頼度向上にもつながり、企業にとって大きな利益となります。
物流DXに取り組むことで、満足度が向上するのは顧客だけではありません。従業員の満足度向上も期待できるメリットのひとつです。例えば、手作業で行っていた在庫管理や配送業務の自動化によって業務効率が向上すれば従業員の業務負担を軽減できる一方で、満足度を高め、働きやすい環境を整備できます。
満足度が高まることで、従業員の定着率も向上し、長期的な人材の確保が可能となります。従業員が定着すれば、物流業界が抱える人手不足問題の解消も期待できるでしょう。
企業にさまざまなメリットをもたらす物流DXの具体的な取り組みとして、まず挙げられるのがペーパーレス化やデジタル化です。ペーパーレス化やデジタル化によって、スムーズな業務を実現できるでしょう。
また、AIなどのデータ分析を活用した自動化が、業務プロセスの効率向上に貢献します。
さらに、サイトやSNSを活用した顧客との密接なコミュニケーションも、物流DXの取り組みのひとつです。
ここでは物流DXの具体的な取り組みについて解説します。
物流業界におけるペーパーレス化は、DXによって作業効率を改善するための第一歩とも呼べる取り組みです。伝票や書類のやり取りは、時間がかかり、ミスが発生する原因となりかねません。
デジタル化を進めることで、これらの手続きをオンラインで完結できます。例えば、配送指示や請求書、納品書などの書類をデジタル化すれば、クラウドシステムで管理できます。このようなデジタル化により、書類の紛失リスクが減少し、業務をスムーズに進められるでしょう。
さらに、リアルタイムで情報を更新できるため、状況把握が迅速になり、業務効率が向上します。
AIなどのデータ分析による自動化も、物流DXの具体的な取り組みのひとつです。AIを活用して、過去の配送データを分析すれば、需要予測や運行管理の最適化が可能になります。
例えば、商品の配送時期や頻度を予測し、必要な在庫量を正確に算出でき、作業の効率化を実現します。
さらに、AIを活用することで、倉庫内での商品管理やピッキング作業も自動化できるため、人的エラーを減らし、作業スピードの向上につながるでしょう。これにより、全体的な業務効率が向上し、コスト削減やリソースの最適化を実現できるため、企業の競争力が強化できます。
物流業務において、配送ルートの最適化も課題のひとつです。AIを用いたルート最適化技術によって、最短時間で効率的に配送が行えるようになります。AIは交通状況や天候、荷物の特性などを考慮して、最適な配送経路を計算し、無駄な時間や燃料の浪費を防ぎます。
さらに、ドローン配送が浸透すれば、都市部や過疎地域での迅速な配送が期待できるでしょう。ドローンによる配送は、交通渋滞を避けることができ、配送効率の向上につながります。
また、ドローンはアクセスが難しい地域でも活用でき、より多くの顧客に迅速かつ効率的に商品を届けることが期待できるでしょう。
物流業界においても、顧客とのコミュニケーションは欠かせません。近年、SNSやウェブサイトを活用した顧客とのリアルタイムコミュニケーションが一般的となっています。
例えば、SNSを利用して、配送状況や配送時間の変更を迅速に伝えることができます。また、顧客からのフィードバックや質問にリアルタイムで対応することが可能になり、顧客満足度の向上につながるでしょう。
さらに、顧客が自分の荷物の配送状況をオンラインで確認できるトラッキング機能を提供すれば、透明性が高まり、信頼を獲得できます。
蓄積したデータ分析によるマーケティングも、物流DXの取り組みです。物流DXによって蓄積されたデータは、マーケティング戦略の立案に役立ちます。顧客の購買履歴や配送パターンを分析すれば、ターゲット層を絞り込み、より効果的なプロモーションにつなげられるでしょう。
例えば、特定の地域でよく利用される配送サービスや商品の種類を把握し、その情報を基にキャンペーンを展開できます。さらに、蓄積したデータを活用して、顧客に対してパーソナライズされたサービスを提供でき、顧客ロイヤルティの向上が期待できるでしょう。
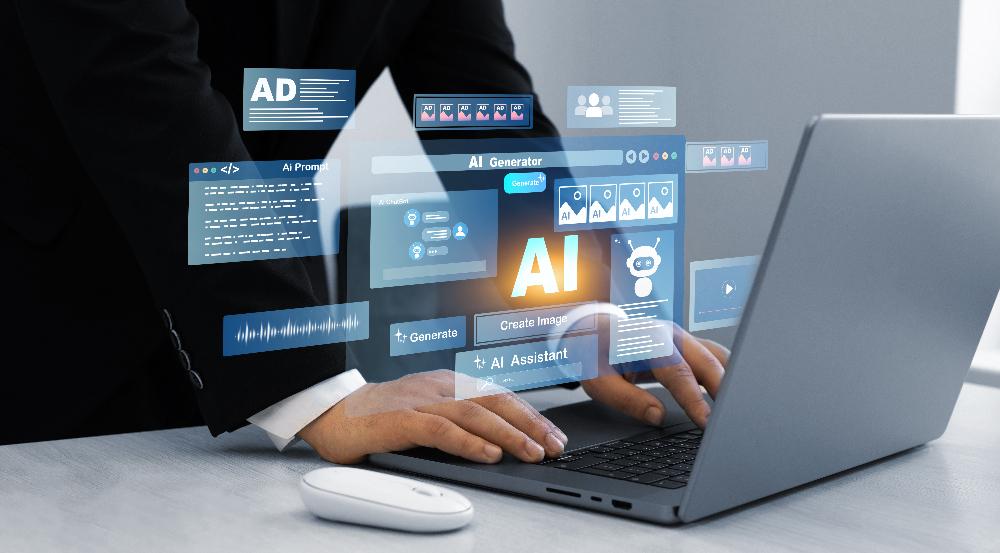
物流DXを推進しようとすると、DX人材の不足やシステム導入の費用負担、従業員の抵抗などが課題として浮かび上がることがあります。特に、デジタル技術に精通した人材が不足している企業では、スムーズな導入が難しくなりかねません。
また、システム導入には初期投資がかかり、ROIを見越した戦略的投資が求められます。
これらの課題には適切な人材育成プログラムや、段階的なシステム導入、コスト削減策の検討などで対処しましょう。
物流DXを進めるためには、専門的な知識とスキルを持った人材が必要です。しかし、DXに精通した人材は不足傾向にあるため、物流DXの促進が遅れかねません。この課題を解決するためには、社内の人材育成を検討しましょう。
例えば、従業員に対して定期的なトレーニングを実施し、DX関連のスキルを習得させることが有効です。
その結果、社内リソースを最大限に活用しながら、迅速かつ効果的にDXを実現できます。
また、外部の専門家やコンサルタントを活用する方法もあります。外部専門家の知見を借りることで、業務における課題解決を加速させ、効果的にDXを推進できるでしょう。
物流DXを実現するためには、さまざまなツールの導入が必要です。そのため、初期投資が必要であり、企業によっては負担になりかねません。初期投資の負担を軽減するのであれば、補助金や助成金の活用を検討しましょう。これらの補助金は、特に中小企業にとって助けとなります。また、初期投資を一度にすべて負担するのではなく、段階的に導入していく方法も効果的です。
例えば、最初はシステムの一部を導入し、効果を確認しながら次のステップを踏むことで、リスクを分散できます。このアプローチにより、企業は長期的に見て、コストパフォーマンスを最大化しながらDXを進めることができます。
出典参照:サービス等生産性向上IT導入支援事業|独立行政法人中小企業基盤整備機構
物流業界の多くの企業は、既存のシステムやソフトウェアを使用しているのが一般的です。これらのシステムがDX促進の障害となる場合があります。特に、古いシステムや異なるプラットフォーム間でのデータ連携が進まないケースもあります。
このような問題に直面した場合、API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を利用した連携が有効です。API活用によって、異なるシステム間でのデータのやり取りがスムーズに行えるようになります。
また、API連携は、既存システムを完全に交換することなく、効率的にDX化を進める手段として非常に有用です。API連携に取り組むことで、既存の投資を無駄にせず、システムの進化をスムーズに行うことができます。
物流DXに取り組む際のステップは主に以下のとおりです。
物流DXに取り組む際、最初に行うべきは現状分析と課題の明確化です。現場の業務フローやシステムを詳細に分析し、改善点を洗い出します。
次に目標設定とロードマップを策定し、具体的な達成基準を決めていきましょう。ここでは物流DXにおける各ステップを詳しく解説します。
物流DXに取り組むにあたり、まずは現状分析を行い、業務上の課題を明確にしましょう。現状の業務フロー、使用しているシステム、従業員のスキルレベルなどを詳細に評価し、どこに改善の余地があるかを洗い出します。分析によって、どの部分がデジタル化に適しているか、またどのプロセスが効果的に改善できるかが見えてきます。
例えば、在庫管理が手動で行われており、エラーが頻発している場合、該当の作業フローの改善がDX促進の最初のステップとなるでしょう。
また、配送ルートの最適化が進んでいない場合には、AIを活用したルート最適化が課題解決につながります。
現状分析が終わったら、次に目標設定を行いましょう。DXに取り組む目的は、単なる技術の導入にとどまらず、業務効率の向上や顧客サービスの向上など、具体的な成果を上げることです。そのためには、以下から構成されるフレームワークであるSMARTの法則を活用しましょう。
上記に基づいた目標が明確になることで、達成すべき方向性が定まり、全従業員が一丸となって取り組むことができます。
目標設定が終わったら、それを達成するためのロードマップを策定しましょう。ロードマップを策定することで、進捗の管理がしやすくなり、計画的にDXを進めることができます。
物流DXを促進させる際は、初期投資や運用のリスクが伴います。そのため、いきなり全体のシステムを変更するのではなく、スモールスタートで始めることを検討しましょう。スモールスタートとは、最初に小さな範囲でDXに取り組み、その効果を検証しながら段階的に拡大していく方法です。
例えば、まずは倉庫管理システムや配送管理システムの一部をデジタル化し、その効果を確認します。効果が見込めると判断できれば、次の段階として別のプロセスにデジタル技術を適用していきましょう。
このアプローチにより、リスクを抑え、成功事例を積み重ねることで、全社をあげたDXへの取り組みがスムーズに進行します。
物流DXを成功させるためには、適切なツール選定も欠かせません。現代の物流業界では、さまざまなDXツールやソフトウェアが提供されていますが、すべてのツールが企業に適しているわけではありません。自社の業務に適したツールの選定が成功の鍵となります。
例えば、倉庫管理や配送管理をデジタル化する場合、AIを活用した在庫管理システムや、最適化された配送ルートを提供するツールを選ぶことが重要です。
また、物流業務は多くのパートナーとの連携が求められるため、他の企業との連携もポイントです。
パートナー企業と協力し、API連携を進めることで、異なるシステム間でスムーズなデータ共有が可能となり、全体的な業務の効率化が進みます。
物流業界には、物流DXを積極的に推進している企業があります。
まず例として挙げられるのがヤマト運輸株式会社です。同社はAIやIoTを活用して配送効率を向上させています。
また、三井物産株式会社は、物流データを基に最適な配送ルートを提案し、業務を効率化しています。日本航空株式会社は、貨物物流のデジタル化に取り組み、リアルタイムでのトラッキングを実現しました。
それぞれの企業の成功事例を詳しく解説します。
ヤマト運輸株式会社は、アルフレッサ株式会社と業務提携を結び、ヘルスケア商品の配送においてAIとビッグデータを活用したシステムを導入しました。この取り組みでは、配送業務量予測システムと適正配車システムを開発し、効率的な配送ルートと適切な配車を実現しました。
まず、配送業務量予測システムでは、アルフレッサが蓄積した販売データや物流データをAIで分析し、顧客ごとの配送業務量を予測します。この予測に基づき、AIは適切な配車計画を自動で作成し、従来の固定的なルートにとらわれない柔軟な配送を実現しました。これにより、配送の効率が向上し、以前よりも最大20%の生産性向上が見込まれています。
出典参照:ビッグデータ・AIを活用した配送業務量予測および適正配車のシステム導入について|ヤマト運輸株式会社
三井物産株式会社は、eコマースの普及や配送ニーズの多様化により、配送業務の負担が増大する中で、AIやIoTを活用して配送計画の効率化を実現しました。従来、配送計画は熟練者の経験に頼り、複雑な条件を満たす計画の立案が難しくなっていました。そこで、株式会社日立製作所と共同でAIを活用した配送計画の自動立案システムを開発したのが三井物産株式会社です。
このシステムは、納品日時、物流センターの位置、走行ルート、渋滞情報、積荷の状態など、多岐にわたるデータをもとに最適な配送計画を自動で立案します。
これにより、熟練者が行っていた膨大な時間を要する配送計画を短時間で立案できるようになりました。
出典参照:AIやIoTを活用した配送計画の立案により、配送業務の負荷軽減、効率化 | 株式会社日立製作所
日本航空株式会社は、ドローン技術を利用した物流業務の効率化を目指し、KDDI株式会社と提携して「1対多運航」の技術開発に取り組んでいます。この技術は、1人の操縦者が複数のドローンを同時に運航できる仕組みを実現するもので、物流業務における効率化を進展させる可能性をもっています。
この取り組みは、ドローンを活用した物流業務の負荷が軽減され、労働力不足の解消が期待できるでしょう。
また、災害対応や点検作業といった分野にも応用が期待されており、ドローンの社会インフラ化が進むことで、物流業務に変革が生まれる可能性もあります。
出典参照:KDDIとJAL、ドローンの社会インフラ化に向け、1対多運航の実現を目指す取り組みを開始 | KDDI株式会社
物流DXによるメリットを引き出すためには、以下のような点に注意しましょう。
いずれの注意点も押さえておくべきですが、特にセキュリティ対策とデータ保護には注意が必要です。セキュリティ対策、データ保護が疎かだと、顧客情報の漏えいによる信頼低下につながりかねません。
ここでは物流DXに取り組む際の注意点を詳しく解説します。
物流DXを成功させるためには、社内全体の理解と協力が大切です。DXは単なるITの導入にとどまらず、業務プロセスの改革を目指す取り組みです。そのため、DXがもたらす変化を社内全員が理解し、協力する体制を整えましょう。社内の理解促進のためには、経営層からの明確な方針を示し、DXの必要性や目的を全従業員に伝えます。
また、各部門のリーダーを中心に、DXの進捗や成果を共有し、従業員一人ひとりの役割を明確にすることが求められます。さらに、業務の変化についても適切にフォローアップし、従業員の不安や疑問を解消できる体制構築が大切です。
社内のDXに対する理解促進を図っても、従業員によっては抵抗感を示す可能性があります。DXに対する抵抗感を覚えてしまうのは、従来の業務フローに慣れてしまっているためです。この抵抗感を取り除くためには、社内セミナーやワークショップを開催し、DXの意義やメリットについて詳細に説明しましょう。
また、早期にDXの効果を実感できるような具体的な成果を示すことが効果的です。
例えば、業務効率が向上した事例やコスト削減に成功したデータを共有することが、従業員の不安を解消し、DXに対する前向きな姿勢を促進します。従業員の積極的な参加を得るためには、単なるトップダウンではなく、ボトムアップでの意見やフィードバックを反映させることも重要です。
物流DXに取り組む際のステップで紹介したとおり、成果を焦らずスモールスタートで段階的にシステムを導入していきましょう。最初に小規模なプロジェクトを選定し、その効果を確認しながら段階的に拡大していく方法です。これにより、大規模なシステム変更に伴うリスクを抑えることができます。
例えば、最初に倉庫管理システム(WMS)や配送管理システム(TMS)など、特定の業務領域からDXに取り組み、その効果を測定した上で次のステップに進めていきましょう。このように、段階的に取り組むことで問題点を早期に発見し、解決策を講じることができます。
スモールスタートでDXを促進させることで、成功する可能性が高まり、全社的な拡大がスムーズに進行します。
物流DXでは、部分最適に終わらせてしまうことなく、全体最適を目指すことが重要です。例えば倉庫や配送の一部だけをデジタル化しても、全体の効率化は期待できません。
全体の業務フローを見直し、各部門やプロセス間での連携強化が、効率化につながります。
具体的には、在庫管理、倉庫管理、配送管理などを統合的にデジタル化し、データの一元管理を実現することが必要です。このように、各システム間でのシームレスな情報連携によって、業務の効率化が進み、全体のコスト削減にもつながります。
また、全体最適を目指すことで、将来的に新たなサービスや機能の追加もスムーズに行うことができ、DXの効果を引き出せます。
物流DXにおいて重要なのは、セキュリティ対策とデータ保護です。物流業務では、膨大な量の個人情報や取引情報を扱うため、情報漏えいやサイバー攻撃のリスクが常に存在します。これに対処するためには、厳格なセキュリティ対策を講じ、適切なデータ保護を行いましょう。
例えば、データ暗号化やファイアウォールの設置、アクセス制限など、基本的なセキュリティ対策が求められます。また、クラウドサービスを利用する場合は、サービス提供者のセキュリティ対策が十分かどうかを確認し、適切な契約を結ぶことが重要です。
さらに、定期的なセキュリティ教育や訓練を行い、従業員全員がセキュリティ意識を高めることも大切です。データの安全性を確保することで、顧客や取引先からの信頼を得ることができ、企業のブランド価値を高めることができます。

物流DXは、業務の効率化やコスト削減、環境負荷の低減を実現するために不可欠な要素です。例えば、自動化やAI、IoTなどのデジタル技術の活用によって、業務の効率化が進み、企業はコストを削減できます。
また、配送状況のリアルタイム可視化により、顧客満足度が向上し、競争力を高められるでしょう。
さらに、ドライバー不足や環境負荷の削減にも貢献できるため、物流業界全体でのDX推進が求められています。物流DXは企業の成長を加速させ、持続可能な社会の構築につながるため、積極的に取り組んでいきましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
