物流DXの成功は体制構築にある!具体例と外部パートナーの役割
物流
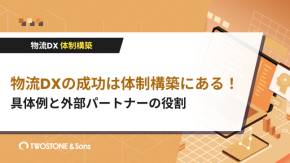
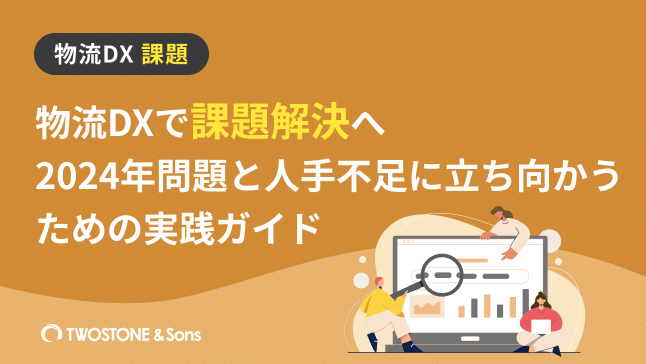
近年、物流業界では人手不足の深刻化や2024年問題への対応、EC市場の急成長に伴う小口配送の増加など、多くの課題を抱えています。これらの課題を解決する切り札として注目されているのが「物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)」です。
物流DXとは、デジタル技術を活用して物流業務を変革し、効率化や生産性向上を実現する取り組みのことです。AIやIoT、ロボット技術などを導入することで、従来の人手に依存した作業を自動化し、データ活用による最適な配送ルートの構築や在庫管理の精度向上が可能になります。
本記事では、物流DXの基本概念から業界が直面する課題、具体的な解決アプローチ、成功事例まで詳しく解説します。物流DXの導入を検討している企業の方や業界の最新動向を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
現在、物流業界では深刻な人手不足による「2024年問題」により、コスト高騰が止まらない状況です。こうした背景から、業務の効率化や最適化は優先的に取り組みたい課題といえるでしょう。
社会インフラの根幹を揺るがす物流業界の課題解決には、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)が重要な役割を果たします。DXは、単なるIT化とは本質的に異なる変革を意味します。
物流DXがもたらす具体的な変革内容について、以下で詳しく見ていきましょう。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、AIやIoT、ロボティクスなどの先進的なデジタル技術を駆使し、個々の業務プロセスからビジネスモデルまで、物流の在り方そのものを根本から変革する経営戦略です。
これは、アナログ業務をデジタルに置き換えるデジタル化とは異なります。DXの「X」が示すとおり、データ活用を核として旧来の慣習や非効率を根底から覆す変革こそが真髄です。
現在、深刻化する人手不足や「2024年問題」などの課題解決にとどまらず、新たな付加価値サービスを創出し競争優位性を確立することが求められています。顧客満足度を高め、社会全体にとって持続可能な物流エコシステムを築き上げることが、物流DXの真価です。
従来の物流現場は、紙伝票や個人の経験に頼る「属人化」が主流で、品質の不安定さ、ベテラン退職による技術継承の難しさが深刻な課題でした。
一方、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、倉庫管理(WMS)や輸配送管理(TMS)などのシステムを有機的に連携させ、業務をデータに基づき標準化・自動化します。
サプライチェーン全体の情報をリアルタイムで可視化し、迅速な意思決定を促し、業務精度を高め、誰もが最適なオペレーションを可能にします。
もはや部分的な効率化ではありません。データ連携によってプロセスを横断した「全体最適」を追求し、物流ネットワーク全体の価値向上を実現できる点こそが、従来との違いです。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の導入は、業界に多岐にわたる変革をもたらします。
例えば、ロボットや自動倉庫は24時間体制での省人化を実現し、深刻な人手不足を直接的に解消可能です。AIによる配送計画の最適化は、天候や交通情報をリアルタイムで分析し、燃料費の削減と「2024年問題」で懸念されるドライバーの労働時間短縮に大きく貢献します。
ビッグデータ分析による高精度な需要予測は、過剰在庫や欠品リスクを低減させ、キャッシュフローの改善が可能です。トレーサビリティの確保などの新たな付加価値提供にも繋がり、企業の競争力を抜本的に強化します。
私たちの生活や経済活動に不可欠な社会インフラである物流業界は今、基盤を揺るがすほどの深刻な危機に直面しています。ドライバーの高齢化による慢性的な人手不足は、「2024年問題」で輸送能力の低下という課題を顕在化させました。
さらにEC市場の拡大がもたらした荷物の小口多頻度化は現場の負担を増大させ、燃料費や人件費の高騰が経営を圧迫しています。
本章では、なぜ今「物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)」による抜本的な変革が求められるのか、背景にある課題を一つひとつ深掘りしていきます。
物流業界が抱える根深い課題は、「人手不足と高齢化」です。特に社会の血液とも言える輸送を担うトラックドライバーは、有効求人倍率が全産業平均の2倍以上に達することもあるほど人材確保が困難な状況にあります。
就業者の平均年齢は50歳に迫り、若年層の入職者が少ないため、このままでは10年後、20年後の物流網の維持自体が危ぶまれています。
人手不足と高齢化の課題に対し、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、不可欠な解決策です。その中でも、パワーアシストスーツのような機器で荷役作業を支援したり、AIで最適な配送計画を組んで労働時間を短縮したりする取り組みが注目されています。
性別や年齢を問わず誰もが働きやすい環境を整備し、業界全体の魅力を高めることで、深刻な人手不足という課題に立ち向かうことが期待されています。
「2024年問題」は、物流の持続可能性そのものを揺るがす、避けては通れない課題です。2024年4月からドライバーの時間外労働が年960時間に制限され、長時間労働で輸送量を補う従来のビジネスモデルが根底から成り立たなくなります。
ドライバーの収入減少は深刻な人材流出を招き、輸送能力の低下から運賃高騰へと直結していきます。その影響は物流業界にとどまらず、最終的に消費者にも波及するでしょう。
2024年問題の解決には、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は欠かせません。AIによる配送ルート最適化や待機時間削減で生産性を飛躍的に向上させ、労働時間を守りながら安定供給を可能にする、持続可能な体制への転換が急がれます。
私たちの暮らしを便利にするEC市場の拡大は、物流現場に「小口多頻度配送の急増」という新たな課題をもたらしています。注文の増加で配送件数は爆発的に増えましたが、荷物は小さく配送先も多岐にわたるため、配送効率は著しく低下し、物流全体の生産性を下げる一因となっています。
不在による再配達は、ドライバーの業務時間と精神的な負担を増大させ、コストを押し上げる大きな要因です。個人の努力では限界のある課題に対し、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)が重要になります。
AIが膨大な配送データから最適なルートと時間帯を導き出し、多様化する顧客の受け取りニーズに応えながら宅配ボックスなどと連携することで再配達を削減します。こうした取り組みによりドライバーの生産性を向上させることが急がれています。
物流業界、特にトラックドライバーの長時間労働は、業界に根付く深刻な課題です。元凶の1つが荷主都合で発生する「荷待ち時間」です。サービス残業の温床になって「長時間労働なのに低賃金」という構造が若手人材の確保を困難にし、悪循環を生んでいます。
負の連鎖を断ち切るには、個人の努力だけでは限界のある構造的な問題を物流DXによる抜本的な業務改革で解決することが不可欠です。
物流DXを導入することにより、バース予約システムで荷待ち時間を根絶し、ロボットやパワーアシストスーツで荷役作業の身体的負担を軽減できます。ドライバーが専門職として尊重され、労働に見合ったやりがいと対価を得られる魅力ある労働環境の整備が可能となります。
日本の物流は、「トラック積載効率の低さ」という根深い課題を長年抱えています。積載率は40%を下回り、多くのトラックが貴重な輸送能力を無駄にしながら空気を運んでいるのが実情です。
EC化による小口化や商慣習に起因する帰りの空荷便が原因で、企業の収益性を悪化させるだけでなく、不要なCO₂排出を招くなど環境にも多大な負荷をかけています。
トラック積載効率の低さ改善への切り札が、物流DXです。帰り便の空きスペースと荷主をつなぐマッチングプラットフォームやAIによる最適な積み付け計算を活用することで積載率を飛躍的に向上させ、経済合理性と環境配慮の両立を目指せます。
出典参照:物流を取り巻く現状と取組状況について(8ページ)|経済産業省
人手不足や2024年問題などの深刻な課題に対し、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は極めて有効な打開策です。
デジタル技術は、これまで解決が困難だった構造的な問題を根本から解消し、単なる業務効率化にとどまらず、持続可能な形で企業を新たな成長ステージへ導く力をもっています。
本章では具体的な解決策として「業務の自動化」「配送最適化」「データによる在庫管理」「ペーパーレス化」の4つを深掘りし、現場をどう変え、競争力を高めるのかを解説します。
人手不足や高齢化という日本が抱える根深い課題に直接アプローチするのが、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)による業務の自動化・機械化です。
例えば倉庫内では、無人搬送車(AGV/AMR)やAI搭載のピッキングロボットが24時間体制で正確な作業を続けます。生産性が飛躍的に向上するだけでなく、重量物の運搬などの身体的負担の大きい危険な作業をなくし、安全な労働環境を構築できます。
年齢や性別を問わず多様な人材が活躍できる職場づくりにも繋がり、人が創造性など本来の強みを活かし、より付加価値の高い管理業務に集中できる体制を整える、極めて有効な対策法です。
経験と勘に頼った従来の非効率な配送計画は、経営リスクでしかありません。こうした課題を解決するのが、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の中核となる「配送の最適化」です。
AI(人工知能)を搭載した輸配送管理システム(TMS)は、天候やリアルタイムの交通情報、納品先の時間指定、車両の積載率など、無数の変動要因を瞬時に計算します。人間では不可能なレベルで最適な配車計画と配送ルートを自動で導き出します。
TMSによる物流DXで、新人ドライバーでもベテラン並みの生産性を発揮できるだけでなく、走行距離を最小化することで燃料費やCO₂排出量を直接的に削減可能です。
過剰在庫による保管コストの増大やキャッシュフローの悪化、逆に欠品による販売機会の損失は、経営に直結する深刻な課題です。多くの現場では、いまだにExcelや紙、特定の担当者の経験と勘に頼った属人的な在庫管理が行われており、ミスの温床と業務のブラックボックス化を招いています。
この課題を解決するには、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)でデータを活用し、在庫管理を改善させるのが有効です。
倉庫管理システム(WMS)を導入すれば、ハンディターミナルやRFIDで入出庫情報をリアルタイムにデータ化でき、誰でも正確な在庫数と保管場所を瞬時に把握できます。
無駄な探索作業や確認の手間がなくなり、ピッキング作業も効率化されます。収益改善と省人化を同時に実現する、極めて効果的な一手です。
紙の伝票や日報に依存した業務は、情報の伝達遅延、入力ミス、保管コストなど、多くの非効率な課題の温床です。ペーパーレス化は、非効率性の課題を解消する物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)での、効果的で導入しやすい重要な第一歩です。
ハンディターミナルやスマートフォンで検品・入出庫作業をその場でデータ化し、情報は即座に基幹システムへ連携できます。現場と事務所がリアルタイムで正確な状況を共有でき、二重入力や転記作業、書類を探す無駄な時間を削減可能です。
これにより、データの正確性と透明性が格段に向上し、従業員は本来のコア業務に集中できます。コスト削減や意思決定の迅速化はもちろん、資源保護などのSDGsの観点からもメリットの大きい取り組みです。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は強力な手段ですが、高価なシステムを導入したものの「現場で使われない」という典型的な失敗は後を絶ちません。
真の企業変革へと繋げるには、トップダウンの号令だけでは不十分であり、経営層から現場までが明確なビジョンを共有し、全社一丸となった慎重なプロセスが求められます。
「段階的な計画」「現場との協調」「適切な技術選定」「継続的な改善」という4つの成功法則が不可欠です。これらは相互に深く関連しており、1つでも欠かすことが出来ません。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を成功に導くには、現実的かつ緻密な導入ロードマップの策定が不可欠です。まず業務プロセスを可視化し、具体的な課題を洗い出します。
次に課題に優先順位をつけ、費用対効果の高い領域から試験的に導入するスモールスタートが賢明です。例えば、ペーパーレス化から着手し、次にWMSで在庫精度を高める、などの段階的なアプローチです。
初期投資とリスクを抑えつつ、小さな成功体験を積み重ねることで、社内のDXへの抵抗感を和らげ、協力体制を築くための強固な土台となります。結果を検証しながら次の一手を打てるため、DX推進の成功確率を大きく高めます。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の成否は、「現場をいかに巻き込めるか」で決まると言っても過言ではありません。最新システムを導入しても、実際に使う現場の従業員が価値を理解し協力的でなければ形骸化します。
「今のやり方で十分だ」などの心理的な抵抗を乗り越えるには、計画初期から現場のキーパーソンを加え、リアルな課題や改善要望を吸い上げ、それを計画に反映させることが不可欠です。
そしてDXで業務がどう楽になるか、会社がどう成長するかのビジョンを経営層が丁寧に伝え続ける必要があります。現場が「自分たちのための改革」と主体的に捉えたとき、DXは真の推進力を得ます。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を実現する技術は多岐にわたるため、自社の課題に直結するツールを冷静に見極める選定眼が何よりも求められます。
他社の成功事例や流行りの技術に安易に飛びつくのは得策ではありません。「積載率の低さ」には「配車計画システム」、「ピッキングミス」には「WMS(倉庫管理システム)」を、というように目的と手段を明確に結びつけることが重要です。
その上で、事業規模や予算、将来の拡張性、既存システムとの連携などを多角的に評価します。操作性やサポート体制も入念に考慮し、導入後の運用まで見据えて複数のベンダーを比較検討しましょう。長期的なパートナーとなり得る信頼できる企業を選ぶことが成功の鍵を握ります。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、システムを導入して完了する短期的なプロジェクトではなく、むしろ継続的な改善活動の始まりです。ビジネス環境は常に変化するため、構築した仕組みが最適であり続ける保証はありません。
「在庫回転率」や「時間外労働時間」などの具体的なKPIを設定し、効果を定期的に測定・分析する体制が不可欠です。データ分析と現場のフィードバックに基づき、プロセスの改善やシステムの調整を繰り返す「PDCAサイクル」を回し続けることが重要です。
DXを一時的なイベントで終わらせず、改善と進化を続ける企業文化として根付かせることが、変化に強い組織を作り上げ、持続的な競争力の源泉となります。
物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)の理論や手法を理解することも重要ですが、実際にどのような効果を得られるのかを知るには、成功事例を参考にするのが効果的です。
以下より、物流業界をリードする大手企業3社の具体的なDX導入事例をご紹介します。
これらの事例から、物流DXがもたらす具体的な効果や導入プロセス、成功のポイントを学ぶことができます。自社の課題解決のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
ヤマト運輸は、デジタルツイン技術を活用した段階的なDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進によって、物流業界の変革をリードしています。
同社は2021年4月からの「データ・ファースト」で、グループ内のフィジカルリソースのデータ化を進め、リアルタイムでモノの動きを把握することを可能にしました。
「トランスフォーメーション」では、輸配送状況の細部にわたるリアルタイム確認と未来予測が可能となり、配達直前でも顧客の都合にあわせて配達指定先や配達日時を柔軟に変更できるサービスの提供を実現しています。
最終的には2030年の「イノベーション」で、荷物が「届く」から「現れる」という革新的な顧客体験の創造を目指しています。
出典参照:データ戦略・イノベーション戦略の推進|ヤマトホールディングス株式会社
佐川グローバルロジスティクスは、東松山SRCに次世代型ロボットソーター「t-Sort」35台を導入し、RFIDシステムと連動した革新的な仕分け業務の自動化を実現しました。
t-Sortは繁閑に応じてロボット台数を変更でき、従来型のソーターと比べ導入リードタイムの短縮や省スペース化を実現しています。この導入により、ヒューマンエラーによる誤発送撲滅と、作業人員を27%削減することに成功しました。
RFIDシステムとの組み合わせにより、出荷作業は1.32倍、返品作業については4.43倍の生産性向上を実現し、人手不足の解消と作業効率の向上を同時に達成しています。
出典参照:仕分け業務のDXにより、東松山SRCの大幅な生産性向上を実現|SGホールディングス株式会社
ロジスティード株式会社は、2019年から独自のデータマネジメント基盤「SCDOS」を構築し、サプライチェーン全体のデータ活用型DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進しています。
SCDOSは単なるシステムではなく、1200社以上の3PL(サードパーティー・ロジスティクス)オペレーションノウハウを集約した包括的なサービスです。同社はクラウド型BI(ビジネスインテリジェンス)プラットフォーム「Domo」と連携し、物流データの可視化と分析の自動化を実現しました。
このデータ活用型DXにより、顧客の2024年問題対応や在庫適正化支援を低コストで実現し、現場の意思決定力を強化することに成功しています。
出典参照:現場の力でお客さまの課題に取り組むデジタル事業基盤を活用し、事業者間の物流情報を連携|ロジスティード株式会社

本記事では、物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)を軸に、業界が抱える深刻な課題とその解決策を解説しました。人手不足や2024年問題など、物流業界の課題は待ったなしの状況です。
物流DXは、AIやデータ活用で配送の最適化や需要予測の精度向上を実現し、業務プロセスを根本から変革します。これにより生産性向上や労働環境改善を達成する、もはや不可欠な経営戦略です。
導入には困難も伴いますが、先進企業の事例を参考に自社の課題と向き合い、計画的に推進すれば道は拓けます。持続可能な社会を支える競争力強化に向け、今こそ物流DXへの第一歩を踏み出しましょう。
ディスクリプション
本記事では、人手不足や「2024年問題」など物流業界の課題を物流DX(デジタル・トランスフォーメーション)で乗り越える方法を紹介します。DXの定義から業務自動化、配送最適化など具体的解決策、成功のポイントまで網羅的に解説しているのでご一読ください。
–end
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
