レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?
医療

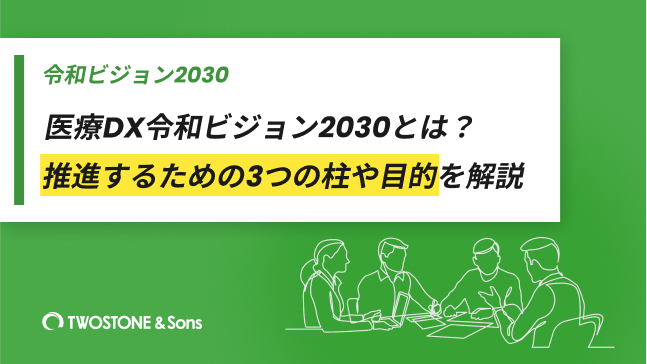
令和ビジョン2030は、少子高齢化や働き方改革を乗り越えて国民皆保険制度の維持を目指す取り組みです。この記事では、医療DX令和ビジョン2030や推進するための3つの柱、その目的までを紹介します。
令和ビジョン2030は、日本の医療が抱える構造的課題を解決するための国家プロジェクトです。具体的には、少子高齢化や働き方改革を乗り越え、国民皆保険制度の維持を目指す取り組みです。
この記事では、医療DX令和ビジョン2030や推進するための3つの柱、その目的まで解説します。医療機関が医療DXを促進して成功させるためのポイントまで解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DX令和ビジョン2030は、政府が国民の健康寿命延伸と質の高い医療の持続的提供を目的とした国家戦略です。ビジョンの核心は「全国医療情報プラットフォーム」の創設にあります。
個人の医療情報や健康に関するデータを必要な時に安全かつ適切に共有・活用し、医療システム全体のデジタル変革(DX)を目指しています。単なる電子化ではなく、データ活用で医療の質と効率を根本から向上させる2030年目標の壮大な計画です。
出典参照:「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム|厚生労働省

医療DX令和ビジョン2030が掲げられた背景は、以下の4つです。
それぞれ解説します。
増え続ける医療ニーズへ限られた人材で応えるには、DXによる生産性向上が不可欠です。日本の医療体制は、急速な高齢化と労働人口減少で維持困難な課題に直面しています。
とくに、団塊ジュニア世代が65歳以上になり高齢者人口がピークを迎える一方で、医療・介護の担い手である生産年齢人口は減少し続けています。需給ギャップは、医療現場の負担を増大させ、地域により必要な医療を提供できなくなる可能性もある状況です。
日本の医療現場は、紙カルテやFAXでの情報共有が多用され、デジタル化が他分野や諸外国に比べて著しく遅れています。原因は、各医療機関の個別システム導入にあります。
その結果、業界全体の標準化が進まず非効率な業務慣行が根強く残りました。アナログ中心の業務体系は、医療従事者の負担を増やし生産性向上の大きな足かせです。
医療情報が各医療機関でバラバラに管理される「サイロ化」は、患者本位の医療を提供する上で大きな障壁です。電子カルテのメーカーごとにデータ規格や用語が異なり、医療機関同士で情報をスムーズに連携できない問題です。
結果的に、患者が転院するたびに同じ検査を繰り返し、過去の投薬やアレルギー情報が新しい医師に伝わらず、最適な治療を受けられない不利益が生じます。患者中心のシームレスな医療を実現するには、情報の壁を打破し全国どこでも必要な医療情報にアクセスできる基盤整備が必要です。
長時間労働や煩雑な事務作業は、かねてより医療現場の大きな負担であり、DXによる業務効率化は待ったなしの状況です。規制を遵守し医療の質を維持するには、医師が診断や治療といった本来の専門業務に集中できる環境整備が求められます。
たとえば、カルテ作成や書類仕事などの事務作業をデジタル技術で効率化・自動化し、医師から他職種へ業務を移管するタスク・シフト/シェアの推進が不可欠です。

医療DX令和ビジョン2030を推進するための3つの柱は、以下のとおりです。
ひとつずつ解説します。
出典参照:医療DXについて|厚生労働省
国民一人ひとりが質の高い医療を享受する根幹のインフラが、全国医療情報プラットフォームです。全国の医療機関や薬局などが持つ患者の医療情報を、オンライン上で安全に共有・閲覧できる仕組みです。
もし基盤が整備されると、救急搬送された患者の正確な既往歴やアレルギー情報をその場で確認が可能です。旅先で体調を崩した際、かかりつけ医と同じレベルの情報を基に診察を受けられます。マイナンバーカードによるオンライン資格確認の仕組みを、拡充する形で整備が進められています。
電子カルテ情報の標準化は、医療機関同士のスムーズな情報連携を実現するポイントです。現在はメーカーごとに仕様が異なる電子カルテのデータ形式や用語、コードを国が定めた標準規格に統一します。
そのため、どの医療機関のシステム間でもデータの相互運用が可能になります。また「標準型電子カルテ」の開発も進められており、導入コストが課題となりがちな中小規模の病院やクリニックが対象です。安価で使いやすいクラウドベースの電子カルテを提供し、DXの恩恵を全国の隅々まで行き渡らせることを目指しています。
診療報酬改定DXは、医療機関やシステムベンダーに多大な労力を強いてきた2年に一度の更新作業負担を抜本的に軽減する取り組みです。従来、診療報酬改定のたび、各ベンダーは複雑な改定内容を読み解きシステムを改修していました。そのため、医療機関は、多額の費用をかけ更新作業をおこなう必要がありました。
この課題に対し、改定情報を標準的な共通言語(マスタ)としての提供を進めています。各システムが自動で取り込めるようになることで、更新作業の効率化と迅速化が図れます。また、医療機関やベンダーは本来の業務により多くのリソースを割けるようになり、医療システム全体の生産性向上も可能です。

医療現場目線での医療DXを推進する目的は、以下の6つです。
それぞれ解説します。
医療DX推進の最大の目的は、より安全で質の高い医療を患者に提供することです。全国医療情報プラットフォームを通じて患者の正確な医療情報が連携されると、医師は既往歴やアレルギー、服用中の薬を瞬時に把握できます。
具体的には、重複投薬や危険な飲み合わせのリスクを回避し、より的確な診断や治療計画の立案が可能です。患者情報が分断されている現状では難しかった、一貫性のある医療提供が実現できます。
医療従事者の深刻な業務負担軽減と働き方改革の推進も、DXの重要な目的です。たとえば、AI音声認識によるカルテ入力自動化や、定型的な文書作成の補助機能を使うことで、医師や看護師の事務作業は大幅に削減されます。
情報共有がスムーズになると、申し送りや部署間の連携時間も短縮できます。また、創出された時間を、患者との対話や高度な専門業務に充てることで、医療の質向上と職員の満足度向上といった好循環を生み出すことも可能です。
DXによる業務効率化は、今後増加が見込まれる医療需要に対応する体制構築に不可欠です。限られた医療スタッフでより多くの患者を診るには、一人ひとりの生産性向上が求められます。
具体的には、Web予約や自動受付機、キャッシュレス決済を導入することで、受付スタッフの業務を大幅に効率化できます。さらに、デジタル技術を活用し業務プロセス全体を最適化できると、医療従事者はより付加価値の高い業務に集中でき、持続可能な医療提供体制の維持が可能です。
医療DXは、限られた医療資源を効率的に活用し、国民皆保険制度を持続可能にするためにも役立ちます。全国で医療情報が共有されることで、転院や救急受診の際に、不必要な重複検査や重複投薬を避けられます。
患者さんの身体的・経済的負担を軽減するだけでなく、国全体の医療費適正化に直結しやすいです。限りある医療人材や高額な医療機器、薬剤といった資源を、必要な場面へ最適に配分するうえで、データにもとづく判断が重要な役割を果たします。
全国規模で集積された質の高いリアルワールドデータは、医学研究や創薬を飛躍的に進展させる可能性を秘めています。匿名化された膨大な診療データを解析することで、見過ごされてきた疾患の予兆を発見しやすいです。
また、特定の治療法がどのような患者さんに有効か、より正確に予測できるようになります。個別化医療(プレシジョン・メディシン)の実現を後押しするとともに、新薬の開発期間短縮やコスト削減にもつながりやすいです。そのため、日本の医療データを世界最高水準の「宝」として活用することが期待されます。
医療DXは、科学的根拠にもとづいた効果的な公衆衛生政策の立案・実行を可能にします。全国の医療情報プラットフォームからリアルタイムに感染症の発生動向を把握できると、パンデミック発生時に迅速かつ的確な対策を講じられます。
また、地域ごとの疾病構造や受診行動をデータで可視化し、限られた医療資源をどこに重点的に配分すべきか、より精度の高い判断が可能です。データにもとづいた政策決定は、国民の健康を守り社会全体の安全性を高めるうえで不可欠です。

患者目線での医療DX推進によるメリットは、以下の2つです。
ひとつずつ解説します。
医療DXが進むと、患者は自身の医療・健康情報をスマートフォンなどで一元的に管理・閲覧ができます。個人の健康記録(PHR)には、健診結果や病院での診療記録、処方薬の情報、日々の血圧や歩数といったライフログまで含まれています。そのため、情報をいつでも自分で確認でき、健康への意識も高まりやすいです。
また、生活習慣の改善や病気の予防に主体的に取り組めるようになります。さらに、診察時にPHRを医師に見せることで、円滑なコミュニケーションと的確な診断につながることも期待されます。
医療DXは、医療機関での待ち時間短縮や手続き簡素化など、医療へのアクセスを格段に向上させやすいです。たとえば、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が普及すると、受付での本人確認がスムーズになります。
また、電子処方箋を利用することで、複数の医療機関や薬局間で情報共有が円滑に進み、薬の受け取りも効率化されます。そのほか、オンライン診療やオンライン服薬指導が普及すると、通院困難な高齢者や遠隔地に住む人々も、自宅で専門的な医療サービスを受けられるようになり、医療の選択肢が大きく広がります。

医療DXが進みづらい理由には、以下の6つが挙げられます。
それぞれ解説します。
医療DXを阻む最大の要因は、高額な導入・維持費用です。電子カルテや各種管理システムの導入には、数百万円から数千万円規模の初期投資が必要なケースも少なくありません。
システムの保守費用や定期的な更新費用といったランニングコストも継続的に発生します。とくに経営基盤が比較的弱い中小規模の病院やクリニックにとって、費用負担は極めて重く、DX推進の大きな足かせです。
費用をかけてシステムを導入しても、効果がすぐには実感しにくい点も、DXが進まない一因です。DXの目的は、長期的な医療の質の向上や業務効率化です。
導入直後に診療報酬が増えたり、劇的に業務が楽になったりするわけではありません。新しいシステムの操作に慣れるまで、一時的に現場の負担が増えることさえあります。投資対効果(ROI)が見えにくいため、経営者が導入の決断をためらうケースは少なくありません。
専門的なIT人材の不足と、既存職員のデジタルスキルの問題も深刻な課題です。多くの医療機関には、院内に情報システム部門を設置する余裕がありません。
そのため、トラブル発生時や新たな活用法を検討する際に、主体的に動ける人材がいません。日々の多忙な業務に追われる医療従事者にとって、新しいデジタルツールを学ぶ時間や精神的な余裕の確保は容易ではないケースがほとんどです。その結果、導入したシステムが十分に活用されない「宝の持ち腐れ」状態に陥る場合もあります。
電子カルテの規格が標準化されていない事実は、医療機関を「ベンダーロックイン」問題に直面させます。一度特定のメーカー(ベンダー)のシステムを導入すると、データの互換性がなく、他社製品への乗り換えが技術的・費用的に極めて困難になる状態を指します。
医療機関は、より良いシステムが登場しても容易に切り替えられません。そのため、既存ベンダーの言い値で保守契約を結ばざるを得ない状況に陥りがちです。構造的な問題が、自由な競争を阻害しDX推進の柔軟性を奪っています。
医療情報は、個人のプライバシーの中でも特に機微な情報であり、取り扱いには万全のセキュリティ対策が求められます。近年、医療機関を狙ったサイバー攻撃(ランサムウェアなど)が頻発しています。
万が一情報が漏洩すると、患者に多大な被害がおよぶだけでなく、病院の社会的信用も失墜しかねません。多くの医療機関がDX化による利便性向上と、情報漏洩のリスクを天秤にかけ、結果として導入に慎重になっています。
医療情報の取り扱いには、個人情報保護法や医療情報システムの安全管理に関するガイドラインなど、遵守すべき複雑な規制やルールが数多く存在します。規制は、患者さんのプライバシーを守るために不可欠ですが、内容は非常に専門的かつ難解です。
また、法務やシステムに詳しい専門人材がいない医療機関にとって、規制をすべて正確に理解し適切に対応することは大きな負担です。規制対応の複雑さが、結果としてDX推進の心理的なハードルを上げています。

医療機関が医療DXを促進して成功させるためのポイントは、以下の5つです。
ひとつずつ解説します。
医療DX成功の最初のステップは、「何のためにDXをやるのか」という目的の明確化です。たとえば、流行りだからといった理由で始めてしまうと、必ず失敗します。
そのため「職員の残業時間を月平均10時間削減する」「患者の待ち時間を15分短縮する」といった、具体的で測定可能な目標設定が重要です。まず自院が抱える課題を洗い出し、DXで何を解決したいのかを組織全体で共有することから始めなければなりません。
システムの導入は、効果を実感しやすい分野から着手する「スモールスタート」が重要です。いきなり電子カルテのような大規模システムを導入しようとすると、費用面でも現場の混乱という面でも、失敗のリスクが高まります。
具体的には、Web予約システムやWeb問診、キャッシュレス決済など比較的小規模な投資で始められるものから導入します。成功体験を積み重ね、現場の協力を得ながら、段階的にDXの範囲を広げていくアプローチが成功のポイントです。
自院の課題や規模、将来の展望に合ったツール選びは、DXの成否を分ける重要な要素です。多機能で高価なシステムが、必ずしも自院に最適とは限りません。
そのため、機能はシンプルでも、現場スタッフが直感的に使えるツールの方が定着しやすい場合があります。また、ツール選び以上に重要なのが、導入から運用まで長期的に伴走する信頼できるパートナー(ベンダーやコンサルタント)選びです。自院の状況を深く理解し、親身に相談に乗ってくれるパートナーの存在は、DX推進の心強い支えです。
DXは、経営層やシステム担当者だけでは絶対に成功しません。実際にツールを使うのは、日々の業務に追われる現場の医師や看護師、事務スタッフです。
具体的には計画段階から現場の意見を十分にヒアリングし、導入ツールの選定にも関わってもらうのが必要不可欠です。システム導入後も丁寧な研修会を実施したり、気軽に質問できる窓口を設けたりする手厚い定着支援が求められます。現場を巻き込む姿勢が、DXを組織文化として根付かせる最も重要なポイントです。
DXは、ツール導入で終わりではありません。システム導入時に設定した目標(例:残業時間の削減)が達成できているか、定期的に効果を測定し結果を評価するのが重要です。
もし期待した効果が出ていない場合は、原因を分析し(Plan)、改善策を実行(Do)、結果を再び評価(Check)、さらなる改善につなげる(Action)のPDCAサイクルを回し続ける必要があります。地道な改善の継続が、DXを真の経営改革へと昇華させます。

令和ビジョン2030は、日本の医療が抱える構造的課題を解決する国家プロジェクトです。少子高齢化や働き方改革を乗り越え、国民皆保険制度の維持を目指す取り組みです。
全国医療情報プラットフォームの創設で情報の分断を解消することで、医療は安全で質の高いものへ進化します。患者一人ひとりに寄り添うケアを実現し、医療従事者の負担軽減を図ります。
導入コストやセキュリティの課題は存在します。医療機関、患者、行政が一丸でデジタル革新に取り組むことで、日本の医療システムを新たなステージへ進めましょう。
株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは
60,000人を超える
人材にご登録いただいており、
ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。
豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。



幅広い支援が可能ですので、
ぜひお気軽にご相談ください!
